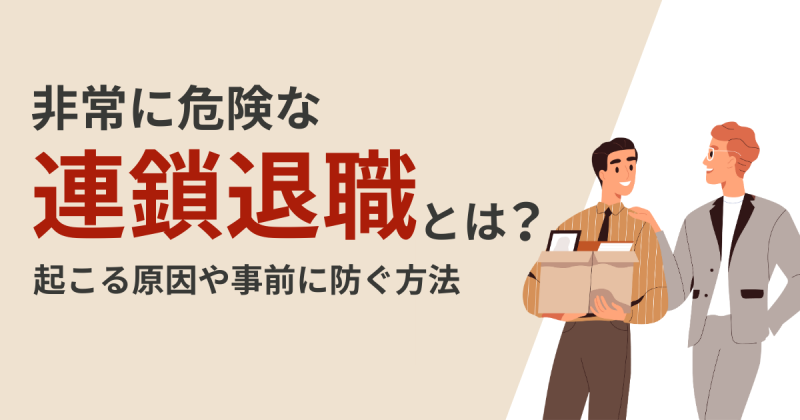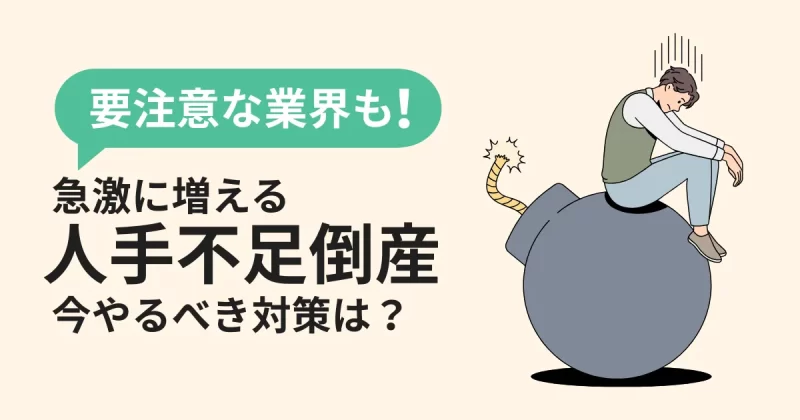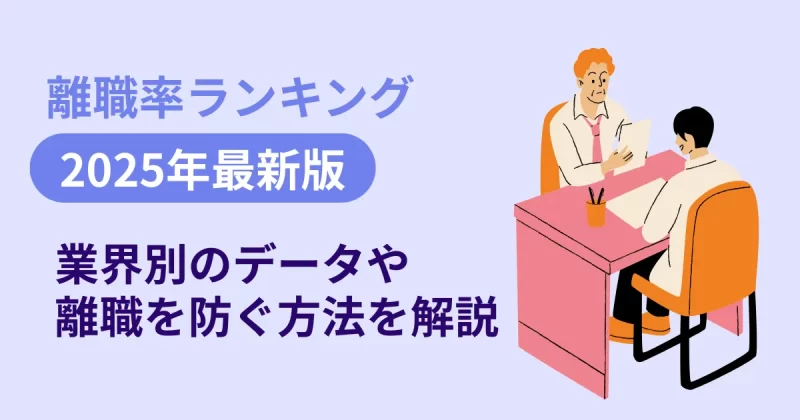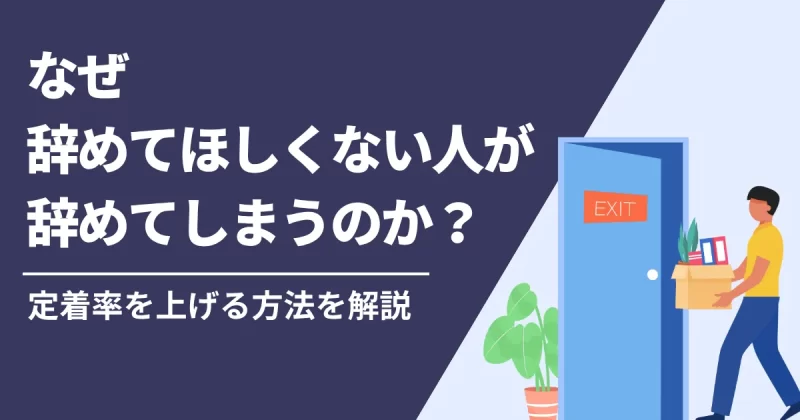連鎖退職とは、ひとりの従業員が退職したことをきっかけに、他の従業員まで次々と退職してしまう現象をさします。
連鎖退職が起こると、残った従業員に業務のしわ寄せがいき不満が蓄積、さらに退職者が増えるという悪循環に陥ってしまう可能性もあります。最悪の場合、人手不足が原因となって企業が倒産するおそれもある、非常に危険な現象です。
本記事では、連鎖退職が引き起こされる原因や、企業に及ぼす影響を解説します。また、連鎖退職を起こさないための予防策、さらに実際に連鎖退職が起きてしまった場合の対処法も紹介します。
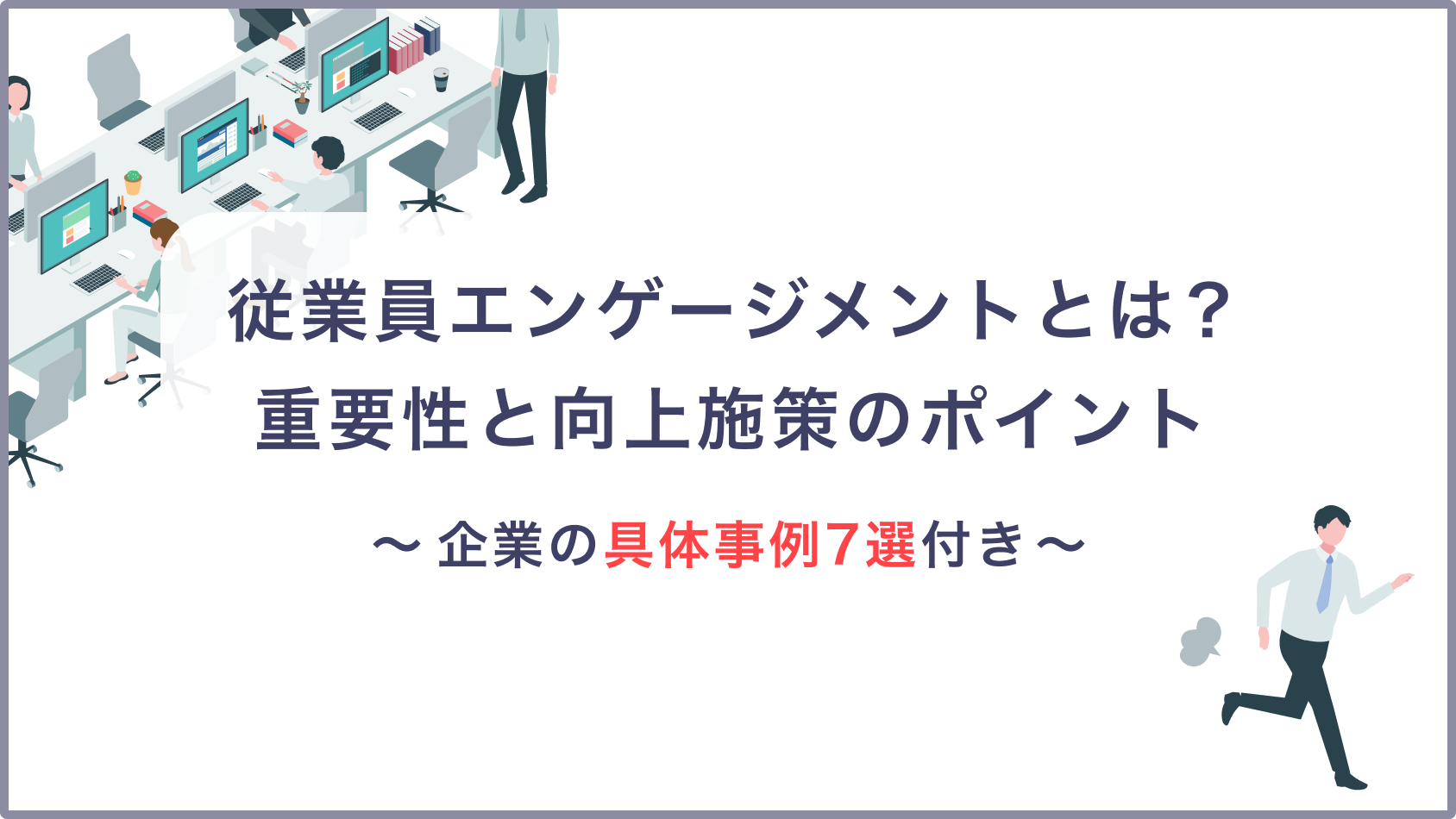
連鎖退職とは
連鎖退職とは、ひとりの従業員が退職したことをきっかけに、他の従業員まで次々と退職してしまう現象のことです。
「信頼していた〇〇さんが辞めると仕事がやりづらくなるから」「仕事のしわ寄せが限られた人員にのしかかり負担が大きくなったから」など理由はさまざまですが、従業員の退職が組織に与えるインパクトは非常に大きいと分かります。
連鎖退職を食い止めない限りどんどん従業員の離脱が続き、人手不足や採用コストの増大が起こるでしょう。早期の段階で食い止めるか、そもそも連鎖退職が起きない盤石な組織づくりが欠かせません。
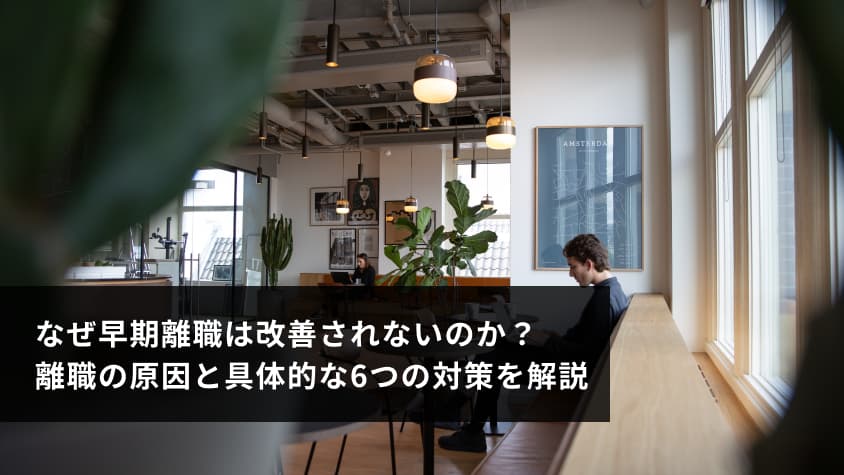
連鎖退職が引き起こされる原因
下記では、連鎖退職が起きる代表的な要因を紹介します。
ひとりの退職が他の従業員にどんな不安を根付かせるのか、根本的な理由を知っておきましょう。
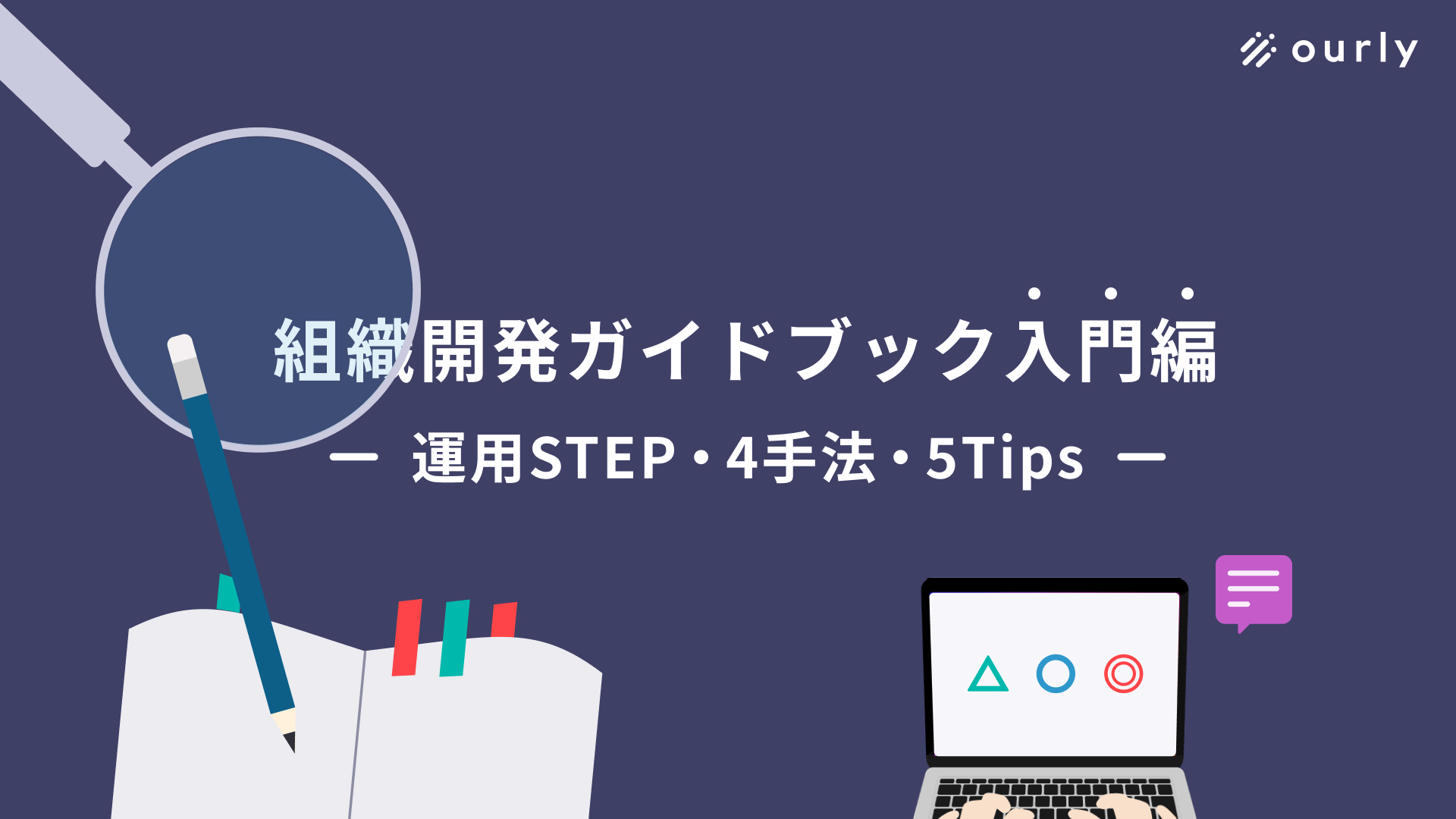
人望のある従業員や管理職の退職
人望のある従業員や管理職者が退職すると、「あの人がいなくて大丈夫だろうか」という不安が蔓延します。
特に強いリーダーシップを発揮していた管理職がいなくなると、代わりに配置されるリーダーの働きぶりに疑問を抱きやすくなります。特定の人物がいないと組織が崩れてしまうように感じ、早期のうちに他社への転職を検討するようになるのです。また、よき相談相手になってくれた先輩社員や、熱意とやる気のある新人の退職もネガティブインパクトが大きいです。キーマンの退職には特に注意しておきましょう。
労働環境や条件への不満
給与が低い、長時間労働が常態化している、休暇が取りにくいといった労働環境や条件への不満は、社員の心に少しずつ蓄積されます。 こうした不満がくすぶっている状態で誰かが退職すると、それが引き金となって「自分もこのままではいけない」「もっと良い条件の会社があるはずだ」という考えが広がり、一気に退職者が増えることがあります。
不適切なマネジメントと人間関係
特定の部署で退職者が続出する場合、その部署の管理職によるマネジメントに問題がある可能性が高いです。 例えば、上司によるパワーハラスメント、公平性を欠いた人事評価、部下の意見に耳を貸さない姿勢などは、部下の心身を疲弊させ、エンゲージメントを著しく低下させます。 また、相談しにくい雰囲気やコミュニケーション不足といった職場の人間関係の問題も、社員が孤立感を深め、退職を決意させる大きな要因となります。
人手不足による業務負荷の増大
一人の退職者が出た後、適切な人員補充が行われないと、残された社員一人ひとりへの業務負荷が増大します。 これが「ドミノ倒し型」の連鎖退職の典型的なパターンです。一時的なら耐えられても、恒常的な人手不足と過重労働は、社員の肉体的・精神的な疲弊を招きます。「これ以上は無理だ」と感じた社員が次々と辞めていくことで、さらに人手不足が深刻化するという負のスパイラルに陥ります。
会社への帰属意識(エンゲージメント)の低下
社員が「この会社で働き続けたい」「会社の成長に貢献したい」と感じる帰属意識、すなわち従業員エンゲージメントの低下も、連鎖退職の根本的な原因です。 会社のビジョンが見えない、自分の仕事にやりがいを感じられない、会社から正当に評価されていないと感じる社員は、会社への愛着が薄れます。このような状態で、同僚の退職など少しのきっかけが加わるだけで、あっさりと退職を決断してしまうのです。

連鎖退職が企業に及ぼす影響
連鎖退職が起きると企業にはどのような影響が出るのでしょうか。
「ひとり辞めたら新しくひとり雇えばいい」とする考えもありますが、従業員数だけでは割り切れない悪影響について下記で解説します。
従業員の不満が蓄積
連鎖退職が起きると、残っている従業員の不満が蓄積します。
新しい人を雇うまでの間、従業員が抜けた穴を補うのは残っている従業員です。新人の育成・教育にも時間がかかり、メンターとしてつく先輩社員や直属の上司の負担は大幅に増大していきます。
結果的に「辞めた者勝ち」の構図ができてしまい、残っていることが損であるかのように感じられてしまうのです。連鎖退職に拍車がかかる可能性もあるので、早期に手を打つ必要があります。
生産性とサービス品質の低下
経験豊富な社員が抜けることで、組織が蓄積してきたノウハウやスキルが失われます。 これにより、業務の効率が落ち、生産性が低下します。また、顧客対応の質が下がったり、納期の遅延が発生するなど、サービス品質の低下にも直結します。これは顧客満足度の低下を招き、最終的には企業の売上にも影響を与えます。
企業イメージの悪化
連鎖退職が続くと、企業イメージが悪化します。同業他社に転職した元従業員が自社の働きづらさに言及したり、家族・親戚・友人などにマイナスイメージを根付かせたりして、知らぬうちに悪評が立ってしまうのです。
近年はSNSや口コミ投稿サイトも勢いを増しており、大きな不満を抱えたまま辞めた従業員がいればインターネット上で悪評が出回るかもしれません。新卒採用や顧客獲得に影響が出る可能性もあり、大きな影響があると分かります。
業績の悪化・倒産
退職による穴を補うため新規採用を続けていると、採用コストの増大により収益が悪化します。
転職サイトや求人誌への出稿料・転職エージェントなど人材紹介に支払う成功報酬など、せっかく売り上げを上げても利益として還元されなくなるのです。また、前項で触れた企業イメージ悪化により、顧客や取引先が離脱する可能性も出てきます。最終的に倒産の危機に陥るなど深刻な影響が出ることもあるので、「ひとり辞めたらまた雇えばいい」と安易に考えるのは禁物です。
連鎖退職の予防策
ここでは、連鎖退職を引き起こさないための予防策を紹介します。
もし従業員がひとり辞めてしまっても他の従業員が引っ張られて辞めないようにするための要素を学び、自社に足りていない部分がないか検討していきましょう。
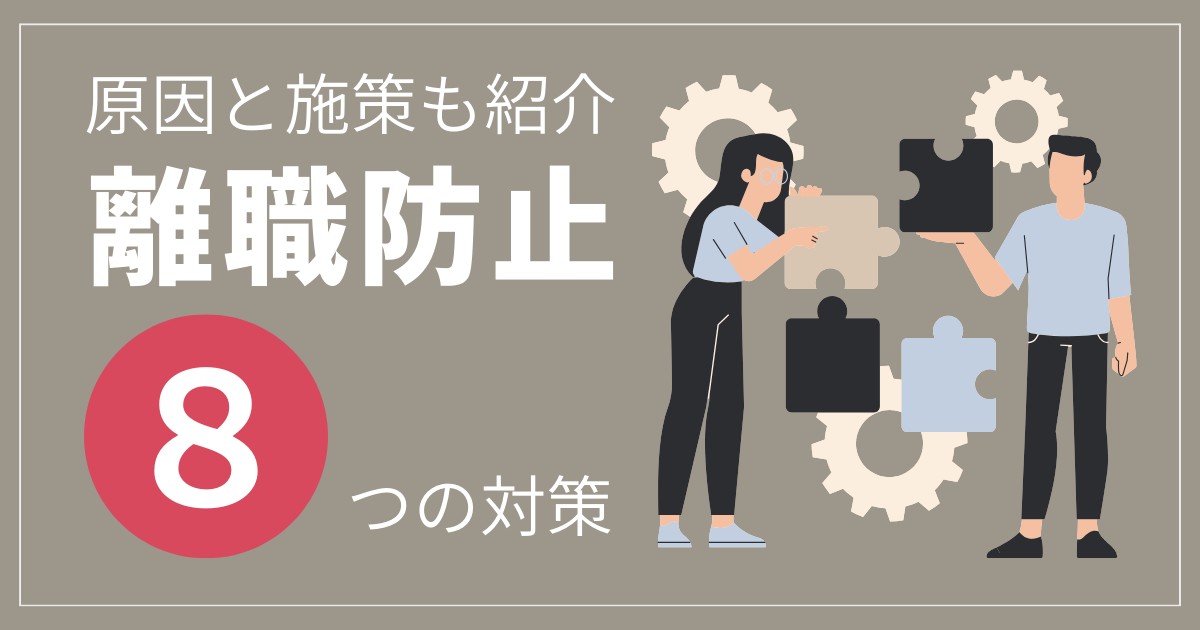
従業員の退職理由を正確に分析する
対策の第一歩は、なぜ退職が起きているのか、その根本原因を正確に把握することです。 退職者との面談では、建前ではない本音の理由を引き出す努力が重要です。また、匿名性のあるアンケートなどを活用して、既存社員が抱えている不満や課題を可視化することも有効です。複数の社員から共通の課題が見つかった場合、それが組織の最優先で取り組むべき問題である可能性が高いです。
労働条件・労働環境を見直す
まずは、自社の労働条件・労働環境を見直すことが大切です。
過度に残業・休日出勤が常態化しているとワークライフバランスを崩しやすく、従業員満足度が下がります。同じく、同業他社と比較して給与の水準が低い、事実上有休休暇を自由に取れない、パワハラ・セクハラが横行している、なども退職を考えるきっかけになります。
労働条件・労働環境が悪いと、ひとり退職しただけで連鎖退職が起きやすくなるので注意が必要です。

管理職やリーダー層の意識改革をおこなう
管理職やリーダー層の意識改革をおこない、連鎖退職のリスクを正しく認識してもらう必要があります。
なかには、前述のような「ひとり辞めてもまた新しく雇えばいい」という考えを持つ管理職・リーダーもいるでしょう。特に応募が殺到しやすい大企業はこの傾向が高くなりやすく、退職のリスクを正しく認識できないことも多いのです。
管理職向けの研修・教育の場を拡充し、退職リスク訴求やマネジメントスキル向上などの施策を図り、現場単位でも退職を予防する動きを取りましょう。
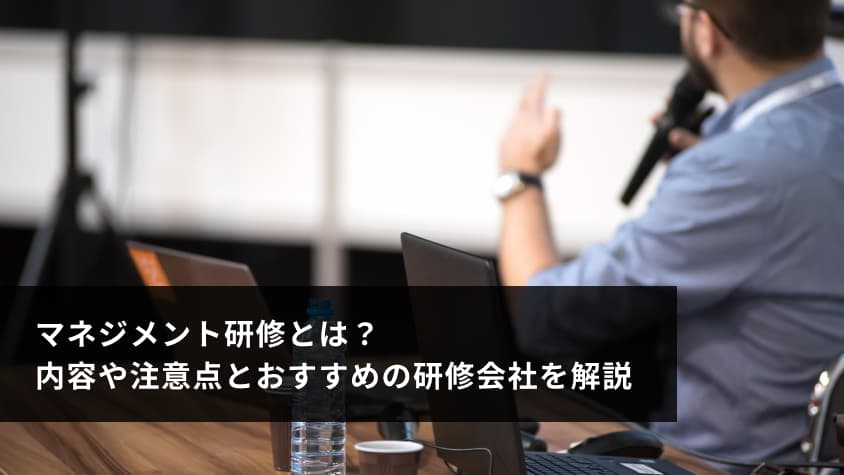
社内コミュニケーションを促す
社内コミュニケーションを促進し、会社の居心地をよくすることも効果的です。
適切なコミュニケーションが取れていれば業務上必要不可欠な報告・連絡・相談がスムーズにでき、ストレスが緩和されます。「仕事がうまくいっている」と思えるので自己実現を実感しやすく、退職が起きづらくなるでしょう。
また、コミュニケーションは心理的安全性の構築にも貢献します。何でも言い合える垣根のない組織であれば、自然と人も根付くのです。
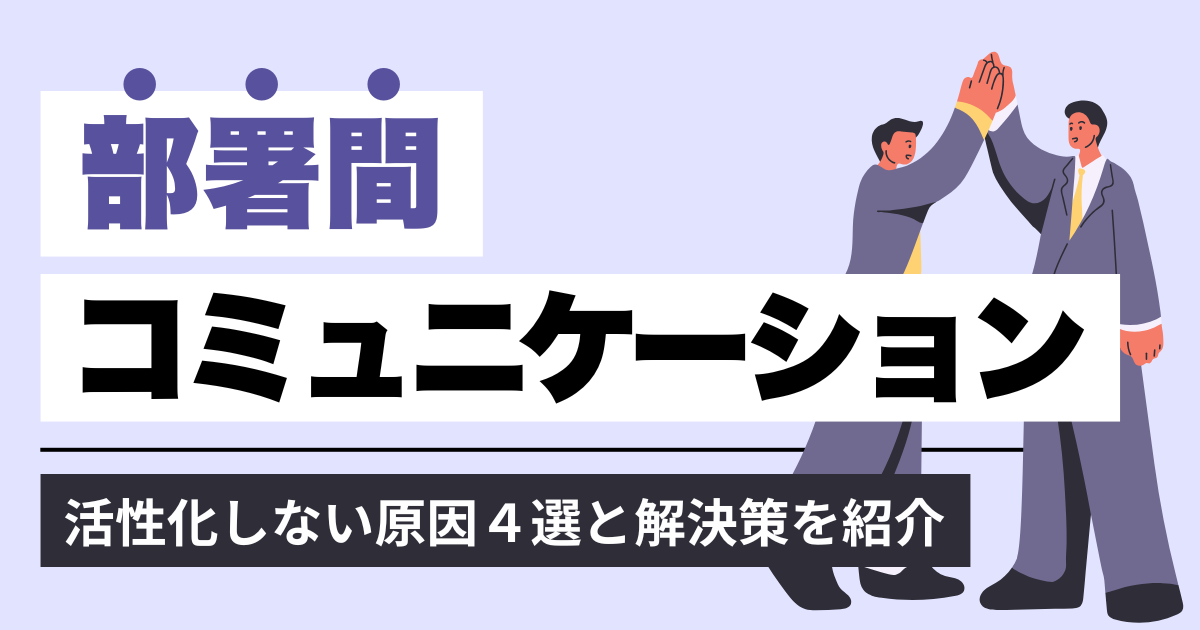
従業員エンゲージメントを定期的に測定し改善する
連鎖退職の予防には、従業員エンゲージメントの状態を定期的に把握し、低下の兆候を早期に察知することが効果的です。 社員の仕事への満足度や会社への貢献意欲を定点観測しましょう。サーベイの結果を分析し、部署ごとや役職ごとに課題を特定し、改善策を実行することで、社員がやりがいを持って働ける組織へと変えることができます。
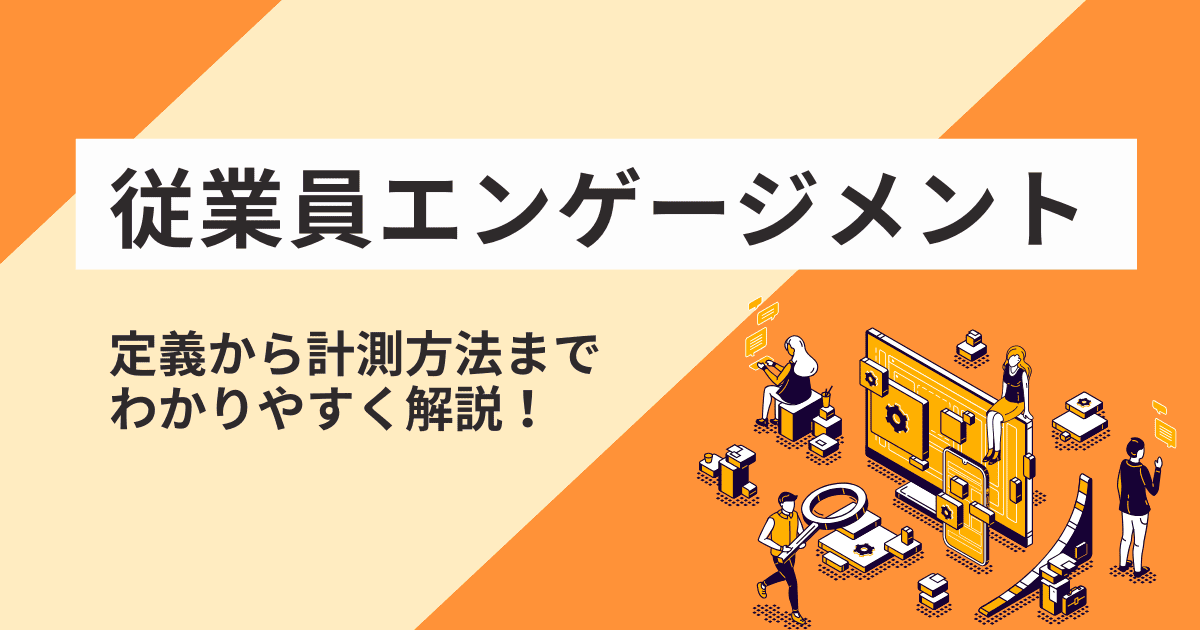
連鎖退職を起こさないためにweb社内報 ourly
ourlyは、従業員のつながりを強化し、組織の離職リスクを低下できるweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
迅速な対応で連鎖退職を防止
連鎖退職を防ぐには、ひとりの退職だからと軽視せず、退職理由を分析・改善していくことが重要です。残された従業員のフォローをするなど迅速な対応を心がけ、従業員の定着を図りましょう。
退職率が下がるなどポジティブな成果が現れたときは、社内報を使い広く訴求していくこともおすすめです。
また、職場環境改善に向けた施策の実施は大々的に公表するなど、改善に向けた動きを取っているとアプローチしてみてはいかがでしょうか。