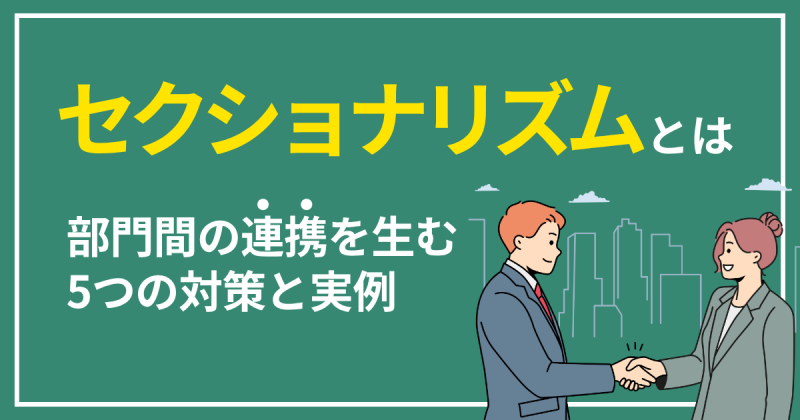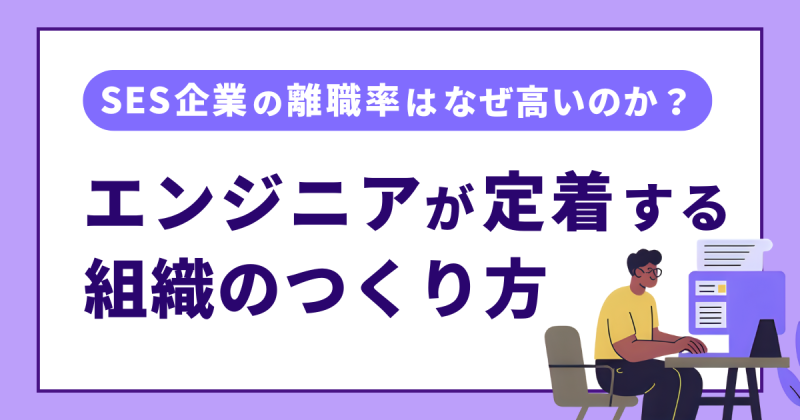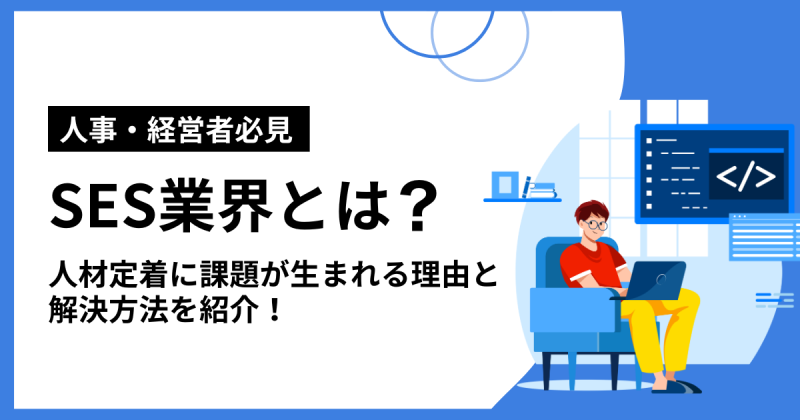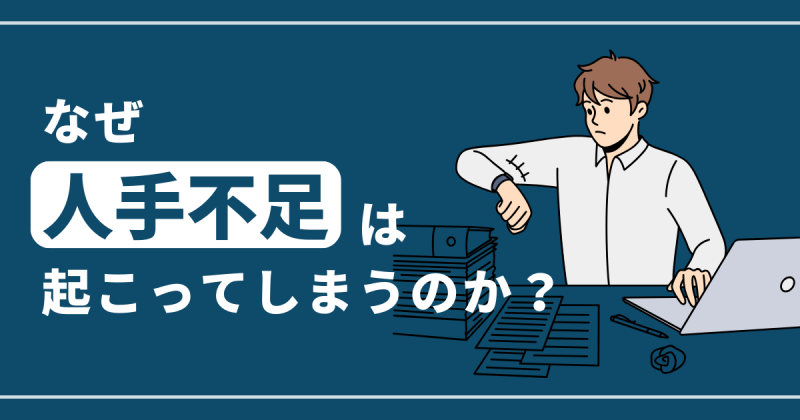主に企業や組織の中で自分が所属する部署やチームの利益だけを優先するセクショナリズム。
本記事ではセクショナリズムが生まれる理由や企業に及ぼす弊害を追求します。またセクショナリズムの対策方法や実際の企業の取り組み事例についても解説します。
部署間の連携がうまくいってないと感じる方はぜひ最後まで読んで、解決のヒントとしてお役立てください。
セクショナリズムとは
セクショナリズムとは主に企業や組織の中で自分が所属するチームの利益だけを優先する状態を指します。
「自分がいるチームのことだけ考えていればよい」というマインドになるため、他の部署や会社全体の利益について配慮することが少なく、非協力的な姿勢になることも少なくありません。
特に縦割り組織や社内競争が苛烈すぎる会社で起きやすい考え方です。
縦割り組織の課題とその解決方法については、実際の企業事例を用いてYouTubeで解説しているのでぜひご覧ください。
2種類のセクショナリズム
セクショナリズムには大きく2つの種類が存在します。
以下でそれぞれの特徴を説明します。
無関心型・非協力型セクショナリズム
無関心型・非協力型セクショナリズムは、「自分が所属するチーム以外のことはどうでもよい」という考え方を指します。
そもそも他のチームについて関心がなく、協力を依頼されても面倒な気持ちが勝ってしまい積極的な姿勢を示すことがありません。逆に自分が所属するチームについては積極的で、自分事として考える性質が強いです。
そのため、チーム内での評価が高いが、他チームからは「影が薄くあまり目立たない人」と思われることも多いです。
批判型・排他型セクショナリズム
批判型・排他型セクショナリズムは、「自分が所属するチーム以外を排除しよう」という考え方を指します。
自分の立ち位置をより優位にしようとするあまり、他を蹴落とそうとする姿勢が強く現れます。
競争的な性格であるため個人の成果が重視される営業職などに適性がある一方、チームワークを大事にする職種には適性がありません。時には手段を選ばず行動してしまうこともあり、周りを傷つけてしまう可能性もあります。
セクショナリズムが生まれる理由
続いてセクショナリズムが生まれる理由を解説します。下記に該当する部分があれば、表面化していないだけでセクショナリズムが存在している可能性があります。
個人の性格だけでなく、組織の体制がセクショナリズムを生むケースもあるので、注意してチェックしてみましょう。
強い縄張り意識がある
部署間で強い縄張り意識があり、他部署からの関与やアドバイスを嫌う風潮が強いと、セクショナリズムの考え方が根付いてしまいます。
例えば、部署合同で行う会議の場で、経営層から「どの部署が担当なのか」「どの部署の責任なのか」と厳しく追及されるような状況があれば、各部署は自らの領域を守ろうとし、縄張り意識が強まりやすくなります。
同様に、部門ごとの権限が明確に分断されている組織体制では、部署間の壁が固定化され、縄張り意識の助長につながる可能性があります。
ジョブローテーションが少ない
ジョブローテーションが少なく、10年以上同じ部署で同じ働きをするだけの会社に在籍していると、どうしても視野が狭くなりがちです。
特定の分野に関する知識・経験に長けているプロフェッショナルであっても、全体を俯瞰して考える視点が身につかず、偏った意見になることも少なくありません。
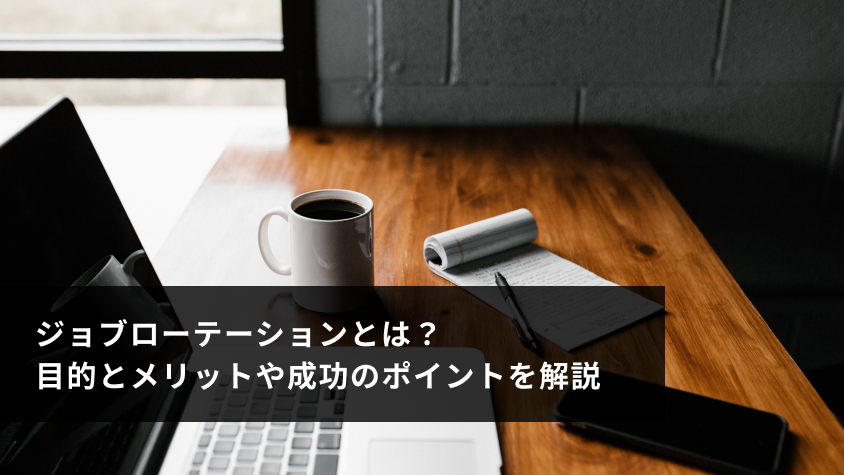
競争が生まれやすい評価制度が採用されている
部署同士・従業員同士の競争を評価し、実績の有無次第で厳しいインセンティブを与える企業には、セクショナリズムが根付きやすくなります。「自分がより優位に立つために他者を蹴落としてでも勝ち上がりたい」という気持ちが育ってしまうことも少なくありません。
また、相対評価だけによる給与査定なども、セクショナリズムの要因となることが多いです。
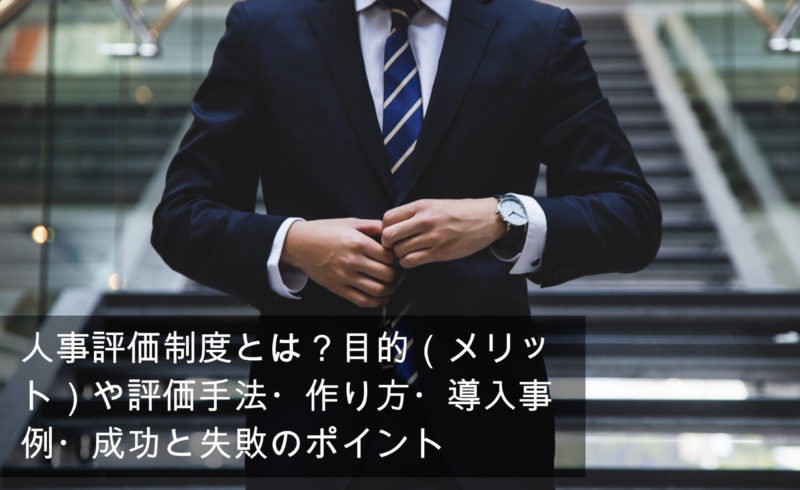
セクショナリズムが企業に及ぼす影響
セクショナリズムは企業にとって大きな弊害となります。
どのような弊害が起きるのか解説していきます。
同調圧力により組織が停滞する
セクショナリズムは同調圧力が強いという特徴があり、自分と意見の異なる人を徹底して排除しようとすることもあります。そのため同調圧力を感じた同僚・部下が意見を発信しづらくなり、組織が停滞してしまうことも少なくありません。
また、「反対意見を出すといじめに遭う」「常にイエスと言っていないと上司の機嫌が悪くなる」などマイナスのイメージが根付き、従業員がストレスを感じやすいでしょう。
部署間の対立や業務妨害に繋がる
セクショナリズムが強くなると、部署間での対立や業務妨害につながります。
部署ごとで仕事を押し付けあって非効率が生じたり、トラブルを「他部署のせいだ」と考えて責任逃れすることで、さらに大きな問題が生じる可能性もあります。また、他部署のミスに気づいていてもあえて見逃すこともあり、大きな対立を生むケースも出てくるでしょう。
これは部署間だけでなく、役職間・地域間・職種間でも同じようなことが起こり得ます。
生産性が低下する
自チームの利益を優先するあまり、組織全体の利益を追求できず、結果として総合的な生産性が下がるケースもあります。
非効率が生まれ、余計な残業や休日出勤が発生したり、クレーム対応にばかり時間と労力を割かざるを得なくなることもあるでしょう。
また、他部署の状況が把握できず、重複した設備投資が行われたり、異動を避けたいという理由で新たなチャレンジを避けるケースもあります。
顧客視点を見失いやすい
自分のことばかり考えてしまうセクショナリズムは、顧客視点を見失いやすく、企業全体への信頼を損ねる要因となります。例えばクレームが生じたときに「〇〇部署のせいだから」と放置することでどんどん対応が後手になり、二次クレームにつながることも少なくありません。
顧客は個人ではなく企業への信頼を重視することが多いので、次第に収益悪化などに発展してしまいます。
セクショナリズムの対策方法
先ほど紹介した弊害を防ぐための4つの対策を紹介します。
自社で取り組めそうなものはないか、ぜひ参考にしてみてください。
ジョブローテーションの実施
ジョブローテーションを実施し、色んな仕事・考え方・従業員に触れて視野を広げるのも効果的です。同じ事象でも部署や働き方次第で意見が異なることを理解しておけば、相手の話に自然と耳を傾けるようになるでしょう。
また、他部署で働く同僚の顔を認識することで、いざというときの連携やコミュニケーションが取りやすくなることもメリットです。
社内イベントの実施
部署の垣根を越えた交流を促すには、社内イベントの実施が効果的です。
全社を巻き込む合同会議や表彰式のような大規模なものから、部署間ランチやレクリエーション、社内報を活用した参加型企画など、気軽に取り組める小規模なイベントまでさまざまな形があります。
普段関わりの少ない社員同士が接点を持つことで、部署の枠を超えて協力しようとする意識が自然と醸成されていきます。

評価制度の見直し
評価制度を見直し、過度な競争を煽らないことも大切です。相対評価から絶対評価に切り替えて個々の良さを見つけるような評価体制にするとよいでしょう。
一方で、従業員のモチベーションを妨げることがないよう、一定以上の実績を出した人にインセンティブを与え、一律に与えるようにすれば過度な競争もなくなります。
企業理念や目標の共有
企業理念・目標を全体に共有し、経営層から新入社員まで同じ意識を持たせることも大切です。全体の方針をブレずに抱くことができれば、個人の利益だけでなく会社全体の利益を追及するようになるでしょう。
また、「部署は違っても同じ会社で働く仲間」という意識が育ち、協力的な姿勢を作りやすくなることもメリットです。従業員から共感されるような企業理念を描いて、エンゲージメントを向上させていきましょう。
セクショナリズム防止へ向けた企業の取り組み事例
最後にセクショナリズム防止へ向けた実際の企業の取り組み事例について紹介します。
自社にも活用できそうな事例はないかチェックしてみてください。
富士フイルムホールディングス株式会社
富士フイルムでは新入社員向けに3年間のジョブローテーション型研修制度を導入しています。期間中は研究開発、営業、品質管理、マーケティングなどの多様な業務を経験します。
これにより、部署を超えた関係構築力が身につくことはもちろん、新しい部署や未経験の業務でも戸惑うことなく、自ら考えて行動する姿勢も身に付きます。
URL:https://careers.fujifilm.com/graduates/growth/training.html
株式会社ロック・フィールド
国内300店舗を展開する株式会社ロック・フィールドでは、全国の販売スタッフが他部門への理解が進まないという課題を抱えていました。そこで全国の販売現場へ情報を届けるためにweb社内報を導入しました。
導入後は製造部門の商品へのこだわりや、販売スタッフが持つお客様の声を発信し合うことで、他部門への理解が進みました。その結果、互いの業務に反映できるようになり、より高品質な商品提供にもつながっています。
詳しくはこちらの記事で紹介しています。

アイリスチトセ株式会社
組織拡大に伴い縦割り意識が強まりつつあったアイリスチトセ株式会社では、部署間のつながりを再構築する手段としてweb社内報を導入しました。
「気になるあの人特集」や「サンクスリレー」などの企画を通じて、普段あまり関わらない社員の顔と名前がわかるようになり、声をかけやすくなりました。その結果、部署を越えた交流のきっかけが生まれ、大型プロジェクトもスムーズに進行するようになりました。
詳しくはこちらの記事で紹介しています。

自社に合わせた対策を
セクショナリズムは企業に様々な弊害を及ぼす危険な状態です。
ただ取り組み次第では、部門を超えて協力し合う組織文化を作ることは可能です。
本記事で一般的な対策方法から各企業の取り組み事例まで紹介しました。
ぜひ自社の課題や組織フェーズなど状況に合わせながら、対策を考えてみてください。