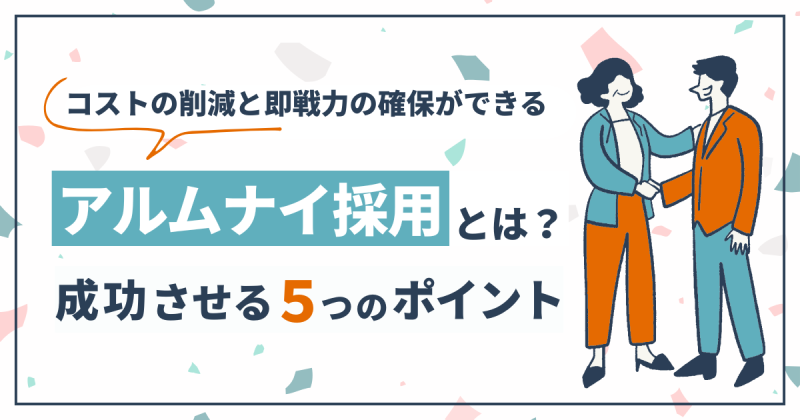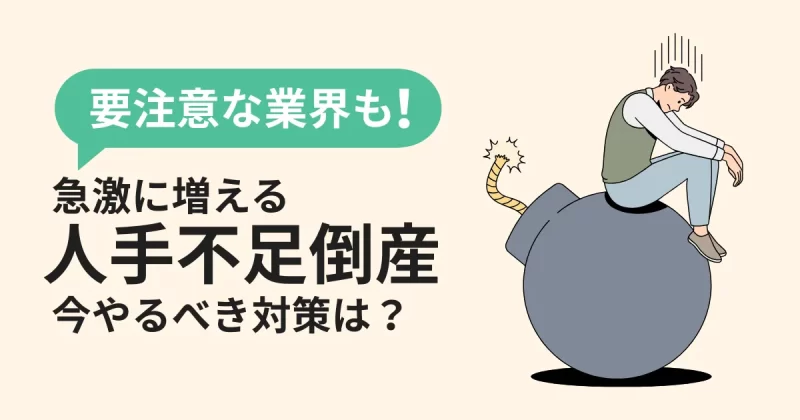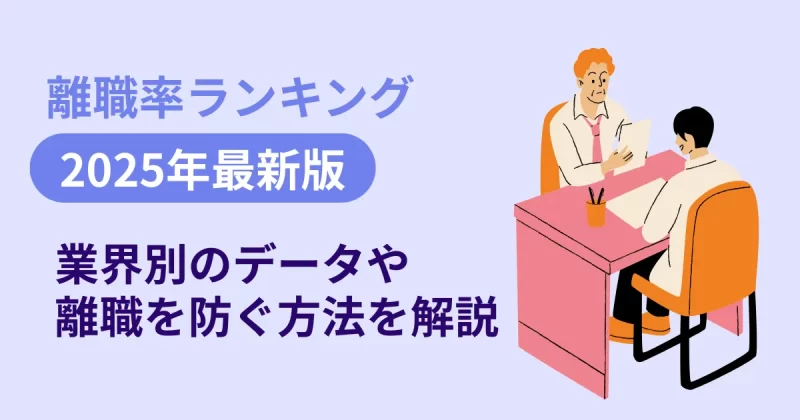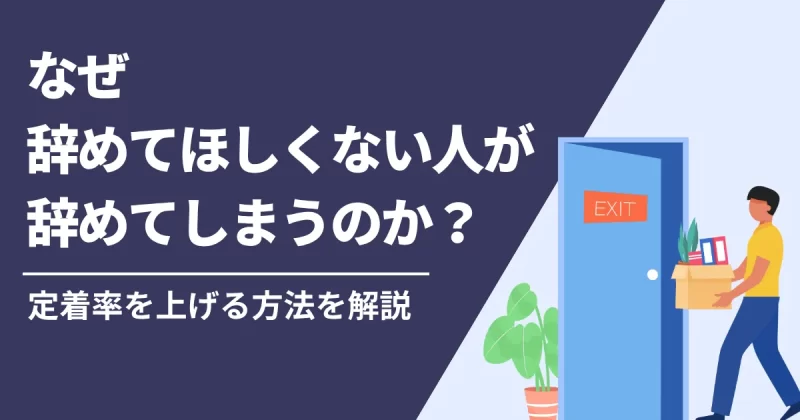近年、採用市場の競争が激化し、多くの企業が優秀な人材の確保に課題を抱えています。こうした状況の中、新たな採用手法として注目を集めているのが「アルムナイ採用」です。アルムナイ採用は、一度退職した元社員を再び雇用する取り組みであり、採用コストの削減や即戦力の確保といった多くのメリットが期待できます。
この記事では、アルムナイ採用の基礎知識から、具体的なメリット・デメリット、成功させるためのポイントまでを詳しく解説します。
アルムナイ採用とは?
アルムナイ採用とは、何らかの理由で自社を退職した元社員を、再び社員として雇用する採用手法のことです。単なる「出戻り」とは異なり、企業が戦略的に退職者とのネットワークを維持し、貴重な人材として再活用することに重きを置いています。
「卒業生」を意味するアルムナイ
「アルムナイ(alumni)」とは、もともとラテン語が語源で、「卒業生」や「同窓生」を意味する言葉です。ビジネスの文脈では、企業の「退職者」を指す言葉として使われるようになりました。
一度は企業を離れた人材も、外の世界で新たな経験やスキルを積んだ「卒業生」と捉え、企業にとって価値ある人的資産と考えるのがアルムナイの基本的な考え方です。
カムバック採用との違い
アルムナイ採用と似た言葉に「カムバック採用」や「出戻り制度」があります。これらも元社員を再雇用する点では同じですが、対象とする退職理由に違いが見られます。従来、カムバック採用は結婚や育児、介護といったやむを得ない事情で退職した社員を対象とすることが一般的でした。
一方、アルムナイ採用は、キャリアアップのための転職や起業など、よりポジティブな理由で退職した人材も対象に含む、より広範な概念です。
| 採用手法 | 主な対象となる退職理由 | 目的 |
| アルムナイ採用 | 転職、起業、独立、家庭の事情など全般 | 即戦力確保、新規ノウハウ獲得、ビジネス連携 |
| カムバック採用 | 結婚、出産、育児、介護、配偶者の転勤など | 離職者の復職支援、人材の定着 |
なぜ今アルムナイ採用が注目されるのか?
アルムナイ採用が近年注目を集めている背景には、日本の労働市場や働き方における大きな変化があります。企業が持続的に成長していくために、従来の採用手法だけでは対応しきれない課題が生まれているのです。
労働人口の減少と採用競争の激化
少子高齢化に伴い、日本の生産年齢人口は減少の一途をたどっています。これにより、多くの業界で人材不足が深刻化し、企業間の人材獲得競争は激しさを増しています。新卒採用はもちろん、中途採用においても優秀な人材を見つけることは容易ではありません。
こうした状況下で、自社の事業や文化をすでに理解しているアルムナイは、効率的に採用できる貴重な人材プールとして注目されています。
働き方の多様性とキャリア観の変化
終身雇用が当たり前ではなくなり、キャリアアップや自己実現のために転職を選択することが一般的になりました。一つの企業に勤め続けるのではなく、複数の企業や環境で経験を積むことがキャリア形成においてポジティブに捉えられるようになっています。
企業側も、こうした人材の流動化を受け入れ、一度は社外に出た人材が持つ新しい視点やスキルを、再び組織に取り入れることの重要性を認識し始めています。
人的資本経営への注目
近年、人材を「コスト」ではなく「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すことで企業価値の向上につなげる「人的資本経営」の考え方が広まっています。
退職者もまた、貴重な人的資本の一部であるという認識が強まりました。経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート2.0」でも、アルムナイとの継続的な関係構築の重要性が指摘されており、国としても企業がアルムナイネットワークを活用することを後押ししています。
参考:https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf
アルムナイ採用のメリット
アルムナイ採用を導入することは、企業にとって多くのメリットをもたらします。コスト削減といった直接的な効果だけでなく、組織文化にも良い影響を与える可能性があります。
採用・教育コストを大幅に削減できる
アルムナイ採用は、求人広告や人材紹介サービスを利用する必要性が低いため、採用にかかる外部コストを大幅に削減できます。また、アルムナイはすでに企業の理念や文化、業務内容を理解しているため、入社後のオンボーディング(研修や教育)にかかる時間と費用も最小限に抑えることが可能です。
一般的な中途採用に比べ、非常にコストパフォーマンスの高い採用手法と言えます。
ミスマッチを防ぎ即戦力を確保できる
通常の中途採用では、「入社前に抱いていたイメージと違った」というカルチャーフィットの問題や、「期待していたスキルと実際の業務内容が合わなかった」といったスキルフィットの問題が発生しがちです。
しかし、アルムナイ採用では、企業側も本人もお互いのことをよく理解しているため、こうした採用後のミスマッチが起こるリスクを大幅に低減できます。これにより、入社後すぐに活躍できる即戦力としての期待が高まります。
新しい知見やノウハウが社内にもたらされる
一度退職したアルムナイは、他社での勤務経験や起業などを通じて、新しいスキルや知識、人脈を獲得しています。彼らが自社に復帰することで、これまで社内にはなかった新しい視点や価値観がもたらされ、組織の活性化やイノベーションの創出につながる可能性があります。
外部の風を取り入れることで、既存の業務プロセスの改善や新規事業のヒントが生まれることも期待できるでしょう。
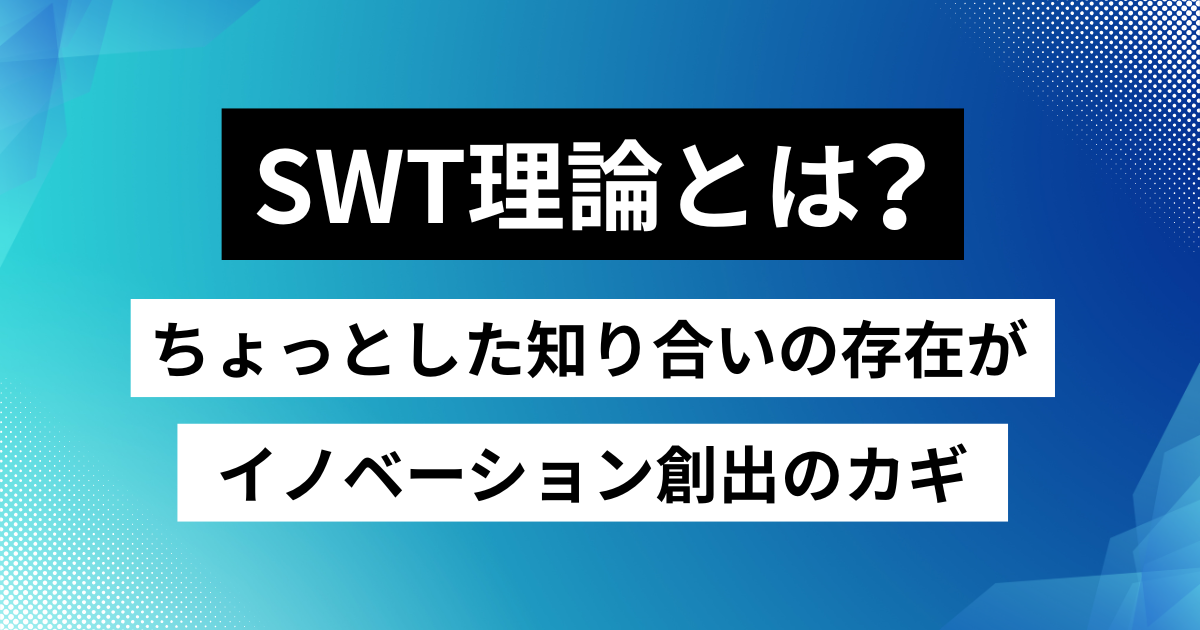
企業ブランディングとエンゲージメントが向上する
アルムナイ採用を積極的に行っている企業は、「一度辞めてもまた戻りたいと思える魅力的な会社」というポジティブなイメージを社外に与えることができます。これは企業のブランディング強化に直結します。
また、社内にいる既存社員に対しても、「会社は社員を大切にしている」というメッセージとなり、エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)の向上に繋がるでしょう。「いざとなれば戻ってこられる」という安心感が、社員の挑戦を後押しする効果も期待できます。
| メリット | 具体的な効果 |
| コスト削減 | 求人広告費や人材紹介手数料の削減、研修コストの低減 |
| 即戦力確保 | 早期の戦力化、採用ミスマッチの防止、定着率の向上 |
| 組織活性化 | 新規ノウハウ・人脈の獲得、イノベーションの促進 |
| ブランド向上 | 良好な企業イメージの構築、既存社員のエンゲージメント向上 |
アルムナイ採用のデメリット
多くのメリットがある一方で、アルムナイ採用には注意すべきデメリットも存在します。制度を導入する際には、これらのリスクを理解し、対策を講じることが重要です。
既存社員から不満が出る可能性がある
アルムナイが復帰する際、役職や給与などの処遇が、長年会社に貢献してきた既存社員との間で不公平感を生む可能性があります。
特に、アルムナイが高いポジションで復帰した場合、「なぜ一度辞めた人が優遇されるのか」といった不満やモチベーションの低下を招きかねません。処遇の決定に際しては、明確で公平な評価基準を設けることが不可欠です。
安易な離職を促進するリスクがある
「いつでも戻ってこられる」というアルムナイ制度の存在が、既存社員の離職に対するハードルを下げてしまう可能性があります。特に、明確なキャリアプランがないまま安易に退職し、うまくいかなかったら戻ればよい、と考える社員が増えることは避けなければなりません。
アルムナイとして再雇用されるためには、一定の条件や選考プロセスがあることを明確に周知し、制度の濫用を防ぐ必要があります。
再入社後の処遇や評価制度の整備が必要になる
アルムナイを再雇用するにあたり、その処遇をどうするかは慎重な検討が必要です。在籍期間を通算するのか、あくまで中途入社として扱うのかによって、給与や退職金の計算が変わってきます。
また、復帰後の役割や評価についても、本人の経験と会社の期待値をすり合わせ、双方が納得できるルールを事前に整備しておくことが、後のトラブルを防ぐために重要です。
アルムナイ採用を成功させるための5つのポイント
アルムナイ採用を効果的に運用し、企業とアルムナイ双方にとって有益なものにするためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらを意識して制度設計と運用を行うことが成功の鍵となります。
ポイント1:円満退職を前提とした関係性を築く
アルムナイ採用の最も重要な基盤は、社員が円満に退職することです。退職時に不満やしこりを残してしまうと、その後の良好な関係構築は望めません。
退職理由を真摯にヒアリングし、これまでの貢献に感謝を伝え、今後のキャリアを応援する姿勢を示す「イグジットマネジメント」が重要です。気持ちよく送り出すことが、将来の再会につながります。
ポイント2:退職後もつながりを維持する仕組みを構築する
退職者との関係を途切れさせないために、定期的に接点を持つ仕組みづくりが不可欠です。例えば、アルムナイ専用のSNSグループやメーリングリストを作成し、会社の近況やイベント情報を発信する方法があります。
また、アルムナイ向けの交流会やセミナーを定期的に開催し、継続的なコミュニケーションを図ることも有効です。こちらの記事ではアルムナイサービスの紹介をしているので、ぜひ合わせてご覧ください。
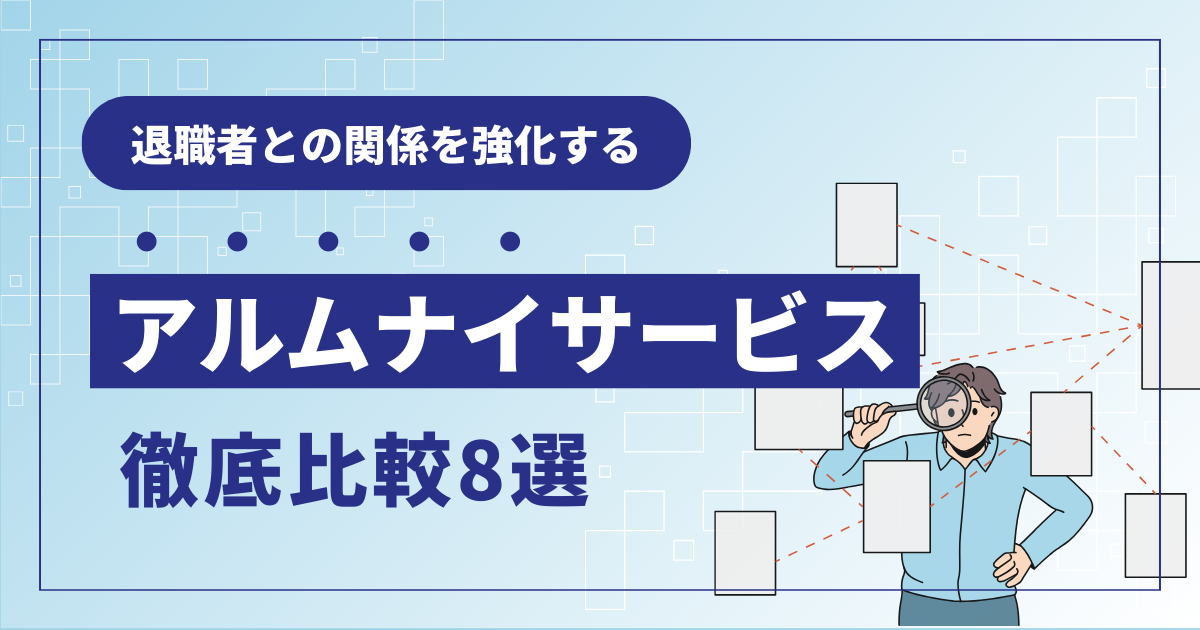
ポイント3:アルムナイ採用の制度を明確化し社内に周知する
どのような条件であれば再雇用が可能なのか、どのようなプロセスを経るのかといった制度のルールを明確に定めます。対象となる退職理由、必要な経験年数、復帰時の処遇などを具体的に設計し、社内規定として整備しましょう。
その内容を、退職を検討している社員だけでなく、全社員に広く周知することが、公平性と透明性の確保につながります。
ポイント4:アルムナイの受け入れ体制を整える
アルムナイが復帰する部署の理解と協力は不可欠です。「裏切り者」といったネガティブな見方ではなく、新たな価値をもたらしてくれる仲間として歓迎する雰囲気づくりが重要です。
受け入れ部署のマネージャーやメンバーに制度の趣旨を事前に説明し、スムーズな人間関係を築けるよう人事がサポートする必要があります。
ポイント5:柔軟な働き方やポジションを用意する
アルムナイの中には、フルタイム勤務が難しい人や、専門性を活かした業務委託のような関わり方を希望する人もいます。正社員としての再雇用だけでなく、時短勤務やリモートワーク、プロジェクト単位での契約など、多様で柔軟な働き方の選択肢を用意することで、より多くの優秀なアルムナイとの接点を生み出すことができます。
| 成功のポイント | 具体的なアクション |
| 円満な関係構築 | 丁寧な退職面談(イグジットマネジメント)の実施 |
| 継続的な接点 | アルムナイネットワーク(SNS、イベント)の構築・運営 |
| 制度の明確化 | 再雇用の条件・プロセス・処遇のルール化と社内への周知 |
| 受け入れ体制 | 既存社員への制度趣旨の説明と協力依頼 |
| 柔軟な働き方 | 時短勤務、リモートワーク、業務委託など多様な選択肢の提供 |
アルムナイ採用の導入事例
日本でも多くの企業がアルムナイ採用に積極的に取り組み、成果を上げています。ここでは代表的な2社の事例を紹介します。
トヨタ自動車株式会社の事例
トヨタ自動車では、2005年から「プロキャリア・カムバック制度」を導入しています。これは、配偶者の転勤や介護といったやむを得ない理由で退職した事技専門職以上の社員を対象とした制度です。
退職前に面談の上、再雇用申請を登録しておくと再雇用の申し出が可能という仕組みで、専門的なスキルを持つ人材がキャリアを中断することなく、再び活躍できる道を開いています。
参考:https://global.toyota/jp/detail/1468417
株式会社明治の事例
大手食品メーカーの明治では、2020年から「リ・メイジ制度」という名称でアルムナイ採用を開始しました。この制度は、正規従業員として3年以上勤務した退職者が対象で、専用ホームページから応募が可能です。同社は、アルムナイが社外で得た多様な経験や価値観が、企業に新たな風を吹き込み、成長の原動力になることを期待しています。
参考:https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2020/0123_01/index.html
こちらの記事ではアルムナイ採用を導入し、成果を上げている企業の事例を業界別に紹介しているので、ぜひ合わせてご覧ください。
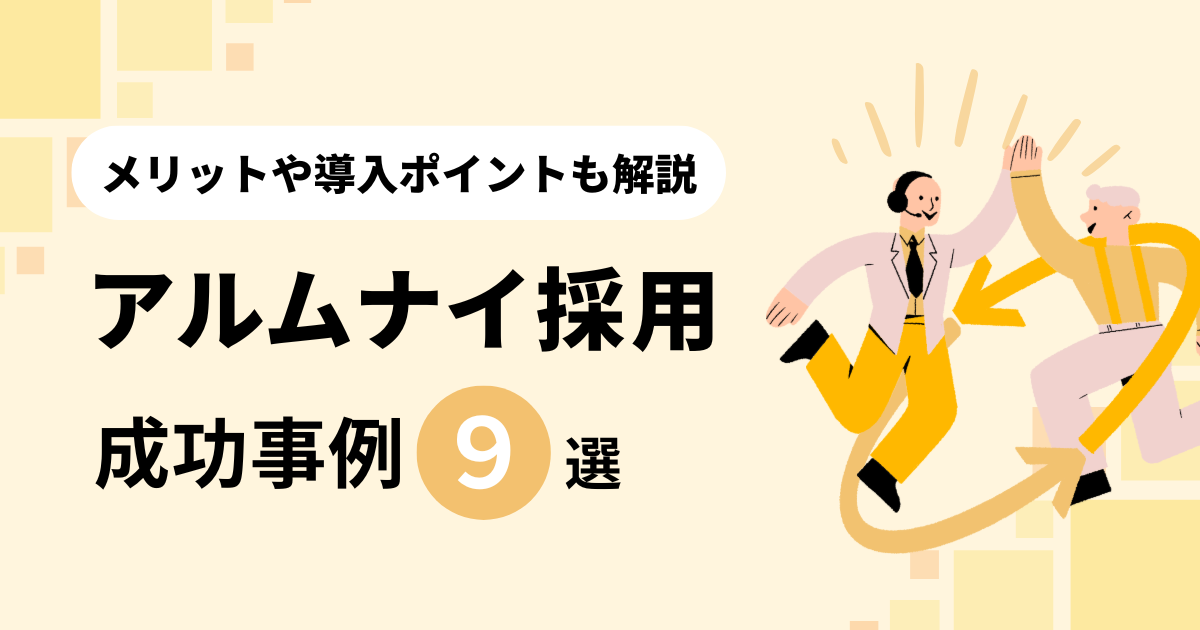
ourlyをアルムナイサービスとして活用する

ourlyは、web社内報とプロフィール機能を組み合わせることで、在籍社員とアルムナイ(退職者)とのつながりを継続・発展させられます。
- プロフィール機能
経歴・スキル・興味を可視化し、人となりやキャリアが一目でわかる。相談や案件連携もスムーズになる。 - web社内報
経営方針や部署の動き、新入社員の紹介といった情報を継続的に発信。アルムナイにも組織の動きを届け、心理的距離を縮める。
これらの機能により、在籍中から退職後まで一貫したつながりを支援します。
さらに「社外で得た知見を組織に還元」「リファラル採用の加速」など、持続的な関係構築を実現。
部署単位から全社展開まで、規模に応じた料金プランをご用意しています。
まとめ
アルムナイ採用は、人材獲得競争が激化する現代において、企業が競争力を維持し、成長を続けるための非常に有効な戦略の一つです。採用・教育コストの削減やミスマッチの防止といった直接的なメリットに加え、組織の活性化や企業ブランドの向上にも繋がります。
成功のためには、円満な退職のサポートから退職後の継続的な関係構築、そして公平で透明性の高い制度設計と社内の受け入れ体制の整備が不可欠です。本記事で紹介したポイントを参考に、自社にとって最適なアルムナイ採用の導入を検討してみてはいかがでしょうか。