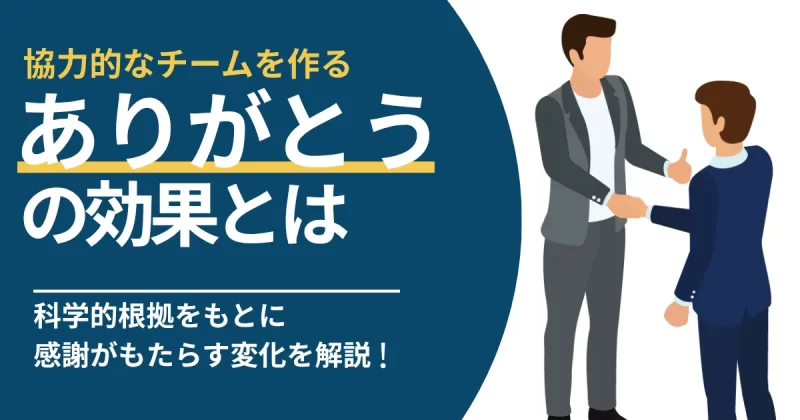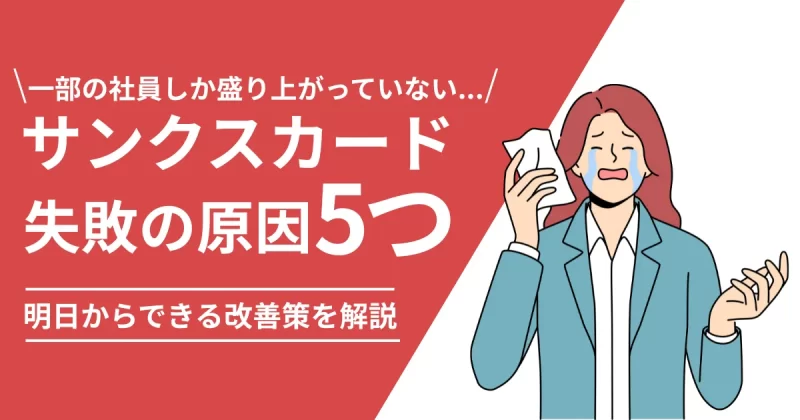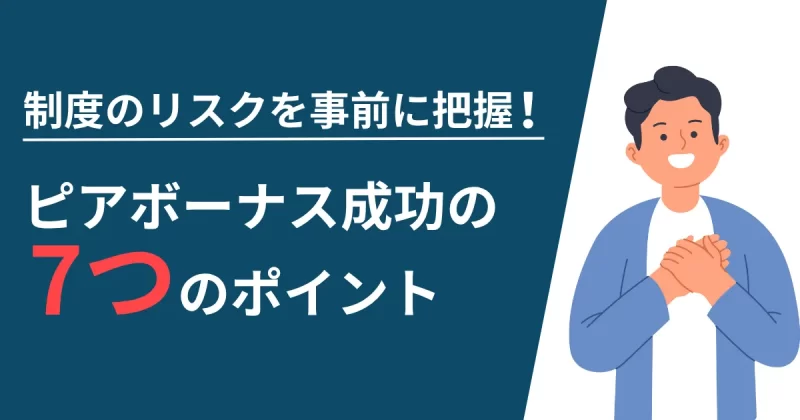組織の成果が上がらない、従業員の主体性が見られないといった課題に対し、短期的な施策を繰り返してはいないでしょうか。組織が継続的に成長するためには、目先の成果だけを追うのではなく、その土台となる従業員同士の関係性から見直すことが重要です。
そこで注目されているのが、マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム氏が提唱した「成功循環モデル」です。本記事では、成功循環モデルの基本的な考え方から、組織で実践するための具体的な方法までを分かりやすく解説します。
成功循環モデルとは?組織が成果を出し続ける仕組み
成功循環モデルは、組織が継続的に成果を上げ続けるために必要な要素とその関係性を体系的に示した組織開発のフレームワークです。多くの企業が組織開発にこのモデルを活用しており、その理論は「関係の質」「思考の質」「行動の質」「結果の質」という4つの要素で構成されています。
このモデルの最大の特徴は、良い結果を得るためには、まず「関係の質」から高めていくことが不可欠であると説いている点です。
マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム氏が提唱
この成功循環モデルは、マサチューセッツ工科大学(MIT)組織学習センターの共同創始者であるダニエル・キム氏によって提唱されました。 彼は、多くの組織が陥りがちな「結果ばかりを追い求め、かえって成果が出なくなる」という悪循環に着目し、持続的な成功を生み出す組織のメカニズムを明らかにしました。
一見すると遠回りに見える「関係の質」の向上が、最終的に良い結果をもたらすという考え方は、多くの組織開発の実践現場でその有効性が支持されています。
モデルを構成する「4つの質」とは
成功循環モデルは、組織の状態を4つの異なる「質」で捉え、それらが相互に影響を与えながら循環すると考えます。具体的には、「関係の質」「思考の質」「行動の質」「結果の質」の4つです。これらの質がどのように連鎖し、組織の成果に結びつくのかを理解することが、モデル活用の第一歩となります。
| 質の種類 | 概要 | 具体例 |
| 関係の質 | 従業員同士の相互理解や尊重、信頼関係の状態 | 挨拶、声かけ、オープンな対話、一体感 |
| 思考の質 | 物事の捉え方や考え方、意識の状態 | 当事者意識、ポジティブ思考、創造性、気づき |
| 行動の質 | 業務に対する主体性や積極性、行動の状態 | 主体的な行動、新しいことへの挑戦、協働、支援 |
| 結果の質 | 組織として生み出される業績や成果の状態 | 業績向上、生産性向上、顧客満足度、イノベーション |
関係の質:すべての土台となる人間関係
「関係の質」とは、組織のメンバー同士が互いを尊重し、信頼し合えているか、オープンなコミュニケーションが取れているか、といった人間関係の状態を指します。 これには、日々の挨拶や声かけといった基本的なコミュニケーションから、チームとしての一体感や信頼関係の構築までが含まれます。
この「関係の質」は、他の3つの質を生み出すための土台であり、成功循環モデルにおいて最も重要視される要素です。関係の質が低い状態では、従業員は萎縮し、自由な発想や行動が生まれにくくなります
思考の質:気づきや面白さが生まれる
「思考の質」とは、従業員一人ひとりの考え方や物事の捉え方、仕事に対する意識などを指します。 関係の質が高まり、従業員が安心して意見を言えるようになると、対話の中から新しい気づきや仕事の面白さが生まれます。
これにより、物事を前向きに捉えたり、当事者意識を持って課題を考えたりするようになり、「思考の質」が向上するのです。思考の質が高い組織では、従業員は受け身ではなく、自ら考えてアイデアを生み出すようになります。
行動の質:主体的・積極的に仕事に取り組む
「行動の質」とは、従業員がどれだけ主体的かつ積極的に行動しているかを示します。思考の質が高まり、仕事に対する面白さや意義を見出すと、従業員は自発的に新しいことに挑戦したり、他者と協力して仕事を進めたりするようになります。これが「行動の質」の向上です。
行動の質が高い組織では、従業員は指示を待つのではなく、自ら課題を見つけて改善策を実行するなど、活発な動きが見られます。
結果の質:組織としての成果
「結果の質」とは、これら3つの質が高まった結果として表れる、組織全体の業績や成果を指します。 生産性の向上や業績の達成、イノベーションの創出などがこれにあたります。重要なのは、この結果の質は他の3つの質の向上によって「もたらされるもの」であるという点です。
そして、良い結果が生まれることで、従業員は達成感や自信を得て、互いを称賛し合うようになり、それがさらなる「関係の質」の向上へとつながっていくのです。
組織の明暗を分けるグッドサイクルとバッドサイクル
成功循環モデルでは、4つの質が循環する方向によって、組織が良い方向へ向かう「グッドサイクル」と、悪い方向へ向かう「バッドサイクル」の2つの状態があると考えられています。この2つのサイクルの違いは、サイクルの起点がどこにあるかという点です。
組織を健全に成長させるためには、グッドサイクルを回すことを意識的に目指す必要があります。
グッドサイクル:関係の質から始める好循環
グッドサイクルは、「関係の質」を高めることから始まります。 まず、従業員同士が互いを尊重し、オープンに対話できる環境を整えます。すると、そこから新しいアイデアや気づきが生まれ、「思考の質」が高まります。次に、従業員は自発的に行動を起こすようになり、「行動の質」が向上します。
その結果として、業績向上などの「結果の質」が高まります。そして、得られた成果によって従業員同士の信頼関係がさらに深まり、より強固な「関係の質」へとつながる、という好循環が生まれるのです。
バッドサイクル:結果の質から始める悪循環
一方、多くの成果の出ない組織が陥りがちなのがバッドサイクルです。 これは、目先の「結果の質」を性急に求めることから始まります。結果を出すために従業員にプレッシャーをかけ、行動を管理しようとすると、従業員同士の対立や責任のなすり付け合いが生まれ、「関係の質」が悪化します。
関係性が悪くなると、従業員は指示待ちで受け身になり、「思考の質」が低下します。そして、自発的な行動は失われ、「行動の質」も低下し、最終的に望んだ成果が得られず、「結果の質」も下がってしまうという悪循環に陥るのです。
成功循環モデルを組織に導入するメリット
功循環モデルを理解し、組織運営に活かすことには多くのメリットがあります。組織が抱える課題を根本から解決し、持続的な成長を遂げるための土台を築くことができます。
組織の現状を客観的に把握できる
成功循環モデルのフレームワークを活用することで、自社の組織が現在どのような状態にあるのかを客観的に分析できます。 「関係」「思考」「行動」「結果」の4つの質の観点から課題を整理することで、問題の根本原因がどこにあるのかを特定しやすくなるでしょう。
例えば、「結果が出ていない」という問題の根本原因が、実は「関係の質」の低さにある、といった気づきを得ることができます。
従業員のエンゲージメントが向上する
グッドサイクルを回す取り組みは、従業員のエンゲージメント向上に直接的につながります。 従業員同士の信頼関係が深まり、自分の意見が尊重される環境では、仕事に対するやりがいや組織への貢献意欲が高まります。
結果として、従業員は自らの能力を最大限に発揮しようと努力するようになり、離職率の低下にもつながるでしょう。

コミュニケーションが活性化し組織風土が改善する
成功循環モデルは「関係の質」を重視するため、導入プロセスそのものがコミュニケーションの活性化を促します。 従業員同士の対話の機会が増え、相互理解が深まることで、組織全体の風通しが良くなります。
これにより、部署間の壁が低くなったり、建設的な意見交換が活発に行われたりするなど、組織風土そのものがポジティブに変化していくことが期待できるでしょう。
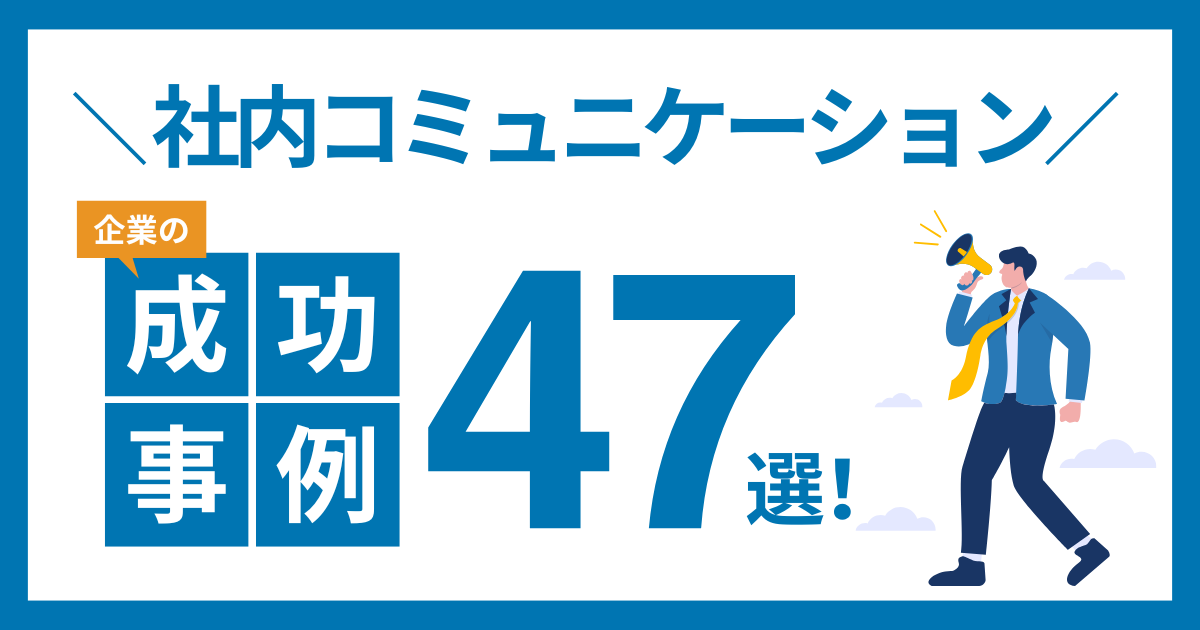
変化に強い柔軟な組織が育まれる
グッドサイクルが回っている組織では、従業員が自ら考え、主体的に行動することが習慣化されています。 このような状態は、予測困難な市場の変化や新たな課題に直面した際に、組織としての柔軟な対応力を生み出します。
トップダウンの指示を待つのではなく、現場の従業員が自律的に判断し、協力し合うことで、変化に迅速かつ的確に対応できる強い組織が育まれるのです。
成功循環モデルのグッドサイクルを回す具体的な方法
成功循環モデルの理論を理解した上で、実際に組織でグッドサイクルを回していくためには、それぞれの「質」を高めるための具体的なアプローチが必要です。ここでは、グッドサイクルの起点となる「関係の質」から順番に、各質を高めるための具体的な方法を紹介します。
関係の質を高める:心理的安全性を確保する
グッドサイクルの第一歩は、「関係の質」を高めることです。そのためには、従業員が「この組織では何を言っても大丈夫だ」と感じられる「心理的安全性」の確保が不可欠です。
具体的には、会議で全員に発言機会を設けたり、どのような意見が出ても頭ごなしに否定しないといったルールを徹底したりします。また、1on1ミーティングなどを通じて上司が部下の話を傾聴し、個々の状況や考えを理解しようと努めることも、信頼関係の構築につながります。
思考の質を高める:組織の目標やビジョンを共有する
良好な関係性が築けたら、次は「思考の質」を高める段階です。 これには、組織がどこへ向かっているのか、その目的やビジョンを従業員全員で共有することが重要です。会社の目標と自分の業務がどのようにつながっているのかを理解することで、従業員は当事者意識を持ち、自らの頭で考えるようになります。
SMARTの法則などを用いて、具体的で分かりやすい目標を設定し、それを繰り返し共有する場を設けることが効果的です。
行動の質を高める:称賛される行動を発信する
思考の質を高めたうえで、それを「行動の質」へとつなげるには、従業員にとって具体的なロールモデルが必要です。どんな行動が組織に貢献し、評価されるのかを知ることが、主体的な行動のきっかけになります。
そのために有効なのが、社内広報を通じて誰かの活躍を取り上げ、称賛を文化することです。身近な同僚の成功事例や努力が発信されることで、他の従業員も「自分もやってみよう」と前向きな行動を取りやすくなります。
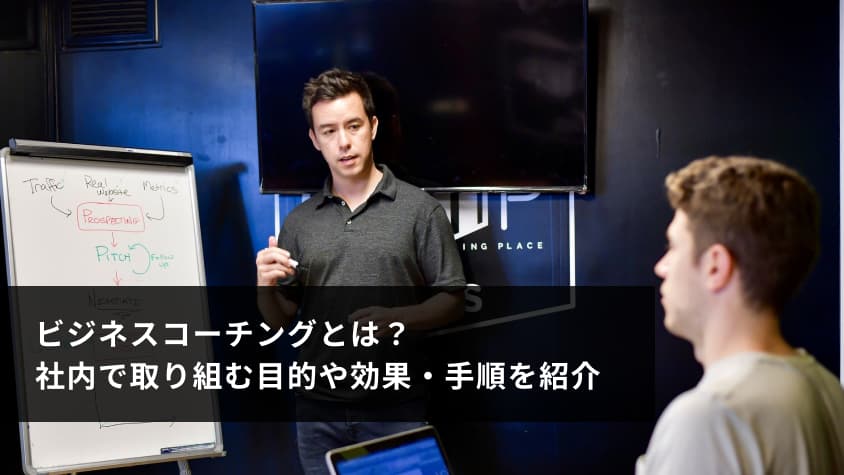
結果の質を高める:行動プロセスを評価に含める
最後の「結果の質」については、成果そのものだけでなく、そこに至るまでの行動プロセスも評価の対象とすることが重要です。 たとえ目標が未達だったとしても、新しい挑戦をしたことや、チームに貢献した行動などを正しく評価する仕組み(バリュー評価など)を取り入れます。
これにより、従業員は失敗を恐れずに挑戦するようになり、それが次のグッドサイクルへとつながっていくのです。
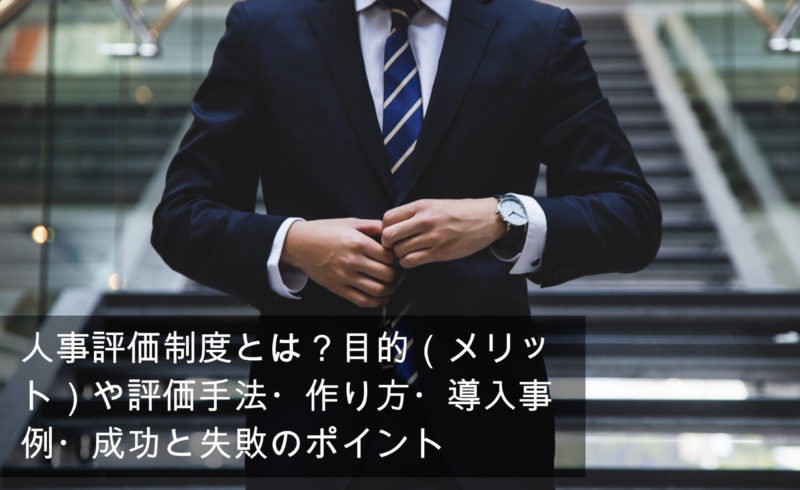
web社内報を用いて「関係の質」を起点に組織改善を進めた事例
成功循環モデルのグッドサイクルは、「関係の質」を高めることから始まります。そこで有効なのが、社員同士の活動や想いを可視化できるweb社内報です。ここでは、実際にweb社内報を導入し、関係性を起点に組織改善を進めた2社の事例を紹介します。
株式会社GENDA GiGO Entertainment
国内外で350店舗以上のアミューズメント店舗を展開する同社は、M&Aにより多様な文化を持つ組織が一体となる中、従来の社内ポータルでは一方通行の情報発信に限界を感じていました。そこで双方向でスピード感あるやり取りを実現するため、web社内報を導入しました。
店舗スタッフから本社まで幅広い層が気軽に読めるフランクな記事や役員全員のインタビュー記事などを通じて、記事の内容をきっかけにしたコミュニケーションや記事を執筆したいという社員が増えました。
また海外拠点の立ち上げに従事している社員のヘルプに行く社員が増えるなど行動の変化も表れました。まさに「関係の質」を高めることが、新しい行動や挑戦の連鎖につながった好例です。

マックス株式会社
小型ホッチキスで有名な同社は、コロナ禍で対面でのコミュニケーションの機会が減る中で、より社員の結びつきを強め、いきいきと働く社員を増やしたいと思い、web社内報を導入しました。
社員にフォーカスした記事を中心に発信することで、普段接点の少ない社員や経営層への理解が深まり、他部署の方ともコミュニケーションが取りやすくなりました。結果的にチームのメンバーに対する親近感や会社、仕事への愛着心も高まりました。

関係性の質を高めて組織改善するならweb社内報ourly

ourlyは、組織改善に特化したweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」や「web社内報を活用して組織改善したい」という方におすすめのweb社内報ツールです。
成功循環モデルを実践する際の注意点
成功循環モデルは強力なフレームワークですが、その考え方を誤って解釈すると、意図しない結果を招く可能性があります。モデルを実践する際には、いくつかの注意点を理解しておくことが重要です。
「ぬるま湯組織」との違いを理解する
「関係の質」を高めることを重視するあまり、単に仲が良いだけの「ぬるま湯組織」になってしまうことがあります。 成功循環モデルが目指す良好な関係性とは、言うべきことを言い合い、互いに切磋琢磨できる建設的な関係です。
意見の対立を恐れず、より良い成果のために率直な議論ができる環境こそが、真に関係の質が高い状態と言えます。馴れ合いの関係ではなく、適度な緊張感を保つことが重要です。
管理職の役割が成功の鍵を握る
成功循環モデルを組織に根付かせる上で、管理職の役割は極めて重要です。 管理職自身がモデルを深く理解し、日々のマネジメントにおいて実践することが求められます。部下の話を傾聴し、心理的安全性を確保し、適切な目標設定を支援するなど、グッドサイクルを回すためのハブとなるのが管理職です。
そのため、管理職向けの研修を実施するなど、組織として管理職の意識とスキルを高めるための支援が不可欠です。
まとめ
成功循環モデルは、組織が持続的に成果を上げていくための普遍的な原則を示しています。目先の「結果の質」だけを追うのではなく、全ての土台となる「関係の質」から着実に高めていくことが、組織を好循環へと導く唯一の道です。
本記事で紹介した具体的な方法を参考に、自社の組織を見つめ直し、グッドサイクルを回すための第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。