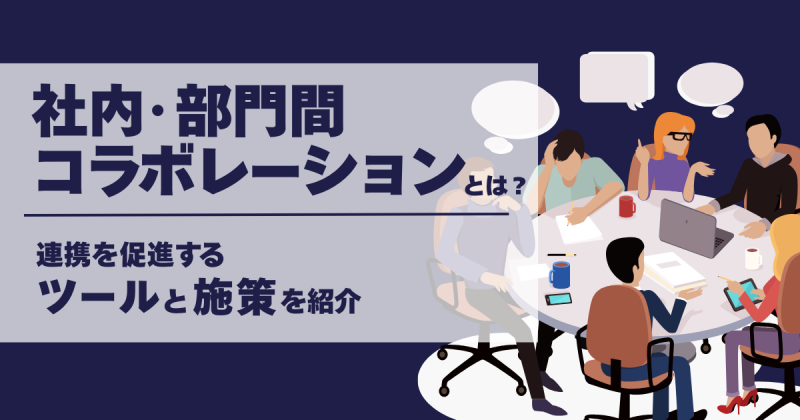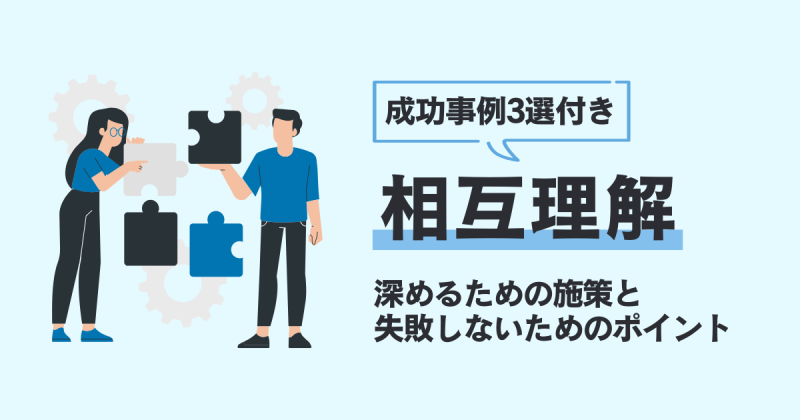コロナをきっかけに出社や社内イベントが減少したことで、部署内外のつながりが希薄になっている企業が増えています。こうした背景から、部署や職種を越えた「社内コラボレーション」の重要性がますます高まっています。
また、「情報が共有されない」「業務が属人化している」といった課題も、チーム間の連携によって解決できるかもしれません。
本記事では、社内コラボレーションをおこなうことで得られるメリットや施策、成功事例をご紹介します。
社内コラボレーションとは?
社内コラボレーションとは、部署や役職の垣根を越えて社員同士が協力し、共通の目的に向かって取り組むことを指します。
たとえば、営業と開発が連携して新サービスを企画したり、店舗スタッフと本部が一体となって現場オペレーションの改善に取り組んだりするような部門を横断した取り組みです。
- リモートワークの普及で社内で連携が取りづらい
- プロジェクトごとにチームが編成されるため組織への帰属意識が低い
- 部署同士が独立して動いているため、全社でナレッジが共有されない
といった組織の課題を解消するためにも、社内コラボレーションの重要性が高まっているのです。
社内コラボレーションがもたらす8つのメリット
では、社内コラボレーションによって得られるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
代表的な8つのメリットをご紹介します。
業務の効率化・生産性の向上
部門間の連携によって業務の重複や調整の手間が減り、作業工程がスムーズになります。
特に、各部門の強みを組み合わせて役割分担することで、限られたリソースでも高い生産性を実現できます。
ノウハウやナレッジ共有の促進
部門を越えて連携することで、個人や部署・部門内に留まっていたナレッジを共有し、活用できます。
自分たちの知識では行き詰まっていた業務に対しても、他部署のナレッジによって解決のヒントが得られるかもしれません。
イノベーションの促進
ナレッジの共有や、コラボレーションをきっかけにしたコミュニケーションによって、今までにはなかった多様な視点が交わります。
それにより、新しい発想や価値が生まれやすくなるため、イノベーション創出の可能性が高まります。

組織文化・一体感の強化
他の部門や部署とコラボレーションを活発におこなうことで、ノウハウやナレッジを共有し合ったり、それによるイノベーションが起こりやすい文化が醸成されます。
社内でそれが「当たり前」になると、自然と他の部門や部署とのつながりを意識するようになり、組織として一体感が生まれます。

従業員エンゲージメントの向上
自分の仕事が他部門とつながっていると実感できると、自分の仕事は意味のあるものだという認識が高まり、エンゲージメントが高まります。
また、組織や同僚に対する理解が互いに深まることによって帰属意識が高まり、「自分は組織に貢献している」と感じやすくなります。
結果として従業員のエンゲージメントが高まり、人材の定着率向上にもつながります。

サービス品質の向上
他部門と連携することで、顧客の課題や要望に対して、迅速かつ的確に対応できます。
また、製品やサービスの開発・提供においても、顧客ニーズを反映できたり、製品のこだわりを伝えたりすることができます。

業績・競争力の向上
社内コラボレーションが進むと、意見がまとまりやすくなり、組織としての対応や展開がスピーディかつ的確になります。その結果、社会の変化にも柔軟に対応できるため、企業全体としての成果や市場での存在感が高まっていきます。
社内コラボレーションを円滑にする8つの施策
ここでは、社内コラボレーションをより円滑におこなうための施策を紹介します。
コラボレーションを円滑にするための大前提として、社内のコミュニケーションを活性化することがとても重要です。
具体的にどんな取り組みをすればいいか分からない、今実行している施策以外の可能性を模索したい場合に、お役立てください。
社内イベント
新年会・忘年会・運動会・誕生日パーティー・バーベキューなど、社内イベントを開催する方法です。
部署を超えた参加メンバーの選定がしやすく、普段コミュニケーションを取る機会が少ない部署の人とも会話しやすくなるでしょう。
また、オフィス以外でおこなわれることが多いため、業務外のコミュニケーションも活発になり、その人の価値観や趣味といった人となりの理解につながります。結果的に、業務における部門間の連携も円滑に進むでしょう。
家族の話・趣味の話など、フランクにお互いの情報を交換する場として最適です。

社内報
社内報は、経営者からのメッセージをトップダウンで周知させたり、経営の方向性について共通認識を設けたりしたいときに便利です。
場所を選ばずいつでも誰でも閲覧できるため、複数の拠点を持つ会社とも相性がよいでしょう。
また、社員インタビューやプロジェクト紹介など、コンテンツを充実させれば会話のきっかけとしても効果的です。
自社のことをより詳しく知らせつつ、コミュニケーション活性化の施策も取りたい場合は、社内報の導入を検討してみましょう。
社員面談
上司と部下が定期的に面談することで、普段は言いづらいことも言えるような場を作れます。
人事評価・賞与評価時のフィードバック面談とは異なり、お互いフランクに発言する場としてイメージするのがよいでしょう。
そのため、月に2~3度程度、頻度を高めに実施することがポイントです。
仕事上発生している悩みやプライベートでの困りごとなど、幅広く対話できるきっかけにもなるでしょう。
社員研修・ワークショップ
社員研修を開催し、社員のスキルアップを図りながらコミュニケーションを活性化させる方法です。
一方的なノウハウ指導だけでなく、ワークショップやグループディスカッションを導入し、社員が発言するきっかけを作るとよいでしょう。
それぞれが持っている意見や理想を把握しやすく、知らなかった一面を知ることも可能です。
また、管理職研修・入社3年目研修・IT部門研修など、フェーズを分けて開催するのもよいでしょう。
自分と似たようなポジションにいる社員と交流することで、相談相手を見つけやすくなります。
コミュニケーション研修に関してはこちらの記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。

社内サークル・部活
社内サークルや部活を設け、業務外のコミュニケーションをするのもよいでしょう。
共通する趣味があれば、普段関わるのことが少ない社員とも親睦を深められます。
経営層が好むサークルだけにならないよう、運動系・音楽系・アウトドア系・インドア系など、複数のジャンルでサークルを設けるのが理想です。
ときには、大会のようなイベントを実施するのもおすすめです。
ひとつの目標に向かって全員で努力することができれば、社内コラボレーションでも良い効果が得られるでしょう。
フリーアドレス制度
フリーアドレス制度とは、自席を固定せず、その日によって仕事をする席を変える方法です。
席を固定することで、自分と関連性の高い社員とコミュニケーションが取りやすくなるメリットが得られる一方、特定の人としか会話しなくなるというデメリットが生じます。
ランダムで席を指定するような制度を導入すれば、このデメリットも解消されるでしょう。
部署の壁を取り払ってコミュニケーションしたい企業には、特におすすめです。
社内コミュニケーションツールの導入
チャット・オンラインミーティング・グループウェアなど、社内コミュニケーションツールを導入する方法もあります。
ノウハウやナレッジを共有して社内情報格差の是正に取り組んだり、働く地域や場所に縛られずコミュニケーションを取ったりすることが可能です。
議論も活性化しやすく、パフォーマンス向上戦略としても有効でしょう。
引継ぎの手間やミスコミュニケーションをなくすという意味でも、一定の効果がありそうです。
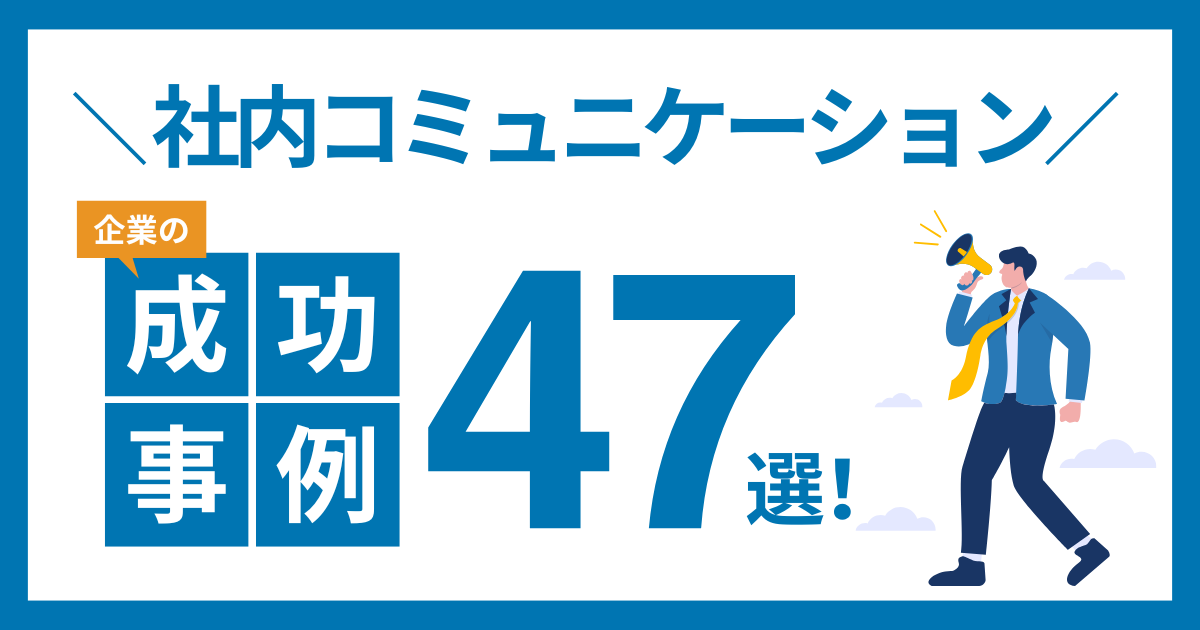
社内コラボレーションの成功事例3選
次に、社内コラボレーションによって成果が出た事例をご紹介します。
アイリスチトセ株式会社
アイリスチトセ株式会社では、急成長にともなう組織の縦割り化が進んだことで、部署間の連携に課題が生まれました。
そこで社内報を用いて、インタビュー記事を発信し、社員紹介や部署紹介をおこないました。
他部門への理解が深まったことで、営業と品質管理など部門同士の連携が強まり、大型プロジェクトでもスムーズに遂行しました。

株式会社GENDA GiGO Entertainment
株式会社GENDA GiGO Entertainmentでは、各店舗における業務改善のスピードが上がらないという課題がありました。
とくに店舗運営においては「店長→SV→本社→店舗」の流れで改善施策が決定するので、半年以上の時間がかかってしまうこともあります。
そこで社内報を用い、店長が主体となって自店舗の改善施策の事例を共有しました。
すると、全国の店舗間でノウハウの共有が進み、業務の改善スピードを上げることができました。

株式会社インフォマート
株式会社インフォマートでは、組織の拡大化にともなう縦割り化から、全社の動きを把握するための横串の情報共有が不足していました。
そこで、社内報で部門の紹介や社内イベントの様子を記事化して発信しました。
記事をきっかけに社内イベントに参加する社員が増えたことで、横のつながりが広がりました。
その結果、業務に関する相談やヒアリングがしやすくなり、部署を超えた情報共有が進みました。

社内コラボレーションを円滑にするツール6選
社内報
企業内での情報共有や理念浸透を目的とした広報媒体です。紙やPDFで配布されることが一般的でしたが、近年では、更新性や双方向性に優れた「web社内報」が主流となり、社員のエンゲージメント向上や組織内コミュニケーションの活性化に活用されています。
社内SNS
チャットや投稿によって、社員同士が気軽に情報交換や雑談をおこなえるコミュニケーションツールです。リアルタイム性が高く、気軽にやり取りができるため、情報共有のハードルが下がります。
ただし、情報が流れやすいため、検索性や発信ルールを整えないと「流れて終わる」リスクもあります。
社内Q&Aプラットフォーム
業務の疑問やノウハウを投稿・回答する社内版「知恵袋」のようなツールです。部署を超えて知識や経験が共有されることで、属人化の防止とナレッジの蓄積につながります。
ただし投稿や回答が活発になるには、気軽に質問しやすい文化づくりや回答しやすい制度づくりが必要です。
社内タスク・プロジェクト管理ツール
タスクや進捗状況を部署横断で可視化・共有できる、業務のコラボレーション支援ツールです。役割分担が明確になり、複数部門での連携や調整が効率的におこなえます。
ただし、運用ルールや更新の習慣がないと“形骸化”につながることもあります。
バーチャルオフィスツール
仮想空間上で社員が集まり、会話や雑談ができるツールです。リモート環境でも、話しかけるきっかけを作ることができ、思わぬコラボレーションに繋がります。
ただし、導入初期は「なにをどう操作すればいいのかわからない」と戸惑う人も多いため、操作方法や利用の仕方におけるサポート体制を整えることが重要です。
ナレッジ共有ツール
社内の情報・ノウハウを蓄積・共有するためのツールです。成功事例やFAQを全社的に活用でき、同じ問題を繰り返さない仕組みづくりに役立ちます。
ただし、情報が古くなる・更新が止まると意味がない点で、運用体制と整理ルールが重要です。
社内コラボレーションの円滑化に ourly を
ourlyは、コミュニケーションを意図的に促進させるweb社内報ツールです。
- コミュニケーションの心理的ハードルが下がるリアクション、コメント機能
- 社内のコミュニケーションを可視化できる分析機能
- web社内報をきっかけに社内コミュニケーションが活性化するアイデアを提案するサポート体制
これらの独自の強みによって、社内コミュニケーションの活性化を実現し、より円滑な社内コラボレーションを手助けします。
コミュニケーションを加速させるコメント/リアクション機能
ourly独自の「段落ごとにできるリアクション機能」によりコミュニケーションのハードルを下げて、書き手と読み手の双方向的のなコミュニケーションを実現できます。
段落ごとに「いいね」「もっと知りたい」を気軽に押せる・コメントができます。
またオプションのプロフィール機能を活用すれば、人となりの理解や共通点の発見、誰が何を知っているか(know who)の可視化が促進されます。
相互理解に留まらず、業務に役立つコミュニケーションも生み出せます。
またオプションのプロフィール機能を活用すれば、人となりの理解や共通点の発見、誰が何を知っているか(know who)の可視化が促進されます。
相互理解に留まらず、業務に役立つコミュニケーションも生み出せます。
専門コンサルティングチームによる伴走支援体制
ourly利用企業の支援を通じて蓄積した、豊富なweb社内報の活用事例・運用ノウハウをもとに専門コンサルティングチームが伴走支援。
リリース前には課題ヒアリングを通じて、定性/定量の目標設計をおこない、リリース後は分析レポートを用いた定例ミーティングを毎月実施。効果検証と次の施策ディスカッションをおこないます。
専門コンサルティングチームのサポートにより、よりオフライン施策の効果を最大化する社内報運用が実現でき、双方向コミュニケーションの活性化が可能です。
さらに、社内報の記事作成代行や導入時の全社説明会の実施、社員へのライティング研修など、さまざまな支援策を提供しています。
社内コラボレーションをつくろう。
部署や役職などの領域を超えて社員同士が協力し合う「社内コラボレーション」により、ナレッジ共有の促進やイノベーションの促進、一体感の強化など、さまざまなメリットが得られます。
そして、社内コラボレーションを実現するには、お互いにコミュニケーションが取れる土台が必要です。
自社の課題に適した施策やツールの導入を通じて、社内コラボレーションを実現しましょう。