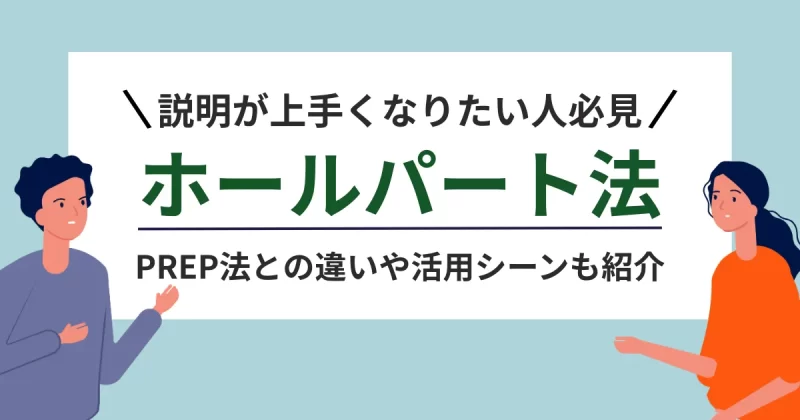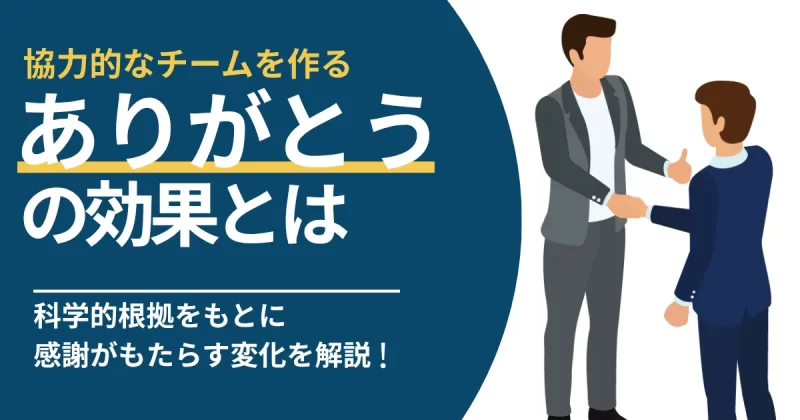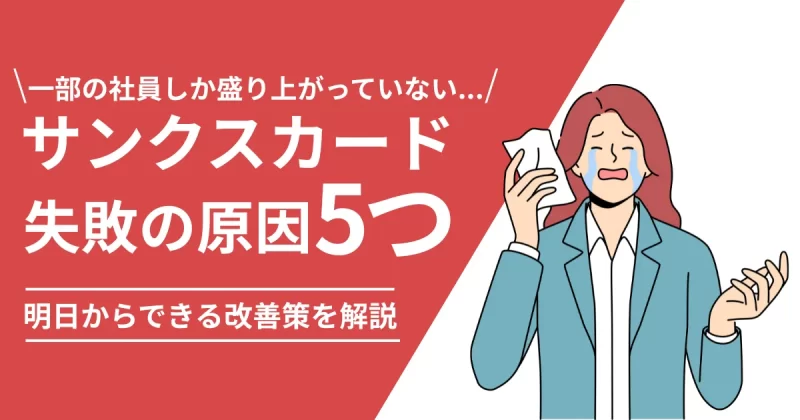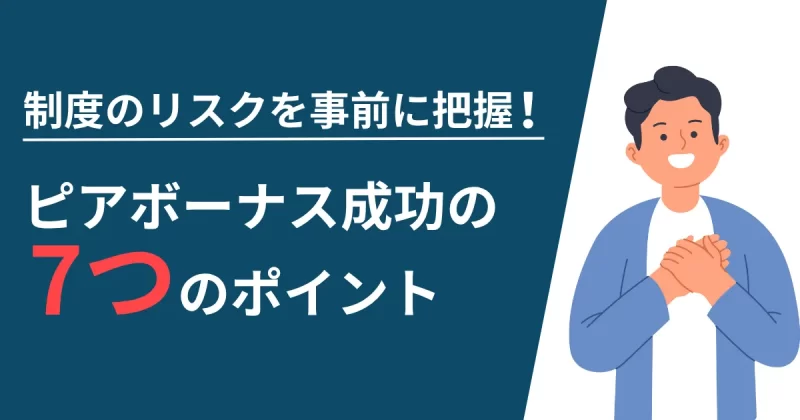「結局、何が言いたいの?」と、会議やプレゼンテーションの場で、聞き手を混乱させてしまった経験はありませんか。
良かれと思って詳細に説明すればするほど、かえって話が複雑になり、要点が伝わらなくなってしまうのは、ビジネスシーンでよくある課題です。
その課題を解決する強力な武器が、今回ご紹介する「ホールパート法」です。
ホールパート法は、話の全体像から伝えることで、聞き手の理解を飛躍的に高めるコミュニケーションのフレームワークです。この記事では、ホールパート法の基本的な考え方から、PREP法との違い、具体的な活用シーンまで、分かりやすく解説します。
ホールパート法とは?分かりやすい説明の基本となる思考法
ホールパート法は、効果的なコミュニケーション、特に説明の場面で力を発揮するフレームワークの一つです。
名前の通り、「全体(Whole)」と「部分(Part)」を意識した構成で、聞き手の理解を促します。
具体的には、まず話の「全体像」を提示し、次にその全体像を構成する「各部分」を詳細に説明、最後に再び「全体像」をまとめて締めくくるという流れを取ります。
| 構造 | 説明 | 聞き手のメリット |
| Whole(最初) | これから話す内容の全体像や結論を提示する | 話の目的やゴールが分かり、安心して聞ける |
| Part | 全体像を構成する各要素を具体的に説明する | 全体の中での位置づけが分かるため、理解が深まる |
| Whole(最後) | 全体を要約し、改めて結論を提示する | 話の要点が整理され、記憶に定着しやすい |
「全体像」から話すサンドイッチ構造
ホールパート法の最大の特徴は、「全体像→部分→全体像」という、まるでサンドイッチのような構造にあります。
最初に話の全体像を示すことで、聞き手は「これから何についての話が始まるのか」「話のゴールはどこか」という地図を手にした状態で話を聞き始めることができます。
その地図があることで、続く各部分の詳細な説明が、全体の中のどこに位置する情報なのかを迷うことなく理解できるようになります。そして最後に再度全体像を提示することで、話の要点が記憶に定着しやすくなるのです。
なぜホールパート法は伝わりやすいのか?
ホールパート法が伝わりやすい理由は、人間の脳の働きに合っているからです。
私たちは、新しい情報に触れるとき、まずその概要や全体像を掴もうとします。最初に枠組み(全体像)が提示されることで、脳は後から入ってくる詳細な情報を整理し、格納する準備を整えることができます。
もし、詳細な情報(部分)から話し始めてしまうと、聞き手はそれぞれの情報が何のために語られているのか分からず、頭の中で情報を整理するのに大きな負担がかかります。その結果、話の内容が理解されにくくなるのです。
ホールパート法は、この認知のプロセスに沿っているため、聞き手にストレスを与えることなく、スムーズな理解を促進します。
ホールパート法とPREP法の違いは?
分かりやすい説明のフレームワークとして、ホールパート法と共によく挙げられるのが「PREP(プレップ)法」です。
どちらも優れた手法ですが、得意な場面や目的が異なります。その違いを理解し、適切に使い分けることが、説明力をさらに向上させる鍵となります。
| フレームワーク | 目的 | 適したシーン |
| ホールパート法 | 複数の要素を持つ事柄の全体像を伝え、体系的な理解を促す | プレゼンテーション、業務説明、研修、プロジェクトの概要報告 |
| PREP法 | 自分の主張や結論を明確に伝え、相手を説得する | 意見表明、質疑応答、会議での発言、上司への報告・提案 |
結論から伝えるPREP法
PREP法は、「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(具体例)」「Point(結論)」の頭文字を取ったもので、その名の通り「結論」から先に伝えることを最大の特徴としています。
自分の主張や意見を明確に伝え、その理由と具体例を挙げることで、相手を強く説得したい場合に非常に有効です。特に、時間が限られている中で、端的に意見を述べる必要があるビジネスの報告や議論の場で多用されます。
全体像から入るホールパート法
一方、ホールパート法は「Whole(全体像)」から入ります。これは必ずしもPREP法のような単一の「結論」とは限りません。
例えば、「本日は、新プロジェクトの概要について、背景・目的・スケジュールの3点からご説明します」といったように、話のテーマと、それを構成する要素(部分)を最初に示すのが特徴です。
複数の項目にわたる事柄を、聞き手に分かりやすく整理して伝えたい場合に適しています。
目的別!どちらのフレームワークを使うべきか
ホールパート法とPREP法の使い分けは、「何を最も伝えたいか」で判断するのが良いでしょう。
自分の「意見」や「主張」を強く訴え、相手の納得を得たいのであればPREP法が適しています。一方で、複数の要素を持つ事柄の「全体像」を共有し、体系的な理解を促したいのであればホールパート法が効果的です。
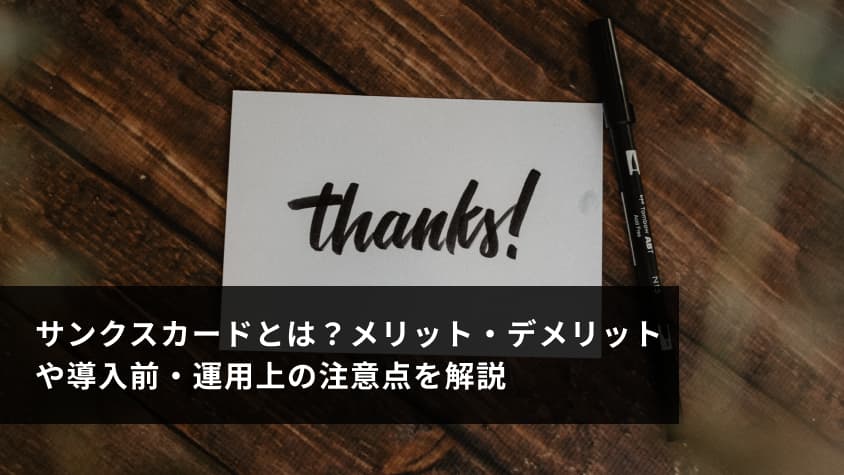
ホールパート法を活用する3つのメリット
ホールパート法を意識的に使うことで、コミュニケーションはより円滑になり、ビジネスにおける成果にも繋がりやすくなります。ここでは、ホールパート法がもたらす主要な3つのメリットについて解説します。
| メリット | 具体的な効果 | ビジネスへの好影響 |
| 理解度の向上 | 聞き手が話の構造を把握し、内容をスムーズに吸収できる | 認識の齟齬が減り、意思決定が迅速化する |
| 情報の整理 | 複雑な内容を構造化し、論理的に説明できる | 報告や提案の質が向上し、説得力が増す |
| 脱線の防止 | 話の軸がぶれず、時間内に要点を伝えきれる | 会議やプレゼンテーションの生産性が向上する |
聞き手が話の全体像を理解しやすい
最大のメリットは、聞き手が話の全体像を最初に把握できることです。話の冒頭で「これから話すことの地図」が渡されるため、聞き手は安心して話に集中できます。
詳細な説明に入っても、「今、全体のどの部分について話しているのか」が明確なため、話の途中で迷子になることがありません。結果として、伝えたい内容が正確に、そして深く理解されるのです。
複雑な内容も整理して伝えられる
複数の要素が絡み合う複雑なテーマや、情報量が多い内容を説明する際に、ホールパート法は特にその真価を発揮します。話し手自身も、まず全体像を定義し、それを構成する部分(Part)に分解して整理するプロセスを経ることで、思考がクリアになります。
例えば、「新サービスの仕様について」という漠然としたテーマも、「コンセプト」「主要機能」「料金体系」という3つのPartに分けることで、話し手も聞き手も情報を構造的に捉えることができるようになります。
話が脱線しにくく、時間内に要点を伝えられる
最初に話の全体像と構成(Part)を宣言することで、話の「レール」が敷かれます。
話し手はこのレールに沿って話を進めることを意識するため、途中で関係のない話題に逸れたり、細かな部分にこだわりすぎて時間切れになったりするのを防ぐことができます。
限られた時間の中で、伝えるべき要点を漏れなく、かつ効率的に伝えるためのガイドラインとして機能するのです。
ホールパート法のデメリットと注意点
ホールパート法は非常に強力なフレームワークですが、万能ではありません。状況によっては、その特性がデメリットとして働く可能性もあります。効果的に活用するためにも、注意点を理解しておきましょう。
| デメリット・注意点 | 具体的な状況 | 対処法 |
| 結論が後回しになる | 相手が結論を急いでいる報告や議論の場 | PREP法と組み合わせ、最初に結論(Point)を提示する |
| 説明に時間がかかる | エレベーターピッチなど、極端に時間が限られている場面 | 最も重要な要点(Part)のみを伝えるなど、構成を簡略化する |
結論が後回しになり、聞き手を焦らす可能性
ホールパート法は、まず「全体像」から入るため、聞き手が最も知りたい「結論」や「主張」が後回しになることがあります。
特に、意思決定を急いでいる上司への報告や、短い時間で意見を求められる場面では、「結論から言ってくれ」と聞き手を焦らせてしまう可能性があります。
このような場合は、まずPREP法で結論を述べ、その補足としてホールパート的な構成で全体像を説明するなど、柔軟な対応が求められます。
時間が限られている場面には不向きな場合も
「全体像→部分→全体像」という構成は、丁寧な説明ができる反面、ある程度の時間を要します。
エレベーターピッチのような極端に短い時間で要点を伝えなければならない場面では、全体像の説明を省き、最も重要なPartや結論だけを伝える判断も必要です。
常に状況を見極め、フレームワークに固執しすぎないことが重要です。
ホールパート法の具体的な使い方【3ステップで解説】
ホールパート法の理論を理解したら、次は実践です。ここでは、実際にホールパート法を使って説明を組み立てるための、具体的な3つのステップを解説します。
| ステップ | 目的 | 具体的なアクション |
| Step1:Whole(全体像) | 聞き手に話の全体像と構成を理解してもらう | これから話すテーマと、ポイントの数を明確に宣言する |
| Step2:Part(部分) | 各構成要素について具体的に説明し、理解を深める | ポイントごとに区切りながら、詳細な情報やデータを示す |
| Step3:Whole(まとめ) | 話の要点を再確認し、記憶に定着させる | 全体を要約し、最も伝えたいメッセージを改めて強調する |
Step1:Whole(全体像)で話の地図を示す
まず、説明の冒頭で、これから話す内容の全体像、いわば「話の地図」を提示します。ここでのポイントは、聞き手が話の全体像と、これから続く説明のポイント数を把握できるようにすることです。
例えば、「本日は、来期のマーケティング戦略について、主に3つのポイントからご説明します。一つ目はターゲット層の見直し、二つ目は新たな広告チャネルの活用、そして三つ目はWebサイトのコンテンツ強化です」のように伝えます。これにより、聞き手は話の全体構造を理解し、心の準備をすることができます。
Step2:Part(部分)で詳細を説明する
次に、Step1で提示した各部分(Part)について、一つひとつ具体的に説明していきます。
このとき、各Partが独立した話にならないよう、「一つ目のポイントは〜」「次に、二つ目のポイントである〜についてですが」のように、今どの部分を話しているのかを明確にしながら進めることが重要です。
それぞれのPartを詳細に説明することで、全体像の解像度を上げていきます。
Step3:Whole(まとめ)で再度全体像を提示する
全てのPartの説明が終わったら、最後に改めて全体像を示して締めくくります。ここでは、各Partの要点を簡潔に振り返りながら、話の結論や最も伝えたかったメッセージを強調します。
例えば、「以上、来期のマーケティング戦略として、ターゲットの見直し、新チャネルの活用、コンテンツ強化の3点についてご説明しました。これらを実行することで、目標達成を目指します」のようにまとめます。
これにより、聞き手は話の全体像を再確認でき、内容が記憶に定着しやすくなります。
【シーン別】ホールパート法の活用例文
理論やステップを学んだ後は、具体的なビジネスシーンでどのように活用できるのかを例文で見ていきましょう。
ここでは「プレゼンテーション」「会議での報告」「新人研修」の3つのシーンを想定しました。
プレゼンテーションでの活用事例
(Whole)
「本日は、弊社の新サービス『クラウド会計DX』について、皆様の業務をどのように変革できるか、主に『効率化』『コスト削減』『セキュリティ』の3つの観点からご提案させていただきます。」
(Part1:効率化)
「まず1点目の『効率化』についてです。本サービスはAI-OCR機能を搭載しており、紙の領収書や請求書を自動でデータ化します。これにより、これまで手入力にかかっていた時間を90%以上削減可能です。」
(Part2:コスト削減)
「次に2点目の『コスト削減』です。ペーパーレス化が進むことで、紙代や印刷代、書類の保管スペースといった物理的なコストを大幅に削減できます。ある導入企業様では、年間50万円のコスト削減に成功しました。」
(Part3:セキュリティ)
「そして3点目が『セキュリティ』です。データは金融機関レベルの暗号化技術で保護されており、アクセス権限も細かく設定できます。これにより、書類の紛失や情報漏洩のリスクを最小限に抑えます。」
(Whole)
「以上のように、『クラウド会計DX』は『効率化』『コスト削減』『セキュリティ』の3つの側面から、貴社の経理業務を強力にサポートするソリューションです。ぜひ導入をご検討ください。」
会議での進捗報告の活用例文
(Whole)
「〇〇プロジェクトの進捗についてご報告します。現在、全体として計画通りに進んでおりますが、共有すべき事項が2点ございます。1点目は『デザインFIXの遅延リスク』、2点目は『追加開発要件の発生』です。」
(Part1:遅延リスク)
「まず1点目の遅延リスクですが、A社のデザイン担当者の退職に伴い、デザイン案の最終FIXが当初の予定より3営業日ほど遅れる可能性が出てきました。現在、後任の方と連携を密にし、遅れを最小限に抑えるよう努めています。」
(Part2:追加要件)
「次に2点目の追加要件です。先日、営業部から顧客管理システムとの連携機能を追加したいとの要望がありました。技術的な実現可能性と、追加工数・費用の見積もりを現在進めている段階です。」
(Whole)
「ご報告は以上です。共有事項は『デザイン遅延リスク』と『追加開発要件』の2点です。引き続き、リスク管理と関係部署との調整を徹底してまいります。」
新人研修での業務説明の活用例文
(Whole)
「これから皆さんに担当していただく、経費精算の業務フローについて説明します。全体の流れは大きく3つのステップに分かれています。ステップ1が『申請書の作成』、ステップ2が『上長の承認』、ステップ3が『経理への提出』です。」
(Part1:申請書の作成)
「まず、ステップ1の『申請書の作成』です。使用した経費の領収書をもとに、社内システムにログインして経費精算申請のフォームに入力します。入力項目や注意点については、配布したマニュアルの5ページを参照してください。」
(Part2:上長の承認)
「次に、ステップ2は『上長の承認』です。システムで申請書を提出すると、自動的に皆さんの直属の上長に承認依頼が飛びます。もし内容に不備があると差し戻されますので、提出前によく確認しましょう。」
(Part3:経理への提出)
「最後のステップ3が『経理への提出』です。上長の承認が得られたら、申請書をシステムから印刷し、領収書の原本を裏面に貼り付けて、月末までに経理部の担当者へ提出してください。これで一連の流れは完了です。」
(Whole)
「以上が経費精算業務の全体の流れです。『申請書の作成』、『上長の承認』、『経理への提出』という3つのステップを覚えておいてください。何か質問はありますか。」
ホールパート法を実践する際の2つのポイント
ホールパート法をさらに効果的に活用するためには、いくつかのポイントがあります。ここでは、特に意識したい2つの点について解説します。
これらのポイントを押さえることで、あなたの説明はより洗練され、聞き手の心に響くものになるでしょう。
| ポイント | 理由 | 具体的な実践方法 |
| Partを3つに絞る | 人間が一度に記憶しやすい情報量には限界があるため | 伝えたい項目が多数ある場合は、グルーピングして3つのカテゴリにまとめる |
| PREP法と組み合わせる | 全体の分かりやすさと、各論の説得力を両立できるため | 各Partを説明する際に、「結論→理由→具体例→結論」の構成を意識する |
Part(部分)の数は3つに絞るのが理想
人間が一度に記憶しやすい情報の数は、「3つ」がマジックナンバーであると言われています。これは心理学で「マジカルナンバー3」とも呼ばれ、多すぎる情報はかえって記憶に残りにくいという性質に基づいています。
そのため、ホールパート法で説明を構成する際、詳細を説明するPart(部分)の数は、できる限り3つに絞るのが理想的です。
もし伝えたい項目が4つ以上ある場合は、関連するものをグルーピングして3つのカテゴリにまとめるなどの工夫をすると、聞き手にとって非常に分かりやすくなります。
Part(部分)の説明ではPREP法を組み合わせる
ホールパート法で全体の構造を作り、その中の各Partを説明する際にPREP法を組み合わせることで、説明の説得力を格段に向上させることができます。
まずホールパート法で「これから3つの点について話します」と全体像を示し、続く各Partの説明を「結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→結論(Point)」の構成で展開するのです。
これにより、聞き手は話の全体像を見失うことなく、各論についても深く納得することができます。
まとめ
本記事では、分かりやすい説明のためのフレームワーク「ホールパート法」について、その基本構造からPREP法との違い、具体的な活用法までを解説しました。
ホールパート法は、「全体像→部分→全体像」というシンプルな構成で、聞き手の理解を劇的に促進する力を持っています。
会議での報告、クライアントへのプレゼンテーション、部下への指示など、ビジネスにおけるあらゆるコミュニケーションシーンで活用できます。
今回ご紹介したステップや例文を参考に、ぜひ明日からの業務にホールパート法を取り入れ、あなたの「伝える力」を最大限に引き出してください。