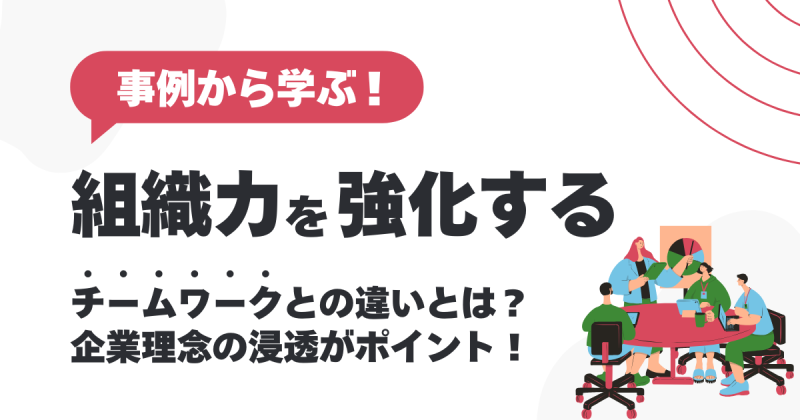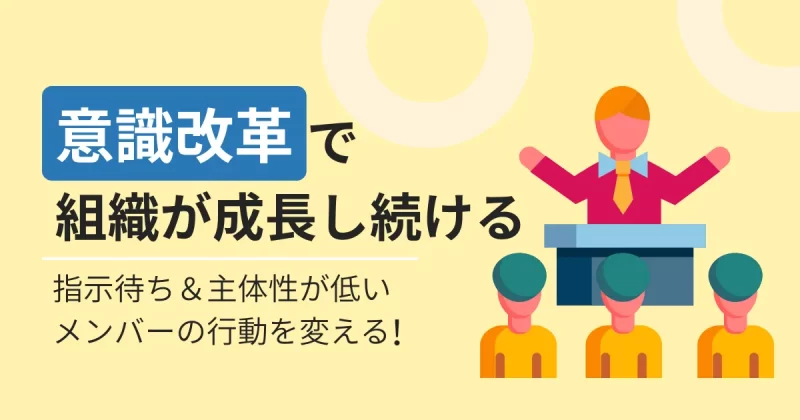企業の成長が伸び悩んでいる、社員の一体感がなく生産性が上がらない、といった課題を抱えていませんか。
これらの問題の根源には、「組織力」の低下が潜んでいるかもしれません。変化の激しい現代において、個人の能力を最大限に引き出し、企業全体の力として結集させる組織力は、持続的な成長に不可欠です。
そこでこの記事では、組織力が強化された企業の特徴、組織力を強化する方法や成功事例を徹底解説します。
組織力とは
組織力とは、単に優秀な人材が集まっている状態を指すのではありません。企業が掲げる目標やビジョンに向かって、組織全体が一体となって進むための総合的な力のことです。
>>【お役立ち資料】組織力の定義から強化方法・事例まで解説内容を拡充した資料を公開
個人の能力の総和以上の力
組織力の本質は、1+1が2以上になる相乗効果を生み出す力にあります。 個々の社員が持つスキルや知識が、組織というプラットフォームの上で有機的に結びつき、連携することで、一人ひとりが単独で発揮する以上の大きな成果を生み出します。 企業のビジョンが共有され、社員間のコミュニケーションが円滑であればあるほど、この相乗効果は大きくなります。
チームワークとの違い
組織力とチームワークは混同されがちですが、厳密には異なります。チームワークは、特定のチーム内でメンバー同士が協力し、目標を達成する能力を指します。
一方、組織力は、チームワークを含むさらに大きな概念です。部門間の連携、経営層と現場の意思疎通、企業文化、人材育成の仕組みなど、企業全体を機能させるためのあらゆる要素が含まれます。優れたチームワークは、高い組織力を構成する重要な要素の一つですが、それだけでは組織力全体が高いとは限りません。
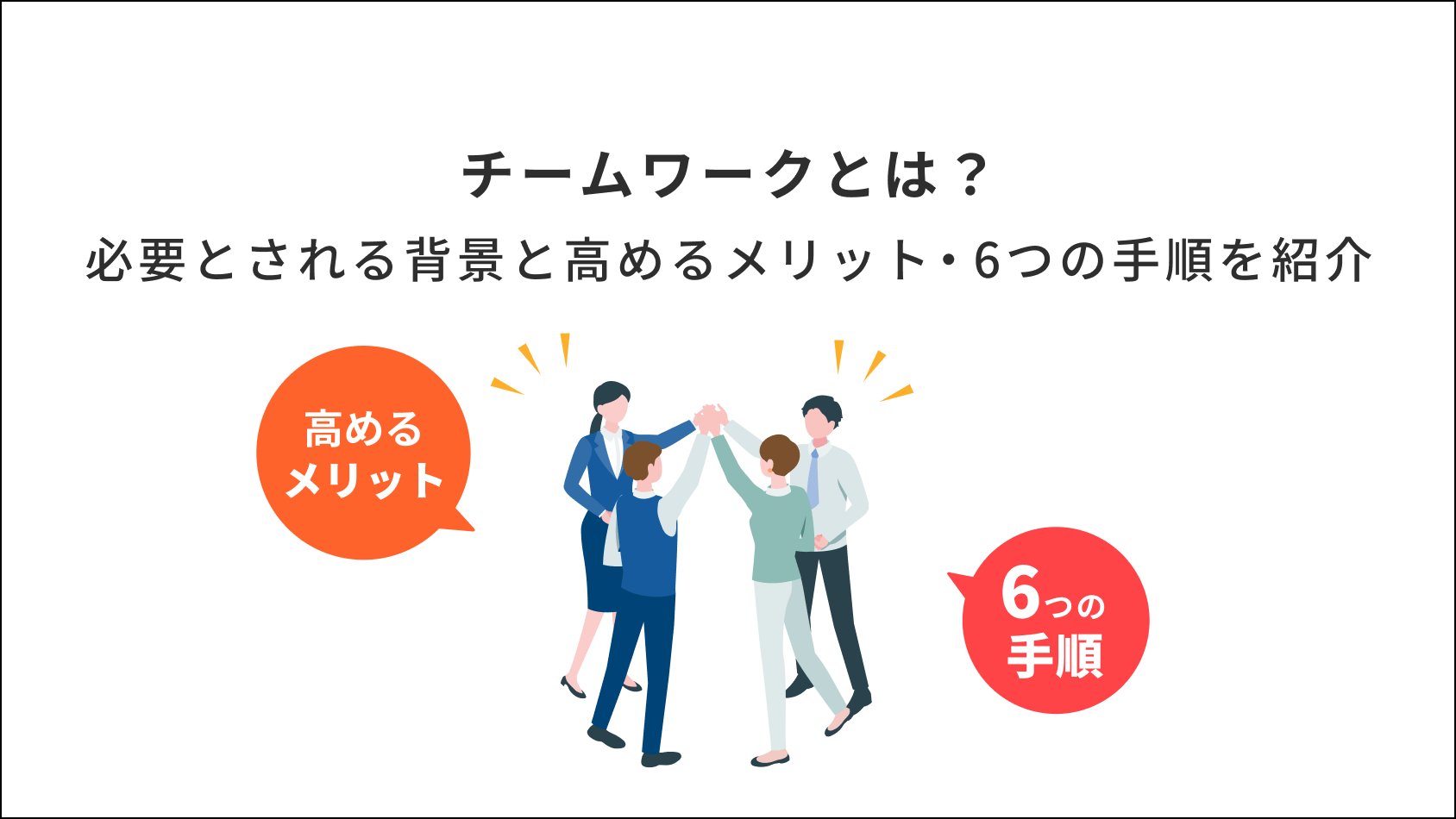
組織力の強化が必要な背景
近年、ビジネス環境の複雑化に伴い、組織力の重要性はますます高まっています。なぜ今、多くの企業が組織力強化に取り組むのでしょうか。
VUCA時代を乗り越えるため
現代は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った「VUCA」の時代と呼ばれています。
- V:Volatility(変動性)
- U:Uncertainty(不確実性)
- C:Complexity(複雑性)
- A:Ambiguity(曖昧性)
市場のニーズ、テクノロジー、競合状況などが目まぐるしく変化し、将来の予測が非常に困難な時代です。このような環境で企業が生き残り、成長を続けるためには、変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織力が不可欠です。トップダウンの指示を待つだけでなく、現場の社員が自律的に考え、行動し、部門間で連携して課題を解決していく力が求められます。
人材の定着と多様化への対応
働き方改革や価値観の多様化により、人材の流動性は高まっています。社員が企業に求めるものは、給与や待遇だけでなく、働きがい、成長機会、良好な人間関係など、より多岐にわたるようになりました。
組織力が高い企業は、社員一人ひとりが尊重され、能力を発揮できる環境が整っているため、エンゲージメントが高まり、優秀な人材の定着につながります。 また、多様なバックグラウンドを持つ人材が互いの違いを認め、活かし合うことで、イノベーションが生まれやすくなります。
組織力が高い企業の特徴
ここでは、組織力強化に成功した企業に共通している特徴を紹介します。
組織力強化に必要な要素とも言えますので、参考にしてみましょう。
一方で「組織力強化が必要な組織力の低い企業」の特徴については、こちらの記事(ダメな組織の特徴20選 | 職場崩壊の予兆と改善策の解説)で解説しています。
企業と従業員が同じ目標を共有している
企業と従業員が同じ目標を共有していて、目指すべき方向性がはっきりしていることが重要です。組織力強化に成功している多くの企業では、ミッション・ビジョン・バリューなど基本的な方針を広く浸透させています。
また、「今期の目標」「創業〇周年に向けた指針」など対外的に発表していない目標も共有し、直近のゴールを定めていることも特徴的です。
会社と従業員が一心同体であるという意識も喚起しやすく、前向きなモチベーションにつながる効果も期待できるでしょう。
コミュニケーションが活発である
普段から積極的な社内コミュニケーションがおこなわれており、風通しのよい社風であることも共通しています。
例えば役職・年代・部署の垣根なくいつでも意見やアイディアを発信できる仕組みが整っていたり、雑談を含め業務内外のありとあらゆる情報交換を日常的におこなっていたりする場合、精神的な安定が図れます。
「会社やメンバーのことが好き」という従業員エンゲージメントを育成しやすくなり、ゴールに向けて努力しようという自然な気持ちを育めるでしょう。組織力強化には社内コミュニケーションが欠かせないことが分かります。
社内コミュニケーションの成功事例はこちらにまとめていますので、ご参考ください。
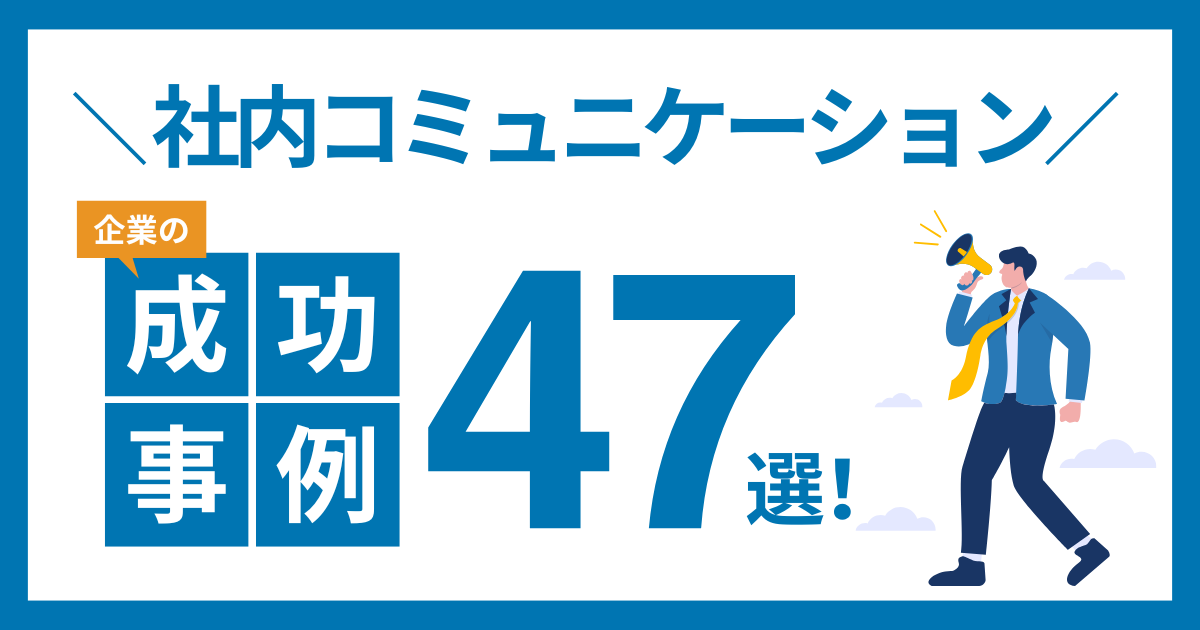
助け合いの精神がある
会社と従業員は一心同体であるという認識が浸透していると、助け合いの精神が生まれます。
困っている部下や後輩にアドバイスをしたり、例え他部署や別プロジェクトであっても求められれば積極的に情報提供したり、相互扶助することが当たり前になっていると言えるでしょう。
反対に自分が助けてもらうことも多く、「この前助けてもらったのだから今回は何か力になりたい」という健全な精神を育めます。
助け合いの精神は従業員同士の信頼関係構築にも役立ちますので、組織力強化だけでなくさまざまなメリットが生まれるでしょう。
人材育成制度が整備されている
社員教育・社内研修・メンター制度・スキルアップ支援などの制度が整っていることも、組織力強化ができている企業に共通しています。
組織に所属しているということへの安心感が高まるほか、少しずつ自分がステップアップしている実感を抱くことによるモチベーションアップも期待できるでしょう。「自分が成長できているのは会社のお陰」と感じるシーンが多くなり、組織力強化につながります。
また、透明性と客観性のある人事評価体制が敷かれていることも重要な要素です。
社内教育・社内研修について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
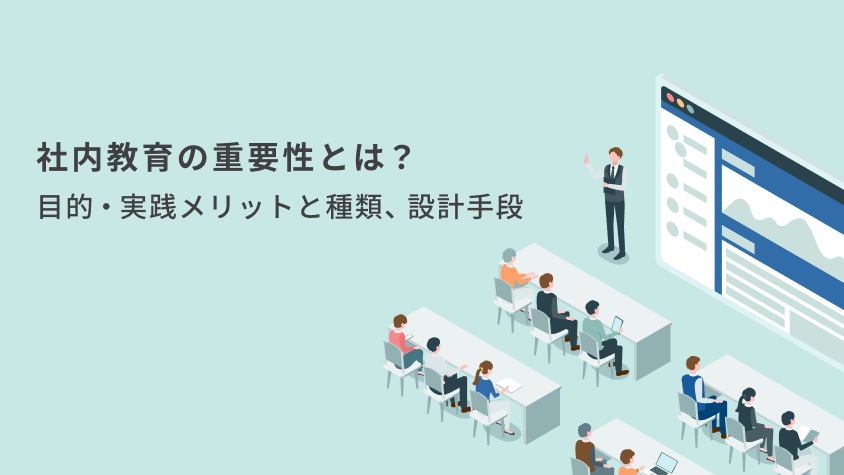
個人の能力を最大限活かせる人事配置をしている
個人の能力を最大限活かせる人事配置をしている場合、従業員それぞれが持っている知識・知見・ノウハウ・経験を発揮しやすくなります。
パフォーマンスを発揮できるため仕事にやりがいを感じ、働くことが楽しくなるような会社として成長できるでしょう。「会社から期待してもらえている」という健全な自己肯定感を育めることも、組織力強化の要因となります。
従業員のモチベーションを高めることこそが、組織力強化に欠かせないと言えるでしょう。

組織力が低い企業の特徴
一方で、組織力が低下している企業には、以下のような危険信号が現れます。一つでも当てはまる場合は、注意が必要です。
| 兆候 | 具体的な状況 |
| 指示待ち社員が多い | 上司の指示がないと動けず、自ら課題を見つけて行動しようとしない。失敗を恐れるあまり、挑戦を避ける傾向がある。 |
| 部門間の連携が悪い | いわゆる「セクショナリズム」が蔓延し、他部署への協力に非協力的。情報が共有されず、組織全体として非効率な状態に陥っている。 |
| ネガティブな発言が多い | 会議や普段の会話で、他者への批判や会社の愚痴など、後ろ向きな発言が目立つ。助け合いの精神が欠如している。 |
| 離職率が高い | 若手や中堅社員が次々と辞めていく。社員が会社に将来性を感じられず、エンゲージメントが著しく低い状態。 |
| 挑戦を許容しない風土 | 一度失敗すると厳しく追及され、再挑戦の機会が与えられない。リスクを取ることを極端に恐れる文化が根付いている。 |
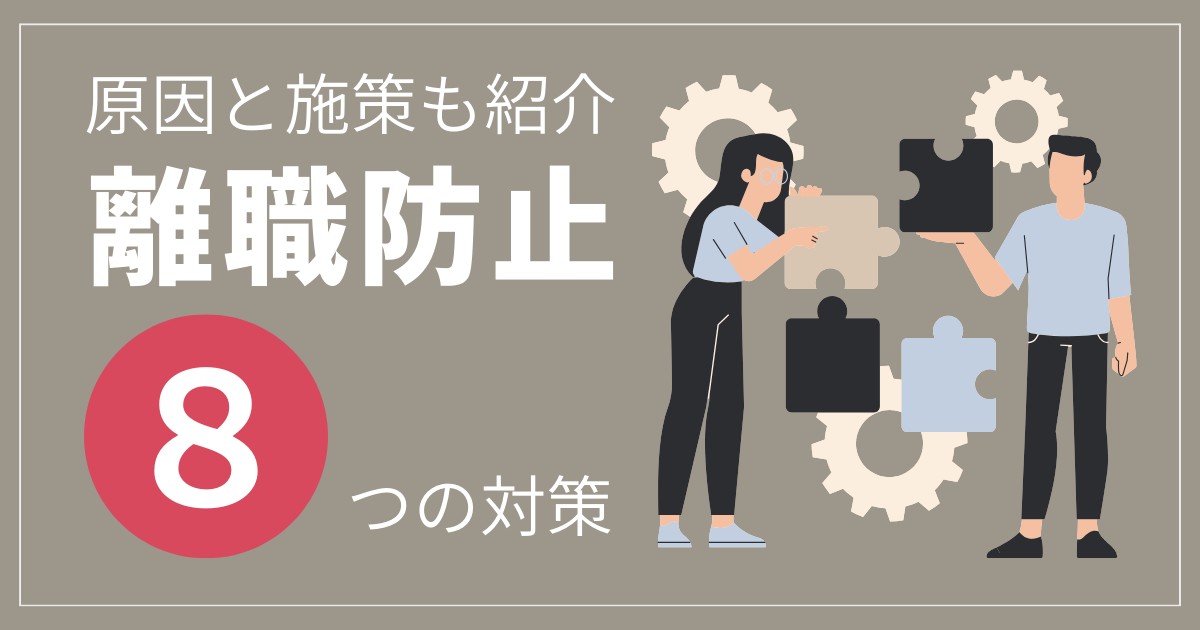
組織力を強化する方法
ここからは、組織力強化をするための方法を紹介します。自社で実施したときのイメージをしながら、施策考案に役立てていきましょう。
企業のビジョンや理念を従業員に浸透させる
まずは自社が持つビジョンや理念を従業員に浸透させ、理解と共感を喚起することが大切です。
目の前の業務だけでなくその先にある目的や意義を理解できれば仕事に身が入りやすくなり、組織力強化の要因となるでしょう。
また、「会社からビジョンや理念を説明してもらえている」ということ自体が安心材料につながるケースも多く、従業員からの信頼度向上にも寄与します。
入社式や周年イベントなどセレモニー色が濃いシーンだけでなく、社内報や朝礼などを活用して複数回触れていくことがおすすめです。

コミュニケーションが取りやすい環境を整える
組織力強化には、社内コミュニケーション活性化させることが効果的です。
業務上必要な情報を確実に共有できるため仕事の抜け・漏れ・被りなど非効率が減り、効率アップやストレス軽減に役立つでしょう。また、日常的な雑談やプライベートでの悩みも気軽に相談できる社風になれば、従業員同士の信頼構築につながります。
普段やり取りするメンバーだけでなく他部署・他職種のメンバーとも交流できるような仕組みをつくり、風通しのよい職場を目指しましょう。
社内コミュニケーション促進には、さまざまな手段があります。弊メディアで行っているインタビューも参考にしてみてください。企業ごとの成功事例を学ぶことができます。
チャレンジしやすい環境を作る
役職・年代・部署を問わず誰でも新たなチャレンジができる環境を作ることも理想です。
チャレンジしたことそのものを賞賛するような組織であれば、失敗を恐れすぎることなく意見やアイディアを発信しやすくなるでしょう。
会社が時代のニーズに合わせてどんどん変化していくための組織力向上であると考えれば、チャレンジしやすい環境を作ることが急務だと分かります。
反対に失敗を必要以上に糾弾してしまう企業の場合、「チャレンジすることが怖い」というマイナスの考えを抱かせやすく、組織全体の創造性が下がるため注意が必要です。
戦略に基づいて人材の配置や育成を行う
自社が持つ成長戦略に基づいて人材を配置・育成することを心がけましょう。
「適材適所」という言葉がある通り、従業員ごとに異なるスキル・適性に合わせてマネジメントしていくことが重要です。
自分の能力を最大限活かせる部署に配置してもらうことでより仕事が楽しくなることも多く、従業員のモチベーション向上の効果も期待できます。
また、ひとりひとりの適性を理解しようとする会社の姿勢自体にも、共感が集まるでしょう。部署ごとにどんな人材を求めているのか明確にしたうえで、個人ごとの得意分野を探ることが重要です。一般的にこうした活動のことを、「タレントマネジメント」と呼びます。詳しくは以下の記事をご覧ください。

自発的な行動を促す
会社からの指示を受けて動くだけでなく、自発的な行動を促すことも組織力向上のカギとなります。
「努力することは自分のためにも会社のためにもなる」と動機付けをすることにより、ひとりひとりのパフォーマンスが向上します。
具体的には、EVPと呼ばれる活動を行うと良いでしょう。会社がどんな人物を評価するのか人事評価規程に盛り込んだりキャリアパスを提示したりできれば、より効果的でしょう。
率先して業務を請け負う、新しいアイディアを積極的にプロジェクトへ落し込むなど、それぞれのスキルを活かした働きが期待できます。自発的な行動をする従業員が増えれば、自ずと組織力も向上するのです。

令和の経営に必要な「カルチャー・マネジメント」とは
すでにお気づきかもしれませんが、組織力を強化するために必要なものは「待遇の良さ」でも「事業内容」でもありません。従業員が企業理念を理解し、体現すること・従業員がいきいきと自発的に動ける環境を作ることが何よりも え重要です。
しかし、企業理念の浸透も、自主性が高い組織の文化づくりも決して簡単ではありません。何からはじめて、どのように組織をかえていくのか?について、以下の資料にて解説しています。

組織力の強化に成功した企業の具体的な取り組み事例
最後に、組織力強化を成功させた事例を紹介します。どんな施策を取って成功に導いたのかヒントを探り、自社施策を考えていきましょう。
ソントン食品|経営と従業員の目線を揃えるインナーコミュニケーション
ソントン食品では、経営陣が常に「情報発信を大切にする」という文化を大事にしてきました。具体的には、中期経営計画を策定し、説明会や勉強会、さらには社内報を通じて共有。
また、必要に応じて経営陣自らが現場に足を運び、直接説明したり、自身の想いを語ることもあります。
結果的に、経営と従業員のお互いの理解と目標が共有され、今川焼きの新しい味や新商品の開発といったように、食文化を創造することでに成功しています。

C&G Value Design|従業員同士の仲間意識が、高品質な顧客体験を提供
C&G Value Designでは、複数の業態やブランドを展開しており、自然と縦割りの組織文化が根付いていました。しかし、チームとしての一体感や仲間意識が醸成されていない状態では、お客様に高品質な体験を提供できないと考えました。
独自の取り組みである、拠点や職種を横断した次世代リーダー育成研修や、社内報やプロフィールを活用したコミュニケーションのきっかけ作りをおこない、組織の一体感を育んでいます。

シコー | web社内報による理念浸透を実現
シコーでは、web社内報を導入し、本社だけでなく、全国に展開する支社・工場の全体的なIT化を行いました。
IT化の手段として社内報を選択することで、企業のビジョンや理念を浸透しやすい環境を整えることに成功。また、社内報で発信された記事を発端として、デジタル上で全国規模のコミュニケーションが生み出されました。一見すると組織の統一が難しそうな全国規模の製造会社において組織力強化を実現した、先進的な事例です。

まとめ
本記事では、組織力の定義からその重要性、そして具体的な強化方法までを解説しました。組織力強化は、企業の持続的な成長を実現するための重要な経営課題です。
紹介した組織力を強化する方法を地道に取り組むことが、強くしなやかな組織への第一歩となります。自社の現状を分析し、できるところから始めてみてはいかがでしょうか。