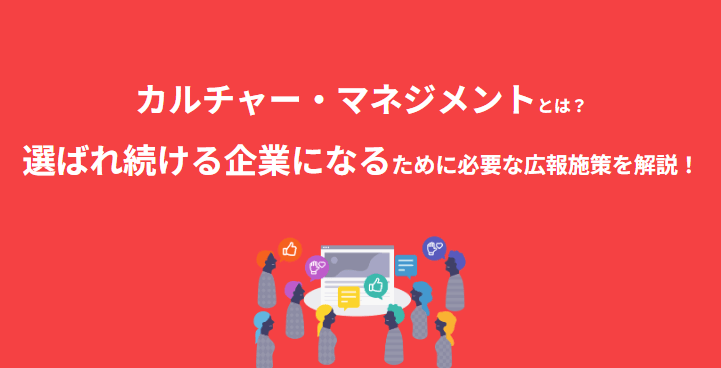ビジョンとは、企業が事業を通じて実現したい未来を明文化したものです。また、中長期的な視点の目標を達成したのち、企業がどのような姿になりたいかを描きます。
企業理念やミッションなどとセットで語られることが多い言葉ですが、どのような違いがあるのでしょう。また、ビジョンを作ったり浸透させたりするには、どのような方法があるのでしょうか。
本記事では、ビジョンの意味や作り方、実現に向けて浸透させる方法を説明したのち、実際の企業がビジョンに掲げる具体的な事例を解説します。
記事下部では、上場企業100社のミッションビジョンバリューをまとめたシートを配布しておりますので、ぜひご覧ください。
そもそも企業におけるビジョンとは?
企業経営について考える際、頻繁に「ビジョン」という言葉を耳にしますが、その本質を正しく理解できているでしょうか。ビジョンとは、単なるスローガンではなく、企業が将来達成したいと心から願う「あるべき姿」や「未来像」を明確に描き出したものです。それは、組織全体で共有する夢であり、日々の活動の先に目指す目的地を示します。このセクションでは、ビジョンが持つ意味合いと、関連する用語との違い、そして現代のビジネス環境においてビジョンがなぜ不可欠なのかを掘り下げていきます。

ビジョンとミッション・バリューとの違い
ビジョンとしばしば混同される言葉に「ミッション」と「バリュー」があります。これらは相互に関連し合っていますが、それぞれ異なる役割を担っています。
| 用語 | 役割 | 時間軸 |
| ビジョン(Vision) | 企業が目指す未来の理想像・あるべき姿 | 未来 |
| ミッション(Mission) | ビジョンを実現するための企業の使命・存在意義 | 現在 |
| バリュー(Value) | ミッションを遂行する上での行動指針・価値観 | 現在 |
ビジョンが「どこへ向かうのか(Where)」という目的地を示すのに対し、ミッションは「なぜそこへ向かうのか(Why)」という存在理由と、「何をすべきか(What)」という使命を定義します。そしてバリューは、目的地へ向かう過程で「どのように行動するのか(How)」という日々の行動規範や価値観を定めるものです。これら3つが一体となって初めて、企業は一貫性のある活動を展開できます。

ビジョンと経営理念・企業理念の違い
ビジョンと混同しがちな言葉に「経営理念」と「企業理念」があります。
経営理念は、「企業活動の目的」を指します。創業者や経営者の「価値観・思い」が込められているニュアンスがあり、「哲学」とも呼べるものです。
企業理念は「その会社の目的や存在意義」を示すもので、厳密には経営理念と意味が異なります。経営理念は時代背景などによって変わることがありますが、企業理念は創業者の考えや意思を参考に策定されることが一般的です。
これらに対してビジョンは会社の将来について述べたものです。
なぜ今、企業にビジョンが必要なのか?
現代は、市場のグローバル化、テクノロジーの急速な進化、働き方の多様化など、変化が激しく予測困難な「VUCA時代」と呼ばれています。このような時代において、企業が羅針盤なくして航海を続けるのは非常に危険です。明確なビジョンは、不確実な状況下でも進むべき方向を示す北極星のような役割を果たします。
ビジョンがあることで、従業員は自社の未来に希望を持ち、日々の業務に意味を見出すことができます。 結果として、組織としての一体感が生まれ、変化に強く、持続的に成長できる企業体質が育まれるのです。
ビジョンの意義
ビジョンが重要な理由は、企業の発展には欠かせないものであるからことです。企業規模が大きくなればなるほど、経営者の直接のマネジメントが及ばなくなります。多くの社員に企業としての理念を浸透させ、方向性をそろえるためにビジョンを示す必要があるのです。
ビジョンが重要な理由は、具体的には以下の3つが挙げられます。
- 企業の方向性を社内外に示すため
- 社員の行動や判断の基準にするため
- 社員のモチベーションを上げるため
詳しくみていきましょう。
企業の方向性を社内外に示すため
ビジョンを設定することで、社員をはじめとしたすべてのステークホルダーに、会社が進む方向性を示す必要があるためです。明確なビジョンがない場合、社員がバラバラな考えのもと行動するため、力が集約されることはありません。こうした状態は企業の衰退につながります。
ビジョンを示すことで中長期的な目標を提示し、社員の足並みをそろえ、力を集約できるのです。また、企業の将来像や価値観を示すことは、外部のステークホルダーの賛同を得るためには不可欠なものといえます。
社員の行動や判断の基準にするため
ビジョンは、社員の判断軸としても機能するものです。大局的な経営判断から現場の業務にいたるまで、判断に悩む場合の判断基準として作用します。ビジョンが組織の中で浸透し共通認識となることで、多くの社員が会社にとっての正しい行動をとるようになるでしょう。
また、変化に対応する必要がある場合は、新たなビジョンを浸透させることが有効です。刷新されたビジョンを浸透させることで、新たな行動指針や判断基準として機能するのです。
社員のモチベーションを上げるため
企業ビジョンの浸透は、社員のモチベーションによい影響を及ぼします。自身のビジョンに向けた努力が、企業のビジョン実現にリンクする場合、日々の仕事に意欲をもって取り組めるようになるためです。
ビジョンの浸透は、共通の判断軸の浸透にもつながるため、組織内のコミュニケーションも円滑になり業務がスムーズに進みます。社員の足並みが揃うことで、企業としての一体感が醸成され、さらなる個々のモチベーション向上が見込めるでしょう。
企業ビジョンを作成する3つのメリット
魅力的なビジョンを策定し、社内に浸透させることは、企業に多くの恩恵をもたらします。それは単に企業イメージを向上させるだけでなく、組織運営の根幹に関わる具体的なメリットを生み出します。ここでは、ビジョンを持つことによる主要な3つのメリットについて解説します。
経営判断における明確な軸ができる
企業経営は、日々の大小さまざまな意思決定の連続です。市場の変化や予期せぬトラブルに直面した際、判断の基準が曖昧であれば、場当たり的な対応に終始してしまい、経営の一貫性が失われかねません。明確なビジョンは、そうした場面で「その決定は、我々の目指す未来像に合致しているか?」という揺るぎない判断軸を提供します。 この軸があることで、経営層は迅速かつ合理的な意思決定を下すことができ、事業戦略に一貫性をもたらします。
従業員のエンゲージメントが向上する
従業員は、単に給与を得るためだけに働いているわけではありません。自身の仕事が会社の未来にどう貢献しているのか、社会にどのような価値を提供しているのかを実感することで、仕事への誇りとやりがいを感じます。ビジョンは、企業の目指す魅力的な未来像を従業員と共有し、日々の業務に大きな意味を与えるものです。 自分の仕事がビジョン実現の一部であると感じることで、従業員のエンゲージメント、すなわち仕事に対する熱意や貢献意欲は自然と高まります。
採用活動で企業の魅力を伝えやすくなる
採用活動は、企業と求職者のマッチングの場です。給与や福利厚生といった条件面も重要ですが、多くの優秀な人材は「この会社で何を実現できるのか」「どのような未来を目指しているのか」といった将来性や働きがいに強い関心を抱いています。ビジョンは、自社がどのような未来を描いているのかを社外に発信する強力なメッセージとなります。企業の理念や将来性に共感した求職者が集まることで、カルチャーフィットの精度が高まり、入社後のミスマッチを防ぎ、定着率の向上にも繋がります。
企業ビジョン作成の具体的な5つのステップ
それでは、実際に企業のビジョンを作成するには、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。思いつきやトップダウンだけで決めるのではなく、体系的なプロセスを経ることで、より実効性の高いビジョンを策定できます。ここでは、多くの企業で採用されている普遍的な5つのステップを紹介します。
ステップ1:プロジェクトチームを結成する
ビジョン策定は、経営層だけで行うべきではありません。全社的な取り組みとして、多様な部署や役職、年齢の従業員を巻き込んだプロジェクトチームを結成することが最初のステップです。多様な視点を取り入れることで、一部の人間だけの理想に偏らず、全社が「自分たちのビジョン」として納得感を持てるようになります。このチームが中心となり、策定プロセス全体を推進していくことになります。
ステップ2:自社の現状と外部環境を分析する
次に、自社が現在どのような立ち位置にいるのかを客観的に把握する必要があります。自社の強み・弱み、創業から続く価値観、企業文化などを分析する「内部環境分析」と、市場のトレンド、競合の動向、技術革新、社会の変化などを分析する「外部環境分析」の両面から行います。 この分析を通じて、自社のユニークな価値と、社会から求められている役割を明らかにすることが、未来を描く上での土台となります。
| 分析項目 | 具体的な内容 |
| 内部環境分析 | 強み、弱み、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)、企業文化、価値観 |
| 外部環境分析 | 市場動向、競合分析、顧客ニーズ、技術トレンド、社会・経済情勢 |
ステップ3:会社の未来像を言語化する
現状分析で得られた土台の上に、会社の未来像を描いていきます。「10年後、我々の会社は社会でどのような存在になっていたいか?」「顧客にどのような価値を提供していたいか?」「従業員がどのように働いている状態が理想か?」といった問いを立て、プロジェクトチームで自由にアイデアを出し合います。 この段階では、実現可能性に縛られすぎず、夢や理想を大胆に語り合うことが重要です。出てきたキーワードやアイデアを整理し、未来像の核となるコンセプトを固めていきます。
ステップ4:ビジョンを魅力的な言葉にまとめる
未来像のコンセプトが固まったら、それを誰の心にも響く、簡潔で魅力的な言葉(ビジョン・ステートメント)に磨き上げていきます。 従業員が覚えやすく、日々の会話の中で自然と口にできるような、分かりやすい言葉を選ぶことが重要です。また、顧客や株主など、社外のステークホルダーにも共感を呼ぶような、普遍的な魅力も必要です。いくつかの案を作成し、多くの従業員の意見を聞きながら、最もふさわしい言葉を選び抜きます。
ステップ5:社内への浸透施策を計画する
ビジョンは、策定して終わりではありません。むしろ、全従業員に共有され、日々の業務に根付いて初めて価値を発揮します。そのため、策定と同時に、どのように社内に浸透させていくかの計画を立てることが不可欠です。 社内報や全社朝礼での発表、ビジョンについて語り合うワークショップの開催、評価制度への組み込みなど、多角的なアプローチを計画し、継続的に実行していくことが求められます。
ビジョン作成で失敗しないための注意点
せっかく時間と労力をかけてビジョンを策定しても、それが形骸化してしまっては意味がありません。ビジョンが「絵に描いた餅」で終わってしまうケースには、いくつかの共通した落とし穴が存在します。ここでは、そうした失敗を避け、真に機能するビジョンを作るための注意点を解説します。
経営層だけで策定を進めない
ビジョン策定において最も陥りやすい失敗の一つが、経営層や一部の部署だけでプロセスを完結させてしまうことです。トップの強い想いは不可欠ですが、現場の意見や感覚から乖離したビジョンは、従業員にとって「他人事」になってしまいます。策定の初期段階から多様な従業員を巻き込み、全社で議論するプロセスを経ることで、当事者意識が生まれ、納得感の高いビジョンが生まれます。
現実離れした内容にしない
ビジョンは未来の理想像を描くものですが、現状からあまりにもかけ離れた、実現不可能な内容では従業員の共感を得ることはできません。 「どうせ達成できない」という諦めは、かえって組織の士気を下げてしまいます。自社の強みやリソースといった現状を冷静に分析し、その延長線上にありながらも、挑戦意欲をかき立てるような、絶妙なバランスの「ストレッチした目標」を設定することが重要です。
作成して終わりだと思わない
ビジョンは、立派な額に入れて飾っておくためのものではありません。策定はゴールではなく、スタートです。ビジョンを日々の業務や意思決定の基準として活用し、常に立ち返るべき指針として組織に根付かせていく継続的な努力が不可欠です。経営者自らが率先してビジョンについて語り、ビジョンを体現する行動を称賛するなど、ビジョンを風化させないための地道な活動を粘り強く続ける必要があります。
ビジョンを社内に浸透させる方法
ビジョンは策定するだけでは意味がありません。多くの社員の共感を得て、行動に変化が表れてこそ意味があるものになります。ビジョンの浸透は、以下のプロセスを経ることでスムーズに進むでしょう。
- 認知 ビジョンを伝え、知ってもらう
- 理解 コミュニケーションを図り、理解を深めてもらう
- 共感 自身のビジョンと企業のビジョンがリンクする
- 実践 ビジョンに基づいた行動をとる
- 協働 ビジョンが浸透し、多くの社員がビジョンに基づいた行動をとる
ビジョンの策定は、この「協働」のステップまでを意識しておこなう必要があるのです。

ビジョンの浸透には ourly
ourlyは、ビジョンの浸透やカルチャー醸成に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
経営層のメッセージを現場へ届けるだけでなく、現場の声も発信できるため、双方向のコミュニケーションを実現します。ourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援と詳細な分析、洗練されたコンテンツ配信から、効率的なビジョン浸透や文化醸成を実現します。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」「理念浸透・文化醸成を通して組織改善したい」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
企業ビジョンの具体的な事例
ここでは、企業ビジョンの浸透に成功した、2社の具体的な企業事例を紹介します。魅力的なビジョンは、多くの社員のモチベーションを向上させているようです。
- サイバーエージェント
- 無印良品
いずれの企業も優れた企業ビジョンを浸透させたことで、人材の持てる力を最大限に引き出し、事業成長を遂げている点が興味深いところです。企業ビジョン浸透の成功事例として、参考になるものです。
詳しくみていきましょう。
サイバーエージェント
サイバーエージェントの企業ビジョンは、「21世紀を代表する会社をつくる」というものです。進化の早いインターネット領域において、さまざまな分野に事業拡大を図り、変化対応力を磨いています。
基幹事業に加え新たな分野で多数の子会社を創業することで、社員に活躍の機会を提供し「人材力」と「技術力」を高めることに成功しています。企業ビジョンが、事業展開と人材活用のありかたに、密接にリンクした好事例といえるでしょう。
出典:https://www.cyberagent.co.jp/corporate/vision/
無印良品
無印良品の企業ビジョンは、「良品には、あらかじめ用意された正解はない。しかし、自ら問いかければ、無限の可能性が見えてくる」というものです。
同社は著名なデザイナーを役員に招き、ビジョン策定にあたります。その結果、接客サービスから商品にいたるまで「無印らしさ」が統一された世界観を構築しました。流行にとらわれないシンプルなアイテムや無印らしい店構え・接客が確立され、ブランドとしての独自性を広く社会に認知させるにいたっています。ビジョンの浸透により、ブランディングに成功した好事例といえるでしょう。
出典:https://www.ryohin-keikaku.jp/corporate/philosophy/
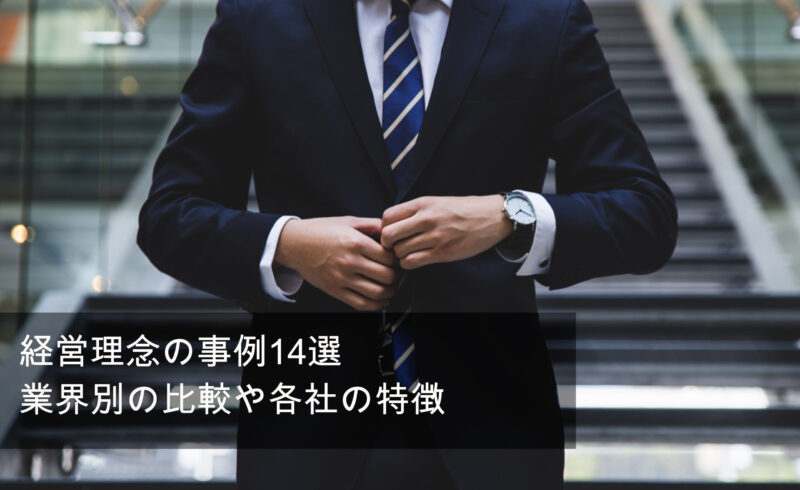
ビジョンに関するよくある質問
ビジョンに必要な要素はなんですか?
ビジョンには以下の要素が必要です。
- 「Why(なぜ)」で目的や使命を明確にすること
- 「How(どのように)」で価値観や原則に基づく進め方を定めること
- 「What(何を)」で具体的な目標や行動計画を示すこと
これにより、共感を生み、全員が一丸となって目指すべき未来像が共有されます。
「個人」のビジョンとはなんですか?
個人のビジョンは、自分の価値観や情熱、興味を反映した将来像です。自身の目標や現時点での優先事項に基づき、どのような自分になりたいかを明確にします。これにより、日々の行動がその目標達成に向けて具体化し、人生の方向性をしっかりと定めることができます。
「ビジョン」の言い換えはなんですか?
ビジョンは、「将来像」や「未来の姿」、「目指すべき方向」、「理想の状態」といった言い換えが可能です。また、組織や個人が達成したい「目標」や「展望」、「指針」としても使われます。これにより、ビジョンは単なる目標設定ではなく、未来への道筋や望む結果を示す言葉として理解できます。
上場企業100社のMVVまとめ集
ourly株式会社では、上場企業100社のMVVや経営理念などを1つのシートにまとめた資料をお配りしております。
ご興味お持ちの方はぜひこちらよりダウンロードください。
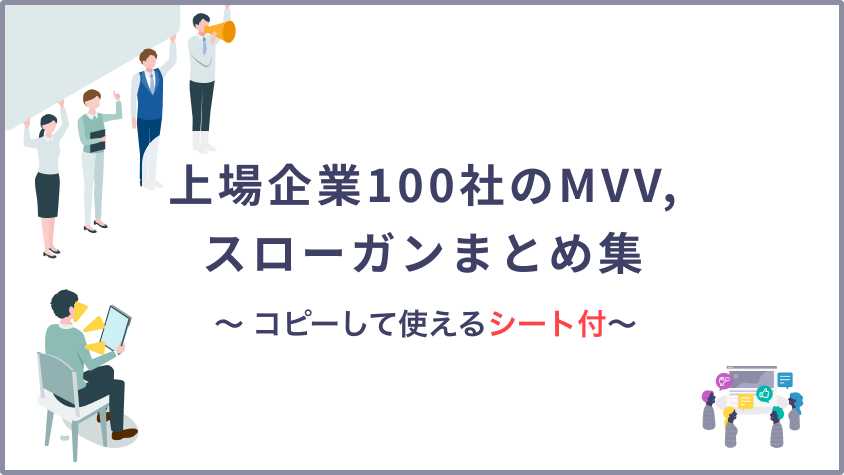
ビジョンで企業の将来を明確に
将来のビジョンを明確に示し、社員のエンゲージメントを高めることは、企業が発展していくためには欠かせない要素です。ビジョンは策定するよりも、浸透させ実践につなげることのほうが難しいです。多くの社員に正しく伝え、共感を集めることがビジョン浸透の第一歩となるでしょう。