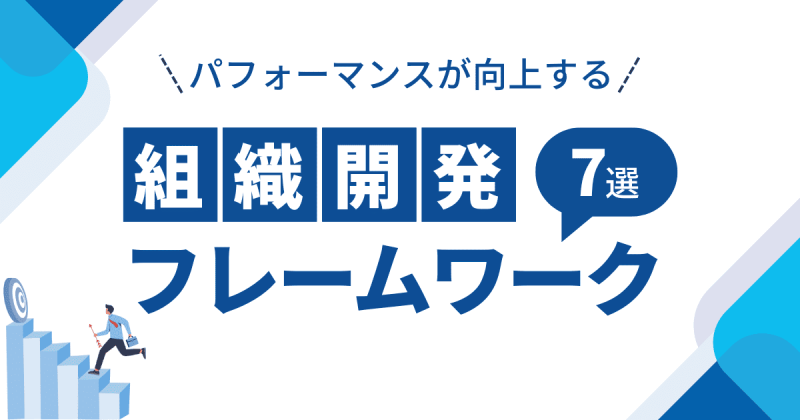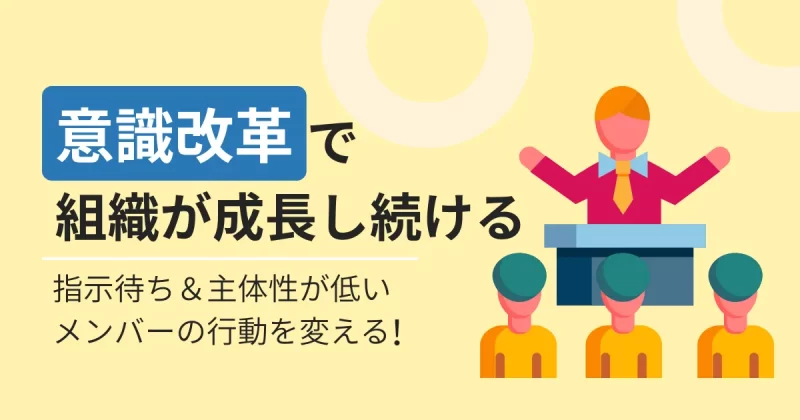企業などの組織が組織開発に取り組むことで、チーム全体の関係性が向上し組織のパフォーマンスが向上することが期待できます。
組織開発に効率よく取り組むためには、フレームワークを用いることがかかせません。
そこで本記事では、組織開発に役立つフレームワークとして「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」「7S」「ワールドカフェ」「OKR」「AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)」「コーチング」「タックマンモデル」の7つについて概要や特徴、運用方法などを解説します。
組織開発とは?
組織開発(Organization Development)とは、組織に所属する人材同士の関係性や相互作用に働きかけることで、組織全体のパフォーマンスを向上させ、より健全で効果的な組織を目指す一連の取り組みです。
単に制度やルールを変えるだけでなく、対話やワークショップを通じて、組織の風土や文化といった目に見えない部分にもアプローチするのが特徴です。
組織開発の目的
組織開発に取り組む大きな目的は、組織力強化による生産性向上です。
例えば、業務効率が上がれば限られた人員・時間でも効果的に成果を上げられ、パフォーマンスが向上します。残業代・休日出勤手当などのコストも削減でき、その分の費用を新たな設備投資や人員獲得に回すことができるでしょう。
また、組織の風通しをよくすることで従業員のエンゲージメントやモチベーションを上げ、活気をよくするのも組織開発のひとつです。新入社員から新しいアイディアが出てくるなどイノベーションが起きやすく、組織全体の利益につながります。
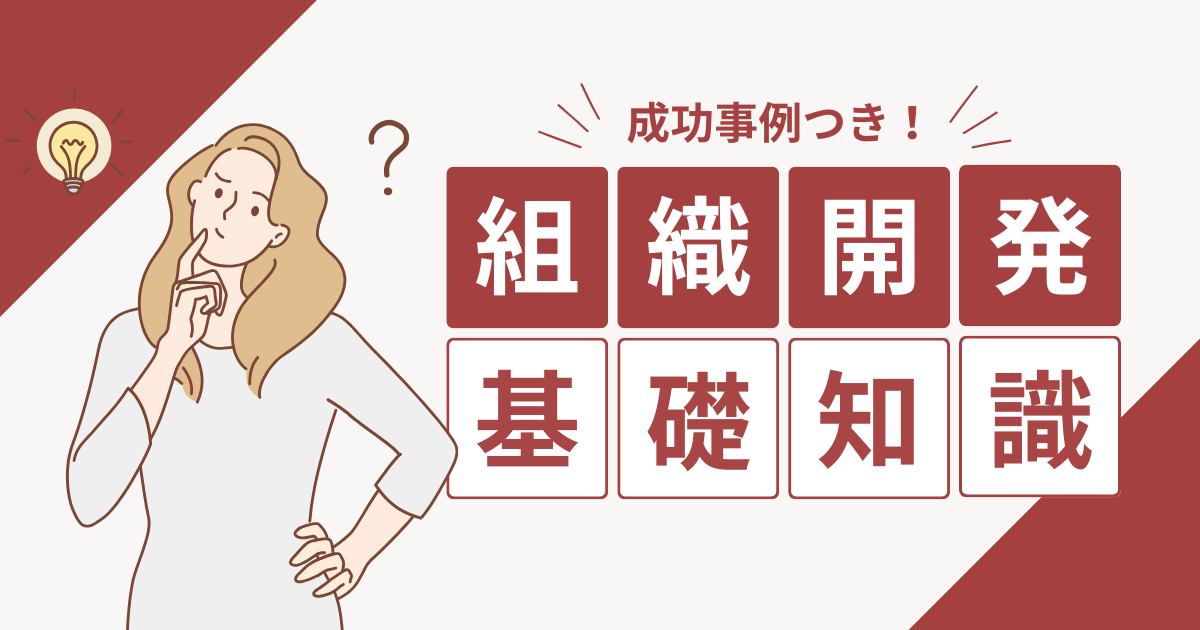
人材開発との違い
組織開発とよく似た言葉に「人材開発」があります。この二つの違いは、アプローチの対象にあります。人材開発が個々の従業員の知識やスキル向上に焦点を当てる「個人」へのアプローチであるのに対し、組織開発は従業員同士の関係性やチーム間の連携、組織の仕組みといった「関係性」や「全体」に焦点を当てます。
| アプローチ | 対象 | 具体例 |
| 人材開発 | 個人 | 研修、OJT、資格取得支援 |
| 組織開発 | 関係性・組織全体 | チームビルディング、1on1、組織文化変革 |
もちろん、個人の成長なくして組織の成長はありません。人材開発と組織開発は、車の両輪のように連携させて進めることが、企業の持続的な成長にとって不可欠です。
なぜ今、組織開発が注目されているのか?
現代のビジネス環境において、組織開発の重要性はますます高まっています。その背景には、働き方の多様化や市場の急速な変化があります。
働き方の多様化と人材の流動性
リモートワークの普及や雇用形態の多様化により、従業員の価値観は大きく変化しました。かつてのような画一的なマネジメントでは、従業員一人ひとりのエンゲージメントを高めることは困難です。
また、人材の流動性が高まる中で、従業員が「この組織で働き続けたい」と思えるような、魅力的な組織文化や良好な人間関係を構築することが、企業の競争力に直結しています。
市場の変化と求められる組織の姿
テクノロジーの進化や顧客ニーズの多様化により、ビジネスを取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。このような変化に迅速に対応するためには、トップダウンの指示を待つだけでなく、現場の従業員が自律的に考え、部門間で連携しながら新しい価値を創造していく組織体制が求められます。
組織開発は、このような変化に強いしなやかな組織を作るための重要なアプローチなのです。
組織開発のフレームワーク7選
ここでは、組織開発を成功させる代表的なフレームワークを紹介します。自社で検討したことのないフレームワークがあれば積極的に導入し、組織開発を効率化していきましょう。
1. MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は、企業の存在意義・理想像・行動指針を明確にすることで、従業員全員が同じ方向を目指しやすくなる組織開発の基盤です。部署や役職を超えて共通のゴールを持つことで一体感が生まれ、社内外からの信頼を高める効果も期待できます。
しかし、策定するだけでは形骸化しやすいため、浸透させる取り組みが不可欠です。
例えば、1on1ミーティングで繰り返し伝えることで理解を深め、バリューに沿った行動を評価する社内表彰制度でインセンティブを設ける方法が有効です。
また、社内報を通じて意義や事例を継続的に発信することで、従業員が日常的に意識できる環境をつくれます。
こうした取り組みにより、MVVは単なる理念に留まらず、行動や意思決定を支える実践的な指針として機能していきます。

2. 7S
7Sとは、企業が持つ7つの経営資源を整理・分析し、強みを生かした戦略立案を可能にするフレームワークです。「戦略」「組織構造」「システム・制度」というハード面と、「共通の価値観」「経営スタイル」「人材」「スキル」というソフト面に分かれ、それぞれが相互に影響し合います。
例えば、戦略やシステムが整っていればコンサルティング事業に適性があり、人材やスキルが豊富なら技術者派遣などのモデルが有効です。運用にあたってはまず各項目の現状を可視化し、強みと課題を明確にします。
その上で、不足を補う強化施策や強みをさらに伸ばす方策を考えることで、自社の競争力を高められます。

3. ワールドカフェ
ワールドカフェは、カフェのようなリラックスした雰囲気の中で少人数に分かれて自由に対話し、新たなアイディアやイノベーションを生み出すフレームワークです。
従来の会議のように結論を急ぐのではなく、テーマに沿って思いつきを共有し合うことが目的であり、新入社員や異なる部門のメンバーも気兼ねなく発言できる点が特徴です。心理的安全性が高まり、発言が否定されない環境をつくることで組織全体のエンゲージメント向上にもつながります。
運用にあたっては、4〜5人程度の小グループを編成し、全員が発言できる場を設けることが効果的です。話し合いの中で出た気づきや視点は、最後にチームごとに共有し、異なる意見の違いを学び合うことで新たな発想の土台となります。
この積み重ねにより、多角的な視野を持った組織づくりを促進できます。

4. OKR
OKR(Objectives and Key Results)は、組織や個人の目標を明確化し、成果を可視化するためのフレームワークです。Objectiveで「目標」を設定し、Key Resultsでその達成度を測る指標を定めることで、進捗確認や方向性の修正がしやすくなります。
OKRは「会社」「チーム」「個人」の3層で設定するのが望ましく、会社では経営目標や方針決定、チームではプロジェクト進捗や予算管理、個人ではスキルアップや成長実感の促進に役立ちます。
運用の際は、期限内に達成可能でありながらも挑戦的な水準に設定することが重要です。理想が高すぎると実行につながらず、簡単すぎると意義が薄れるため、努力すれば届く目標が適切です。また、定期的な振り返りを行うことで改善点が明確になり、次のアクションへつなげやすくなります。
こうしたサイクルを回すことで、OKRはモチベーションを高めつつ成果を最大化する仕組みとして機能します。

5. AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)
AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)は、ポジティブな質問を繰り返すことで組織や個人の強みを見出し、未来への可能性を広げるフレームワークです。
弱みや課題に焦点を当てるのではなく、価値や成功体験を起点に改革を進められるため、義務感ではなく自発的なモチベーションを生み出せるのが特徴です。
運用は「発見(Discover)」「夢(Dream)」「設計(Design)」「実行(Destiny)」の4ステップで進めます。まず過去の成功体験から強みを発見し、それを活かして描く未来像を共有します。続いて、その理想を形にする実行プランを設計し、具体的なアクションへと移していきます。さらに定期的に振り返りを行うことで改善を重ね、持続的な成長へとつなげます。
ポジティブな切り口で進めることで参加者の自信と熱意を高め、組織全体に前向きな変革を促す効果が期待できます。
6. コーチング
コーチングとは、マネージャーなど管理する側の立場が繰り返し質問・対話の場を設け、部下や後輩が自ら答えに辿り着けるよう誘導するフレームワークのことです。
似たようなフレームワークに「ティーチング」や「カウンセリング」がありますが、本来の目的が異なると理解しておきましょう。
ティーチングは「指導」の意味合いが強く、答えを直接的に授けるのが特徴です。社員研修・勉強会・セミナーなどの場は原則としてティーチングに該当します。また、コンサルティングは「相談」を意味する言葉であり、具体的な改善成果より精神的な安心・安定を目的とすることが多いです。心理的安全性の向上には寄与しますが、具体的な成果・成績の改善は見込めないケースがあるので注意しておきましょう。
一方、コーチングは「自走力」をつけるためのトレーニングであり、ゆくゆくはマネジメントがなくても自発的に行動・判断する従業員を育てます。
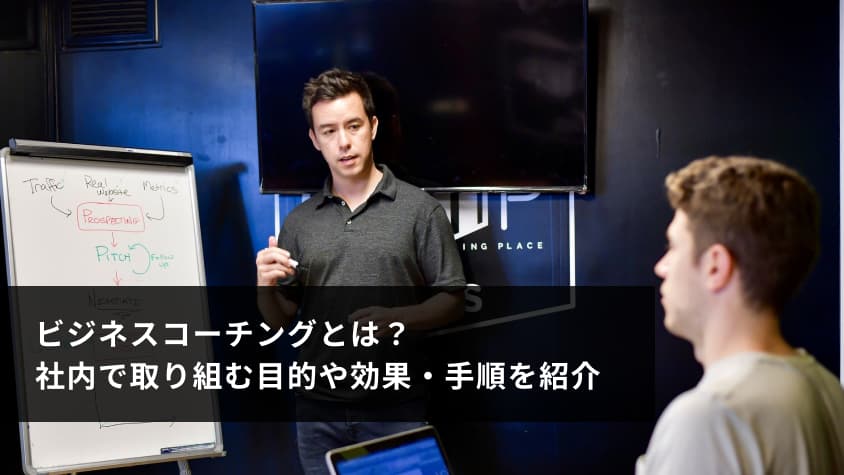
7. タックマンモデル
タックマンモデルとは、組織の成長段階を可視化しながらフェーズに合った対策をしていくフレームワークです。組織は「形成期」「混乱期」「統一期」「機能期」「散会期」の順で成長するとした考え方であり、心理学者のブルース・W・タックマン氏により提唱されました。
自社が今どのフェーズにいるか判断することで、今後の組織拡大に向けた戦略がとりやすくなるのがメリットです。経営判断に妥当性を持たせることもでき、社内の混乱・衝突を避ける意味合いも強いです。

組織開発を成功させるための5ステップ
フレームワークを選んだら、次はいよいよ実践です。組織開発は、以下の5つのステップで計画的に進めることが成功の鍵となります。
ステップ1:現状把握と課題の特定
まずは、自社の組織がどのような状態にあるのかを客観的に把握することから始めます。従業員アンケートやサーベイ、ヒアリングなどを通じて、組織の現状をデータで可視化します。その上で、「何が本当の課題なのか」という本質的な問いを立てることが重要です。
ステップ2:目的とゴールの設定
現状把握で見えてきた課題をもとに、「組織開発を通じてどのような状態になりたいのか」という目的とゴールを明確に設定します。このとき、「コミュニケーションを活性化させる」といった曖昧な目標ではなく、「部門間の定例会議の満足度が半年で20%向上する」のように、具体的で測定可能なゴールを設定することがポイントです。
ステップ3:アクションプランの策定
設定したゴールを達成するために、具体的な行動計画(アクションプラン)を作成します。どのフレームワークを用いて、誰が、いつまでに、何を行うのかを詳細に計画します。計画の実現可能性を高めるために、現場の従業員も巻き込みながらプランを策定することが望ましいです。
ステップ4:小規模での試験的な導入と効果検証
いきなり全社で大きな改革を進めるのはリスクが伴います。まずは特定の部署やチームを対象に試験的にアクションプランを導入し、その効果を検証します。この小さなサイクルを回す中で得られた学びや改善点を、次の計画に反映させていきます。
ステップ5:全社への展開と定着
試験導入で効果が確認できた施策を、全社的に展開していきます。展開して終わりではなく、新しい取り組みが組織の文化として根付くまで、継続的にフォローアップし、定期的に効果を測定・改善していくことが不可欠です。
組織開発を進める上での注意点
組織開発は一朝一夕に成果が出るものではありません。取り組みを成功させるために、いくつか注意すべき点があります。
経営層の主体的なコミットメント
組織開発は、人事部だけに任せるのではなく、経営層が強い意志を持って主導することが不可欠です。経営層が自らの言葉で改革の必要性やビジョンを語り、積極的に関与する姿勢を見せることで、従業員の意識も変わり、改革への協力が得られやすくなります。
長期的な視点を持つこと
組織の文化や人の関係性は、長い年月をかけて形成されたものです。それを変えるには、相応の時間と粘り強さが必要です。短期的な成果だけを求めず、少なくとも1年以上の長期的な視点を持って、継続的に取り組む覚悟が求められます。
フレームワークの目的化を避けること
フレームワークは、あくまで組織の課題を解決するための「手段」です。フレームワークを導入すること自体が目的になってしまい、本来解決すべき課題が見えなくなってしまうケースが少なくありません。常に「何のためにこれを行うのか」という目的に立ち返ることが重要です。
組織開発に役立つweb社内報 ourly
ourlyは一体感のある組織づくりを支援するweb社内報サービスです。
社内報運用に関する伴走支援が充実しているため、取り組みをやりっぱなしにせず、学びや気づきを組織の資産として活かすことができます。
ourlyの特徴
- SNSのようなコメント機能で、振り返りや共感を引き出す
- web知識不要で、誰でも発信できる
- 閲覧率・読了率の浸透度が可視化できる豊富な分析機能
- 支援体制が充実しており、運用負担が最小限にできる
「チームビルディングゲームを一過性で終わらせたくない」そんなご担当者様におすすめの社内報ツールです。
組織開発にはフレームワークを用いるのが効果的
効果的かつスピーディーな組織開発をするには、フレームワークを用いるのがおすすめです。自社の強み・弱み・課題はもちろん、働く従業員のスキル差や行動特性まで可視化しながら目標を策定できるので、無駄なく達成に向けて動くことができるでしょう。
なお、フレームワークの考え方を社内報で広く共有し、従業員の知識強化を図るのもおすすめです。「なぜこの手法で組織開発を目指すのか」など、根本的な背景・目的意識も広く共有していきましょう。