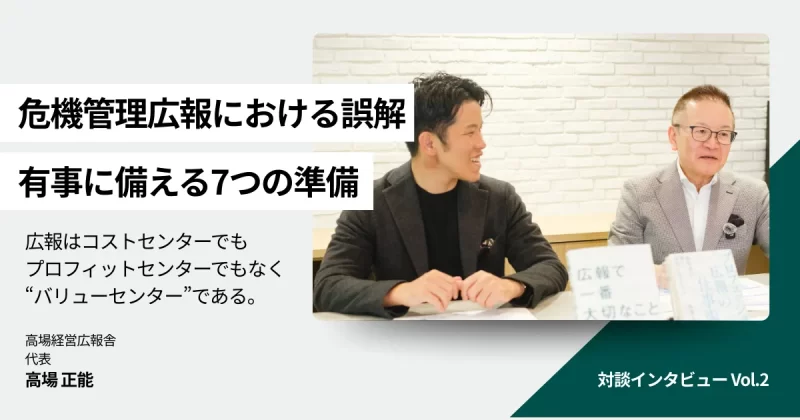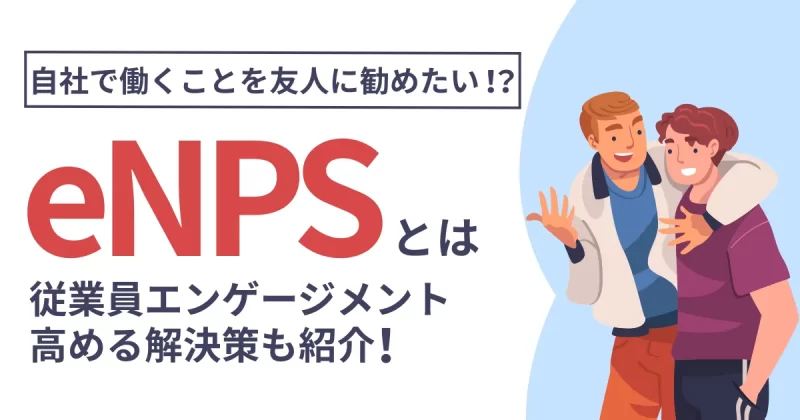従業員エンゲージメントの重要性が多く語られるようになりましたが、どのような施策を打てばいいのか、悩む企業様が多くいらっしゃいます。ここでは、従業員エンゲージメントについての調査・研究を元にオススメの施策10選をご紹介します。
従業員エンゲージメントとは
従業員エンゲージメントとは、従業員が企業や職場に対して抱くポジティブな感情・態度のことです。例えば、自分の仕事への情熱・熱意や、会社への忠誠心(愛着心)、仕事を通じて会社に貢献しようとする意欲などが含まれます。
会社との絆や繋がりの強さが高めることが、社員のモチベーションアップに繋がり、結果として、離職率の低下や業績の向上、労働生産性の向上などに寄与するとして、重要視されています。
・従業員エンゲージメントの定義
・従業員エンゲージメントの構成要素:2つの軸
・従業員エンゲージメントが事業や組織にもたらす好影響
などは、従業員エンゲージメントとは?定義・業績との関係性・施策を徹底解説をご覧ください。
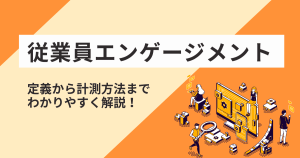
従業員エンゲージメント向上策を考える際の2つの軸
エンゲージメントに関する議論を整理すると、多くの研究やコンサルティング企業の定義では「仕事」と「組織」の大きな2軸が用いられています。それは、「日々の担当業務や職務内容への熱意・没頭感:仕事へのエンゲージメント」と「企業や組織そのものへの愛着・貢献意欲:組織へのエンゲージメント」です。
仕事へのエンゲージメント(ワークエンゲージメント)
「担当業務に面白さややりがいを感じるか」「自分の強みやスキルを活かせているか」といった、職務レベルの熱意や没頭感が焦点。
組織へのエンゲージメント(組織コミットメント)
「この会社(組織)で働き続けたいと思うか」「経営陣や組織文化に共感しているか」といった、組織全体へのロイヤルティや愛着が焦点。
この2つの軸は相互に影響し合います。仕事への熱意が高まれば組織への愛着が高まるケースもあれば、逆に「この会社が好き」という思いが強いから仕事も頑張れるケースもあります。
そのため、どちらかにかだけ効果的な施策というものではありませんが、主な狙いから施策を分類して紹介します。
なお、エンゲージメントサーベイを実施して、自社の課題を明確にした後に、これからご紹介する具体施策を検討することで、従業員エンゲージメント全体の底上げが期待できます。
従業員エンゲージメントの計測方法は【徹底解説】エンゲージメントサーベイとは?実施目的・手順・活用方法までをご覧ください。
【施策10選】従業員エンゲージメント向上策
ワークエンゲージメント(仕事への熱意・没頭感)を高める
(1) 仕事の意味づけ・役割明確化
施策の狙い
従業員が「自分の業務が組織や顧客にどう貢献しているか」を理解できるほど、仕事そのものへのモチベーションが高まるため、自律的かつ責任をもって業務に取り組みやすくなる。
具体施策例
・ジョブディスクリプション(JD)の明確化:各ポジションのミッション・期待成果を文書化し、本人と合意形成する。
・OKRやMBOなどの目標管理:個人目標と会社目標をリンクさせ、業務目的の明確化と進捗可視化を行う。
・上司・先輩からのこまめなフィードバック:日々の仕事での小さな成功や改善点を共有し、業務の価値を再認識できるようにする。
(2) キャリア開発・スキルアップ支援
施策の狙い
将来に向けたキャリアパスやスキルアップの見通しが持てると、仕事に対する意欲・没頭感が高まりやすい。また、社員が「自分の成長が会社の成長にもつながっている」と感じやすくなる。
具体施策例
・キャリア面談・目標設定面談の定期実施:半年〜年に一度、本人のキャリアビジョンをヒアリングし、必要な育成プランを設計する。
・ジョブローテーションや社内公募制度の導入:希望する部署やプロジェクトにチャレンジできる仕組みを作り、成長意欲を刺激する。
・学習プラットフォーム・社内勉強会の充実:オンライン学習ツールの無料利用枠やセミナー参加補助など、学習機会を拡充する。
(3) 公正な評価・フィードバック
施策の狙い
「正当な評価を受けている」と感じられるほど、従業員は担当業務に熱意や責任感を持ちやすくなる。適切なフィードバックが仕事の質を高め、さらなるモチベーション向上に繋がる。
具体施策例
・評価項目・プロセスの明確化・見える化:どのような基準・行動指標で評価が行われるかを具体的に周知する。
・評価者トレーニング・ピアレビュー:主観評価の偏りを防ぐため、複数の視点から評価する仕組みを導入。
・1on1ミーティングや定期面談によるフィードバック強化:結果だけでなくプロセスや行動にも注目し、業務の質とモチベーションを高める。
(4) 柔軟な働き方・ワークライフバランスの整備
施策の狙い
フレックス勤務やテレワークなどの制度が実際に機能し、「働きやすさ」を感じられるほど、日々の仕事に集中できる心理的余裕が生まれる。また過度な長時間労働の防止や休暇取得推進が、持続可能なパフォーマンスに繋がる。
具体施策例
・フレックス勤務・リモートワークの実装:勤務場所や時間帯を柔軟に調整し、ライフスタイルに合わせた働き方を実現する。
・制度利用促進&ロールモデルの活用:管理職や経営層が積極的に活用する姿勢を見せ、部署間の制度利用格差を減らす。
・休暇取得の推奨・強制取得制度:プロジェクト管理を徹底し、定期的な休暇でリフレッシュと効率化を図る。
組織コミットメント(企業への愛着・ロイヤルティ)を高める
(5) 企業理念・ビジョンの徹底浸透
施策の狙い
「会社がどんな社会的価値を提供し、何を大切にしているのか」を深く理解・共感するほど、会社への誇りや帰属意識が強まる。また組織文化への愛着が高まることで、離職率低減にも寄与する。
具体施策例
・経営トップによる定期的なビジョン共有:タウンホールミーティングや動画メッセージなどで、経営方針・理念を繰り返し発信する。
・理念・バリューを体現する行動の社内紹介:成功事例だけでなく、失敗やチャレンジ事例も含めて共有し、理念の“生きた姿”を伝える。
・オンボーディングへの組み込み:新入社員や異動者に対し、理念・ビジョン・カルチャーを学ぶプログラムを必須化する。
(6) 経営層とのコミュニケーション強化
施策の狙い
経営層が“遠い存在”にならないようにするほど、従業員は自社の方向性に納得感を持ちやすくなる。経営者を身近に感じることで、組織全体への信頼や愛着が育まれる。
具体施策例
・経営陣とのタウンホールミーティング定期開催:Q&Aやディスカッションを設け、双方向コミュニケーションを重視。
・経営トップによる社内報・動画発信:日々の意思決定の裏側や経営方針をタイムリーに共有し、透明性を高める。
・ランチセッションや若手との対話イベント:立場を超えた気軽な交流で、“経営の想い”を伝える場を増やす。
(7) 社員間の心理的安全性・信頼関係醸成
施策の狙い
社員同士が尊重し合い、遠慮なく意見交換できる文化が根付くほど、「この会社に属していることへの安心感・誇り」が高まる。組織として連帯感が強まり、ロイヤルティが向上する。
具体施策例
・定期的な1on1やグループワークショップ:部署を超えた交流イベントを企画し、カジュアルなコミュニケーションを促す。
・フラットな意見交換の場づくり:アンケートやチャットツールで気軽に声を上げられる仕組みを整え、組織の風通しを良くする。
・ハラスメント防止研修・マネジメント研修:管理職が心理的安全性を低下させる要因を理解し、適切なリーダーシップを発揮。
(8) 非公式ネットワークを活用するコミュニティ・社内サークル活動
施策の狙い
“趣味や興味”を通じた交流が非公式ネットワーク(組織図や業務フローに表れない社内ネットワーク)を形成し、部署を越えた情報共有やアイデア創出を促します。部門を超えた会話がしやすくなることで、仕事の効率化にも役立ち、組織としての一体感も高まりやすくなります。
具体施策例
・サークルなどの活動支援:活動費補助、オンラインコミュニティ(社内報など)の結成支援を行う。
・交流イベントの定期開催:アフター5のイベントや雑談会を定期開催し、職場の垣根を超えた繋がりを拡大する。
・協働活動の共有、承認:コミュニティ発のアイデアや改善事例を社内報などで共有し、仕事面でも意義があることを周知して、承認する。
(9) 社会的意義の共有(CSR・CSV・SDGsなど)
施策の狙い
社員が「自社の活動が社会の課題解決に貢献している」と感じるほど、会社を誇りに思う気持ちが高まります。結果的に組織コミットメントが強まり、「この会社の一員でありたい」と思う意識が育ちます。
具体施策例
・社会貢献プロジェクトへの参加機会提供:ボランティアやNPO連携など、従業員が自主的に参画できる枠組みを用意。
・SDGs推進チームやワークショップの実施:社員主体で目標を設定し、プロジェクト化して進める。
・成果・事例の社内外への発信:社内報やSNSを通じて取り組み内容を共有し、従業員の誇りとモチベーションをさらに高める。
(10) 多様性推進(D&I:ダイバーシティ&インクルージョン)
施策の狙い
性別・年齢・国籍・障がい・性的指向など、多様なバックグラウンドの社員が力を発揮できる環境は、イノベーションと心理的安全性に好影響を及ぼし、組織への誇りとワークエンゲージメントが同時に高まります。
具体施策例
・D&I研修の実施:階層別・目的別にD&I研修を行い、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を可視化する。
・ERG(Employee Resource Group)の支援:女性・LGBTQ+・外国籍社員などがコミュニティを形成し、経営層と対話。
・採用・評価・昇進プロセスの透明化と見直し:組織の中にある構造的な差別やハードルを排除する
“仕事”と”組織”のポジティブな循環を生む
仕事(ワークエンゲージメント)と組織(組織コミットメント)は、切り離しては考えられない表裏一体の存在です。個々の仕事への熱意が高まるほど、組織への愛着も強まりやすくなり、逆に「この組織で働きたい」というロイヤルティがあるほど日々の業務にも全力で取り組めるという、ポジティブな循環が生まれます。
また、どの施策をどの程度実行するかは、企業の規模や業態、文化によって異なります。
まずは自社の課題を特定し、優先度を決めて導入・改善を行い、さらに効果測定をしながら、施策を改善していくPDCAサイクルが重要です。
結果として、自社の強みと従業員の特性を活かしながら“自社らしい”エンゲージメント向上策が確立され、ワークエンゲージメントと組織コミットメントの両面が継続的に高まっていきます。