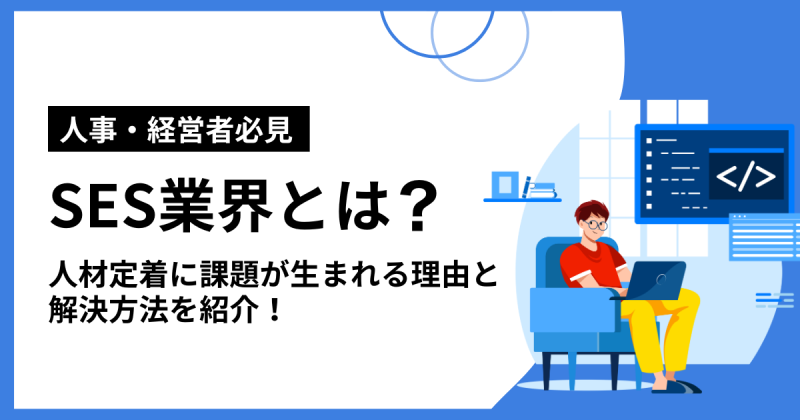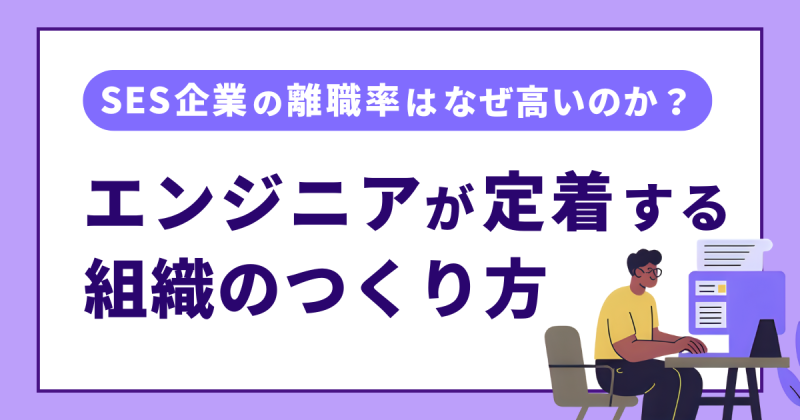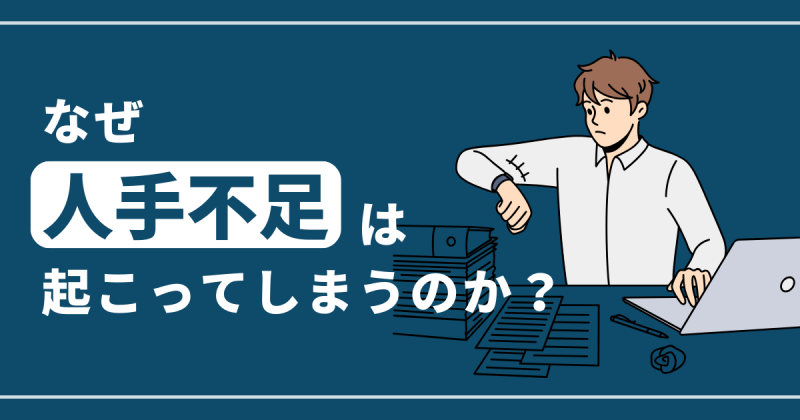多くのSES(システムエンジニアリングサービス)企業が、「エンジニアの離職率の高さ」や「採用活動の難化」といった共通の課題を抱えています。この問題の背景には、個々のエンジニアの価値観だけでなく、SESというビジネスモデルに根差した業界特有の「構造」が存在します。
特に、多様な経験を求めてこの業界を選ぶエンジニアにとって、「成長実感の停滞」は離職を考える大きなきっかけとなり得ます。
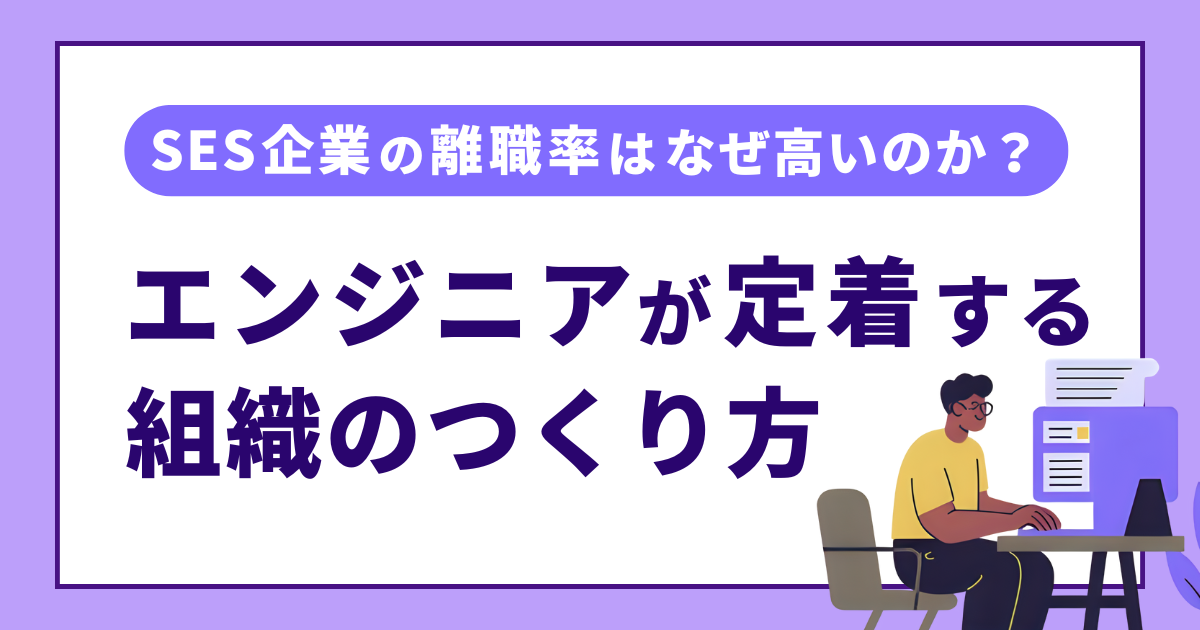
本記事では、SES業界の基本構造から、エンジニアの成長を阻害し人材定着を困難にする構造的課題、そしてエンジニアに選ばれる組織作りの方策までを、経営・人事の視点で体系的に解説します。
【経営視点で再整理】SES業界の全体像
まず、業界が抱える課題を理解するため、SESのビジネスモデルと現状を整理します。
SES(システムエンジニアリングサービス)のビジネスモデルとは
SESとは、クライアント企業に対し、ITエンジニアの技術力を労働力として提供するサービスです。
SES企業は自社で雇用するエンジニアをクライアントのプロジェクトに参画させ、その対価として報酬を得ます。契約形態は、業務の完成を目的としない「準委任契約」が一般的です。
SES業界の市場規模と成長性
DXの進展を背景にIT人材への需要は高まり続けており、SES業界の市場規模も拡大傾向にあります。
経済産業省が公表した「IT人材需給に関する調査」によると、2030年のIT人材の需給ギャップは78.7万人になると試算されており、IT人材の確保は企業にとって喫緊の課題であると言えます。
しかし、これは企業間の人材獲得競争が激化することも意味しており、組織としての魅力がなければ、エンジニアに選ばれることは一層困難になるでしょう。
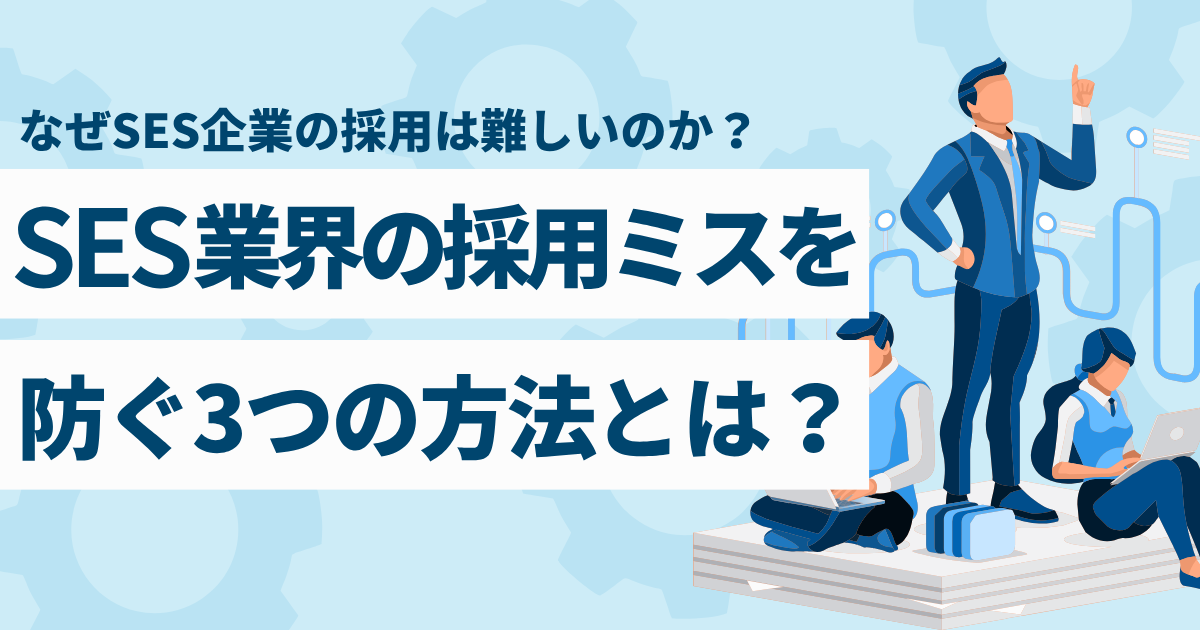
「派遣」「請負」「SIer」との違いとビジネス上の注意点
SESは他のITサービスと混同されやすいですが、経営視点では契約上の違いを明確に理解しておく必要があります。
派遣契約との違い
最大の違いは「指揮命令権」の所在です。派遣契約ではクライアントがエンジニアに直接指示を出しますが、SESでは指揮命令権はSES企業側にあります。
請負契約との違い
請負契約は「成果物の完成」に責任を負いますが、SESはエンジニアの労働力を提供することに責任を負います。
SIerとの違い
SIerはプロジェクト全体を一括で請け負う企業であり、SES企業はSIerから人材提供を依頼される協力会社、という関係性が一般的です。
人材定着を阻む、SES業界の3つの構造的課題
市場が成長する一方で、SES業界にはエンジニアのエンゲージメントを低下させ、離職につながる特有の構造的課題が存在します。
客先常駐モデルが招く「組織文化の醸成不全」と「帰属意識の低下」
エンジニアが自社ではなくクライアント先で就業する「客先常駐」は、自社の理念やビジョンを共有する機会を減らしてしまいます。特に、エンジニアが一人でクライアント先に常駐する状態では帰属意識が希薄になり、「どの会社にいても同じ」という感覚に陥りがちです。
一方で、複数人のチーム単位で参画する場合は、日常的な相談や連携が生まれ、一体感を醸成しやすくなります。このアサイン形式の違いが、帰属意識の維持に大きく影響します。
「キャリアの停滞感」を生む案件と評価の不透明性
多くのエンジニアは、多様な環境で実践経験を積み、スキルを広げることを目的にSES業界を選びます。しかし、アサインされる案件が本人の意向と異なったり、単調な業務が続いたりすると、その成長意欲は「このままではキャリアが停滞してしまう」という危機感へと繋がります。また、客先での働きぶりを自社が直接確認できないため、評価の客観性や公平性が担保されにくく、キャリアパスを描きにくいという問題も、成長実感の低下を招く一因となります。
多重下請け構造が引き起こす「利益率の圧迫」と「還元への限界」
IT業界、特に大規模プロジェクトでは、元請けから二次請け、三次請けへと仕事が再委託される「多重下請け構造」が常態化しています。この構造の下層に位置する企業ほど利益率が圧迫され、エンジニアの貢献に対して十分な報酬で応えることが難しくなります。エンジニアが自身の市場価値と待遇の間にギャップを感じた時、それは離職の直接的な動機となり得ます。
「この会社で働き続けたい」と思われる組織の作り方
これらの構造的課題に対し、企業はどのような対策を講じるべきでしょうか。ここでは4つの方向性を示します。
自社の理念やビジョンを共有できる場をつくる
最も大切なことは、自社の社員に対し、経営の理念や目指すべき方向性を共有していくことです。社員一人ひとりが企業の理念やビジョンを意識できるようにするためには、全社的な発信と交流の機会が欠かせません。
例えば、全社集会や食事会などを定期的におこない、フォーマル/インフォーマルなコミュニケーションを通して仕事への共通認識を育むことが必要です。
また、社内報やイントラネットなどを通じての情報発信をおこなうことで、いつでもどこでも見返せる仕組みをつくることも効果的です。

「チーム」を基本単位とし、心理的安全性を醸成する
帰属意識の低下や孤独感を解消する上で、チームでの案件参画を基本戦略とすることは有効です。すぐに相談できる仲間がいる環境は、心理的安全性を担保し、困難な課題へ挑戦する支えとなります。活発なコミュニケーションが生まれる土壌は、個人のパフォーマンス向上だけでなく、組織全体のナレッジ蓄積にも貢献します。
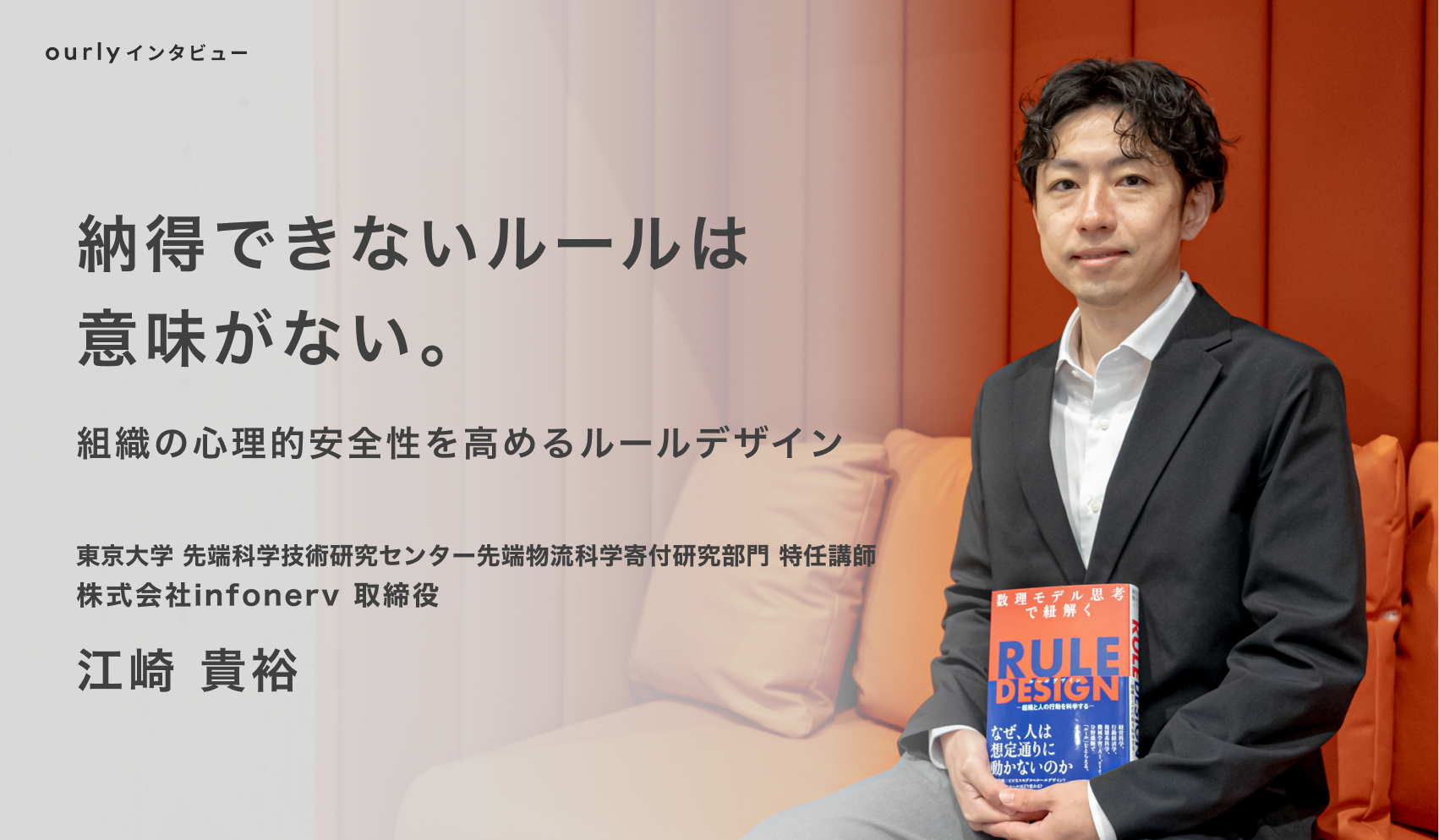
「キャリアサポーター」として、成長機会を共に創出する
エンジニアの成長意欲に応えることは、企業にとって重要な経営課題です。単に案件を割り振るのではなく、定期的な1on1やキャリア面談を通じて、本人が描くキャリアパスを会社が深く理解し、共に考える「サポーター」としての役割が求められます。会社の支援のもと、新しい技術やプロセスに挑戦できる機会を提供することが、エンゲージメントと定着に直結します。
成果と挑戦を正当に評価し、透明性の高い制度を構築する
エンジニアが安心して挑戦し続けるためには、そのプロセスと成果が正当に評価される文化と制度が不可欠です。スキルマップや明確な評価基準を公開して評価の透明性を高めること。そして、たとえ失敗しても、その挑戦を評価し、学びとして次に活かせる風土を醸成することが、エンジニアの挑戦意欲を育む上で重要です。
帰属意識の醸成にはweb社内報ourly
ourlyはもともとSES企業で親会社でもある、株式会社ビットエーでの組織課題を解決するために開始したサービスです。

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
SES業界の未来は「組織開発」にかかっている
本記事では、SES業界のビジネスモデルから、多くの企業が直面する人材定着の課題、そしてその背景にある構造的な問題と対策について解説しました。
客先常駐、キャリアの停滞感、多重下請け構造といった課題は、一朝一夕に解決できるものではありません。しかし、これらの課題と向き合い、自社の「組織力」を高めるための投資、すなわち「組織開発」に戦略的に取り組むことが、今後のIT人材獲得競争を勝ち抜く上で不可欠です。
個々のエンジニアのスキルに依存するだけでなく、従業員エンゲージメントを高め、社員が安心して長く働き続けられる組織を作ること。それが、SES企業の持続的な成長の鍵となります。