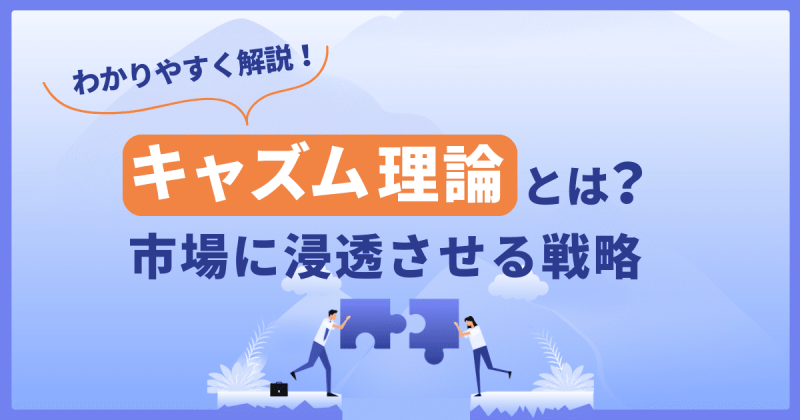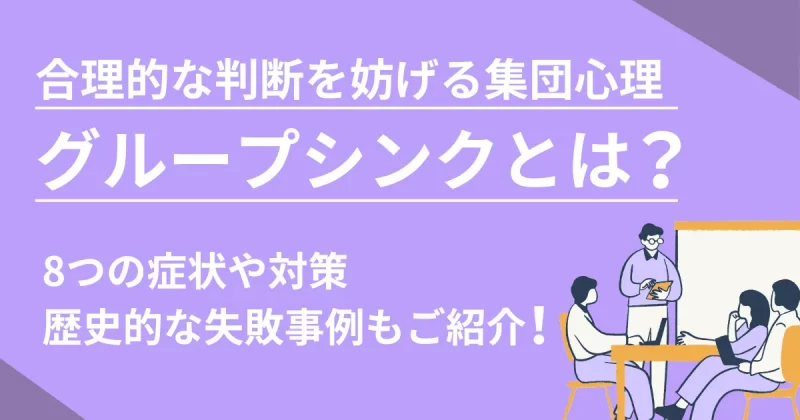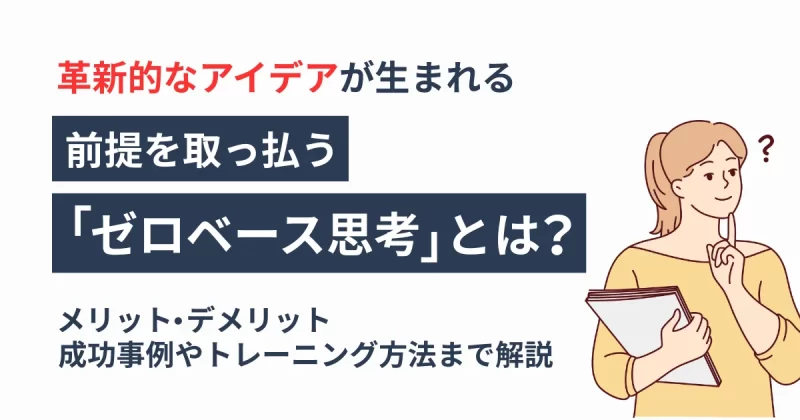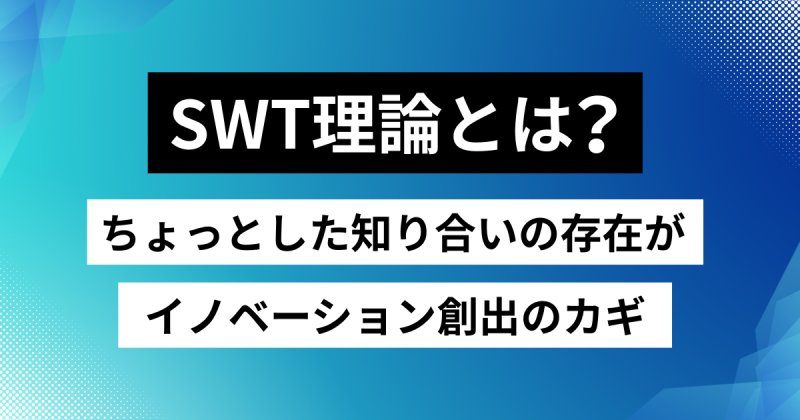新しい技術やサービスを市場に投入し、一部の先進的な顧客には受け入れられたものの、そこからなかなか普及が進まない、という経験はありませんか。その現象は「キャズム」が原因かもしれません。
キャズム理論は、特に新規事業やスタートアップにおいて、製品が市場に広く受け入れられるために越えなければならない「深い溝」の存在を示唆しています。
この記事では、キャズム理論の基本的な概念から、その発生原因、そして乗り越えるための具体的な戦略まで、成功事例を交えながら分かりやすく解説します。
キャズム理論とは?新規事業の成否を分ける「深い溝」
キャズム理論とは、新しい製品やサービスが市場に普及していく過程で、初期の顧客層から主要な顧客層へと移行する際に存在する、深刻な断絶(溝)を指すマーケティング理論です。
この溝を越えられるかどうかが、事業の成功を大きく左右します。
ハイテク業界から生まれたマーケティング理論
キャズム理論は、アメリカのマーケティングコンサルタントであるジェフリー・ムーア氏が1991年に出版した著書『キャズム(Crossing the Chasm)』で提唱しました。
当初は、技術革新のスピードが速いハイテク業界の製品を対象としていましたが、現在では様々な業界で新規事業を成功に導くためのフレームワークとして活用されています。
新しいものが市場に浸透する際の障壁を理解する上で非常に重要な考え方です。
前提となる「イノベーター理論」の5つの顧客層
キャズム理論を理解するには、その土台となった「イノベーター理論」を知る必要があります。
イノベーター理論は、社会学者のエベレット・ロジャース氏が提唱したもので、新製品の採用時期によって消費者を5つのタイプに分類します。
| 顧客層のタイプ | 市場構成比 | 特徴 |
|---|---|---|
| イノベーター(Innovators) | 2.5% | 革新者。リスクを恐れず、新しいものを最も早く採用する。情報感度が高い。 |
| アーリーアダプター(Early Adopters) | 13.5% | 初期採用者。流行に敏感で、他の消費者への影響力が大きい。「オピニオンリーダー」とも呼ばれる。 |
| アーリーマジョリティ(Early Majority) | 34% | 前期追随者。新しいものには比較的慎重だが、アーリーアダプターの動向を見て採用を決める。 |
| レイトマジョリティ(Late Majority) | 34% | 後期追随者。周囲の大多数が採用してから導入を検討する、懐疑的な層。 |
| ラガード(Laggards) | 16% | 遅滞者。最も保守的で、イノベーションに関心が薄い。変化を好まない。 |
アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に存在する「キャズム」
イノベーター理論では、アーリーアダプターの心を掴むことができれば、その影響力が波及し、自然とアーリーマジョリティ以降の層にも製品が普及していくと考えられていました。
しかしムーア氏は、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には、簡単には越えられない「キャズム(深い溝)」が存在すると指摘したのです。
この溝に落ちてしまい、広く普及することなく消えていく製品は少なくありません。
なぜキャズムは発生するのか?その主な原因
キャズムが発生する根本的な原因は、溝を隔てた両側の顧客層、つまり「アーリーアダプター」と「アーリーマジョリティ」の価値観が全く異なることにあります。
それぞれが製品やサービスに求めるものが違うため、同じアプローチでは通用しないのです。
「新しさ」を求める初期市場の価値観
イノベーターとアーリーアダプターで構成される「初期市場」の顧客は、製品の「新しさ」や「先進性」に強い魅力を感じます。
他の誰も持っていない最先端の技術をいち早く手に入れることに価値を見出し、多少の不具合や使いにくさには寛容です。
彼らは、自らの力で製品の可能性を見出し、活用方法を開拓していくことを楽しみます。
「安心感」を求めるメインストリーム市場の価値観
一方、アーリーマジョリティ以降の「メインストリーム市場」の顧客は、製品に対して「安心感」や「信頼性」「利便性」を求めます。
彼らは新しいものを採用することにリスクを感じており、「多くの人が使っているか」「導入することで確実にメリットがあるか」「サポート体制は万全か」といった点を重視します。
先進性よりも、実用性や他者の評価を判断基準とするのです。
| 市場 | 構成する顧客層 | 求める価値 |
|---|---|---|
| 初期市場 | イノベーター、アーリーアダプター | 新規性、先進性、技術的な魅力 |
| メインストリーム市場 | アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガード | 安心感、信頼性、実績、利便性、他者からの評価 |
キャズムを乗り越えるための具体的な戦略
価値観の異なるアーリーマジョリティの心を掴み、キャズムを越えるためには、初期市場とは全く異なる戦略が必要です。
ジェフリー・ムーア氏は、キャズムを越えるための具体的な戦略モデルを提唱しています。
ニッチ市場を攻略する「ボーリングアレー戦略」
キャズムを越えるための最初のステップは、特定のニーズを持つニッチな市場セグメント(=ボーリングの1番ピン)にターゲットを絞り、そこでの圧倒的なシェアNo.1を目指すことです。
そのセグメントの顧客が抱える課題を完全に解決する製品・サービスを提供することで、熱狂的なファンを獲得します。
そこで得た成功実績と評判が、隣接する他の市場セグメント(=2番ピン、3番ピン)へと波及し、ドミノ倒しのように市場を拡大していくのが「ボーリングアレー戦略」です。
市場全体を席巻する「トルネード戦略」
ボーリングアレー戦略によってニッチ市場を攻略し、メインストリーム市場への足がかりを築いた後は、市場全体を席巻するフェーズへと移行します。これが「トルネード戦略」です。
トルネード(竜巻)のように、業界標準となることを目指して一気に市場シェアの拡大を図ります。
この段階では、製品の供給体制やサポート体制を強化し、大量の需要に応えられるようにすることが重要です。
顧客の期待を超える「ホールプロダクト戦略」
アーリーマジョリティは、単体の製品(コアプロダクト)だけでなく、購入後のサポートや周辺サービスを含めた「完全な製品(ホールプロダクト)」を求めています。
ホールプロダクトとは、顧客が期待する成果を達成するために必要な、すべての要素が揃った状態を指します。
自社だけで提供できない場合は、他社とのパートナーシップも視野に入れ、顧客の満足度を最大化するエコシステムを構築することが、キャズム越えの鍵です。
キャズム理論の成功事例から学ぶ
理論を理解するために、実際にキャズムを乗り越えて成功した企業の事例を見ていきましょう。
【BtoC事例】メルカリ:利用者を拡大させた戦略転換
フリマアプリの「メルカリ」は、キャズム越えの好事例です。
メルカリは2013年7月のサービス開始後、比較的早期からマーケティング戦略を重視し、プロダクトの改善と並行して積極的な広告展開を計画していました。
実際、2013年末にはすでにテレビCMの制作を開始し、資金調達のタイミングを見計らっていました。
そして、2014年3月に約15億円の資金調達を完了後、アプリのダウンロード数が200万を突破したタイミング(2014年4月末)で、テレビCMなどの大規模なプロモーションを開始。
この戦略的タイミングにより、口コミ効果とCM効果の相乗効果を生み出し、「みんなが使っている」という安心感を醸成してアーリーマジョリティ層への普及を一気に加速させ、CM開始後には400万ダウンロード、月間流通額10億円を達成し、現在の地位を築きました。
出典:テレビCM活用し急成長を遂げたメルカリの広告戦略|KAIGI GROUP
【BtoB事例】セールスフォース:クラウド市場を創出した戦略
今では当たり前となったSaaS(Software as a Service)ですが、登場当時は画期的なモデルでした。
セールスフォース社は、「ソフトウェアの終焉」というキャッチーなメッセージを掲げ、従来のパッケージソフトに不満を持つイノベーターやアーリーアダプターに強く訴求しました。
そして、ニッチな市場で実績を積み上げた後、大企業でも安心して使えるセキュリティや機能拡張性をアピールすることで、保守的なメインストリーム市場の信頼を獲得し、クラウド市場そのものを創出することに成功しました。
キャズム理論を活用する際の注意点
キャズム理論は強力なフレームワークですが、活用する際にはいくつかの注意点があります。
すべての製品に当てはまる理論ではない
キャズム理論は、特にこれまでにない新しい技術やビジネスモデルを持つ「非連続なイノベーション」を伴う製品・サービスで顕著に見られる現象です。
既存製品の改良版など、顧客が価値を理解しやすい製品の場合は、明確なキャズムが発生しないこともあります。
自社の製品の特性を見極めることが重要です。
市場の変化に合わせた柔軟な対応を行う
市場や顧客のニーズは常に変化しています。
理論に固執するのではなく、自社の製品が今どの市場フェーズにあるのかを定期的に見極め、顧客の声に耳を傾けながら、戦略を柔軟に修正していく必要があります。
現状を正しく把握し、ターゲット顧客に合わせたアプローチを心がけましょう。
顧客の導入障壁を正しく理解する
アーリーマジョリティが製品導入に踏み切れない理由は、「価格が高い」「使いこなせるか不安」「導入事例が少ない」など様々です。
なぜ彼らが不安を感じるのか、その導入障壁(ハードル)を正確に理解し、それを取り除くための施策(導入サポート、分かりやすいマニュアル、成功事例の提示など)を講じることが、キャズムを乗り越えるためには不可欠です。
まとめ
キャズム理論は、新しい製品やサービスを市場に普及させる上で避けては通れない障壁と、それを乗り越えるための道筋を示してくれます。
初期市場の熱狂に満足することなく、その先にいるメインストリーム市場の顧客層の価値観を理解し、彼らに響くアプローチへと戦略を転換することが成功の鍵です。
本記事で紹介した内容が、皆様のビジネスを成功に導く一助となれば幸いです。