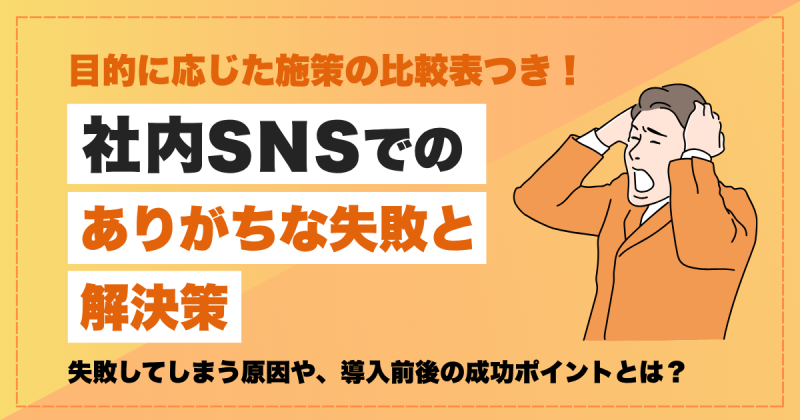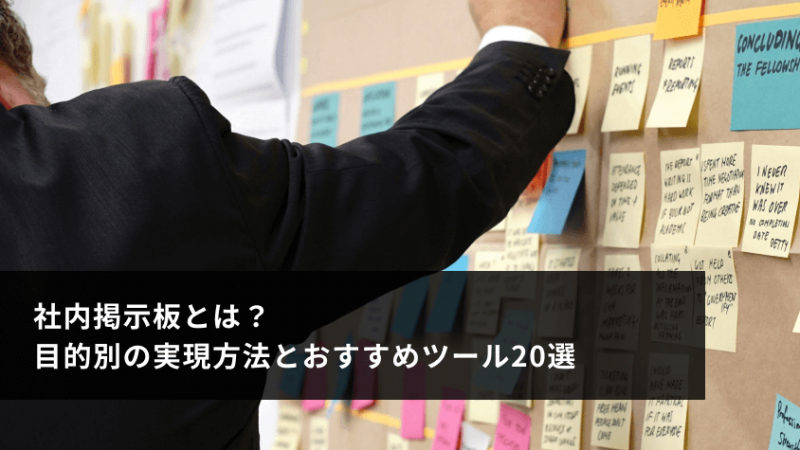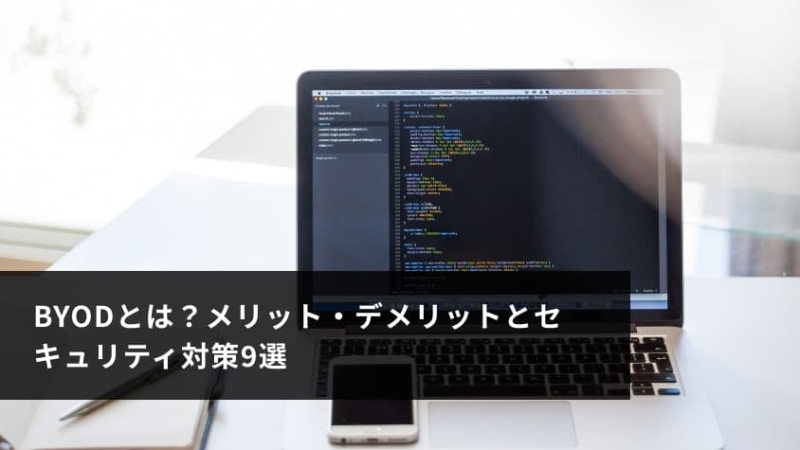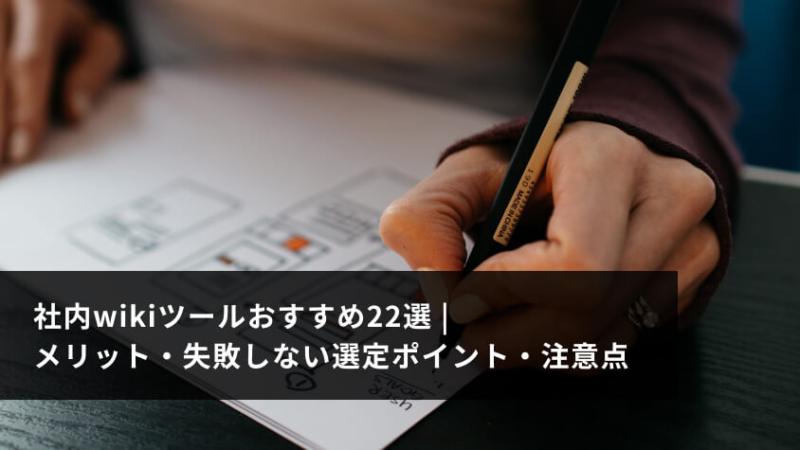リモートワークの普及により社内SNSの需要は高まっており、すでに社内SNSを導入している企業や、これから導入を検討される企業もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、社内SNS上でのコミュニケーションや、他ツールとの差別化などに課題を持つ企業は少なくありません。
本記事では、社内SNSの導入に失敗する原因や対策、成功するためのポイントを解説します。
また、以下の記事では社内SNSツール7選の比較をしていますので、具体的なツールを検討されている方はご覧ください。

社内SNSでよくある失敗事例
この章では、よくある失敗事例を2つのパターンに分けて紹介します。
投稿数が少なくなる
社内SNS内での投稿数が少なくなる、つまり利用されなくなることによって、導入失敗となるパターンです。
投稿が少なくなる原因としては、「ツールの使い分けができていないこと」や「上司や役員が恐れられていること」や「利用者が限定されていること」などが挙げられています。
詳しくは次の章の「社内SNS導入の失敗原因」を見直してみてください。
投稿内容が意図しないものになる
社内SNS内での投稿内容が、当初意図していたものとは違うものばかりになったことによって、導入失敗となるパターンです。
具体的には、プライベートな投稿ばかりになった場合や、決まった業務報告(日報など)ばかりになった場合が挙げられます。
原因としては、「目的・使い方を定めていないこと」「目的・使い方が浸透していないこと」が挙げられます。成功するポイント・成功事例については次章以降で解説します。
社内SNSで失敗する原因8選
社内SNSを導入する企業が増加する一方で、コミュニケーションの円滑化やスピーディーな情報共有といった、期待した効果を得られなかった企業は少なくありません。
社内SNS導入の失敗について、どのような原因が考えられるでしょうか。
他のコミュニケーションツールとの使い分けをしていない
社内SNSと他のコミュニケーションツールとの使い分けができていないことも、導入失敗の原因のひとつです。
職場でのコミュニケーションツールは、社内SNSに限らずメールや電話、テレビ会議など多岐にわたります。
コミュニケーションツールの明確な使い分けができていない場合には、情報があちこちに分散され混乱につながります。そのため、結果として浸透するツールもあれば、反対に浸透されないツールもでてきてしまうでしょう。

社内SNSの導入目的が不明確
社内SNSの導入目的が不明瞭であることも、導入失敗を招く恐れがあります。
注目度が高いからなんとなく社内SNSを導入する場合や、社内SNSを導入することそれ自体が目的になっている場合など、導入目的が不明瞭であると、導入してもやがて利用しなくなってしまうでしょう。
目的によっては、社内SNSよりも社内報や社内ポータルなどといった類似ツールを用いた方が組織活性化に繋がる可能性があります。
| 特徴 | 社内SNS | Web社内報 | イントラネット グループウェア | チャットツール |
|---|---|---|---|---|
| 理念方針浸透 | 〇 | |||
| 組織間の相互理解促進 | 〇 | 〇 | ||
| 社員間の個人的な繋がり強化 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| コミュニケーション速度向上 | 〇 | 〇 | ||
| 社内規則などの掲示/伝達 | △ | |||
| コミュニケーションの性質 | ボトムアップ型 | トップダウン型 | トップダウン型 | 個人→個人型 |
| 情報の再活用/ストック性 | △ | 〇 | 〇 | × |

目的や使い方が浸透していない
たとえ目的を持って社内SNSを導入していたとしても、目的を達成するための使い方・ルールを定め、それを浸透させなければ、導入失敗に終わってしまいます。例えば「プライベートな投稿ばかりになる」などが失敗事例として挙げられるでしょう。
Twitterを含め、SNSはプライベートで使用することが多いツールです。つまり一般的に、SNSを仕事で使うことは慣れていないことであるため、全社に使い方・ルールを示すことが重要なのです。
利用者が固定化してしまう
利用できる人を制限したり、決まった人しか積極的に利用していないなど、利用者が固定化されてしまうと、失敗につながります。
一部の決まった人しか利用しなければ、社内SNSを利用する人と利用しない人でコミュニティが分断されてしまい、より社内SNSを使う人たちが限定されていく可能性があります。
こうなると、本来の社内コミュニケーションの活性化を達成できずに終わってしまうでしょう。
投稿頻度が利用者に依存する
社内SNSは誰でも投稿ができる一方で、投稿頻度も利用者に依存する可能性があります。
継続的な運用をおこなうための仕組みづくりが必須であり、ここが機能しないと全く使われなくなり形骸化して失敗してしまうケースもあるでしょう。
上司や役員が恐れられている
「怖い」と思われている上司や役員がいると、従業員は投稿をしづらくなります。特に普段から厳しい上司が、社内SNS上で叱責や注意を行うと、投稿数は減少していくでしょう。
誰もが気軽に投稿できることが、本来の社内SNSの魅力といえます。SNSは文面でのコミュニケーションで表情が見えづらいため、伝え方には注意が必要です。
投稿に強制感がある
強い目的意識から生まれる強制感が、従業員にとってストレスになってしまうと目的は達成できないでしょう。
従業員に強制的に社内SNSで何か投稿させたり、強制ではなくとも、
「自分も投稿しないといけないのかな・・」
など、半強制になってしまっても、社内SNSが失敗してしまいます。
リアクションやコメントがない
リアクションやコメントが無いと投稿自体が減少し、導入の目的を達成できず、失敗に終わってしまいます。
例えば、TwitterやFacebookでは「いいね数」が各投稿に表示されています。SNSではこうしたリアクションこそ、投稿のモチベーションになるものです。
社内SNSを成功させるポイント
社内SNSに失敗する原因について解説しました。
では、社内SNSを成功させるためには、どのようなポイントを意識する必要があるのでしょうか。導入前と導入後に分けて解説します。
導入前のポイント
利用目的を明確にする
まず、なぜ社内SNSを導入するのかという目的が明確になっていなければ、施策に対する評価も改善もできません。「コミュニケーションの円滑化」「スピーディな情報共有」など、導入の目的を明確にすることにより、目的に適した社内SNSツールを選ぶことができます。
利用シーン・活用シーンを具体的にする
目的が決まったら、「誰が・いつ・どんな場面で使うのか」も明確にしましょう。
たとえば「プロジェクト進捗の共有」「新入社員の自己紹介」「週次の数値目標の共有」など、具体的な業務の中に社内SNSが組み込まれることを想定しましょう。
事前に利用シーンを設定しておけば、現場での活用がスムーズになります。
他ツールとのすみわけを明確にする
すでに導入しているツールとの役割を明確にすることも大切です。
たとえば、「Slackでは日々の業務連絡」「社内SNSではカジュアルな交流」といったように、目的に応じて、どの情報をどこに投稿すべきかをあらかじめ決めておきましょう
役割の棲み分けを明確にすることで、情報が分散したり、ツールが形骸化したりするのを防ぎます。

最低限のルールを決めておく
オンボーディングを実施する際には、最低限のルールを決めておきましょう。
極端に硬い投稿ばかりになってしまったり、逆にプライベート化してしまうことは、社内SNS導入失敗の典型例です。
そこで、一定のルールを設けることにより、導入目的に沿わない浸透を防ぐことができます。
導入後のポイント
トライアル期間を設ける
多くの社内SNSなどのツールは、無料トライアル期間などが設けられています。
そのため、トライアル期間を利用し、その社内SNSが導入目的を果たせるかどうか試すことも、導入成功につながるでしょう。
トライアル期間で実際の従業員の様子を伺うことで、社内SNS導入後のイメージがつきやすくなります。
担当者が周りを巻き込む
オンボーディングをする際や導入してすぐの時期は、投稿することをためらう社員は少なくないでしょう。
ですが、社内SNS上のコミュニケーションが活性化されれば、投稿やコメントをするハードルを下げることができます。
まずは、施策の担当者となる人事や広報部門が積極的に活用し、いかに周囲を巻き込み盛り上げられるかがポイントです。
気軽に発信できる雰囲気・空気を作る
社内SNSが失敗する原因として、従業員がストレスを感じてしまうということを紹介しました。
そういった状況を生まないためにも、積極的に役員や上司などのマネージャー職の方から、共有しやすい内容を発信をしましょう。また、若手従業員が何か発信した際には、積極的にいいねやコメントなどで反応をしてあげましょう。
社内SNSを盛り上げるポイント
社内SNSがなかなか盛り上がらないことに苦しむ企業は少なくないでしょう。
では社内SNSを盛り上げるために、どのような工夫をすることができるでしょうか。以下で説明していきます。
投稿にその人らしさを出す
社内SNS上で何か情報を共有する際、投稿者は自身の意見や共有した理由を記載し、その人らしさを出すのが効果的です。
有益な情報をいち早く共有したいがために、リンクのみを投稿しても、閲覧者からの反応が起こりにくいでしょう。
そのため、投稿時に投稿者自身のコメントがあることにより、その後の議論の活性化につながります。
社内SNSのプロフィールを充実させる
社内SNS導入の際に、しっかりとプロフィール欄を記載しておくことも重要です。
社内SNSが狭い領域で利用される場合には、利用者は互いに面識があるかもしれません。しかし、広い範囲で社内SNSを利用する場合には、投稿者の事を知らない可能性もあります。
そのため、プロフィール欄を充実させることによって、誰もが投稿者の人物像を知ることができ、投稿された内容への理解も深まるでしょう。
数値の進捗はと行動はセットで投稿する
社内SNS上で目標やKPIの進捗を共有する企業も多いでしょう。
多くの人に簡単に共有できる点で優れていますが、数値だけを共有すると読みづらく、また興味を示す人が限られてしまうかもしれません。
そのため、数値と共に目標・KPIに対して寄与した社員について投稿するなど、社員の興味を引く内容を紐づけることも効果的です。
時間帯で投稿内容を分ける
時間帯によって、投稿内容を分けることも重要です。
勤務中や出勤中あるいは勤務後など、時間帯によって社員の求める情報は異なるでしょう。プライベートの時間に重い内容を投稿しても、興味を示す社員は少ないかもしれません。
そのため、時間帯を意識した投稿を心がけることにより、社内SNSを盛り上げることにつながります。
読みやすさを意識する
投稿者は、太字や色付けなど各社内SNSツールの機能を利用し、読みやすさを意識することが大切です。
長い文章や硬い内容の文章であると、閲覧者の興味を引くことが難しくなります。多くの人の興味を引くためにも、太字や文字色の変更などをし、読みやすい投稿になるようにしましょう。
社内SNSの失敗は、慎重な導入で回避できる
社内SNSを導入する企業は、急速に増加しています。しかしその反面、社内SNSの導入や浸透に苦しむ企業も少なくないでしょう。
目的をきちんと整理し、「社内SNSの導入で組織課題を解決できるのか」「他のツールと検討の余地がないか」「導入後、どのように盛り上げていくか」など、多くの利用者に浸透させ、活用していくためにも、入念な準備をして導入しましょう。
失敗しない組織活性化ツールなら ourly(アワリー)
ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制の強みを持ち、新たな社内コミュニケーションを創出する魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「社内の雑談が減った」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。