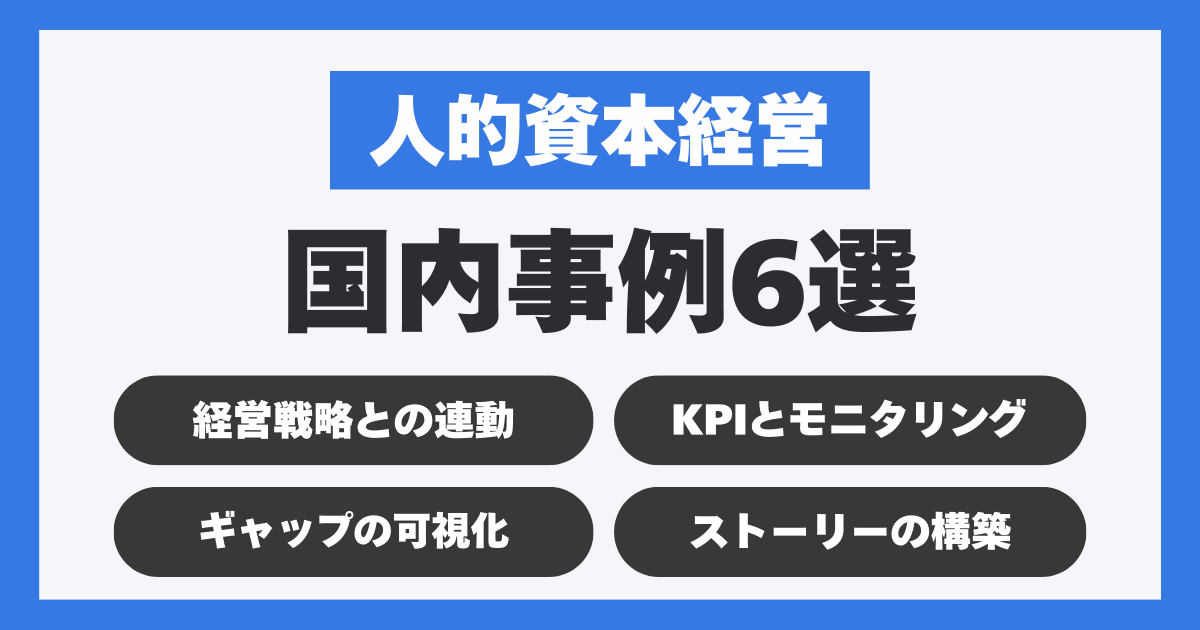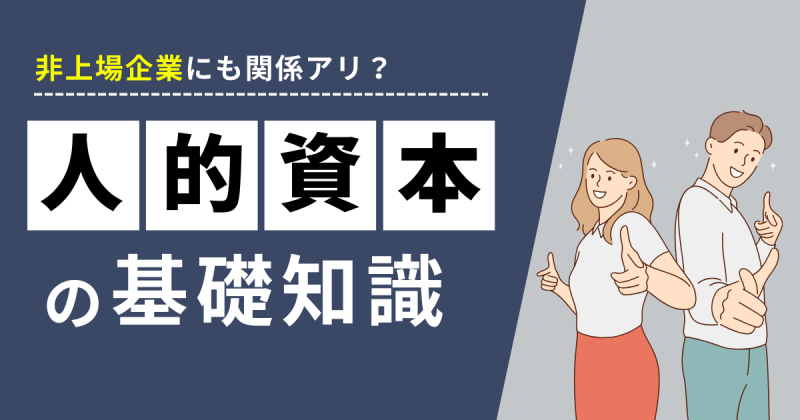近年、企業の持続的成長における「人的資本」の重要性が高まるなか、多くの経営者や人事担当者が指針としているのが、経済産業省が公表した「伊藤レポート」です。
この記事では、経済産業省が公開する資料をもとに「人材版伊藤レポート」「人材版伊藤レポート2.0」「SX版伊藤レポート3.0」の要点を整理し、人的資本経営を実践するためのフレームワークである「3つの視点(3P)」と「5つの共通要素(5F)」について解説します。
人的資本経営を推進する担当者の方が、その目的と具体的なアクションプランを理解し、経営層への説明や社内での企画立案に活用できる内容となっています。
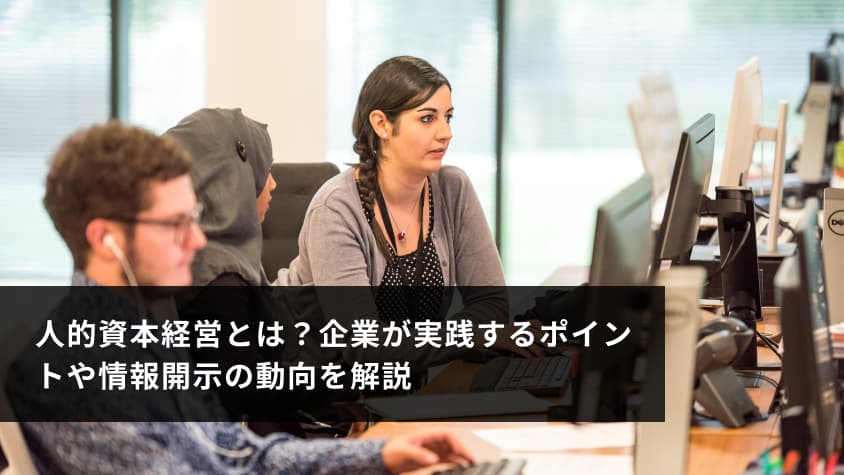
伊藤レポートとは
「伊藤レポート」とは、一橋大学の伊藤邦雄氏が座長を務めた経済産業省の研究会が公表した、一連の報告書の総称です。企業価値の決定要因が、工場や設備といった有形資産から人材などの無形資産へと移行する現代において、日本企業が持続的に価値を創造していくための経営のあり方を示しています。
人材版伊藤レポートとは
人的資本経営の文脈で「伊藤レポート」という場合、一般的には2020年9月に公表された「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書」、通称「人材版伊藤レポート」を指します。
このレポートは、企業の競争力の源泉は人材であり、人材はコストではなく価値創造の担い手となる「資本」であると定義しています。
参照:https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf (最終閲覧日:25/08/26)
人材版伊藤レポート策定の背景
「人材版伊藤レポート」策定の背景には、産業構造の急激な変化や少子高齢化、個人のキャリア観の多様化など、企業と個人を取り巻く環境の大きな変化があります。
こうした変化のなかで多くの日本企業が直面する経営課題は、人材面の課題と密接に関係しています。従来の雇用慣行や人事制度のままでは変化に対応できず、持続的な成長が困難になるという問題意識から、経営戦略と連動した新たな人材戦略への変革を促すことを目的としています。
人材版伊藤レポート2.0とは
2022年5月に公表された「人材版伊藤レポート2.0」は、初版のレポートが示した問題提起をさらに一歩進め、企業が人的資本経営を具体的に実践するためのアイデアや施策を提示するものです。
初版の公表後、多くの経営者から「具体的に何から始めればよいのか」という声が寄せられたことを受け、より実践的なガイドとなるよう、先進企業の取り組み事例なども盛り込まれました。
参照:https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220513001/20220513001.html (最終閲覧日:25/08/26)
伊藤レポート3.0とは
2022年8月に公表された「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」では、「サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)」という概念が提示されました。これは、気候変動や人権問題といった社会のサステナビリティ(持続可能性)と、企業のサステナビリティ(長期的に稼ぐ力)を「同期化」させる経営変革を指します。
このレポートは人的資本経営を「SX」という、より大きな経営の枠組みのなかに位置づけ、企業と投資家が対話を通じて長期的な企業価値を創造していくためのフレームワークを示しています 。
参照:https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220831004/20220831004.html (最終閲覧日:25/08/26)
人材戦略に求められる「3つの視点(3P)」
「人材版伊藤レポート」では、経営戦略と連動した人材戦略を構築する上で重要となる、3つの視点(Perspectives)が示されています。
経営戦略と人材戦略の連動
最も重要な視点は、人材戦略がビジネスモデルや経営戦略と深く連動しているかという点です。企業ごとにビジネスモデルが異なるように、人材戦略も各社独自のものであるべきだとされています。自社の経営戦略を実現するためにどのような人材が必要で、どのように育成・配置するのかを具体的に考えることが第一歩となります。
「As is-To be」ギャップの定量把握
次に、目指すべき姿(To be)と現状(As is)のギャップを、可能な限り定量的に把握することが求められます。
例えば、デジタル化を推進する経営戦略がある場合、「必要なデジタル人材の人数」をKPIとして設定し、現状との差を明確にすることがこれにあたります。
このギャップを客観的なデータで把握することで、人材戦略の進捗を管理し、PDCAサイクルを回すことが可能になります。
企業文化への定着
策定した人材戦略を単なる人事制度の変更で終わらせず、組織や個人の行動変容を促し、企業文化として定着させているかという視点も重要です。
企業文化は一朝一夕に醸成されるものではなく、人材戦略を実行するプロセスを通じて育まれるものとされています。経営トップ自らがその重要性を粘り強く発信し続けることが不可欠です。
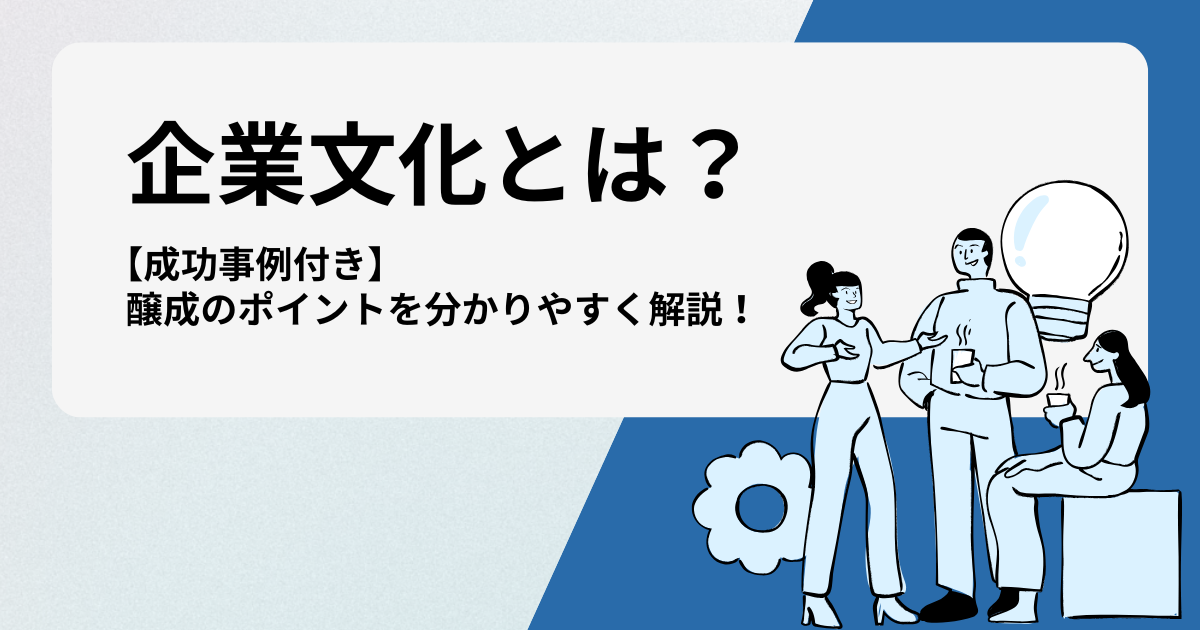
人材戦略に求められる「5つの要素(5F)」
3つの視点に基づき、具体的な人材戦略を検討する上で共通となる5つの要素(Common Factors)も示されています。
動的な人材ポートフォリオ
経営戦略の実現に向けて、必要な人材を質・量の両面で最適化することを指します。
将来の目標から逆算して必要な人材要件を定義し、平時からリスキルや外部からの獲得、戦略的な再配置などを行うことで、常に最適な人材ポートフォリを維持することが求められます。
知・経験のダイバーシティ&インクルージョン
中長期的な企業価値向上のためにはイノベーションが不可欠であり、その原動力となるのが多様な個人の掛け合わせです。
性別や国籍といった属性だけでなく、他業界での経験や専門性など、多様な「知と経験」を積極的に取り込み、それらを活かせる組織環境を整えることが重要です。

リスキル・学び直し
急速な事業環境の変化に対応するため、従業員のスキルの再開発(リスキル)や学び直しを促進する要素です。
特にITリテラシーの向上は必須とされ、同時にAIには代替できない創造性などのスキルも重要視されています。
企業は従業員の自律的なキャリア構築を支援する立場として、学びの機会を提供することが求められます。
従業員エンゲージメント
従業員が企業の目指す姿や方向性に共感し、その達成に向けて自発的に貢献しようとする意欲を指します。
従業員エンゲージメントは、他の施策の基盤となる重要な要素です。
企業は多様な働き方を認め、魅力的な就業機会を提供することで、従業員エンゲージメントを高める必要があります。
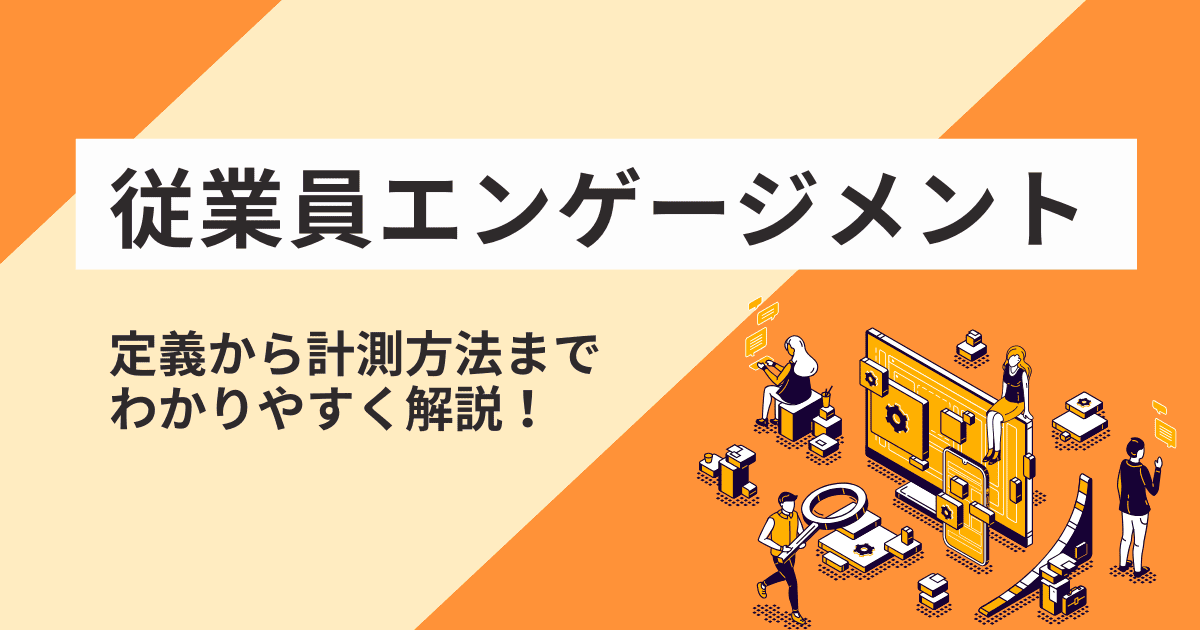
時間や場所に捉われない働き方
新型コロナウイルス感染症への対応のなかで、その重要性が一層明確になった要素です。
テレワークなどの柔軟な働き方を可能にする環境を平時から整備しておくことは、事業継続の観点からも不可欠です。
同時に、こうした働き方に対応したマネジメントスキルの育成も重要な課題となります。
伊藤レポートを実務で活用する3つの方法
レポートの概要を理解した上で、次はその内容を自社の組織開発に活かす方法が重要です。具体的な活用法を3つのステップで紹介します。
経営層への説明・合意形成の根拠資料として活用する
人的資本経営の推進には、経営層の深い理解とコミットメントが不可欠です。伊藤レポートは経済産業省が公表したものであり、人的資本経営の重要性や方向性について、客観的かつ信頼性の高い根拠として提示できます。
レポート内で示されている経営陣や取締役会の役割を引用し、自社の取り組みが国の方針に沿ったものであると示すことで、円滑な合意形成を促せます。
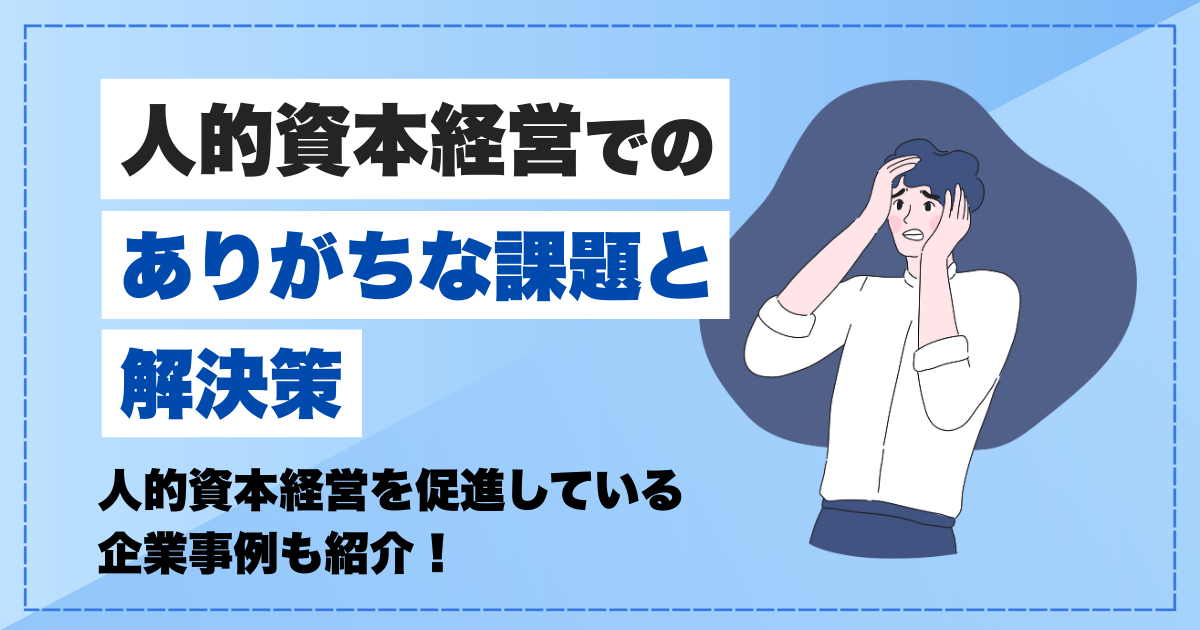
自社の現状把握と課題特定のためのフレームワークとして活用する
「3つの視点・5つの共通要素」は、自社の人的資本経営の現状を評価し、課題を特定するためのフレームワークとして活用できます。各項目について「できていること」「できていないこと」を洗い出し、目指すべき姿との「As is – To be ギャップ」を整理することで、取り組むべき課題が明確になります。
これにより、感覚的ではなく構造的に自社の強みと弱みを把握することが可能です。
人事施策の優先順位付けの判断基準として活用する
人的資本経営においては、研修制度の拡充、評価制度の見直し、ダイバーシティの推進など、取り組むべき施策は多岐にわたります。限られたリソースのなかで全ての施策を同時に進めることは困難です。
そこで、伊藤レポートで示された方向性、特に「経営戦略との連動」を判断基準にすることができます。自社の経営戦略に最も貢献する施策は何か、という観点から優先順位を決定することで、効果的かつ戦略的な投資が可能になります。
人的資本経営における従業員エンゲージメントの重要性
伊藤レポートでは、「従業員エンゲージメント」が重要な共通要素の一つとして位置づけられています。
伊藤レポートにおける従業員エンゲージメントの位置づけ
レポートでは、従業員エンゲージメントを「企業が目指す姿や方向性を、従業員が理解・共感し、その達成に向けて自発的に貢献しようという意識を持っていること」と定義しています。
そして、このエンゲージメントスコアと企業の営業利益率や労働生産性の間には相関関係があることもデータで示されており、企業価値向上のための重要な指標とされています。
従業員エンゲージメントが他の施策の基盤となる理由
従業員エンゲージメントは、単独の施策ではなく、他のあらゆる人事施策の効果を最大化する土台となります。
例えば、エンゲージメントが高い従業員は、会社の成長と自身の成長を重ね合わせ、リスキルや学び直しに対して意欲的です。
また、エンゲージメントレベルが高い社員に対して、より挑戦的な役割(ストレッチアサインメント)を任せることで、さらなる成長と貢献を引き出せます。
従業員のエンゲージメントが低い状態では、優れた研修制度を導入しても、従業員が受け身の姿勢となり、投資効果が限定的になる可能性があります。
このように、従業員エンゲージメントを高めることは、多様な人材が自律的に能力を発揮し、組織全体の活力を生み出すための基盤となるのです。
従業員エンゲージメントの可視化なら「ourly」
「従業員エンゲージメント」は、人的資本経営の土台となる重要な要素です。従業員が自社の理念に共感し、主体的に仕事に取り組む状態なくして、企業の持続的な成長はありえません。
しかし、エンゲージメントという目に見えないものを、どのように測定し、改善に繋げていけば良いのでしょうか。
ourlyは、組織のエンゲージメント状態を可視化し、改善をサポートするツールです。web社内報の閲覧データや組織診断サーベイを通じて、従業員のエンゲージメントを多角的に分析します。
これにより組織の課題を特定し、効果的な施策の立案を支援します。人的資本経営の第一歩として、まずは自社のエンゲージメント状態を把握することから始めてはいかがでしょうか。
まとめ
本記事では、人的資本経営の羅針盤となる「伊藤レポート」シリーズの概要と、その中核をなす「3つの視点・5つの共通要素」について解説しました。
- 伊藤レポートは、人材を「資本」と捉え、経営戦略と連動した人材戦略の重要性を説く、国が示した人的資本経営のガイドラインです。
- 3つの視点は、「経営戦略との連動」「As is-To beギャップの定量把握」「企業文化への定着」であり、人材戦略を構築する上での大局的な考え方を示します。
- 5つの共通要素は、「動的な人材ポートフォリオ」「ダイバーシティ&インクルージョン」「リスキル・学び直し」「従業員エンゲージメント」「時間や場所に捉われない働き方」であり、具体的な施策を検討する上で重要な切り口となります。
2023年3月期決算から有価証券報告書での人的資本情報の開示が義務化され、人的資本経営への取り組みは、もはや一部の先進企業だけのものではありません 。開示内容を検討する上でも、本レポートのフレームワークは公的な指針となります。
まずはこの記事で解説したフレームワークを活用して自社の現状を整理し、次回の経営会議で課題共有のアジェンダを設定するなど、具体的な第一歩を踏出してみてはいかがでしょうか。