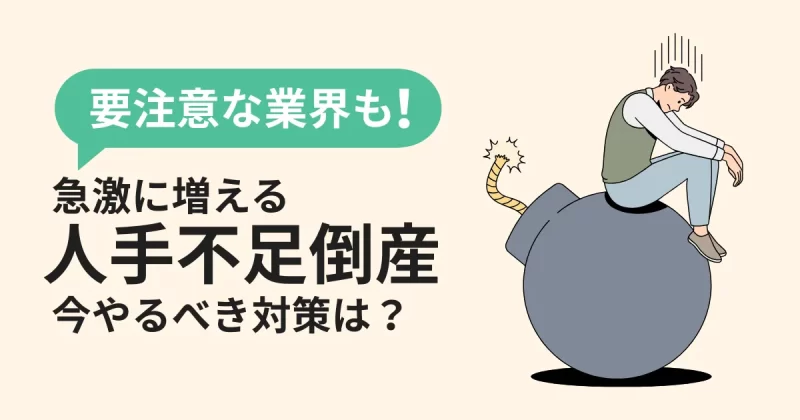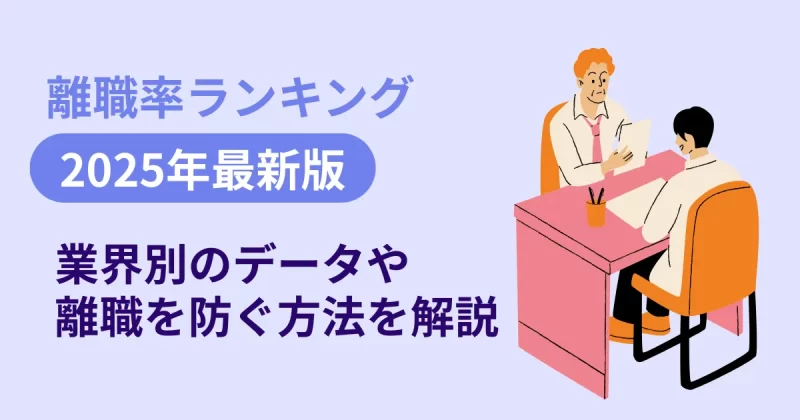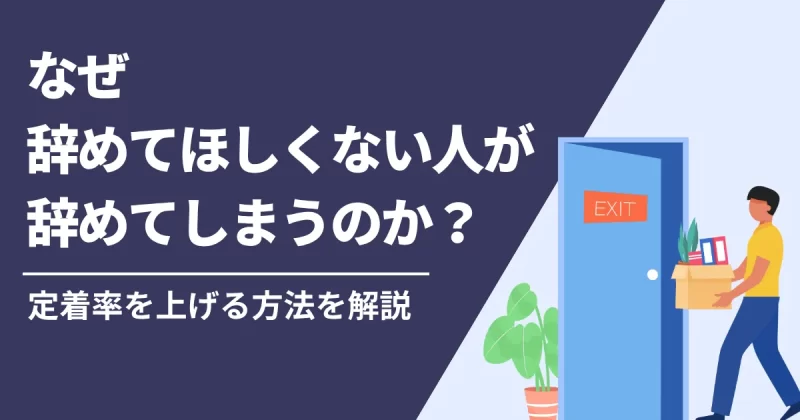多くの小売業の経営者や店舗責任者が、深刻な人手不足という課題に直面しています。求人を出しても応募が来ない、採用してもすぐに辞めてしまう、その結果として既存従業員の負担が増え、サービスの質が低下する、という悪循環に陥っていませんか。
この問題は、単に人が集まらないというだけでなく、企業の競争力や存続そのものを脅かす重大なリスクです。
本記事では、小売業で人手不足がなぜ深刻化するのか、その根本的な原因を5つの側面から分析し、明日からでも取り組める8つの具体的な解決策を成功事例とともに詳しく解説します。
小売業で人手不足が深刻化する原因
小売業の人手不足は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生しています。業界特有の構造的な問題から、社会全体の変化まで、その根本原因を理解することが解決への第一歩です。
ここでは、特に影響の大きい4つの原因を掘り下げて解説します。
長時間労働と不規則なシフト
小売業は、土日祝日や夜間も営業する店舗が多く、従業員は不規則なシフト勤務を求められます。カレンダー通りに休むことが難しく、プライベートとの両立に悩む人は少なくありません。
また、慢性的な人手不足がさらなる残業の常態化や休日出勤の増加を招き、一人ひとりの従業員に過度な負担を強いています。このような労働環境は、心身の健康を損なう原因となり、離職へとつながります。
身体的・精神的な負担の大きさ
小売業の業務は、長時間の立ち仕事、重い商品の品出し、そして多様な顧客への対応など、身体的にも精神的にも負担が大きいのが実態です。特に、クレーム対応は従業員にとって大きなストレスとなります。
これらの負担に見合うだけの待遇や休息が確保されなければ、従業員のモチベーションは低下し、働き続けることが困難になります。
地方への勤務に消極的
転勤先として、地方が好まれにくいという実態もあります。地方で頑張ろうと思っても、周囲に相談できる人がいないのでそのまま離職というしか手段が思い浮かばないこともあるようです。
地方店舗では、新しい人材の確保が難しく、離職数が入社数よりも多くなってしまうことが考えられます。
キャリアパスが描きにくい
非正規雇用の割合が高いことも、小売業の人手不足の一因です。
パートやアルバイトとして働く従業員にとって、将来のキャリアプランを描きにくいという問題があります。正社員への登用制度が整っていなかったり、スキルアップのための研修機会が乏しかったりすると、従業員は成長を実感できず、より良いキャリアを求めて他業種へ転職してしまう可能性があります。
また社員であったとしても、店長以降のキャリアが見えにくかったり、本社でどのようなキャリアがあるのかわからないといった課題も散見されます。
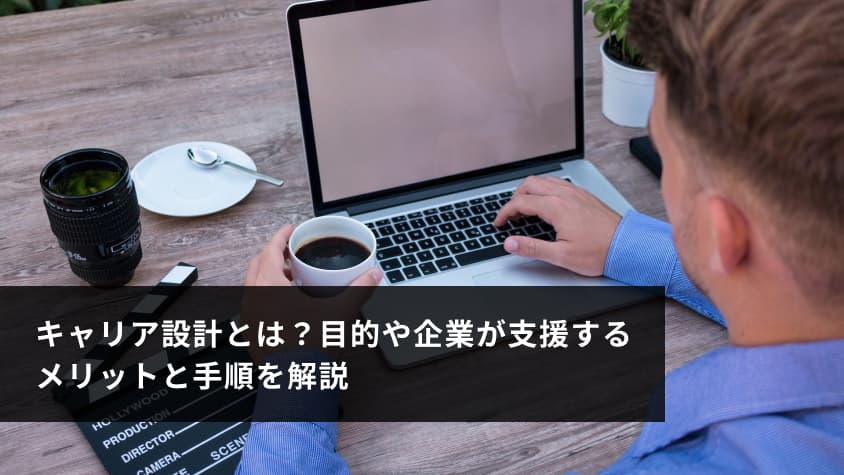
少子高齢化による労働人口の減少
日本全体の課題である少子高齢化は、小売業にも深刻な影響を及ぼしています。15歳から64歳までの生産年齢人口は年々減少しており、労働力の確保はますます困難になっているのが現状です。特に、これまで労働力の中心であった若年層の確保が難しくなり、採用競争は激化の一途をたどっています。
この構造的な問題を乗り越えるためには、従来の採用戦略を根本から見直すことが必要です。
人手不足が小売業にもたらすリスク
人手不足は、単に「忙しい」という問題にとどまらず、経営の根幹を揺るがす深刻なリスクを内包しています。スタッフが足りない状況が続くと、現場のオペレーションに支障をきたし、最終的には企業の収益性や持続可能性にまで悪影響を及ぼす可能性があるのです。
ここでは、人手不足が引き起こす3つの主要なリスクについて解説します。
事業機会の損失と売上減少
人手不足は、売上を伸ばす機会を逃す原因になります。
例えば、繁忙期に十分なスタッフを配置できなければ、増加する顧客に対応しきれず、販売機会を失ってしまいます。また、新店舗の出店や営業時間の延長といった事業拡大戦略も、実行に必要な人材を確保できなければ計画倒れに終わります。
人手不足は、企業の成長を阻害し、売上減少という直接的なダメージにつながるのです。
顧客サービスの質の低下
店舗運営に必要な人員が不足すると、レジの待ち時間が長くなる、商品の補充が遅れる、清掃が行き届かないといった問題が発生します。また、スタッフ一人ひとりが多忙になることで、顧客への丁寧な対応が難しくなり、結果として顧客サービスの質が著しく低下します。これは顧客満足度の低下に直結し、客離れを引き起こす大きな原因です。
既存従業員の負担増と離職率の悪化
人手が足りない分の業務は、すべて既存の従業員にしわ寄せされます。一人当たりの業務量が増加し、長時間労働が常態化することで、心身ともに疲弊してしまいます。
このような状況は、従業員のモチベーションを著しく低下させ、エンゲージメントの悪化を招くでしょう。結果として、優秀な人材が次々と離職し、さらなる人手不足に陥るという負のスパイラルに突入してしまいます。
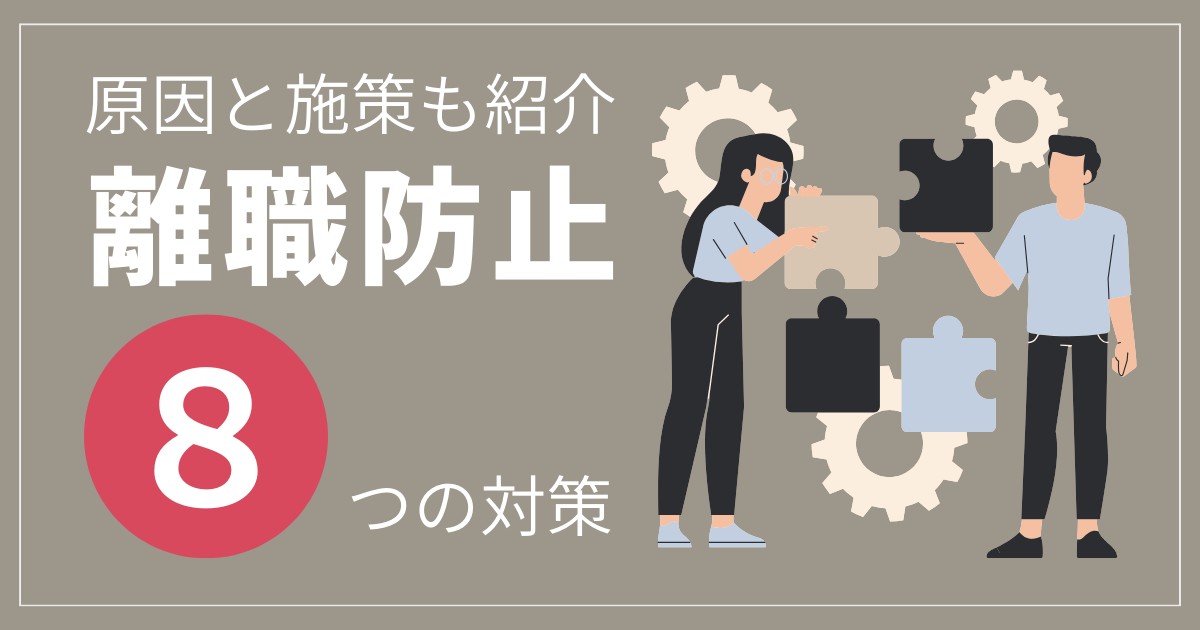
小売業の人手不足を解消する7つの対策
人手不足という厳しい課題を乗り越えるためには、多角的なアプローチが必要です。
賃金や労働時間といった待遇面の改善はもちろん、従業員の働きがいを高める取り組みや、テクノロジーを活用した業務効率化など、抜本的な改革が求められます。
ここでは、人手不足の解消に向けて有効な7つの対策を具体的に紹介します。
労働条件や福利厚生を見直す
小売業で人材を確保するためには、他業種や競合他社に見劣りしない魅力的な労働条件を提示するのは一つの手です。
賃金の引き上げや、従業員が安心して長く働けるような福利厚生の充実などが挙げられます。自社の現状を分析し、従業員が何を求めているのかを把握した上で、改善策を検討することが大切です。
キャリアパスを示す
店長から先のキャリアの進め方や本社でどのようなポジションがあるのかなど、社内でキャリア設計について共有をおこなうことで、社員がキャリアパスを描きやすくなります。
社内でキャリアパスが描ければ、企業側もそのキャリアパスに合わせて支援が可能になり、社員側も支援のもとキャリアを進めていこうという姿勢が強くなっていきます。
具体的には、社内報やイントラネットなどでキャリアについての情報を発信したり、社内イベントなどでキャリアについて会話する時間を取るという取り組みがあります。
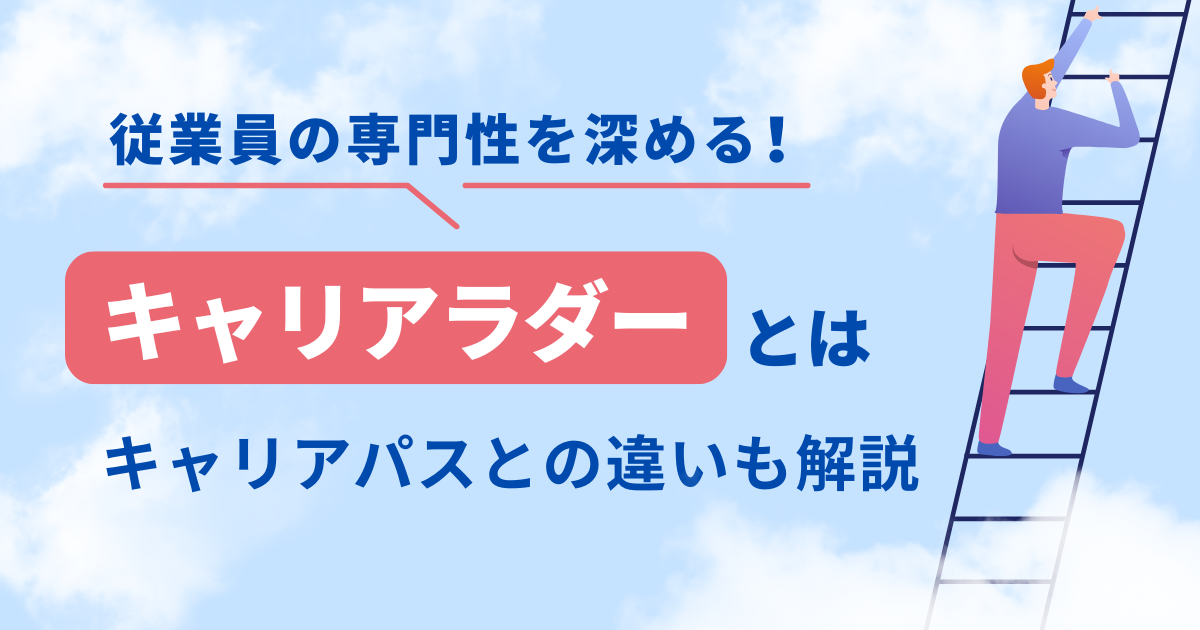
多様な人材の採用を推進する
労働人口が減少する中で、従来の採用ターゲットに固執していては、人材の確保は困難です。
シニア層や主婦(主夫)、外国人留学生など、これまで十分に活用できていなかった層にも目を向け、積極的に採用することが求められます。それぞれのライフスタイルや価値観に合わせた、柔軟な働き方を提案することが重要です。
例えば、短時間勤務や特定の曜日のみの勤務など、多様なシフトパターンを用意することで、応募者の裾野を広げることができます。
従業員のエンゲージメントを高める
従業員の定着率を高めるためには、働きがいのある職場環境を作ることが不可欠です。従業員エンゲージメント、すなわち仕事への熱意や貢献意欲を高める取り組みが重要です。
具体的には、社内イベントや社内報などによるコミュニケーションの活性化、従業員の意見を経営に反映させる仕組みづくり、個人の功績を正当に評価し称賛する文化の醸成などが挙げられます。
従業員が「この会社で働き続けたい」と思えるような環境整備が、離職率の低下につながります。
こちらの資料では、従業員エンゲージメントを向上させる社内コミュニケーション施策の設計方法を解説しております。ぜひご活用ください。
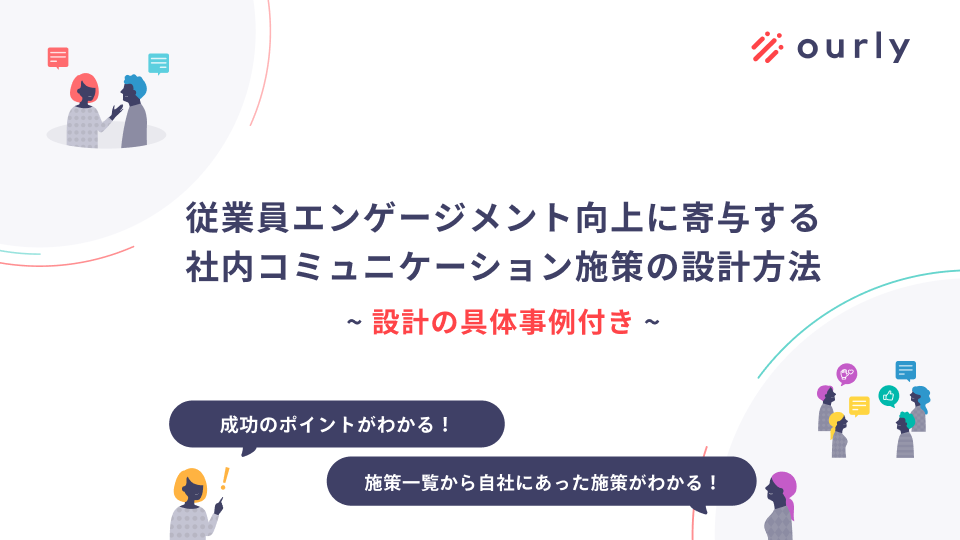
DXを推進し業務を効率化する
テクノロジーの活用は、人手不足解消の強力な切り札となります。AIやRPA(Robotic Process Automation)といったデジタルツールを導入することで、これまで人が行っていた定型業務を自動化し、従業員をより付加価値の高い業務に集中させることができます。
例えば、自動発注システムやセルフレジ、キャッシュレス決済端末の導入は、業務負担を大幅に軽減することが可能です。DXの推進は、省人化と生産性向上の両方を実現する重要な戦略です。
採用方法を多様化する
求人サイトに広告を出すだけの待ちの採用では、競争の激化する中で人材を確保することは困難です。リファラル採用(社員紹介)やSNSを活用した採用広報、自社採用サイトの強化など、より能動的な採用活動を展開する必要があります。
特に、現場で働く従業員の紹介によるリファラル採用は、企業文化にマッチした人材を効率的に採用できる可能性が高く、定着率の向上も期待できます。

リスキリングで多能工を育成する
一人の従業員が複数の業務をこなせる「多能工」を育成することも、人手不足への有効な対策です。特定のスタッフが休んだ際に、他のスタッフがその業務をカバーできる体制を築くことで、店舗運営の安定性が増します。
従業員に新しいスキルを習得してもらう「リスキリング」の機会を提供し、レジ業務や品出し、接客など、様々な業務に対応できる人材を育てることで、少ない人数でも効率的に店舗を運営することが可能になります。
人手不足解消に成功した小売業の事例
人手不足という大きな課題に対し、創意工夫によって活路を見出している企業も少なくありません。他社の成功事例から学ぶことで、自社に合った解決策のヒントを得ることができます。ここでは、独自の取り組みによって人手不足の解消やエンゲージメントの向上を実現した2社の事例を紹介します。
セブン-イレブン
セブン‐イレブン・ジャパンは人手不足対策として最先端技術を積極的に活用しています。同社では2022年より空中ディスプレイ技術を活用した非接触セルフレジの実証実験を開始し、現在全国17店舗まで拡大しています。また、2023年に導入したAI発注システムでは、天候や販売実績データを基に需要予測を行い、発注業務にかかる時間を約40%削減することに成功しました。これらの取り組みにより、従業員はレジ接客時間の大幅短縮と発注作業の効率化を実現しています。
【参考】https://sustainability.sej.co.jp/action/000144/
アントワークス

飲食業を中心に全国各地で店舗を展開する株式会社アントワークスは、web社内報「ourly」を活用した情報発信を開始。代表や経営陣からの未来像の共有や、店舗で活躍する社員を取り上げることで、刺激やキャリアパスのヒントを届けました。
その結果、現場に伝わりづらかった経営陣の3年後・5年後のビジョンや実際のキャリアアップ事例が共有され、社員の定着につながり、離職者数は25%減少。社員数も純増基調へと転じました。
ファミリーマート
株式会社ファミリーマートは2019年度に人手不足対策として250億円の設備投資を実施しました。人材派遣会社と連携した店舗スタッフ派遣サポートや24時間奨励金の増額を行い、加盟店の人材確保を支援しています。また、FC店長・スタッフ向けに健康診断支援サービスの無償化や店長ヘルプ制度を充実させ、働きやすい環境づくりに取り組んできました。これらの施策により、店舗運営の効率化と従業員の定着率向上を図っています。
【参考】https://www.family.co.jp/company/news_releases/2019/20190425_01.html
マキチエ

補聴器メーカーとして全国に38拠点の直営店を展開し、開発から製造、販売までを担うマキチエ株式会社は、2024年にweb社内報「ourly」を導入。社内報やプロフィール機能を活用し、社員同士の理解を深めることで、コミュニケーションの質の向上を図りました。
その結果、組織全体に一体感が生まれ、新規参画者のオンボーディングにも良い効果を発揮。さらに、離職率は10.5%から5.4%へと大幅に改善しました。
離職を低減し、人手不足を改善するweb社内報「ourly」
ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
まとめ
小売業の人手不足は、低賃金や長時間労働といった業界特有の課題と、少子高齢化という社会構造の変化が相まって深刻化しています。この問題を放置すれば、サービスの質の低下や売上減少を招き、企業の存続を脅かす事態になりかねません。
本記事で紹介したように、労働条件の見直しや多様な人材の活用、DXの推進など、取り組むべき対策は多岐にわたります。自社の課題を正確に把握し、可能なところから一歩ずつ改善を進めることが、この困難な状況を乗り越えるための鍵となるでしょう。