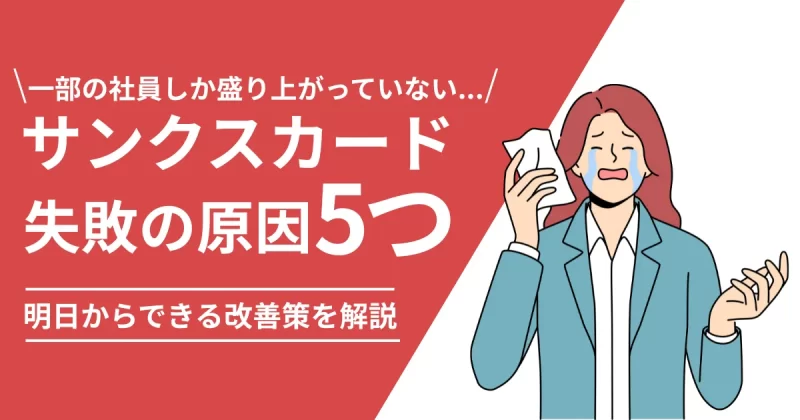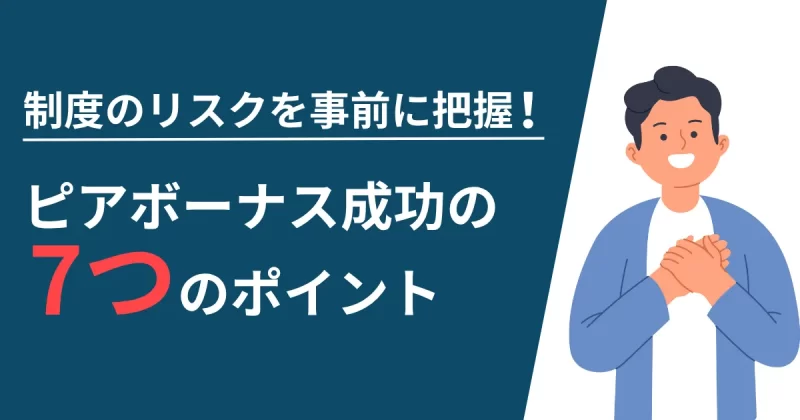サンクスカードは、従業員同士が感謝の気持ちを伝え合う素晴らしい制度ですが、運用方法を誤ると形骸化し、逆効果になることも少なくありません。
「導入したはいいものの、誰も使っていない」「一部の人しか盛り上がっておらず、かえって不公平感を生んでいる」といった悩みを抱える担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、サンクスカードが失敗する典型的な原因を分析し、明日から実践できる具体的な改善策と成功事例を交えながら、制度を成功に導くためのポイントを詳しく解説します。
サンクスカードとは?改めて目的と効果を理解する
サンクスカード制度の改善に取り組む前に、まずはその基本的な目的と期待される効果について再確認しましょう。
目的が明確になることで、自社が本当に解決したい課題が見え、適切な運用方法を選択する助けとなります。
感謝を伝え合う文化を醸成する制度
サンクスカードは、日常業務の中で生まれた「ありがとう」の気持ちを、カードやデジタルツールを通じて気軽に伝え合うための制度です。
日頃は照れくさくて言えないような感謝も、カードという形にすることで伝えやすくなります。
この小さな感謝の積み重ねが、組織全体にポジティブな雰囲気をもたらし、互いを尊重し、助け合う文化を育む土壌となります。
従業員エンゲージメント向上への貢献
エンゲージメントとは、従業員が仕事に対して感じる「熱意」「没頭」「活力」を指します。
サンクスカードを通じて自分の仕事ぶりや貢献が認められ、感謝される経験は、従業員の承認欲求を満たし、仕事へのモチベーションを高めます。
自分が組織の一員として価値を提供できていると実感することは、エンゲージメント向上に直結する重要な要素です。
| 期待される効果 | 具体的な内容 |
| モチベーション向上 | 感謝されることで仕事への意欲が高まる |
| 離職率の低下 | 組織への帰属意識や愛着が深まる |
| 生産性の向上 | ポジティブな職務態度が業務効率を上げる |
コミュニケーション活性化とチームワーク強化
サンクスカードは、部署や役職を超えたコミュニケーションのきっかけを生み出します。普段あまり接点のない従業員同士でも、カードを贈ることで新たな関係性が構築されることがあります。
互いの仕事内容や貢献への理解が深まることで、部署間の連携がスムーズになり、チームワークの強化にもつながるのです。
サンクスカードが失敗する5つの典型的な原因
多くの企業がサンクスカードの導入でつまずく背景には、共通した原因が存在します。ここでは、代表的な5つの失敗原因を掘り下げ、それぞれの問題点を明らかにします。
自社の状況と照らし合わせながら、課題を特定してみてください。
| 失敗原因 | 具体的な状況 |
| ノルマ化 | 提出が義務になり、感謝の気持ちが失われる |
| 利用者の偏り | 一部の従業員のみが利用し、全社的な活動にならない |
| 運用の手間 | 紙媒体での運用は配布・回収・集計が負担になる |
| 効果の不可視化 | ポジティブな影響が分からず、モチベーションが続かない |
| 感謝の強要 | 制度自体に「気持ち悪い」と抵抗を感じる人がいる |
原因1:ノルマ化による「やらされ感」の蔓延
失敗事例として最も多く聞かれるのが、サンクスカードの提出をノルマ化してしまうことです。
「毎月5枚提出」といったルールを設けることで、感謝の気持ちを伝えるという本来の目的が失われ、従業員は義務感でカードを書くようになります。
その結果、内容が形式的になったり、感謝の気持ちがこもらない作業になったりして、「やらされ感」が職場に蔓延してしまいます。
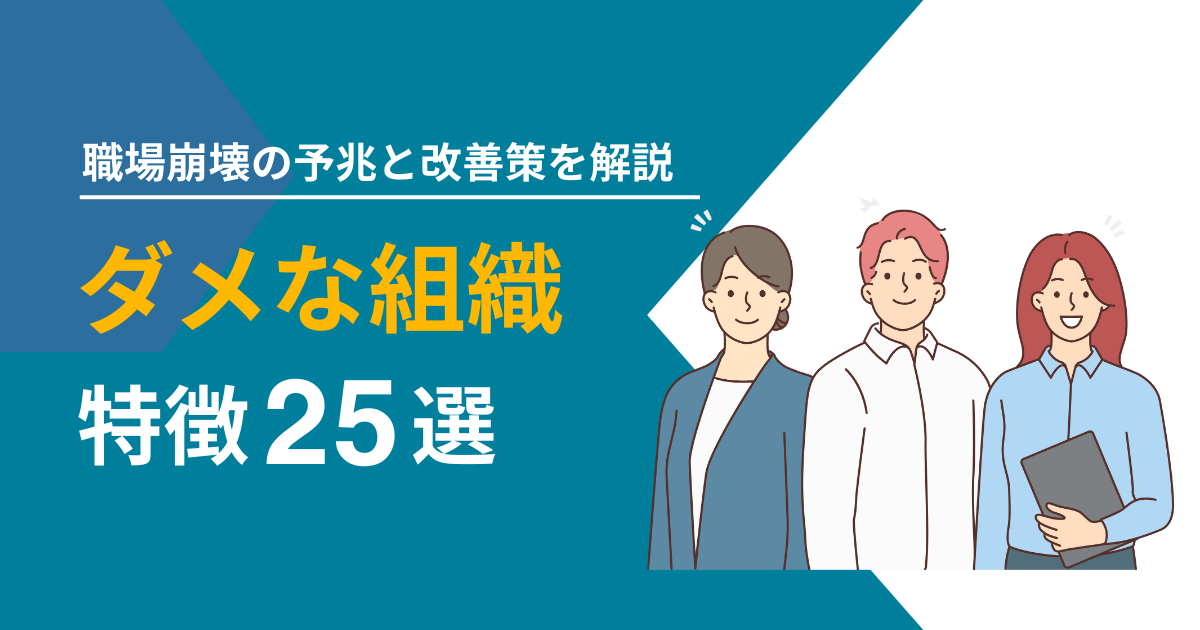
原因2:一部の従業員しか使わない状況の発生
導入当初の目的が従業員に十分に伝わっていないと、「何のためにやるのかわからない」と感じる人が増え、結果的に一部の意欲的な従業員しか利用しない状況に陥ります。
特に、管理職やリーダー層が積極的に参加しない場合、その部署のメンバーも利用しづらくなります。
一部の人だけが利用するツールという認識が広まると、制度そのものが形骸化してしまいます。
原因3:運用の手間がかかりすぎてしまう
紙のカードで運用する場合、カードの配布、回収、集計、掲示といった作業に多くの手間と時間がかかります。
担当者の負担が大きくなるだけでなく、日々の業務に追われる従業員にとっても、手書きでカードを作成することが後回しになりがちです。
このような運用の煩雑さが、制度が定着しない大きな原因となります。
原因4:感謝の効果が見えにくく形骸化する
サンクスカードを送っても、相手にどのように受け止められたのか、組織にどんな良い影響があったのかが可視化されないと、従業員は「本当に意味があるのだろうか」と疑問を感じ始めます。
感謝の行動が評価や称賛に結びつかない場合も同様で、モチベーションが低下し、次第に誰も利用しなくなるという悪循環に陥ります。
原因5:感謝の強要が「気持ち悪い」と感じさせてしまう
感謝や称賛をオープンに伝え合う文化に慣れていない職場では、サンクスカード制度自体が「わざとらしい」「気持ち悪い」と受け取られてしまうことがあります。
特に、成果を上げた特定の従業員に称賛が集中すると、嫉妬や不公平感を生み出し、かえって職場の人間関係を悪化させるリスクもあります。
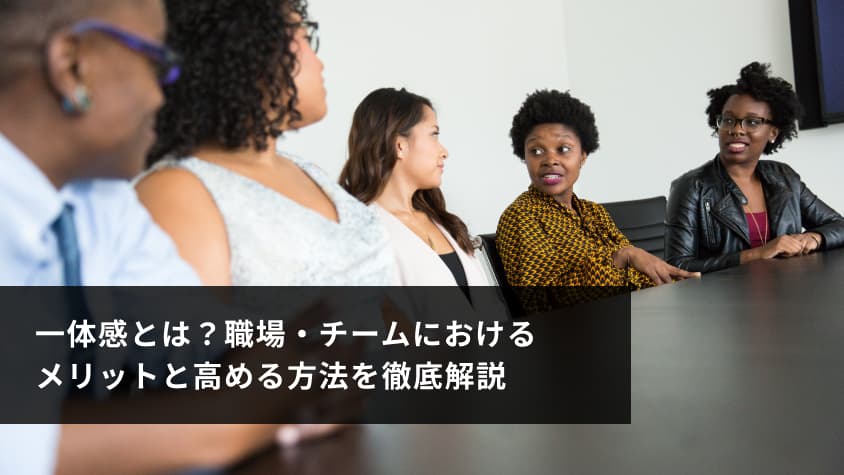
失敗事例から学ぶ!サンクスカードを成功に導く改善策
サンクスカードの運用で壁にぶつかったとしても、諦める必要はありません。
失敗の原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで、制度を再活性化させることが可能です。
ここでは、具体的な改善策を5つ紹介します。
| 改善策 | 実施内容 |
| コミュニケーションの土台を整える | 定期的な1on1や社内イベントを通じて社員同士の仲を深める |
| 目的の共有 | 経営層から導入目的を繰り返し発信する |
| ルールの見直し | ノルマを廃止し、気軽に参加できる仕組みを作る |
| ITツールの活用 | アプリなどを導入し、運用の手間と時間を削減する |
| 上層部の参加 | 経営層や管理職が率先してサンクスカードを利用する |
| 成果の可視化 | カードのやり取りを共有し、優れた行動を表彰する |
感謝や賞賛が生まれるコミュニケーションの土台を整える
ピアボーナスの効果を最大化するためには、社員同士が安心して感謝を伝え合える文化づくりが欠かせません。
感謝や称賛は制度によって生まれるものではなく、日常的な信頼関係や心理的安全性の中で育まれるものです。
社内でオープンな対話やポジティブなフィードバックが交わされる環境を整えることで、ピアボーナスが義務的な制度ではなく、自然なコミュニケーションの延長として定着します。
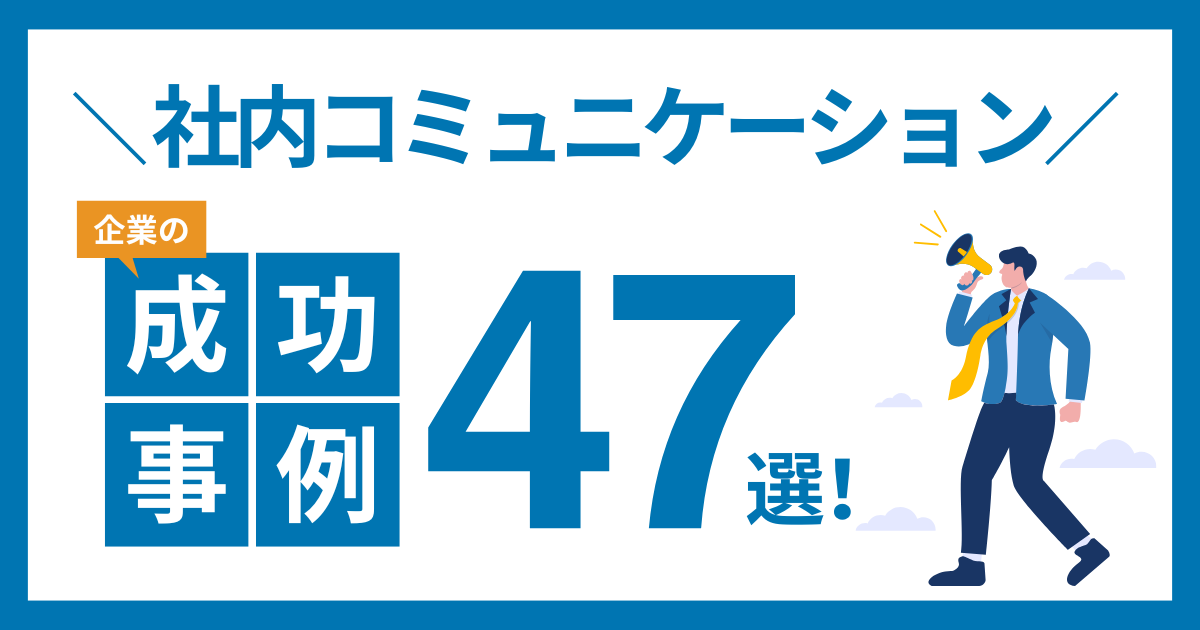
導入目的を明確にし、全社で共有する
まず最も重要なのは、「なぜサンクスカードを導入するのか」という目的を明確にし、経営層から全従業員に向けて繰り返し伝えることです。
「部署間の連携を強化するため」「互いの貢献を認め合う文化を作るため」など、具体的な目的を共有することで、従業員は制度の意義を理解し、主体的に参加しやすくなります。
従業員の負担にならないルールを設計する
厳しいノルマは撤廃し、従業員が自発的に参加できるような、負担の少ないルールに見直しましょう。
例えば、手書きにこだわらず、短いメッセージでも良いとする、テンプレートを用意するなど、利用のハードルを下げることが有効です。
従業員が「これならできそう」と感じられるような気軽さが、継続の鍵となります。
ITツールを活用して手間を削減する
紙での運用に限界を感じている場合は、サンクスカードアプリやツールの導入を検討しましょう。
スマートフォンやPCから手軽にメッセージを送れるようになれば、場所や時間を選ばずに利用できます。また、データの自動集計機能を使えば、管理者の負担を大幅に軽減できます。
経営層や管理職が積極的に参加する姿勢を見せる
サンクスカードを文化として定着させるためには、経営層や管理職が率先して利用する姿を見せることが不可欠です。
上司から部下へ感謝の気持ちを伝えることで、部下は「自分の頑張りを見てくれている」と感じ、モチベーションが高まります。トップの積極的な姿勢が、全社的な取り組みへとつながっていきます。
成果を可視化し、ポジティブな行動を称賛する
誰がどんな感謝のメッセージを受け取ったのかを、社内報や掲示板などで共有し、「見える化」しましょう。
例えば、月に一度、最も多くのカードを受け取った従業員やチームを表彰する制度を設けるのも効果的です。
感謝の行動が認められる文化を作ることで、従業員の参加意欲はさらに高まります。
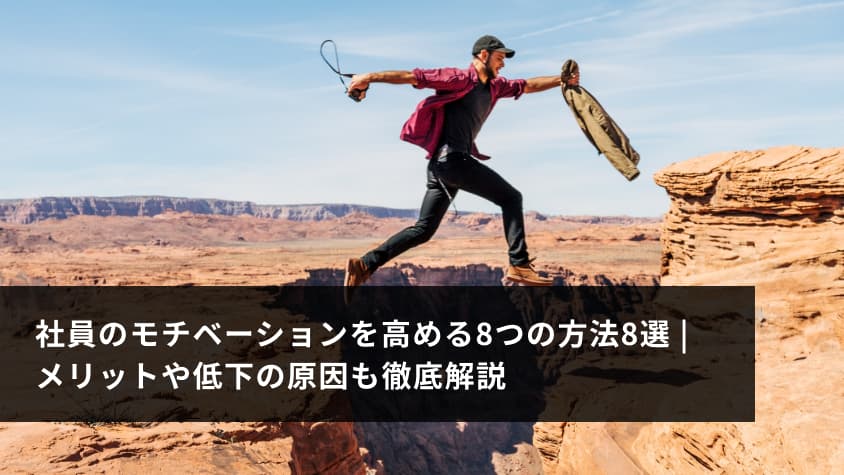
成功事例に学ぶ!サンクスカード定着のポイント
他社はどのようにしてサンクスカードの運用を成功させているのでしょうか。ここでは、具体的な企業の成功事例から、制度を組織に定着させるためのヒントを探ります。
JALグループ:感謝の気持ちを直接伝える「Thanks card」で褒める文化を醸成
JALグループでは、各職場で発生した身近な事象に対し、仲間の行動に対して感謝の気持ちを直接伝える方法として「Thanks card」を導入しています。
これは、JALフィロソフィに則り優れた行動をした社員を表彰する制度と合わせて運用され、個を高め組織の活性化を図りながら褒める企業文化の浸透を図る取り組みです。
さらに、JALマイレージバンクでは、既存のサンクスカード文化をより気軽に活用できるよう電子版のトライアルを実施し、デジタル化による利便性向上にも取り組んでいます。
社員からは「みんなもよかったら活用してみてね」という声が聞かれ、自然な形で制度が浸透していることが分かります。
参考:褒める企業文化の醸成 | CSR情報 | JAL企業サイト
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション:従業員同士の感謝を可視化する仕組み作り
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社では、社内コミュニケーションの活性化につなげるべく、2022年秋頃から「サンクスカード」の取り組みをスタートさせました。
この制度では、新しいことに積極的に取り組む姿勢や日常の協力に対して感謝の気持ちを表現し、従業員同士で日常の感謝の気持ちをカードとチップで贈り合うしくみを構築しています。
また、健康経営の一環として「サンクスカード&チップ制度」を導入し、従業員の心身の健康と職場環境の向上を同時に実現する工夫を行っています。
技術者が多い組織特性を活かし、フラットな組織文化の中で感謝を表現しやすい環境を整備している点が特徴的です。
参考:健康経営 | サステナビリティ | パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社
サンクスカード運用に最適なツールを選ぶポイント
サンクスカード制度の成否は、運用ツールの使いやすさに大きく左右されます。特にデジタルツールを導入する際は、以下の3つのポイントを基準に、自社に合ったものを選びましょう。
| ツール選定のポイント | なぜ重要か? |
| マルチデバイス対応 | 多様な働き方の従業員が誰でも手軽に利用できるため |
| データ集計・分析機能 | 制度の効果を客観的に測定し、改善に活かすため |
| 既存ツールとの連携 | 従業員が日常的に使うツールと連携させ、利用のハードルを下げるため |
PC・スマホ両対応の手軽さ
オフィス勤務者だけでなく、リモートワーカーや外出の多い営業担当者など、多様な働き方の従業員がストレスなく利用できることが重要です。
PCはもちろん、スマートフォンやタブレットからも直感的に操作できるアプリであれば、いつでもどこでも気軽に感謝を伝えられます。
データ集計・分析機能の有無
どの部署で、どのような感謝のやり取りが活発に行われているかをデータで把握できる機能は、制度の効果測定や改善に役立ちます。
送受信数のランキングを表示したり、ポジティブなキーワードを分析したりする機能があれば、組織の状態を可視化し、次の施策につなげやすくなります。
既存ツールとの連携のしやすさ
普段から利用しているビジネスチャットツール(SlackやMicrosoftTeamsなど)と連携できるかも重要なポイントです。
サンクスカードを受け取った際にチャットツールに通知が届けば、見逃しを防ぎ、よりリアルタイムなコミュニケーションを促進できます。
まとめ
サンクスカードの導入と運用が失敗に終わる原因は、ノルマ化や運用の手間、効果の不可視化など、複数の要因が複雑に絡み合っています。
しかし、これらの課題は、導入目的の明確化と共有、従業員の負担を軽減する工夫、そしてITツールの活用によって乗り越えることが可能です。
本記事で紹介した改善策や成功事例を参考に、自社のサンクスカード制度を見直し、従業員一人ひとりが前向きに働ける、感謝と称賛にあふれた職場環境を築いていきましょう。