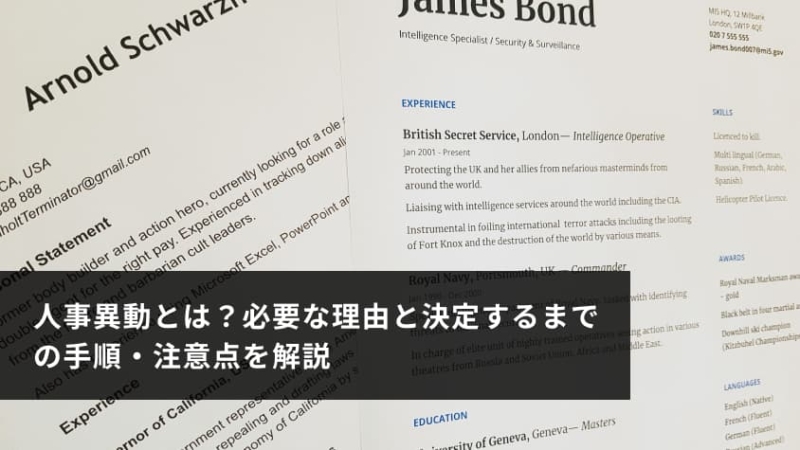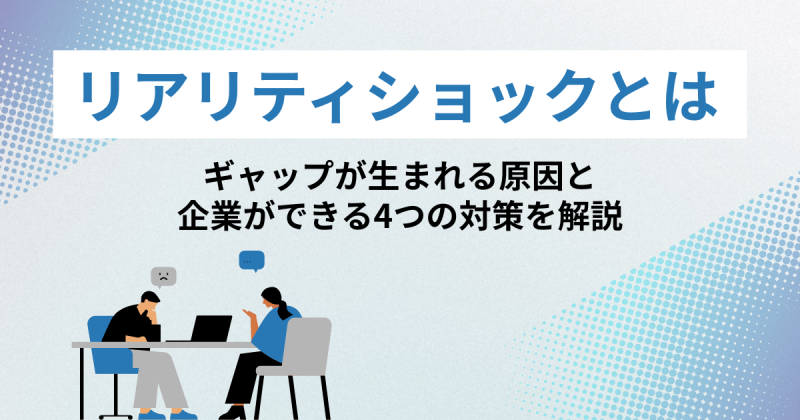離職率を改善するには、
- 働きやすい環境づくり
- 良好な人間関係の確保
- 将来に向けた展望の提示
といった多面的な対策が欠かせません。
労働人口の減少や労働力の流動化を背景に、企業にとって人材定着は喫緊の課題となっています。業務効率や企業イメージを向上させるため、離職率を改善したい企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、離職率の改善に必要な5つの取り組みを解説し、実際に成果を上げた10社の事例を紹介します。
離職率の改善が必要な理由

離職率の改善が必要な理由は、収益悪化に歯止めをかけるためです。
人が続けて離職した場合、当然新しい人材を確保するため採用に着手する必要があります。転職サイトや求人誌への出稿料・エージェントへの成功報酬がかかるほか、人事部門のリソースも割かれます。
これを続けていくうちに採用コストが収益を圧迫するなど、思わぬ財務状態になる可能性があるので注意しておきましょう。
その他、既存社員のモチベーションが下がる、業界内で悪評が立つなどのリスクもあります。どの企業でも、離職率の改善は必須の課題なのです。
離職率が高くなる3つの原因

離職率が高い企業では、下記3つの要因のうちいずれかが発生している可能性が高いです。
ときには複数の問題が生じていることもあるので、自社に当てはまる部分がないか確認していきましょう。
労働条件に対して不満があるから
同業他社と比較して賃金が圧倒的に低く、残業や休日出勤が常態化していると、労働条件に不満を抱きやすくなります。最低限の収入に達していない場合、生計を維持するために転職せざるを得ません。
ワークライフバランスが著しく損なわれている場合、「10年後も同じ働き方はできない」と考えられる可能性が高まります。社員の期待に応えつつ、労働条件を向上させることが必要です。
社内外で人間関係の問題を抱えているから
パワハラやセクハラを受けていたり、深刻な職場内いじめに遭っていたりする場合も、離職につながります。同様に取引先や顧客との関係性が上手くいかず、ストレスが蓄積されているときも同じことが起こり得ます。
人間関係の問題は表面化しづらく、直接社員にヒアリングしても遠慮や恥ずかしさが勝ることが多いです。
本来であれば人間関係について相談できる相手であるはずの上司が原因であることも多く、直接訴えられないまま離職を選んでしまう人も少なくありません。
自分や会社の将来に不安があるから
将来に不安を感じたり、会社が不安定な状態にあると、早めに離職する人が増えることがあります。例えば、「バックオフィスの社員が続々と辞めている」「売上が伸び悩み、リストラの噂が現実味を帯びてきた」といった不安材料がある場合、離職が急増する可能性があるため、これには注意が必要です。
同時に、企業理念や行動指針に共感できない場合も、「これまでどおり働いていくべきか」といった疑問が生まれ、納得できる他企業に転職する可能性が高まります。
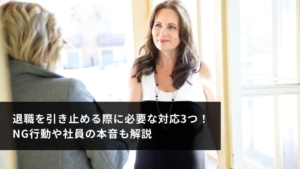
離職しかねない社員の特徴
離職しかねない社員の特徴として、下記が挙げられます。
- 覇気・元気がない
- 目を合わせて会話しない
- 研修や勉強会に積極参加しない
- 提出物や事務処理の期限が遅れる
- 遅刻・早退・欠勤がある
- 社内コミュニケーションに消極的
- 慢性的な体調不良を訴えている
モチベーションやエンゲージメントが低く退職を検討している場合、上記のような特徴が現れやすくなります。
また、「以前と比べて元気がなくなった」「急に早退が増えた」などこれまでの様子と変わる部分があれば要注意です。単純にその日のコンディションが悪いだけの可能性もあるので、普段の様子との違いにフォーカスを当ててチェックしてみるのがおすすめです。
離職防止に対する5つのアイデア

離職率の改善には、5つの観点から取り組み内容を精査する必要があります。
既に万全の対策ができている項目についてはそのまま継続で問題ありませんが、課題となっている項目があれば要注意です。自社の弱みを可視化し、改善施策を練っていきましょう。
明確な基準によって賃金や評価を決める
賃金や評価を決定する際には、明確な基準を設定することが有益です。透明性の高い人事評価制度があれば、「誰がどのように評価されるか」「自分の評価がどうなっているか」が理解しやすくなります。
これにより、個人ごとの目標がクリアになり、努力が直接評価に結びつく仕組みができます。その結果、納得感が高まり、労働条件に対する不満が軽減されます。評価に振り回されず、着実な戦略を取りやすくなるのもメリットです。
働きやすい制度や環境を整備する
働きやすい制度・環境を整備し、勤続しやすい会社にすることも大切です。
例えば、リモートワークやサテライトオフィス勤務制度を導入し、通勤時間短縮による負担軽減を目指してもよいでしょう。フレックスタイム制度などフレキシブルに働ける制度を採用するのもひとつの手段です。
また、時短勤務の期限を伸ばして働くパパ・ママ社員が離職せず勤続できるようにするなど、多彩な取り組みができます。「辞めたくないけれど辞めざるを得ない」という離職を予防する効果もあるので、積極的に取り入れましょう。
社内のコミュニケーションを活性化する
社内のコミュニケーションを活性化し、風通しをよくする方法です。
普段から円滑なコミュニケーションが築けていると、上司・部下間の報告・連絡・相談がスムーズになります。日常業務がやりやすくなるメリットが得られるほか、細かなことでも相談しやすくなり、お互いの信頼感が増していきます。
また、横のコミュニケーションを意識するのもおすすめです。縦割り組織が解消されて部門間連携しやすくなるので、組織全体に一体感が生まれます。
当たり前にコミュニケーションできる組織になれば、エンゲージメントが上がります。「この会社にこそ貢献したい」という気持ちを大切にするためにも、ぜひ着手してみましょう。

教育や研修体制を充実させる
教育・研修の体制を整え、成長を実感できるようにすることが重要です。毎日同じルーティンの作業だけが続くと、仕事の意義ややりがいを見失いやすくなります。これが続くと、仕事がつまらなく感じられ、やりたいことが見つかった時に離職するリスクが高まります。
一方で、充実した教育・研修プログラムがあれば、仕事を通じて自己実現を達成できます。将来の成長イメージを持てれば、その会社で働く価値を見つけやすくなります。役職や入社年数に応じた独自の研修を提供し、従業員の参加を奨励することが大切です。
離職防止に有効なツールを活用する
離職防止に有効なツールを活用し、これまで見えなかった課題を可視化することも効果的です。
例えばパルスサーベイを週1回もしくは月1回程度実施すれば、個人ごとのモチベーショングラフが見えてきます。繁忙期など忙しい時期だけ極端にモチベーションが下がる社員と、慢性的にモチベーションが下がる社員とでは、取るべき対策も異なります。
その他、採用のミスマッチを防ぐリファレンスチェックなどのツールもおすすめです。
何が自社の課題になっているか明らかにするためにも、有効活用していきましょう。
【資料】エンゲージメント向上に繋げる社内コミュニケーション施策の設計方法
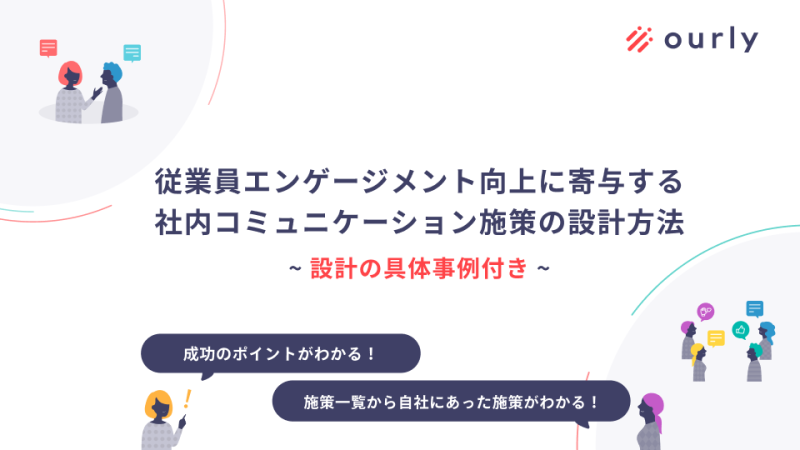
社内コミュニケーションの活性化は、組織にあった施策を適切に行い続けることで実現します。しかし、組織にあった施策を選ぶことは難しく、成果も見えづらいため、活性化に成功する企業は多くはありません。
そこで弊メディアでは、「自社にあった社内コミュニケーション施策の選び方」、「施策設計方法」「活用事例」をまとめた資料を作成しました。
組織の離職率やエンゲージメントスコア、理念・文化の浸透にお悩みの方は是非ご覧ください。
資料はこちら:https://ourly.jp/document/download_internalcommunication/
離職率を改善した9社の成功事例

ここでは、離職率改善に成功した企業事例を紹介します。課題に対してどのような施策をしたか知り、自社のケースにも活用できそうか検討してみましょう。
サイボウズ┃一人ひとりの働き方を尊重
サイボウズはもともと離職率が28%と高い状態にありましたが、一人ひとりの働き方を尊重する組織に変えたことで大幅に改善しています。2020年度には3%程度にまで離職率が下がるなど、高い効果が現れました。
具体的には、情報共有クラウドやバーチャルオフィスを使っていつでもどこでもリアルタイムな社内コミュニケーションができるよう環境を整備したこと、テレワークや育児休暇を拡充したことなどが挙げられます。
多様な働き方ができるからこそ離職せず続けられる環境が整い、多くの社員が継続的に業務にコミットするようになった事例です。
鳥貴族┃組織の壁にとらわれない連携
URL:会社概要 | 企業情報 | 株式会社 鳥貴族ホールディングス
鳥貴族では、組織の壁にとらわれない連携により離職率を改善させています。
本社では全員がひとつのフロアで仕事をするスタイルを構築し、社長室・役員室などの垣根をなくしました。誰がどんな仕事をしているか分かりやすく、部門間連携も取りやすくなる効果が現れています。
また、鳥貴族では「正しい人間」「利他の精神」「プラス発想」「自己責任」の4つを共通の価値観として定めており、トップダウン型の一方的な指示をしないことからも働きやすさが上がっています。
カネテツ┃新人を手厚くサポート
URL:リクルート – カネテツデリカフーズ株式会社コーポレートサイト
カネテツでは、新人を手厚くサポートするためマンツーマン制度を導入しました。現場の先輩が担当教員になって新人一人ひとりにつき、徹底的に教育する方針に変えています。
結果として、個人単位での振り返りや目標設定がしやすくなり、業務上のもやもやを解消しやすくなりました。もともと新入社員の離職率が50%を超える危機的状況でしたが、今では数%に低下しています。
きめ細かな指導と協力的な姿勢が構築できれば、新人は離れないと分かる事例です。
レオパレス┃研修や評価制度の見直し
レオパレスでは、社員アンケートにより教育を受けたいと考えるニーズが高いと分かって以降、研修・評価制度を積極的に見直しています。
労働時間による評価からパフォーマンス重視の評価に変えたことで、社員のワークライフバランスが格段に向上しました。「限られた時間でも確実にパフォーマンスを上げれば評価してもらえる」ということがモチベーションになり、仕事へのやる気や熱意も上がっています。
離職率だけでなく、月6時間の残業削減や研修への自発的な参加も見られるようになりました。制度の見直しにより、複合的なメリットが生じた事例と分かります。
ビースタイル┃コミュニケーションの改善
URL:CULTURE|ビースタイル グループ 採用情報ページ
ビースタイルは、社内コミュニケーションの改善により離職率を下げることに成功しています。
例えばマネージャーとマンツーマンで面談する「1on1ミーティング」を取り入れたり、社員同士が感謝の気持ちを送り合う「バリューズアワード」を開催したりしました。これまで欠けていた社内コミュニケーションを意識するきっかけになり、組織への帰属意識が高まったことで離職率を低下させています。
また、選択式時短勤務制度や午前・午後6時から9時には在宅を推奨する「69ファミリーシフト」などを導入し、働きやすさも同時に見直しました。
竹屋旅館┃社員教育の負担を軽減
URL:採用情報 | 株式会社 竹屋旅館
竹屋旅館は、指導マニュアルの整備により社員教育の負担を軽減しています。
指導担当者のスキルごとに教育のクオリティがバラけてしまうこともなくなり、納得感の高い教育が得られるようになったことで離職率も改善しています。マニュアルは新人社員だけでなくパート・アルバイトにも適用され、誰でも同じ内容を学べるようになりました。
接客スキルの底上げも叶い、一人ひとりができるようになったことが増えたからこそ仕事へのやりがいも充実します。自己実現と負担軽減を同時に叶えた、効果的な施策と言えるでしょう。
ビッグ・エー┃研修時間やコストを改善
ビッグ・エーは、マニュアル作成ツールを導入したことで年間1万6,000時間の研修時間削減に成功しています。
これまで実業務に加えて受講すべき研修が多く、実態として残業・休日出勤が常態化してワークライフバランスを損ねていることが課題となっていました。研修時間を改善したことで働きやすさが上がっただけでなく、本業に集中できるようになったことで業務効率も上がっています。
研修に伴うコストも削減でき、収益の大幅な改善にも貢献しました。
ジオコード┃社員の声を反映した制度づくり
URL:ジオコード採用トップ
ジオコードは、社員の声を反映した制度改革をおこない、特に福利厚生を充実させています。
現在では軽食を1日1回配布したり、サッカーを観戦できるよう試合のスケジュールに合わせて臨時休暇を取ったりできるよう整備されています。他にも夏の期間に連休が取れるエンドレスサマー制度など、オリジナリティのある福利厚生が揃いました。
同業他社と比較して圧倒的な福利厚生があれば、人材の流出は防げます。従業員満足度も上がりやすく、会社にとっても社員にとってもメリットのある取り組みです。
ホットランド┃新入社員の離職率を改善
URL:株式会社ホットランド|会社概要
ホットランドは、人事部によるフォローや個別面談を充実させることで新入社員の離職率を改善しています。
悩みや不満を気軽に相談できる場を作ったことで、「上司に相談するまでもないか」と躊躇ってしまう声も積極的に吸い上げられるようになりました。退職が決定した社員にも個別で面談し、離職を決めた原因を教えてもらうなど情報収集に努めています。
また、新入社員同士でコミュニケーションできるイベントやグループワークを設けるなど、社内コミュニケーションの活性化も意識しました。これにより、新入社員の離職率は5分の1にまで下がっています。
離職率は取り組み次第で改善できる
離職率に悩んでいる場合は、ますます自社の課題を明確に把握しましょう。課題に適した対策を講じることで、離職率は確実に低減します。それに加えて、既存社員の満足度の向上など、複数のメリットが期待できます。
社内コミュニケーションの促進による離職予防を目指す場合、社内報の導入がおすすめです。これにより相互理解が進み、ミッション・ビジョン・バリュー、企業理念への共感が容易になり、帰属意識も向上します。
ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。