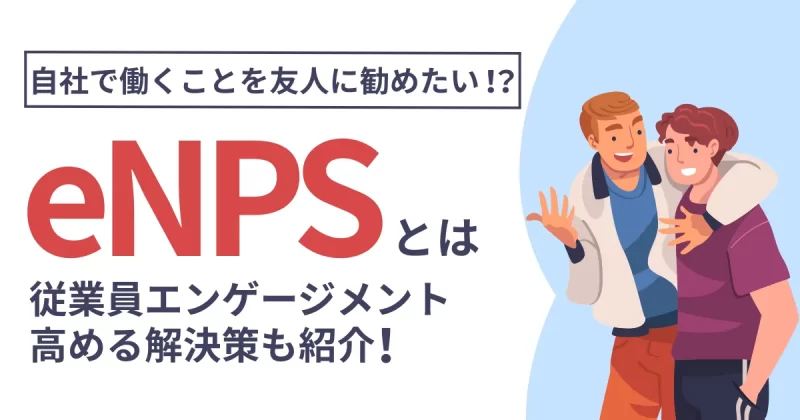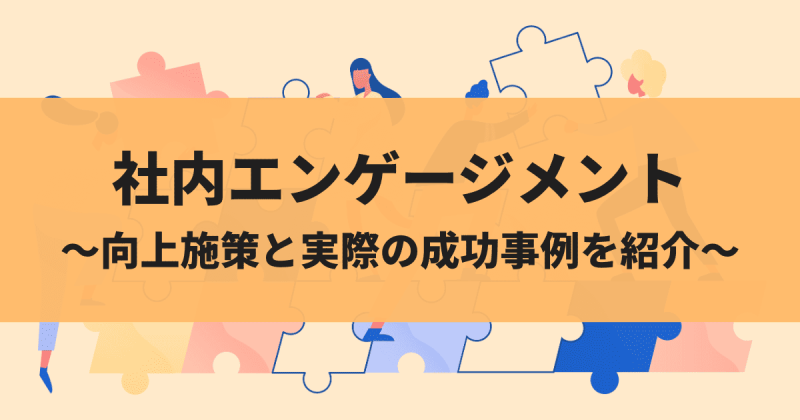福利厚生費とは、会社が従業員に対して給与以外の方法で与えるサービスや報酬です。たとえば健康保険や厚生年金などの一部費用のほか、通勤費や健康診断、社員旅行費用なども福利厚生費として認められます。福利厚生費は法人税の節税にも活かせるという点も大きなメリットです。しかしそのためにはいくつかの条件を満たす必要があるため、注意が必要です。
本記事では、福利厚生費と混同されやすい交際費や消耗品費との違い、福利厚生費として計上するための条件のほか、具体的な例を解説します。
福利厚生費とは

福利厚生費とは、その名の通り福利厚生にかける費用を指す言葉です。給与・賞与など労働への対価として毎月支給するものの他、通勤費・家族手当など属性に応じて支給するものがあれば福利厚生費にカウントします。
他にも、健康診断費用の補助や厚生年金保険料・健康保険料の労使折半分なども、福利厚生費に含まれるので注意しましょう。
下記では、福利厚生費と混同されやすい項目について解説します。
交際費との違い
交際費は、取引先・顧客など社外の人のためにかける費用を指す言葉です。同時に居合わせる自社従業員の飲食・宿泊費なども同時に出すため福利厚生費と間違えやすいですが、対象が社内か社外かで区別する必要があります。
また、交際費を非課税にするには範囲や限度額が定められています。従業員だけが参加する飲み会や社員旅行の補助は、福利厚生費に含まれることにも注意しておきましょう。
消耗品費との違い
福利厚生として消耗品を支給することがある企業では、かかったコストを福利厚生費にすべきか消耗品費にすべきか迷うことがあります。その際は、業務に必ず使うものかどうかをベースに考えるとよいでしょう。
例えば、パソコン・スマートフォン・タブレットや各種文房具、業務に必須の制服など、業務に必要不可欠なものは消耗品費として扱います。反対に、業務に必須ではないお菓子やお茶の買い置きなどは福利厚生費として計上します。買ったものではなく、用途に合わせて使い分けていきましょう。
福利厚生費の種類は2つ
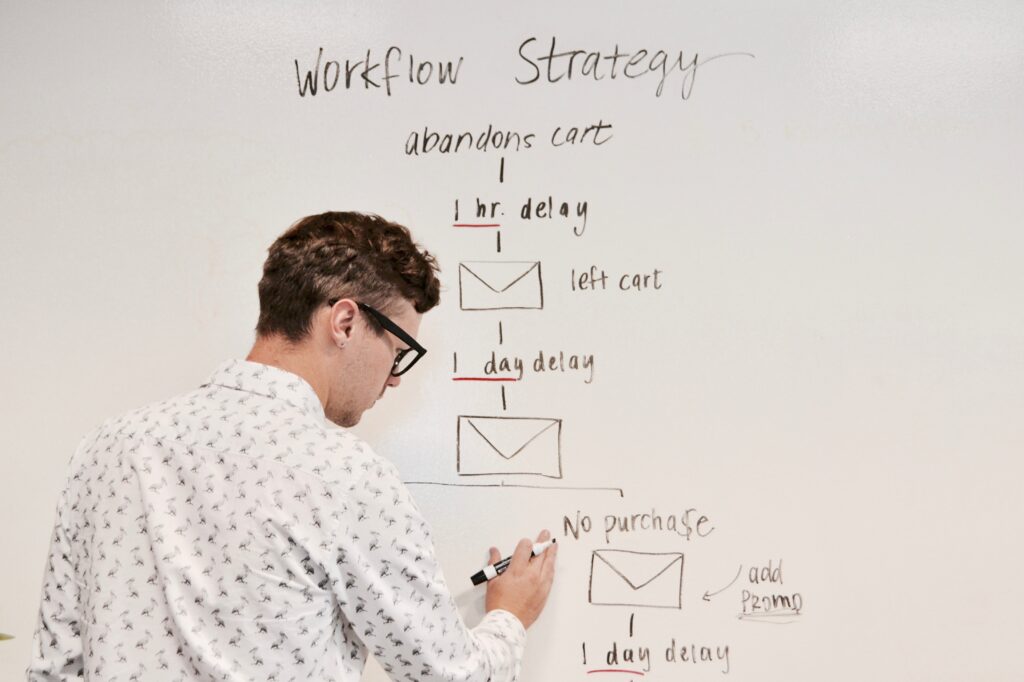
福利厚生費に含まれるものとして、「法定福利費」と「法定外福利費」とが挙げられます。下記で具体的な例を出しながら、紹介します。
1. 法定福利費
法定福利費とは、法定福利厚生にかかる費用のことです。
- 雇用保険料の労使折半分
- 健康保険料の労使折半分
- 介護保険料の労使折半
- 厚生年金保険料の労使折半分
- 労災保険料
- 子ども・子育て拠出金
つまり、法律で定められている必須の福利厚生にかかる費用は、法定福利費とみなしてよいでしょう。一定以上の規模・従業員数がある企業に義務づけられる福利厚生が多く、「最低限かかる福利厚生費」とも言われています。
2. 法定外福利費
法定外福利費とは、法律で整備することが義務づけられた法定福利厚生以外にかかる福利厚生費のことです。自社独自の福利厚生を導入している場合、かかるコストは全て法定外福利費として計上します。
- 住宅手当
- 通勤手当
- 扶養手当の支給
- 結婚祝い金
- フィットネスジムの利用代金補助
- 人間ドックの受診料補助
上記は全て法定外福利に含まれるので、チェックしておきましょう。
福利厚生費を計上するメリット

ここでは、福利厚生費を計上するメリットを解説します。同じコストがかかるのであれば何に計上しても同じと考えがちですが、大きなメリットがあるので必見です。
節税に繋がる
福利厚生費は経費計上できるため損金扱いとなり、収入から差し引かれて見かけの収益を減らすことできます。法人税は収益の大小に応じてかかるので、収益を減らすことができればその分税金も安くなり、高い節税効果が期待できるのです。
ただし、税務上の諸基準を満たしていない福利厚生費については、福利厚生費として計上できないケースがあるので注意しましょう。
優秀な人材が獲得できる
福利厚生費として計上する額を増やすため、法定外福利厚生を積極的に導入することにより、採用市場での注目度が集まります。福利厚生を重視して就職先・転職先を選びたい優秀な人が応募してきたり、スキルある人材を獲得しやすくなったりするでしょう。
また、自社に在籍している従業員のうち、福利厚生に魅力を感じてくれる人がいれば離職を予防する効果も発揮されます。優秀な人材を長く獲得し続けたいときにこそ、有効な手段です。
従業員満足度が向上する
福利厚生によって従業員に生じる節税効果もあるので、結果的に従業員満足度が上がるケースもあります。
例えば、福利厚生で獲得したポイントをギフトカードやホテル・飛行機の利用代に交換する場合、得した金額に対して税金や社会保険料が課せられることはありません。同じ金額であっても給料に上乗せする形で支給されてしまうと、税金や保険料が増えてしまうことがあるので注意しましょう。
なお、住宅手当や資格手当のように毎月の固定給として発生するものには、税金・社会保険料ともにかかります。支給の仕方次第では、従業員にとってもメリットになるので覚えておきましょう。

福利厚生費としての計上が認められる条件

福利厚生費として計上するには、下記の条件を満たす必要があります。
- 機会の平等性があること
- 金額に妥当性があること
- 現金支給ではないこと
機会の平等とは、自社の従業員が等しく利用できる状態であることを指します。特定の部署・地域・役職の人しか使えない福利厚生は、福利厚生費として計上できません。
また、法外に高額な福利厚生を提供したり、給与に上乗せせず現金で支給したりすることはNGです。忘年会や新年会の開催頻度が多すぎたり、豪遊に近い社員旅行をしていたりする場合は、課税対象となることがあるので注意しましょう。
福利厚生費の具体的な例
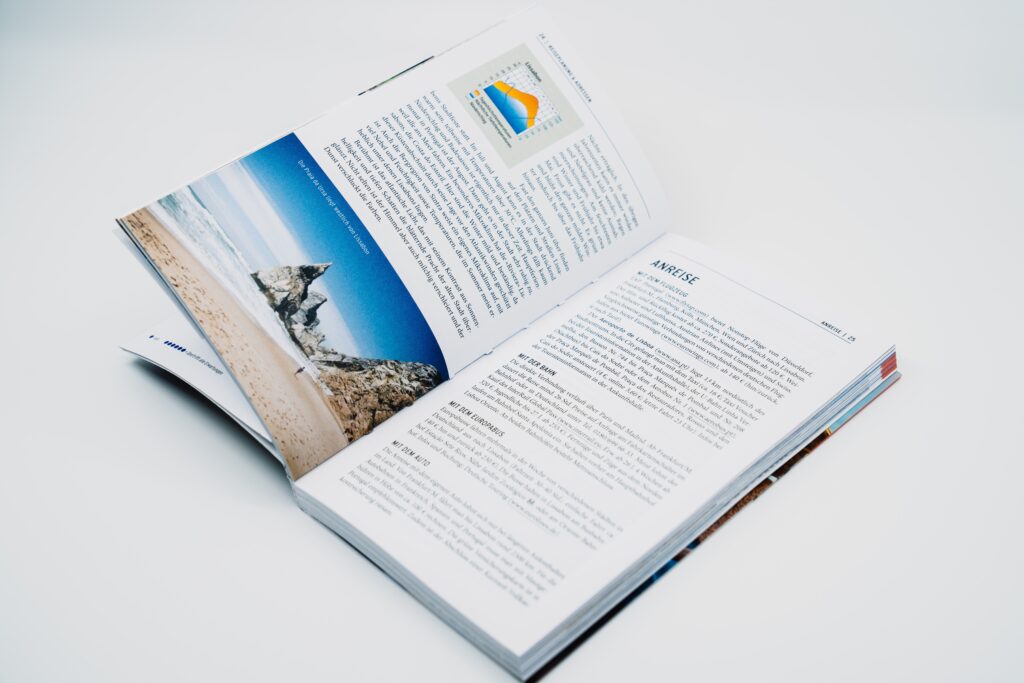
最後に、福利厚生費の具体的な例を紹介します。コストだけでなく、従業員のニーズに合った福利厚生にするためにも、事例をチェックしてみましょう。
通勤費
通勤費は、通勤にかかる電車・バスの運賃を支給する福利厚生です。車やバスの場合はガソリン代や駐車代(駐輪代)も支払うことがあります。
実費もしくは定期券代を支給することが多いですが、なかには上限額を定めている企業もあるのでチェックしておきましょう。なお、いくらを上限とするかは企業が自由に決められるので、膨大な負担額にならない程度に調整するのがおすすめです。
健康診断費
健康診断の費用も、福利厚生費として計上できます。法定健診として最低限必要な検査項目だけでなく、追加の検査・がん検診・人間ドックなども費用を補助する場合も、福利厚生費に該当します。
また、2015年より実施が義務化されたストレスチェックについても、健康診断と同じ福利厚生の扱いとなるのでチェックしておきましょう。ただし、超高級な人間ドックなどの場合、経費計上できない可能性があるので注意が必要です。
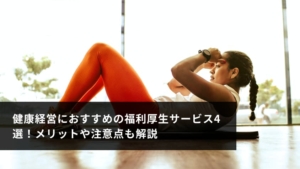
食事補助費
社食・お弁当・コーヒーなどのドリンク・無農薬野菜など、食事補助費も福利厚生費として計上できます。食べる場所は問わず、持ち帰りで調理するミールキットやファミリーレストランでの食事代補助なども含まれます。
ただし、会議参加者が口にするお弁当などは会議費に計上することもあるので注意しましょう。「食事代の企業負担額が従業員ひとり当たり3,500円以下であること」「従業員は食事代の50%以上を負担していること」が条件です。
社員旅行・研修旅行費
社員旅行や研修旅行の費用も、福利厚生に含みます。旅行先でレジャーをするのではなく、ほぼ全日程を研修に充てる場合でも、福利厚生とみなされるケースがあります。
なお、福利厚生費として計上する場合、「旅行期間が4泊5日以内であること」「全体の50%以上が旅行に参加すること」「会社負担額が高額すぎないこと」が条件となるので注意が必要です。
社内レクリエーション費
社内でのレクリエーション・イベント・運動会などを開催する場合、費用の一部が福利厚生費となることがあります。「全従業員が参加対象となっていること」「高額すぎないこと」「現金支給ではないこと」が条件となっているので確認しましょう。
つまり、レクリエーションの景品として現金を用意し、従業員に配布する場合は福利厚生費に追加できません。また、ギフトカードなど換金性の高いものや、車など高額なものを商品とした場合も認められないことがあります。
福利厚生の情報共有に ourly
ourlyは一体感のある組織づくりを支援するweb社内報サービスです。
社内報運用に関する伴走支援が充実しているため、取り組みをやりっぱなしにせず、学びや気づきを組織の資産として活かすことができます。
ourlyの特徴
- SNSのようなコメント機能で、振り返りや共感を引き出す
- web知識不要で、誰でも発信できる
- 閲覧率・読了率の浸透度が可視化できる豊富な分析機能
- 支援体制が充実しており、運用負担が最小限にできる
「チームビルディングゲームを一過性で終わらせたくない」そんなご担当者様におすすめの社内報ツールです。
福利厚生費を正しく理解し従業員が満足する組織作りを
福利厚生は従業員に対するサービスだと捉えがちですが、福利厚生費として経費計上できれば企業側へのメリットも現れます。特に法人税の節税効果が高いので、処理を間違えないようにしておきましょう。
また、福利厚生の内容を考えるときは従業員のニーズに合わせることも重要です。満足度の高い福利厚生および運用手法になるよう、工夫していきましょう。