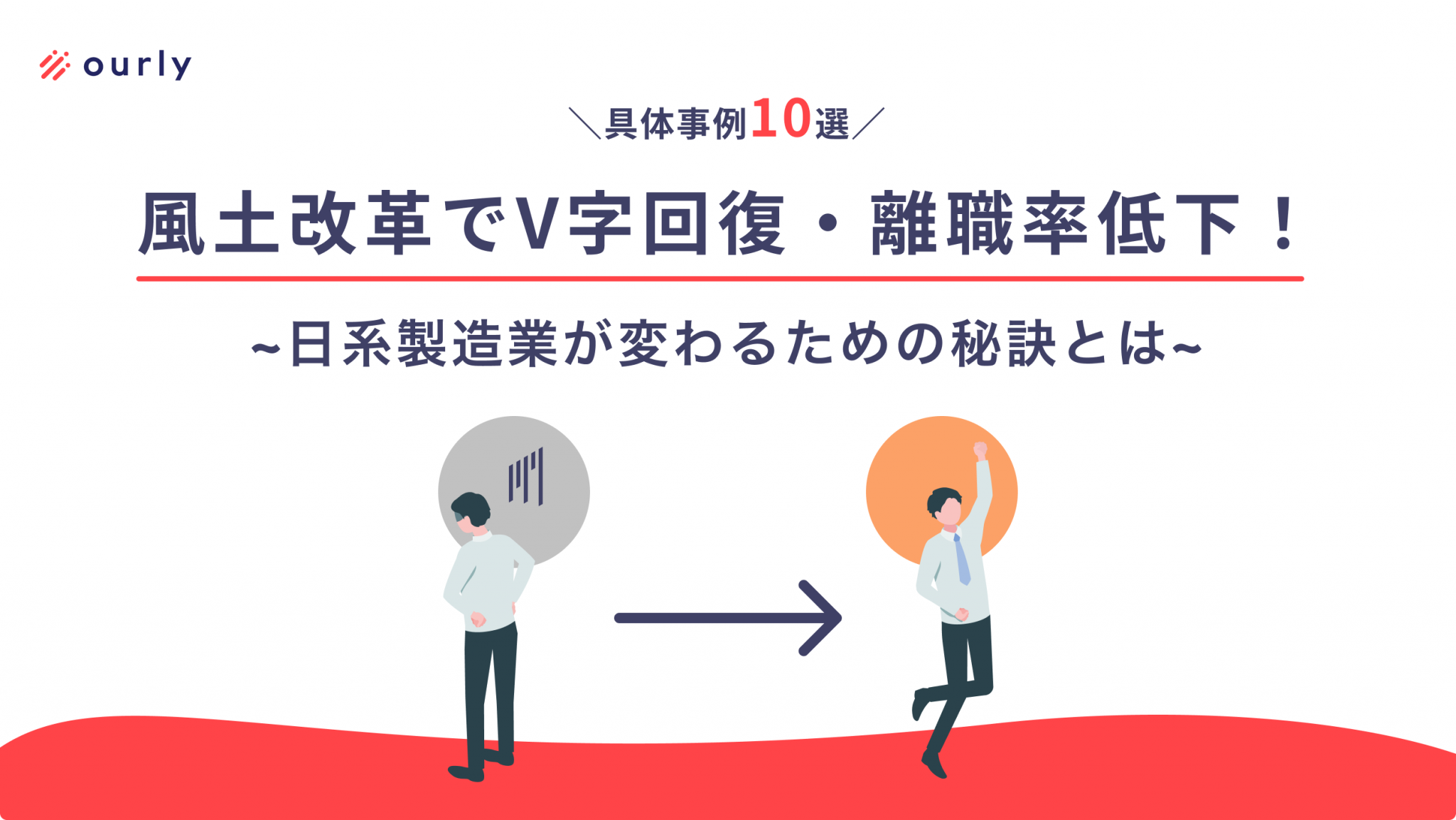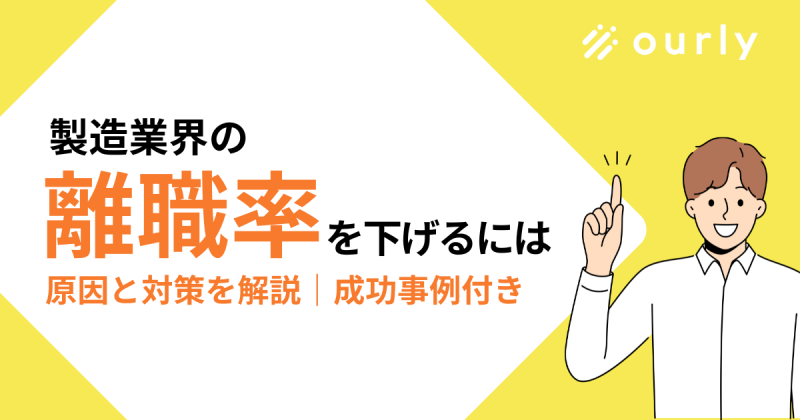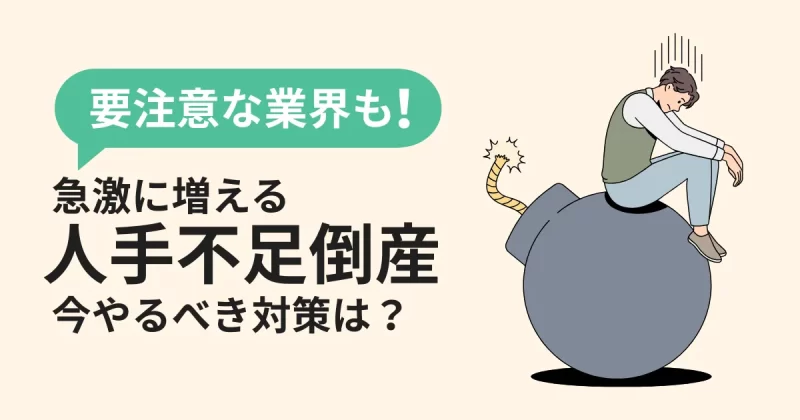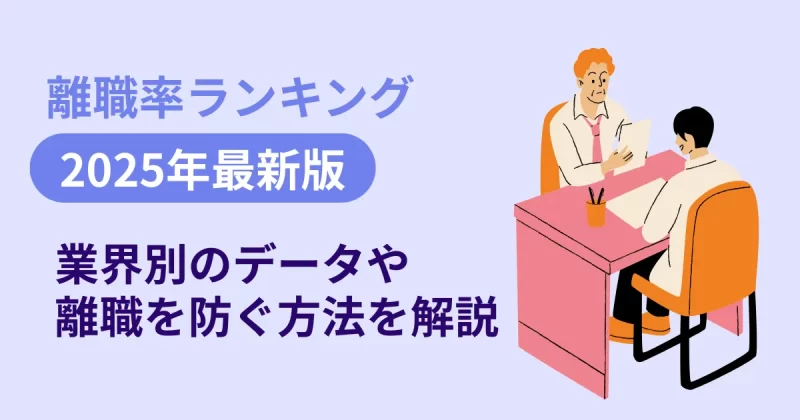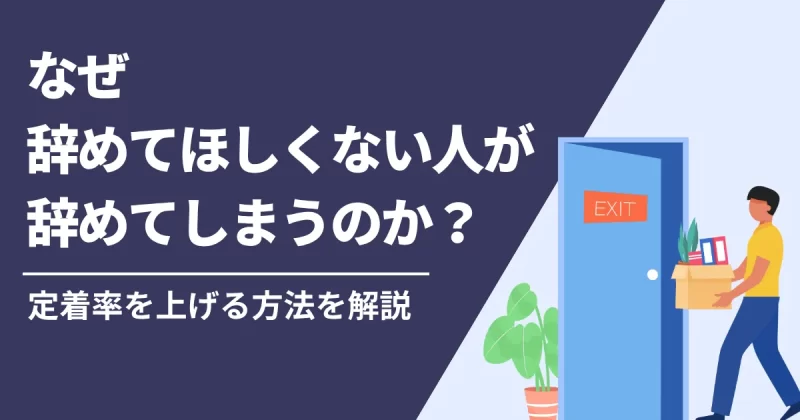製造業の離職率は全産業の中でも比較的低い水準にありますが、若手の定着や人手不足に悩む企業は少なくありません。現場の働きがいやコミュニケーションのあり方が、離職率に大きく影響しているケースも多いです。
本記事では、製造業の離職率の実態とともに、離職を引き起こす原因、そして実際に改善に成功した企業事例も紹介します。ぜひ最後まで読んで、自社に合う離職率改善のヒントを見つけてください。
製造業の離職率について
厚生労働省発表の「令和4年 雇用動向調査結果の概要」によると、製造業は入職者73.9万人に対し、離職者数78.9万人で、入職率は9.6%、離職率は10.2%でした。
一方、同年の全産業計は、入職者数779.8万人に対し、離職者数765.7万人で、入職率は15.2%、離職率は15.0%となります。
| 入職者数 | 離職者数 | 入職率 | 離職率 | |
| 製造業 | 73.9万人 | 78.9万人 | 9.6% | 10.2% |
| 産業計 | 779.8万人 | 765.7万人 | 15.2% | 15.0% |
製造業の離職率は、全産業平均と比較すると低い水準にあります。16業種中4番目に低く、相対的には安定した雇用環境といえます。
しかし、産業全体では「入職者数 > 離職者数」で労働力が増えているのに対し、製造業は「離職者数 > 入職者数」となっており、労働者が減少している点に注意が必要です。特に中小製造業では若年層の確保が困難な状況が続いており、人材定着の重要性は今後ますます高まると予想されます。
製造業で離職が生まれる理由
まず製造業で離職が生まれる理由について説明していきます。
自社に当てはまる部分はないか確認してみてください。
世代間ギャップやノウハウの属人化
製造業では、職人の高齢化によりノウハウが属人化し、言語化されないままの現場も少なくありません。こうした環境に違和感を抱いた中堅層が離職し、現場には20代と50代以上が中心に残るケースも少なくありません。
その結果、世代間の価値観や働き方の違いが顕在化し、若手にとって働きづらい職場環境となることがあります。
仕事のやりがい・成長機会の不足
製造業の現場では、ライン作業など同じ作業を繰り返す業務が多く見られます。品質や安全を守る上で重要な役割を担っていますが、スキルアップやキャリア形成を求める従業員にとっては、単調な作業が続くことでやりがいを見出しにくくなる傾向があります。
努力しても評価や昇進に結びつかないと感じる場合、長期的に働くモチベーションが低下し、離職を検討する大きな要因となります。
過酷な職場環境による肉体的負担
製造業は体力を必要とする作業が多く、重い部品や機材を扱う場面や長時間の立ち作業が日常的に発生します。
特に交替制で長時間働く職場では、疲労や体の痛みが慢性的に蓄積しやすく、体力的に続けることが難しいと感じる従業員も少なくありません。このような身体的な負担が、離職を考えるきっかけとなります。
長時間労働や不規則な勤務体制
製造業では、納期や生産計画に追われ、残業や休日出勤が多くなることがあります。また、夜勤や交替勤務制が導入されている職場では生活リズムが乱れ、睡眠不足や体調不良につながることも少なくありません。
こうした勤務体制はワークライフバランスを崩しやすく、家庭や健康を優先して離職を選ぶ従業員を増やす一因となります。
給与・待遇面の不満
給与水準が低かったり、昇給やボーナスの機会が限られていると、従業員の仕事に対する意欲は低下します。
さらに、正社員と非正規社員の間で待遇格差が大きい職場では、不公平感がモチベーション低下を引き起こします。福利厚生が十分でない場合や利用条件が制限されている場合も、働き続ける魅力が感じられず離職につながることがあります
人間関係やコミュニケーション不足
品質や安全管理の厳しさから、製造業の現場は黙々と作業を進める雰囲気になりやすく、従業員同士のコミュニケーションが希薄になりがちです。さらに、本社と全国各地の拠点が物理的に離れている場合は、日常的なやり取りが難しくなり、現場との温度差や帰属意識の低下にもつながります。
上司や同僚に相談しづらい環境が続けば、心理的安全性が低下し、孤立感を抱いたまま働くことになります。このような職場環境ではストレスが蓄積しやすく、離職の要因となります。
製造業で離職率を下げるために
離職対策では雇用条件や労働環境の改善が浮かびますが、どの企業も取り組み、差別化が難しく実行するハードルも高いです。だからこそ、人・組織、理念、事業への魅力で差別化をすることが大事です。

社員が一体感や仕事の意義を感じられる環境をつくることが、やりがい向上や定着率改善につながります。以下で製造業で離職率を下げる方法を紹介します。
採用段階で理念・事業・人を伝える
離職の大きな原因は、入社後に「思っていた職場と違う」というギャップです。給与や条件だけでなく、会社の理念や事業の意義、一緒に働く人の雰囲気を採用段階から明確に伝えることで、ミスマッチを防げます。
具体的には、採用サイトや説明会で社員インタビュー動画や現場の様子を写真で紹介する、社内プロジェクトの成果を記事化して公開するなどが効果的です。
現場の声を経営とつなぐ双方向コミュニケーション
理念や目的が現場に浸透していないと、モチベーションは下がりがちです。一方通行の情報発信ではなく、現場からの声を吸い上げ、それを全社で共有する仕組みを持つことが大切です。
例えば、定期的な社内報、意見を投稿できるチャットツール、社内アンケートを通じて現場の声を収集・共有する方法があります。
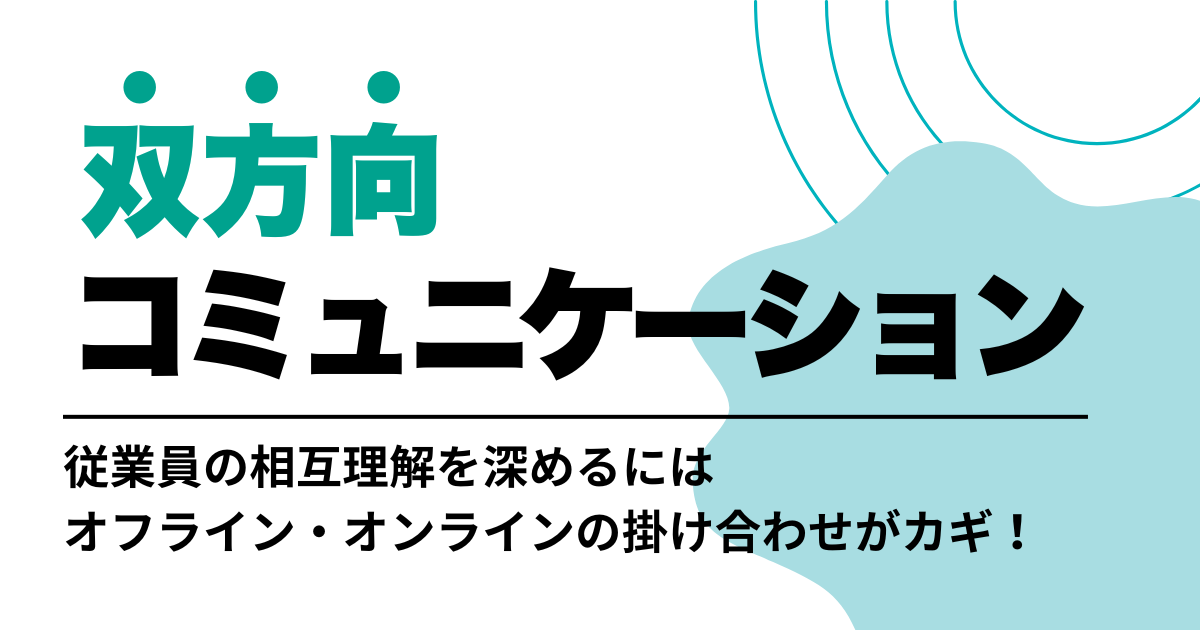
事業の価値や社会的意義を発信する
製造業の現場では、自分の作業が会社や社会にどう貢献しているのか見えづらく、やりがいを失いやすくなります。製品やサービスが顧客や社会に与えた影響を定期的に共有しましょう。
例えば、製造プロセスや製品が社会で使われている様子を動画で紹介する、納品先からの活用事例を社内ミーティングで共有する、受賞歴やメディア掲載実績を社内報や社内ポスターで告知するといった方法があります。
社員同士のつながりを深める取り組み
人間関係の希薄さや世代間ギャップは離職要因の一つです。部署横断の活動や社員同士のストーリーを発信することで、つながりを深めることができます。
具体的には、社内報での自己紹介リレーや部署紹介、他部署訪問や交流イベントの開催などがあります。

キャリア支援と成長機会の提供
キャリアの不安を転職でしか解決できないと考える社員は少なくありません。実際、転職者の約59%が「後悔した・失敗した」と感じており、その背景には、在籍中に将来像や不安を相談できる場がなかったことがあります。
単調な業務が続くと成長実感を得にくく離職につながりやすいため、定期的なキャリア相談の場を設けることが重要です。相談を通じて「仕事への意識が高まった」「目指すべきキャリアが明確になった」と感じる社員は多く、将来像が描ける職場は長期的な定着につながります。
参照:https://hrzine.jp/article/detail/4264(最終閲覧日:2025/08/08)
製造業における離職率低下の事例
製造業において離職率低下を実現した事例を紹介します。
自社に採用できそうな部分はないか参考にしてみてください。
マキチエ株式会社|組織の信頼関係を築いて離職者数32名→17名へ
マキチエ株式会社では、部署や拠点が異なることで「誰が何をしているのか分からない」「営業と製造の主張が嚙み合わない」といった連携不足が課題でした。そこで人材定着ツール「ourly」を導入し、記事やプロフィールを通じて社員同士がお互いの人となりや想いを知ることができる環境を整えました。
その結果、上司・部下や拠点を越えて情報交換しやすくなり、組織全体に一体感と信頼関係が広がりました。最終的には年間離職者数は32名から17名へ、入社1年未満に限れば16名から4名へと大幅に改善しました。

カネテツデリカフーズ株式会社|新人離職率50%→約10%へ
カネテツデリカフーズでは、入社3年以内の若手社員の離職率が約50%と高く、スキル共有や指導が不十分な「見て覚えろ」の風土が課題となっていました。そこで、年次の近い先輩社員によるマンツーマン指導制度と定期的な1on1面談、毎月の目標設定と振り返りを導入。
これにより新人の不安が軽減され、スキル習得とコミュニケーションが活性化しました。その結果、離職率は約10%まで大幅に改善し、職場全体の一体感も高まりました。
参照:https://ameand.co.jp/service/hr-pentest/contents/retention-success/#toc33(最終閲覧日:2025/08/08)
株式会社河合電器製作所|若手離職率を3年で0%に改善
愛知県の中小製造業・河合電器製作所では、価格競争と短納期対応に追われ、従業員が疲弊していました。そこでメンター制度や挑戦を評価する仕組み、「入社5年間ひとり暮らし」制度、部門横断のプロジェクト活動、社内イベントの強化など多面的なコミュニケーション施策を導入。
これにより社員同士や経営層との対話が活性化し、職場の一体感が高まりました。その結果、入社3年以内の離職率0%を達成し、厚生労働省の表彰も受けるなど職場の風土改革に成功しました。
参照:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/405996.pdf(最終閲覧日:2025/08/08)
アイコクアルファ株式会社|大学卒の3年以内離職率を1%未満に
アイコクアルファ株式会社では、新入社員の早期離職が課題で、育成制度の改善が求められていました。そこで「夢親制度」という、直属の上司ではなく、先輩社員が“親代わり”として5年間、業務から私生活まで幅広くサポートする仕組みを導入。
この取り組みにより、大学卒の3年以内離職率は1%未満、高卒でも3%以下に低下しました。
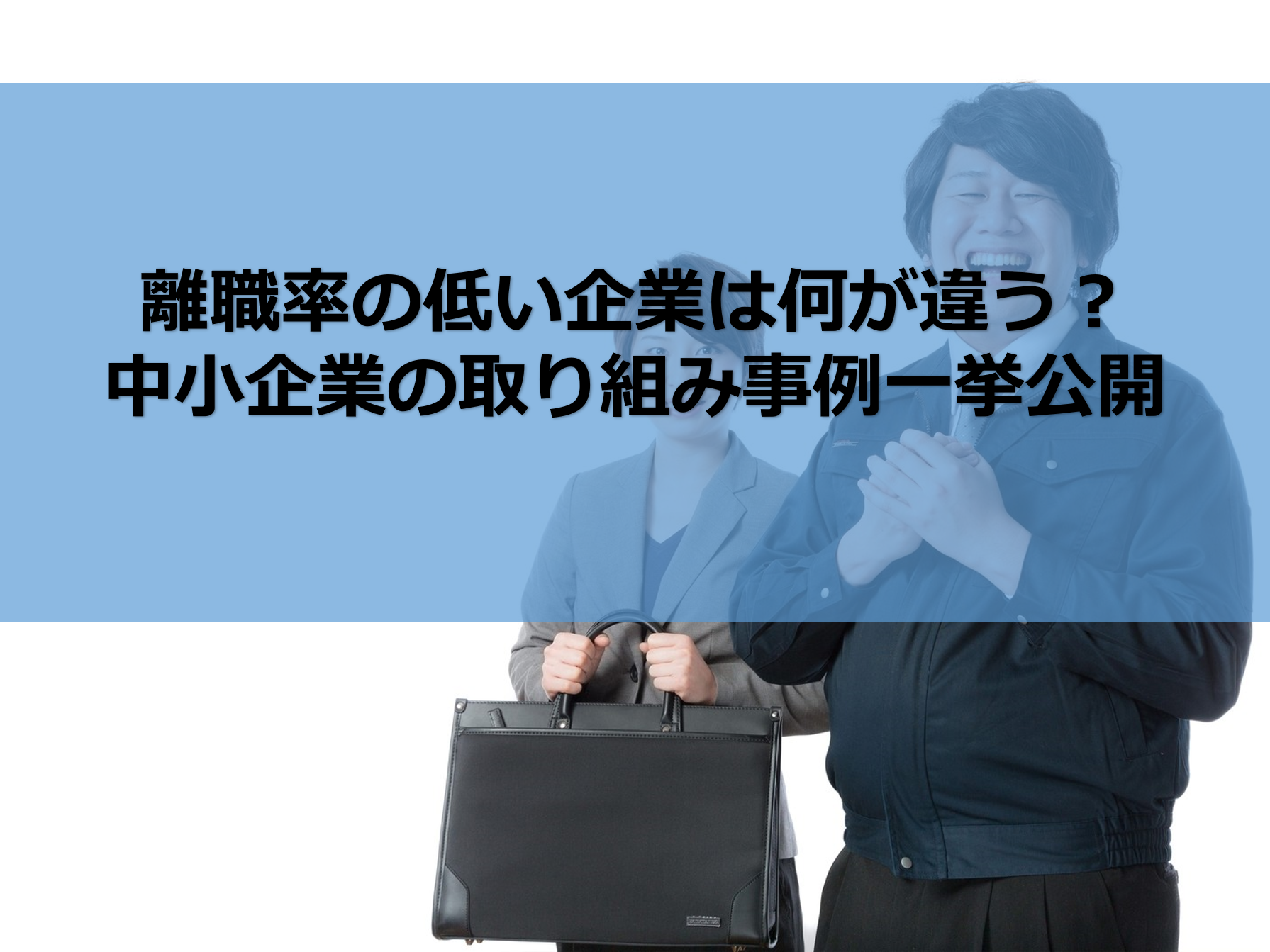
組織課題を見直そう
ここまで読んでくださった方は、離職問題の改善には給与や待遇だけでなく、コミュニケーションのあり方や働きがいなどの見直しが欠かせないことをお分かりいただけたかと思います。
とはいえ、そうした見えにくい組織課題の改善に取り組むのは簡単ではありません。
そこで以下に製造業の現場で実際に風土改革に取り組み、離職率の改善以外にも事業成長につなげた企業の事例を載せています。ぜひ読んで自社の取り組みの参考にしてみてください。