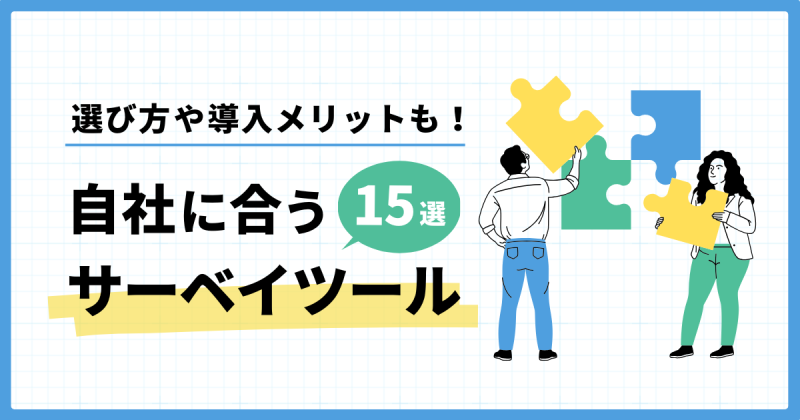エンゲージメントサーベイを実施したものの、「集まったデータをどう分析すれば良いのだろう」「分析結果をどう次のアクションに繋げれば良いか分からない」と悩んでいませんか。
サーベイは、実施するだけでは意味がありません。正しい方法で分析し、組織改善に繋げてこそ、その価値が発揮されます。
本記事では、サーベイの分析に初めて取り組む方でも実践できるよう、具体的な分析のステップや注意点を分かりやすく解説します。
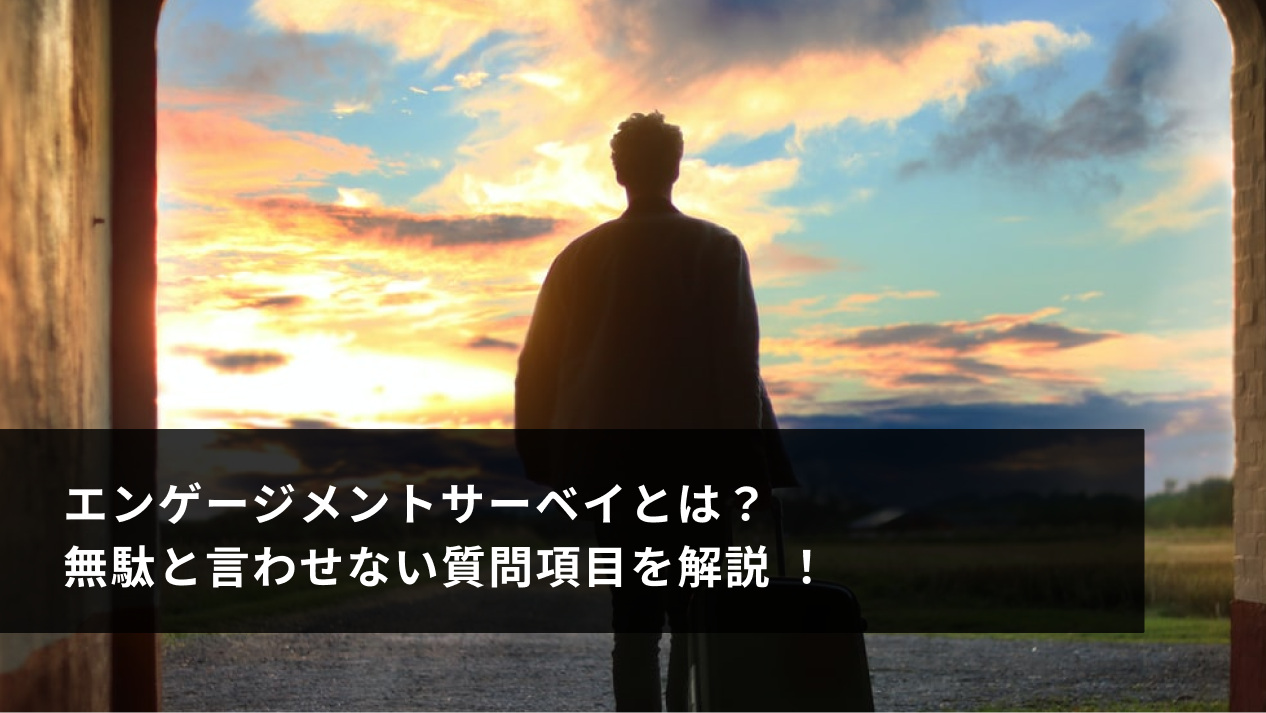
エンゲージメントサーベイの分析が重要な理由
エンゲージメントサーベイの分析は、単に数値を眺める作業ではありません。組織をより良くするための指標を得るための重要なプロセスです。
なぜ分析が重要なのか、その理由を2つの側面から解説します。
組織の現状を客観的に把握するため
従業員の声は、組織の健康状態を示す貴重なバロメーターです。しかし、個々の意見や感覚だけでは、組織全体の姿を正確に捉えることは困難です。
エンゲージメントサーベイのデータを分析することで、これまで感覚的にしか分からなかった組織の強みや課題を、客観的な数値や事実として可視化できます。
これにより、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた組織運営の第一歩を踏み出せます。
打ち手の優先順位を判断するため
組織が抱える課題は一つではありません。限られたリソースの中で最大の効果を上げるためには、どの課題から手をつけるべきか、優先順位の判断が必要です。
分析を通じて、エンゲージメントスコアに最も大きな影響を与えている要因は何か、どの部署や階層で課題が深刻なのかを特定できます。
これにより、効果的な施策に集中的に投資し、効率的な組織改善を実現できます。
| 課題の優先度判断の視点 | 具体例 |
|---|---|
| 影響の大きさ | 全社的にスコアが低く、多くの従業員に影響している項目は何か。 |
| 緊急度 | 離職意向と強く関連している項目はないか。 |
| 解決の実現可能性 | 比較的少ないコストや時間で改善が見込める項目は何か。 |
分析を始める前の準備
効果的な分析を行うためには、いきなりデータを見始めるのではなく、事前の準備が重要です。
ここでは、分析を始める前に押さえておくべき2つのポイントを紹介します。
分析の目的を明確にする
まず、「何のために分析を行うのか」という目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままでは、どのような分析手法を選べば良いか分からず、得られた結果も解釈できません。
「若手社員の離職率低下」「マネジメント層の育成」「生産性の向上」など、サーベイを通じて解決したい経営課題と結びつけることが重要です。
目的が明確であれば、分析の軸がぶれることなく、本当に価値のある洞察を得られます。
データの全体像を把握する
詳細な分析に入る前に、まずはデータの全体像を大まかに掴むことが大切です。
具体的には、サーベイの回答率、総合スコアの平均値や中央値、各質問項目の平均点などを確認します。
これにより、「今回のサーベイ結果は、どのくらいの従業員の意見を反映しているのか」「全体的にポジティブな傾向か、ネガティブな傾向か」といった、分析の前提となる基本情報を把握できます。
| 確認すべき全体像の指標 | チェックポイント |
|---|---|
| 回答率 | 全体の回答率は何%か。部署や役職によって回答率に大きな偏りはないか。 |
| 総合スコアの分布 | スコアは正規分布しているか。極端に高い、または低いスコアに偏っていないか。 |
| スコアが高い項目 | 組織の強みとして考えられる項目は何か。 |
| スコアが低い項目 | 組織の課題として考えられる項目は何か。 |
エンゲージメントサーベイ分析の具体的な5ステップ
準備が整ったら、いよいよ具体的な分析に入ります。
ここでは、基本的な分析の流れを5つのステップに分けて解説します。
このステップに沿って進めることで、網羅的かつ体系的にデータを分析できるでしょう。
ステップ1:全体傾向の把握(単純集計)
最初のステップは、設問ごとの全体のスコア(平均値など)を算出し、全体の傾向を把握することです。
これにより、組織全体の強みと弱みが明らかになります。例えば、「人間関係」のスコアは高いが、「成長の機会」のスコアは低い、といった大まかな傾向が見えてきます。
この段階では、まだ深掘りせず、組織の健康状態を大局的に捉えることが目的です。
ステップ2:属性別の傾向比較(クロス集計)
次に、部署、役職、年齢、勤続年数といった「属性」でデータを切り分け、グループごとのスコアを比較します。これがクロス集計です。 全体平均だけでは見えなかった、特定の属性における課題や強みが浮き彫りになります。
例えば、「営業部のエンゲージメントが他部署に比べて著しく低い」「勤続3〜5年の層でキャリア展望に関するスコアが落ち込んでいる」といった発見が、具体的な施策を考える上で重要な示唆となります。
| 属性(切り口)の例 | 分析によって明らかになることの例 |
|---|---|
| 部署・部門 | 特定の部署におけるマネジメントや業務負荷の問題 |
| 役職・階層 | マネージャー層と一般社員層の意識のギャップ |
| 勤続年数 | 入社後の年次ごとのエンゲージメントの変化と課題 |
| 年齢・世代 | 年代ごとの価値観の違いやキャリアに関する悩み |
ステップ3:影響要因の特定(相関分析)
エンゲージメントを向上させるためには、どの要素がエンゲージメントスコア全体に強く影響しているかを知る必要があります。ここで用いるのが相関分析です。
これは、総合的なエンゲージメントを示す質問(例:「あなたは、この会社で働き続けることを誇りに思うか」)のスコアと、その他の各質問項目のスコアとの関連性の強さを分析する手法です。
相関が強い項目ほど、エンゲージメントへの影響度が大きい、つまり「重要な改善項目」である可能性が高いと判断できます。
ステップ4:課題の深掘り(フリーコメント分析)
数値データ(定量データ)だけでは分からない、従業員の具体的な意見や感情を把握するために、フリーコメント(定性データ)の分析が欠かせません。
全てのコメントに目を通し、キーワードやテーマごとに分類(テキストマイニングなど)することで、スコアの背景にある具体的な理由や従業員の本音が見えてきます。
「なぜ、評価制度のスコアが低いのか」「具体的に、どのような成長機会を求めているのか」といった問いへの答えが、ここから得られます。
ステップ5:改善アクションプランの策定
分析によって明らかになった課題を基に、具体的な改善アクションプランを策定します。このステップがサーベイの最終目的です。
課題の特定だけで終わらせず、「何を(What)」「誰が(Who)」「いつまでに(When)」実行するのかを明確に定めます。プラン策定の際は、分析結果を基に課題の優先順位をつけ、実現可能性の高い施策から着手することが成功の鍵です。
“測って終わりにさせない” サーベイツール『ourly survey』

ourly surveyは、自由な設問設計と施策立案・実行までを支援する“測って終わり”にさせないサーベイです。
細かい分析機能で組織課題を可視化
「所属/部署」「役職」「職種」「拠点」などのユーザー属性で回答結果を分析することが可能です。理念の浸透度合いや、エンゲージメントが低い層を見える化できます。
組織課題に応じた自由な設問
従業員エンゲージメントの向上や人事施策の成果測定、ビジョンの浸透度合いの計測など、自社が手に入れたい組織状態から逆算して自由に質問の作成が可能です。
行動データを組み合わせた分析
弊社が提供するweb社内報「ourly」の閲覧行動とサーベイで集計した結果をクロス分析することで、組織改善のサイクルを加速させます。
一気通貫した改善支援
弊社の組織開発コンサルタントが、サーベイで集計した結果をもとに組織課題の特定や改善施策の提案、実行を支援します。
以下の資料では、ourly surveyの具体的な特徴や機能を紹介しています。サービスの比較や導入のご検討などに、ご活用ください。

エンゲージメントサーベイ分析で陥りがちな注意点
分析プロセスには、いくつか陥りがちな罠が存在します。これらを事前に知っておくことで、より客観的で有益な分析が可能になります。
ネガティブな結果から目をそむける
スコアが低い項目や、耳の痛いフリーコメントなど、ネガティブな結果はどうしても避けたくなるものです。
しかし、それらこそが組織が成長するための最大のヒントです。課題を真摯に受け止め、改善に取り組む姿勢を示すことが、逆に従業員の信頼を高めることに繋がります。
分析そのものが目的化してしまう
高度な分析手法を駆使したり、詳細すぎるレポートを作成したりすることに満足し、分析自体が目的になってしまうケースがあります。
重要なのは、分析から得られた示唆を基に、いかに組織を良くしていくかです。常に「この分析は、具体的なアクションに繋がるか?」という視点を忘れないようにしましょう。
一度の結果だけで判断してしまう
サーベイは一度実施して終わりではありません。組織の状態は常に変化するため、継続的に実施し、時系列で変化を見ていくことが重要です。
過去のデータと比較することで、実施した施策の効果測定ができ、より長期的な視点での組織改善が可能になります。
| 継続的な分析のメリット | 具体的なアクション |
|---|---|
| 施策の効果測定 | 施策実施後にスコアが改善したかを確認し、次の打ち手を考える。 |
| 変化の早期発見 | スコアが悪化した項目を早期に特定し、迅速に対応する。 |
| 定点観測 | 組織の健康状態を定期的にチェックし、大きな問題になる前に対処する。 |
分析結果を組織改善に繋げるためのポイント
分析結果を価値あるものにするためには、その後の活用方法が鍵を握ります。
分析結果を組織全体で共有し、改善活動を推進するための2つのポイントを解説します。
分かりやすいレポートを作成し共有する
分析結果は、専門家でない経営層や現場のマネージャーにも理解できるよう、専門用語を避け、グラフや図を用いて視覚的に分かりやすくまとめることが重要です。
レポートには、単なるデータの羅列ではなく、「この結果から何が言えるのか(So What?)」という解釈と、「次に何をすべきか(So What?)」というアクションへの提言を含めることで、関係者の理解と協力を得やすくなります。

各部署を巻き込み改善を推進する
組織全体のエンゲージメント向上は、人事部だけで成し遂げられるものではありません。
特に、分析によって明らかになった部署ごとの課題については、当該部署のマネージャーやメンバー自身が主体となって改善に取り組むことが不可欠です。
分析結果を各部署にフィードバックし、対話の機会を設け、現場主導の改善活動をサポートする役割を担いましょう。
まとめ
エンゲージメントサーベイの分析は、組織と従業員の対話を促進し、より良い職場環境を築くための強力な手段です。
本記事で紹介した5つのステップと注意点を参考に、データに基づいた客観的な分析を行い、具体的な改善アクションに繋げてください。分析を過度に難しく考える必要はありません。
従業員の声に真摯に耳を傾け、組織を良くしたいという想いを持って取り組むことが、最も重要なのです。