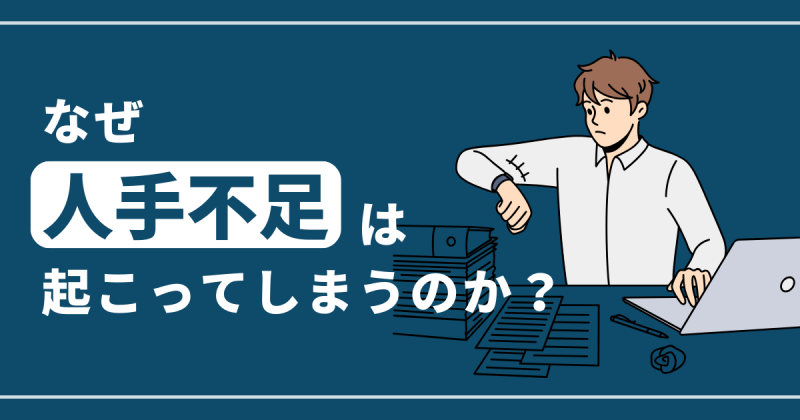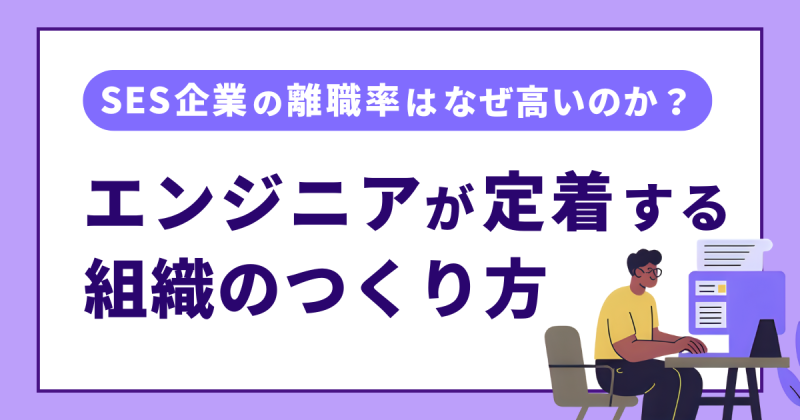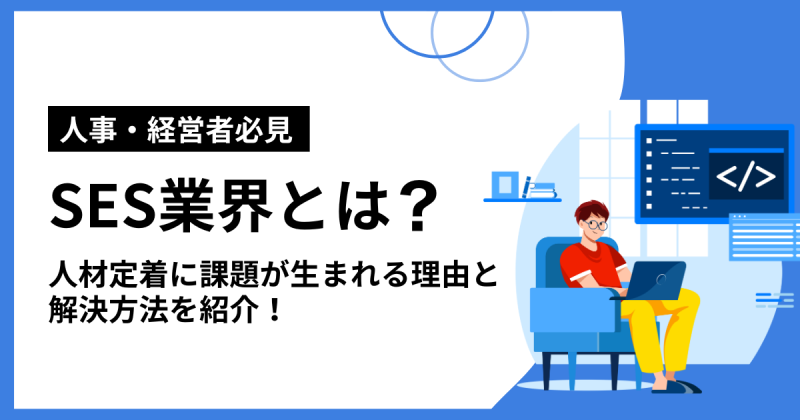多くの企業で「人が足りない」という声が聞かれるようになって久しいですが、自社の採用活動がうまくいかなかったり、離職者が増えたりする中で、この問題の根深さを実感している経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。人手不足は、単なる一時的な現象ではなく、日本の社会構造の変化に起因する深刻な経営課題です。
本記事では、人手不足がなぜ起こるのか、その根本的な原因を多角的に分析し、企業が今すぐ取り組むべき具体的な対策について分かりやすく解説します。
日本企業が直面する人手不足の現状
現在、日本の多くの企業が人手不足という深刻な課題に直面しています。これは一部の業界に限った話ではなく、日本経済全体に広がる構造的な問題となっています。まずは、データと具体的な業界の状況から、その深刻さを確認しましょう。
データで見る人手不足の深刻度
帝国データバンクが2024年10月に行った調査によると、正社員が不足していると感じる企業の割合は51.7%に達しており、半数以上の企業が人材確保に困難を感じている状況が明らかになりました。 この数値は年々増加傾向にあり、企業の成長にとって大きな足かせとなっています。
人手不足は、もはや「他人事」ではなく、すべての企業が向き合うべき喫緊の課題なのです。
参考:https://www.tdb.co.jp/report/economic/20241113-laborshortage202410/
人手不足が深刻化する5つの主な原因
なぜこれほどまでに多くの企業が人手不足に悩まされているのでしょうか。その背景には、社会構造の変化から個々の企業が抱える問題まで、複数の原因が複雑に絡み合っています。
少子高齢化による生産年齢人口の減少
最も根本的な原因は、日本の急速な少子高齢化です。 労働力の中核をなす「生産年齢人口(15歳~64歳)」は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。 働き手の絶対数が減っていく中で、企業間の人材獲得競争はますます激化しているのです。
働き方の価値観の多様化への対応遅れ
現代の働き手は、給与だけでなく、ワークライフバランスや自己成長、社会貢献などを重視する傾向が強まっています。 リモートワークやフレックスタイム制度など、柔軟な働き方を求める声が高まる中で、旧来の画一的な労働制度しか提供できない企業は、求職者から選ばれにくくなっています。
特定の業界・職種における需要と供給のミスマッチ
IT業界のように需要が急拡大している分野がある一方で、一部の産業では仕事内容や労働条件から求職者が集まりにくいという構造的なミスマッチが生じています。
特に、肉体労働が中心となる建設業や、不規則な勤務形態が多い小売・サービス業などで、その傾向が顕著です。
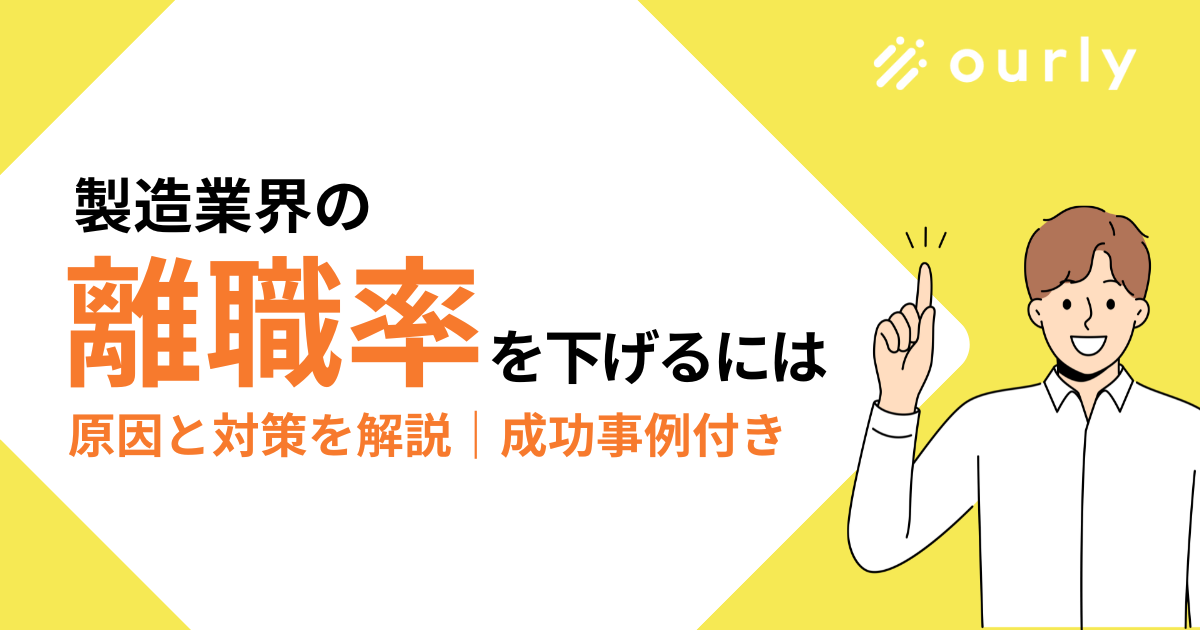

労働条件や職場環境に対する不満
賃金が仕事内容に見合っていない、長時間労働が常態化している、休暇が取りにくい、人間関係が良好でないといった労働条件や職場環境への不満は、離職の大きな原因となります。 新しい人材を採用できても、既存の従業員が定着しなければ、人手不足は一向に解消されません。
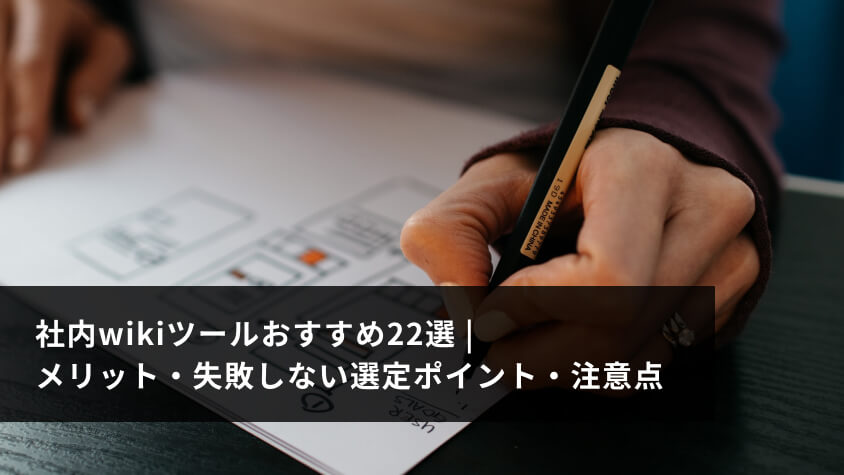
採用市場における企業間競争の激化
生産年齢人口の減少に伴い、採用市場は「買い手市場」から「売り手市場」へと完全にシフトしました。その結果、少ない求職者を多くの企業が奪い合う構図となり、特に知名度や待遇面で大企業に劣る中小企業は、採用活動において厳しい戦いを強いられています。
人手不足が企業経営に与える3つの深刻な影響
人手不足は、単に「忙しくなる」という問題にとどまらず、放置すれば企業の存続そのものを脅かしかねない深刻な影響を及ぼします。
事業の縮小やサービスの質の低下
必要な人員を確保できなければ、受注を制限したり、店舗の営業時間を短縮したりと、事業規模の縮小を余儀なくされます。また、一人当たりの業務量が増えることで、製品やサービスの質が低下し、顧客満足度の低下や顧客離れにつながる恐れもあります。
既存従業員の負担増加と離職リスクの増大
人手不足のしわ寄せは、必然的に今いる従業員に向かいます。長時間労働や過剰な業務負荷は、心身の疲弊を招き、生産性の低下や休職につながります。さらに、不満が限界に達した従業員が次々と辞めていく負の連鎖に陥り、人手不足がさらに深刻化するリスクも高まります。
技術やノウハウの継承の停滞
特に熟練の技術を持つ従業員が退職した場合、その技術やノウハウが社内で継承されず、失われてしまう危険性があります。若手人材が十分に育たないままベテラン層が引退していくと、企業の競争力の源泉である技術力が低下し、長期的な成長を阻害する要因となります。
人手不足を解消するための8つの具体的な対策
深刻な人手不足を乗り越え、持続的な成長を遂げるためには、企業は従来のやり方を見直し、多角的な対策を講じる必要があります。ここでは、今すぐ取り組むべき8つの対策を紹介します。
採用ターゲットと戦略の根本的な見直し
これまでの採用基準に固執せず、未経験者や異業種からの転職者にも門戸を広げ、ポテンシャルを重視した採用に切り替えることが重要です。また、求人媒体だけに頼るのではなく、リファラル採用(社員紹介)など、多様な採用チャネルを積極的に活用しましょう。

魅力ある労働条件と職場環境の整備
従業員が安心して長く働ける環境を整えることは、人材定着の基本です。
賃金の引き上げや適正な評価制度の導入はもちろんのこと、長時間労働の是正、有給休暇の取得促進、ハラスメントのない風通しの良い職場づくりなどを通じて、働きがいのある環境を整備することが求められます。
多様な人材の積極的な採用と活用
シニア層の経験や知識、子育て中の柔軟な働き方ニーズ、意欲ある外国人材など、これまで十分に活用されてこなかった多様な人材に目を向けることが重要です。
それぞれの事情に合わせた勤務形態やサポート体制を整えることで、新たな労働力を確保できます。
従業員エンゲージメントの向上施策
従業員が自社に対して愛着や貢献意欲を持つ「従業員エンゲージメント」を高めることは、離職率の低下に直結します。
福利厚生などは他の企業も改善を図るため、どうしても制度面での差別化がしづらくなってくるでしょう。従業員に定着してもらうためには、制度面だけでなく、従業員エンゲージメントを向上させる必要があります。
定期的な1on1ミーティングの実施、キャリアパスの提示、社内報での企業のビジョン共有などを通じて、従業員一人ひとりが「この会社で働き続けたい」と思えるような関係性を築きましょう。
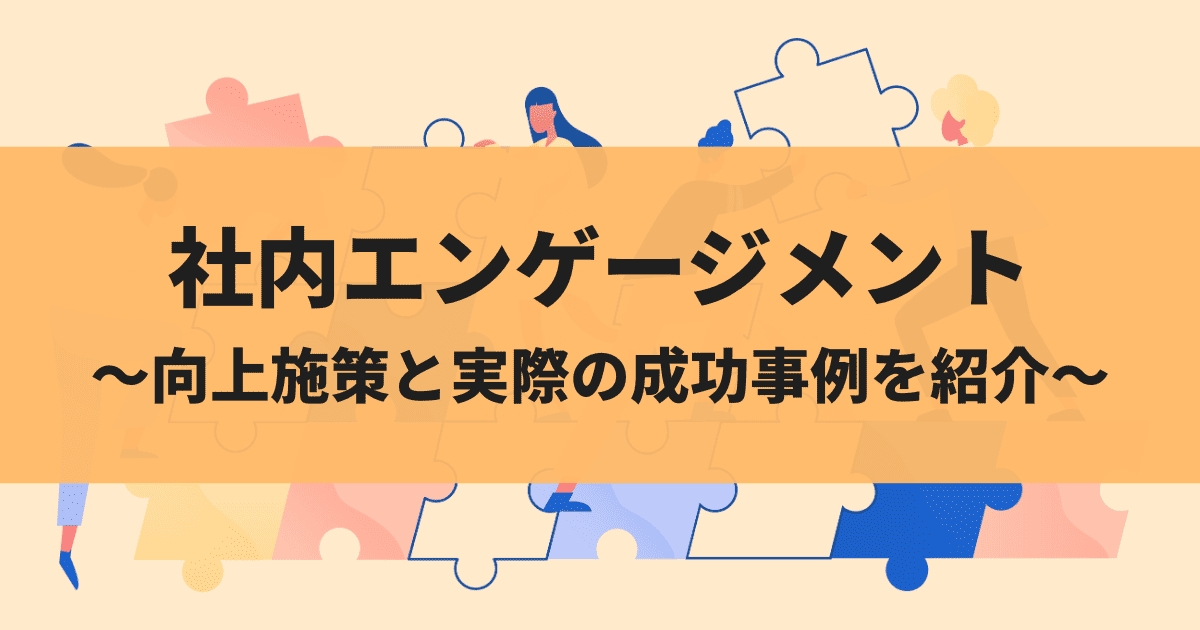
効果的な人材育成とスキルアップ支援
未経験者を採用した場合でも、体系的な研修プログラムやOJT(On-the-Job Training)を用意することで、早期に戦力化することが可能です。また、資格取得支援制度やリスキリング(学びなおし)の機会を提供し、従業員のスキルアップを後押しすることは、本人の成長意欲を高め、定着率の向上にも貢献します。

企業の魅力向上につながる採用ブランディング
自社のウェブサイトやSNSなどを通じて、事業内容だけでなく、企業文化や働く環境、社員の姿などを積極的に発信し、「この会社で働くと、こんなに魅力的な経験ができる」というイメージを伝えることが重要です。
求職者に対して自社の魅力を効果的に伝え、応募意欲を高めましょう。
DX推進による業務効率化と生産性向上
RPA(Robotic Process Automation)などのツールを導入して定型業務を自動化したり、情報共有ツールを活用して業務プロセスを見直したりすることで、少ない人数でも高い生産性を維持することが可能です。 人にしかできない付加価値の高い業務に集中できる環境をつくることが、従業員の満足度向上にもつながります。
アウトソーシングや外部サービスの戦略的活用
経理や労務などのノンコア業務を専門の外部企業に委託(アウトソーシング)することで、社員をコア業務に集中させることができます。 また、人材派遣や業務委託などのサービスを戦略的に活用し、繁閑に応じて柔軟に労働力を調整することも有効な手段です。
人手不足対策に成功した企業事例
ここでは、実際に独自の工夫で人手不足対策に成功している企業の事例を2つ紹介します。
トヨタ自動車
トヨタ自動車では、人手不足の課題に対してデジタルツインとロボット技術を活用した革新的な解決策を実施しています。貞宝工場における金型・設備部品加工設備では、これまで人に依存していた材料投入作業を3Dモデル上で改善・自動化することで、生産性を3倍に向上させ、改善リードタイムを3分の1に短縮することに成功しました。また、元町工場では車両搬送ロボット(VLR)を導入し、慢性的な人手不足に悩む完成車ヤードでの作業負荷軽減を実現しています。
【参考】https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/39758393.html
アントワークス

飲食業を中心に全国各地で店舗を展開する株式会社アントワークスは、web社内報「ourly」を活用した情報発信を開始。代表や経営陣からの未来像の共有や、店舗で活躍する社員を取り上げることで、刺激やキャリアパスのヒントを届けました。
その結果、現場に伝わりづらかった経営陣の3年後・5年後のビジョンや実際のキャリアアップ事例が共有され、社員の定着につながり、離職者数は25%減少。さらに社員数も純増基調へと転じました。
マキチエ

補聴器メーカーとして全国に38拠点の直営店を展開し、開発から製造、販売までを担うマキチエ株式会社は、2024年にweb社内報「ourly」を導入。社内報やプロフィール機能を活用し、社員同士の理解を深めることで、コミュニケーションの質の向上を図りました。
その結果、組織全体に一体感が生まれ、新規参画者のオンボーディングにも良い効果を発揮。さらに、離職率は10.5%から5.4%へと大幅に改善しました。
離職を低減し、人手不足を改善するweb社内報「ourly」
ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
まとめ
人手不足は、少子高齢化という社会構造的な問題を背景に持つ、一朝一夕には解決できない根深い課題です。しかし、原因を正しく理解し、自社の状況に合わせて採用戦略の見直しや労働環境の改善、エンゲージメントの向上、DXの推進といった対策を粘り強く実行することで、必ず活路は見いだせます。
本記事で紹介した内容を参考に、人材に選ばれ、従業員が長く活躍できる企業づくりへの第一歩を踏み出してください。