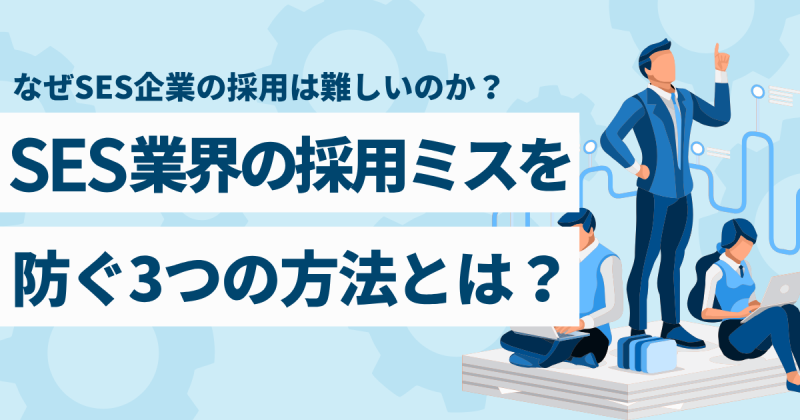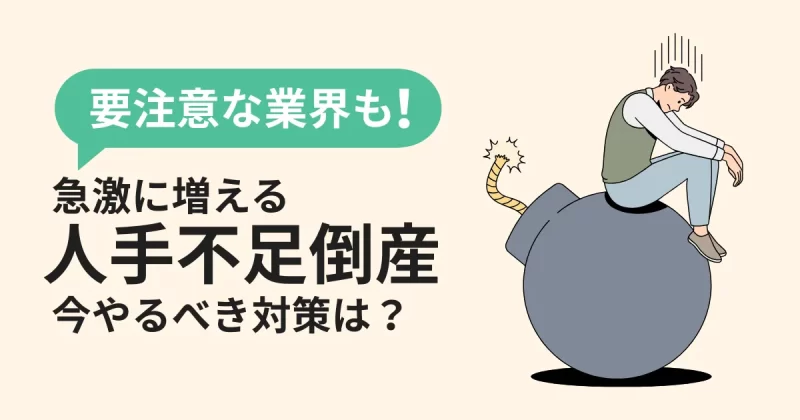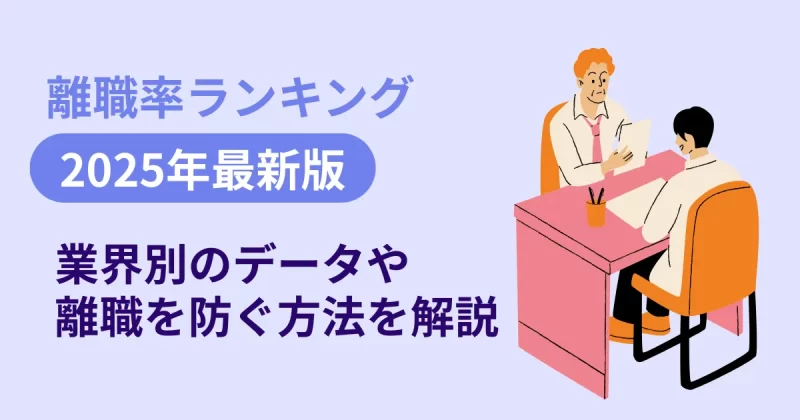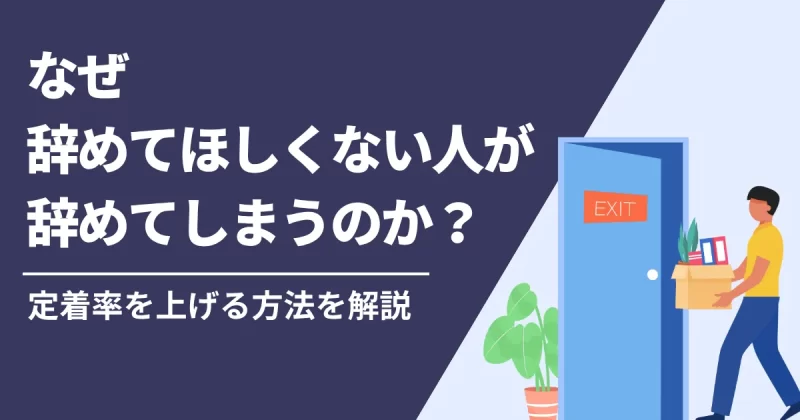「多額の採用コストをかけても、エンジニアからの応募が集まらない」「採用に至っても、企業の文化に合わず早期に離職してしまう」
SES(システムエンジニアリングサービス)企業の多くの採用担当者は、このような根深い課題に直面しています。採用競争の激化により、従来の求人媒体やエージェントに依存した採用活動は限界を迎えつつあります。
本記事では、SES業界特有の採用課題を構造的に分析し、実践可能な解決策を「採用ブランディング」「採用チャネルの多様化」「入社後の定着」の3つの観点から解説します。採用の成功が従業員エンゲージメントの向上と不可分であるという視点から、組織を活性化させるための具体的な方策を解説します。
SES業界の採用が難しい構造的な課題
SES企業の採用が難しい背景には、業界特有の構造的な課題が存在します。
これらを理解することは、自社の課題を客観的に把握する第一歩です。
自社の魅力や文化が候補者に伝わりにくい
SESは、エンジニアが顧客先に常駐して業務を行うビジネスモデルです。そのため、自社開発企業のように「自社プロダクトへの愛着」や「一体感のある開発文化」を直接的な魅力として伝えにくい側面があります。
候補者から「どの会社も同じに見える」「働く環境や文化がイメージしづらい」と見なされ、結果として知名度や待遇条件が優れた企業に応募が集中する傾向があります。
事業や仕事で他社と差別化することが難しいからこそ、人や組織の魅力、企業の理念や目的を積極的に候補者に伝えていくことがポイントです。

キャリアパスの不透明性への懸念
候補者は、入社後にどのようなスキルを習得し、どのように成長できるかというキャリアパスを重視します。
しかし、参画プロジェクトが顧客企業の状況に左右されやすいSESの特性上、体系的で明確なキャリアパスを提示することが困難な場合があります。
「希望するスキルが身につかないのではないか」「将来のキャリアを描きにくい」といった懸念が、応募の障壁となることがあります。
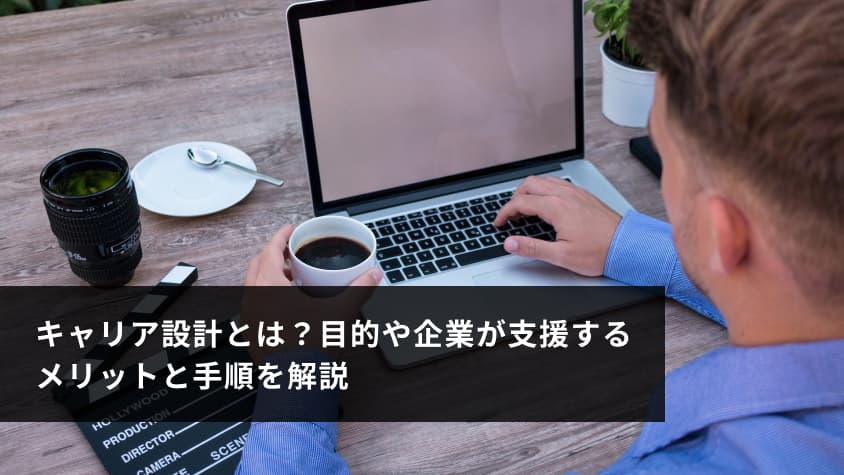
ミスマッチを防ぐ3つの具体的アプローチ
構造的な課題を踏まえ、次に応募者とのミスマッチを防ぎ、自社に適合する人材を惹きつけるための具体的なアプローチを解説します。
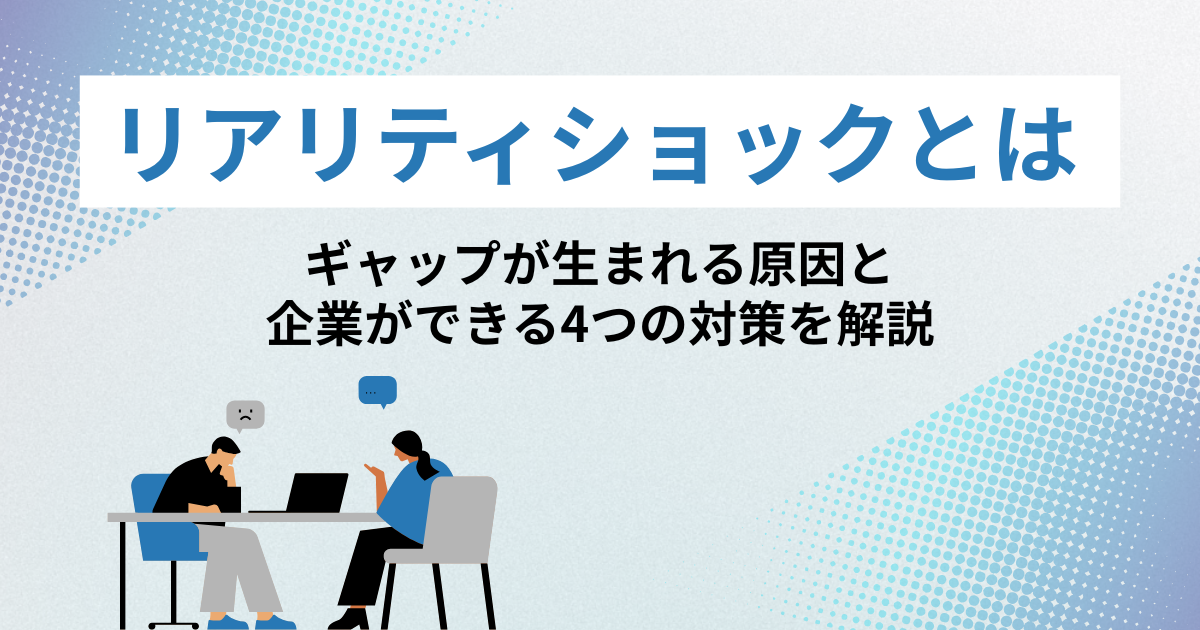
採用ブランディングを強化する
他社との差別化を図り、「この会社で働きたい」という動機を形成するには、採用ブランディングの強化が重要です。特に「何を」伝えるかが鍵となります。
待遇や案件内容だけでなく、企業の理念やビジョン、そして「どのような人材が、どのように働いているか」という組織文化や人の魅力を積極的に発信することが有効です。

具体的には、社員インタビューやブログ、SNSなどを通じて自社のカルチャーを可視化し、候補者の共感を呼ぶ情報を伝えることが求められます。
弊メディアでも「オープン社内報」として、複数の企業様の社内報を限定公開しておりますので、ご参考にご覧ください。
採用チャネルを多様化する
従来の求人媒体や人材エージェントだけでなく、自社に合った人材に直接アプローチできる採用チャネルの開拓が重要です。
リファラル採用の推進
社員紹介によるリファラル採用は、カルチャーフィットした人材と出会いやすい有効な手法です。
自社の文化を深く理解している社員から紹介をしてくれるため、入社後のミスマッチが起こりにくく、定着率が高い傾向が見られます。
インセンティブ制度の設計はもちろん、社員が知人を紹介したいと思える組織文化への投資は必要です。

SNS採用の活用
X(旧Twitter)やnoteなどを活用し、自社の技術的な取り組みや社内の雰囲気などを継続的に発信することで、企業のファンを増やし、潜在的な候補者層との接点を構築できます。
広告的な情報発信ではなく、企業のリアルな姿を見せることが、候補者の共感と信頼を得る鍵となります。
カルチャーフィットを見極める選考プロセスを設計する
採用基準に「カルチャーフィット」を明確に位置づけ、それを見極めるための質問を面接に組み込むことが有効です。
「どのようなチームで働くことを好みますか」「困難な状況にどう対処しましたか」といった質問を通じ、候補者の価値観や行動特性が自社の文化と合致するかを確認します。
また、現場のエンジニアに選考に参加してもらうことで、より実務に近い視点でのマッチング精度を高められます。
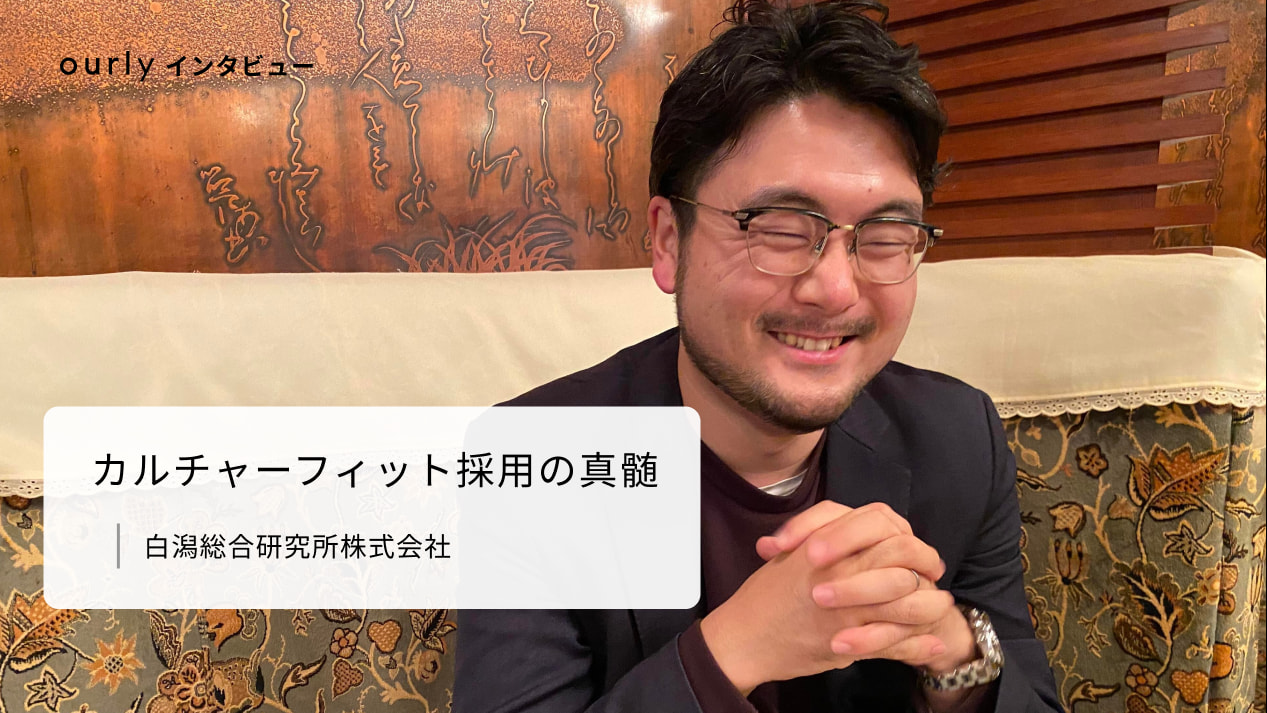
定着から逆算したカルチャーづくり
採用活動の成功は、内定承諾で完結しません。採用した人材が入社後に能力を発揮し、定着してこそ成功と言えます。
そのためには、採用という「入口」の施策と、入社後の「定着」の施策を連携させたカルチャーづくりを推進する必要があります。
ここでは、カルチャーづくりにつながる施策の例を3つ紹介します。

手厚いオンボーディングの実施
入社後の不安を解消し、円滑な業務開始を支援するオンボーディングは、定着率を左右する重要なプロセスです。
業務スキルの習得支援に加え、自社の文化や歴史を伝え、役員や他部署のメンバーと交流する機会を設けるなど、組織への理解と関係構築を促すプログラムの設計が重要です。
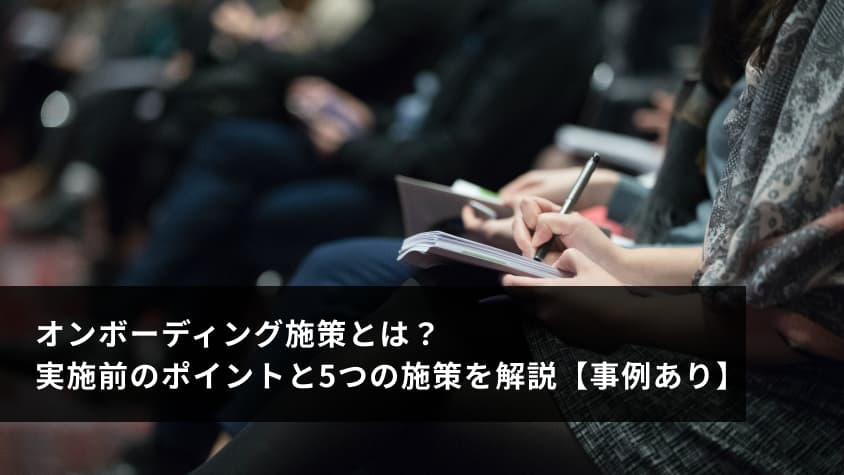
帰属意識を高めるコミュニケーション施策
顧客先に常駐するエンジニアが孤立しないよう、意識的にコミュニケーションの機会を作ることが求められます。
定期的な1on1ミーティングによる状況把握、社内報での情報共有、月1回の帰社日や社内イベントの開催など、物理的な距離を補う工夫が必要です。
こちらの資料では、インナーコミュニケーションを活性化させるノウハウを3つのステップで解説しておりますので、ぜひご参照ください。
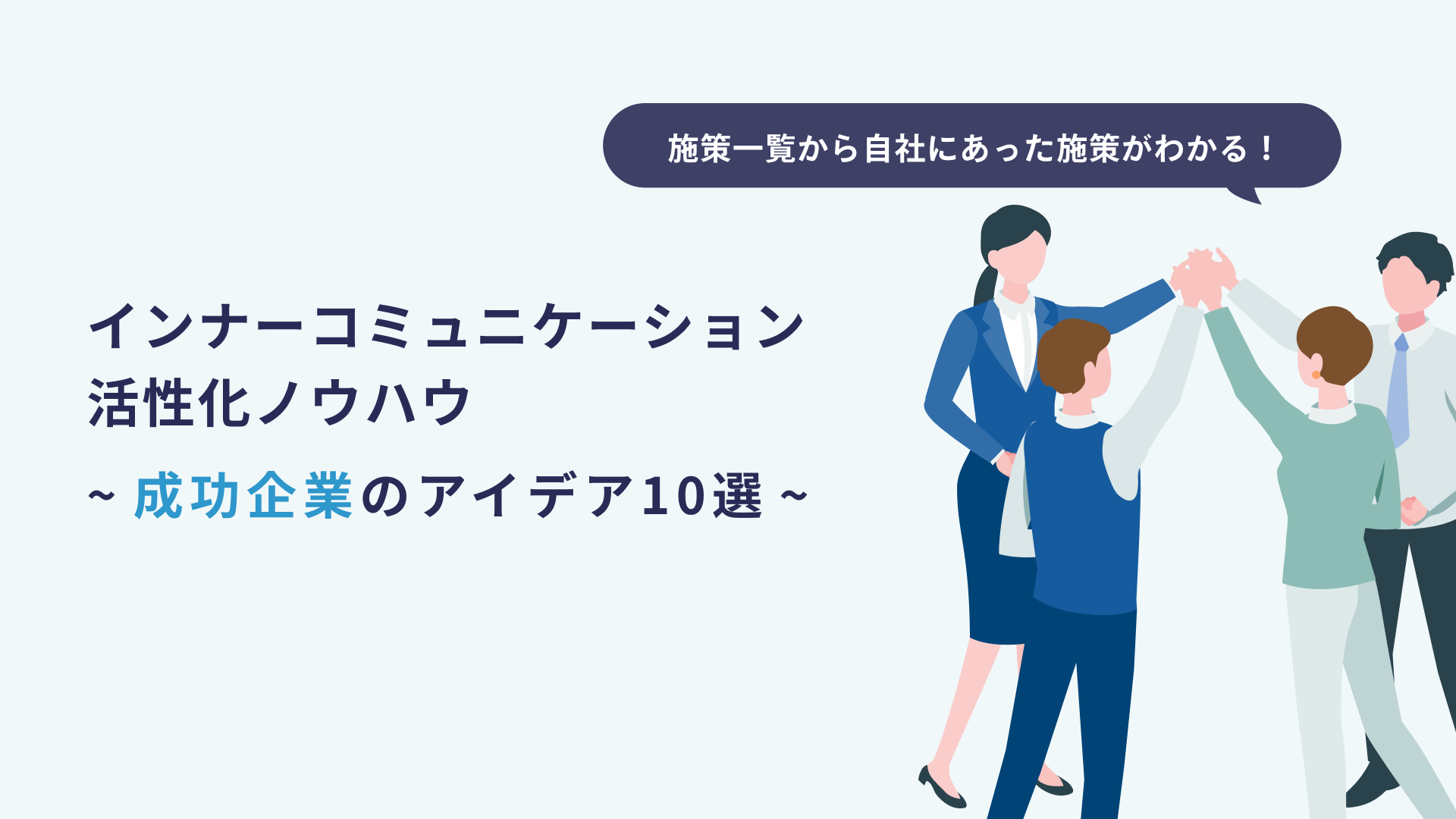
キャリアパスの明示と成長支援
エンジニア一人ひとりのキャリアプランに寄り添い、その実現を会社として支援する姿勢を示すことは、エンゲージメントの向上に直結します。
資格取得支援や研修制度の充実、目標管理制度(MBO)などを通じて、個人の成長と会社の方向性をすり合わせ、納得感のあるキャリアパスを共に構築していくことが求められます。
カルチャーの醸成・共有にはweb社内報ツール「ourly」
SES企業は、事業や仕事内容で他社と差別化することが難しいからこそ、人や組織の魅力、企業の理念や目的を積極的に候補者に伝えていくことがポイントです。
そのためにはまず、社内でカルチャーを醸成していくことが何よりも重要であるといえます。
ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
ourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援と詳細な分析、洗練されたコンテンツ配信から、効率的な理念浸透や文化醸成を実現します。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」「理念浸透・文化醸成を通して組織改善したい」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
実際にSES企業のお客様の事例もございます。ぜひご覧ください。


まとめ
SES企業の採用は、そのビジネスモデルの特性上、いくつかの困難を伴います。課題の本質は「自社の魅力が伝わりにくいこと」と「入社後の帰属意識の醸成が難しいこと」にあります。
本記事で解説したように、採用の成功は単一の施策で実現できるものではありません。「採用ブランディング」で自社ならではの魅力を伝え、「多様な採用チャネル」で共感する人材と出会い、「カルチャーフィットを見極める選考」でミスマッチを抑制します。そして、採用をゴールと捉えず、入社後の「定着」と「活躍」を見据えた組織開発の一環として、各施策を継続的に実行することが不可欠です。
そしてそのためには、自社のカルチャーをしっかりと育んでいくことが、競争優位の源泉となります。
本記事で提示したアプローチが、各社の採用活動、ひいては組織開発を前進させる一助となれば幸いです。