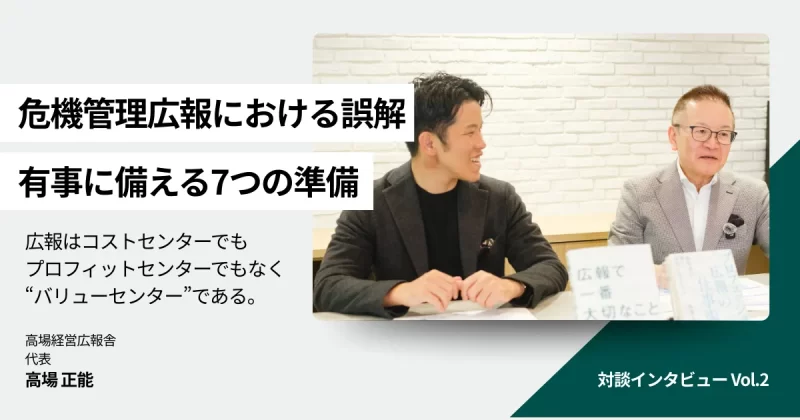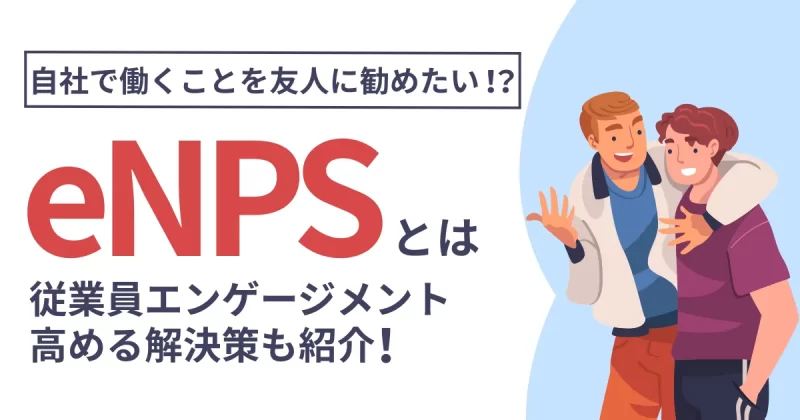人的資本経営とは、企業の人材はコストではなく付加価値を生み出す資本であり、投資対象であると位置付ける経営の手法です。ESG投資やイノベーションへの期待から、世界中で注目されるようになりました。
海外の一部では人的資本情報の開示が義務化され、国内でも可視化に向けた指針が2022年に発表されています。人的資本経営への対応が急務であることは明らかですが、どのように戦略を立て直していくべきか、困惑している企業も多いようです。
本記事では、企業が人的資本経営を実践するためのポイントや、取り組むための3ステップを解説します。情報開示をめぐる動向や可視化指針のポイントなども説明していますので、人的資本経営の理解にぜひお役立てください。
人的資本経営とは
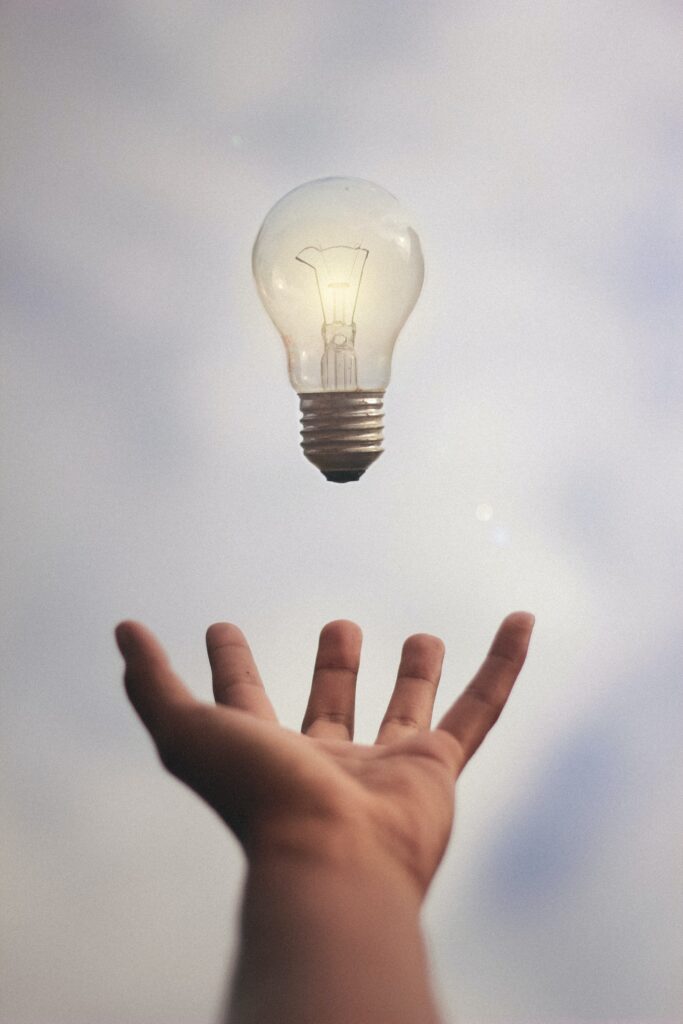
人的資本経営とは、「人材」を「コスト」ではなく「資本」と捉え、投資の対象とする経営手法です。人材の持てる力を最大限に引き出し高めていくことを目的に、あらゆる投資をおこない、中長期的な企業価値向上を目指していきます。
人的資本の情報を「企業の将来性を判断する指標」と捉え、開示を求める声が強くなりつつあります。海外の一部では人的資本の情報開示が義務化され、日本においても可視化に向けた動きが加速しはじめました。
人的資本経営と従来型の経営との違い
人材を「資本」ではなく「資源」と捉えている点が、従来型の経営と人的資本経営との大きな違いです。従来型の経営では、人材は「資源」であるため管理の対象であり、育成など人材に対する取り組みはコストと考えます。
これに対し人的資本経営では、人材は永続的な企業の成長を支える大切な資本として捉えます。人材の活用や育成にかかる費用は、将来のための戦略的な投資と考え、組織と人材の自律した関係性を目指すものです。
人的資本とその他の資本との違い
企業が投資対象とする「資本」は大きく「無形資本」と「有形資本」に分類されます。有形資本には株式や借入などの「財務資本」、建物や設備といった「製造資本」が挙げられるでしょう。
「人的資本」は無形資本に分類されます。所属する従業員の能力や知識、意欲といった形のないものが人的資本です。そのほか特許権やブランドなどは「知的資本」、ステークホルダーとの関係性を構築する能力を「社会・関係資本」、再生可能・不可能な環境資源を「自然資本」と定義しています。
人的資本経営が必要とされる背景

人的資本が注目を集め、多くの企業で必要とされるのには、以下のような社会情勢の変化が背景にあります。
- ESG投資への注目
- 人材や働き方の変化
- AIやロボット技術の進歩
それぞれ、詳しく解説します。
1. ESG投資への注目
ESGとは、環境(Environmennt)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字をとったものです。近年、企業を取り巻くステークホルダーの意識が変化し、このESGへの投資状況を企業評価の基準と考える傾向が強くなっています。
なかでも、社会とガバナンスに関連する人的資本は重視される要素です。近年、人的資本に対する投資状況を、企業の成長性を判断するポイントと捉える投資家や消費者が増加していることが背景にあるようです。
2. 人材や働き方の変化
労働環境の変化も、人的資本経営が注目される理由の一つです。人手不足のなか、事業を運営するには、人員補充だけでなく既存の従業員のスキル向上が必要です。また、外国人やシニアといった、あらゆる層の人材の戦力化も考えなくてはなりません。
こうした人材構造の変化への対応力が、企業が存続していくためには必要です。個々の人材の価値を最大化する環境や仕組みを構築するうえで欠かせないのが、人材を資本と考える人的資本経営といえるのです。
3. AIやロボット技術の進歩
AIやロボット技術の進歩により業務のデジタル化が進む反面、専門技術を支える人材の不足も問題となります。こうした変化に対応できる優秀な人材を確保するには、採用による補充だけでなく、既存人材のスキル向上も必要です。
また、テクノロジーの進歩による成熟した市場においては、技術力の差だけでは競合との差別化が難しくなります。そこで必要となるのが、新たなアイデアによる価値創造を担えるクリエイティブな人材です。人的資本経営により、人材が価値を発揮できる環境の整備が求められるのは自然な流れといえるでしょう。
人的資本の情報開示をめぐる動向

人的資本への投資状況が、企業の成長性への重要な判断指標であることは前述しました。そのため、人的資本に関する情報開示が強く求められています。ここでは、海外と国内における情報開示の動向を解説します。
1. 海外で進む人的資本の情報開示
人的資本の情報開示を求める動きは、まず欧米で活発化しました。2018年には国際標準化機構(ISO)により、人的資本の情報開示ルールを整備した「ISO30414」が制定されます。2020年には米国証券取引委員会(SEC)が、アメリカ国内の上場企業に対し人的資本に関する情報開示の義務化を定めました。
EUでは、2023年にサステナビリティ開示に関する法令(CSRD)が改訂され、人的資本に関する領域が情報開示の対象として追加されています。
2. 情報開示を求める国内の動き
日本における人的資本の情報開示の動きは、2020年に経済産業省が「人材版伊藤レポート」を公表したことにより重要性が認識され、広がりをみせはじめました。2016年には、上場企業を対象とした企業統治のガイドラインである「コーポレート・ガバナンスコード」が改訂され、人的資本の情報開示に関する項目が追加されています。
2022年には「人的資本可視化指針」が内閣官房から発表され、開示が望ましいとされる経営情報について方針が示されました。さらに2023年には金融庁により、人的資本に関する情報の有価証券報告書への記載が、上場企業を対象に義務付けられています。
【2022年策定】人的資本可視化指針のポイント

ここでは、2022年8月に内閣官房より発表された「人的資源可視化指針」のポイントについて解説します。この指針では、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4要素に沿って開示することが効果的としています。
人的資本の可視化が必要とされる背景
この指針における「人的資源の可視化」とは、企業・経営者が自らの人的資本への投資状況や人材戦略を、投資家や資本市場に分かりやすく伝えることと定義しました。
人的資本の可視化が必要とされる背景には、多くの投資家が「サステナビリティ経営」を重視していることが挙げられます。持続可能な社会と、長期的な企業の利益拡大の両立には人的資本への投資が欠かせません。人的資源に対する取り組みは、すべてのステークホルダーで共有し相互理解を深める必要があると考えられているのです。
人的資本を可視化する方法
「人的資源可視化指針」では、人的資源の可視化は以下の4ステップでおこなうことが望ましいとされています。
- 可視化において企業・経営者に期待されることを理解する
- 人的資本への投資と競争力のつながりの明確化
- 4つの要素(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標)に沿った開示
- 開示事項の類型(独自性・比較可能性)に応じた個別事項の具体的な内容の検討
自社に求められることを理解し、人材への投資と競争力向上の関連性を明確にします。そのうえで、体系的に開示内容をまとめることが求められるのです。
人的資本経営を企業が実践するためのポイント

人的資本経営を実践するにあたって、まずは「人材版伊藤レポート」を参考にすることが望ましいでしょう。ここでは同レポートの概要と、取り上げられている実践ポイントを解説します。
人材版伊藤レポートから読み解く人材戦略の実践
「人材版伊藤レポート」とは、経済産業省が主催した「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」の成果としてまとめられた最終報告書の通称です。
2020年9月に公表されたこのレポートでは、これからの人材戦略において重要なものとして、「3つの視点」と「5つの共通要素」がまとめられています。日本国内において、人的資本の重要性が認識される「きっかけ」となったレポートといっても過言ではありません。
人材戦略に必要な3つの視点(3P)
人材版伊藤レポートでは、人材戦略に必要な3つの視点を以下のように挙げています。
- 経営戦略と人材戦略の連動
- AS is – To beギャップの定量把握
- 企業文化への定着
継続的に企業価値を向上させるには、経営戦略の実現に向けた人材戦略を整えることが求められます。経営戦略は短期的な利益だけを追求するのではなく、人材の価値を高めることにより長期的な企業成長が見込めるものでなくてはなりません。そのうえで、As is(理想)とTo be(現実)のギャップを数値化して把握し、アクションプランを策定します。アクションの実行・検証を通じて人材戦略を企業文化として定着させていくのです。
人材戦略に必要な5つの共通要素(5F)
さらに、人材版伊藤レポートでは、人材戦略に必要な共通要素として以下の5つを挙げています。
- 動的なポートフォリオ
- 知・経験のダイバーシティ&インクルーション
- リスキル・学び直し
- 従業員エンゲージメント
- 時間と場所にとらわれない働き方
人材構成を把握し状況に応じて調整することや、個人のスキルアップといった人材の活性化の重要性を挙げています。また多様化する働き方への対応や、従業員エンゲージメントが盛り込まれている点も特徴です。
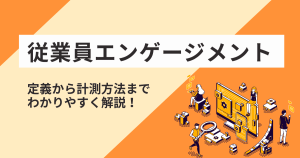
人的資本経営に企業が取り組むための3ステップ

企業が人的資本経営に取り組む際には、以下の3ステップで実行することが望ましいでしょう。
- 経営戦略に基づく人材戦略を策定する
- 課題の解決に向けた施策や目標を決める
- 施策を実行して効果を検証する
詳しく解説します。
1. 経営戦略に基づく人材戦略を策定する
人材版伊藤レポートにもある通り、経営戦略と人材戦略は密接に連動することが求められます。経営層が把握している自社の課題を、人事部門が共有することが欠かせません。
たとえばDX推進が自社の課題であれば、デジタル人材の確保・育成が人材戦略の基本になります。経営層と人事部門が連携を深めるためには、より経営に近い立場で人事施策を立案するCHRO(最高人事責任者)を登用することも有効です。
2. 課題の解決に向けた施策や目標を決める
次は経営課題解決に向けた具体的なアクションプランと、達成目標を決めるステップです。目指す姿・あるべき姿と、現実とのギャップを定量的に把握し、そのギャップを埋めるために「何をすべきか」必要な施策を策定します。
なお施策を考案する際には、進捗の指標となるKPIを設定することも必要です。KPIの設定は、数値化することが望ましいとされますが必須ではありません。「未来志向であるか」、「経営戦略との整合性は担保されているか」、「自社の独自性が打ち出せているか」に着目するとよいでしょう。
3. 施策を実行して効果を検証する
施策の実行と効果を検証するステップです。実行する際には、PDCAサイクルを意識した定期的なモニタリングが欠かせません。社内の変化や、目標の達成度を可視化するためには、人事データの活用が有効です。システムを導入しデータを収集することにより、定量的な把握が可能です。次の施策にも活かしやすくなるでしょう。
また、従業員エンゲージメントなど可視化・定量化しにくい要素については、各種サーベイを用いることも有効です。いずれにせよ、客観的な指標としての判断材料を揃えることで、施策の精度を向上させることが大切です。
従業員エンゲージメント向上に ourly
ourlyは、組織の意識改善を支援するweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能があり、施策の効果測定が可能になります。
またourlyは、単なるツールにとどまらず、専門の組織コンサルタントが運用をサポートし、ゴール設定、現状把握、行動計画、改善提案など一気通貫で支援を行います。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「社内広報施策の効果測定ができない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
人的資本経営に関する情報開示や可視化の動きに注目を
投資家をはじめとしたステークホルダーにとって、企業の人材に対する姿勢や取り組みは大きな関心事となっています。これからの企業運営では、人的資本に関する情報開示や可視化の動きを注視していくことが欠かせません。自社の人材価値を高めることが、企業価値を高めることに直結するのです。
人的資本への投資は、自社の従業員を大切にすることにつながります。積極的な取り組みを実行し、自社の従業員に周知することは、エンゲージメント向上にも有効な施策となるでしょう。