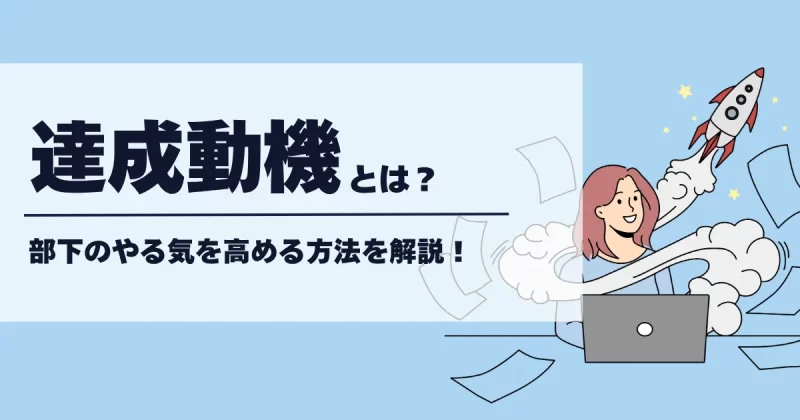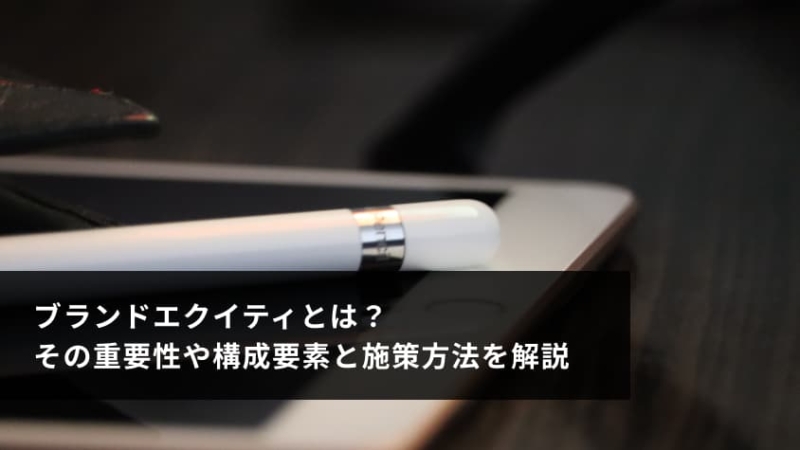「部下のモチベーションが上がらない」「どうすれば主体的に動いてくれるだろうか」と悩む管理職やリーダーの方は多いのではないでしょうか。その鍵を握るのが、心理学の概念である「達成動機」です。
達成動機を正しく理解し、部下の育成に活かすことで、個人の成長を促し、チーム全体のパフォーマンスを向上させることができます。
本記事では、達成動機の基本的な意味から、具体的な高め方、人材育成への活用方法までを分かりやすく解説します。
達成動機とは何か?
達成動機とは、単に「やる気」といった言葉で片付けられるものではなく、人の行動や成果に深く関わる心理的な要因です。まずは、その基本的な定義と、現代のビジネスシーンでなぜ重要視されているのかについて解説します。
達成動機の基本的な定義
達成動機とは、「もっと良い成果を出したい」「自分の力を試したい」と思って行動する上でのモチベーションのことを指します。
人がどのくらい意欲的に行動できるかは、目標を達成できるという期待、成果を出したときの喜びや報酬、そして職場の雰囲気や評価のあり方などによって変わります。
この概念は、アメリカの心理学者デイビッド・マクレランドらによって研究が進められ、社会や組織の発展にも影響を与える重要な要素とされています。
なぜ今、達成動機が注目されるのか
現代のビジネス環境は、変化が激しく、将来の予測が困難な時代です。このような状況下では、指示を待つだけでなく、社員一人ひとりが自律的に課題を発見し、解決に向けて行動することが求められます。
達成動機が高い人材は、困難な状況でも主体的に目標を掲げ、粘り強く取り組むことができるため、組織のイノベーションや生産性向上に不可欠な存在です。
そのため、人材育成や組織開発の文脈で、社員の達成動機をいかに引き出し、高めていくかという点に注目が集まっています。
| 時代背景 | 求められる人材像 | 達成動機の重要性 |
| 高度経済成長期 | 指示に忠実に従い、効率的に業務をこなす人材 | 決められた目標を確実にこなす上で重要 |
| 現代(VUCA時代) | 自律的に課題を発見し、主体的に行動・挑戦する人材 | 予測困難な状況で新たな価値を創造するために不可欠 |
達成動機理論の全体像
達成動機の強さは、人によって異なります。なぜ個人差が生まれるのでしょうか。そのメカニズムを説明するのが、心理学者ジョン・アトキンソンが提唱した「達成動機理論」です。
アトキンソンが提唱した理論モデル
アトキンソンは、人の達成に関する行動は、2つの相反する動機の結果であると考えました。
それは、目標を達成して成功したいと願う「成功追求動機」と、目標達成に失敗することを避けたいと願う「失敗回避動機」です。人の行動は、この2つの動機のどちらがより強いかによって決定されると説明されました。
つまり、達成への意欲は、成功への期待と失敗への不安という、2つの感情のせめぎ合いの中で生まれるのです。
「成功追求動機」と「失敗回避動機」
「成功追求動機」が強い人は、成功すること自体に喜びや価値を見出し、挑戦的な課題を好む傾向があります。彼らにとって、目標達成は自身の能力を証明し、成長を実感する機会となります。
一方、「失敗回避動機」が強い人は、失敗によって自分の評価が下がったり、周囲に迷惑をかけたりすることを避けたいという気持ちが強く働きます。そのため、確実に成功できる簡単な課題か、あるいは到底達成できそうにない非常に困難な課題を選ぶ傾向があります。
これは、失敗による心理的負担を軽減し、自分や他者との関係を守るための自然な戦略ともいえます。
どちらの傾向も、人が状況に適応しようとする異なる形の動機づけであり、重要なのはどちらが強いかではなく、そのバランスと使い分け方です。
達成動機と関連の深い動機づけのメカニズム
達成動機は、より広い「動機づけ(モチベーション)」の枠組みの中で理解することが重要です。特に、「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」との関係性を知ることで、より効果的なアプローチが可能になります。
内発的動機づけとの関係
内発的動機づけとは、報酬や評価といった外的な要因ではなく、物事そのものへの好奇心や探求心、達成感といった内的な要因によって行動が促される状態を指します。達成動機は、この内発的動機づけと非常に密接な関係にあります。
「より高いレベルで物事を成し遂げたい」という欲求は、まさに内側から湧き出るエネルギーであり、達成動機が高い人は、課題をクリアすること自体に喜びを感じるため、内発的に動機づけられている状態にあると言えます。
外発的動機づけとの違い
外発的動機づけは、昇給や昇進、あるいは罰則といった外的な要因によって行動が促される状態です。例えば、「ボーナスのために頑張る」というのが典型的な例です。
外発的動機づけは、即効性があり、行動を促す上で有効な手段です。しかし、外的な報酬がなくなるとモチベーションが低下しやすく、持続性に欠けるという側面も持ち合わせています。
達成動機を長期的に高めていくためには、外発的動機付けだけに頼るのではなく、仕事そのものの面白さや成長実感といった内発的動機付けをいかに刺激するかが重要になります。
| 動機付けの種類 | 原動力 | 具体例 | メリット | デメリット |
| 内発的動機づけ | 内的な興味、関心、達成感 | 仕事の面白さ、自己成長、探求心 | 持続性が高い、創造性が発揮されやすい | 意図的に持たせることが難しい |
| 外発的動機づけ | 外的な報酬、罰則、評価 | 昇給、ボーナス、称賛、懲罰 | 即効性がある、行動を誘導しやすい | 報酬がないと続かない、自主性が育ちにくい |
達成動機を人材育成に活用する方法
部下の達成動機を高めるためには、一人ひとりの動機のタイプを理解し、それに合わせたアプローチをとることが極めて重要です。画一的な目標設定や関わり方では、かえってモチベーションを下げてしまう可能性もあります。
部下の動機のタイプを見極める
まずは、日々の言動や業務への取り組み方から、部下が「成功追求動機」と「失敗回避動機」のどちらが強いタイプなのかを見極めることが第一歩です。
1on1ミーティングや、社内プロフィールなどで、過去の成功体験や失敗体験について「その時どう感じたか」「原因は何だったと思うか」といった内容をシェアし、その人の思考の傾向が見ます。
例えば、失敗を「良い経験だった」と前向きに捉えるか、「自分の能力不足だった」と落ち込むかで、タイプを推測することができます。
| 動機タイプ | 効果的な目標設定 | コミュニケーションのポイント |
| 成功追求動機が強い | 成功確率50%程度の挑戦的な目標 | 裁量権を与え、プロセスよりも結果を評価し称賛する |
| 失敗回避動機が強い | 成功確率が高い、スモールステップでの目標 | 失敗を許容し、具体的なプロセスを一緒に考え支援する |
成功追求動機が強い部下へのアプローチ
成功追求動機が強い部下には、ある程度難易度の高い、挑戦的な目標を設定させることが効果的です。成功確率が五分五分くらいの「ストレッチ目標」を与えることで、彼らの「達成したい」という意欲を最大限に引き出すことができます。
また、業務を任せる際には、細かく指示を出すよりも、裁量権を与えて本人の創意工夫を促す方が良いでしょう。そして、目標を達成した際には、その成果を具体的に称賛し、さらなる挑戦への意欲を掻き立てることが重要です。
失敗回避動機が強い部下へのアプローチ
失敗回避動機が強い部下に対して、いきなり高い目標を設定するのは逆効果です。まずは、本人のスキルや経験で確実に達成できるような、成功体験を積ませることから始めましょう。
小さな成功を繰り返すことで、「自分にもできる」という自己効力感を育むことが大切です。
また、失敗した際には、本人を責めるのではなく、「失敗は成長の糧である」というメッセージを伝え、具体的な改善策を一緒に考える姿勢を示しましょう。失敗に対する不安を和らげ、徐々に挑戦へのハードルを下げていくことがポイントです。
達成動機を組織全体で高めるためのポイント
個人の達成動機は、その人の特性だけでなく、所属する組織の文化や風土にも大きく影響されます。社員の達成動機を引き出し、組織全体の活力を高めるためには、仕組みや環境づくりが不可欠です。
適切な目標設定を促す文化の醸成
組織として、挑戦を奨励する目標設定のフレームワークを導入することが有効です。例えば、OKR(Objectives and Key Results)のように、達成が困難な高い目標(Objectives)を掲げ、その達成度を測る具体的な指標(Key Results)を設定する手法は、社員の挑戦意欲を引き出す助けとなります。
重要なのは、目標達成度合いが直接的な人事評価に結びつきすぎないように設計することです。そうすることで、社員は失敗を恐れずに高い目標に挑戦しやすくなります。
挑戦を称賛し、失敗を許容する風土
社員が安心して新しいことに挑戦するためには、結果の成否に関わらず、その挑戦する姿勢自体を評価し、称賛する文化が欠かせません。
たとえ失敗に終わったとしても、そこから得られた学びや経験を組織の資産として共有し、次に活かす仕組みがあれば、失敗は単なる「負け」ではなく「貴重なデータ」に変わります。
経営層や管理職が率先して自らの失敗談を語るなど、組織全体で失敗に対してオープンな姿勢を示すことが重要です。
仕事への意味づけと納得感のある目標設定
社員の達成動機を高めるためには、本人が「この仕事は意味がある」と実感できること、そして「この目標なら自分にもできる」と納得していることの二つが欠かせません。
まず上司が「あなたの仕事は会社のこの部分を支えている」と具体的に伝え、仕事の価値や意義を本人に気づかせることが出発点となります。
次に、目標を一方的に押し付けるのではなく、本人と対話を重ねながら設定することで、目標への当事者意識が生まれます。
このように「意味のある仕事」と「納得できる目標」が両立したとき、社員は自発的に行動し、最大限の成果を発揮できるのです。
具体的なフィードバックの重要性
達成動機を高める上では、客観的で具体的なフィードバックが不可欠です。
単に「良かった」「悪かった」と伝えるだけでなく、「〇〇という行動が、こういう結果につながった」「次は△△を試してみてはどうだろうか」というように、具体的な行動レベルでフィードバックを行うことで、本人は次に何をすべきかを明確に理解できます。
ポジティブなフィードバックは自信を育み、改善点を指摘するフィードバックは成長への道筋を示します。定期的な1on1などを通じて、質の高いフィードバックの機会を設けることが、社員の成長と動機向上につながります。
達成動機が高まる組織文化をつくるweb社内報「ourly」
ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
ourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援と詳細な分析、洗練されたコンテンツ配信から、効率的な理念浸透や文化醸成を実現します。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」「理念浸透・文化醸成を通して組織改善したい」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
まとめ
本記事では、達成動機の基本的な概念から、その理論的背景、そして人材育成や組織開発への具体的な活用方法について解説しました。
達成動機は、個人の成長と組織の発展を支える重要なエンジンです。部下一人ひとりの動機の源泉を理解し、挑戦を後押しする環境を整えることで、組織全体の活力を高めていきましょう。