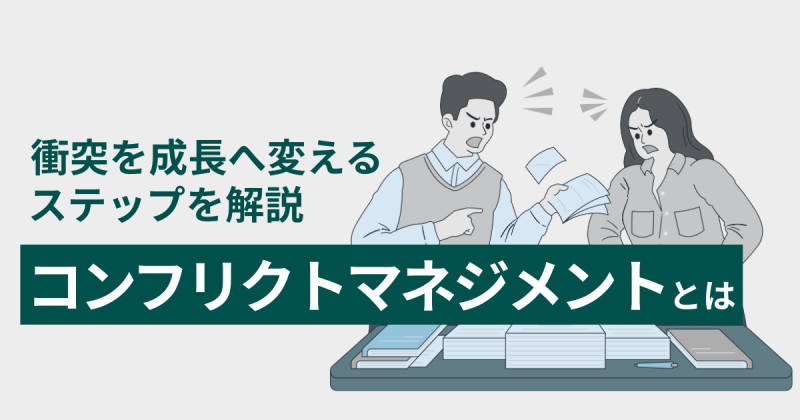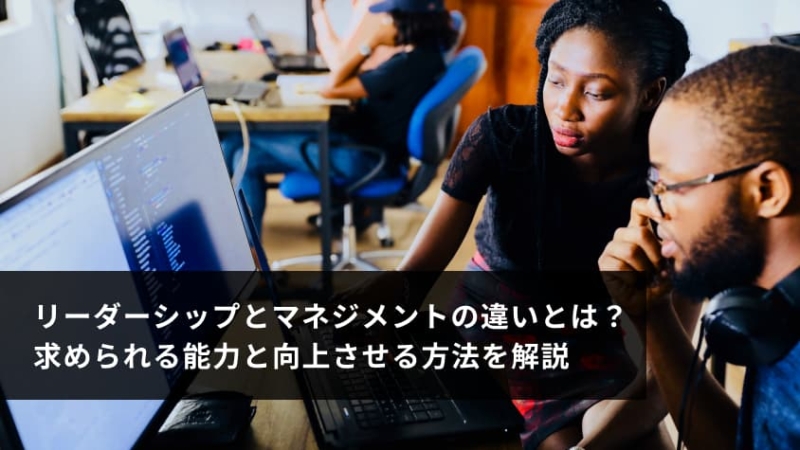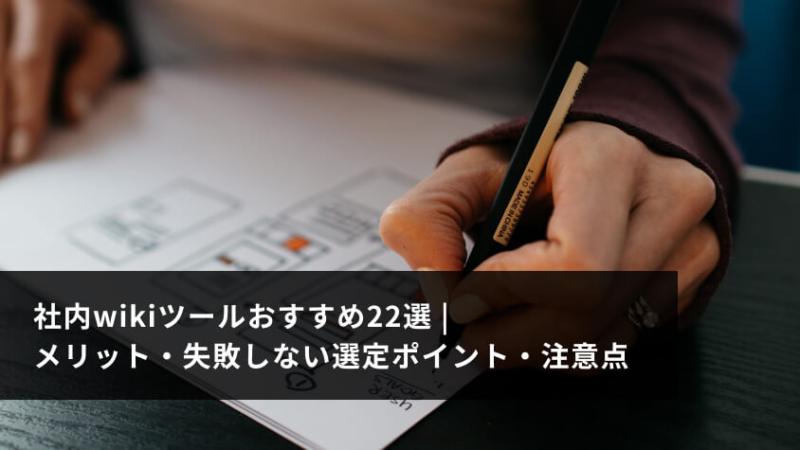組織に人が集まれば、意見の対立や価値観の衝突は避けて通れません。このような「コンフリクト」をネガティブなものとして放置するのではなく、組織成長の糧として活かす考え方が「コンフリクトマネジメント」です。
本記事では、コンフリクトマネジメントの基本的な知識から、具体的な実践手順、成功事例までを分かりやすく解説します。
コンフリクトマネジメントとは組織の成長に不可欠なスキル
コンフリクトマネジメントとは、組織内で発生する対立や衝突を建設的に解決し、むしろ組織や個人の成長につなげるためのマネジメント手法です。
対立を単なる問題として捉えるのではなく、より良い解決策や新しいアイデアを生み出すための機会として積極的に関与していく点が特徴です。
コンフリクト(対立)は一概に悪いものではない
「コンフリクト(対立)」と聞くと、人間関係の悪化や生産性の低下など、ネガティブなイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし、健全な対立は、組織に新たな視点や気づきをもたらします。
異なる意見がぶつかり合うことで、これまで見過ごされてきた問題点が明らかになったり、議論を通じて従業員間の相互理解が深まったりすることもあります。重要なのは、対立そのものをなくすことではなく、対立を建設的な結果に導くことです。
なぜ今コンフリクトマネジメントが重要なのか
近年、働き方の多様化やグローバル化が進み、一つの組織に様々な価値観やバックグラウンドを持つ人材が集まるようになりました。このような環境では、意見の相違や対立が発生するのは当然のことと言えます。
コンフリクトマネジメントを適切に行うことで、多様な人材がそれぞれの意見を表明しやすい風通しの良い職場環境が生まれ、多様性を組織の強さに変えることができます。
コンフリクトが発生する3つの主な原因
コンフリクトは、その原因によっていくつかの種類に分類できます。原因を正しく理解することが、適切な解決への第一歩となります。
目標や役割の違いから生じる「条件の対立」
これは、立場や役割の違いによって発生する対立です。例えば、「売上を最大化したい営業部門」と「コストを最小限に抑えたい製造部門」のように、それぞれの部門が持つ目標や条件が異なるために生じます。
これは業務上、避けがたい対立であり、比較的解決しやすいものとされています。
考え方や価値観の違いから生じる「認知の対立」
同じ事象であっても、人それぞれの経験や価値観によって解釈が異なることから生じる対立です。例えば、伝統を重んじる考え方と、革新を求める考え方の衝突などがこれにあたります。
個人の深い部分に根差しているため、解決には相互理解の努力が必要となります。
個人的な感情のもつれから生じる「感情の対立」
好き嫌いや、優越感・劣等感といった個人的な感情が原因で発生する対立です。上記の「条件の対立」や「認知の対立」が解決されないまま続くと、この「感情の対立」に発展しやすくなります。
一度感情的な対立になると、問題が複雑化し、解決が非常に困難になる傾向があります。
コンフリクトを放置するデメリット
コンフリクトを適切にマネジメントせず放置してしまうと、組織に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
従業員のメンタルヘルス悪化とエンゲージメント低下
対立が続く職場環境は、従業員にとって大きな精神的ストレスとなります。これによりメンタルヘルスが悪化し、仕事へのモチベーションや組織への帰属意識(エンゲージメント)が著しく低下する恐れがあります。
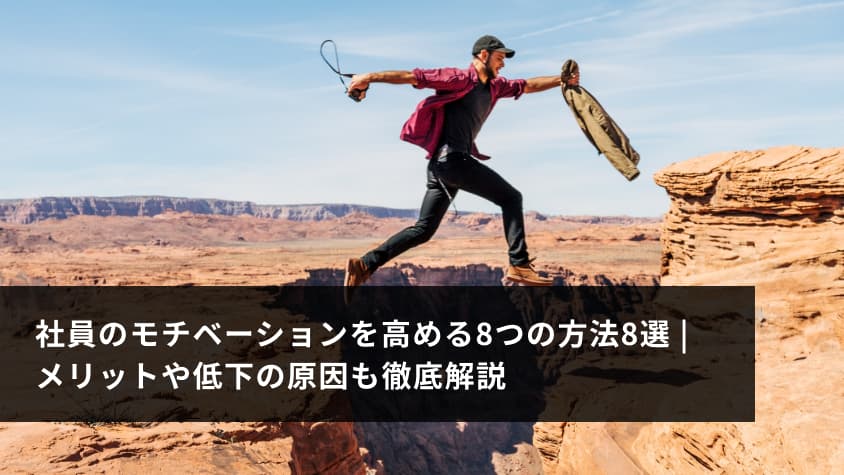
チームの生産性低下と意思決定の遅延
部門間や個人間の対立は、円滑なコミュニケーションを阻害し、情報共有や協力体制の構築を困難にします。その結果、業務に支障が出てチーム全体の生産性が低下するだけでなく、重要な意思決定が遅れる原因にもなります。
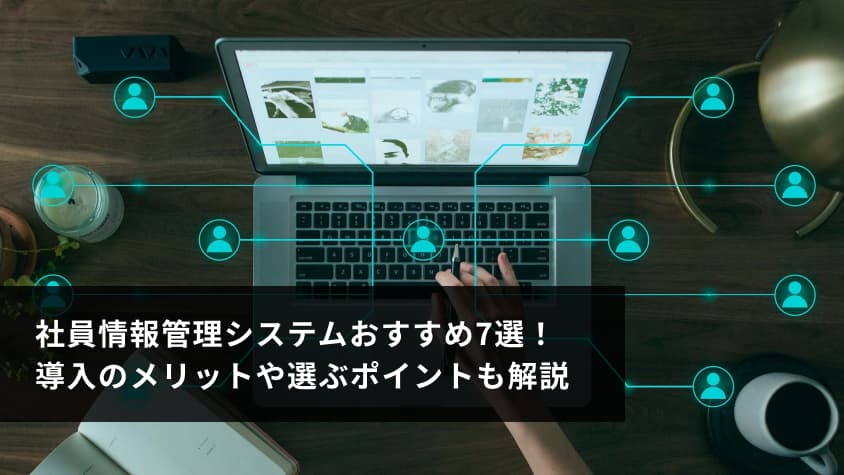
離職率の増加と組織イメージの悪化
居心地の悪い職場環境は、優秀な人材の流出につながります。離職率の増加は、採用コストや教育コストの増大を招くだけでなく、「働きにくい会社」という評判が広がり、企業のブランドイメージを損なうことにもなりかねません。
コンフリクトマネジメントがもたらすメリット
一方で、コンフリクトにうまく対処することができれば、組織は多くのメリットを享受できます。
新たなアイデアやイノベーション創出
異なる意見や視点がぶつかり合うことは、新たな発想を生む土壌となります。活発な議論を通じて、既存の枠組みにとらわれない画期的なアイデアやイノベーションが創出される可能性が高まります。
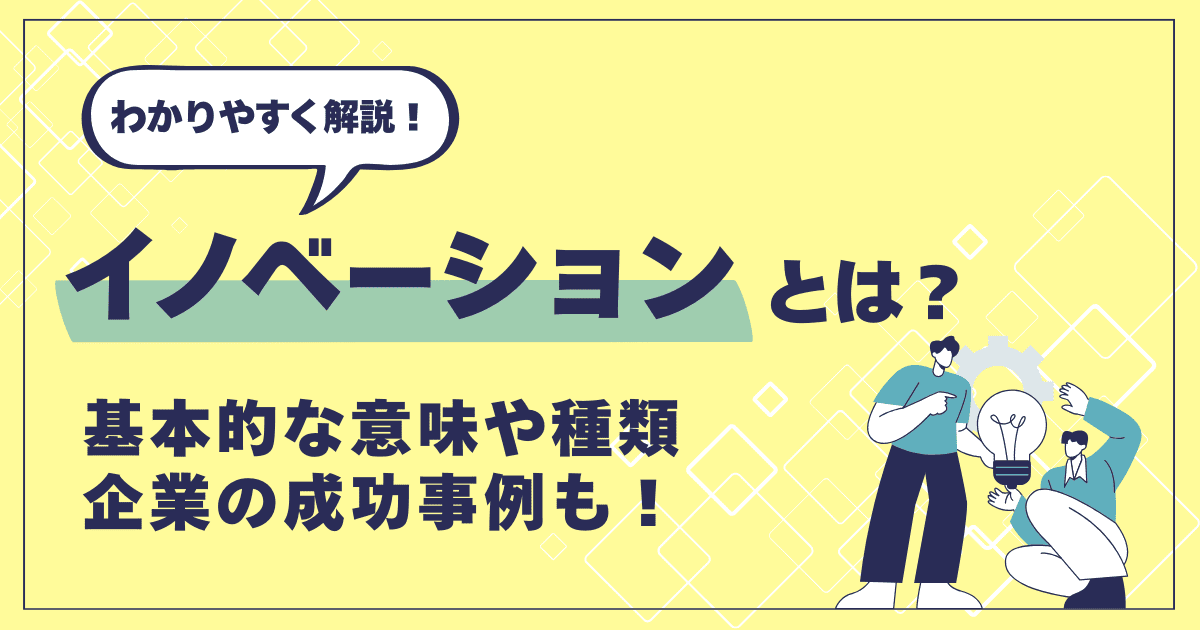
従業員間の相互理解と信頼関係の構築
対立を乗り越える過程で、従業員は互いの考え方や価値観を深く理解することができます。課題解決に向けて協力し合う経験は、強固な信頼関係を築き、チームの結束力を高めることにつながります。
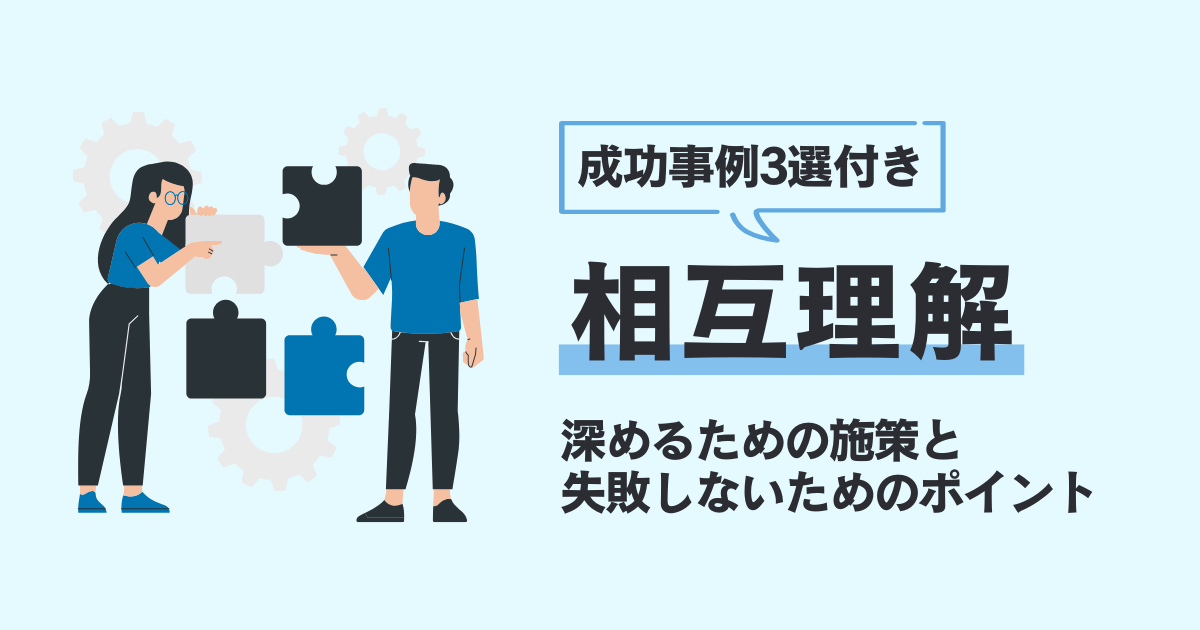
組織全体の課題解決能力の向上
コンフリクトマネジメントを組織全体で実践することで、対立を前向きに捉え、建設的に解決しようとする文化が醸成されます。これにより、組織全体の課題解決能力が向上し、変化に強いしなやかな組織を構築できます。
対立における5つの代表的な対応方法
心理学者ケネス・トーマスとラルフ・キルマンが提唱したモデルによると、対立した際の人の対応は、自己主張の度合いと協調性の度合いによって5つのスタイルに分類されます。状況に応じて最適なスタイルを選択することが重要です。
| 対応方法 | 自己主張 | 協調性 | 特徴 | 適した状況 |
| 競争(Compromising) | 高 | 低 | 自分の意見を押し通し、相手に勝利することを重視します。 | 緊急性が高く、迅速な意思決定が必要な場合。 |
| 協調(Collaborating) | 高 | 高 | 双方の意見を尊重し、Win-Winの関係を目指します。 | 問題が重要で、双方のコミットメントが必要な場合。 |
| 妥協(Compromising) | 中 | 中 | 互いに譲歩し、部分的な満足で合意点を見つけます。 | 複雑な問題で、一時的な解決策が必要な場合。 |
| 回避(Avoiding) | 低 | 低 | 対立そのものに関わることを避け、問題を先送りにします。 | 問題が些細であるか、より重要な問題がある場合。 |
| 順応(Accommodating) | 低 | 高 | 自分の意見を抑え、相手の意見を受け入れます。 | 自分よりも相手にとって問題が重要である場合。 |
競争:自分の意見を押し通す
自己の利益を最優先し、相手を説得または強制してでも自分の主張を通そうとするスタイルです。緊急の決断が求められる場面では有効ですが、多用すると相手との関係性を損なうリスクがあります。
協調:互いの利益を最大化する
対立する両者の意見を統合し、お互いが完全に満足できる解決策(Win-Win)を模索するスタイルです。最も理想的な形ですが、時間と労力がかかります。
妥協:互いに譲歩し中間点を探る
双方が少しずつ譲り合い、「Win-Lose」でも「Lose-Win」でもない中間的な着地点を見つけるスタイルです。迅速な解決が可能ですが、根本的な問題解決には至らない場合もあります。
回避:対立から距離を置く
対立状況から物理的・心理的に距離を置き、問題への関与を避けるスタイルです。時間が解決してくれる場合や、冷静になる時間が必要な場合には有効ですが、問題の先送りに過ぎないことも多いです。
順応:相手の意見を受け入れる
自分の意見や要求を取り下げ、相手の主張を全面的に受け入れるスタイルです。関係性の維持を最優先したい場合などに選択されますが、自己犠牲が続くことで不満が溜まる可能性があります。
コンフリクトマネジメントを成功させる6つの実践手順
実際にコンフリクトが発生した際、どのように対処すればよいのでしょうか。ここでは、基本的な6つの手順を紹介します。
手順1:対立の原因を客観的に分析する
まずは感情的にならず、「何が問題なのか」「なぜ対立しているのか」を客観的に分析します。当事者の立場、関係性、対立の原因(条件・認知・感情)などを冷静に整理することが重要です。
手順2:対話のための安全な場を設定する
当事者同士が安心して話せる環境を整えます。第三者が介入する場合は中立的な立場を保ち、誰かが一方的に攻撃されたり、非難されたりすることのないよう、明確な対話のルール(例:相手の話を遮らない、人格攻撃はしない)を設定します。
手順3:それぞれの意見や感情を表明し共有する
各当事者に、事実だけでなく、その背景にある考えや感情についても表明してもらいます。このとき、相手の意見を否定せず、まずは「そう考えているのですね」と受け止める姿勢が、相互理解の第一歩となります。
手順4:すべての当事者の利益となる解決策を探す
対立点を明確にした上で、「この状況で、お互いにとって最も良い結果は何か」という共通のゴールを探ります。ブレインストーミングなどを用いて、できるだけ多くの解決策の選択肢を出し合います。
手順5:合意形成を行い具体的な行動計画を立てる
出し合った選択肢の中から、双方が最も納得できる解決策を選び、合意を形成します。そして、「誰が」「いつまでに」「何をするのか」という具体的な行動計画に落とし込みます。
手順6:決定事項を実行し状況を評価する
合意した行動計画を実行に移します。実行後も、問題が本当に解決したか、新たな問題が発生していないかを定期的に確認し、必要に応じて再度話し合いの場を持つことが大切です。
コンフリクトマネジメントで求められる重要なスキル
コンフリクトマネジメントを効果的に行うためには、いくつかのスキルが必要となります。
相手の話を正確に理解する傾聴力
相手の意見やその裏にある感情、価値観を正確に理解する能力です。ただ話を聞くだけでなく、相槌や質問を交えながら、相手が本当に伝えたいことを深く引き出すことが求められます。
自分の意見を適切に伝えるアサーションスキル
相手を尊重しつつ、自分の意見や感情を正直に、しかし攻撃的にならずに伝えるスキルです。感情的な反発を招くことなく、建設的な対話を進めるために不可欠です。
論理的に問題を整理し解決に導く分析的思考力
複雑に絡み合った問題の構造を理解し、原因と結果を論理的に整理する能力です。感情的な対立の裏にある本質的な課題を見抜き、効果的な解決策を導き出すために役立ちます。
コンフリクトマネジメントの企業事例
コンフリクトマネジメントは、実際のビジネス現場でどのように活用されているのでしょうか。
日本航空におけるJALフィロソフィを通じた組織統合
日本航空(JAL)は2010年の経営破綻後、JALフィロソフィの導入により組織の再統合を実現しています。同社が策定したJALフィロソフィは「すばらしい人生を送るために」と「すばらしいJALとなるために」の二部構成で、全社員が共有すべき価値観と考え方を示しました。
特に「本音でぶつかれ」「ベクトルを合わせる」「心をひとつにする」といった原則を通じて、社員間の意見の対立を建設的に解決し、組織の一体化を図っています。フィロソフィ導入により全社員の意識改革が進み、翌期には営業利益1,884億円を計上する世界最高収益の航空会社へと転身を遂げました。
参考:https://www.jal.com/ja/philosophy-vision/conduct
パナソニックにおける「MAKE HAPPYプロジェクト」の組織風土改革
パナソニック インダストリーでは、2018年から「MAKE HAPPYプロジェクト」を推進し、社員の幸福感向上を通じた組織風土改革に取り組んでいます。同プロジェクトは「学び(はぴ学®)」「関係性構築(はぴ会®)」「健康促進(はぴ楽)」「自分らしさの実現(はぴ色)」の4つの活動を柱としており、年間20回以上のイベントを開催し延べ3万3000人が参加しています。
特に「はぴ会®」では経営幹部と社員の対話を通じて相互理解を深め、組織内の摩擦を未然に防ぐ仕組みを構築しました。この取り組みにより従業員エンゲージメント指標(eNPS®値)が36ポイント向上し、「HRテクノロジー大賞 人事マネジメント部門 優秀賞」を受賞するなど、組織一体感の醸成に成功しています。
参考:https://www.panasonic.com/jp/industry/csr/cultural-change.html
まとめ
コンフリクトマネジメントは、単なる対立解消のテクニックではありません。多様な人材が集まる現代の組織において、対立を恐れず、それを成長のエネルギーに変えていくための重要な経営スキルです。この記事で紹介した考え方や手順を参考に、組織内の健全なコミュニケーションを促進し、より強くしなやかな組織作りを目指してください。