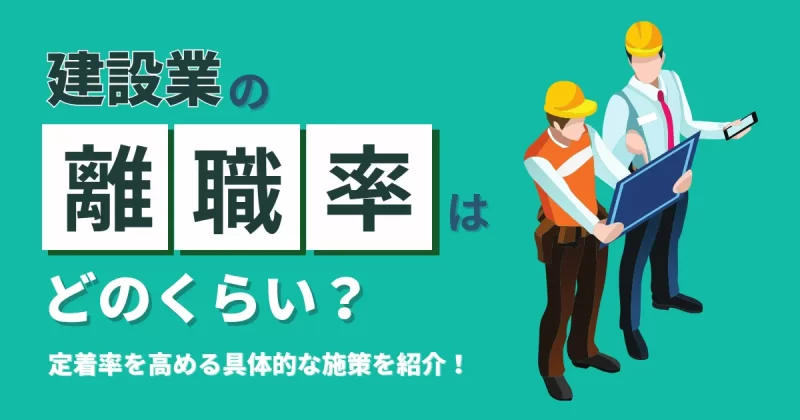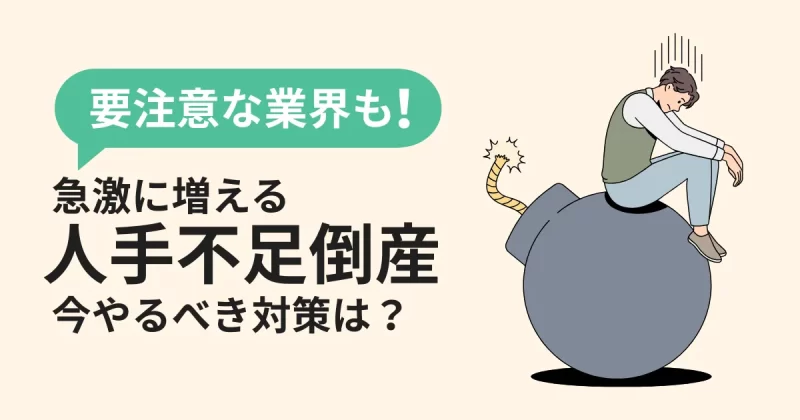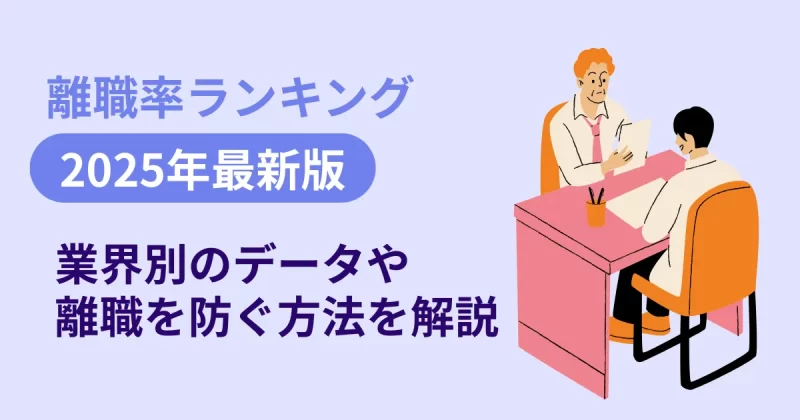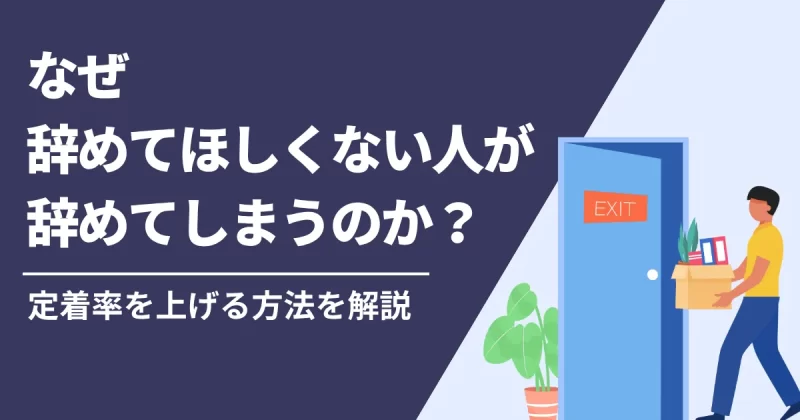「最近、若手社員がすぐに辞めてしまう」「人手不足がなかなか解消されない」といった悩みを抱える建設業の人事担当者様や経営者様は多いのではないでしょうか。
建設業界は、その専門性や社会貢献度の高さから非常に魅力的な産業ですが、一方で「離職率の高さ」が長年の課題とされています。
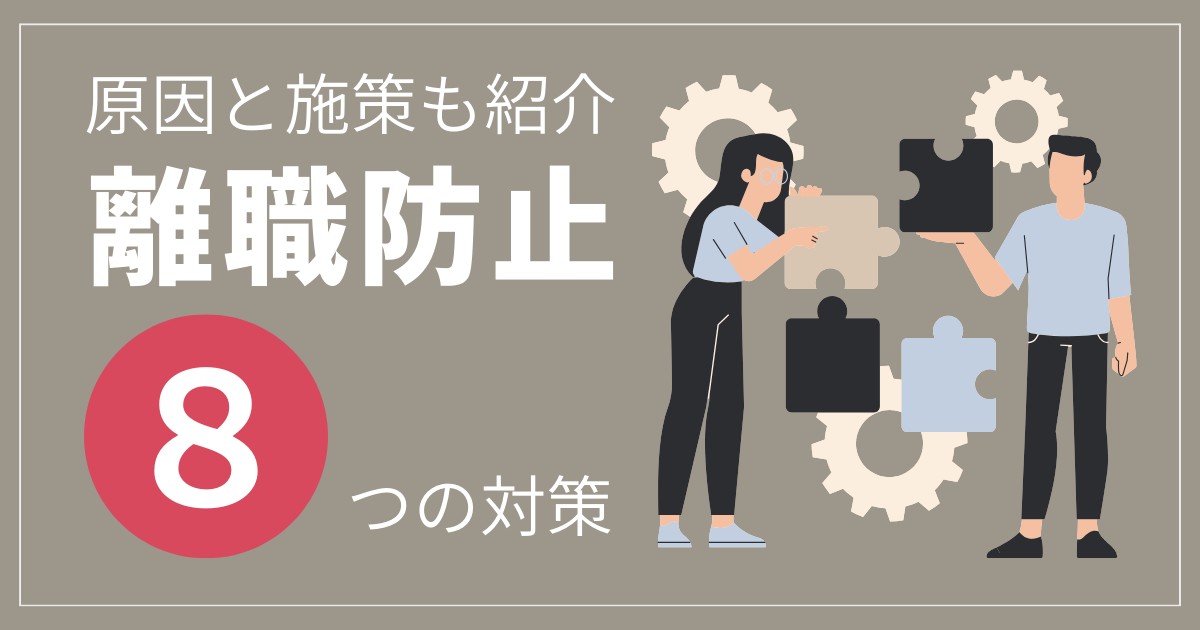
この記事では、建設業の離職率の現状をデータに基づいて解説し、離職の背景にある原因を深掘りします。その上で、人材の定着率を高めるための具体的な改善策を、成功事例を交えながら分かりやすく紹介します。
建設業の離職率の現状
建設業の離職率は高い、というイメージを持たれがちですが、実際のデータを見ると、産業全体の中では比較的低い水準にあります。しかし、新卒者の早期離職や入職者数を上回る離職者数など、構造的な課題を抱えているのも事実です。
他の産業と比較した離職率
厚生労働省が発表した「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、2023年の建設業の離職率は10.1%でした。これは、産業全体の平均離職率である15.4%を大きく下回る数値です。
例えば、「宿泊業、飲食サービス業」の26.6%や「生活関連サービス業、娯楽業」の 28.1%と比較すると、建設業の離職率は決して高くはないことが分かります。
しかし、注目すべきは入職率と離職率の関係です。
同調査では、建設業の入職率が10.0%であるのに対し、離職率は10.1%と、離職者が入職者をわずかに上回る「離職超過」の状態にあります(入職超過率-0.1ポイント)。
この点が、建設業界における人手不足の深刻さを示唆しています。
| 産業 | 離職率 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 26.6% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 28.1% |
| 産業計 | 15.4% |
| 医療、福祉 | 14.6% |
| 建設業 | 10.1% |
新規学卒者の離職率の傾向
全体的な離職率は低い一方で、若年層、特に新規学卒者の早期離職率は高い傾向にあります。厚生労働省のデータ(令和3年3月卒業者)によると、建設業に就職した新規高卒者の3年以内離職率は43.2%にのぼり、産業全体の38.4%を上回っています。
新規大卒者の場合は30.7%と、産業全体の34.9%よりは低いものの、約3割が3年以内に離職している状況です。このように、将来を担う若手人材が定着しにくいことが、建設業界の大きな課題となっています。
参考:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します|厚生労働省
建設業で離職率が高くなる主な原因
では、なぜ建設業では離職者が後を絶たないのでしょうか。その背景には、業界特有の労働環境や構造的な問題が複雑に絡み合っています。
長時間労働と休日の少なさ
建設業における離職の最も大きな要因の一つが、長時間労働と休日の少なさです。工期遵守が最優先される現場では、天候不順や予期せぬトラブルによる遅れを取り戻すために、残業や休日出勤が常態化しやすくなります。
国土交通省の調査でも、週休二日制を導入できていない企業が多いことが指摘されており、ワークライフバランスの確保が難しい状況が離職につながっています。
参考:建設産業・不動産業:建設業:令和5年度調査「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」の結果を公表 – 国土交通省
身体的な負担と安全への懸念
建設現場での作業は、夏場の猛暑や冬の厳寒の中での肉体労働を伴い、身体的な負担が非常に大きいのが実情です。また、高所作業や重機の操作など、常に危険と隣り合わせの環境であることから、安全面への不安を感じる人も少なくありません。
こうした過酷な労働環境が、特に若手従業員の離職理由となるケースが多く見られます。
給与・評価制度への不満
「労働に対して賃金が低い」と感じることや、評価制度の不透明さも離職の要因です。現場では年功序列の風潮が根強く残っている場合があり、若手が成果を上げても正当に評価されず、昇給や昇進の基準が不明確であることも少なくありません。
自身の成長や貢献が待遇に反映されないと感じると、仕事へのモチベーションが低下し、転職を考えるきっかけとなります。
| 企業が考える離職理由 | 離職した若者の本当の理由 |
| 作業がきつい | 雇用が不安定である |
| (若者の)職業意識が低い | 遠方の作業場が多い |
| 人間関係が難しい | 休みが取りづらい |
| 賃金が低い | 労働に対して賃金が低い |
| 休みが取りづらい | 作業に危険が伴う |
出典:建設業の働き方として目指していくべき方向性(参考資料)|国土交通省
人間関係とコミュニケーションの課題
建設現場は、様々な専門業者や職人が集まる特殊な環境であり、円滑な人間関係を築くのが難しい側面があります。特に、経験豊富なベテラン層と若手との間に価値観のギャップが生じやすく、厳しい指導やコミュニケーション不足から若手が孤立感を深めてしまうケースが見られます。
悩みを相談できる相手がいないまま、精神的な負担を抱え込んで離職に至ることも少なくありません。

キャリアパスの不透明さ
「この会社で働き続けて、将来どうなれるのか」というキャリアパスが見えにくいことも、若手の離職につながる一因です。スキルアップのための具体的な研修制度がなかったり、資格取得支援が不十分だったりすると、自身の将来像を描くことが難しくなります。
成長を実感できず、将来に不安を感じた結果、より良いキャリアを求めて他社へ移ってしまうのです。
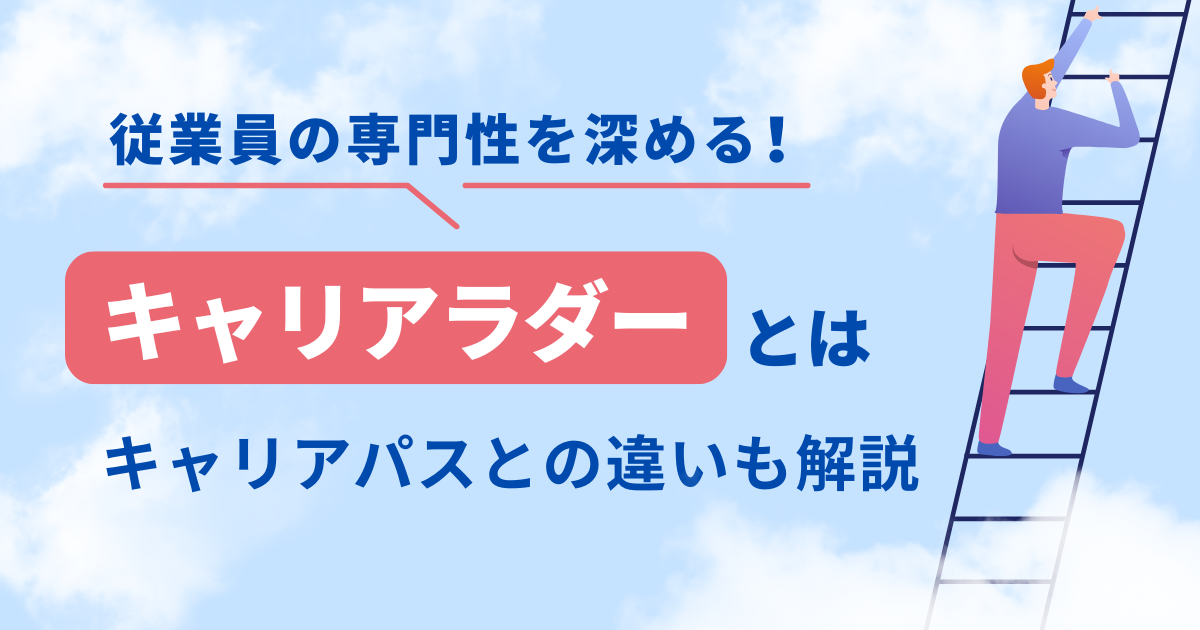
離職率が高いことによる企業へのデメリット
従業員の離職は、単に人員が一人減るというだけでなく、企業経営に様々な悪影響を及ぼします。離職率の高さを放置することは、企業の成長を阻害する大きなリスクとなります。
人材不足による生産性の低下
離職によって従業員が減少すれば、当然ながら一人当たりの業務負担が増加します。これにより、残された従業員の長時間労働がさらに深刻化し、心身の疲労から業務の質や生産性が低下する悪循環に陥ります。
最悪の場合、人手不足が原因で受注機会を逃したり、工期遅延を招いたりするなど、事業そのものに支障をきたす恐れがあります。
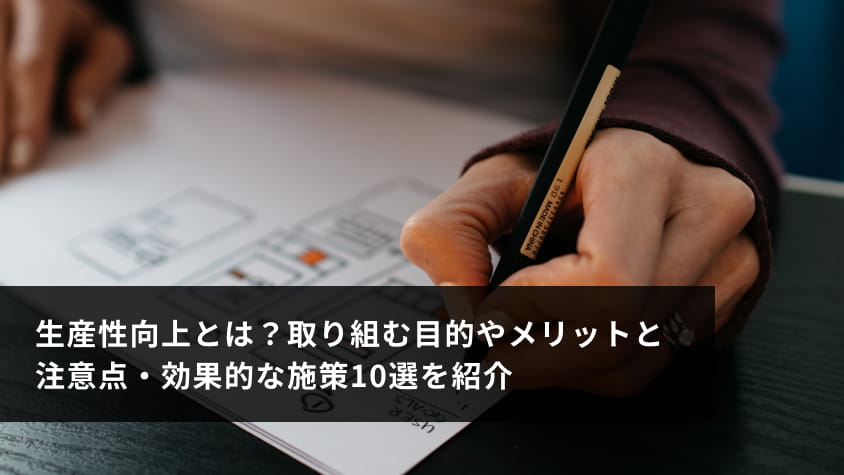
採用・教育コストの増大
一人の従業員が離職すると、その穴を埋めるために新たな人材を採用しなければなりません。求人広告費や人材紹介会社への手数料といった採用コストに加え、新入社員を一人前に育てるための教育コストも発生します。
従業員が定着せずに離職と採用を繰り返していると、これらのコストが経営を圧迫する大きな要因となります。
技術継承の断絶リスク
建設業は、長年の経験によって培われる専門的な技術やノウハウが非常に重要な産業です。特に経験豊富な中堅・ベテラン社員の離職は、企業にとって大きな損失となります。
彼らが持つ貴重な技術が若手へ継承されないまま社外へ流出してしまうと、企業の競争力が低下し、将来的な事業継続が困難になるリスクさえあります。
建設業の離職率を改善するための具体的な対策
人材の定着率を高め、企業の持続的な成長を実現するためには、離職の原因となっている課題に真摯に向き合い、具体的な対策を講じることが不可欠です。ここでは、すぐにでも取り組める改善策を紹介します。
労働時間や休日制度の見直し
まず着手すべきは、長時間労働の是正と休日確保です。
国土交通省も推進する「週休二日制」の導入は、従業員の心身の健康を守り、ワークライフバランスを向上させる上で極めて重要です。勤怠管理システムを導入して労働時間を正確に把握し、不要な残業を削減する仕組み作りを進めましょう。
| 対策 | 具体的なアクション |
| 長時間労働の是正 | 勤怠管理システムで労働時間を可視化する |
| ノー残業デーを設定する | |
| 休日確保 | 週休二日制(4週8閉所)の導入を目指す |
| 有給休暇の取得を奨励する |
給与・評価制度の適正化
従業員が納得感を持って働けるよう、給与体系や評価制度を見直しましょう。年齢や経験年数だけでなく、個人のスキルや実績、貢献度を正当に評価する仕組みを構築することが重要です。
評価基準を明確にし、定期的なフィードバック面談を行うことで、従業員のモチベーション向上につなげることができます。
ICTやデジタルツールの活用による業務効率化
ICT建機や施工管理アプリ、情報共有ツールなどのデジタルツールを積極的に活用し、業務効率化を図ることも離職率低下に効果的です。
例えば、書類作成や情報共有にかかる手間を削減することで、現場作業に集中できる環境を整えたり、残業時間を削減したりすることが可能になります。デジタル化は、若手人材にとって魅力的な職場環境づくりにも繋がります。
スキルアップ支援と教育制度の構築
若手社員が将来のキャリアを描けるよう、体系的な教育制度を整備しましょう。新人研修はもちろんのこと、資格取得支援制度(費用補助や講習会の実施)や、スキルアップに応じたキャリアプランの提示などが有効です。
従業員一人ひとりの成長を企業が支援する姿勢を示すことが、定着率の向上に不可欠です。
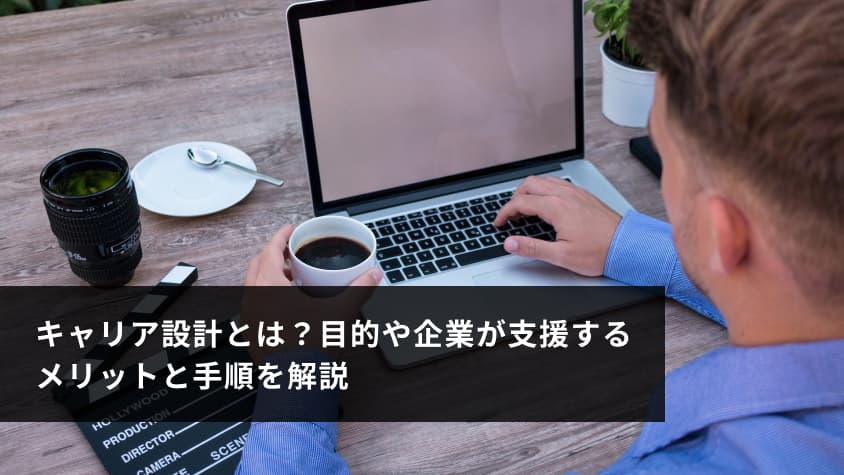
コミュニケーションの活性化と職場環境の改善
従業員が孤立することなく、安心して働ける職場環境づくりも重要です。定期的なミーティングや1on1面談の実施、社内イベントの開催などを通じて、部署や役職を超えたコミュニケーションを活性化させましょう。
また、女性専用の更衣室やトイレを整備するなど、多様な人材が働きやすい環境を整えることも、人材確保の観点から有効な対策となります。
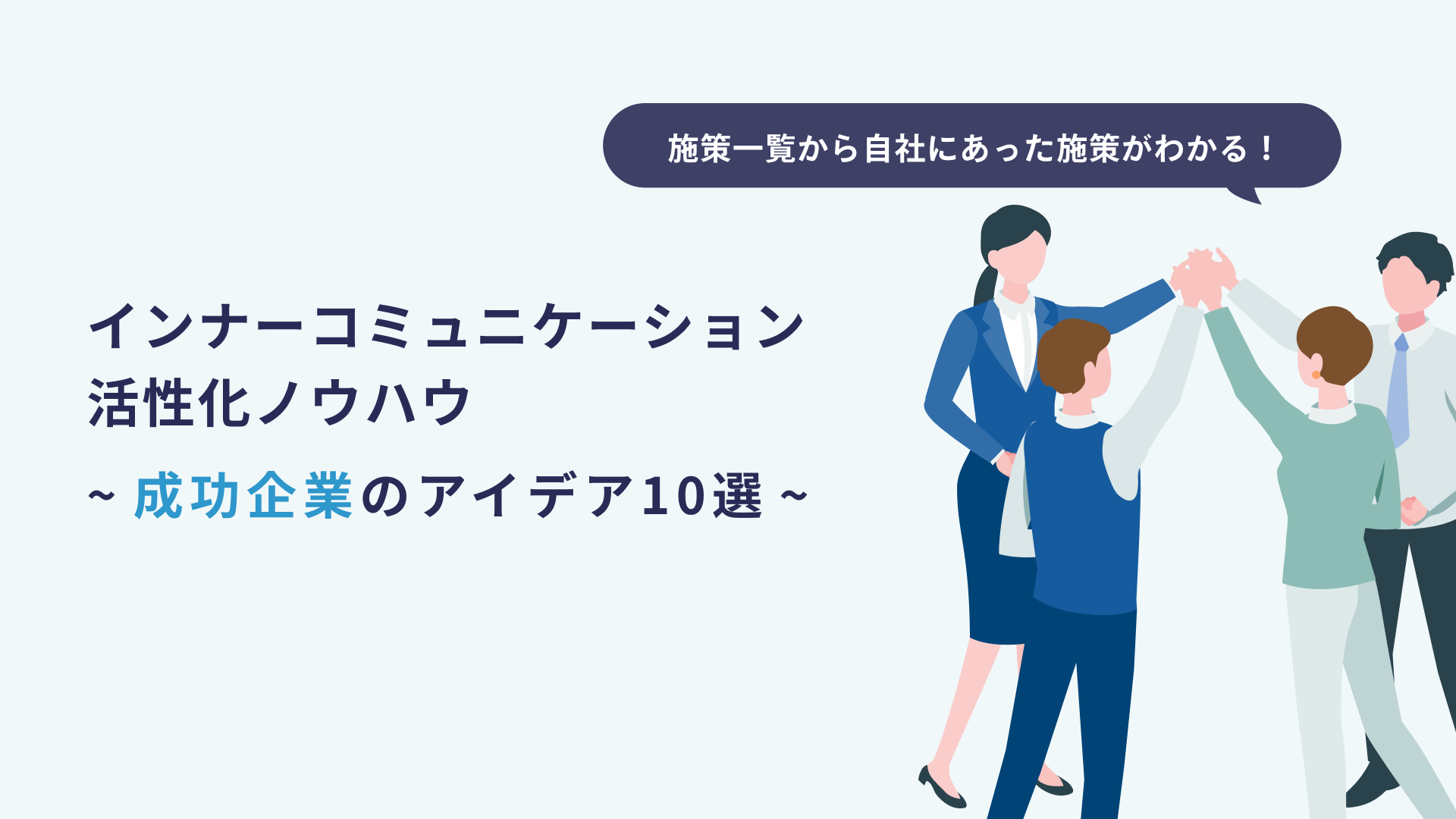
従業員のエンゲージメントを高める
従業員の定着率を高めるためには、働きがいのある職場環境を作ることが不可欠です。従業員エンゲージメント、すなわち仕事への熱意や貢献意欲を高める取り組みが重要です。
具体的には、社内イベントや社内報などによるコミュニケーションの活性化、従業員の意見を経営に反映させる仕組みづくり、個人の功績を正当に評価し称賛する文化の醸成などが挙げられます。
従業員が「この会社で働き続けたい」と思えるような環境整備が、離職率の低下につながります。
こちらの資料では、従業員エンゲージメントを向上させる社内コミュニケーション施策の設計方法を解説しております。ぜひご活用ください。
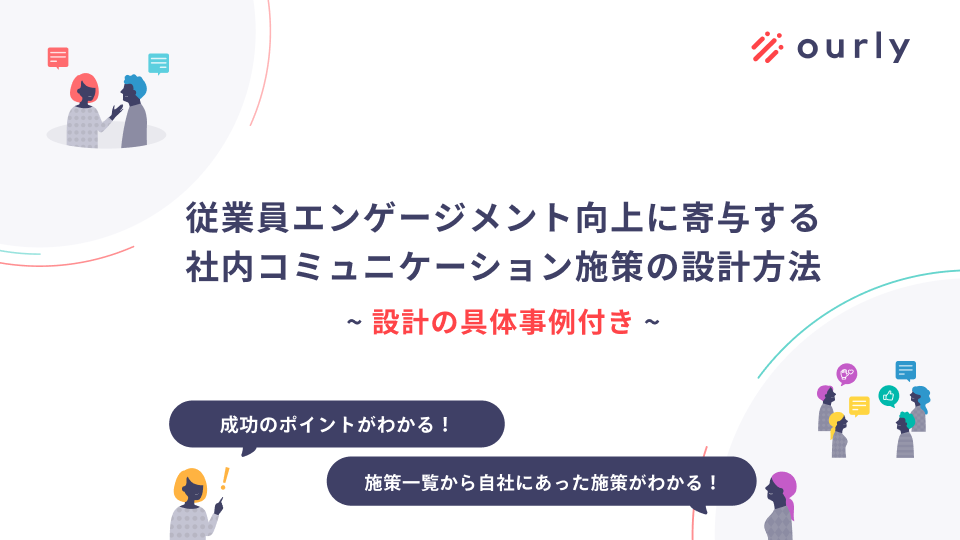
離職率改善に成功した企業の事例紹介
建設業界では深刻な人手不足と高い離職率が長年の課題となっていますが、働き方改革や職場環境の改善により、離職率の大幅な削減に成功している企業も存在します。ここでは、実際に離職率改善に成功した建設業界の企業事例を紹介します。
鹿島建設株式会社による働き方改革の徹底実施
鹿島建設は建設業界において極めて低い離職率を実現している企業です。
2024年度の離職率はわずか1.2%となっており、直近5年間の平均離職率は0.98%という驚異的な数値を記録しています。
同社では2017年4月から「鹿島働き方改革」を推進し、現業部門の長時間労働削減を主軸とした施策を展開してきました。具体的にはICTツールの導入による業務効率化、RPAやAI/OCRの活用による業務プロセス改革、リモートワーク環境の整備などを通じて「魅力ある働き方」の実現に取り組んでいます。
その結果、社員一人ひとりの心と体の健康維持が図られ、建設業界の平均離職率10.1%(2023年)を大幅に下回る成果を上げています。
参考:人事データ | サステナビリティデータ・GRI内容索引 | サステナビリティ | 鹿島建設株式会社
大津建設株式会社のICT技術活用による労働環境改善
広島県三次市に拠点を構える大津建設株式会社は、ICT建機の導入により生産性向上と労働環境改善を同時に実現した好事例です。
従来3人必要だった現場作業を1人で対応可能にし、労働時間の大幅な短縮を達成しました。同社は広島県働き方改革実践認定企業として認定されており、段階的な業務改革と定着支援を目的とした取り組みを継続的に実施しています。
創業60年を迎えた同社では「人を尊び 自然に優しく 地域社会に潤いを届け 共にあゆむ」を企業理念とし、地域に根ざした建設業者として働く人々の負担軽減と離職防止に積極的に取り組んでいます。
参考:大津建設株式会社 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省
離職を低減し、人手不足を改善するweb社内報「ourly」
ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
まとめ
建設業の離職率は、全体としては他産業より低いものの、若年層の早期離職という大きな課題を抱えています。長時間労働、厳しい労働環境、不透明な評価制度といった要因が、人材の定着を妨げています。
しかし、週休二日制の導入やデジタルツールの活用、評価制度の見直し、そして従業員エンゲージメントの向上といった具体的な対策を講じることで、離職率を改善し、従業員が長く働きたいと思える魅力的な企業になることは十分に可能です。
この記事で紹介した内容を参考に、自社の働き方改革に取り組んでみてはいかがでしょうか。