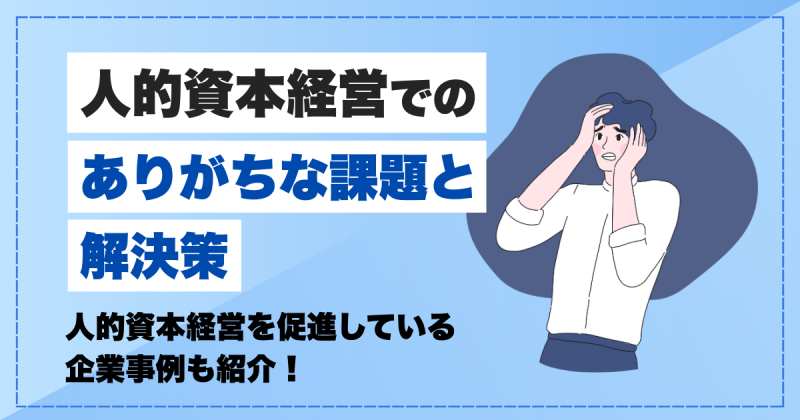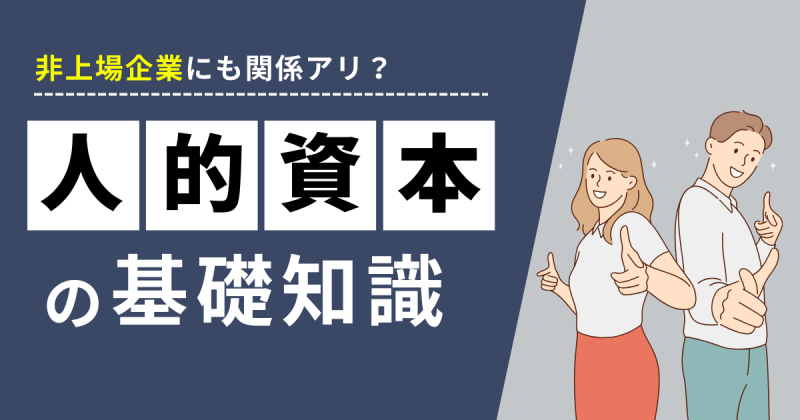「経営層から人的資本経営の推進を指示されたものの、何から手をつければよいか分からない」
「情報開示が義務化されたと聞くが、自社に落とし込む際の具体的な進め方が見えない」
これらの声は、人的資本経営への注目度を反映する一方で、推進担当者が抱える悩みを浮き彫りにしています。取り組みの重要性は理解しつつも、具体的なアクションプランを描けずにいる担当者も少なくありません。
本記事では、多くの企業が人的資本経営を推進する上で直面する7つの代表的な課題を構造的に解説します。さらに、各課題の根本原因や陥りがちな失敗、そして明日から実行できる具体的な次の一手までを提示します。
そもそも人的資本経営とは?
人的資本経営とは、人材を「コスト」や「資源」ではなく、価値創造の源泉となる「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上を目指す経営のあり方です。
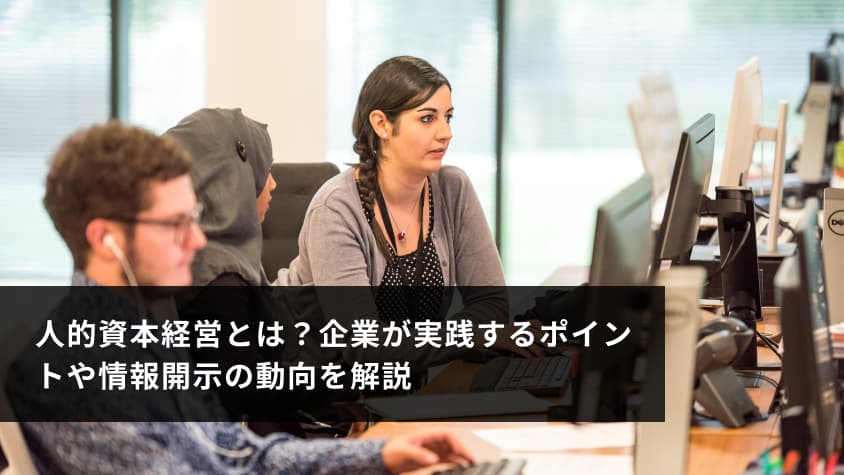
経済産業省が2020年に公表した「人材版伊藤レポート」を契機に、国内でもその重要性が広く認識されるようになりました。これまで財務情報が中心であった企業評価の軸に、人材戦略などの非財務情報が加わったことは、大きな変化です。
特に、2023年3月期決算以降、大手企業(有価証券報告書発行企業)を対象に人的資本に関する情報開示が義務化されたことも、各社が本格的に取り組みを始める大きなきっかけとなりました。本記事では、実践における「課題」に焦点を当てて解説します。
人的資本経営で多くの企業が直面する7つの課題
具体的な7つの課題と、その解決の方向性を解説します。
1. 経営層の理解が得られず、全社的な協力体制が築けない
人的資本経営は人事部門だけで完結する施策ではなく、経営戦略そのものです。そのため、経営層が本質を理解し、強力なコミットメントを示すことが成功の絶対条件となります。しかし、短期的な業績を重視する視点からは、人材への投資がコストと見なされやすく、優先順位が上がらないことも少なくありません。
ありがちな失敗
人事担当者が熱意を持ってデータやプランを提示しても、経営会議で「それで、いくら儲かるのか?」という一言で議論が終わる状態に陥ります。経営層の理解が不十分なままでは、他部署も「人事部の新しい取り組み」と認識し、データ提供や施策実行への協力が得られず、推進が困難になります。
ネクストアクション
まずは、経営層の視点や言語に合わせて対話することから始めます。例えば、競合他社や業界トップ企業の統合報告書を基に、「競合はこれだけの情報を開示し、投資家と対話している」という外部の視点を提示する手法が有効です。また、経営陣が問題視している「若手人材の離職」といった具体的な経営課題と、人的資本への投資を直接結びつけて説明することも、対話の重要な糸口となります。
2. 何を開示すべきか、具体的な項目が定められない
情報開示が義務化されたものの、何をどのレベルで開示するかは各企業の判断に委ねられています。内閣官房が示す開示指針や国際的なガイドライン「ISO 30414」など、参考にするべき指針は存在しますが、選択肢の多さがかえって、自社にとって最適な項目を選び出すことを困難にしています。
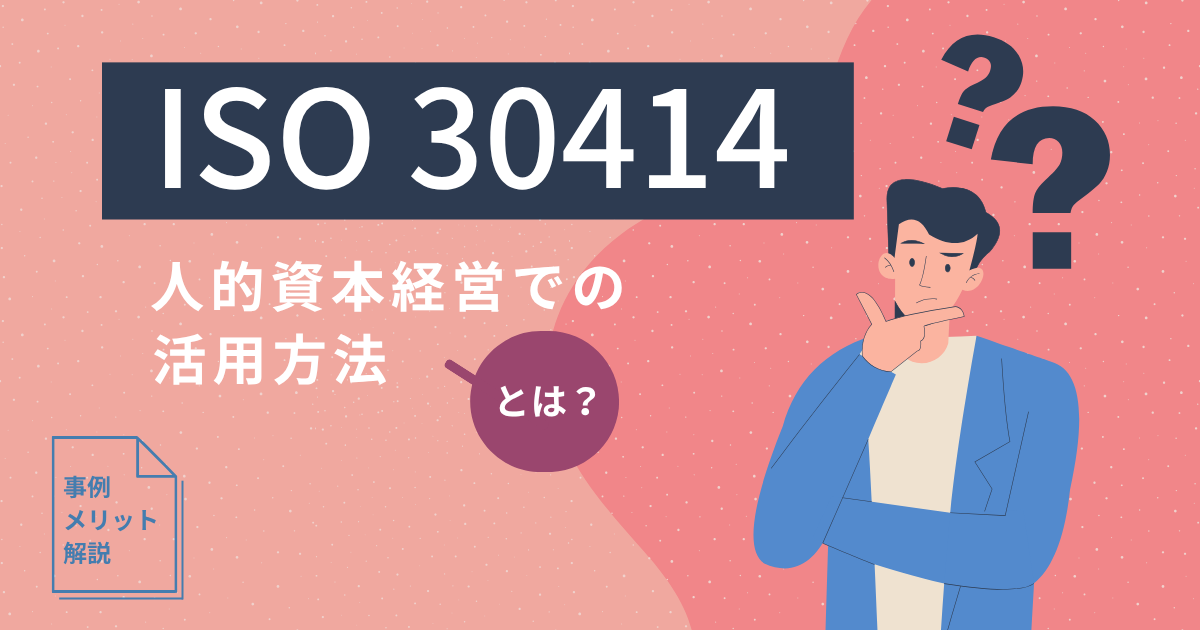
ありがちな失敗
「まず何か開示しなければ」という焦りから、他社の開示項目をそのまま模倣する状態に陥ります。その結果、自社の経営戦略と関連の薄い情報を開示してしまい、投資家などから「なぜこの指標なのか?」という問いに答えられません。これは「開示のための開示」という典型的な失敗です。
ネクストアクション
自社の中期経営計画や事業戦略を全ての起点とします。まず、経営計画の達成に最もインパクトを与える人材面の要素は何かを議論し、それに関連する情報項目を2~3個に絞り込むことから始めましょう。例えば、「グローバル展開の加速」が戦略の柱であれば、「海外拠点の従業員比率」や「グローバルリーダーの育成人数」などが候補となります。
3. 収集・測定すべき指標(KPI)が設計できない
開示項目が決まった後、その状況を客観的に示すための指標(KPI)を設計する必要があります。このKPIは、単に進捗を測るだけでなく、現場の行動を促し、組織を良い方向へ導く機能が求められます。しかし、何を測れば企業価値の向上に繋がるのか、その因果関係を設計することは容易ではありません。
ありがちな失敗
「測定のしやすさ」を優先するあまり、本来の目的からずれたKPIを設定してしまうことがあります。例えば、「研修時間」をKPIに設定した場合、従業員は時間数をこなすことが目的となり、研修の質や実務への活用度合いが問われなくなる可能性があります。また、指標が多すぎると、現場はデータ測定に疲弊し、本来の業務が疎かになるという本末転倒な事態も起こり得ます。
ネクストアクション
ここでもスモールスタートが有効です。まず、最も重要な経営課題を一つ特定し、それと関連性の高いKPIを1~2個設定することから試してみましょう。例えば、企業の成長に「従業員の主体性」が重要だと考えれば、その代理指標として「従業員エンゲージメントスコア」や「社内公募制度への応募率」などを設定し、その推移を追うことが具体的な一歩です。
4. 社内にデータが散在し、収集・管理体制が整っていない
人的資本に関するデータは、勤怠、給与、評価、採用、スキル管理など、様々なシステムに散在しているのが一般的です。効果的な分析を行うには、これらのデータを統合し、一元的に管理する基盤が必要ですが、多くの企業でこのデータ基盤の整備が大きな壁となっています。
ありがちな失敗
分析を始める前に、完璧なデータ基盤を構築しようとしてしまうことです。大規模なシステム導入には多額の費用と時間がかかり、プロジェクトが始動する頃には経営環境が変わっている可能性もあります。また、部署ごとにデータの定義(例:「優秀人材」の定義)が異なり、データを統合したものの、比較・分析ができないという事態も頻繁に発生します。
ネクストアクション
全てのデータを一度に統合しようとせず、まず解決したい課題に必要な最小限のデータを手作業で統合することから始めましょう。例えば、「ハイパフォーマーの特性分析」が目的であれば、人事評価データと対象者の勤怠データや研修履歴データをExcel上で統合するだけでも、有益な示唆が得られることがあります。小さな成功体験を積み重ね、データ活用の有効性を社内に示すことが、将来的な基盤整備への投資判断にも繋がります。
5. 開示した情報が企業価値向上に繋がっているか実感できない
様々な取り組みや情報開示を行った結果、それが本当に株価や業績といった企業価値の向上に貢献しているのか、その効果を測定することは非常に難しい問題です。投資の成果が見えにくいことは、取り組みを継続する上でのモチベーション低下や、経営層から追加投資への理解を得られない原因となります。
ありがちな失敗
取り組みの評価を「従業員満足度の向上」といった内部的な成果に留めてしまうことです。従業員の満足はもちろん重要ですが、それだけでは「事業への貢献」を説明することはできません。人的資本への投資と、売上や生産性といった経営指標との繋がりをストーリーとして語れないと、取り組みは自己満足で終わってしまいます。
ネクストアクション
取り組みを始める前に、「人的資本に関するKPI(例:エンゲージメントスコア)が10%向上すれば、労働生産性が3%向上するはずだ」といった仮説を立てることが重要です。そして、定期的にKPIの推移と経営指標の変動を比較分析し、その相関関係をレポーティングする仕組みを構築しましょう。明確な因果関係がすぐに見つからなくても、相関関係の傾向を示すことで、投資家や経営層への説明責任を果たすことができます。
6. 他社の動向が分からず、自社の取り組みレベルが適切か判断できない
人的資本経営は比較的新しい概念であり、確立された「正解」は存在しません。そのため、多くの担当者は「自社の取り組みは他社と比べて進んでいるのか、遅れているのか」という不安を抱えています。適切なベンチマーク対象が見つからず、自社の現在地が分からないまま、手探りで進めざるを得ない状況に陥りがちです。
ありがちな失敗
情報収集に多くの時間を費やし、肝心な自社のアクションが止まってしまうことです。また、他社の表面的な取り組み(例:ユニークな福利厚生制度)だけを取り入れ、自社の戦略や組織風土を無視して導入し、失敗に繋がることもあります。
ネクストアクション
まず、自社と同じ業界で企業規模が近い競合他社を3~5社選び、それらの企業が発行する統合報告書やサステナビリティレポートを読み込むことから始めましょう。どのような情報を、どのようなストーリーで開示しているかを比較することで、業界内での一般的な開示レベルを把握できます。また、経済産業省が主催する「人的資本経営コンソーシアム」などのコミュニティに参加し、他社の担当者と情報交換することも有効な手段です。
7. 推進を担う専門人材やノウハウが社内に不足している
人的資本経営の推進には、人事の知識だけでなく、経営戦略、財務、データ分析といった多岐にわたるスキルが求められます。しかし、これらのスキルを全て兼ね備えた人材は極めて稀であり、多くの企業、特に人事部門において専門人材とノウハウの不足が深刻な課題です。
ありがちな失敗
担当者が一人で全ての業務を抱え込み、過度な負担から疲弊してしまうことです。また、専門性の高い領域を外部のコンサルティング会社に全て委託した結果、コストがかさむ一方で、社内にノウハウが全く蓄積されないという状況も散見されます。
ネクストアクション
全てを自社で完結させようと考えず、外部の知見やツールを戦略的に活用することが現実的な解決策です。例えば、データ分析の初期段階では専門家のアドバイスを受け、その後の定型的なレポーティングは自社で行う、といった役割分担が考えられます。また、人事部内でデータリテラシー向上のための勉強会を開催するなど、長期的な視点で組織能力を高めていく投資も不可欠です。
人的資本経営に取り組んでいる事例
ここでは、実際に人的資本経営を推進している企業の事例をご紹介します。
人的資本経営の具体的な事例については、こちらの記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。
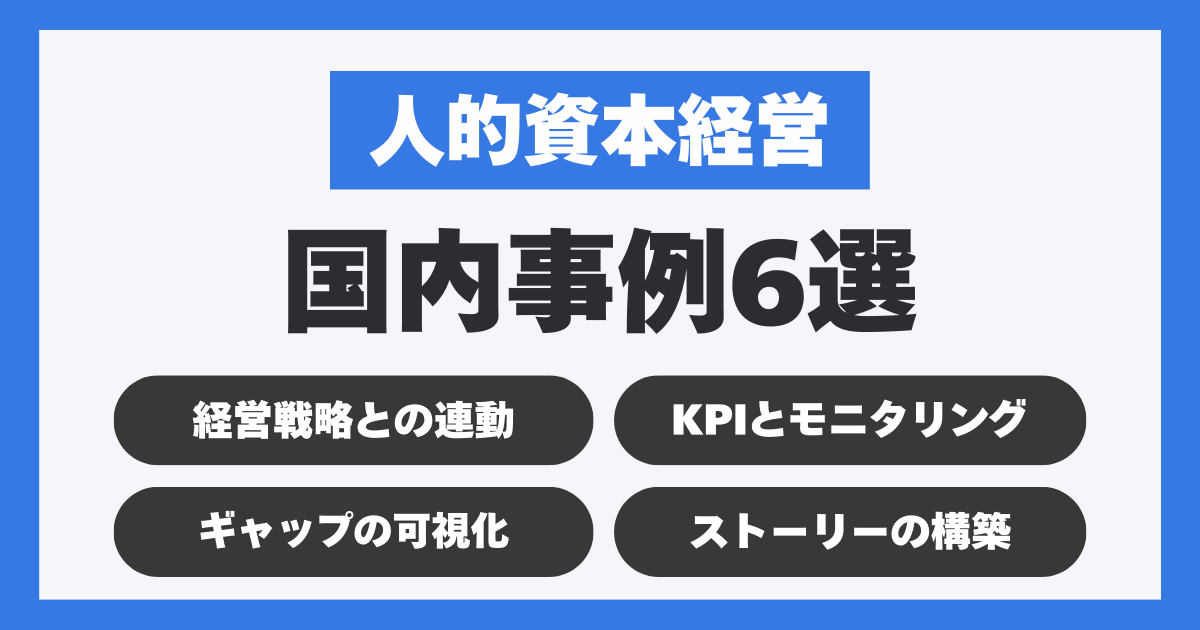
セイコーエプソン株式会社
同社は、グローバルな競争を勝ち抜くため、長期ビジョンに沿った人材基盤の確立を重要課題としていました。特に、成長領域・新領域への人材の重点配置が求められていました。
具体的な取り組みとして、①中長期的な事業戦略から逆算した人材ポートフォリオの策定、②理想と現状のギャップを解消するためのスキルアップ施策や採用計画、③KPI設定とその開示、を推進。事業戦略と人材戦略の連動性を担保するため、現状とあるべき姿のギャップを定量的に把握し、それを埋めるための具体的な施策とKPIをセットで設計している点が特徴です。
出典:https://hcm-consortium.go.jp/pdf/topic/2023_soukai03_GoodPractice_v3.pdf
中外製薬株式会社
同社は、2030年に向けた成長戦略の実現にはデジタル等を担う人材の獲得・育成が不可欠であるとし、社員の自律的な成長を促す仕組みづくりが課題でした。
具体的な取り組みとして、①成長戦略に基づいたジョブ型人事制度の導入、②リスキリングを促す「Future Skilling」の提唱、③自律的学びを支援するキャリア開発サイクルの実行、を推進。ジョブ型人事制度でゴールを明確化すると同時に、そこに至るための学びのサイクルを提示することで、社員の自律的なキャリア形成を効果的に支援しています。
出典:https://hcm-consortium.go.jp/pdf/topic/2023_soukai03_GoodPractice_v3.pdf
課題解決を加速させるためのツール「ourly」の紹介
自社だけですべての課題を解決することが難しい場合、外部のツールやサービスを戦略的に活用することが有効です。特に「従業員エンゲージメントの可視化」や「全社的な協力体制の構築」といった課題に対しては、組織の状態を可視化し、対話の共通言語を持つためのプラットフォームが役立ちます。
弊社が提供するサービス「ourly」は、web社内報とサーベイ機能を組み合わせることで、組織内の情報流通を活性化させると同時に、従業員のエンゲージメントを継続的に測定・可視化します。
・経営メッセージの浸透度を可視化し、経営層と現場の認識ギャップを埋める
・エンゲージメントスコアを客観的なKPIとして設定し、施策の効果測定を行う
・部署やチームごとの状態をデータで把握し、的確なマネジメントを支援する
人的資本経営の第一歩である「組織の現状把握」と「対話の土台作り」の実現を、「ourly」は支援します。ご興味のある方は、ぜひ以下をご覧ください。
まとめ
本記事では、人的資本経営を推進する上で多くの企業が直面する7つの代表的な課題と、その具体的な解決策を解説しました。
人的資本経営の推進は一度きりのプロジェクトではなく、継続的な取り組みが求められる長い道のりです。多くの課題に直面し、時には後退するように感じられることもあります。
しかし、最も重要なのは、まず自社の課題を正しく特定し、できることから一歩を踏み出すことです。本記事で紹介したネクストアクションが、皆様の取り組みの参考となれば幸いです。