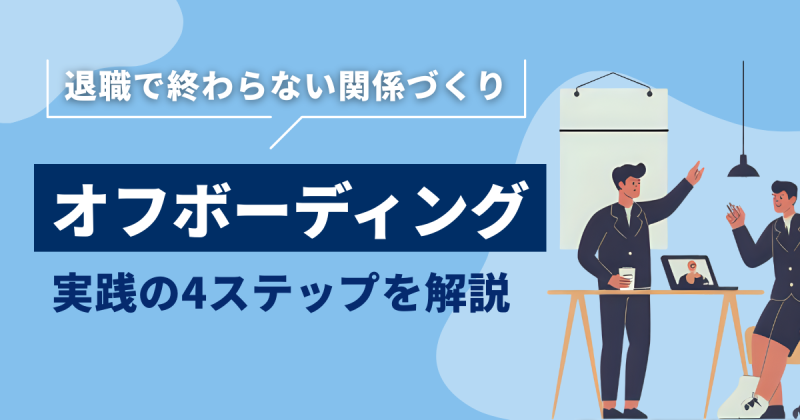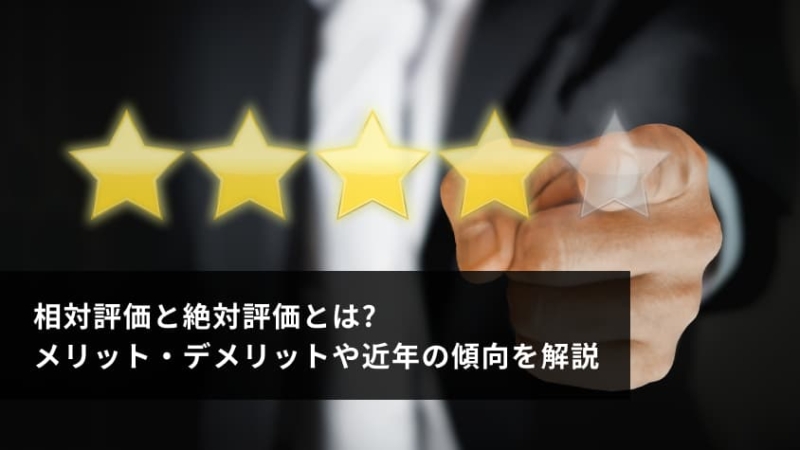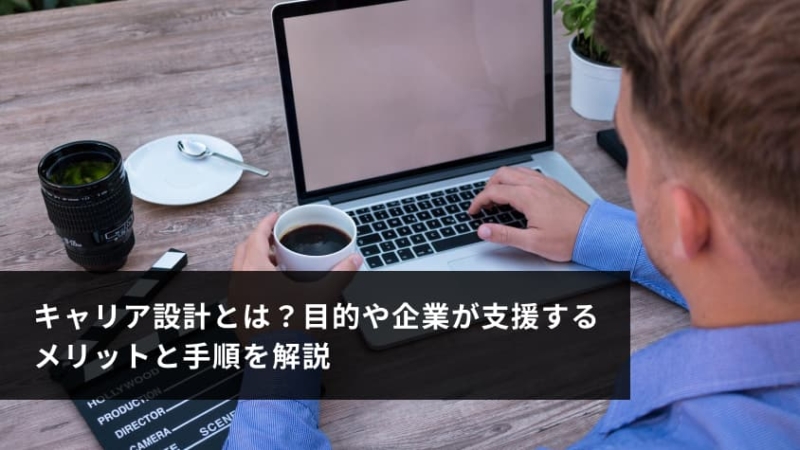近年、人材の流動化が進む中で「オフボーディング」という言葉に注目が集まっています。
従業員の退職は、企業にとって避けられない出来事ですが、その対応次第で企業の未来は大きく変わります。退職時の手続きがうまくいかず業務に支障が出たり、企業の評判が下がってしまったりと、悩みを抱える人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、オフボーディングの基本的な知識から、具体的な進め方、成功のポイントまでを体系的に解説します。
オフボーディングとは?円満な退職を支援する取り組み
オフボーディングとは、従業員が退職の意思を表明してから、最終的に退職するまでの一連のプロセスや体験を向上させるための取り組みです。
単なる事務手続きだけでなく、退職者が円満に会社を去り、退職後も良好な関係を築くことを目的としています。従業員体験(エンプロイーエクスペリエンス)の終着点である退職時の対応を丁寧に行うことで、退職者は会社に対して良い印象を抱きやすくなります。
また、退職理由のヒアリングを丁寧におこなうことは組織課題を把握する機会にもなるため、組織づくりにも繋げることができます。
オンボーディングとの違い
オフボーディングは、しばしば「オンボーディング」と対義語として用いられます。それぞれの目的と対象者は明確に異なります。
オンボーディングが新入社員の定着と即戦力化を目指す「入り口」の施策であるのに対し、オフボーディングは退職者が気持ちよく次のステップに進めるように支援する「出口」の施策と言えます。
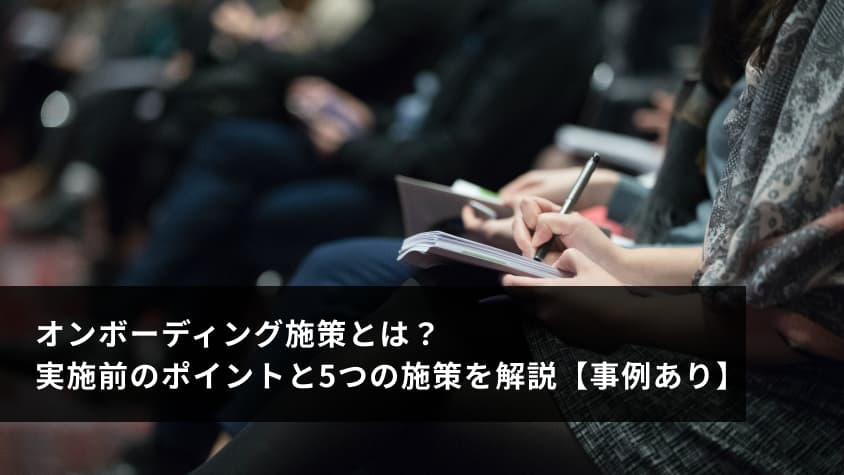
オフボーディングが注目される3つの背景
なぜ今、これほどまでにオフボーディングが重要視されているのでしょうか。その背景には、社会や働き方の大きな変化があります。
雇用の流動性の高まり
終身雇用が当たり前ではなくなり、キャリアアップや働き方の多様化のために転職を選択することが一般的になりました。
人材の流動性が高まる現代において、企業は退職をネガティブなものとして捉えるのではなく、避けては通れないプロセスとして適切に管理する必要が出てきました。退職者が増えるからこそ、一人ひとりの退職体験の質が組織全体に与える影響も大きくなっています。
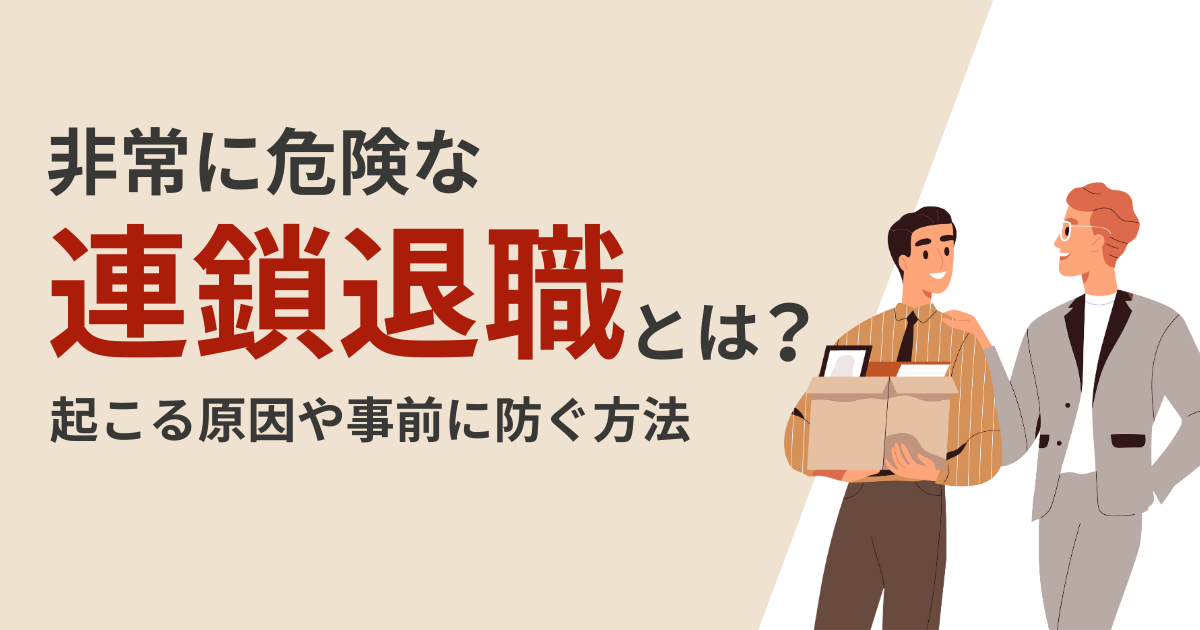
SNSの普及による企業評判の変化
現代では、SNSや口コミサイトを通じて誰もが情報発信者になれます。
退職時に不誠実な対応をされた従業員が、その体験をオンラインで共有すれば、企業の評判は瞬く間に広がり、採用活動やブランドイメージに深刻なダメージを与える可能性があります。逆に、ポジティブな退職体験は良い口コミにつながり、企業の魅力を高める要因にもなります。
アルムナイ・ネットワークの重要性
「アルムナイ」とは、企業の「卒業生」である退職者を指します。
一度退職した人材を再び雇用する「アルムナイ採用」や、退職者とのネットワークを通じてビジネスチャンスを創出する動きが活発化しています。オフボーディングを通じて退職者と良好な関係を築くことは、将来的に貴重な人的資産となるアルムナイ・ネットワークを構築するための第一歩となるのです。
オフボーディングがもたらす4つのメリット
オフボーディングに戦略的に取り組むことで、企業は多くのメリットを得ることができます。
スムーズな業務引き継ぎとリスク回避
計画的なオフボーディングは、業務の引き継ぎを円滑に進める上で不可欠です。退職者が持つノウハウや情報を確実に後任者へ移管することで、業務の停滞や顧客への影響を最小限に抑えます。また、貸与品の返却や情報システムのアカウント削除などを徹底することで、情報漏洩などのセキュリティリスクを回避できます。
| リスクの種類 | オフボーディングによる回避策 |
| 業務停滞 | 詳細な引き継ぎ計画の策定と実行支援 |
| 情報漏洩 | PCやIDカードなど貸与品の確実な回収、アクセス権の削除 |
| 顧客信用の低下 | 顧客情報の丁寧な引き継ぎと後任者の紹介 |
| 法務トラブル | 退職関連の書類手続きを法的に正しく行う |
企業ブランドイメージの向上
退職者を丁重に送り出す企業文化は、社外からの評価を高めます。
退職者が自社の「応援団」となり、知人や友人に良い評判を伝えてくれることで、採用候補者の増加や、製品・サービスの顧客獲得につながる可能性があります。良い退職体験は、企業の社会的評価を向上させる無形の資産となるのです。
既存社員のエンゲージメント向上
退職者への誠実な対応は、現在働いている社員にもポジティブな影響を与えます。
「この会社は人を大切にする」という安心感が生まれ、組織への信頼や愛着(エンゲージメント)が高まります。また、退職面談で得られた組織課題に関するフィードバックを職場改善に活かすことで、より働きやすい環境を構築でき、離職率の低下にもつながるでしょう。
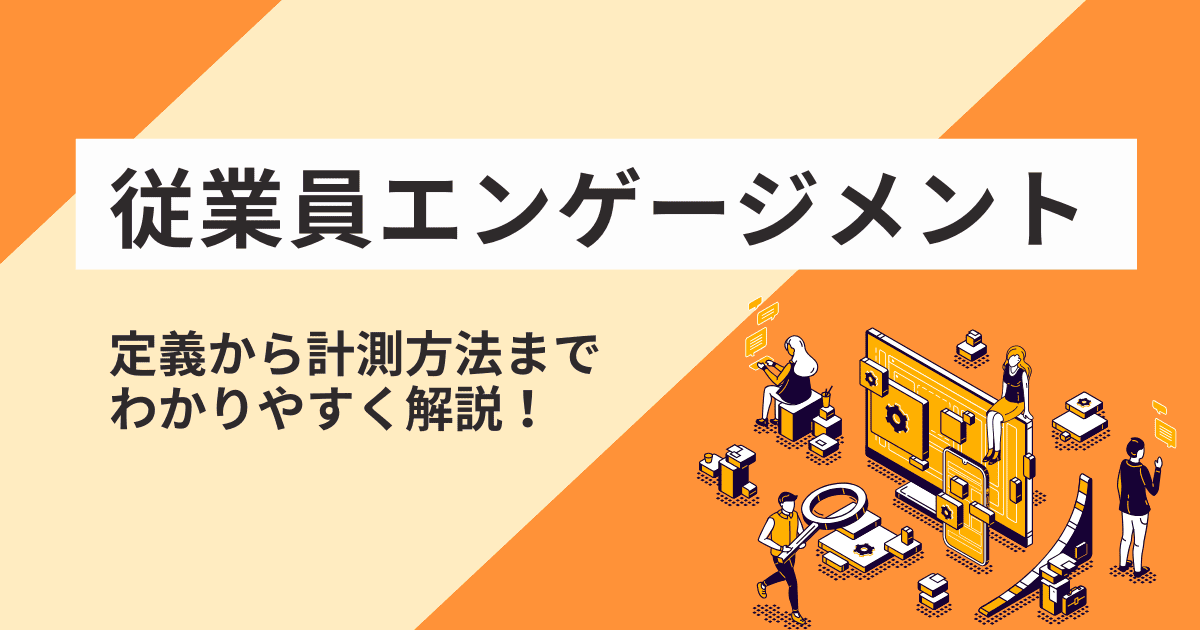
将来的な再雇用や協業への発展
オフボーディングを通じて良好な関係を維持することで、退職者は将来の貴重なパートナーとなり得ます。
他社で新たなスキルや経験を積んだ退職者が、即戦力として自社に復帰する「アルムナイ採用」は、採用ミスマッチが少なく、大きなメリットがあります。また、退職者が顧客や取引先となり、新たなビジネスチャンスをもたらすことも期待できるでしょう。
離職理由による組織課題の特定
オフボーディング時に離職理由を丁寧にヒアリングすることは、組織が現状抱えている課題を知るきっかけになります。
もちろんやむを得ない事情もあるかもしれませんが、組織を離れる決断に至った原因を明らかにすることで、同様の理由で退職する従業員を減らすための改善策を打つことが可能になります。
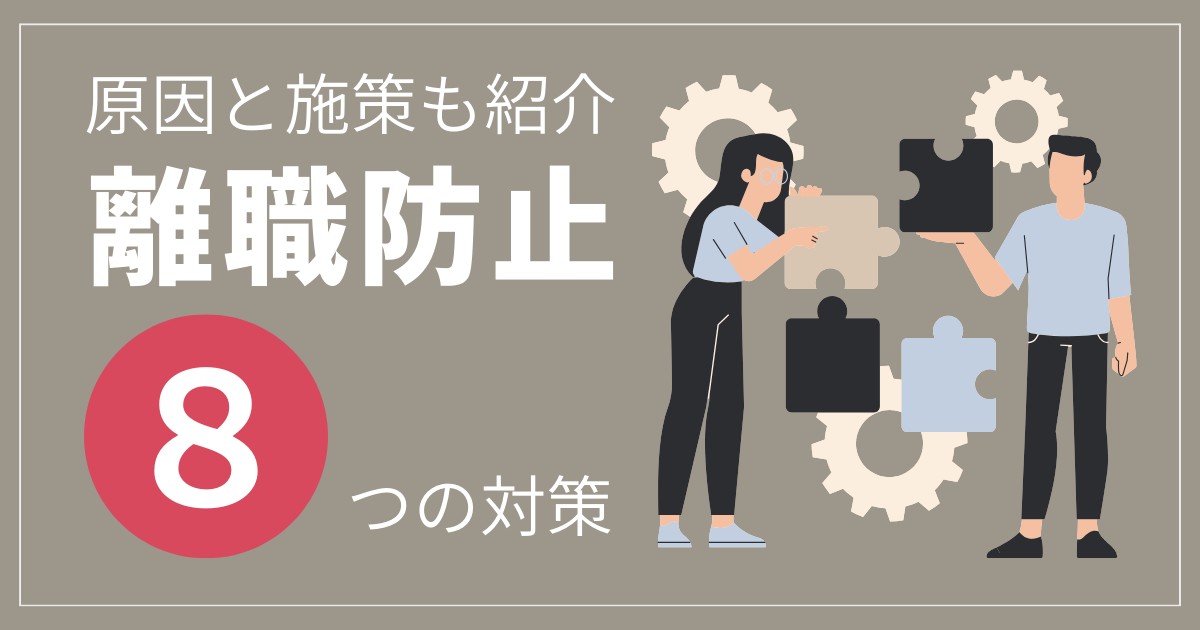
オフボーディングの具体的な手順
効果的なオフボーディングは、場当たり的な対応ではなく、一貫したプロセスに沿って進めることが重要です。ここでは、4つのステップに分けて具体的な手順を解説します。
手順1:退職意思の受領と面談
従業員から退職の意思表示を受けたら、まずは直属の上司が面談を行います。この際、感情的に引き止めたり、問い詰めたりするのではなく、まずは本人の意思を尊重し、話を聞く姿勢が大切です。退職理由や背景を丁寧にヒアリングすることで、組織の課題発見につながることもあります。その後、人事担当者も面談を行い、今後の手続きやスケジュールについて説明します。
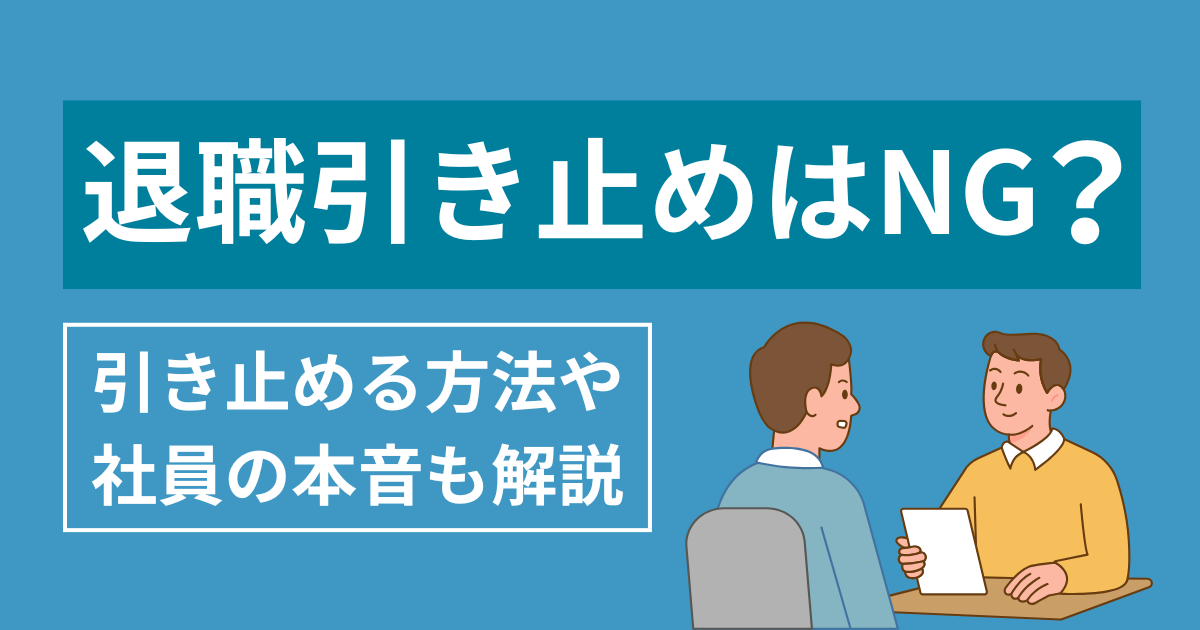
手順2:各種手続きと業務の引き継ぎ
退職日を確定させ、社会保険や雇用保険の手続き、退職金の計算など、必要な事務手続きを進めます。同時に、最も重要な業務の引き継ぎを開始します。引き継ぎリストを作成し、後任者と共にスケジュールを管理することで、抜け漏れを防ぐことが可能です。業務マニュアルの整備や、関係者への挨拶回りなどもこの段階で行います。
| 引き継ぎ項目 | 具体的な内容 |
| 業務内容 | 担当業務のフロー、ノウハウ、進捗中の案件 |
| 社内情報 | 関連部署のキーパーソン、社内ルール、過去の経緯 |
| 社外情報 | 顧客や取引先の担当者情報、連絡先、関係性 |
| データ・資料 | PC内のファイル、書類、各種アカウント情報 |
手順3:退職日当日の対応
最終出社日には、貸与していたPC、社員証、名刺などをすべて回収します。また、社内システムへのアクセス権限を削除し、セキュリティを確保します。朝礼や夕礼などで本人から挨拶の機会を設け、部署内でささやかな送別会を開くなど、感謝の気持ちを伝えて温かく送り出す配慮も大切です。
手順4:退職後の関係構築
退職後も、企業とのつながりを維持するための仕組み作りが重要です。本人の同意を得た上で、アルムナイ専用のSNSグループやメーリングリストに招待し、定期的に会社のニュースやイベント情報を発信します。これにより、退職後も緩やかな関係を保ち、将来的な協力関係へとつなげやすくなります。
オフボーディングを成功させるためのポイント
オフボーディングを形式的な手続きで終わらせず、真に効果的なものにするためには、いくつかの重要な心構えがあります。
退職者の本音を引き出す姿勢を持つ
退職面談では、退職者が安心して本音を話せる雰囲気作りが何よりも大切です。退職理由を深く聞くことは、会社の改善点を見つける絶好の機会です。「会社をより良くするために、ぜひ意見を聞かせてほしい」という真摯な姿勢で臨みましょう。得られたフィードバックは必ず経営層や関連部署に共有し、具体的な改善アクションにつなげることが重要です。
退職後のキャリアを応援する
たとえ自社を去る人材であっても、その人のキャリアを応援する姿勢を示すことは、良好な関係を築く上で非常に効果的です。退職理由がポジティブなものであれば、「新しい挑戦を応援している」「今後の活躍を楽しみにしている」といった言葉をかけましょう。会社が自分の未来を応援してくれていると感じることで、退職者の会社に対する印象は格段に良くなります。
属人化しない業務体制を構築する
オフボーディングは退職時に行うものですが、その効果を最大化するためには、日頃からの準備が欠かせません。特定の担当者しか業務内容を知らない「業務の属人化」は、急な退職の際に大きなリスクとなります。普段から業務マニュアルを整備したり、複数人で情報を共有したりするなど、誰かがいなくなっても業務が滞らない体制を整えておくことが、円滑なオフボーディングの土台となります。
ヒアリングした離職理由から組織課題を改善する
オフボーディングを問題なく執りおこなうことももちろん大事ですが、離職が発生した原因を見つめ直すこともまた重要です。
ヒアリングで得られる離職の理由は1人から得られた定性的なデータであるといえますが、既存社員に対してもアンケートやサーベイで調査することで定量的なデータとして裏付けができます。
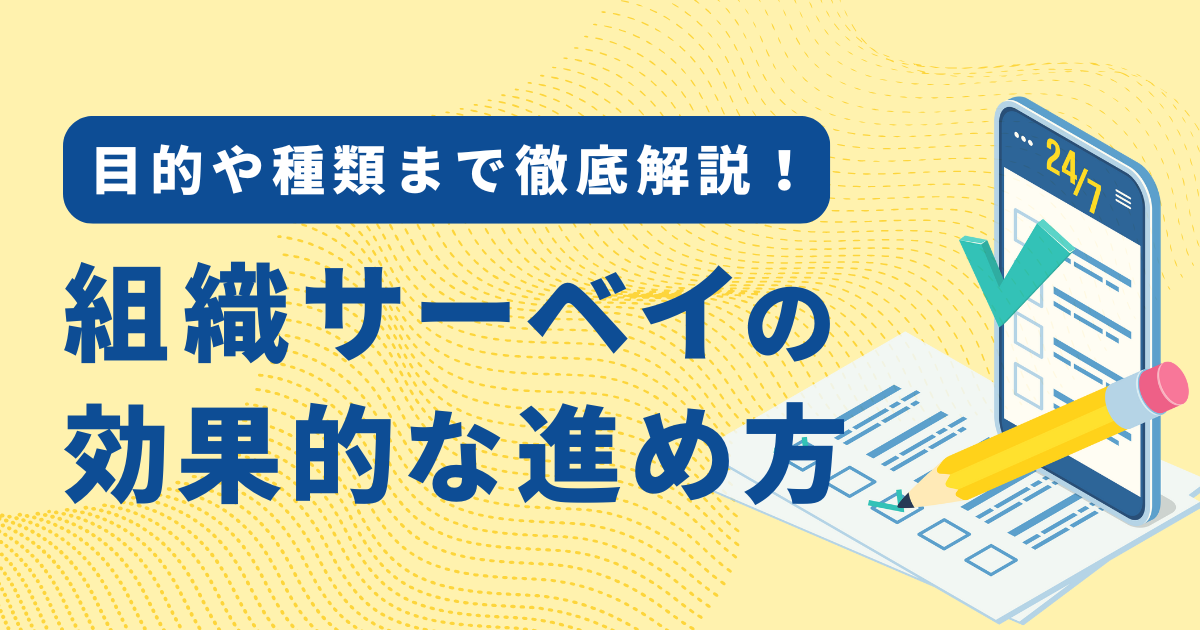
サーベイの項目に離職理由に関連する項目を設定し、実態を把握することで、その問題を解決するかの優先度の指標にもなります。
組織改善のためのサーベイに「ourly survey」
ourly surveyは、部下やチーム全体の状況を的確に把握して、改善施策の立案・実行までを支援する“測って終わり”にさせないサーベイです。

細かい分析機能でチーム課題を可視化
「所属/部署」「役職」「職種」「拠点」などのユーザー属性で回答結果を分析することが可能です。仕事への満足度やエンゲージメントが低い層などを可視化できます。
チーム課題に応じた自由な設問
従業員エンゲージメントの向上やマネジメント施策の成果測定、ビジョンの浸透度合いの計測など、手に入れたいチームの状態から逆算した自由な設問設計が可能です。
行動データを組み合わせた分析
弊社が提供するweb社内報「ourly」の閲覧行動とサーベイで集計した結果をクロス分析することで、チーム改善のサイクルを加速させます。
一気通貫した改善支援
弊社の組織開発コンサルタントが、サーベイで集計した結果をもとにチーム課題の特定や改善施策の提案、実行を支援します。
以下の資料では、ourly surveyの具体的な特徴や機能を紹介しています。サービスの比較や導入のご検討などに、ご活用ください。

まとめ
オフボーディングは、単なる退職手続きではなく、企業の未来を左右する重要な経営戦略です。退職者との関係を良好に保つことは、企業ブランドの向上、組織の改善、そして将来のビジネスチャンスへとつながる貴重な投資と言えます。
本記事で紹介した手順とポイントを参考に、自社のオフボーディングを見直し、退職という出来事を企業の新たな資産に変えていきましょう。