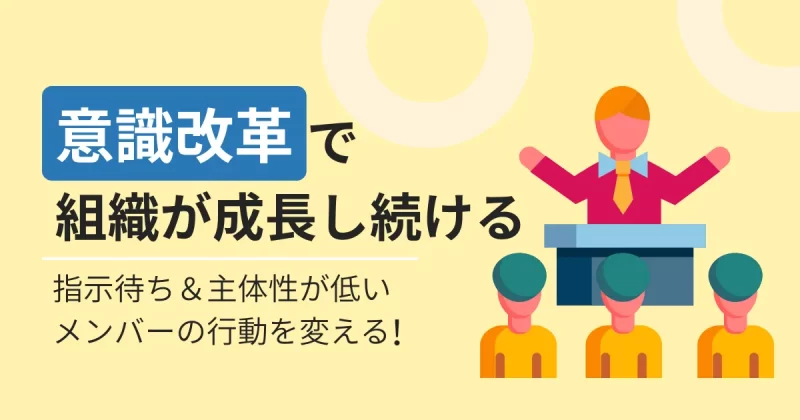組織開発とは、人と人との関係性や相互作用へ働きかけて、一人ひとりの能力を引き出し、組織を活性化させて、組織全体のパフォーマンスを向上させる取り組みのことです。
組織開発では、組織の目標や課題を明確化し、それに対して試験的アプローチをした後、効果検証とフィードバックで精度を高め、組織全体に展開するというプロセスをとります。
この記事では、組織開発のフレームワーク、プロセスや成功事例について解説していきます。
組織開発とは
組織開発とは、人と人との関係性や相互作用へ働きかけてひとりひとりの能力を引き出し、組織全体のパフォーマンスを向上させる取り組みのことです。
「Organization Development」の頭文字から「OD」と表現されることもあり、組織の主体性を引き出すための手法として確立しました。
【資料】縦割り組織・離職率の改善ノウハウ – 組織開発ガイド –
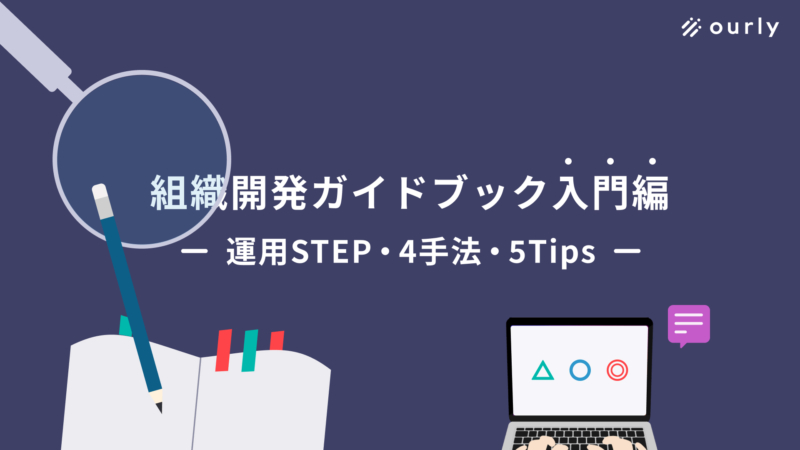
近年「組織開発」と頻繁に聞くようになりました。その一方で、言葉の意味合いは曖昧で、正確に理解し組織に落とし込めている企業は少ないかもしれません。
そこで弊メディアでは、「組織開発とはそもそも何か」や「組織開発の進め方」、「組織開発の豆知識」などをまとめた資料を作成しました。
組織開発に興味がある方や、これから組織開発に取り組まれる方は是非ご覧ください。
URL:https://ourly.jp/document/download_inner-communication-knowhow/
組織開発と人材開発の決定的な違い
組織開発とよく似た言葉に「人材開発」があります。両者は組織を良くするという目的は共通していますが、アプローチの方法が根本的に異なります。
アプローチ対象の違い
最も大きな違いは、働きかける対象です。
人材開発:従業員「個人」を対象とします。研修やOJTなどを通じて、個人の知識やスキルを高めることが主目的です。
組織開発:個人間の「関係性」やチーム・組織全体の「相互作用」を対象とします。ミーティングの進め方や情報共有の仕組みなど、組織のプロセスに働きかけます。
課題の原因特定の違い
課題に対する考え方にも違いが見られます。
例えば、「若手社員の離職率が高い」という課題があったとします。
人材開発のアプローチ:「若手社員個人のスキルや意識に問題がある」または「上司の育成スキルに問題がある」と捉え、若手向け研修や管理職研修を実施します。
組織開発のアプローチ:「若手社員と上司やチームメンバーとの関係性に問題がある」と捉え、相互理解を深めるためのワークショップや、期待役割をすり合わせる1on1ミーティングなどを実施します。
どちらか一方が正しいというわけではなく、組織の状況に応じて両方のアプローチを組み合わせることが重要です。
組織開発の目的
組織開発は多岐にわたる活動を含みますが、その根底にある目的は共通しています。主に「健全性」「生産性」「適応力」の3つを高めることが、組織開発の大きな目的です。
組織の健全性を高める
組織の健全性とは、従業員がいきいきと働ける良好な状態を指します。具体的には、従業員エンゲージメントの高さ、心理的安全性の確保、部門間の円滑なコミュニケーション、ワークライフバランスの質などが含まれます。
組織開発を通じて、従業員同士の信頼関係を構築し、風通しの良い職場環境を整えることで、組織の健全性を高めます。これは、従業員の定着率向上やメンタルヘルスの改善にも直結する重要な目的です。

組織の生産性を高める
組織開発は、個人の能力を足し算するだけでなく、チームや部門が連携することで相乗効果を生み出し、組織全体の生産性を向上させることを目指します。
部門間の対立や非協力的な関係は、業務の遅延や質の低下を招く大きな要因です。組織開発のアプローチによって、こうした関係性の問題を解決し、部署やチーム単位でのパフォーマンスが最大化される状態をつくることで、1+1が2以上になるような組織を目指します。
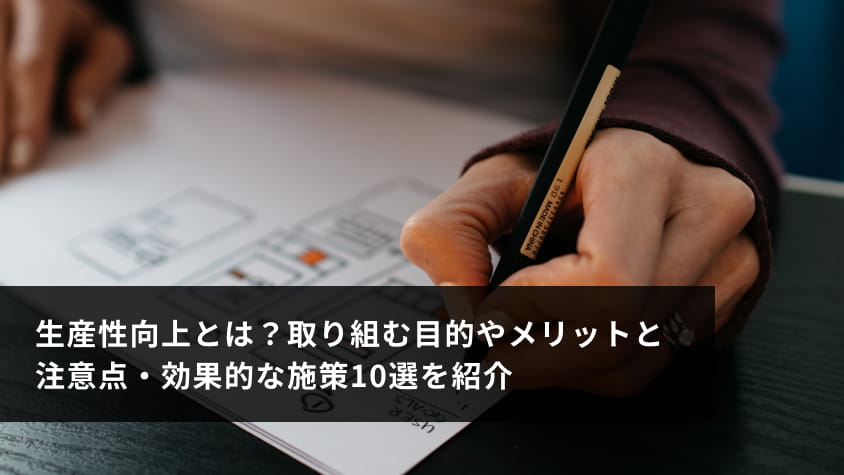
外部環境への適応力を高める
現代のビジネス環境は、市場のニーズ、技術、競合状況などが目まぐるしく変化します。こうした変化に迅速かつ柔軟に対応できなければ、組織の持続的な成長は望めません。
組織開発は、従業員が自ら課題を発見し、対話を通じて解決策を生み出していくプロセスを重視します。 このような自律的な組織文化を醸成することで、外部環境の変化に対して後手に回るのではなく、先んじて適応し、変革し続けられるしなやかな組織をつくることが目的です。
なぜ今、組織開発が必要とされるのか?
近年、組織開発の重要性が増している背景には、ビジネスを取り巻く環境の大きな変化があります。これまでのやり方が通用しなくなり、多くの企業が組織のあり方そのものの変革を迫られているのです。
事業環境の変化への対応
現代のビジネス環境は、変化の予測が困難な「VUCA時代」と呼ばれています。商品のライフサイクルは短くなり、グローバル化やデジタル化の進展により、これまでの成功体験が通用しなくなりました。
このような環境で企業が生き残り、成長し続けるためには、外部環境の変化に迅速かつ柔軟に対応でcきる組織能力が不可欠です。組織開発は、部門間の壁を取り払い、円滑な情報共有や意思決定を促すことで、変化に対応できるしなやかな組織構造を構築します。
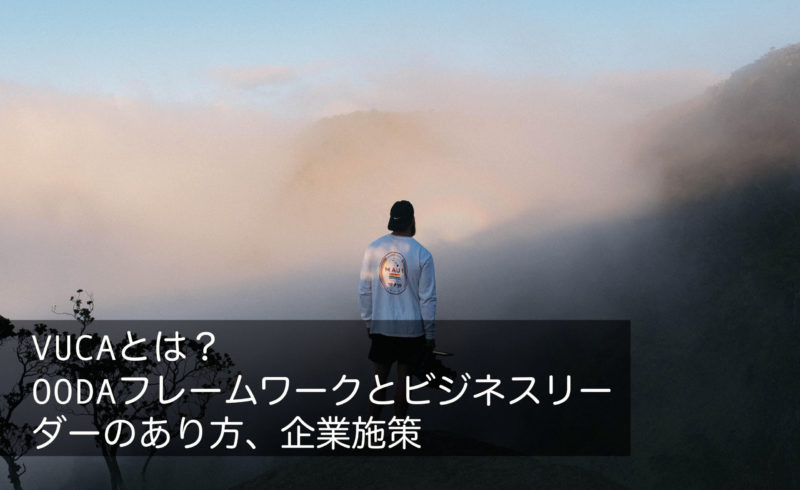
働き手の価値観の多様化
終身雇用や年功序列といった従来の日本型雇用システムが変化し、働き手の価値観は大きく多様化しました。 働く場所や時間、キャリアに対する考え方は人それぞれであり、企業は多様な人材を惹きつけ、その能力を最大限に活かすことが求められています。
画一的なマネジメントでは、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高めることは困難です。組織開発を通じて、多様な価値観を持つ従業員同士の相互理解を深め、一人ひとりが尊重され、活躍できる組織文化を醸成することが重要になります。
エンゲージメント向上の重要性
従業員エンゲージメント、すなわち従業員の「企業に対する愛着心」や「仕事への熱意」は、企業の業績と密接な関係があることが分かっています。エンゲージメントの高い組織は、生産性や顧客満足度が高く、離職率が低い傾向にあります。
組織開発は、従業員同士のコミュニケーションを活性化させ、心理的安全性の高い職場環境を整えることで、エンゲージメントの向上に直接的に貢献します。自分の意見が尊重され、チームに貢献できているという実感は、従業員の働きがいを高め、組織全体の活力を生み出します。
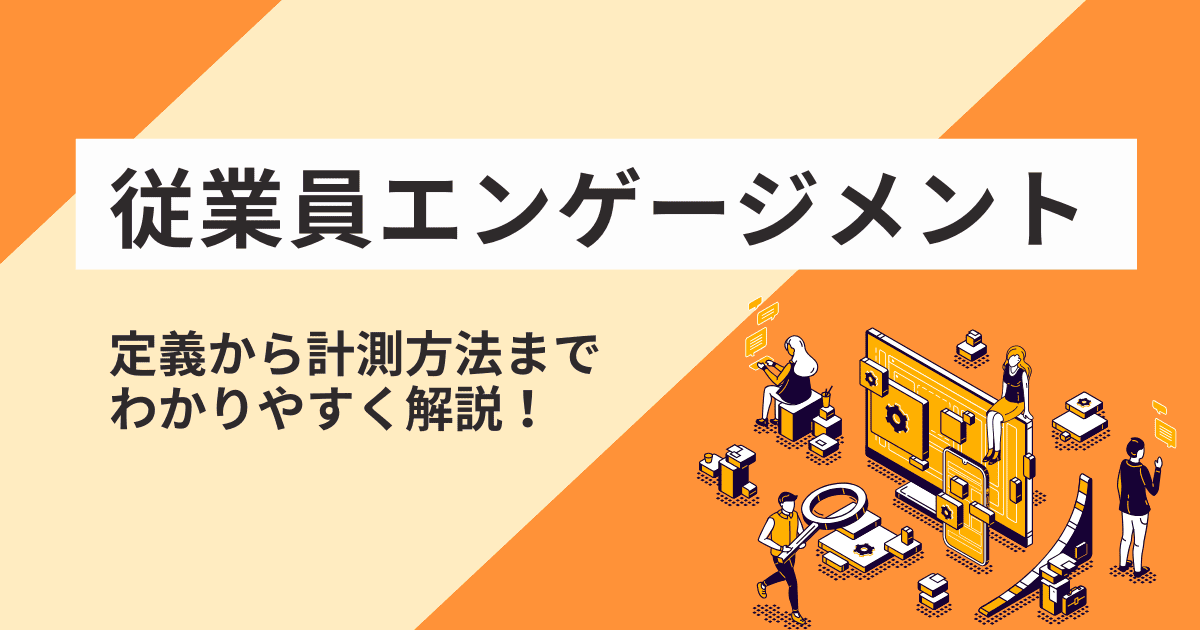
組織開発を成功に導く7つのステップ
組織開発は、思いつきで施策を実行してもうまくいきません。成功のためには、計画的かつ体系的にプロセスを進めることが重要です。ここでは、組織開発を実践するための基本的な7つのステップを紹介します。
目的を明確にする
最初に、「何のために組織開発を行うのか」「どのような状態を目指すのか」という目的を具体的に設定します。「離職率を10%削減する」「顧客満足度を15%向上させる」など、できるだけ定量的で具体的な目標を掲げることが、後のステップでの効果検証にもつながります。この目的設定の段階で、経営層や関係者の間で共通認識を持つことが極めて重要です。
現状を正確に把握する
次に、設定した目的に対して、組織の現状がどのような状態にあるのかを客観的に把握します。従業員へのアンケート調査(サーベイ)やインタビュー、ワークショップなどを通じて、人間関係やコミュニケーション、組織風土に関する「事実」を収集します。「職場の風通しが悪い」といった漠然とした印象ではなく、具体的なデータに基づいて課題を可視化することが大切です。
課題を具体的に設定する
現状把握で得られたデータをもとに、目的達成を阻害している根本的な課題は何かを特定します。 例えば、「部門間の情報共有が不足している」「管理職のフィードバックが一方的である」といったように、具体的な課題を設定します。複数の課題が複雑に絡み合っていることも多いため、関係者で議論を重ね、優先順位をつけて取り組むべき課題を絞り込みます。
小規模な施策から試す
特定した課題を解決するための具体的なアクションプランを策定しますが、いきなり全社で展開するのではなく、まずは特定の部署やチームに限定して試験的に導入します(スモールスタート)。 小規模で試すことで、リスクを最小限に抑えながら、施策の効果を早期に検証できます。また、うまくいけば、それが成功事例となり、全社展開への説得材料にもなります。
効果を検証しフィードバックする
試験的に導入した施策が、どのような効果をもたらしたかを検証します。 事前に設定した目標がどの程度達成できたか、参加者からどのような反応があったかなどを定量的・定性的に評価します。期待通りの成果が得られた場合は、その成功要因を分析します。うまくいかなかった場合は、その原因を探り、改善策を検討します。この検証とフィードバックのサイクルを回すことが、組織開発の質を高めます。
成功事例を全社へ展開する
小規模な試行で効果が確認され、成功のポイントが明確になったら、その取り組みを全社へと展開していきます。 展開する際には、試行で得られたノウハウや成功事例をマニュアル化したり、共有会を開催したりすることで、他の部署でもスムーズに導入できるよう支援します。重要なのは、各部署が当事者意識を持って取り組めるよう、目的や必要性を丁寧に説明することです。
定期的な振り返りで定着させる
全社へ展開した後も、取り組みを継続的にモニタリングし、定期的に効果を振り返る仕組みを設けることが重要です。 施策が形骸化していないか、新たな課題は発生していないかなどをチェックし、必要に応じて改善を加えます。組織開発は一度行えば終わりではなく、組織を取り巻く環境の変化に対応しながら、継続的に改善を続けていく活動なのです。
組織開発における6つのフレームワーク
組織開発のために効果的な手法として、下記6つのフレームワークが挙げられます。
ひとつずつ特徴を紹介していくため、参考にしてみましょう。
コーチング
コーチングとは、社員自ら新たな発見を得られるよう方向性をサポートしていく手法です。
答えとなる正解を直接教える「ティーチング」ではなく、正解に向けて誘導していく「コーチング」であることを意識するとよいでしょう。
視点を広くして物事を分析する力を養ったり、自分の意見だけでなく人の意見にも耳を貸しながら判断していくスキルを身につけたりするシーンに役立ちます。
組織開発だけでなく人材開発に役立つ手法でもあり、社員教育の一環として取り入れている企業も多いです。
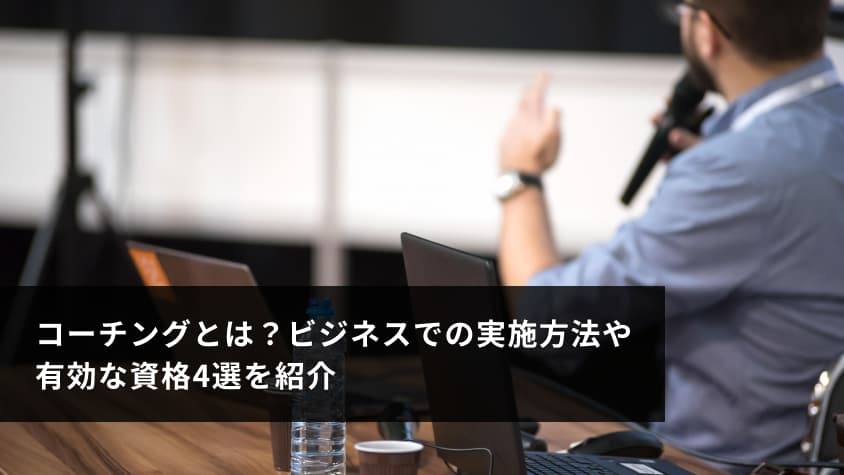
フューチャーサーチ
フューチャーサーチとは、「過去」「現在」「未来」を意識しながら複数人でアイディアを出し合い、意思決定をする手法です。
『フューチャーサーチ』の著者であるマーヴィン・ワイスボード氏とサンドラ・ジャノフ氏によって提唱されたミーティングスタイルの一種であり、会社の経営を自分事として捉えることに役立ちます。
ミーティングに参加するのは社員だけとは限らず、株主・顧客・取引業者・地元の人が参画することもあります。
民主的な合意をするための場として活用しやすく、将来のビジョン実現について考える組織を育成できることがポイントです。
ワールドカフェ
ワールドカフェとは、カフェのようにリラックスした空間で自由きままに意見交換するミーティングスタイルです。
上下関係のないフラットな雰囲気を演出しやすく、部署・年齢・役職・勤続年数の壁を取り払ってコミュニケーションできます。
また、自分の意見を発信することだけでなく相手の意見に耳を傾けることが前提となるスタイルであるため、新たな意見を取り入れたいときに便利でしょう。
フレキシブルなアイディアを出してほしいときにも、ワールドカフェが有効です。

AI(Appreciative Inquiry)
AI(Appreciative Inquiry)とは、探求による価値の認識・価値の自覚をしていく手法です。
具体的には、社員への質問を通して自分の強み・情熱・夢などを引き出したり、ポテンシャルを発見したりします。
社員の視点を広げて自分の可能性に気づかせる手法として確立しており、能力を再発見するためのフレームワークとして有名になりました。
自分が将来会社で活躍している姿をイメージするきっかけにもなるため、今必要な努力の方針を定めたいときにも便利です。
ミッション・ビジョン・バリュー
ミッション・ビジョン・バリューは、「組織の存在意義(ミッション)」「組織が目指巣姿(ビジョン)」「価値観・行動指針(バリュー)」を広く社員に周知する手法です。
会社がどんなことを目標にしていて、今後どんな成長を遂げたいと考えているか知らせることで目的意識の共有ができるようになるでしょう。
社員も会社のミッション・ビジョン・バリューに沿った行動がしやすくなり、意思決定のタイムラグを短縮できます。
帰属意識やエンゲージメントを高める手法としても有効です。


OKR(Objectives and Key Results)
OKR(=Objectives and Key Results)とは、確実に実現できそうな目標よりひとつ上のレベル(ストレッチゴール)を目標に据えていく目標管理手法です。
挑戦心を忘れない組織として成長できるほか、企業・チーム・個人の目標をリンクさせることで高いパフォーマンスを得ることができます。
会社と社員のベクトルを一致させたいときや、取り組むべき課題を可視化してパフォーマンス向上を狙いたいときに有効です。


組織開発を成功させるためのポイント
組織開発は、ただ手法を導入すれば成功するわけではありません。そのプロセスを効果的に進めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
経営層の積極的な関与
組織開発は、時に既存の組織構造や慣習に変化を促すため、現場だけの力で進めるには限界があります。経営層が組織開発の重要性を深く理解し、その目的やビジョンを全社に繰り返し発信することが不可欠です。トップの強力なコミットメントがあることで、変革への抵抗を乗り越え、全社的な協力体制を築くことができます。
現場のキーパーソンを巻き込む
変革を推進する上では、各部署で影響力を持つキーパーソン(管理職やリーダー層など)を早期に巻き込むことが成功の鍵となります。彼らに組織開発の目的を理解してもらい、推進の協力者となってもらうことで、施策が現場にスムーズに浸透し、より現実的で効果的なものになります。
長期的な視点で取り組む
組織の文化や風土、従業員の関係性といったものは、一朝一夕に変わるものではありません。組織開発は、短期的な成果を求めるのではなく、少なくとも1年以上の長期的な視点で腰を据えて取り組む必要があります。成果が出ないからといってすぐに諦めるのではなく、試行錯誤を繰り返しながら、粘り強く継続していく姿勢が求められます。
組織開発に役立つweb社内報 ourly
ourlyは一体感のある組織づくりを支援するweb社内報サービスです。
社内報運用に関する伴走支援が充実しているため、取り組みをやりっぱなしにせず、学びや気づきを組織の資産として活かすことができます。
ourlyの特徴
- SNSのようなコメント機能で、振り返りや共感を引き出す
- web知識不要で、誰でも発信できる
- 閲覧率・読了率の浸透度が可視化できる豊富な分析機能
- 支援体制が充実しており、運用負担が最小限にできる
「チームビルディングゲームを一過性で終わらせたくない」そんなご担当者様におすすめの社内報ツールです。
組織開発の企業成功事例
最後に、組織開発に成功した企業の事例を紹介します。
組織開発としてどんな手法を取るかは、企業ごとの社風や課題感によりさまざまです。下記を参考に、自社に最適な組織開発手法を検討していきましょう。
ヤフー|コーチングの「1on1ミーティング」を実施
ヤフーでは、ティーチングとコーチングを使い分けた1on1ミーティングを開催しています。
「週に1度30分間、場所を確保し、部下の話を聞く」ことを取り組みとして課すと同時に、「経験学習」というスキームを導入するようになりました。
特にコーチングに主体を置き、部下が自ら考え自発的に行動できる力を養う組織開発をしています。
育った時代・やりたいこと・特徴が異なる社員でも最大限のぱパフォーマンスを発揮できるよう、ヤフー独自の工夫がされていることが分かります。

パーソルキャリア|新たなミッション・バリューを制定
パーソルキャリアでは、2019年10月1日から新たなミッション・バリューを制定しています。
働き方に対する多様なニーズが出ていることをきっかけに、『人々に「はたらく」を自分のものにする力を』をミッションとして制定することでキャリアの選択肢や可能性を広げる取り組みをするよう意識しなおしています。
また、ミッションの制定に伴ってバリュー(行動指針)を示し、社員ひとりひとりが課題解決に向けて動くことを求めています。
全社的に舵取りを仕切りなおす組織開発手法であり、新たな価値観として一新することができた事例です。
URL:https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/corporate/2019/20191001_01/
メルカリ|ミッション・バリューを体現するためOKRを導入
メルカリでは、自社のミッション・バリューを体現するためにOKR導入に踏み切っています。
「Go Bold(大胆にやろう)」「All for One(全ては成功のために)」「Be a Pro(プロフェッショナルであれ)」という3つのバリューのなかでも、特に「All for One(全ては成功のために)」に視点を当てた施策となりました。
成功を貪欲に追及するハングリー精神を忘れないよう、常に高めの目標を意識してフィードバックをおこなっています。
創業10年に満たない会社でありながら、誰もが知るサービスを展開できているのはOKRによる目標管理が影響しているとされています。
URL:https://get.wevox.io/media/mercari-story
組織開発で組織を強くしよう
組織開発に成功すれば、組織全体のパフォーマンスを向上することが可能です。
自社に合った組織開発手法を身につけ、「自社にとって足りない要素は何か」を社員と共有していきましょう。
組織開発手法の周知・目的意識の共有には、社内報が有効です。
社内全体に情報を伝達しやすく、トップメッセージや課題感の共有にも役立つため、組織開発前にぜひ検討してみましょう。