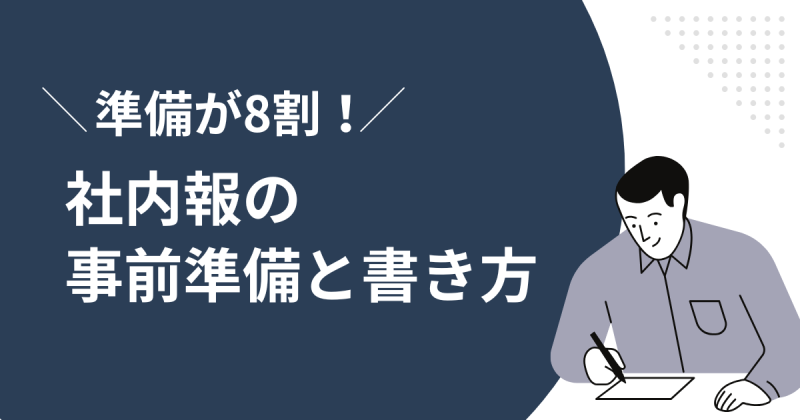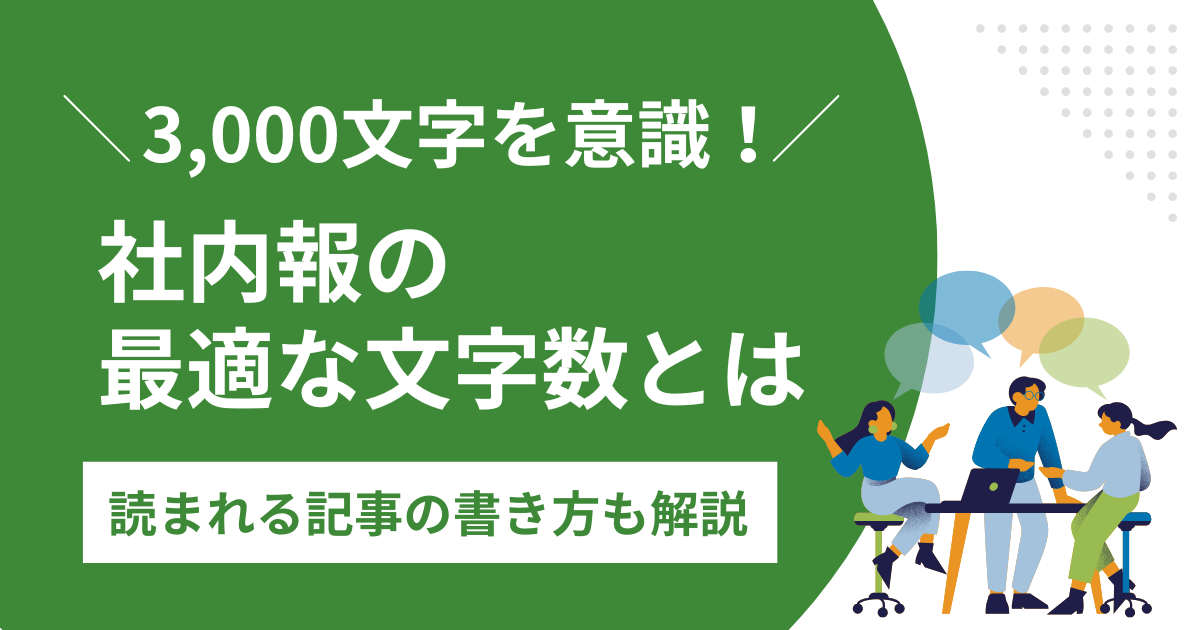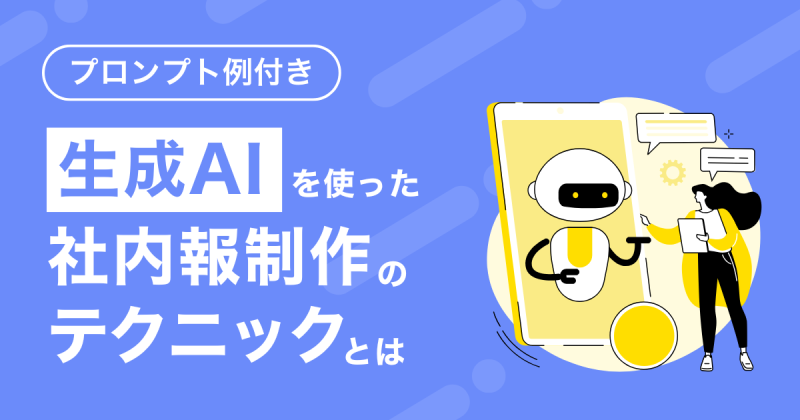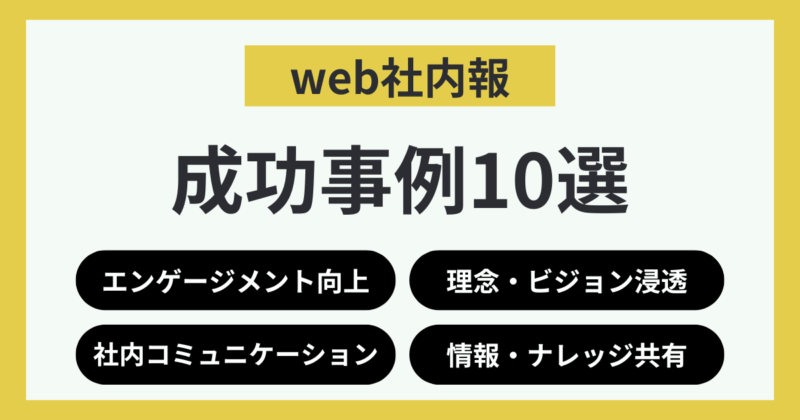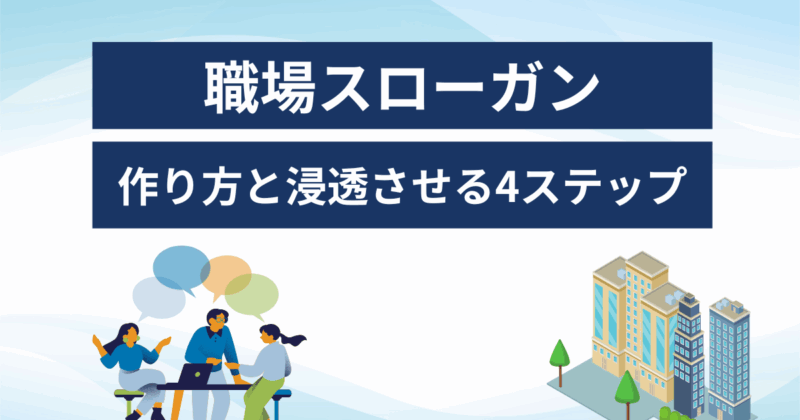近年、多くの企業が社内コミュニケーションの強化を目的として、社内報に力を入れるようになりました。なかでも、社員一人ひとりに情報を正しく届ける「インナーブランディング」の重要性が高まっており、社内報はその中核を担う存在です。
本記事では、社内報執筆において重要とされる具体的な準備内容を詳しく解説します。実際の運用で使えるポイントを押さえながら、「なぜ準備が大切なのか」「準備を怠るとどうなるのか」という疑問にもしっかりお答えしていきます。ぜひ最後までご覧いただき、今後の社内報運用に活かしてください。
【社内報なんとなくやってませんか?】本当に効果を出す目標設定とは
弊社ourlyでは、社内報の運用や社内コミュニケーションの活性化といったノウハウを発信しておりますので、こちらもご活用ください。
準備をしないとどうなる?失敗事例と起こりがちな問題
社内報を執筆するとき、いきなり文章を書き始めていないでしょうか。
準備をしない状態で記事を執筆すると、大きく3つの問題が起こりがちです。
記事の目的やターゲットが不明確になる
いきなり執筆を始めると、最も重要な「この記事は何のために書くのか」という目的が曖昧になりがちです。
たとえば、新入社員向けに書いたつもりでも、気づくと管理職向けの情報も盛り込み過ぎてしまい、結局誰にも刺さらない記事になってしまうケースがあります。
文章が長くなり過ぎて要点が伝わらない
準備段階で記事の構成や見出しが決まっていないと、思いついたことをとりあえず盛り込もうとしてしまい、どんどん文章量が増えてしまいます。
その結果、ポイントが散らばり、読み手にとって分かりづらい記事となり、途中で読むのをやめられてしまう可能性も高まります。
書き手の自己満足記事になってしまう
「自分が伝えたいこと」だけを書いてしまうと、読者にとって役立つ情報や面白さがなくなり、書き手の自己満足で終わるケースが多いです。
社内報は広報活動の一環として読者目線が非常に重要です。読者が何を知りたいか、どんな行動を促したいかといった観点が不十分だと、結局は読まれない記事になってしまいます。
読まれる社内報を作るために必要な事前準備の3ステップ
ここからは、読まれる社内報を作るための具体的に行うべき事前準備の3ステップを解説していきます。
目的とターゲットの明確化
まずは「何のためにこの記事を書くのか」「誰に読んでほしいのか」という目的とターゲットを明確にします。
企業としての方向性や、読者のニーズ・課題といった情報をまとめ、この記事を読んで読者にどう感じてもらいたいかをはっきりさせましょう。

記事構成の決定
次に、実際に文章を書き始める前に記事の構成を作っておきます。
「起承転結」や「導入・本題・まとめ」など、どのパートで何を伝えるのかを箇条書きレベルでまとめておくと、執筆中の迷うことが少なくなります。
文字数と読みやすさの調整
最後に、仕上がりの文字数の目安やレイアウトのイメージを想定しておくと、読者が最後までスムーズに読める記事に近づきます。
段落の分け方や小見出し(H3)の設置、写真やイラストの挿入タイミングなども考慮しておくと良いでしょう。
具体的な準備のポイント
ここからはより踏み込んで、「企画」「記事構成」「タイトル案」について詳しく解説します。これらをあらかじめ決めておくことで、執筆時の負担が大幅に軽減され、読みやすい記事の完成度が格段にアップします。
【企画編】ターゲット設定とニーズの洗い出し
企画を考えるときに必ず考えるべきは、ターゲットとなる読者層とニーズ・課題です。
若手社員をターゲットにするのであれば、「入社して間もないころに感じる不安や疑問を解決する情報を提供できるか」。管理職をターゲットにするなら、「チームマネジメントに役立つ具体例や成功事例がほしいのではないか」などを想定します。
- 目的:社内コミュニケーションの強化、新施策の認知度向上、企業理念の浸透
- ターゲット:若手社員、管理職、特定部署などなるべく具体的に設定
- ターゲットのニーズ・課題:仕事上の困りごとや社内で解消したい課題は何か?
- 伝えたいメッセージ:それらの課題や疑問にどう答えるか?どんな行動を促したいか?
- 醸成したい読後感:読み終わったあとに「なるほど、やってみよう」と思わせたいのか、それとも「知らなかったことを知れた」「楽しい気分になった」と思わせたいのか?
- 記事の訴求ポイント:記事の面白さや斬新さ、他では読めない独自情報など
例)
「新入社員向けに職場の雰囲気を伝えたい」のであれば、先輩社員の体験談や座談会形式のインタビューを企画に盛り込むと効果的です。こうした段階的な洗い出しこそが、企画出しの核となります。
【記事構成編】起承転結と見出しの作成
企画で方向性が定まったら、次は記事の構成を考えます。
タイトル案
まず仮タイトルをいくつか作ってみる。「社内報の記事執筆は準備が8割」「若手社員必見!初めての○○ガイド」など、最低でも3つほど候補を並べると全体像がつかみやすいです。
記事概要(要約)
5行程度の要約を作成します。「この記事のポイントは何か」「読者が得られるメリットは何か」を簡潔にまとめることで、執筆時の迷いを防ぎます。
見出し(H2/H3)の作成
1.導入(起):読者の興味をひく問いかけや背景を説明する
2.本題(承・転):具体的な情報や事例、解決策を解説する
3.まとめ(結):記事全体を振り返り、読者に行動を促すメッセージを添える
構成がしっかりしていると、読者は見出しをざっと読むだけで記事の内容を把握でき、深く読み込みたい部分をピンポイントで確認しやすくなります。
【タイトル案編】最低3つは考える
タイトルは記事の「顔」です。社内報内でのクリック率や閲読率にも大きく影響するため、必ず複数案を用意して比較検討することが大切です。
たとえば、「社内報の記事執筆は準備が8割」「準備が肝心!読まれる社内報の書き方」「社内報担当者必見:効果的な記事執筆ポイント」といった形です。
また以下のポイントも意識しましょう。
- キーワードを意識する:社内報や記事執筆、準備、書き方など、読者が求めているキーワードを織り込む
- 短くわかりやすく:長すぎるタイトルは読みづらく、クリックやタップしてもらえない原因になる
社内報における最適な文字数とは
社内報記事の文字数は、読み手の集中力や社内報媒体の形式(デジタル or 紙)にもよりますが、一般的には1,000〜1,500字前後が読みやすいと言われています。ourlyの社内報の運用データを分析すると、以下のような傾向が見えています。
- 1,000字未満:情報量が少なく、内容が薄いと感じられがち
- 2,000字以上:要点が埋もれ、途中離脱率が高まる可能性がある
とはいえ、文字数はあくまで目安です。内容によっては短く収めるよりも、必要な情報をしっかり盛り込んだほうが読者の満足度が高まるケースもあります。
そのため、記事の目的と読者のニーズをしっかりと踏まえながら、最適な文字量を判断することが重要です。必要に応じて写真や図、箇条書きを取り入れ、見た目のメリハリをつけることも有効です。
実際の執筆時に気をつけたいポイント
企画・構成・タイトルを考えたあとは、執筆に移ります。読みやすい記事を書くために、大きく3つのポイントを意識しましょう。
初稿は一気に書き上げる
準備を万全にしておけば、執筆中に「この情報、本当に必要だろうか」と迷う時間が減ります。初稿は勢いよく書き上げ、その後の編集段階で文章のブラッシュアップを行う方が効率的です。
客観的な視点での校正を取り入れる
自分一人で書いた記事は、どうしても思い込みや抜け漏れが発生しやすいものです。別の部署の同僚や、社内報編集に関わっていない第三者に読んでもらうことで、文中の誤字脱字だけでなく、内容のわかりやすさもチェックしてもらいましょう。
見やすいレイアウトを心がける
文章の読みやすさはレイアウトやデザインの影響も大きいです。
段落ごとに改行を入れたり、小見出しを設置して視線を誘導したりと、ビジュアル面での工夫が重要です。可能なら写真やイラスト、アイコンなどを活用し、飽きさせない工夫をしましょう。
まとめ
事前準備を徹底することで、読者が欲しい情報を的確に伝えられる記事へと仕上げ、結果的に社内コミュニケーションやインナーブランディングの強化につなげることができます。
ぜひ今回ご紹介したポイントを取り入れながら、次回以降の社内報執筆に活かしてみてください。