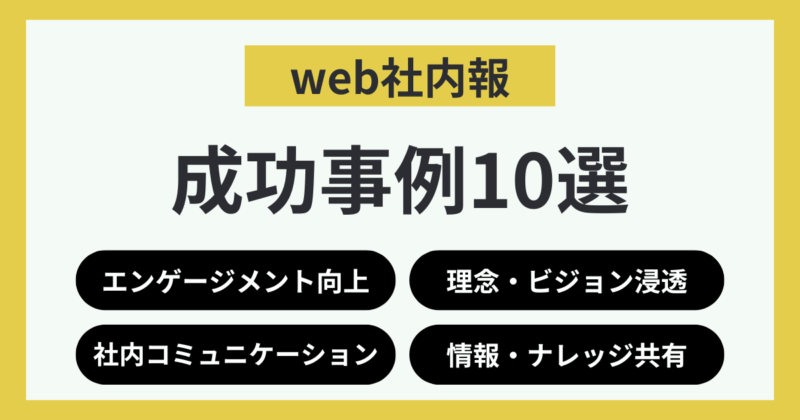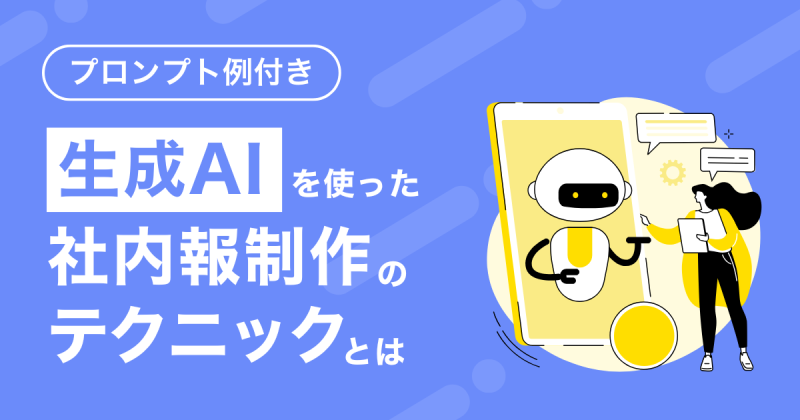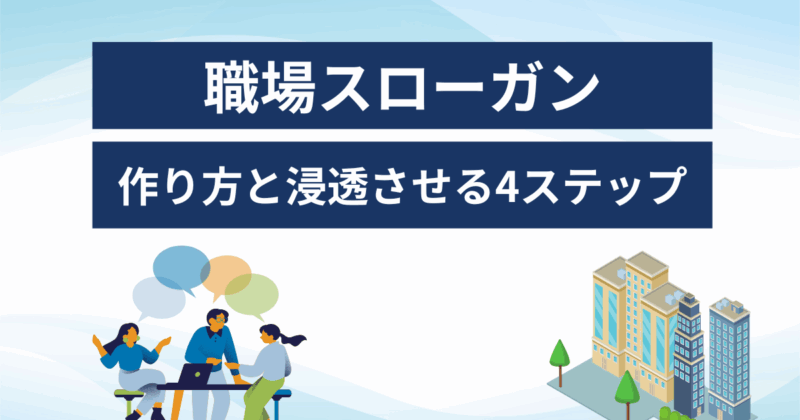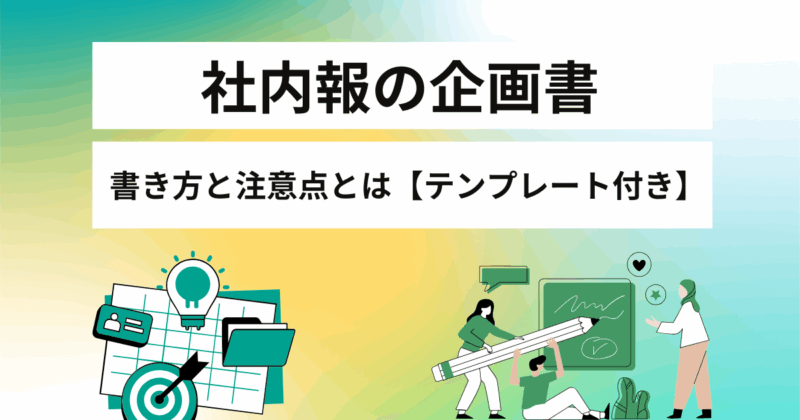社内コミュニケーションの活性化や従業員エンゲージメントの向上のために社内報を活用していきたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
今回は、web社内報を導入することで得られた成功事例をご紹介します。また、社内報の運用を成功させるためのポイントも解説します。
web社内報の成功事例10選
web社内報の成功事例を活用シーン別にご紹介します。
【エンゲージメント向上】会社のことを知れば知るほどエンゲージメントは高まる
マックス株式会社では、コロナをきっかけに対面でのコミュニケーション機会が減りました。物理的な制約がある中で、より社員の結びつきを強め、いきいきと働く社員を増やしたいという思いからweb社内報の導入をおこないました。2022年からエンゲージメントサーベイを使って社内調査をおこなっているが、アンケート結果も良く、社内報が貢献している実感もあるといいます。
課題:リモートワークの導入により、対面でのコミュニケーション機会が減少した。
効果:経営陣の人柄を知れたり、他部署の仕事内容の理解促進につながった。
方法:誰でも使えるシンプルなweb社内報で、届けたい情報を届けたいときに発信できるように。

【エンゲージメント向上】従業員サーベイの数値が20pt以上アップ
株式会社ペンシルでは、経営陣への信頼回復と全社員に情報と伝えるためにweb社内報の刷新と運用を始めました。社内報をきっかけにコミュニケーションが生まれたり、社員からの意見や知りたいことを社内報で発信することで、結果的に従業員サーベイの数値が40.9から64.8まで上昇しました。また離職率も30%から10%前後まで減少したといいます。
課題:従業員エンゲージメントにおける経営陣への信頼のスコアが低かった。
効果:従業員サーベイの数値が20pt以上アップ
方法:サーベイで届いた意見に社内報で返答。また部署ごとに閲覧率を分析し、記事を届ける施策を実行。

【経営理念の浸透】社員が経営陣の想いを自分ごと化できた
シコー株式会社では、ビジョンの刷新をしていく中で、ビジョンを社員と一緒に作りながら、またそのプロセスを公開していくことでビジョンが浸透していくと考えていました。コミュニケーション手段の一つとして、web社内報の導入を決定しました。
課題:各工場や営業所を訪問すると、企業理念が浸透していないと感じるように
効果:経営陣の考えていることやビジョンを自分ごと化して、理解が深まるようになった。
方法:社員を巻き込みながら理念をつくり、web社内報で情報を発信し続けた。

【カルチャーの醸成】社内報がカルチャーの教科書に
株式会社Cygamesは、組織の拡大に伴ってカルチャーを発信・蓄積する場を作るためにweb社内報を自社で作成しました。社内報が「読んで当たり前」の存在になるよう決まった日時に記事を公開し続けたり、発信する内容がカルチャーと一致しているかを社長が必ず確認したりと徹底的な運用をおこなっています。
課題:約3年で従業員数が1,000名になった中でも、カルチャーを浸透させていきたい。
効果:社内報がカルチャーやマインド教育のツールになっている
方法:大切にしたいカルチャーや考え方をもとに作られたコンテンツを継続的に発信

【社内コミュニケーション活性化】顔と名前が一致し、仕事がやりやすくなった
アイリスチトセ株式会社では、アイリスグループが発信する紙社内報が存在していましたが、拠点や部署を超えたコミュニケーションを醸成するために社内独自のアプローチとしてweb社内報を導入しました。部署を巻き込みながら社内報を発信することで、社員同士の認知率が上がったことや、結果的に、複数の部署が関わる大型プロジェクトもスムーズに遂行することもできたそうです。
課題:拠点や従業員数が多くなり、縦割り組織化。顔と名前が一致しない問題が多発。
効果:エンゲージメントサーベイの社員同士の認知率のスコアが格段に上がった。
方法:部署や年代を超えて全社員を巻き込みながら、リレー記事を発信。

【人材定着】キャリアパスや経営方針の発信で、離職者数が減少
株式会社アントワークスでは、経営陣が考えている数年後の未来や、どんなキャリアアップを実現している人がいるのか、などを現場に直接届けるためにweb社内報の導入をおこないました。結果的に、退職者数が25%減少し、社員数が純増基調になったそうです。
課題:全社集会やSV(スーパーバイザー)を通じた情報共有だけでは、伝える頻度が足りなかった。
効果:退職者数が25%減少し、社員数が純増基調になった。
方法:経営陣の数年後の考えや、どんな社員が他店舗で活躍しているのかを記事で発信。

【情報共有の効率化】現場社員に情報が行き届くように
イーグル工業株式会社では、PCを持っていない現場社員に情報を届けるために、web社内報の導入をおこないました。一部の人しか知り得なかった社内の情報が全体にも行き渡るようになり、会話のきっかけになったり社内の動きを自分ごとかに捉える社員が増えたそうです。
課題:工場で働く人たちはパソコンを持っておらず、情報が伝わりづらかった。
効果:現場社員がスマホで情報を見れるようになり、情報が行き渡るようになった。
方法:シンプルで操作が簡単、かつアプリ対応しているweb社内報の導入。

【ノウハウ共有】コンペ勝率UPに貢献
GMO NIKKO株式会社は「Surprising Partner」というビジョンを掲げ、全従業員が「期待値を超えるパートナー」であり続けることを自分ごと化し、理解し、行動できるようになってほしいという思いでweb社内報を活用しています。社内報を運用する中でビジョンの浸透と自分ごと化が進み、「期待値を超える」ためにノウハウを共有する動きが自発的に生まれたといいます。
課題:社内の持つ知見をフル活用するために、社内のコミュニケーションを活発にしたかった。
効果:コンペに特化した記事が年で10本ほど出るようになり、コンペの勝率アップにも貢献。
方法:コンペの必勝法や勉強会の内容をweb社内報で共有。

【ノウハウ共有】各店舗が持つノウハウ・好事例共有に革命が起きた
株式会社GENDA GiGO Entertainmentでは、歴史や文化の違う会社や仲間が一緒になるので、文化を統合していくために本社と店舗、店舗同士をつなぐコミュニケーションツールとしてweb社内報を導入しました。店舗事業では、店長が現場の改善アイデアを実験して、改善した事例を社内報で連載することで、ノウハウの共有と問題解決が一気に進みました。
課題:現場から本社までのコミュニケーションコストが大きく、改善施策の提案から実行まで時間が掛かった。
効果:店舗での問題解決アイデアの実行とノウハウの共有が一気に進んだ
方法:現場で改善アイデアをどんどん実験して、改善した事例を社内報で連載。

【運用コスト軽減】記事の作成工数が3分の1になった
金属技研株式会社では、紙社内報からWeb社内報に切り替えたことにより、社内報運用にかかる工数が3分の1に軽減しました。工数が減ったことで記事公開の頻度も増えて、より素早く情報を共有できるようになったそうです。
課題:紙社内報を年2回発刊していたが、作成に時間が掛かった。またフレッシュな情報を届けることができない。
効果:運用工数は体感1/3に。記事公開の頻度が年間3回から約1ヶ月で8記事へと増加。
方法:シンプルで気軽に記事を書けるシステムで、誰でも記事を発信できる環境に。

社内報を成功させるために必要なこと
社内報の目的を明確にする
社内報を成功させたい場合には、目的が明確になっているかをまず確認しましょう。社内報の運用が上手くいかないときは、「社内報を発行する」ことが目的になっていて、手段が目的化しているケースが多くあります。
「社内コミュニケーションを活性化し、イノベーションを起こしたい…」
「エンゲージメントを向上させて、離職率を下げたい…」
など、どのような組織課題を解決したいのかによって社内報の運用方法や目標設定も変わります。まずは目的を言語化するところから始めましょう。
具体的な目標設計についてはこちらの動画で解説しておりますので、ぜひご覧ください。
適切な運用体制を構築する
目的が明確になったら、目的を達成するために必要なことを分解し、どんな運用体制であれば目的が達成できるかまで具体的に考えていきましょう。
例えば、組織の一体感を醸成したい場合は、拠点や部門を超えたつながりが生まれる記事や情報を発信することが重要です。そのため運用体制としても、人事や広報部門だけで動くのではなく、各拠点の部門長や現場メンバーの協力が必要不可欠です。
こちらの記事で運用体制についてを解説しておりますので、参考にしてみてください。
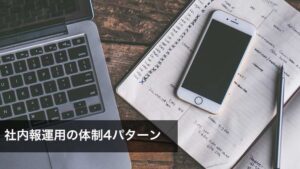
目的に沿ったネタを企画する
自社の組織課題を解決するには、どんな記事を発信する必要があるのかを考えましょう。
例えば、拠点間や世代間のコミュニケーションを活性化させたい場合、社員インタビューや部署紹介が効果的です。コミュニケーションのきっかけになるように、記事の中では人となりがわかるようなパーソナルな情報をメインに執筆することも重要です。
その他のネタや企画については、こちらの記事で詳しく解説しております。
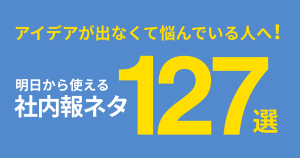
定期的に数値ベースで振り返る
最後に、web社内報を効果的に運用するためには、「定期的に数値ベースで振り返る」ことが欠かせません。
どの記事が閲覧数や読了率が高いのか、どの部署や社員が読んでいるのか、逆に届いていない層はどこか、といったデータを分析することで、次にどんな記事やタイトルを作ればよいか、精度の高い施策につなげることができます。感覚に頼らず、数値に基づいて改善を繰り返すことが、社内報の効果を最大化するカギとなります。
組織課題の解決に「社内報」は効果的!
本記事では、web社内報によって組織課題を解決してきた成功事例をご紹介してきました。
社内報と言えば、紙媒体を想像されるかと思いますが、現在はデジタル化の流れもありwebに切り替える企業が多い傾向です。web社内報の強みである定量的なデータ分析を通じて、組織課題の解決につながる効果的な社内報運用をしていきましょう。