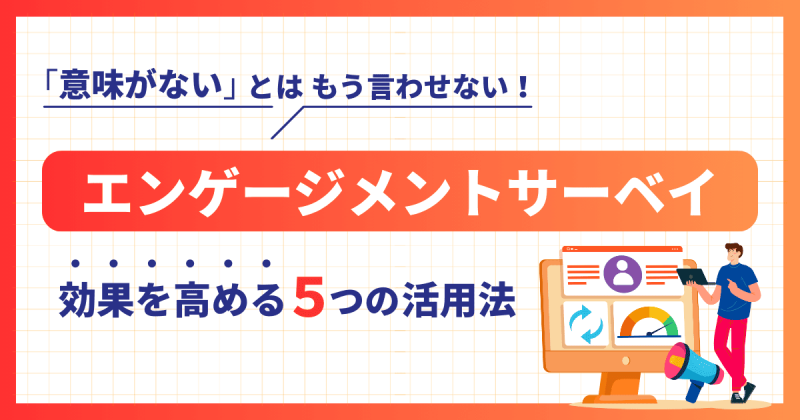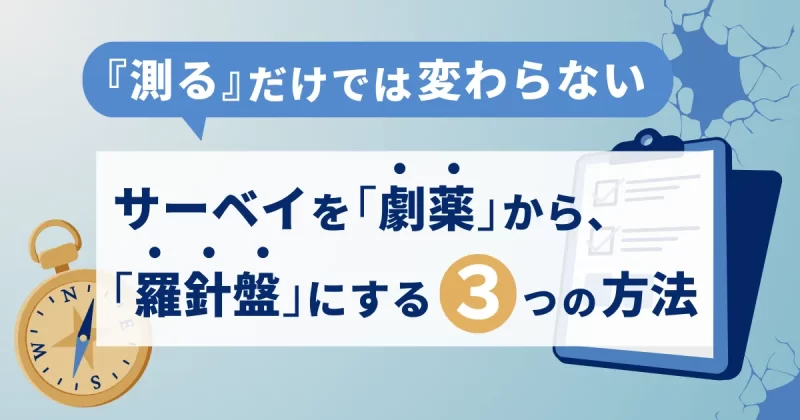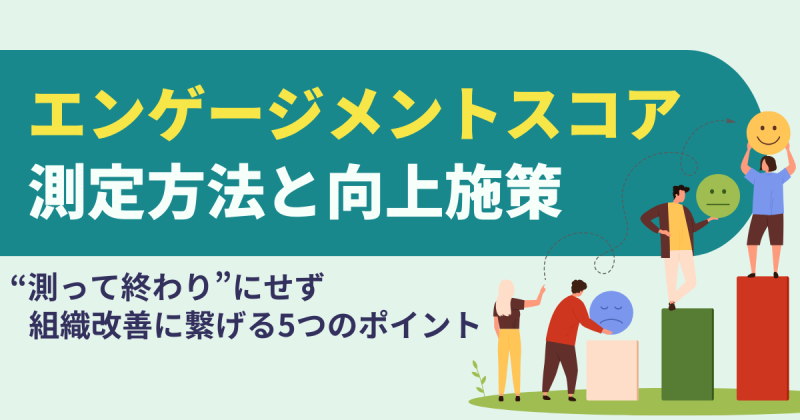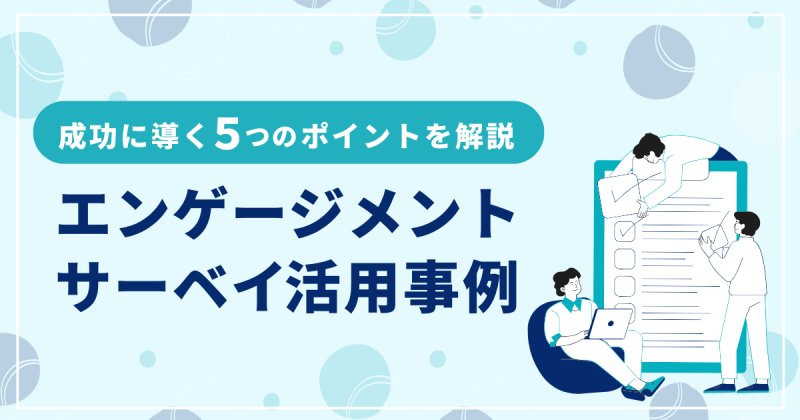従業員のエンゲージメントを高めるために、多くの企業がエンゲージメントサーベイを導入しています。
しかし、その一方で「サーベイを実施しても意味がない」「結局何も変わらない」といった声が聞かれ、施策が無駄だと感じられているケースも少なくありません。
なぜ、エンゲージメントサーベイは形骸化してしまうのでしょうか。
本記事では、エンゲージメントサーベイが無駄だと言われる理由を深掘りし、サーベイを本当に価値あるものにするための具体的な活用ポイントを解説します。
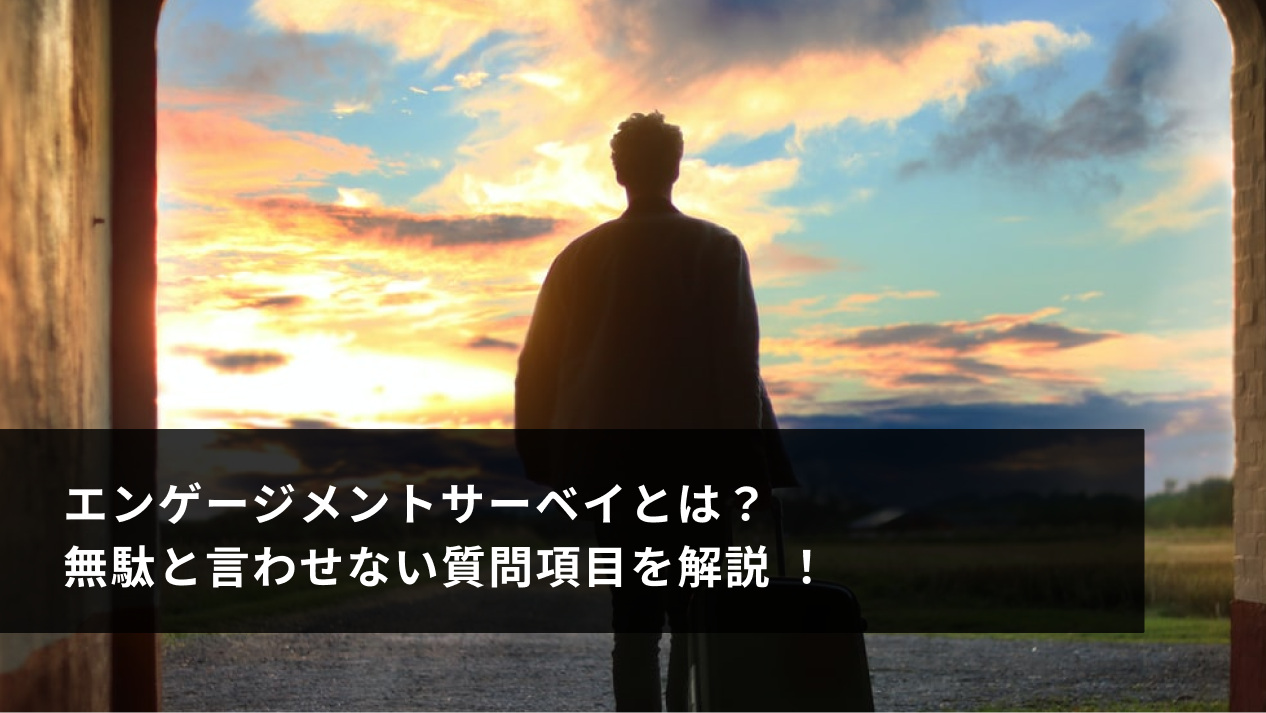
エンゲージメントサーベイが無駄だと言われる5つの理由
エンゲージメントサーベイが「無駄だ」と感じられてしまう背景には、いくつかの共通した原因が存在します。
自社の状況と照らし合わせながら、何が問題となっているのかを確認してみましょう。
実施する目的が曖昧になっている
エンゲージメントサーベイを導入すること自体が目的化してしまい、「何のために調査を行うのか」「結果をどう活用して組織をどう変えたいのか」という最も重要な目的が曖昧になっているケースです。
目的が明確でなければ、設問の設計も的確に行えず、得られたデータも十分に活用できません。
従業員から見ても、目的がわからない調査に協力する意義を見出すのは難しいでしょう。
従業員へ結果がフィードバックされない
多くの従業員は、時間を割いてサーベイに協力した以上、その結果がどうだったのか、会社としてそれをどう受け止めたのかを知りたいと思っています。
しかし、サーベイを実施したきり、結果が従業員に共有されないままでは、「自分の声は届いていない」「結局、聞くだけで終わりか」という不信感が募ります。
このような状況が続けば、次回のサーベイへの協力意欲は著しく低下してしまうでしょう。

分析結果が具体的な改善アクションに繋がっていない
サーベイを実施し、結果を分析して組織の課題を特定したとしても、それが具体的な改善アクションに結びつかなければ何の意味もありません。
「課題は分かったが、どうすれば良いか分からない」「分析して満足してしまった」という状態では、従業員の「どうせ何も変わらない」という諦めを強化するだけです。
サーベイは、あくまで組織改善のスタート地点であるという認識が不可欠です。
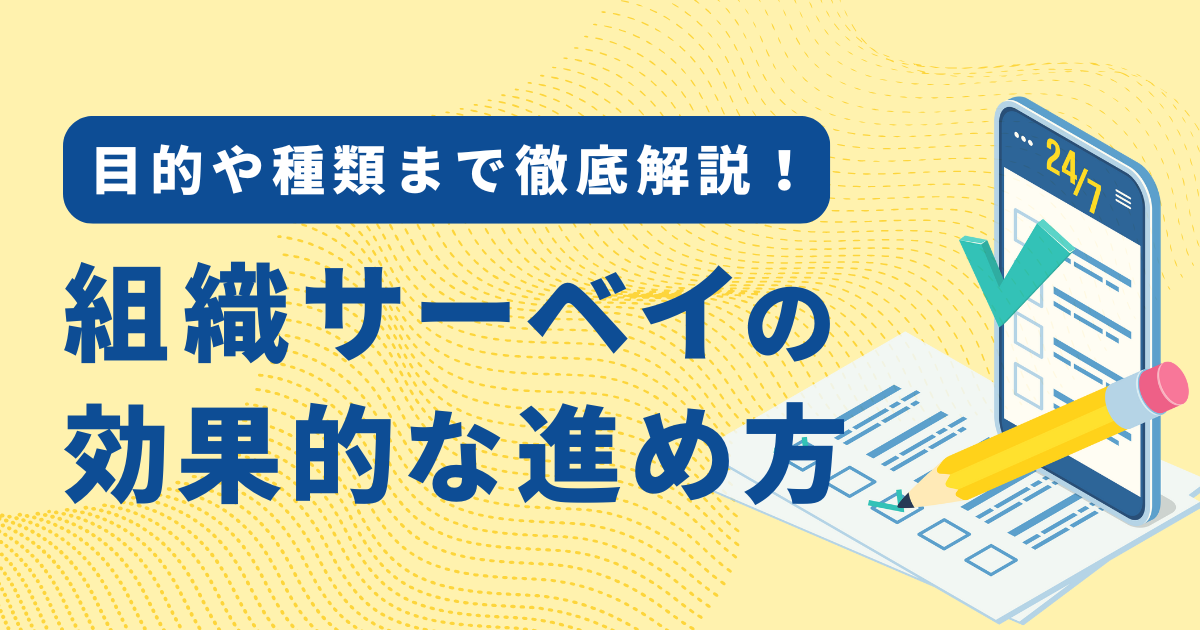
従業員が回答することに負担を感じている
サーベイの質問数が多すぎたり、表現が分かりにくかったり、回答に時間がかかりすぎたりすると、従業員は大きな負担を感じます。
特に、業務の繁忙期に実施されると、「ただでさえ忙しいのに」という不満が高まり、適当な回答や無回答が増える原因となります。
回答の質が低下すれば、得られるデータ全体の信頼性も損なわれ、正確な現状把握が困難になります。
心理的安全性が確保されていない
従業員が「本音で回答すると、誰が回答したか特定されてしまい、人事評価に悪影響が出るのではないか」といった不安を感じている場合、正直な回答は期待できません。
特に、人間関係や上司のマネジメントに関する質問では、当たり障りのない回答に終始しがちです。
このような状態では、組織の真の課題が隠されてしまい、サーベイ本来の目的を達成することはできません。
エンゲージメントサーベイを無駄にしないための5つの活用ポイント
エンゲージメントサーベイを形骸化させず、組織改善に繋げるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
ここでは、サーベイを成功に導くための5つの活用法を紹介します。
目的を明確にし、従業員へ丁寧に説明する
まず最も重要なのは、「なぜサーベイを実施するのか」という目的を明確にすることです。
「離職率の低下」「生産性の向上」「部署間の連携強化」など、具体的なゴールを設定します。
そして、その目的をサーベイ実施前に全従業員に対して丁寧に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。
「サーベイの結果は、より良い職場環境を作るために活用します」という会社の真摯なメッセージが伝われば、従業員も当事者意識を持ってサーベイに臨むことができます。
また、ゴールを達成するのに必要なデータを得るための設問項目を用いることも重要です。
テンプレートの設問を闇雲に使うだけでは、エンゲージメントサーベイを実施すること自体が目的になりかねません。
大事なのは、得たデータをどのように使って組織課題を解決するかです。理想の組織状態を実現するための設問を用いることを意識しましょう。
結果を迅速かつ分かりやすくフィードバックする
サーベイ実施後は、できるだけ速やかに結果を集計・分析し、全社や各部署にフィードバックすることが重要です。
フィードバックの際は、単に数値を羅列するのではなく、グラフや図を用いて視覚的に分かりやすく示す工夫をしましょう。
良かった点と課題点を明確に伝え、会社として結果をどう受け止め、今後どのように活かしていこうと考えているのかを誠実に共有することで、従業員の信頼を得ることができます。
サーベイ結果を基に具体的な改善策を実行する
サーベイで明らかになった課題に対しては、必ず具体的な改善アクションプランを策定し、実行に移します。
よくあるのが、“サーベイだけ取って数字が低いことがわかったので、エンゲージメントを上げるようにしろ”という漠然とした依頼が社内で投げられるケースです。
エンゲージメントという用語自体の抽象度が高いため、戦略的に施策を実行していかなければいつまで経っても状況は改善されません。
施策を考える際は、エンゲージメント向上を妨げている原因を特定し、その原因を解消できるような施策を打ちましょう。
以下の記事では、従業員のエンゲージメントを向上させるための施策と事例について詳しく解説しておりますので、併せてご覧ください。

定期的に実施して継続的な改善サイクルを回す
組織の状態や従業員の意識は常に変化します。一度のサーベイで満足するのではなく、半年に1回、あるいは年に1回など、定期的に実施することが大切です。
継続的にデータを測定することで、前回からの変化を把握し、実行した改善策の効果を検証することができます。
このように、サーベイ→改善→効果測定というPDCAサイクルを回し続けることで、組織は着実に良い方向へ変わっていきます。
従業員が安心して本音で回答できる環境を整える
従業員から本音を引き出すためには、安心して回答できる環境作りが欠かせません。
サーベイは匿名で実施することを徹底し、個人が特定されることは決してなく、回答内容が人事評価などに影響しないことを明確に約束しましょう。
外部の専門機関のサーベイツールを利用することも、中立性・公平性を担保する上で有効な手段です。
心理的安全性が確保されて初めて、サーベイは組織の真の課題を映し出す鏡となります。
“測って終わりにさせない” サーベイツール『ourly survey』

ourly surveyは、自由な設問設計と施策立案・実行までを支援する“測って終わり”にさせないサーベイです。
細かい分析機能で組織課題を可視化
「所属/部署」「役職」「職種」「拠点」などのユーザー属性で回答結果を分析することが可能です。理念の浸透度合いや、エンゲージメントが低い層を見える化できます。
組織課題に応じた自由な設問
従業員エンゲージメントの向上や人事施策の成果測定、ビジョンの浸透度合いの計測など、自社が手に入れたい組織状態から逆算して自由に質問の作成が可能です。
行動データを組み合わせた分析
弊社が提供するweb社内報「ourly」の閲覧行動とサーベイで集計した結果をクロス分析することで、組織改善のサイクルを加速させます。
一気通貫した改善支援
弊社の組織開発コンサルタントが、サーベイで集計した結果をもとに組織課題の特定や改善施策の提案、実行を支援します。
以下の資料では、ourly surveyの具体的な特徴や機能を紹介しています。
サービスの比較や導入のご検討などに、ご活用ください。

エンゲージメントサーベイを導入するメリットとは?
エンゲージメントサーベイを正しく活用すれば、企業にとって多くのメリットが期待できます。
サーベイが無駄ではないことを理解するためにも、その利点を確認しておきましょう。
組織やチームの課題を客観的に可視化できる
日々の業務ではなかなか見えにくい、組織やチームが抱える課題を、サーベイを通じて客観的なデータとして可視化できます。
従業員のモチベーション、人間関係、労働環境、キャリアへの考え方などを定量的に把握することで、感覚的ではなく事実に基づいた課題特定が可能になります。
従業員のモチベーション向上に繋がる
自分の意見が会社に届き、職場改善に活かされるという実感は、従業員のモチベーションを大きく向上させます。
「会社は自分たちのことを見てくれている」という安心感や信頼感が生まれ、仕事へエンゲージメントが高まるのです。
離職率の低下と人材定着が期待できる
サーベイを通じて従業員の不満やストレスの要因を早期に把握し、改善策を講じることは、離職防止に直接的な効果があります。
働きがいのある職場環境を整えることで、優秀な人材の流出を防ぎ、長期的な人材定着を実現できます。
企業の生産性向上に貢献する
従業員エンゲージメントと企業の業績には強い相関関係があることが、多くの調査で明らかになっています。
エンゲージメントの高い従業員は、自身の業務に誇りと情熱を持ち、自発的に創意工夫を行うため、結果として組織全体の生産性向上に大きく貢献します。
エンゲージメントサーベイを効果的に実施する流れ
エンゲージメントサーベイを成功させるためには、計画的な準備と実行が不可欠です。
ここでは、効果的な実施の流れを6つのステップで解説します。
手順1:目的の設定と従業員への周知
まず、「何のためにサーベイを行うのか」という目的を明確にします。
その上で、実施目的、スケジュール、結果の活用方法などを全従業員に事前に丁寧に説明し、理解と協力を求めます。
手順2:実施計画の策定と質問項目の設計
目的に合わせて、実施時期、対象者、頻度などを決定します。
質問項目は、目的達成に必要な情報を得られるように設計しますが、従業員の負担を考慮し、数を絞り込むことも重要です。
手順3:サーベイの実施
定めた計画に沿ってサーベイを実施します。
実施期間中は、回答を忘れている従業員に適度なリマインドを行い、回答率を高める努力も必要です。
手順4:結果の集計と分析
回答期間が終了したら、速やかにデータを集計し、分析作業に入ります。
全社、部署別、役職別など、様々な切り口で分析を行い、組織の強みと課題を客観的に抽出します。

手順5:改善アクションプランの策定と実行
分析結果に基づき、具体的な改善アクションプランを策定します。
現場の従業員の意見も取り入れながら、現実的で効果的なプランを作り、責任者と期限を明確にして実行に移します。
手順6:効果測定と次回のサーベイへの反映
改善アクションを実行した後、その効果がどうであったかを次回のサーベイで測定します。
良かった点は継続し、課題が残る点は新たな改善策を検討するなど、PDCAサイクルを回し続けることが組織の継続的な成長に繋がります。
まとめ
エンゲージメントサーベイは、ただ実施するだけでは「無駄」な施策に終わってしまいます。
重要なのは、明確な目的意識を持ち、従業員との対話を大切にしながら、得られた結果を真摯に受け止め、具体的な改善行動に繋げていくことです。
本記事で紹介した活用ポイントや実施フローを参考に、形骸化したサーベイから脱却し、従業員一人ひとりが働きがいを感じられる、より良い組織作りのための有効なツールとしてエンゲージメントサーベイを活用してください。