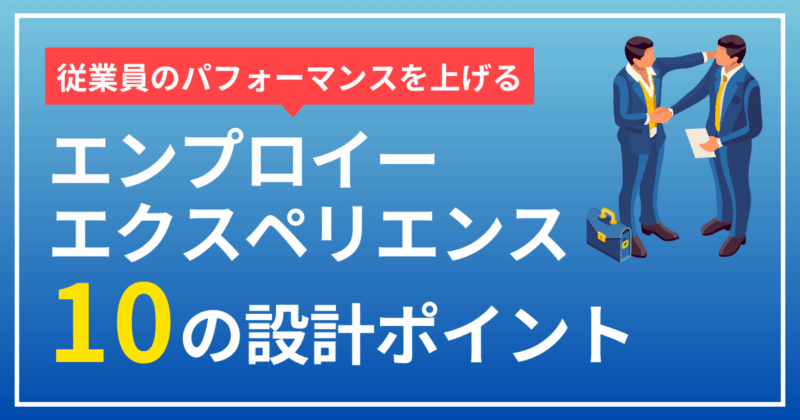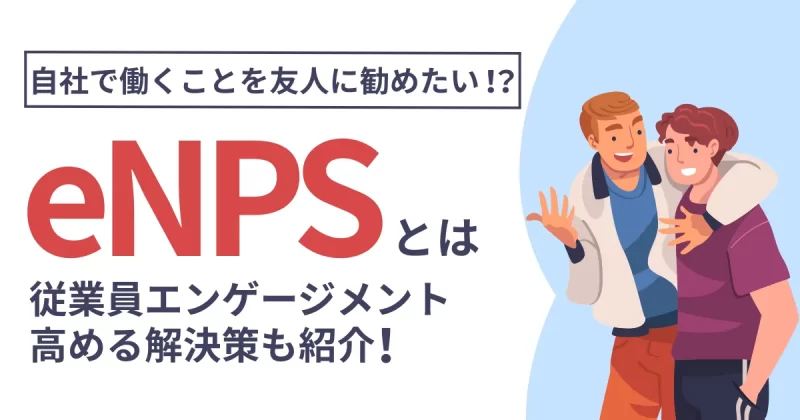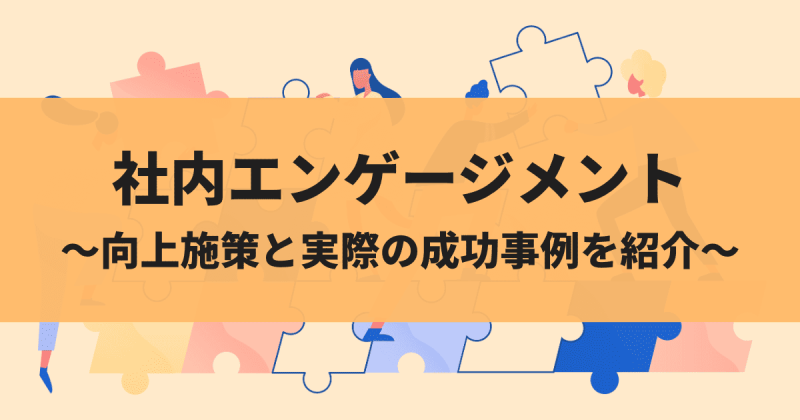「優秀な人材が定着しない」「社内のエンゲージメントが低下している」「人的資本開示に向けて具体的な数値改善が必要」、 こうした課題に直面する企業は多いのではないかと思います。
ただ、魅力的なオフィス環境や充実した福利厚生などを整えても、それが企業の本質的な価値観とつながっていなければ、一時的な満足度向上にとどまり、真のエンゲージメント向上には至りません。
本記事では、人材の採用・定着・育成に対して一貫性を持たせ、従業員エンゲージメントを高めるために、「エンプロイーエクスペリエンス」と「エンプロイージャーニーマップ」について解説します。特に「組織文化」を軸にした一貫性のあるエンプロイーエクスペリエンス設計の考え方と具体的な実践方法をご紹介します。
エンプロイーエクスペリエンス(EX)とは
エンプロイーエクスペリエンス(Employee Experience:従業員体験、通称EX)とは、従業員が組織内で経験する、すべての体験を包括した概念です。具体的には、採用活動における最初の接触から退職までの全プロセスにおける体験が含まれます。
従来、企業は従業員満足度(Employee Satisfaction)の向上を目指してきましたが、エンプロイーエクスペリエンスはより広範な視点から、従業員の体験全体を設計する点で異なります。福利厚生や報酬制度など、環境や待遇面の改善にとどまらず、企業文化や価値観との一致感、業務内容の意義、成長機会など、多角的な要素を含んだ包括的な概念です。
エンプロイーエクスペリエンスはエンゲージメントを高める主要因の一つと考えられます。
そのため、優れたエンプロイーエクスペリエンス設計が、結果として従業員エンゲージメントの向上をもたらし、それが組織パフォーマンスの向上につながると言えるでしょう。

カルチャーフィット(組織文化との適合)がエンプロイーエクスペリエンスを高める理由
エンプロイーエクスペリエンスを向上させる上で、組織文化との適合性(カルチャーフィット)が重要といわれています。その本質的な理由は、自身と企業の「期待値の一致」にあります。
期待値の一致がもたらすパフォーマンス向上
組織文化とは、企業内で「当たり前」とされている行動様式や思考パターン、価値判断基準です。多くの場合、これらは明文化されていない暗黙の了解として存在します。
例えば、
・意思決定の方法(トップダウンか分散型か)
・コミュニケーションのスタイル(率直さを重視するか調和を重視するか)
・リスクに対する姿勢(挑戦を奨励するか安定を重視するか)
・成功の定義(短期的成果か長期的価値か)
などです。
これらの暗黙的な期待値と個人の価値観や行動様式が一致していれば、従業員は自然体で力を発揮できます。逆に、大きな乖離があれば、常に自分本来の思考や行動を抑制・修正する必要が生じて、無駄なエネルギーを消費します。
組織心理学の研究では、カルチャーフィットが高い従業員に次のような効果が確認されています。
心理的負担が少ない
「感情労働」の研究によれば、自分の価値観と組織の期待が一致していると、感情や行動を偽る必要がなく、「表層演技」による精神的消耗が減少します。
意思決定の効率が向上する
「組織文化プロファイル」研究では、個人と組織の価値観の一致度が高いほど、意思決定プロセスが効率化されることが示されています。これは、共有された価値観が意思決定の「フレーム」として機能するためです。
エネルギーをコア業務に集中できる
人間の認知リソースには限りがあります。「真正性(真の自己と行動や価値観が一致している状態)」が高い環境では、行動規範の解読に使われるはずだった認知リソースを本質的な業務に振り向けられることが確認されています。
ストレスレベルが低下する
個人と組織の適合度が高いほど職務満足度が高く、ストレスレベルが低いことが実証されています。特に、価値観の一致は職務満足度と強い相関を示しました。
「心理的契約」の観点から見たカルチャーフィット
組織心理学では、従業員と企業の間に存在する明文化されない期待の集合を「心理的契約」と呼びます。
この概念は、正式な雇用契約とは別に存在する暗黙の了解事項で、双方の期待と義務を含みます。
カルチャーフィットの高い従業員は、この心理的契約の理解と受容がスムーズです。
入社前から企業の価値観や行動規範を正確に理解し、それに共感している状態であれば、入社後の「心理的契約違反(psychological contract breach)」の認識が生じにくくなります。
反対に、カルチャーフィットが低い場合、心理的契約「違反」を感じる頻度が高まります。
心理的契約違反の認識は、信頼の低下、職務満足度の低下、組織コミットメントの低下、離職意図の上昇と強く関連していることが示されています。つまり、カルチャーフィットの低さは心理的契約違反を通じて、最終的には離職につながりやすくなるといえます。
エンプロイージャーニーマップを用いた体験設計
エンプロイージャーニーマップとは、従業員が入社から退社するまでの経験を「一連の旅」と仮想して、その長い時間軸のなかでの従業員体験を、社員目線で図示化したものです。

従業員のライフサイクルごとに施策を整理しますが、その際に、「企業の組織文化・価値観をどう体験してもらうのか」という視点を加えることで、より効果的なエンプロイーエクスペリエンス設計が可能になります。
ここでは、主要4フェーズ(採用・オンボーディング・育成・退職)それぞれについて、エンプロイーエクスペリエンスの設計ポイントを解説します。
採用フェーズ:カルチャーフィットを採用基準に組み込む
カルチャーフィット採用とは、スキルや経験だけでなく、組織の価値観や文化との適合性を重視した採用アプローチです。これがエンプロイーエクスペリエンスの起点となる理由は次の3点です。
1.ミスマッチの早期解消
自社の価値観と合わない人材は選考プロセスで辞退が促進されるため、入社後の期待ギャップによる離職を防止できる。
2.高いエンゲージメント状態でのスタート
応募者自身が組織文化に共感して自ら選んで入社することで、高いエンゲージメントがスタート時点から期待できる。
3.組織文化の強化
価値観を共有する人材が組織内に増えることで、長い目で見れば組織文化が強化され、好循環が生まれる。
Netflixのカルチャーデックに学ぶ
Netflixのカルチャーデックは、Netflixが求める企業文化をまとめた資料です。それを採用広報にも活用することで、入社前のフィルタリング、期待値調整に役立っています。カルチャーデックでは以下のような事が語られています。
価値観の明確化
「自由と責任」などの核となる価値観を具体的な行動と結びつけて定義
才能密度の重視
「普通の人材より優秀な人材は2倍ではなく10倍の価値がある」という信念
率直なフィードバック
「相手の面前で言えないことは、背後でも言わない」という誠実さの重視
高業績か寛大な退職パッケージか
平均的なパフォーマンスでさえ許容せず、組織文化に適合しない人材への明確な対応
Netflixのカルチャーデックはこちらをご覧ください。
自社でカルチャーフィット採用を実践するステップ
カルチャーフィット採用を自社に取り入れるための具体的なステップを以下に示します。
1. 理念を行動レベルに翻訳する
抽象的な企業理念やバリューを、日常の業務で実践できる具体的な行動指針に落とし込みます。
各バリューに対して「こういう行動が重視される」「こういう行動は期待されない」を明文化。また実際のエピソードを集め、「この判断は当社のこの価値観から来ている」と説明できるストーリーを蓄積します。
2. 価値観に紐づく選考質問を設計する
STAR面接法(Situation、Task、Action、Result)をベースに、その人の価値観が現れるような質問を設計します。
例「チームワーク」を重視する企業:「チームの意見が分かれた時、どのように合意形成に貢献しましたか?」
例「挑戦」を重視する企業:「従来のやり方を変革して成果を出した経験を教えてください」
3, 採用広報コンテンツとして開示する
自社の文化や価値観をまとめたコンテンツを自社サイトや外部採用広報サイトに掲載して、共感する候補者を引き寄せる取り組みを行います。
入社~オンボーディングフェーズ:自社の組織文化を体感する
入社して時間が空かないうちに、組織文化や価値観を体験し、自分ごと化してもらうことが重要です。このフェーズでは、抽象的な価値観を具体的な行動や体験に落とし込み、新入社員の「腹落ち」を促進する施策アイデアをご紹介します。
全社横断での現場体験
入社後の一定期間を配属部門以外での現場体験にあてます。自社の顧客提供価値を実感できる部門や、価値観の体現度合いが高い社員がいる部門で業務をすることで、会社の理解度を上げるとともに、自社の組織文化を浸透させます。
価値観体験ワークショップ
自社が掲げる価値観について、「日常業務でどのように実践されるか」をケーススタディやロールプレイで体験するワークショップを実施します。具体的な行動レベルに落とし込むことで、理解を促進させます。
カルチャーメンター制度
組織文化の体現度合いが高い先輩社員をメンターとして割り当てて定期的な1on1の機会を設けます。「この会社ではどんな事が求められるのか」などの暗黙知の共有を促す事でパフォーマンス向上を図ります。
育成フェーズ:組織文化の体現を称賛する
従業員の長期的な成長とエンゲージメントを支えるのが育成フェーズです。個人の業務成果だけでなく、その成果を生む行動が組織文化を体現しているかにも着目してフィードバックを行うことがポイントです。
バリューベースの360度評価
組織文化をどれだけ体現できているかを上司からだけでなく、同僚や部下など多角的にフィードバックする手法です。人事考課ではなく、成長を支援する取り組みという位置づけで実施するのが良いでしょう。
360度評価の導入ステップや事例についてはこちらもご覧ください。
バリュー体現者へのポイント制度
組織文化や価値観を体現する行動や貢献に対して、ポイントを付与したり称賛したりすることで、本人のモチベーションを高め、また周囲にもどのような行動が称賛に値するのかを伝えます。ただし、金銭報酬目的にならないような設計は必要です。
外発的動機づけ(金銭報酬など外的報酬)の注意点についてはこちらをご覧ください。
退職フェーズ:アルムナイとしての関係継続
退職は従業員ライフサイクルの終わりではなく、新たな関係の始まりと捉えるべきです。労働人口が減少していく日本においては、退職者ともつながり続けることで出戻りやリファラル紹介の可能性が高まります。
アルムナイ・コミュニティ
退職者を「卒業生(アルムナイ)」としてつながり続ける専用コミュニティを構築し、企業の価値観に共感するOB/OGのネットワークを維持します。定期的な情報提供やイベントで関係を継続し、出戻りやリファラル紹介の機会を創出します。
退職者インタビュー
退職者インタビューを実施して、在籍中に特に印象に残ったバリュー体現エピソードなどを社内報記事として残します。退職者が自社の企業文化を語ることは、新入社員にとってもポジティブであり、また退職者自身も良い印象を持って自社を退職することができます。
エンプロイージャーニーマップ作成の流れとポイント
上記フェーズを踏まえて、カルチャーフィットを軸としたエンプロイージャーニーマップの作成プロセスは以下の通りです。
エンプロイージャーニーマップは一度作って終わりではなく、定期的に実際の体験データを収集し、継続的に改善していくことが重要です。特に価値観フィット感の観点からは、社員の声を丁寧に聴き、現実の体験と理想の体験のギャップを常に把握することが成功の鍵となります。
フェーズごとの現状の体験把握
各フェーズでの体験を従業員インタビューやサーベイで収集。特に価値観フィットが高い/低い従業員の体験談を比較、分析する。
理想体験の設計
各タッチポイントで「この価値観をどう体験させるか」を具体化する。
ギャップの特定
企業の掲げる価値観と、実際の従業員体験のギャップを可視化。
実行計画の策定
優先度の高いタッチポイントから改善施策を立案、実行する。
事例①Netflix:カルチャーデックを採用の中心に
Netflixは採用ページに自社のカルチャーデックを明示し、応募者自身がカルチャーフィットするかどうか確認することを促しています。
同社によると「カルチャーデックの公開後、応募数は絞られたが、オンボーディング後の活躍率は大幅に向上した」とのことです。
また、同社は「キーパーテスト」という独自の評価基準を設け、「もしこの社員が退職を申し出たら、全力で引き止めるか」という観点でマネージャーに定期的な評価を促しています。この徹底したカルチャーフィット重視の姿勢が、高い従業員エンゲージメントと市場での成功を支えています。
事例②Zappos:カルチャーインタビューの徹底
オンライン靴販売で知られるZapposは、採用プロセスに独自の「カルチャーインタビュー」を組み込んでいます。これは通常の業務適性とは別に、同社の10個のコアバリューとの適合性だけを評価するもので、この評価が低ければ、どれほど優秀な人材でも採用しない方針を貫いています。
さらに特筆すべきは「入社後1ヶ月の研修終了時に、合わないと感じたら退職金を受け取って辞めることができる」という”The Offer“と呼ばれる制度です。この仕組みによって、文化に適合しない人材の早期離脱を促し、結果として組織全体のエンゲージメント向上につなげています。
事例③メルカリ:バリューを体現する行動の可視化
メルカリは「Go Bold(大胆にやろう)」「All for One(全ては成功のために)」などの企業バリューを、具体的な行動レベルで定義し、それを採用基準に組み込んでいます。
特に注目すべきは、四半期ごとに行われる「バリューアワード」で、各バリューを最も体現した社員を表彰する取り組みです。このような可視化によって、抽象的になりがちな価値観を日常の行動に落とし込み、新入社員も「自分もこういう行動を目指そう」というロールモデルを得ることができます。
また、入社時に全社員が参加する「バリューブートキャンプ」を通じて、企業理念への共感と実践をサポートしています。
カルチャーフィットから始めるエンプロイーエクスペリエンス革新
エンプロイーエクスペリエンスの向上は、単なる福利厚生の充実や職場環境の改善にとどまらず、企業文化との適合性を起点に考えることで、より本質的な効果を生み出します。
カルチャーフィット採用を起点に、エンプロイージャーニーマップに「価値観との適合」という視点を加え、一貫した体験を提供することで、真の従業員エンゲージメント向上が実現できます。
人的資本開示が求められる現代において、目に見えやすい環境改善だけではなく、組織文化や従業員体験の質を高める取り組みこそが、持続的な企業価値向上の鍵となるでしょう。
ぜひ本記事を参考に、独自のカルチャーフィットを起点としたエンプロイーエクスペリエンス戦略を構築してみてください。