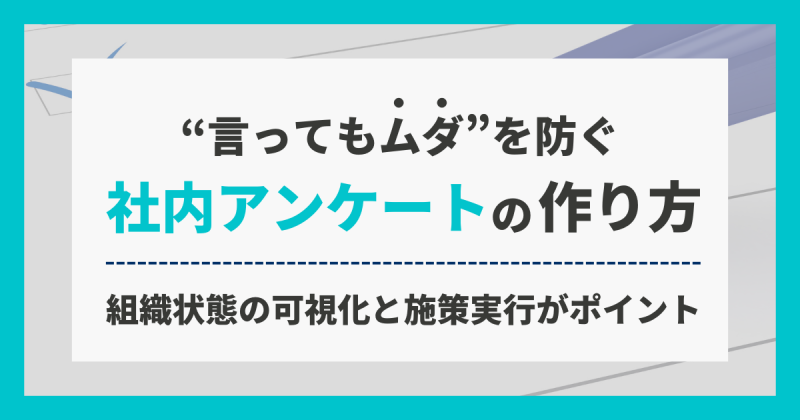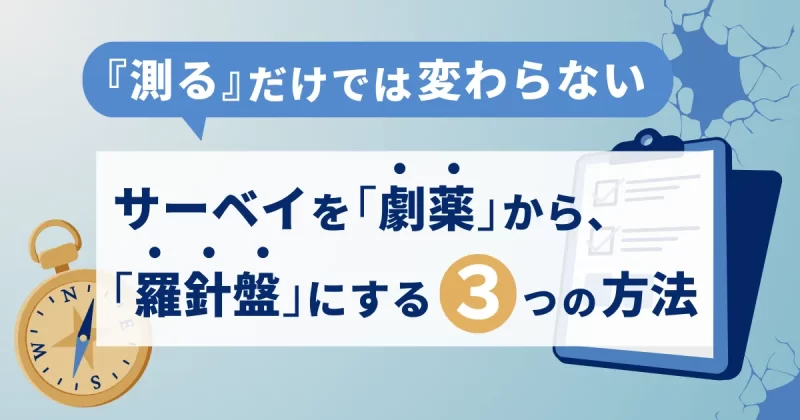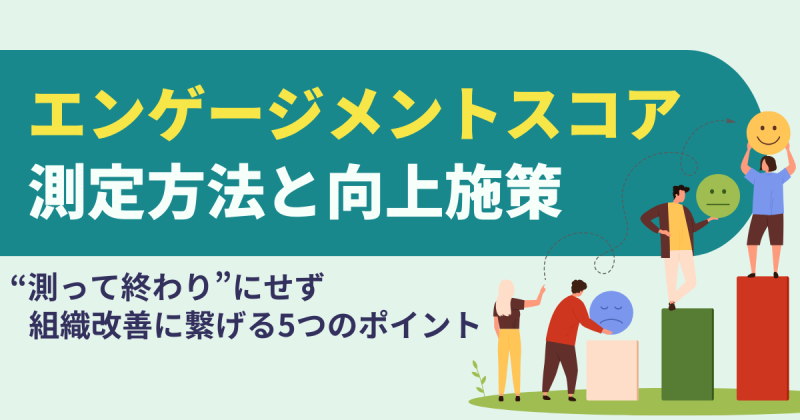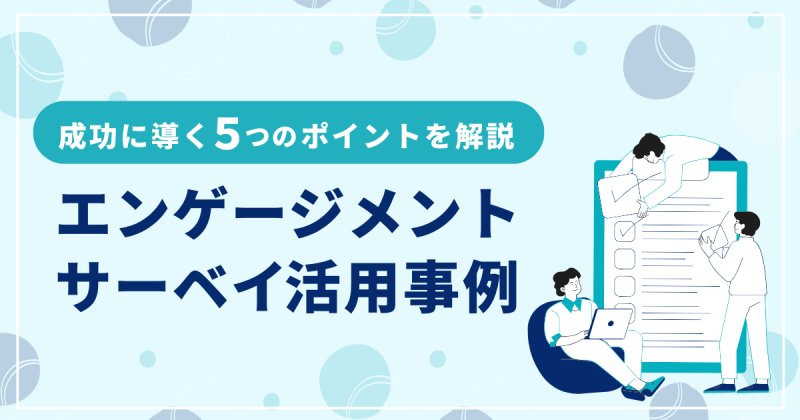社内アンケート(従業員満足度調査)とは、職場や従業員の現状把握を主な目的として行われる調査です。
雇用の流動性や多様な働き方に注目が集まる中、社員の本音を把握して今後の組織改善に生かしたいと考える経営者や責任者は多いのではないでしょうか。
この記事では、
- 社内や部署内の状況を把握して課題解決につなげたい
- 効果的な社内アンケートを実施したい
- 社内アンケートを進める上での注意点を知りたい
このような方々のニーズに役立つよう、社内アンケートの目的や本音を回答してもらうポイントを解説します。
社内アンケート(従業員満足度調査)とは?
社内アンケートとは、自社で勤務する社員を対象にした、アンケート調査の総称です。
多くは職場環境の現状や、会社に対する満足度を測る目的でおこなわれます。従業員満足度調査(ES調査)と、同義であるといっても差し支えないでしょう。
社員の満足度を測ることは、組織状態の現状把握につながります。まず現状を知ることで、組織が抱える課題を明確にしていきます。その上でコミュニケーションの活性化などの組織改善をおこない、より働きやすい職場を構築しなくてはなりません。
社内アンケートは、働く社員の満足度を向上させ、定着を図る取り組みに欠かせないものといえるでしょう。

従業員の本音を把握する重要な手段
社内アンケートは、従業員が会社や仕事、職場環境に対して抱いている意見や感情(本音)を、体系的に収集するための調査です。
日常業務の中ではなかなか表面化しにくい、人間関係の悩み、業務プロセスの非効率さ、キャリアへの不安といった潜在的な課題を可視化することができます。
経営層や人事部門がこれらの課題を客観的に把握し、具体的な改善策を講じるための第一歩となる、非常に重要な手段です。
各種サーベイとの違い
サーベイとは、社員アンケートを調査対象や目的別に細分化したものを指します。代表的なものが「モラールサーベイ」です。モラールサーベイは社員の士気(モラール)に着目し、社員のパフォーマンスに影響している要素を把握するためにおこなわれます。
社員アンケートはこうした各種サーベイの要素を包括し、従業員の満足度を調査するものです。従業員満足度調査(ES調査)と同義であり、昨今注目を集めています。
会社に対する満足度が社員のモチベーションに直結し、ひいては組織力や業績の向上につながるという考えが一般的になりました。こうしたことが、注目を集める背景にあるとされます。

なぜ今、社内アンケートが重要なのか
現代のビジネス環境は、働き方の多様化や価値観の変化により、かつてないほど複雑になっています。このような状況下で企業が持続的に成長するためには、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境を整えることが不可欠です。
社内アンケートは、そのための具体的なアクションに繋がるヒントを与えてくれます。従業員の声に耳を傾け、組織の課題解決に取り組む姿勢を示すことは、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高め、結果として生産性の向上や顧客満足度の向上にも繋がっていくのです。
社内アンケートの質問項目と20の質問例
社員アンケートにより、正確に従業員満足度を把握するためには、質問の精度を上げる必要があります。
調査項目(質問内容)を設定する際に参考にすると良いのが、「二要因理論」です。
「満足」に関わる要因は「動機づけ要因」であり、「不満足」に関わる要因は「衛生要因」の2つに分けられるとする理論です。
動機づけ要因とは、達成感や承認といった、「満足感」に影響する要素を指します。衛生要因は、職場環境や給与面の待遇など、「不満」に影響する要素です。
この2つの要素を明確に分け、バランス良く構成することで、アンケートの精度が向上します。
基本情報
基本情報は、アンケート対象者の属性を明らかにする項目です。どのような属性で傾向を分析したいのか、明確にした上で項目を設定します。具体的には以下が挙げられます。
- 性別
- 年齢
- 役職
- 所属部署
- 勤続年数
調査目的を再度確認し、把握が必要な調査項目に漏れがないように設定します。
業務内容
業務内容に関する質問は、達成感や承認などの「動機づけ要因」に関わるものです。仕事のやりがいや、モチベーションの状態を測る質問を設定すると良いでしょう。
質問例
- 仕事にやりがいを感じますか
- 現在担当している仕事は自分の適性と合っていますか
- 仕事で達成感や満足感を得られますか
企業方針
企業方針についての質問は、会社の運営方針や経営状況に関する項目です。経営陣に対する満足度を問う質問といっても差し支えないでしょう。衛生要因に関わる質問であり、会社への愛着やロイヤリティに影響する項目といえるでしょう。
質問例
- 企業理念や経営方針に共感できますか、またその実現に向け努力できるものですか
- 会社の業績(収益性・成長性・安定性)に満足できますか
- 経営に関する情報をタイムリーに知ることができていますか
処遇
処遇に対する質問は、衛生要因の代表的なものです。給与や賞与といった金銭的報酬は生活に直結するため、不満につながる大きな要素といえます。
また、処遇に連動する人事評価や、キャリア開発に関わることも、この項目に含まれます。
質問例
- 現在の給与は自身の仕事内容と実績に見合ったものですか
- 人事評価制度で、自身は正当に評価されていると感じますか
- 現在のキャリア開発の仕組みは充実していると思いますか
心身の状況
心身の状況に関する質問は、現在の業務負荷を把握するための質問です。衛生要因に関するもので、過重労働により心身に影響が出ていないか、ワークライフバランスを保てているかといったことを確認します。ストレスやハラスメントについての質問も、この項目に含むと良いでしょう。
質問例
- 現在の業務量・業務の質は心身の健康に悪影響を及ぼしていませんか
- 現在の担当業務は精神的に余裕をもってこなせますか、ストレスになっていませんか
- 仕事上の悩みを解決する方法をもっていますか
総合的な満足度
会社全体に対する満足度を問う質問です。これまでの質問にから導き出された、総合的な満足度を答えてもらいます。自身の満足度だけでなく、「家族へ誇れるか」といった、切り口を変えた質問も織り交ぜると良いでしょう。
質問例
- この会社で働くことに満足していますか
- 友人や知人にこの会社で働くことを勧めても良いと感じていますか
- この会社の一員であることを家族や友人に自信をもって誇れますか
社内アンケートで本音を引き出すポイント
アンケートに回答する際、評価への影響を考えて、ネガティブな回答を避ける社員がいるかもしれません。また、何を訴えても変わらないという諦めから、当たり障りのない回答に終始することも考えられます。
社員の本音(実情)が反映されないアンケート結果であれば、正確な現状把握はできず、改善は的外れなものになってしまいます。
アンケートが無駄になるばかりでなく、「会社は何も分かっていない」という諦めの感情を抱かせてしまうかもしれません。
こうした事態を回避するために、社員アンケートは「本音の回答」をしてもらうための工夫が必要になります。
バイアスの回避
回答結果に影響を及ぼしやすいと考えられるバイアスは、以下の3つです。
- 確証バイアス:経営層や上司が望むであろう回答を選択してしまう
- ソーシャルバイアス:社会道徳の観点から、「誰もがこうするべき」とする回答を選択してしまう
- 正常性バイアス:自己評価が甘く、自身の普段の行動と違う回答を選択してしまう
こうしたバイアスを回避するには、「回答に正解がないこと」「素直な回答を求めること」「回答は評価に影響しないこと」を明示して、安心感をもってもらうことが大切です。
適切な設問量
設問の分量にも注意する必要があります。より具体的なデータを収集したいと考えるほど、設問内容は細分化し、ボリュームが増えていきます。
膨大な設問量は回答者の意欲を削ぐものです。負荷がかかりすぎると、回答結果の正確性に影響が出るかもしれません。
アンケートを作成する際は、テーマを広げすぎないことが大切です。「あれもこれも解決したい」と欲張ることなく、優先的なテーマを絞り、必要な情報を取捨選択すると良いでしょう。
答えやすい聞き方
アンケートの依頼文や設問文の工夫が、素直な回答を引き出すことにつながります。
例えば、ビジネス的な文章は避けて、度を過ぎない程度に砕けた調子にすることで、回答しやすい印象になります。「会社にとって都合の悪い回答も真摯に受け止める」といった姿勢を、明示することも効果的でしょう。
回答者が設問の意図を深読みする可能性も、考慮する必要があります。「こう回答して欲しいのだろうな」と、回答者を誘導するような設問も避けなくてはなりません。
回答の心理的安全性を確保する
従業員が本音で回答するためには、「不利益な評価に繋がるのではないか」という不安を取り除くことが最も重要です。
アンケートは匿名で実施することを原則とし、個人が特定できるような質問の仕方は避けましょう。また、結果の取り扱いについても、「回答は統計的に処理され、個人が特定されることは一切ありません」と明記し、心理的安全性を確保することを約束します。
アンケートの目的と結果の活用方法を明示する
「このアンケートが、自分たちの働く環境をより良くするために行われる」という目的が明確に伝われば、従業員の協力意欲は高まります。
なぜ今このアンケートを実施するのか、そして集まった意見を基に、会社としてどのように改善に取り組んでいくのか、その道筋を具体的に示しましょう。アンケート実施後には、必ず結果の概要と改善策をフィードバックすることが不可欠です。
社内アンケートを実施する際の注意点
効果的な社内アンケートの実施には、さまざまな注意点があります。まず、目的が明確ではないアンケートは、警戒心を抱かせ本音の回答を導けません。
回答内容により不利な取り扱いを受けないといった、安心感に対する配慮も必要です。アンケート結果が公表されず、結果が生かされていないといった印象を抱かせてしまうと、不信感につながるでしょう。
明確な目的設定
アンケートを実施する際は、どのような課題の解決につなげたいのか、目的を明確にすることが必要です。目的が曖昧であれば効果が薄れるだけでなく、従業員に不信感を与える恐れもあります。
また、アンケートは理想の組織像を実現するために現状を把握する手段でもあります。形式的なテンプレートに頼らず、自社の事業モデルや目指す組織像から逆算した設問設計が重要です。
中立性と公正性
社員アンケートは、経営者に社員の「生の声」を直接届けるものです。会社側の都合ばかりを考えたアンケートでは、正確な情報を収集できません。社員アンケートは中立性の確保が前提となります。
また、内容によっては匿名での記入を検討する必要があります。アンケートの目的がデリケートな内容の場合は、特に配慮しなくてならないでしょう。
記名式の場合は、回答内容を目的外利用しないことや、機密性の確保を明示することも必要です。
安心して回答できるように、公正性が確保されていることを示さなくてはなりません。
組織改善に活用
社員アンケートが逆効果になるのは、アンケート結果が公表されなかったり、改善につながる施策が見られなかったりするケースです。結果的に、マネージャーや現場社員が「人事がまた何かやっている」「言っても無駄」といったスタンスになり、エンゲージメントの低下を招く可能性があります。
アンケート結果を会社が真摯に受け止め、組織改善を図ることで社員は会社に期待をもつようになります。自分たちの声が改善につながったという実感は、エンゲージメント向上に大きく作用するでしょう。
“測って終わり”にさせない『ourly survey』
ourly surveyは組織課題の解決に向けた最適な施策を選定し、理想の組織文化を築く新しいツールです。
自社が手に入れたい組織状態から逆算した自由な設問作成と、サーベイで得られた数値からの改善施策の提案・実行が強みです。
こちらでは、ourly surveyの具体的な特徴や機能を紹介しています。サービスの比較や導入のご検討などに、ご活用ください。

まとめ|社員アンケートを生かして社員満足度を高めよう
組織の現状把握や課題抽出には、社員アンケートにより現場の「生の声」を集めることが効果的です。しかし、やり方を間違えると逆効果になるため、注意が必要です。
目的や回答の取り扱いを明確にし、社員の心理的安全性を高めなければ、望むような結果は得られません。また、会社が良い方向に進んだことを実感できなければ、不信感にもつながるでしょう。
社員アンケートは、組織改善に向けた会社の強い意思と誠実で真摯な姿勢が伴って、はじめて効果を発揮するのではないでしょうか。