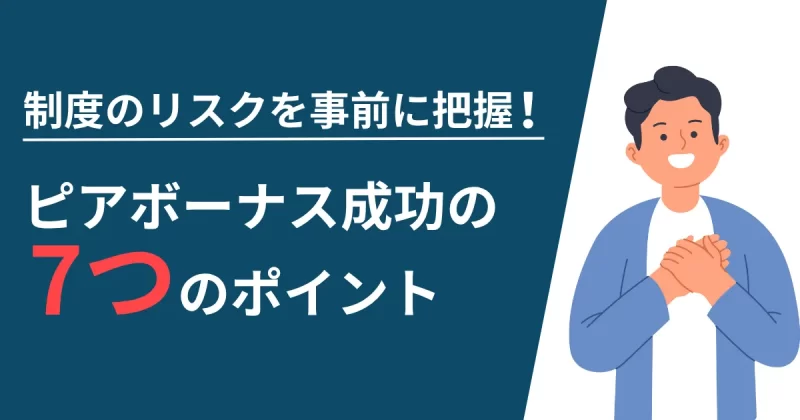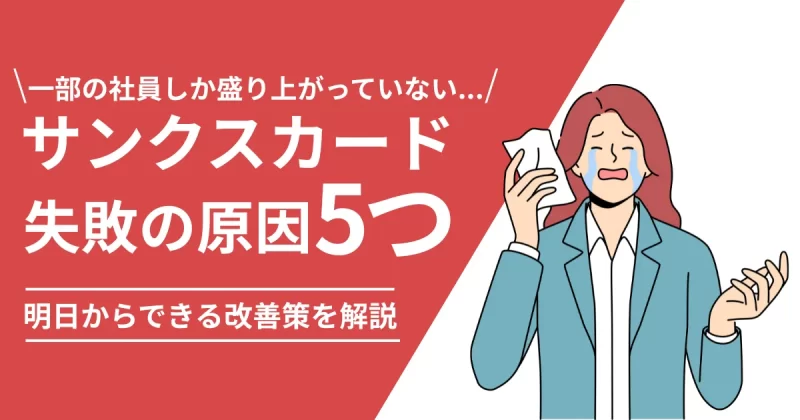従業員同士が感謝や称賛を送り合うピアボーナス制度は、社内のコミュニケーションを活性化させ、エンゲージメントを高める有効な手段として注目されています。
しかし、その一方で「導入したものの、うまく機能していない」という声も少なくありません。
制度が形骸化したり、かえって従業員の不満を招いたりするケースも見られます。
本記事では、ピアボーナスが失敗に終わる原因を深掘りし、実際の事例を交えながら、制度を成功に導くための具体的なポイントを7つに分けて詳しく解説します。
ピアボーナスが失敗する5つの主な理由
ピアボーナス制度が期待通りに機能しない背景には、いくつかの共通した理由が存在します。
設計や運用段階での小さなつまずきが、制度全体の失敗につながることも少なくありません。ここでは、特に多く見られる5つの失敗理由について解説します。
導入の目的が曖昧で浸透しない
なぜピアボーナスを導入するのか、その目的が従業員に明確に伝わっていないケースは失敗の典型です。
「他社で流行っているから」「何となく良さそうだから」といった曖昧な理由で導入すると、従業員は何を基準に行動すれば良いのか分からず、制度の利用が進みません。
目的が共有されていないと、単なる人気投票や、お気に入りの同僚へのポイント配分に終始してしまい、本来目指すべき組織文化の醸成には繋がりません。
評価の基準が不公平で形骸化する
どのような行動が称賛され、ボーナスの対象となるのか、その基準が不明確だと従業員の間に不公平感が生まれます。
例えば、声の大きい人や目立つ部署の従業員にばかりボーナスが集中し、縁の下の力持ち的な貢献が見過ごされるといった事態です。
このような状況が続くと、多くの従業員は制度への信頼を失い、参加意欲が低下します。結果として、ごく一部の従業員だけが利用する形骸化した制度になってしまいます。
一部の人だけで利用され疎外感が生まれる
特に導入初期に起こりがちですが、普段から仲の良いグループ内でのみピアボーナスが交換され、他の従業員が輪に入れない状況も失敗の原因です。
これではコミュニケーションの輪を広げるどころか、既存の人間関係を固定化し、疎外感を生むことになりかねません。
全社的なコミュニケーション活性化という目的とは裏腹に、社内に見えない壁を作ってしまうリスクがあります。
運用が手間になり本業を圧迫する
ピアボーナスの投稿や承認プロセスが複雑すぎると、従業員の負担となり、利用されなくなっていきます。
「感謝を伝えるために、長い文章を書かなければならない」「専用のアプリを立ち上げるのが面倒」といった小さなストレスが積み重なると、従業員は次第に制度から離れていきます。
感謝を伝えるというポジティブな行動が、いつの間にか「やらなければならない面倒な作業」に変わってしまい、本業を圧迫するようでは本末転倒です。
経営層や管理職が非協力的
従業員同士の制度だからといって、経営層や管理職が関与しない姿勢でいると、制度の重要性が社内に伝わりません。
役職者が制度に関心を示さなかったり、全く利用しなかったりすると、従業員も「会社は本気ではないんだな」と感じ、次第に利用しなくなります。
特に管理職が部下の見えない貢献をピアボーナスを通じて認識し、評価するという姿勢を見せることが、制度の信頼性を高める上で不可欠です。
ピアボーナス制度を成功させる8つのポイント
失敗事例から学べるように、ピアボーナス制度を成功させるには、慎重な計画と運用が不可欠です。
ここでは、制度を形骸化させず、組織に良い影響を与えるための8つの重要なポイントを解説します。
| ポイント | 概要 | 実施内容の例 |
| 1.コミュニケーションの土台を整える | 信頼関係と心理的安全性のある職場環境を整える。 | 定期的な1on1や社内イベントを通じて社員同士の仲を深める |
| 2.目的の明確化 | なぜ導入するのかを具体的に定義し、共有する | 「部門間の連携強化」「新人へのサポート文化の醸成」など |
| 3.ルールの透明化 | 誰でも理解できる公平で分かりやすいルールを作る | ポイントの上限設定、評価基準の公開、ポジティブな行動の具体例提示 |
| 4.経営層の参加 | 役員や管理職が率先して制度を利用する姿勢を見せる | 全社会議で役員が部下に感謝を伝える、管理職が部下の投稿にコメントする |
| 5.推進チームの設置 | 各部署からメンバーを選出し、利用促進の旗振り役を担う | 利用方法のレクチャー会開催、月間MVPの選出企画 |
| 6.ポジティブ事例の共有 | 心温まる投稿や良い影響を与えた投稿を社内報などで紹介する | 「今月のベストサンクス」として投稿内容と背景を共有する |
| 7.ツールの選定 | 従業員が日常的に使うツールと連携できるなど、手軽さを重視する | チャットツール上で完結するサービス、スマホアプリで簡単に投稿できるツールを選ぶ |
| 8.定的な改善 | アンケートなどで従業員の意見を収集し、制度を常に見直す | 半年に一度、利用状況の分析と満足度調査を実施し、ルールを改定する |
ポイント1:感謝や賞賛が生まれるコミュニケーションの土台を整える
ピアボーナスの効果を最大化するためには、社員同士が安心して感謝を伝え合える文化づくりが欠かせません。
感謝や称賛は制度によって生まれるものではなく、日常的な信頼関係や心理的安全性の中で育まれるものです。
社内でオープンな対話やポジティブなフィードバックが交わされる環境を整えることで、ピアボーナスが義務的な制度ではなく、自然なコミュニケーションの延長として定着します。
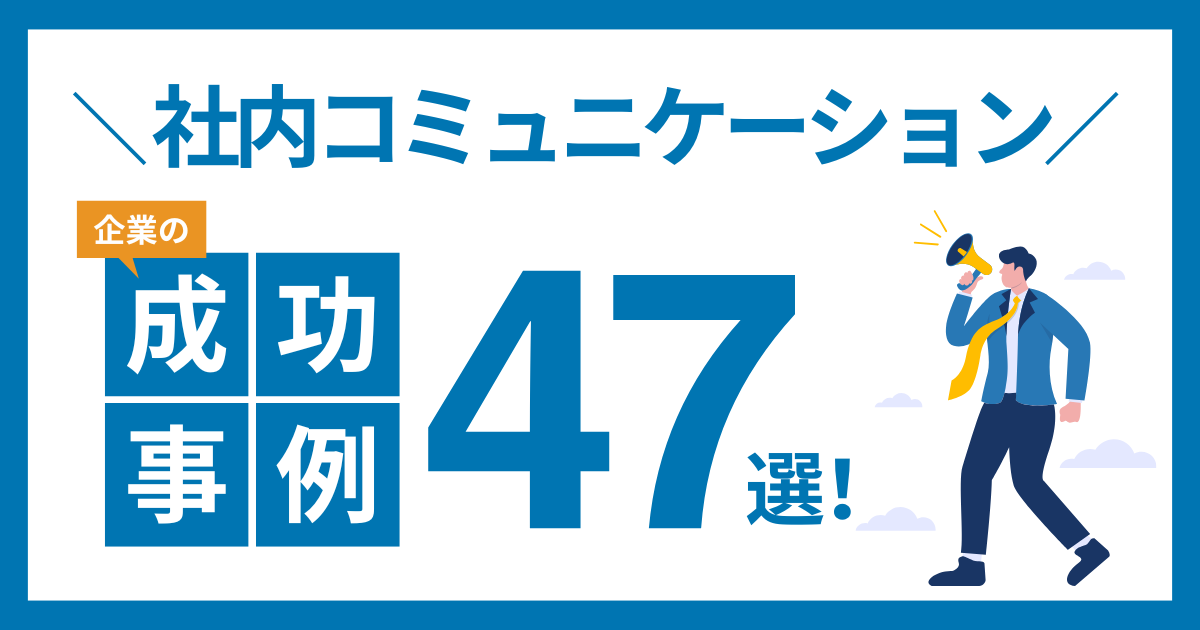
ポイント2:会社の課題に合った導入目的を決める
まず、「自社のどのような課題を解決するためにピアボーナスを導入するのか」を明確に言語化することがスタート地点です。
例えば、「部署間の連携が少なく、サイロ化している」という課題があるなら「部署を横断した協力への感謝を可視化する」が目的になります。
「若手の離職率が高い」のであれば「日々の小さな成長や貢献を承認し、定着を促す」といった目的が考えられます。この目的を全従業員に丁寧に説明し、共感を得ることが重要です。

ポイント3:透明性が高く分かりやすいルールを作る
成功のためには、誰もが納得できる公平なルール設計が欠かせません。1人が1ヶ月に送れるポイント数や回数に上限を設けることで、ポイントのインフレや馴れ合いを防ぎます。
また、どのような行動が称賛に値するのか、会社のバリュー(行動指針)と紐づけて具体例を示すと、従業員が行動しやすくなります。ルールは複雑にしすぎず、シンプルで分かりやすいものにしましょう。
ポイント4:経営層が率先して制度を活用する
経営層や管理職のコミットメントは、制度の成否を大きく左右します。
役員が自ら従業員の素晴らしい行動を見つけてピアボーナスを送ったり、管理職が部下同士の称賛のやり取りに積極的に反応したりすることで、「会社がこの取り組みを本気で推進している」というメッセージが伝わります。
トップの行動が、従業員の利用を促進する何よりの力になります。
ポイント5:推進チームを設置し利用を促す
人事部だけが旗振り役になるのではなく、各部署から推進メンバーを選出してチームを作ることをお勧めします。
推進チームは、制度のアンバサダーとして、部署内での利用を促したり、使い方が分からない人へのサポートを行ったりする役割を担います。
現場の目線で利用を促進することで、制度がよりスムーズに浸透していきます。
ポイント6:ポジティブな投稿を社内で共有する
素晴らしい感謝のメッセージや、称賛をきっかけに生まれた良い変化などは、積極的に社内で共有しましょう。
社内報や全体会議の場で「今月のベストピアボーナス」として紹介することで、他の従業員にとって「こんな使い方があるのか」という手本になります。
心温まるやり取りを共有することは、組織全体のポジティブな雰囲気を醸成することにも繋がります。
ポイント7:従業員の負担にならないツールを選ぶ
制度を継続させるには、手軽に利用できることが絶対条件です。
多くの従業員が日常的に利用しているチャットツール(SlackやMicrosoftTeamsなど)と連携でき、アプリを切り替えることなく投稿できるサービスが理想的です。
スマートフォンからも手軽にアクセスできるかなど、従業員のITリテラシーや働き方に合わせて、最も負担の少ないツールを選定しましょう。
ポイント8:定期的に効果を測定し改善する
ピアボーナス制度は導入して終わりではありません。定期的に利用率や投稿内容を分析したり、従業員にアンケートを実施したりして、効果を測定することが重要です。
利用が特定の部署に偏っていないか、ネガティブな使われ方はされていないかなどをチェックし、問題があればルールを見直したり、追加の施策を考えたりと、常により良い制度を目指して改善を続けていく姿勢が求められます。
ピアボーナス導入を成功させた企業事例
ピアボーナス制度をうまく活用し、組織文化の向上に繋げている企業の事例は、これから導入を考える上で大きな参考になります。ここでは、代表的な2社の成功事例を紹介します。
株式会社メルカリの事例
フリマアプリで知られるメルカリでは、「mertip(メルチップ)」というピアボーナス制度を導入しています。
もともとサンクスカードを送り合う文化がありましたが、よりリアルタイムに、拠点や部署を超えて感謝を伝えられるようにとUnipos社のツールを導入しました。
同社の成功の背景には、会社のバリュー(Go Bold, All for One, Be a Pro)を体現する行動への称賛を推奨し、制度の目的を明確にしたことがあります。
経営層も積極的に利用することで、感謝・称賛の文化がさらに促進され、多いときは1日に1,000件近い投稿がされることもあるなど、社内に深く浸透しています。
参考:贈りあえるピアボーナス(成果給)制度『mertip(メルチップ)』を導入しました。 | mercan (メルカン)
株式会社日阪製作所の事例
熱交換器などを製造する日阪製作所では、「働きがい支援室」の取り組みの一環としてUniposを導入しました。
導入前は、従業員が自分の仕事にやりがいを感じにくいという課題がありました。そこで、ピアボーナスを通じて、普段は目立ちにくい管理部門や現場の貢献にも光を当てることを目指しました。
スマートフォンアプリを活用することで、PCを日常的に使わない現場の従業員も気軽に参加できるようにした点が特徴です。
結果として、部署を超えた感謝のやり取りが活発化し、多くの従業員のエンゲージメント向上に繋がりました。
参考:男性が多い環境でも定着!社内の雰囲気が変わった |株式会社日阪製作所 様支援事例
まとめ
ピアボーナス制度は、従業員のエンゲージメントを高め、ポジティブな組織文化を育む強力なツールになり得ます。
しかし、その成功は導入目的の明確化や公平なルール設計、そして経営層の積極的な関与といった、丁寧な準備と運用にかかっています。
今回紹介した失敗理由と成功のポイントを参考に、自社の文化や課題に合った制度設計を検討してみてください。
ピアボーナスを単なる報酬制度ではなく、組織を強くするためのコミュニケーション基盤として育てていくことが重要です。