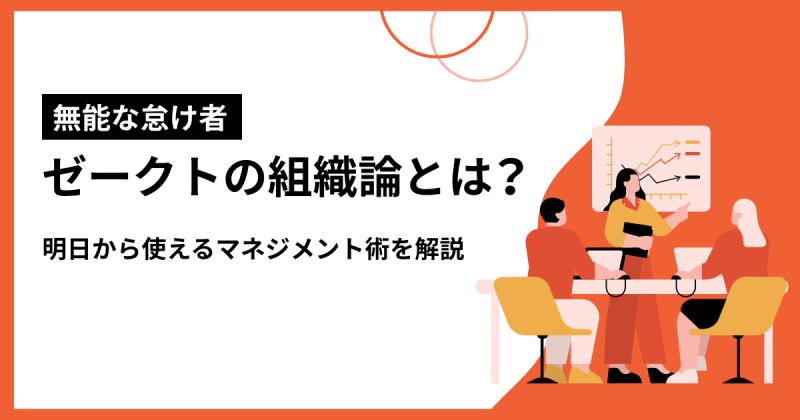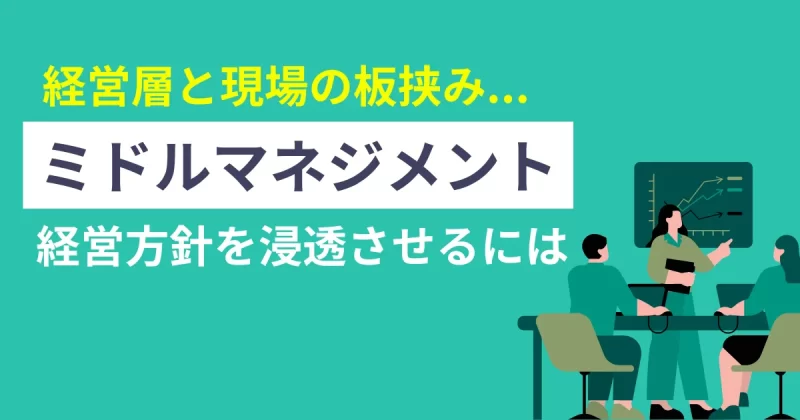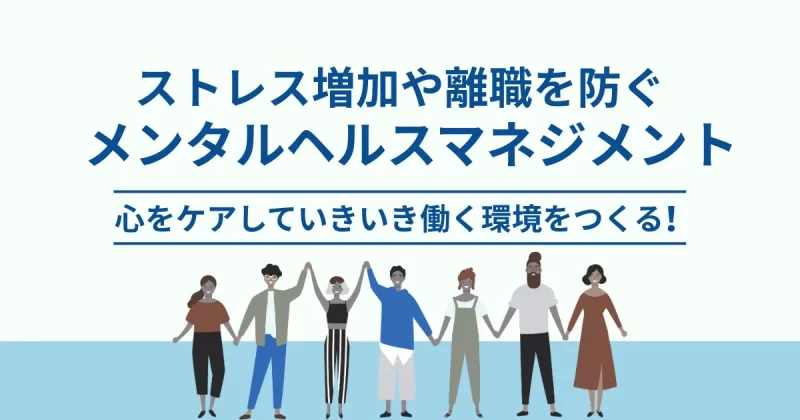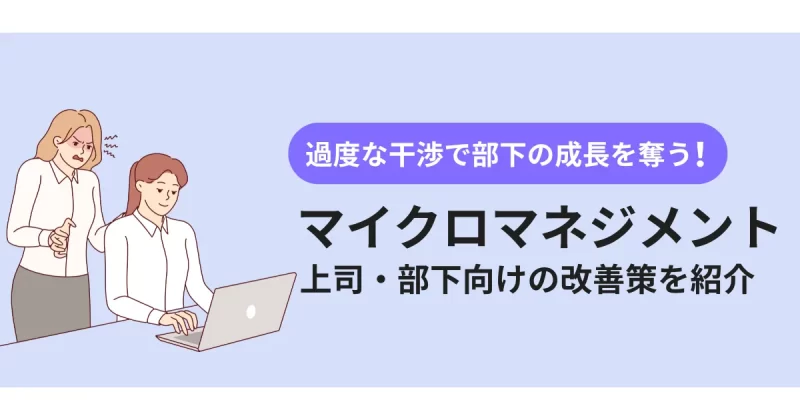「部下のマネジメントがうまくいかない」「チームの生産性が上がらない」といった悩みを抱える管理職の方は多いのではないでしょうか。
その課題は、人材の特性を見極められていないことが原因かもしれません。本記事では、ドイツの軍人によって提唱された「ゼークトの組織論」について詳しく解説します。
この理論は、人材を4つのタイプに分類し、それぞれの役割を明確にすることで、組織のパフォーマンスを最大化するヒントを与えてくれます。明日からのマネジメントに活かせる具体的な方法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
ゼークトの組織論とは何か?
ゼークトの組織論は、組織に属する人間を「能力」と「働きぶり」という2つの軸で4つのタイプに分類し、それぞれのタイプに適した役割を与えることで、組織運営を最適化しようとする理論です。
この考え方は、ビジネスにおける人材配置やマネジメントに応用できるとして、現代でも多くの注目を集めています。
ドイツの軍人が提唱した人材分類論
ゼークトの組織論は、20世紀初頭のドイツで軍人であったハンス・フォン・ゼークトが提唱したとされています。 彼は軍隊という巨大な組織を効率的に機能させるため、兵士たちの能力や性格を深く観察し、この分類法を考案しました。
組織の成果を最大化するためには、単に勤勉な人材を集めるだけでは不十分であり、個々の特性に応じた役割を与えることが重要であるという視点は、現代の企業組織にも通じるものがあります。
「有能・無能」と「勤勉・怠惰」の2軸で分類
この理論の最大の特徴は、人材を「有能か、無能か」という能力の軸と、「勤勉か、怠惰か」という性格の軸の2つを組み合わせて評価する点です。
一般的には「有能で勤勉」な人材が最も理想的だと考えられがちですが、ゼークトの組織論では異なる見解を示しており、それがこの理論の興味深い点でもあります。
| 勤勉 | 怠惰 | |
| 有能 | 有能な働き者 | 有能な怠け者 |
| 無能 | 無能な働き者 | 無能な怠け者 |
元々は軍人ジョークだったという説も
ゼークトの組織論は、その起源について、ゼークト自身が体系的な理論として発表したものではなく、同じ時代の軍人クルト・フォン・ハンマーシュタイン・エクヴォルトが将校を評価する際に用いた分類が元になっているという説や、軍人たちの間で語られていたジョークのようなものだったという説もあります。
しかし、その示唆に富んだ内容は多くの人々の共感を呼び、時代を超えて語り継がれ、現代の組織マネジメント論のひとつとして確立されています。
ゼークトの組織論における4つの人材タイプ
ゼークトの組織論では、前述した2つの軸によって、人材を4つのタイプに分類します。
それぞれのタイプがどのような特徴を持ち、組織においてどのような役割を担うのが最適なのかを見ていきましょう。
【指揮官】有能な怠け者
「有能な怠け者」は、高い能力を持ちながらも、無駄な努力を嫌い、できるだけ楽をしようと考えるタイプです。 このタイプは、常に物事を効率化する方法を模索するため、革新的なアイデアや業務改善策を生み出す力に長けています。
全体を俯瞰して本質を見抜く能力があるため、ゼークトは「指揮官」、つまりリーダーや管理職に適しているとしました。 彼らに裁量権を与えることで、組織全体を正しい方向に導き、大きな成果を上げることが期待できます。
【参謀】有能な働き者
「有能な働き者」は、高い能力と勤勉さを兼ね備えた、一見すると理想的な人材です。 彼らは真面目で責任感が強く、与えられた仕事は完璧にこなそうとします。しかし、何でも自分でやろうとする傾向が強く、部下に仕事を任せるのが苦手なため、リーダーには向かないとされています。
ゼークトの組織論では、このタイプはリーダーを補佐する「参謀」役が適任だとされ、専門知識や実務能力を活かして、リーダーの意思決定をサポートする場面でその真価を発揮します。
【兵卒】無能な怠け者
「無能な怠け者」は、能力は高くないものの、自ら積極的に動こうとはしないタイプです。 このタイプは、余計なことはせず、与えられた指示を忠実にこなすため、組織に大きな害を与えることはありません。
むしろ、定型的な業務やルーティンワークを黙々とこなしてくれるため、組織の基盤を支える存在として重要です。ゼークTの組織論では、彼らを「兵卒」と位置づけ、明確な指示のもとで動く役割が適しているとしています。
【最も有害】無能な働き者
ゼークトの組織論において、最も組織に害を与え、危険な存在だとされるのが「無能な働き者」です。 能力が低いにもかかわらず、意欲だけは人一倍高いため、誤った判断に基づいて行動し、周囲を混乱に陥れます。本人は「よかれと思って」行動しているため、非常に厄介な存在です。ゼークトは、このタイプは組織から排除すべきだとまで述べています。
なぜ「無能な働き者」が組織に最も害を与えるのか?
一見すると、「無能な怠け者」の方が組織にとって問題があるように思えます。しかし、ゼークトの組織論では「無能な働き者」こそが最も有害だとされています。その理由は、彼らの行動が組織全体に多大な悪影響を及ぼすからです。
誤った判断で行動し、被害を拡大させる
「無能な働き者」の最大の問題点は、能力が不足しているにもかかわらず、自信過剰で積極的に行動してしまうことです。
間違った方向に努力を続け、結果として小さな問題を大きなトラブルに発展させてしまいます。彼らの善意からくる行動が、結果的に組織に多大な損害をもたらすことがあるのです。
周囲の報告・連絡・相談を妨げる
このタイプは自己評価が高く、自分の判断が正しいと信じ込んでいるため、上司や同僚への報告・連絡・相談を怠る傾向があります。 周囲が彼らの間違いに気づいたときには、すでに手遅れになっているケースも少なくありません。
情報共有の欠如は、チームの連携を乱し、組織全体のパフォーマンスを低下させる原因となります。
プライドが高く、間違いを認めない
「無能な働き者」は、自分の能力を過大評価しているため、他人からの指摘やアドバイスを素直に受け入れようとしません。
ミスをしても非を認めず、責任転嫁をすることもあります。このような態度は、個人の成長を妨げるだけでなく、チーム内の人間関係を悪化させ、建設的な議論を阻害します。
周囲の従業員の負担を増やし離職を招く
彼らが引き起こしたトラブルの処理や、やり直し作業は、結局のところ他の優秀な従業員が担うことになります。 これにより、一部の従業員に業務負荷が集中し、不公平感からモチベーションが低下します。
最悪の場合、優秀な人材が愛想を尽かして離職してしまうという、組織にとって最も避けたい事態を招きかねません。
ゼークトの組織論を現代の組織で活用する方法
ゼークトの組織論は、元々軍隊の理論ですが、その本質は現代のビジネス組織におけるマネジメントにも大いに役立ちます。個々の従業員の特性を理解し、組織の力を最大限に引き出すための具体的な活用方法を見ていきましょう。
人材の特性を見極め適材適所に配置する
まずは、自分のチームメンバーが4つのタイプのうちどれに当てはまるのかを冷静に分析することが第一歩です。日々の業務の進め方やコミュニケーションの取り方、問題発生時の対応などを観察し、それぞれの特性を見極めます。
その上で、「有能な怠け者」にはプロジェクトのリーダーを、「有能な働き者」には専門的な実務やリーダーの補佐を、「無能な怠け者」には定型業務を任せるなど、適材適所の配置を心がけましょう。

タイプ別にコミュニケーション方法を変える
メンバーのタイプによって、効果的なコミュニケーション方法は異なります。「有能な怠け者」には細かい指示はせず、目的とゴールだけを伝えて裁量を与える方が、モチベーションが上がります。
一方で、「無能な怠け者」には、具体的で分かりやすい指示を段階的に出すことが重要です。タイプに合わせた関わり方をすることで、円滑な意思疎通が可能になります。
明確な目標設定と役割分担を行う
特に「無能な働き者」が誤った方向に努力するのを防ぐためには、チーム全体および個人としての明確な目標を設定し、それぞれの役割と責任範囲をはっきりとさせることが不可欠です。
何をすれば評価されるのかという基準を明確にすることで、全員が同じ方向を向いて業務に取り組むことができ、無駄な行動を減らすことができます。
1on1ミーティングで認識のズレをなくす
定期的に1on1ミーティングなどの個別面談の機会を設け、業務の進捗確認や課題のヒアリングを行うことも有効です。
特に、自己評価と他者評価にギャップが生じやすい「無能な働き者」に対しては、丁寧にフィードバックを行い、認識のズレを修正していくことが重要です。これにより、本人の成長を促し、問題行動を未然に防ぐことができます。

「無能な働き者」への具体的な対処法
組織にとって最も有害とされる「無能な働き者」ですが、すぐに排除するという判断は現実的ではありません。彼らの意欲をうまくコントロールし、組織への悪影響を最小限に抑えるための具体的な対処法を紹介します。
判断を任せず、業務範囲を限定する
彼らが誤った自己判断で行動しないように、意思決定が求められるような仕事は任せず、業務の範囲を明確に限定することが重要です。 裁量権を与えず、上司の許可なく進められる業務を制限することで、独断での行動を防ぎます。
定期的な進捗確認とフィードバックを徹底する
報告・連絡・相談を徹底させ、業務の進捗をこまめに確認する仕組みを作りましょう。 日報や週次のミーティングで進捗を共有させ、もし間違った方向に進んでいる場合は、早期に軌道修正を行います。
その際、感情的に叱責するのではなく、具体的な事実に基づいて冷静にフィードバックすることが大切です。
ルーティンワークや単純作業を任せる
彼らの持つ「勤勉さ」や「意欲」を、組織にとってプラスの方向に活かす方法を考えます。それは、個人の判断が介在する余地が少なく、かつ手順が明確に決まっているルーティンワークや単純作業を任せることです。
このような業務であれば、彼らの勤勉さが正確さやスピードという形で貢献に繋がる可能性があります。
ゼークトの組織論を活用する際の注意点
ゼークトの組織論は、組織マネジメントにおいて非常に有用な視点を提供してくれますが、その活用にあたってはいくつかの注意点があります。これらの点を理解せずに適用すると、かえって組織に悪影響を及ぼす可能性もあります。
人を固定的なラベルで判断しない
この理論はあくまで人をタイプ分けするための一つのフレームワークであり、絶対的なものではありません。
「あの人は無能な働き者だ」といった形で安易にレッテルを貼ることは、その人の可能性を潰し、モチベーションを著しく低下させる危険があります。 人の能力や性格は多面的であることを忘れてはいけません。
成長や変化の可能性を考慮する
人の能力や仕事への姿勢は、経験や学習によって変化するものです。 現在は「無能」と評価される人材でも、適切な教育や指導、経験によって「有能」に成長する可能性は十分にあります。
マネジメントにおいては、個人の成長可能性を信じ、そのための機会を提供し続けることが重要です。
あくまで組織運営の一つの参考に留める
ゼークトの組織論は、すべての組織や状況に当てはまる万能の法則ではありません。 組織の文化や事業内容、メンバーの構成など、自社の状況に合わせて柔軟に解釈し、取り入れるべき部分を取捨選択する姿勢が求められます。
この理論を妄信するのではなく、数あるマネジメントツールの一つとして、客観的に活用することが成功の鍵です。
組織改善に特化したweb社内報ourly

ourlyは組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内コミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」や「web社内報を活用して組織改善したい」という方におすすめのweb社内報ツールです。
まとめ
ゼークトの組織論は、人材を「有能・無能」と「勤勉・怠惰」の2軸で4つのタイプに分類し、適材適所の人材配置を考える上で非常に有効なフレームワークです。特に、組織に最も害を与えるとされる「無能な働き者」への対処法は、多くの管理職にとって重要な示唆を与えてくれます。
しかし、この理論を鵜呑みにせず、あくまで人材を理解するための一つのツールとして活用し、個々の成長や変化の可能性を見据えたマネジメントを心がけることが大切です。この記事を参考に、自社の組織運営やチームビルディングを見直し、より強い組織づくりに役立ててください。