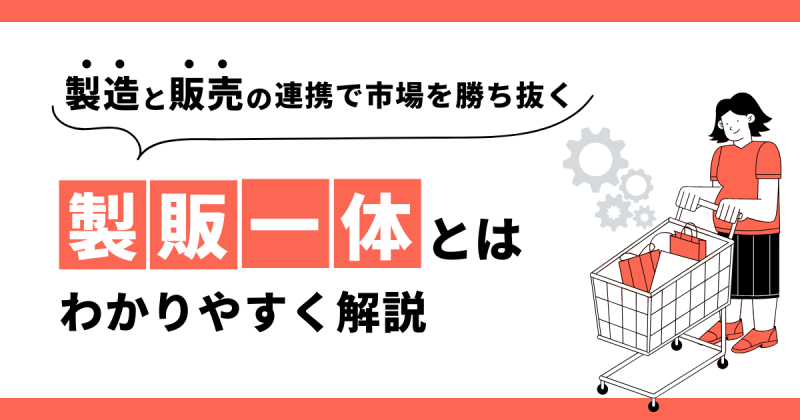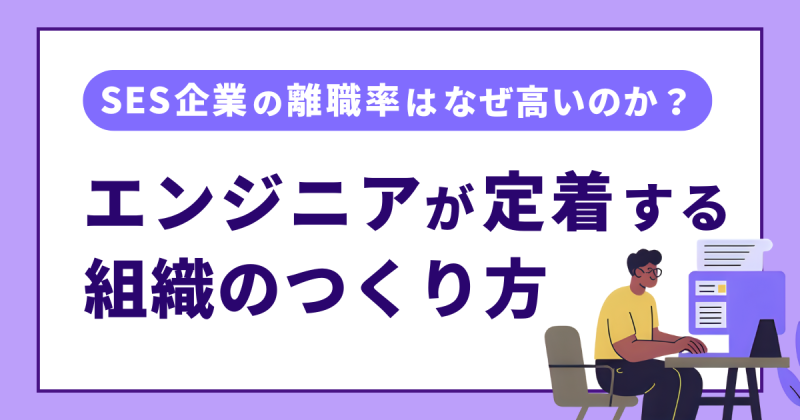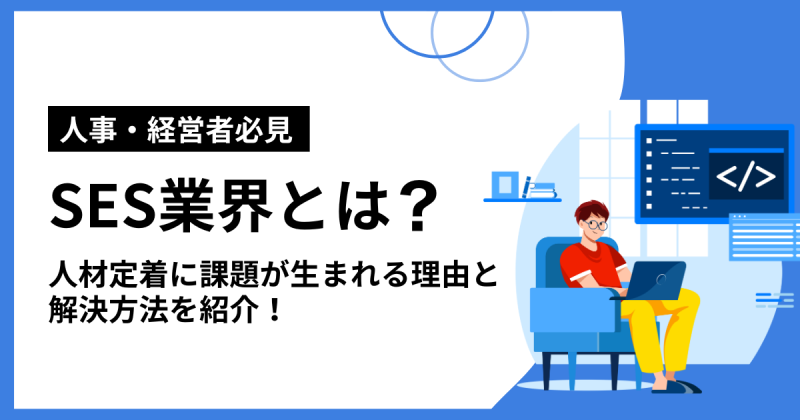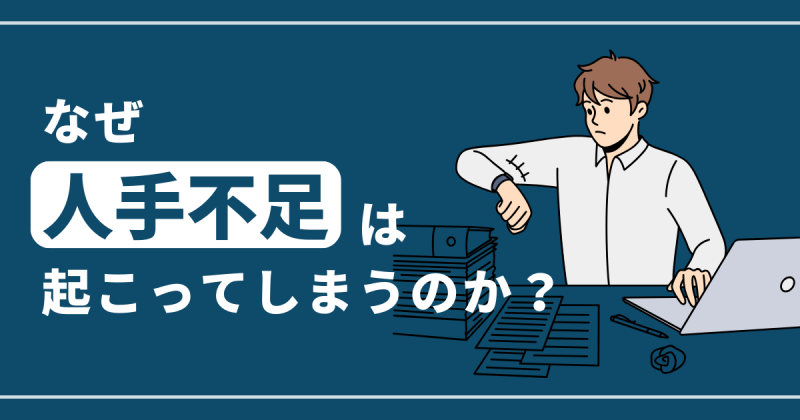自社の製造部門と販売部門の連携がうまくいかず、「作ったものが売れない」「売れるものが在庫にない」といった機会損失や過剰在庫に悩んでいませんか。その課題を解決する鍵が、製造と販売の垣根を越えて協力する「製販一体」の体制です。
この記事では、製販一体の基本的な概念から、導入のメリット・デメリット、そして成功に向けた具体的な進め方までを、事例を交えて分かりやすく解説します。部門間の連携を強化し、変化の激しい市場で勝ち抜くためのヒントとして、ぜひご一読ください。
製販一体とは?
製販一体とは、その名の通り「製造」と「販売」のプロセスを一体化させ、両部門が密接に連携しながら事業を進める経営戦略を指します。顧客のニーズや市場の動向といった販売側の情報をリアルタイムで製造側にフィードバックし、それを製品開発や生産計画に迅速に反映させることで、企業全体の競争力を高めることを目的とします。
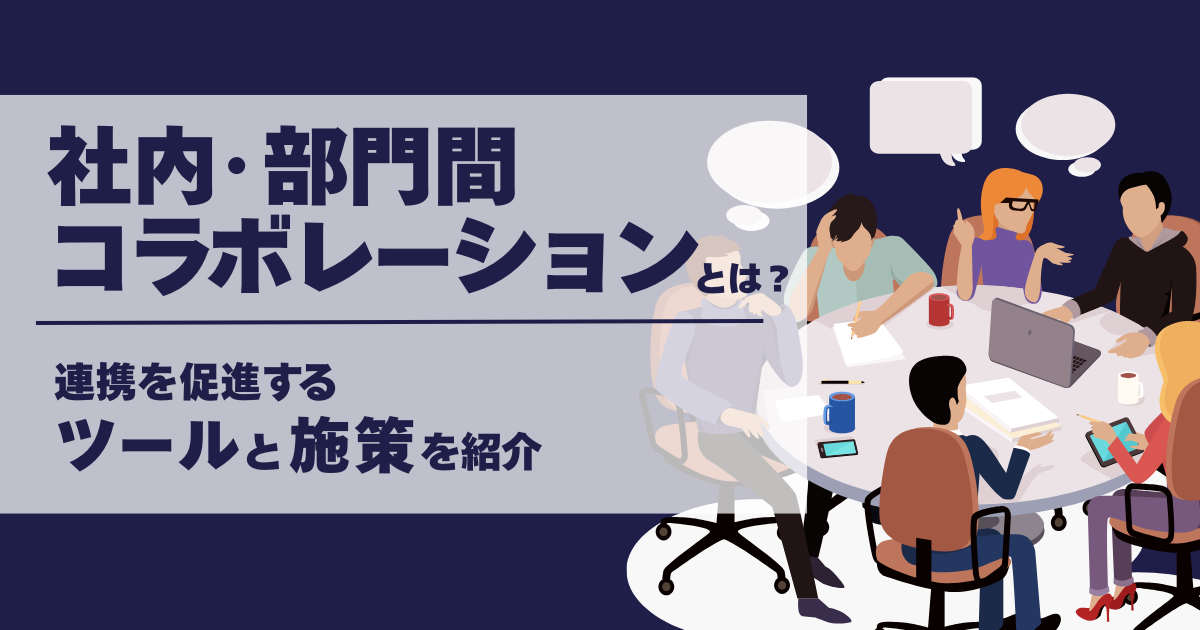
製造と販売の連携がもたらす価値
製販一体の最大の価値は、顧客起点のビジネスプロセスを構築できる点です。販売部門が掴んだ顧客の細かな要望や市場のトレンドを、即座に製造部門と共有します。これにより、市場が本当に求めている製品を、最適なタイミングで、最適な量だけ生産することが可能になります。
結果として、顧客満足度の向上と、無駄な在庫の削減を両立させ、企業全体の収益性を高めることにつながるのです。
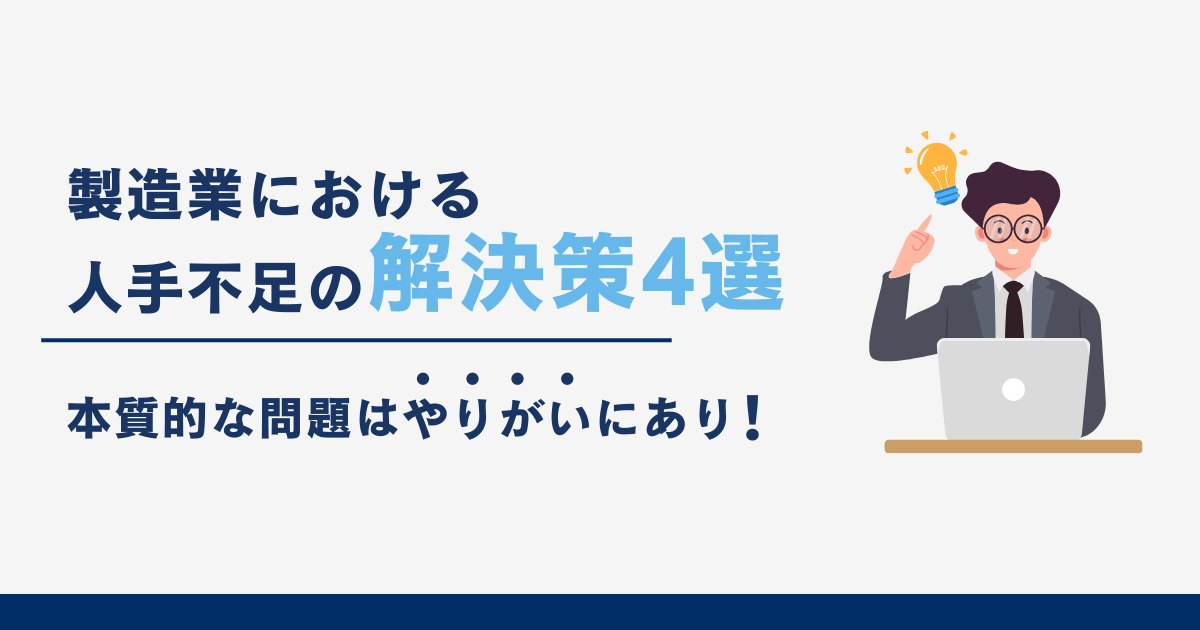
従来の製販分離との違いを比較
多くの企業では、長らく「製販分離」の体制が一般的でした。これは、製造部門は「良いものを作ること」に、販売部門は「作ったものを売ること」にそれぞれ専念する分業体制です。
この体制は各部門の専門性を高める効果がありますが、一方で部門間の連携が希薄になりやすいという課題を抱えています。以下の表で、両者の違いを整理します。
| 項目 | 製販一体 | 製販分離 |
| 意思決定 | 市場や顧客の情報に基づき、両部門が連携して行う | 各部門がそれぞれの目標に基づき、個別に行う |
| 情報共有 | リアルタイムかつ双方向 | 限定的かつ一方通行になりがち |
| 生産計画 | 販売予測や実績に基づき、柔軟に調整(マーケットイン) | 生産効率を重視し、計画的に実施(プロダクトアウト) |
| 主なメリット | 市場対応力、在庫最適化、顧客満足度向上 | 専門性の向上、大量生産によるコスト削減 |
| 主なデメリット | 部門間の調整コスト、導入の難易度 | 機会損失、過剰在庫、顧客ニーズとの乖離 |
このように、製販一体は市場の変化に柔軟に対応できる反面、導入には組織的な変革が求められます。
製販一体が現代の製造業で注目される背景
なぜ今、多くの製造業で製販一体の重要性が叫ばれているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境における3つの大きな変化があります。
多様化する顧客ニーズへの迅速な対応
現代の消費者は、単に機能的な価値だけでなく、個々のライフスタイルに合った製品やサービスを求めるようになりました。このような多様で変化の速い顧客ニーズに応えるためには、販売の最前線で得られる情報をいち早く製品開発や生産に活かす必要があります。製販一体の体制は、このスピード感を実現するために不可欠です。
サプライチェーンの複雑化とグローバル化
部品の調達から生産、物流、販売に至るまでのサプライチェーンは、グローバル化の進展によりかつてないほど複雑化しています。このような状況下では、一部門だけの最適化では対応できず、サプライチェーン全体を見渡した連携が欠かせません。製販一体は、需要と供給の情報を連携させることで、サプライチェーン全体の最適化を図るための重要な第一歩となります。
DX推進によるデータ活用の重要性の高まり
デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、これまで分断されていた各部門のデータを収集・分析し、経営に活かすことが可能になりました。販売データ、生産データ、在庫データなどを一元的に管理・分析することで、より精度の高い需要予測や生産計画の立案が実現します。このデータ活用を最大限に活かすためには、製販一体の組織体制が前提となります。
製販一体がもたらす4つのメリット
製販一体の体制を構築することは、企業に多くの利益をもたらします。ここでは、代表的な4つのメリットについて解説します。
機会損失の削減による売上向上
販売部門からの需要予測や実売データをリアルタイムで生産計画に反映させることで、「人気商品が欠品して売れない」といった販売機会の損失を防ぎます。市場の需要に対して供給を柔軟に合わせることができるため、売上の最大化に直結します。
適正在庫の実現によるキャッシュフロー改善
売れない製品を作りすぎてしまう「過剰在庫」は、保管コストの増大や製品価値の低下を招き、キャッシュフローを圧迫する大きな要因です。製販一体により需要に基づいた生産が可能になることで、不要な在庫を大幅に削減できます。これにより、企業の資金繰りは大きく改善されます。
| 在庫状況 | 製販分離で起こりがちな問題 | 製販一体による改善効果 |
| 過少在庫 | 欠品による販売機会の損失 | 需要に合わせた生産で機会損失を防止 |
| 過剰在庫 | 保管コストの増大、キャッシュフローの悪化 | 需要予測に基づき無駄な生産を抑制 |
| 滞留在庫 | 製品の陳腐化、廃棄ロスの発生 | 市場のニーズに合った製品のみを生産 |
顧客満足度の向上とリピート促進
顧客からの「こんな機能が欲しい」といったフィードバックやクレーム情報を、迅速に製品開発や品質改善に活かすことができます。顧客の声に応えることで、製品や企業に対する信頼が高まり、顧客満足度の向上、さらにはリピート購入へとつながります。
顧客ニーズを反映した製品開発力の強化
販売現場は、顧客の潜在的なニーズや市場の新たなトレンドを発見する宝庫です。製造部門と販売部門が一体となって商品開発に取り組むことで、机上の空論ではない、真に市場に受け入れられるヒット商品を生み出す確率が高まります。
製販一体を進める上でのデメリットと課題
多くのメリットがある一方で、製販一体の実現は容易ではありません。導入を進める上で直面しがちなデメリットや課題についても理解しておくことが重要です。
部門間の対立やコンフリクトの発生
従来、異なる目標や文化を持っていた製造部門と販売部門を連携させる過程では、対立が起こりがちです。「生産効率を重視する製造」と「多様な顧客要望に応えたい販売」のように、利害が衝突する場面も少なくありません。これを乗り越えるには、強力なリーダーシップと丁寧なコミュニケーションが不可欠です。
ITシステム導入と連携にかかるコスト
製販一体を効果的に機能させるためには、各部門のデータを一元管理し、リアルタイムで共有するためのITシステムが欠かせません。CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)、ERP(統合基幹業務システム)などの導入や、既存システムとの連携には、相応の金銭的・時間的コストが発生します。
全社的な意識改革と文化醸成の難しさ
最も大きな課題は、従業員の意識改革です。自部門の利益や効率だけを考える「部分最適」の考え方から、会社全体の利益を考える「全体最適」の視点へとマインドセットを変える必要があります。これには時間がかかり、経営層からの継続的なメッセージ発信や、新しい協力体制を促す評価制度の導入など、組織文化を変えるための地道な努力が求められます。
製販一体を実現するための具体的な4つのポイント
製販一体を成功させるためには、計画的かつ段階的に取り組みを進めることが重要です。ここでは、実現に向けた4つの具体的なポイントを解説します。

全社で明確な目的とビジョンを共有する
まず、「なぜ製販一体を目指すのか」という目的を明確にし、全社で共有することが不可欠です。「顧客満足度No.1を目指す」「在庫回転率を20%向上させる」といった具体的なビジョンを掲げ、経営層がリーダーシップを発揮してその重要性を繰り返し伝えることで、部門の壁を越えた協力体制の土台を築きます。

S&OPを導入し業務プロセスを標準化する
S&OP(Sales and Operations Planning)とは、販売計画と生産計画を統合し、需要と供給のバランスを最適化するための経営手法です。定期的に販売、製造、開発などの関連部門が集まり、最新の需要予測に基づいて生産計画や在庫計画を調整します。このS&OPのプロセスを導入・定着させることで、部門間の連携が仕組み化され、属人的な調整から脱却できます。
データ連携を可能にするIT基盤を構築する
勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいた意思決定を行うために、IT基盤の整備は必須です。前述のCRMやERPといったツールを導入し、これまで各部門に散在していた販売データ、生産実績、在庫情報などを一元的に可視化できる環境を構築します。これにより、全ての関係者が同じ情報を見て議論できるようになります。
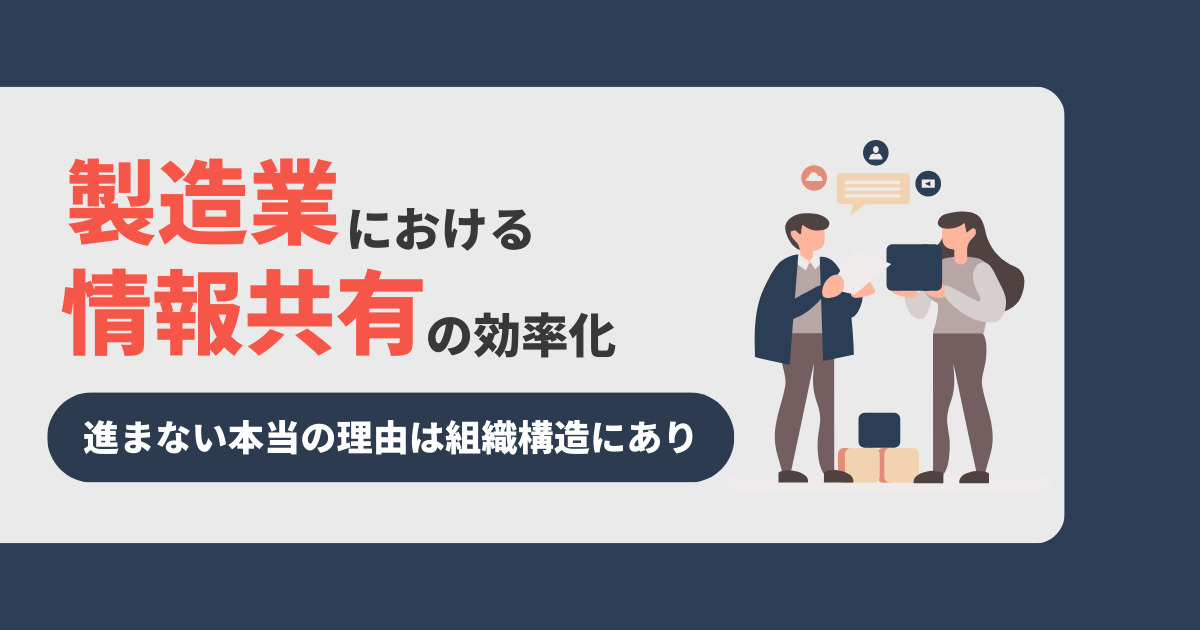
組織横断的なKPIの設定と評価制度の見直し
各部門の評価指標(KPI)が連携を阻害するケースは少なくありません。例えば、製造部門が「生産コストの削減」のみで評価され、販売部門が「売上高」のみで評価されると、両者の協力は進みません。そこで、「在庫回転率」や「受注から納品までのリードタイム」といった、両部門の協力が不可欠な組織横断的なKPIを設定し、評価制度にも反映させることが有効です。
製販一体の成功事例
理論だけでなく、実際の企業がどのように製販一体を成功させているのか、具体的な事例を見ていきましょう。
ロック・フィールド

株式会社ロック・フィールドは、全国に約300店舗の惣菜店を展開しています。製造拠点と販売店舗が全国各地に点在していることから、部門間での相互理解が進みにくいという課題を抱えていました。
そこでweb社内報を活用し、製造部門の「製品に対するこだわり」や、販売現場で寄せられる「お客様の声」を記事として発信しました。
その結果、部門を越えた理解が深まり、製造部門と販売部門が一体となって商品を提供できる体制が確立。現在では、全国どの店舗においても高い店頭品質を安定的に維持しています。
ユニクロ
ファーストリテイリングが展開するユニクロは、製販一体の代表的な成功事例として世界的に知られています。商品の企画開発から製造、販売までを一気通貫して対応することで、高品質ながら低価格な商品を提供するSPA(製造小売業)モデルを確立しました。特に東レ株式会社との戦略的パートナーシップにより、新たな素材開発から生産、商品改良までのプロセスを一体で行う協業体制を構築し、ヒートテックやエアリズムなどの革新的な商品を生み出し続けています。この製販一体の取り組みにより、2024年8月期には欧州・北米で過去最高の業績を達成しています。
【参考】https://www.fastretailing.com/jp/ir/direction/interview.html
アイリスチトセ

アイリスチトセ株式会社は、オフィス家具を中心に、空間デザインから施工までを手がける業務用家具メーカーです。組織の拡大に伴い、部署間のつながりが希薄化し、営業は製造現場を知らず、製造は営業現場(顧客の声)を把握できないといった課題を抱えていました。
そこでweb社内報を導入し、記事を通じて現場の取り組みや顧客の声を共有することで、営業と品質管理をはじめとする部門間の連携が強化されました。その結果、大型プロジェクトもスムーズに進行できるようになっています。
製販一体の体制を支える情報共有の基盤づくりに成功した事例です。
製販一体を実現するweb社内報「ourly」

製販一体は、顧客満足度の向上やイノベーション創出など、多くのメリットをもたらします。
web社内報ourlyは、部門や役職を超えた相互理解を深め、組織に一体感を生み出せる全く新しい社内報ツールです。
ourlyの特徴
- Web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しているためメッセージの浸透度がわかる
- 発信した情報に対する従業員の反応がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
まとめ
本記事では、製販一体の基本的な概念からメリット・デメリット、そして実現のための具体的なポイントまでを解説しました。製販一体は、単なる部門間の連携強化に留まらず、顧客起点のビジネスプロセスを構築し、変化の激しい市場で企業が生き残るための重要な経営戦略です。
実現には部門間の対立やコストなど、乗り越えるべき課題も少なくありません。
しかし、明確なビジョンを共有し、プロセスやIT基盤、評価制度を整えながら着実に進めることで、機会損失の削減や在庫の最適化といった大きな成果を得ることが可能です。