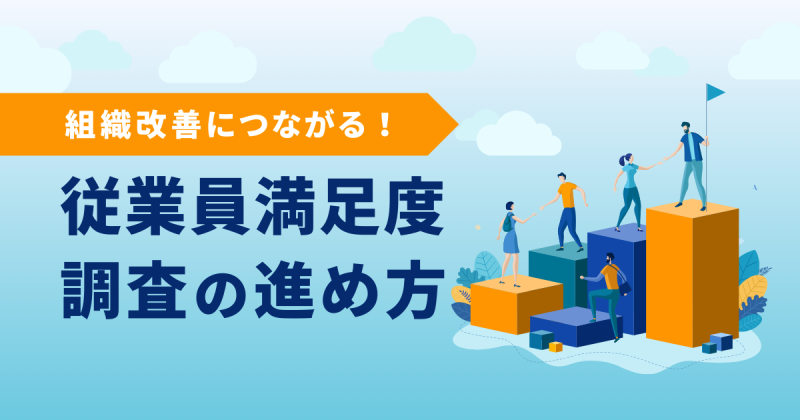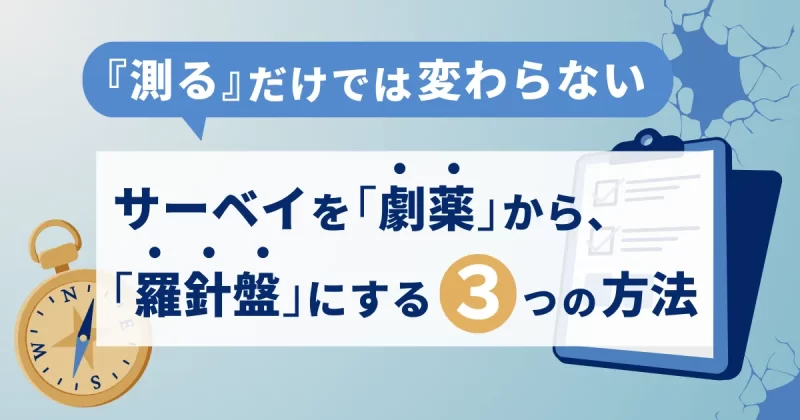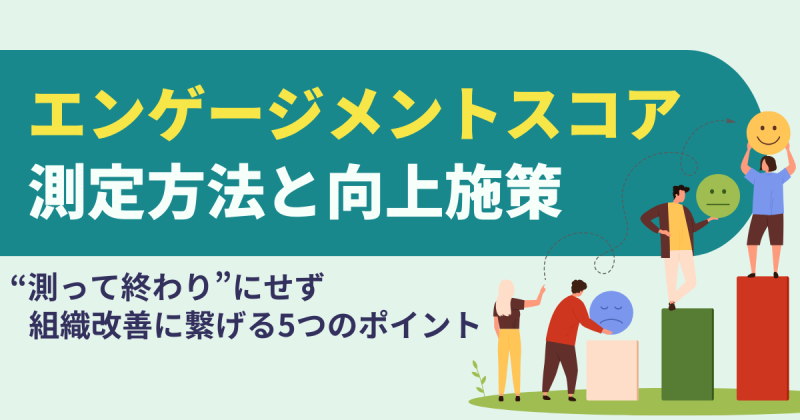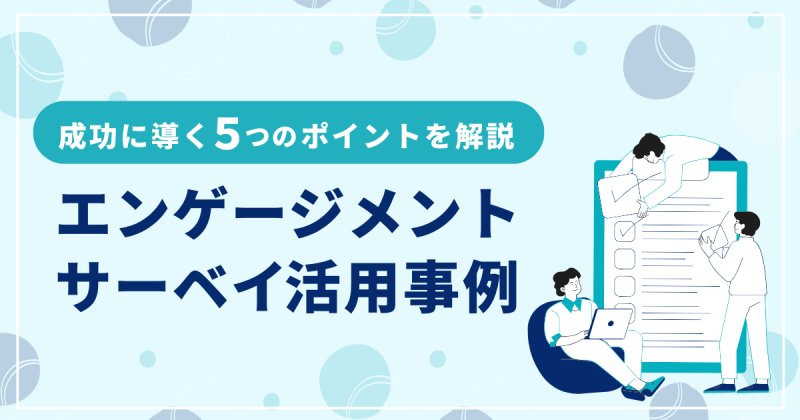「従業員の離職率が高い」「社内に活気がない」「生産性が上がらない」
こうした課題を感じてはいるものの、何から手をつければ良いか分からず悩んでいる経営者や人事担当者の方は多いのではないでしょうか。その解決の第一歩となるのが「従業員満足度調査」です。
この記事では、従業員満足度調査の基本的な知識から、具体的な進め方、成果を出すためのポイントまでを分かりやすく解説します。

従業員満足度調査(ES調査)とは?
従業員満足度調査(ES調査)は、従業員が仕事内容、職場環境、人間関係、会社の制度などに対してどの程度満足しているかを定量的に測定・把握するための調査です。
単に満足度を測るだけでなく、組織が抱える課題を明らかにし、より良い職場環境を築くための重要な手段として注目されています。
従業員の満足度を可視化する調査
従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)とは、文字通り従業員の「満足度」を示す指標です。この満足度は、給与や福利厚生といった待遇面だけでなく、仕事のやりがい、上司や同僚との関係性、企業文化への共感など、様々な要因によって構成されます。
普段の面談や日々のコミュニケーションだけでは見えにくい、従業員の本音をアンケート等の手法を用いて可視化するのが、従業員満足度調査の役割です。
客観的なデータに基づいて組織の状態を把握することで、感覚的な組織運営から脱却し、的確な人事施策を打つことが可能になります。
なぜ今、従業員満足度調査が重要視されるのか
近年、従業員満足度調査の重要性が高まっている背景には、少子高齢化による労働人口の減少と、働き方の価値観の多様化があります。
優秀な人材の獲得競争が激化する中で、従業員に選ばれ、長く働き続けてもらうためには、彼らが満足できる環境を提供することが不可欠です。
満足度の高い従業員は仕事へのモチベーションが高く、生産性向上に貢献するだけでなく、自社への愛着心から離職率が低下する傾向にあります。
このように、従業員満足度は企業の持続的な成長を支える重要な経営指標として認識されています。
混同されがちな「エンゲージメント調査」との違い
従業員満足度調査とよく似たものに「エンゲージメント調査」があります。両者は密接に関連しますが、その焦点には違いがあります。
| 調査項目 | 従業員満足度調査 | エンゲージメント調査 |
| 主な焦点 | 従業員が会社や待遇に「満足」しているか(受動的) | 従業員が会社に「貢献したい」という意欲があるか(能動的) |
| 指標の意味 | 職場環境や制度に対する評価 | 会社と従業員の絆の強さ、成長への貢献意欲 |
| 目指す状態 | 従業員の不満を解消し、満足度を高める | 従業員の自発的な貢献意欲を引き出し、共に成長する |
簡単に言えば、満足度は「会社から与えられるものへの評価」、エンゲージメントは「会社へ自発的に貢献したいという意欲」を測る指標です。従業員満足度は、エンゲージメントを高めるための土台となる要素と捉えることができます。
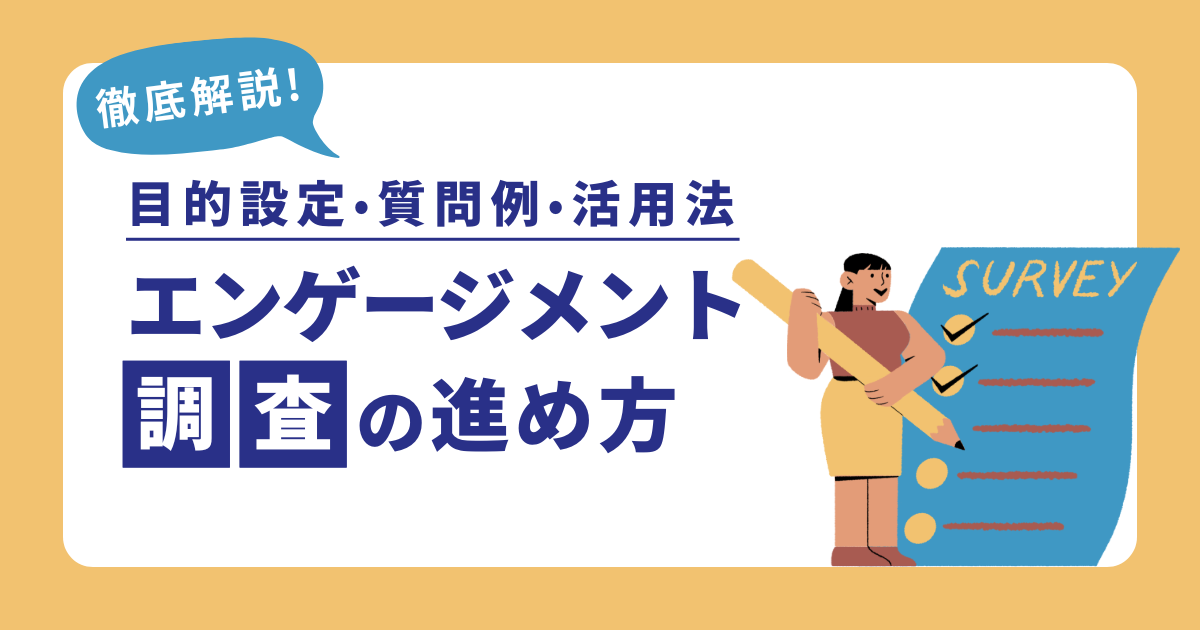
従業員満足度調査を実施する3つのメリット
従業員満足度調査は、時間やコストをかけて実施する価値のある施策です。ここでは、調査によって企業が得られる主な3つのメリットを解説します。
組織や従業員の課題を客観的に把握できる
最大のメリットは、これまで感覚的にしか捉えられていなかった組織の課題を、データに基づいて客観的に把握できることです。
例えば、「人間関係には問題ないはずだ」と経営層が考えていても、調査結果では部署間の連携不足や上司のマネジメントへの不満が明らかになるケースは少なくありません。従業員のリアルな声を数値で可視化することで、思い込みや先入観を排し、本当に解決すべき課題の特定につながります。
生産性の向上と離職率の低下につながる
従業員満足度の向上は、企業の業績に直結します。満足度の高い従業員は仕事への意欲が高まり、その結果として個々のパフォーマンスが向上し、組織全体の生産性アップにつながります。
また、自分の会社に満足している従業員は「この会社で働き続けたい」という帰属意識が高まるため、優秀な人材の流出を防ぎ、離職率を低下させる効果が期待できるでしょう。 これは、新たな人材を採用・育成するコストの削減にも貢献します。
企業のイメージアップと採用力強化に貢献する
従業員を大切にする企業文化は、社外からの評価にも繋がります。従業員満足度を高める取り組みは、「働きがいのある会社」「ホワイト企業」といったポジティブな企業イメージを醸成します。 良い評判は、SNSや口コミサイトを通じて自然と広まり、求職者にとって大きな魅力となるでしょう。
その結果、優秀な人材が集まりやすくなり、採用競争において有利なポジションを築くことができます。
従業員満足度調査のデメリットと注意点
多くのメリットがある一方で、従業員満足度調査にはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。計画段階でこれらを認識し、対策を講じることが成功の鍵となります。
調査の実施にコストと手間がかかる
調査の設計から実施、集計、分析、そして改善策の実行まで、一連のプロセスには相応の時間と労力がかかります。 特に初めて実施する場合、質問項目の作成や分析手法の選定に戸惑うこともあるでしょう。
また、外部の専門会社に委託したり、有料のアンケートツールを利用したりする場合は、当然ながら費用が発生します。これらのリソースを投入する価値があるかを事前に吟味し、社内の協力を得ておくことが重要です。
調査結果の放置は逆効果になる恐れがある
従業員に協力を求めて調査を実施したにもかかわらず、その結果を公表せず、何の改善策も講じないのは最悪のケースです。 従業員は「意見を言っても無駄だ」「会社は自分たちの声を聞く気がない」と感じ、会社への不信感を募らせてしまいます。
これは、調査実施前よりもかえって満足度やモチベーションを低下させる原因となりかねません。調査はあくまでスタートであり、その後のアクションこそが重要であると認識する必要があります。
匿名性の担保など従業員への配慮が必要
従業員満足度調査は、時に上司や会社の制度に対する批判など、デリケートな内容を含みます。そのため、従業員が安心して本音で回答できる環境を整えることが不可欠です。 特に重要なのが「匿名性の確保」です。誰がどのように回答したか個人が特定されない仕組みを整え、そのことを事前に従業員へ明確に説明しましょう。
回答が人事評価に影響しないことを約束することも、正直な意見を引き出す上で欠かせません。
従業員満足度調査の進め方【7つのステップ】
従業員満足度調査を成功に導くためには、計画的にステップを踏んで進めることが重要です。ここでは、目的設定から改善策の実行までを7つのステップに分けて解説します。
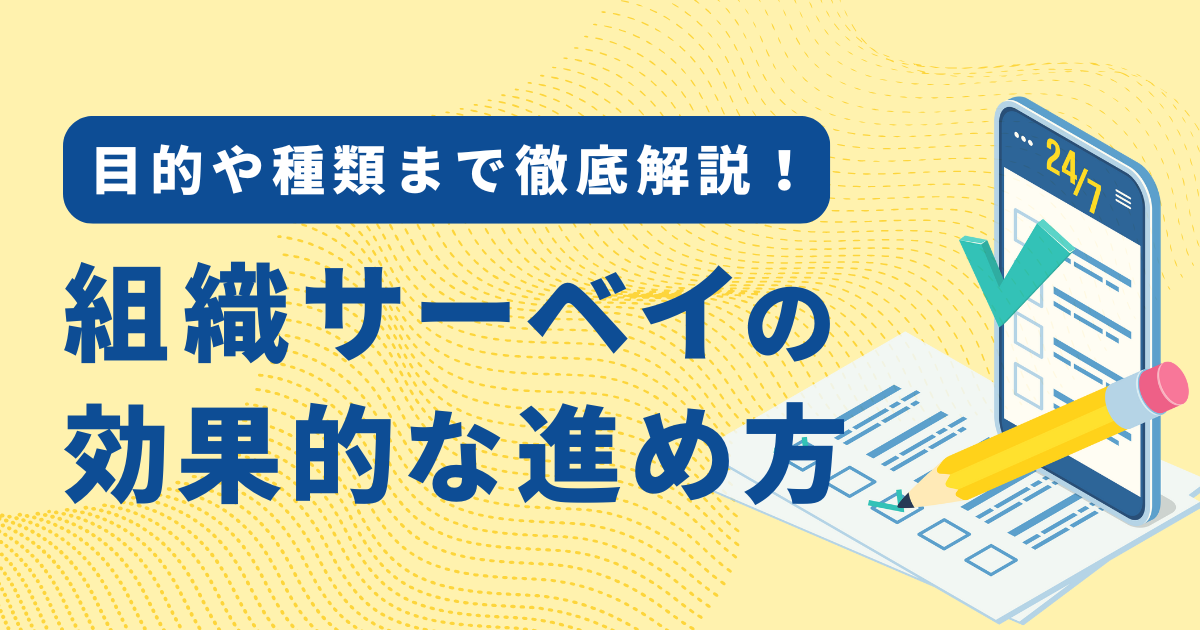
ステップ1:調査の目的を明確にする
まず、「何のために調査を行うのか」という目的を明確にします。 「若手社員の離職率を下げたい」「部署間の連携を強化したい」「新しい人事制度の評価を知りたい」など、目的が具体的であるほど、その後の質問設計や分析がスムーズになります。調査を行うこと自体が目的化しないよう、達成したいゴールを定めましょう。
ステップ2:調査対象と実施方法を決定する
次に、誰を対象に、どのような方法で調査を行うかを決めます。正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなど、全従業員を対象にするのが理想ですが、目的に応じて特定の部署や役職に絞ることも考えられます。
実施方法は、Webアンケートが一般的ですが、紙での配布や、より深く意見を聞くためのインタビューを組み合わせることも有効です。
ステップ3:効果的な質問項目を設計する
調査の成否を分ける最も重要なステップの一つが、質問項目の設計です。ステップ1で定めた目的に沿って、聞くべきことを過不足なく盛り込みます。質問数が多すぎると回答者の負担が大きくなるため、精査が必要です。次章で具体的な質問例を紹介しますので、そちらを参考に設計してください。
ステップ4:従業員へ調査を告知し実施する
調査の準備が整ったら、従業員へ調査の実施を告知します。調査の目的、回答期間、匿名性が担保されていることなどを丁寧に説明し、協力を依頼しましょう。 従業員の協力なくして、正確なデータは得られません。繁忙期を避け、1〜2週間程度の回答期間を設けて調査を実施します。
ステップ5:回答結果を集計・分析する
回答期間が終了したら、結果を集計し、分析します。全体の平均値を出す「単純集計」に加え、部署別、役職別、年代別などで結果を比較する「クロス集計」を行うことで、課題がどこにあるのかをより深く掘り下げることができます。
さらに、どの項目が総合満足度に強く影響しているかを分析する「満足度構造分析」も有効です。
ステップ6:結果をフィードバックし改善策を検討する
分析結果が出たら、必ず従業員にフィードバックを行います。 全社や部署ごとの傾向、強みと弱みなどを共有し、会社として課題に真摯に向き合う姿勢を示すことが信頼関係の構築に繋がります。
その上で、分析結果から明らかになった課題を解決するための具体的な改善策を検討します。
ステップ7:改善策を実行し効果を測定する
検討した改善策を実行に移します。施策の担当者や期限を明確にし、計画的に進めましょう。そして、施策を実行して終わりではなく、一定期間が経過した後に再度調査を行うなどして、施策の効果を測定することが重要です。
このPDCAサイクルを回し続けることで、組織は継続的に改善されていきます。
【例文あり】成果につながる質問項目の作り方
効果的な従業員満足度調査のためには、網羅的かつ的確な質問項目が不可欠です。
ここでは、一般的に調査に含まれるべき項目と、その質問例を紹介します。
仕事内容そのものに関する質問
日々の業務に対するやりがいや負担感を測る項目です。
・現在の仕事内容にやりがいや意義を感じていますか?
・現在の仕事量は適切だと思いますか?
・仕事を通じて、自身の成長を実感できていますか?
人間関係や組織風土に関する質問
上司や同僚との関係性、職場の雰囲気に関する項目です。
・上司はあなたの仕事ぶりを正当に評価し、適切なフィードバックをしていますか?
・職場の同僚とは、気軽に相談や意見交換ができていますか?
・この会社には、挑戦を推奨し、失敗を許容する文化があると思いますか?
会社の制度や待遇に関する質問
給与や福利厚生、人事評価制度などへの満足度を測る項目です。
・あなたの仕事の成果や貢献は、給与や賞与に正当に反映されていると思いますか?
・人事評価の基準は明確で、評価結果に納得していますか?
・有給休暇の取りやすさや、福利厚生の制度に満足していますか?
経営やビジョンに関する質問
会社の方向性や経営陣への信頼感を問う項目です。
・会社の経営方針やビジョンに共感できますか?
・経営陣は、会社の将来について明確な方向性を示していると思いますか?
・会社の将来性や安定性について、どのように感じていますか?
総合的な満足度と自由記述
これまでの項目を総括し、全体的な満足度を測ります。eNPS(従業員推奨度)と呼ばれる「この会社を友人や知人にどの程度勧めたいですか?」という質問もよく用いられます。また、最後に自由記述欄を設け、数値では測れない具体的な意見や要望を収集することも非常に重要です。
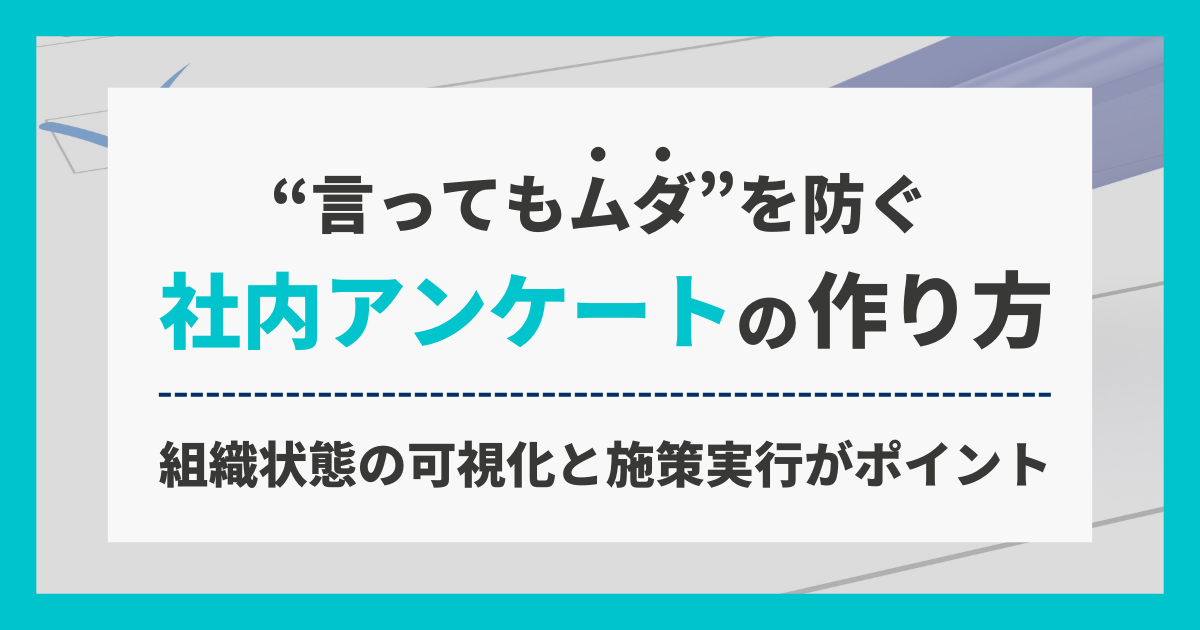
従業員満足度調査を成功させるためのポイント
最後に、従業員満足度調査を「やって終わり」にせず、真に組織改善に繋げるための重要なポイントを3つ紹介します。
経営層が本気で取り組む姿勢を示す
従業員満足度調査は、人事部だけの仕事ではありません。経営層がその重要性を理解し、改善に向けて本気でコミットする姿勢を従業員に示すことが何よりも重要です。 経営トップからのメッセージ発信や、調査結果報告会への出席など、経営層の関与は従業員の調査への協力姿勢や信頼感を大きく左右します。
従業員が本音で回答できる環境を整える
前述の通り、匿名性の担保は絶対条件です。それに加え、なぜ調査を行うのか、結果をどのように活用するのかを丁寧に説明し、従業員の不安を取り除く配慮が求められます。 「回答したら不利益を被るのではないか」という疑念を払拭し、安心して本音を語れる心理的安全性を確保することが、調査の精度を高めることに直結します。
定期的に実施して継続的な改善サイクルを回す
組織の状態や従業員の意識は常に変化します。一度の調査で満足するのではなく、半年に1回、あるいは年に1回など、定期的に実施することが大切です。
継続的にデータを測定することで、前回からの変化を把握し、実行した改善策の効果を検証することができます。このように、調査→改善→効果測定というPDCAサイクルを回し続けることで、組織は着実に良い方向へ変わっていきます。
“測って終わりにさせない” 調査ツール、ourly survey
ourly surveyは、自由な設問設計と施策立案・実行までを支援する“測って終わり”にさせない調査ツールです。

細かい分析機能で組織課題を可視化
「所属/部署」「役職」「職種」「拠点」などのユーザー属性で回答結果を分析することが可能です。理念の浸透度合いや、エンゲージメントが低い層を見える化できます。
組織課題に応じた自由な設問
従業員エンゲージメントの向上や人事施策の成果測定、ビジョンの浸透度合いの計測など、自社が手に入れたい組織状態から逆算して自由に質問の作成が可能です。
行動データを組み合わせた分析
弊社が提供するweb社内報「ourly」の閲覧行動と調査で集計した結果をクロス分析することで、組織改善のサイクルを加速させます。
一気通貫した改善支援
弊社の組織開発コンサルタントが、調査で集計した結果をもとに組織課題の特定や改善施策の提案、実行を支援します。
以下の資料では、ourly surveyの具体的な特徴や機能を紹介しています。
サービスの比較や導入のご検討などに、ご活用ください。

まとめ
従業員満足度調査は、従業員の声に耳を傾け、組織の健康状態を客観的に把握するための強力なツールです。調査を通じて明らかになった課題に真摯に向き合い、改善を続けることで、従業員の満足度やエンゲージメントは高まります
その結果は、生産性の向上、離職率の低下、そして企業の持続的な成長へと繋がっていくはずです。本記事を参考に、ぜひ貴社の組織力強化にお役立てください。