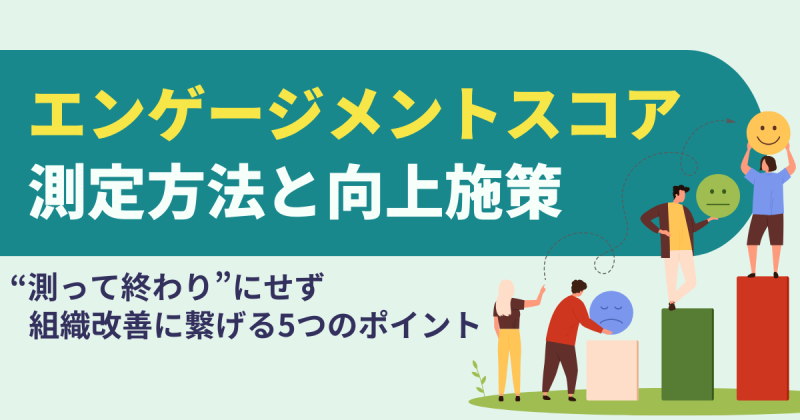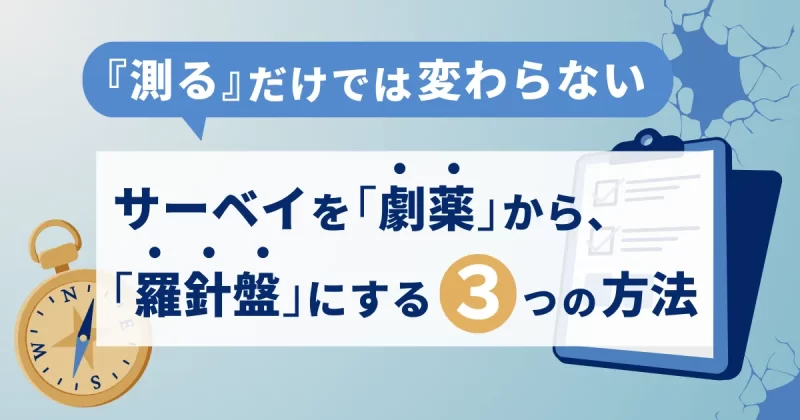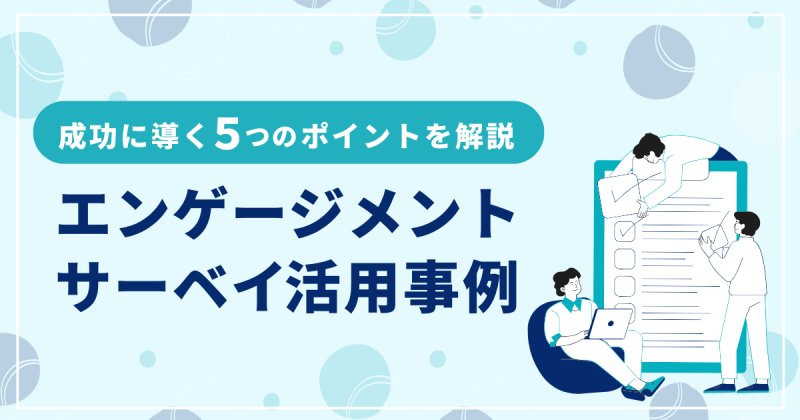近年、企業の成長戦略において「エンゲージメントスコア」という言葉を耳にする機会が増えました。従業員の離職率改善や生産性向上を目指す上で、この指標は欠かせないものとなりつつあります。しかし、その正確な意味や測定方法、具体的な活用法について、深く理解している方はまだ多くないかもしれません。
本記事では、エンゲージメントスコアの基本的な定義から、その重要性、高めることによるメリット、そして具体的な測定方法と向上策までを網羅的に解説します。
エンゲージメントスコアとは?
エンゲージメントスコアは、単なる従業員の満足度を示すものではありません。企業と従業員の間に存在する、より深く、双方向の関係性を可視化するための重要な指標です。このスコアを正しく理解することが、組織改善の第一歩となります。
企業と従業員の信頼関係を数値化する指標
エンゲージメントスコアとは、従業員が所属する企業に対して抱く「愛着心」や「貢献意欲」を、調査を通じて定量的に測定し、数値化したものです。このスコアは、従業員が企業のビジョンや目標にどれだけ共感し、自発的にその成功のために行動したいと考えているかを示します。エンゲージメントが高い状態とは、従業員と企業が互いに信頼し、同じ目標に向かって進んでいる「相思相愛」の状態です。
この目に見えない関係性を客観的な数値で把握することで、組織の健康状態を正確に診断し、的確な対策を講じることが可能になります。
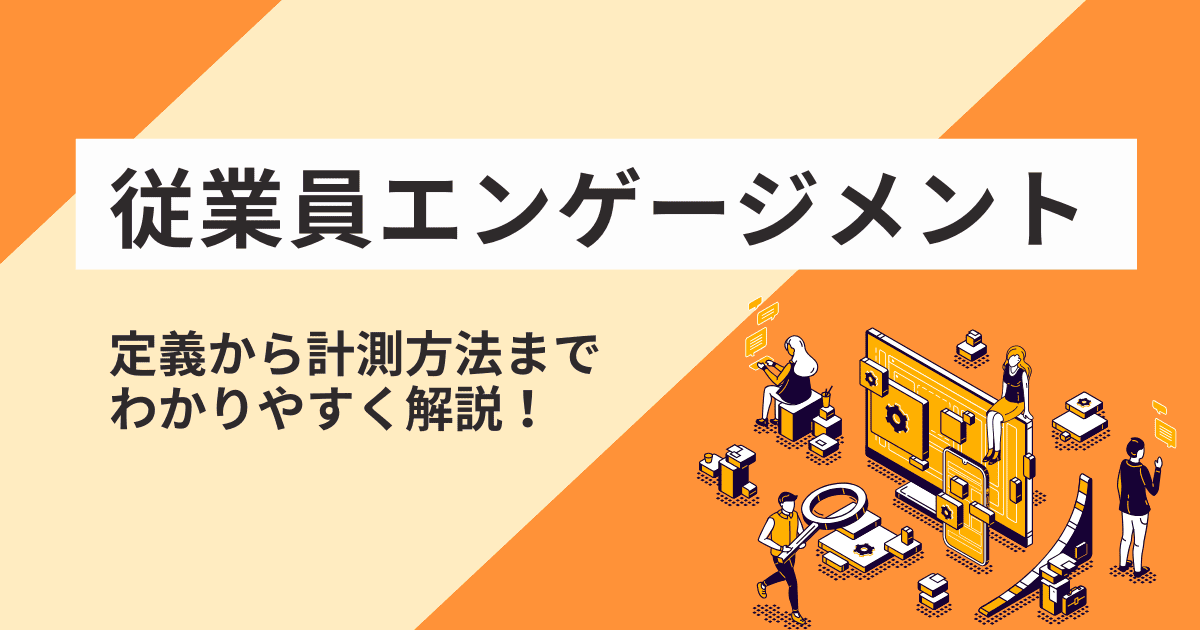
従業員満足度との明確な違い
エンゲージメントスコアは、しばしば「従業員満足度(ES)」と混同されがちですが、両者は根本的に異なる概念です。従業員満足度は、給与、福利厚生、労働時間といった待遇や環境に対する従業員側の「満足」の度合いを測る指標です。これは主に企業から従業員への一方向的な関係性に基づいています。
| 項目 | エンゲージメントスコア | 従業員満足度 |
| 関係性 | 企業と従業員の双方向 | 企業から従業員への一方向 |
| 焦点 | 貢献意欲、信頼、共感 | 待遇、環境への満足 |
| 基盤 | 信頼関係、理念への共感 | 給与、福利厚生、労働条件 |
| 状態 | 能動的に貢献したい状態 | 働きやすさに満足している状態 |
従業員満足度が高くても、それは必ずしも企業の業績向上への貢献意欲に直結するわけではありません。一方で、エンゲージメントスコアは、従業員の能動的な貢献意欲を示すため、企業の生産性や業績と強い相関関係があることが特徴です。

なぜ今エンゲージメントスコアが重要視されるのか?
現代のビジネス環境において、エンゲージメントスコアの重要性は急速に高まっています。その背景には、経営の考え方の変化や、労働市場の構造的な問題があります。
人的資本経営における重要指標の普及
近年、従業員を単なる「労働力」ではなく、企業の価値創造の源泉である「資本」として捉える「人的資本経営」が世界的な潮流となっています。
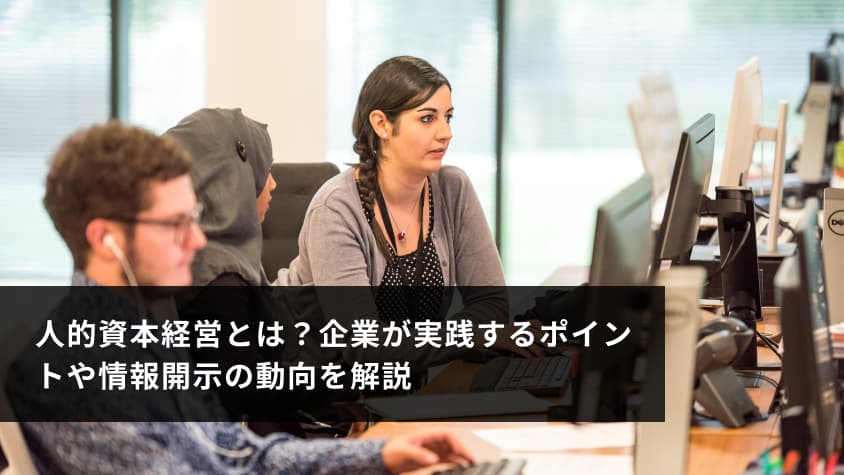
投資家も企業の持続的な成長性を判断する上で、財務情報だけでなく、人的資本に関する情報を重視するようになりました。エンゲージメントスコアは、従業員という資本がどれだけ活かされているか、その価値が最大化されているかを示す客観的なデータとして極めて有効です。
人的資本の情報開示が求められる中で、エンゲージメントスコアは企業の組織力の強さを示す重要な指標として活用されています。
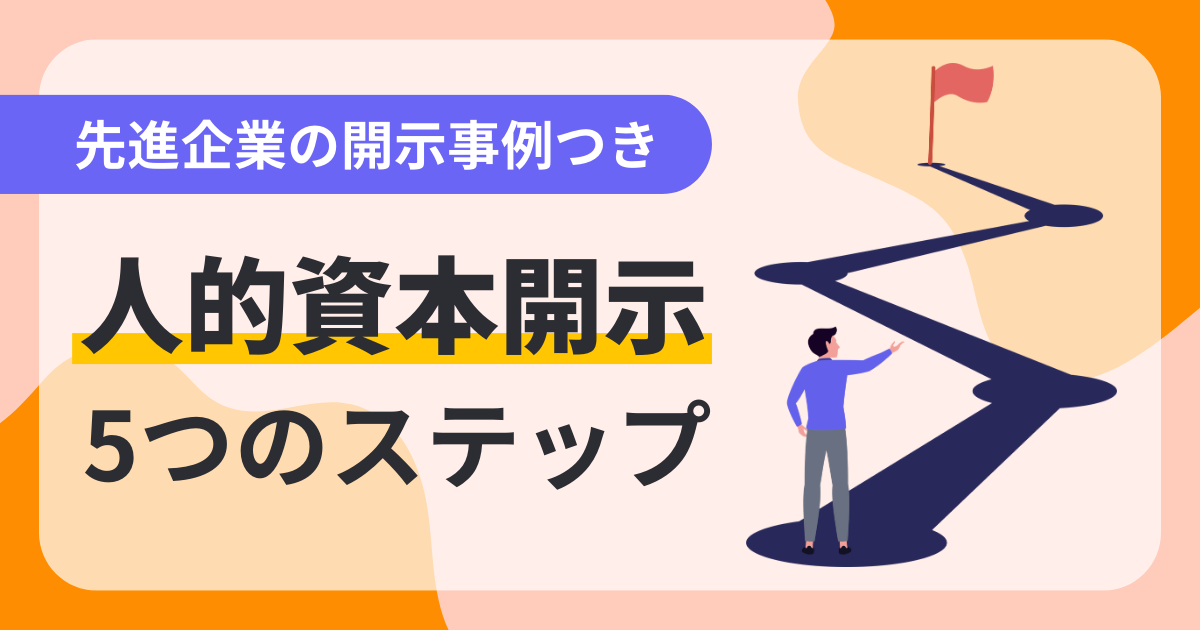
労働人口の減少と人材定着の必要性
日本では少子高齢化に伴い、生産年齢人口の減少が続いており、多くの企業で人材の確保が深刻な経営課題となっています。優秀な人材を獲得する競争が激化する中で、新たに採用するだけでなく、今いる従業員に長く活躍してもらうこと、つまり人材の定着が非常に重要です。エンゲージメントスコアの高い企業は、従業員が自社に強い愛着を持っているため、離職率が低い傾向にあります。
スコアを定期的に測定し、改善していくことは、優秀な人材の流出を防ぎ、持続的な企業成長の基盤を築く上で不可欠な取り組みと言えます。
エンゲージメントスコアを高める4つのメリット
エンゲージメントスコアを高めることは、企業経営に多岐にわたる具体的なメリットをもたらします。ここでは、代表的な4つのメリットについて解説します。
従業員の生産性が向上する
エンゲージメントスコアが高い従業員は、自身の仕事に誇りとやりがいを感じ、企業の成功に貢献したいという強い意欲を持っています。そのため、与えられた業務をこなすだけでなく、より良い成果を出すために自発的に工夫し、行動するようになるのです。厚生労働省の調査においても、ワークエンゲージメントの高い従業員ほど、労働生産性が高いと認識している傾向が示されています。
このような従業員が増えることで、組織全体の生産性が向上し、企業の業績アップに直接的に繋がります。
【参考】https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/19/backdata/2-3-11.html
人材の定着率が高まり離職を防ぐ
従業員が「この会社で働き続けたい」と感じるかどうかは、待遇だけでなく、企業への愛着や仕事へのやりがいに大きく左右されます。エンゲージメントスコアは、この「働き続けたい」という想いの強さを反映しているのです。スコアが高い組織では、従業員と企業の間に強固な信頼関係が築かれており、些細な不満で離職を考える従業員は少なくなります。
実際に、エンゲージメントスコアと離職率には負の相関があることが多くの調査で示されており、スコア向上は人材定着のための効果的な施策となります。
組織に潜む課題を発見し解決できる
エンゲージメントスコアを部署や役職、勤続年数といった属性別に分析することで、組織内に潜む課題を客観的に発見できます。例えば、特定の部署だけスコアが低い場合、その部署のマネジメントや業務プロセスに問題がある可能性が考えられます。
また、スコアが全体的に低下している場合は、経営方針や企業文化に関する根本的な見直しが必要かもしれません。感覚や憶測に頼るのではなく、データに基づいて課題を特定できるため、的を射た改善策を迅速に実行し、組織を健全な状態に導くことができます。
顧客満足度の向上に繋がる
エンゲージメントの高い従業員は、自社の製品やサービスに自信と愛情を持っています。その想いは、顧客への対応にも自然と表れます。どうすればもっと顧客に喜んでもらえるかを自発的に考え、質の高いサービスを提供しようと努力するため、結果として顧客満足度の向上に繋がるのです。従業員の熱意が顧客に伝わり、企業のブランドイメージや信頼性を高めるという好循環が生まれます。
従業員のエンゲージメント向上は、巡り巡って企業の市場における競争力を強化します。
エンゲージメントスコアの代表的な計測方法
エンゲージメントスコアを正確に把握するためには、適切な方法で調査(サーベイ)を実施する必要があります。ここでは、広く用いられている2つの代表的なサーベイ手法を紹介します。
組織全体を把握するエンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイは、年に1回や半年に1回といった頻度で実施される、大規模な意識調査です。数十問からなる詳細な質問項目を通じて、従業員のエンゲージメント状態を多角的に、かつ深く掘り下げて測定します。このサーベイは、組織文化やリーダーシップ、成長機会、待遇など、エンゲージメントに影響を与える様々な要素について従業員の期待度と満足度を問うものです。
組織全体の課題や強みを網羅的に把握し、次年度の経営計画や人事戦略に反映させるための基礎データとして活用されます。
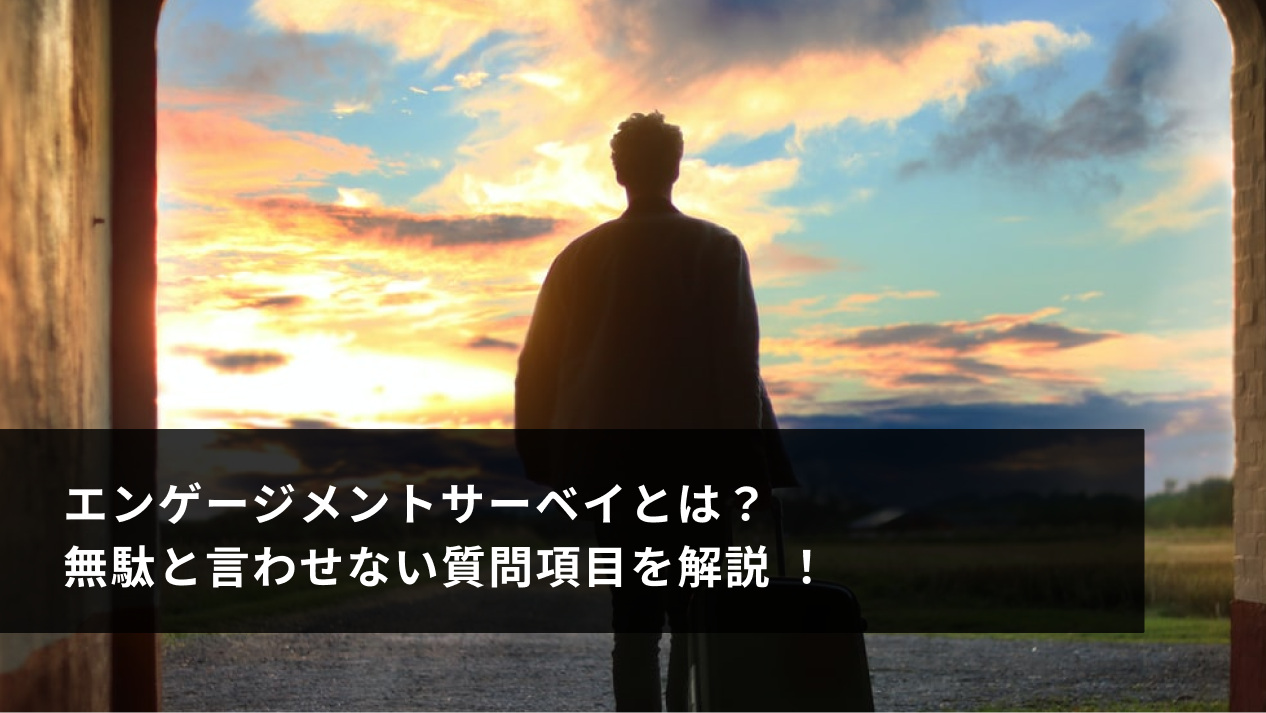
定期的な観測を行うパルスサーベイ
パルスサーベイは、その名の通り「脈拍(パルス)」を測るように、短い間隔で簡易的な調査を繰り返し行う手法です。週に1回や月に1回といった高頻度で、5〜15問程度の少ない質問に絞って実施します。これにより、従業員のコンディションの変化や、特定の施策(新しい制度の導入など)が与えた影響をリアルタイムに近い形で把握できます。エンゲージメントサーベイで特定された課題に対する改善アクションの効果を継続的にモニタリングし、必要に応じて迅速に軌道修正を行う際に非常に有効です。
| 調査方法 | エンゲージメントサーベイ | パルスサーベイ |
| 実施頻度 | 年1回~半年に1回 | 月1回~週1回 |
| 質問数 | 50~100問程度 | 5~15問程度 |
| 目的 | 組織全体の網羅的な課題把握 | リアルタイムな状態観測、施策の効果測定 |
| 特徴 | 長期的な視点での戦略立案に活用 | 迅速な課題発見と軌道修正に有効 |

エンゲージメントスコア向上に繋がる具体的な施策例
エンゲージメントスコアを高めるためのポイントを踏まえ、多くの企業で実践され、効果を上げている具体的な施策例を3つご紹介します。
社内のコミュニケーションを活性化させる
エンゲージメントを高めるための第一歩には、自分がどんな組織で働いているのか、どんな人と一緒に働いているのかを知るという「組織理解」「同僚理解」が重要です。
組織がどのような方針で動いており、社会にどのようなインパクトを与えたいのか、その組織にはどんな人がいてどんな仕事をしているのか、そして自分の仕事がそれらとどのように繋がっているのかを知ることで、組織に対する信頼や同僚に対する連帯感、さらに自分の仕事への誇りが育まれます。
これらの理解を深めるためには、それぞれ適切な社内コミュニケーション戦略が必要になります。
以下の記事では、社内コミュニケーション施策について事例を踏まえて詳しく解説しておりますので、ぜひ併せてご覧ください。
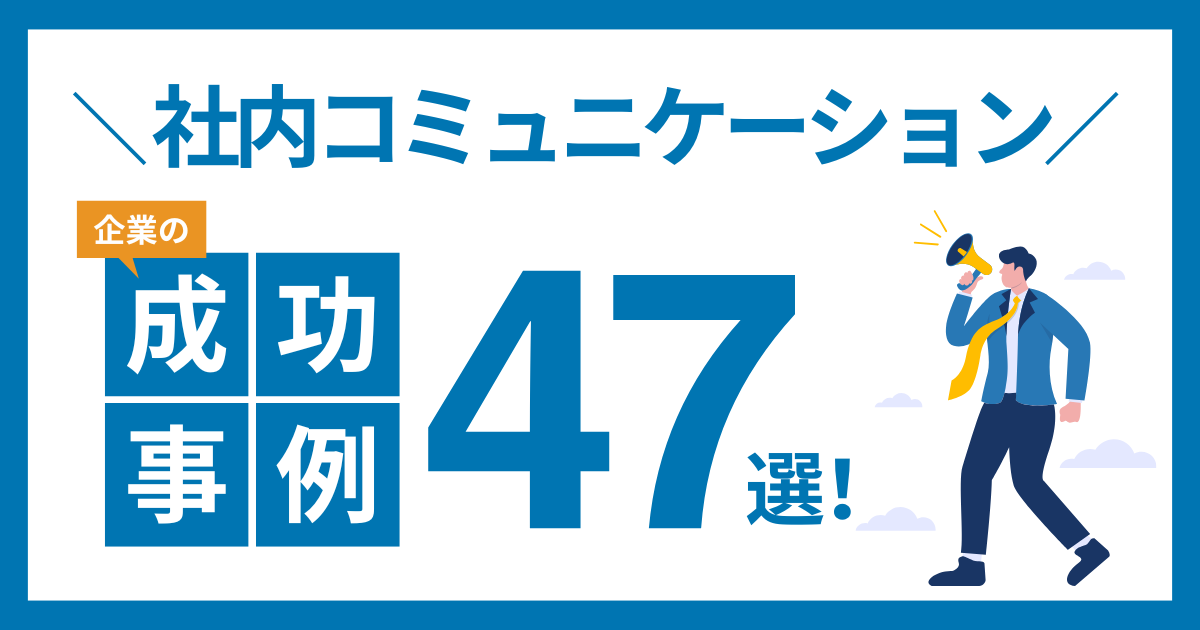
1on1ミーティングの定期的な実施
1on1ミーティングは、上司と部下が1対1で定期的に行う対話の場です。業務の進捗確認だけでなく、部下のキャリアの悩み、プライベートの状況、人間関係の課題など、幅広いテーマについて話し合います。この対話を通じて、上司は部下への理解を深め、信頼関係を構築することが可能です。
部下は「自分のことを気にかけてくれている」と感じ、心理的な安全性が確保されることで、エンゲージメントが高まります。週に1回30分、あるいは隔週に1回など、頻度と時間を決めて継続することが重要です。

従業員のキャリア形成を支援する
従業員が「この会社にいれば、自分は成長できる」と将来の展望を持てることは、エンゲージメントを維持する上で非常に重要です。企業は、従業員が自身のキャリアプランを考え、実現していくための支援制度を整えるべきです。例えば、社内公募制度やFA制度を導入して挑戦の機会を提供したり、資格取得支援や研修プログラムを充実させたりすることが挙げられます。従業員一人ひとりの成長意欲に応える姿勢が、企業への貢献意欲を引き出します。
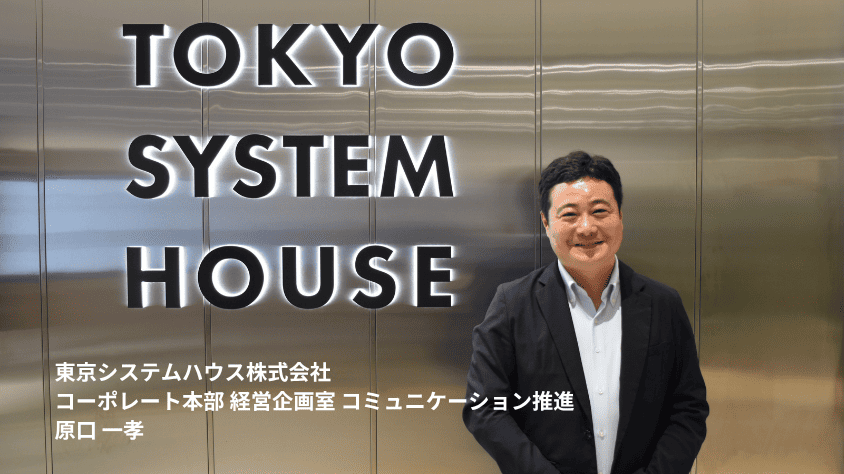
エンゲージメントを高める社内コミュニケーションツール「ourly」
ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制の強みを持ち、新たな社内コミュニケーションを創出する魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「社内の雑談が減った」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
まとめ
エンゲージメントスコアは、現代の企業経営において避けては通れない重要な指標です。このスコアを正しく理解し、継続的に測定・改善していくことは、生産性の向上、離職率の低下、そして持続的な企業成長を実現するための鍵となります。
本記事で解説したポイントや施策を参考に、自社のエンゲージメントを高める第一歩を踏み出してください。