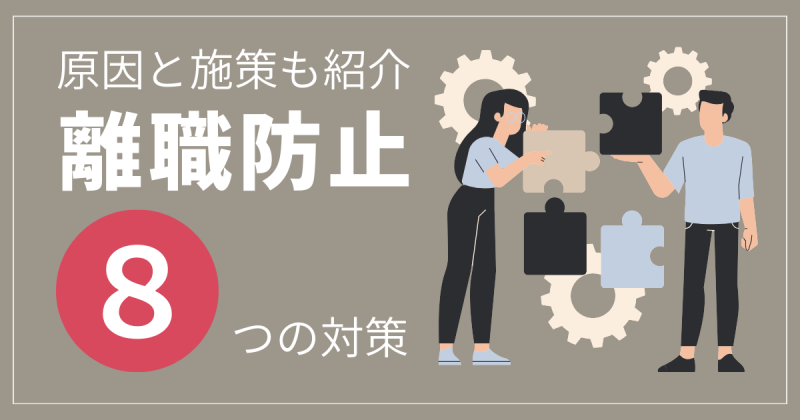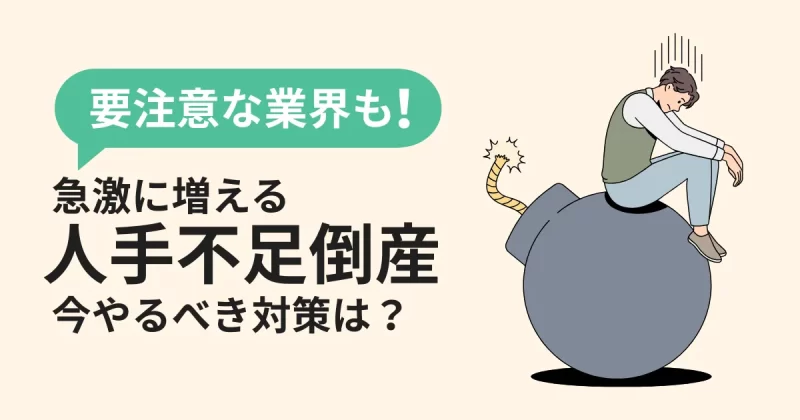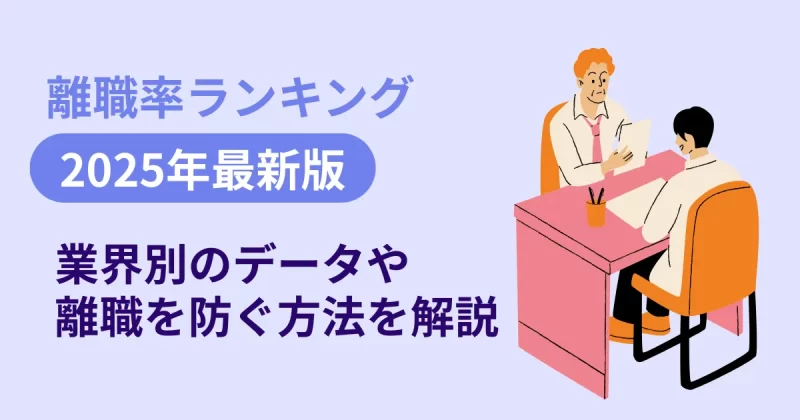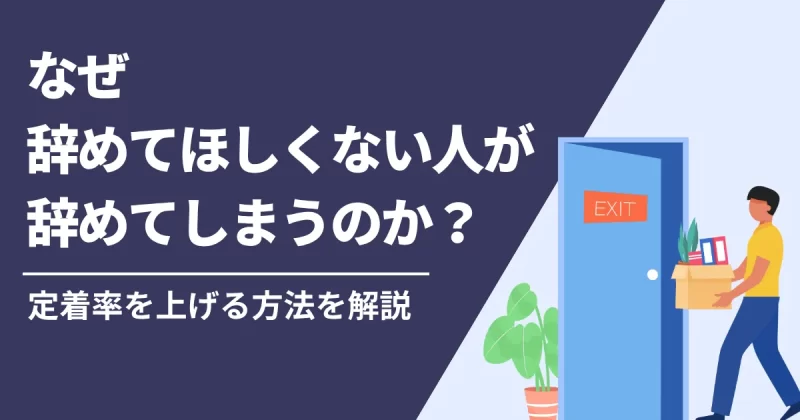離職防止対策をすることで、人材コストの損失を防いだり、企業のイメージダウンを防いだりできますが、離職防止が最も困難な課題の一つでもあります。
コロナ禍によって働きかたが大きく変わる中で、離職率が高まってる企業の担当者も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では離職をする従業員の本音を原因として紹介し、離職防止に利く8つ対策と企業の成功事例を徹底解説していきます。
こちらの記事では、離職率に関してデータを用いて解説していますので、ぜひご覧ください。
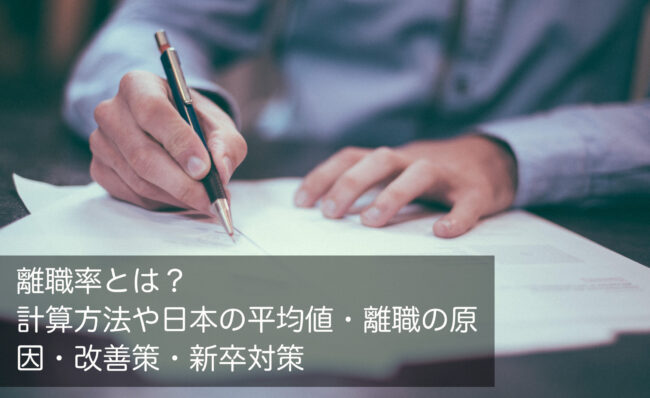
離職防止とは?
離職防止とは、社員が自社を辞めてしまうことを防ぐための、あらゆる取り組みを指します。リテンションマネジメントとも呼ばれ、単に退職者数を減らすだけでなく、社員が意欲的に長く働ける環境を整えることで、企業の持続的な成長を目指す重要な経営戦略の一つです。
離職防止の対策が必要な理由
ここでは、離職防止対策が必要な理由を解説します。
「ひとり辞めてもまたひとり雇えばいい」という考えもありますが、あえてひとりを長く雇用し続けることのメリットを学び、マネジメントに役立てていきましょう。
採用・教育コストの損失を防ぐため
離職防止が成功するということは、採用・教育コストの損失防止にもつながります。例えば、新卒での入社予定者1人あたりの採用費平均は、56.8万円という統計が出ています。
(参考:https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2023/11/s-kigyonaitei-24-003.pdf )
内定者研修・新卒研修に加え、都度発生する研修・トレーニングのコストも加えれば、従業員ひとりを育てるには膨大な費用がかかることが分かるでしょう。
離職により人員補充をする場合、新たに上記のような費用がかかります。1から育て直しになるコストと工数を比較すると、離職防止に手間をかけた方がいいと言えるでしょう。
企業のイメージダウンを防ぐため
離職者の大半は企業に不満を抱いて辞めていくため、両者共にwin-winの関係性にはならないものです。
「頑張っているのに正しく評価されず、いつまでも給料が据え置きだった」「突発的な残業依頼が多く、プライベートとの両立が難しかった」などの不満がいつの間にか広がり、企業のイメージダウンになることもあるでしょう。
近年は会社の内情を吐露する口コミサイトやSNSによる情報拡散も盛んなため、従業員満足度に目を向けておくことが欠かせないのです。
人手不足と従業員の負担増加を防ぐため
突発的な離職が相次いだ場合、現場に残る従業員への不満が増してしまいます。
人手不足をカバーするために長時間労働したり、通常業務に加えて引継ぎ業務をしたりすることで、多忙を極めるようになります。
そのため、これまで起きなかったような単純ミスや確認漏れが生じ、本来の業務に支障をきたすことも少なくありません。
加えて、ルーティンワークを最低限こなすことだけに必死になり、クリエイティブな提案や新しいアイディアの創出が阻害されることもあるため、企業としての底力も減ってしまいがちです。
従業員の離職がもたらす4つの経営リスク
従業員の離職は、単に「社員が一人減る」というだけでは済みません。企業経営に多大な影響を及ぼす、さまざまなリスクをはらんでいます。ここでは、離職がもたらす4つの具体的なリスクについて解説します。
優秀な人材の流出による競争力の低下
企業にとって最も大きな痛手となるのが、豊富な経験や専門スキルを持つ優秀な人材の流出です。彼らが去ることは、業務ノウハウや顧客との信頼関係といった無形の資産を失うことを意味し、製品やサービスの質の低下に直結しかねません。結果として、企業の競争力が削がれ、事業の成長が鈍化する大きな原因となります。
採用・再教育にかかるコストの増大
一人の社員が離職すると、その穴を埋めるために新たな人材を採用し、一から教育するためのコストが発生します。求人広告費や人材紹介会社への手数料、そして採用担当者の人件費など、採用活動には多額の費用が必要です。株式会社リクルートの調査によれば、2020年における中途採用一人あたりの平均採用コストは103.3万円にも上ります。離職者が増えるほど、このコストは企業の財政を圧迫していくことになります。
既存社員の業務負担増とモチベーション低下
離職者が出ると、その業務は残された既存社員で分担せざるを得ません。これにより、一人ひとりの業務量が増加し、時間外労働の増加や心身の疲労につながります。十分な人員補充がされないままの状態が続くと、社員の不満が蓄積し、「自分も辞めたい」と考える「離職の連鎖」を引き起こす可能性も高まります。職場の士気が下がり、組織全体の生産性が低下するという悪循環に陥ってしまうのです。
企業ブランドイメージの悪化と採用難
離職率が高いという事実は、企業の評判にも影響します。現代では、口コミサイトやSNSを通じて、「あの会社は人がすぐに辞める」といった情報が瞬く間に広まります。「ブラック企業」というイメージが定着してしまうと、顧客や取引先からの信頼を失うだけでなく、新たな人材を採用しようとしても応募者が集まらない「採用難」という深刻な事態を招きます。
離職する可能性が高い社員の特徴
従業員が離職を考え始めると、その予兆が日々の行動や態度に現れることが少なくありません。これらのサインは、従業員が何らかの不満や悩みを抱えているSOSである可能性があります。もちろん、これから挙げる特徴が必ずしも離職に直結するわけではありませんが、管理職や人事がこれらの変化を早期に察知し、適切なコミュニケーションをとることが、離職を防ぐための重要な鍵となります。
仕事へのモチベーションや態度の変化
最も分かりやすいサインの一つが、仕事に対する熱意や姿勢の変化です。以前は積極的に会議で発言していた社員が口数少なくなったり、新しいプロジェクトへの参加をためらうようになったりするのは注意が必要な兆候と言えます。 また、これまでには見られなかったようなケアレスミスが増えたり、ミスをしても反省の態度が見えなくなったりする場合も、仕事への関心が薄れている可能性があります。 このような態度の変化は、現在の仕事内容や役割に対する不満の現れかもしれません。
コミュニケーションの量や質の低下
職場でのコミュニケーションの変化も、離職を考えているサインとなり得ます。例えば、以前よりも同僚との雑談が減り、挨拶をしなくなるなど、周囲との関わりを意図的に避けているように見えるケースです。 上司への報告・連絡・相談が遅れたり、内容が雑になったりする場合も注意が必要です。これは、組織への帰属意識が低下し、心理的な距離を置こうとしていることの表れかもしれません。

勤怠や行動パターンの変化
勤怠状況や日々の行動パターンにも、離職の兆候が見られることがあります。特に、遅刻や早退、理由の不明確な欠勤が増えるのは、会社への足が遠のいているサインと考えられます。 また、これまで残業が多かった社員が定時で帰るようになったり、会社の飲み会やイベントへの参加を断るようになったりするのも、会社との関わりを減らそうとしている行動と捉えることができます。 このような変化は、転職活動に時間を使っている可能性も示唆しています。
よくある離職の原因
まずは、従業員が離職する代表的な原因を紹介します。
離職の話が出てから本人にヒアリングしてもなかなか本音が出てこないケースもあるため、どんなことが不満として蓄積されやすいか、知っておくことが肝心です。
労働条件への不満
基本的な労働条件に不満がある場合、「長く働ける会社ではない」とみなされ、離職される可能性が高まります。
代表的なものとして、給与・賞与など報酬に関する不満が挙げられます。給料以上の働きを不当に求められている場合や、スキルに見合った報酬をもらえていないと感じる場合は、不満として現れやすくなるでしょう。
また、休日出勤・残業・持ち帰り仕事が多い、頻繁な転勤があって生活が安定しないなど、プライベートを阻害する働き方も問題視されることが多いです。
労働基準法を遵守するだけでなく、従業員のワークライフバランスにも目を向けて労働条件を見直してみる必要がありそうです。
職場での人間関係の問題
職場での人間関係が悪く、常にギスギスした雰囲気になっている場合は要注意です。
上司や同僚と信頼関係が築けないため常にストレスフルな環境で働くことになり、居心地のいい会社とは言えなくなってしまうでしょう。場合によっては業務上必要な情報共有が適切におこなわれず、ミスや抜け・漏れに繋がる可能性もあります。
また、職場いじめやパワハラ・セクハラなど深刻なトラブルは、経営層からはなかなか見えにくいものです。
「会社は何も分かってくれなかった」という不満のみを残して離職する可能性もあり、大きなリスクであることを知っておきましょう。

企業の将来に対する不安
業績悪化・取引先の離脱・業界内外の評判悪化など、自社の将来性が疑われるような要素があると、離職が起こります。
また、自社の収益が可視化されていない場合や、会社が目指す方向性に賛同できない場合、そもそも会社が目指す方向が示されていない場合にも、不満が高まります。
加えて、離職者が相次ぐことで「自分もそろそろ転職しないと危ないかな」と感じさせるマイナスインセンティブが働きます。
連鎖的に離職が起こす可能性もあるため、十分対策しておく必要があるでしょう。
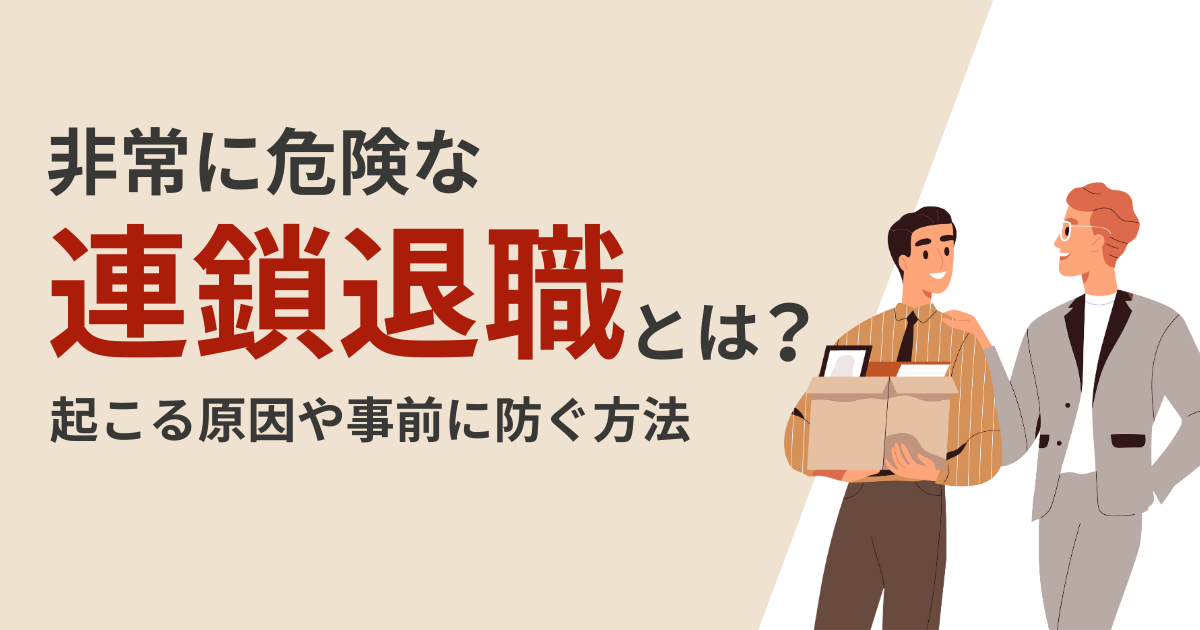
離職防止に有効な8つの対策
ここでは、離職防止に有効な施策8つを紹介します。
- 労働時間の是正
- 柔軟な労働条件の整備
- 人事評価制度の見直し
- 社内コミュニケーションの活性化
- 福利厚生の見直し
- 上司・管理職の教育(職場のハラスメント対策)
- キャリアパスを考える場を設ける
- 社内報を導入しエンゲージメントを高める
離職防止策を図りたいけれどどんな施策が効果的かイメージできない場合は、下記のような内容を参考に、導入案を検討してみましょう。
労働時間の是正
無理なく長期的に働いてもらうため、労働時間を是正する方法があります。
ノー残業デーを作ったり持ち帰り仕事を禁止したりすることで、プライベートや睡眠に影響しないバランスのよい働き方ができるようになるでしょう。
しかし、一方的に残業・休日出勤を禁止するだけでは、離職防止策として効果的ではありません。業務量が変わらないまま労働時間だけを是正した場合、会社都合での無理な施策であるとして却って不満が高まる可能性があります。
あくまでも、業務効率化を図ったうえで労働時間そのものを削減することを目的に、対策していきましょう。
柔軟な労働条件の整備
テレワークを認める、サテライトオフィスやコワーキングスペースを導入する、総合職と一般職の切り替えをしやすくする、フレックスタイム制や裁量労働制を採用するなど、柔軟な労働条件になるよう見直しを図る方法です。
例えば、これまで結婚・妊娠・出産を迎えた女性社員がほとんど退職している場合、パートタイムとして復職したり自宅近くの支店で時短勤務できたりする制度を導入することで、勤続率を高めることができるでしょう。
閑散期に交代で1週間まとめて有給を取ったり、リゾートワークやワーケーションを認めたりすれば、プライベートを重視したい従業員からの支持も高まります。
人事評価制度の見直し
公平かつ納得感の高い人事評価になっているか、見直しを図る方法です。
同じ年収400万円の人でも、「今後少しずつ年収が上がっていく見込みがある」と感じられている人と、「なぜ自分が400万円の評価なのかも分からないし今後キャリアアップの道があるかも分からない」と感じている人とでは、納得感が異なります。
まずは、上司ひとりの好き嫌いで評価される制度になっていないか見直し、360度評価や定性評価を取り入れてみるのがよいでしょう。
また、人事評価後には個別にフィードバックをおこない、評価の理由・今後キャリアアップするための方策・会社が期待していることをなどと伝えていくのが効果的です。
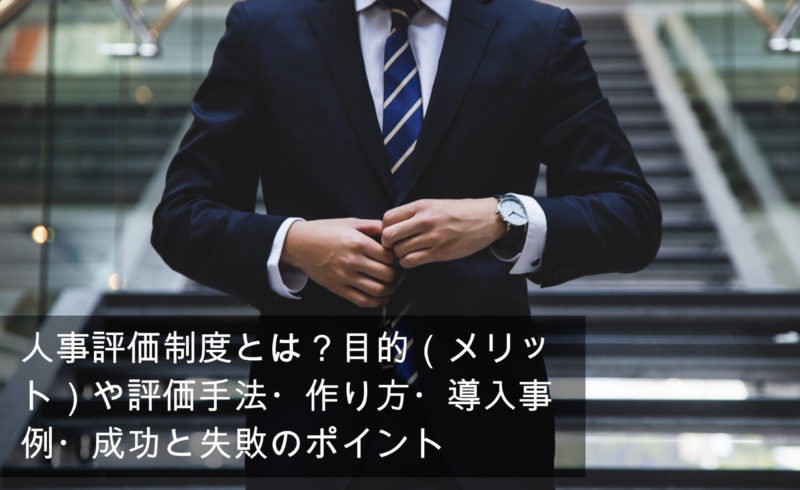
社内コミュニケーションの活性化
社内コミュニケーションを活性化し、誰でもいつでも相談し合いやすい雰囲気を作っていく方法です。
オープンで話しやすい社風を築ければ、業務上の相談事も、基本的な報告・連絡・相談もスムーズにおこなえるでしょう。時にはプライベートでの悩みも相談しあえるなど、風通しのよい組織として確立させることができます。
社内イベントやコミュニケーションゲームを企画し、普段業務上のやり取りをしない従業員同士の交流を深めていくのがおすすめです。
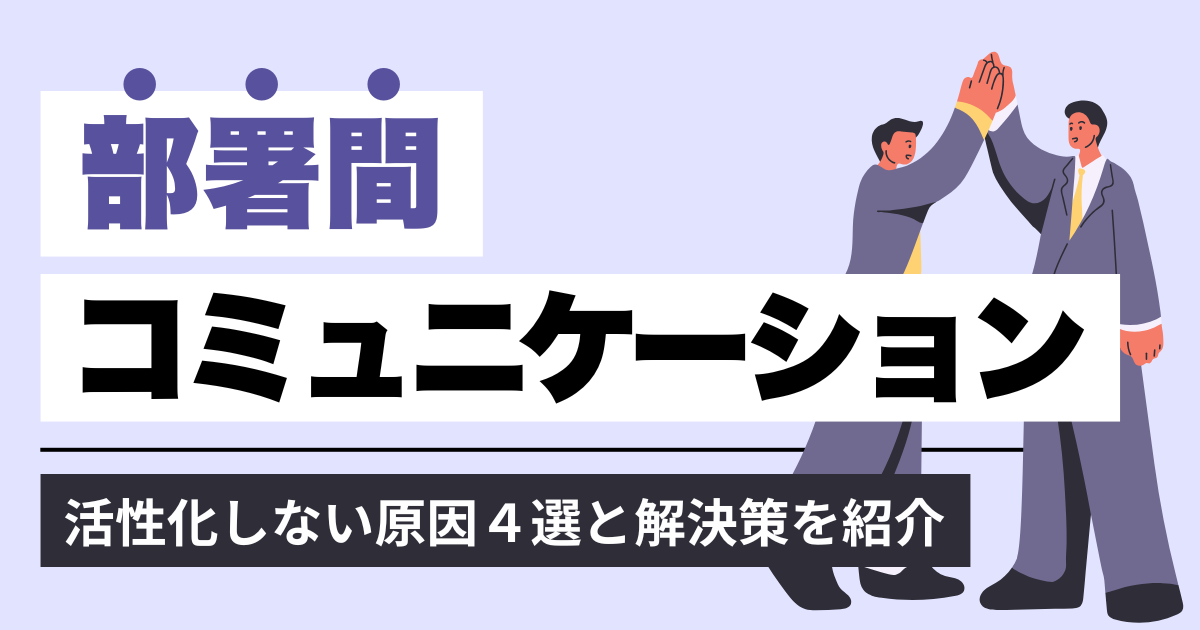

福利厚生の見直し
法定福利だけでなく法定外福利にも目を向け、自社ならではの福利厚生を整える方法です。
通勤手当・住宅手当・資格手当など毎月の収入をあげるための福利厚生や、カルチャースクール・語学レッスン・各種セミナー参加費の補助などスキルアップにつながる福利厚生を導入するのもよいでしょう。
また、社員旅行・運動会・社内サークル活動支援などをおこなえば、社内コミュニケーションの活性化と両立することも可能です。
なかにはオリジナリティあふれる面白い福利厚生を導入している企業もありますので、事例を調べながら社風にあったものを採用していきましょう。

上司・管理職の教育(職場のハラスメント対策)
マネジメント層への教育を強化し、パワハラ・セクハラの防止対策をする方法です。
ハラスメントはいじめや嫌がらせと異なり、無意識のうちにおこなってしまいやすいことが特徴です。
どんな事例がハラスメントに当たるのかケーススタディを調べ、自社に落とし込んで具体例を考えてみるなど、当事者意識を持たせる取り組みをおこないましょう。
また、ハラスメント以外のマネジメント研修をおこない、部下の不満・不安に早く気づけるよう対策していくことも効果的です。
不満の芽を早い段階で摘むことができれば離職防止にも役立ちますので、参考にしてみましょう。

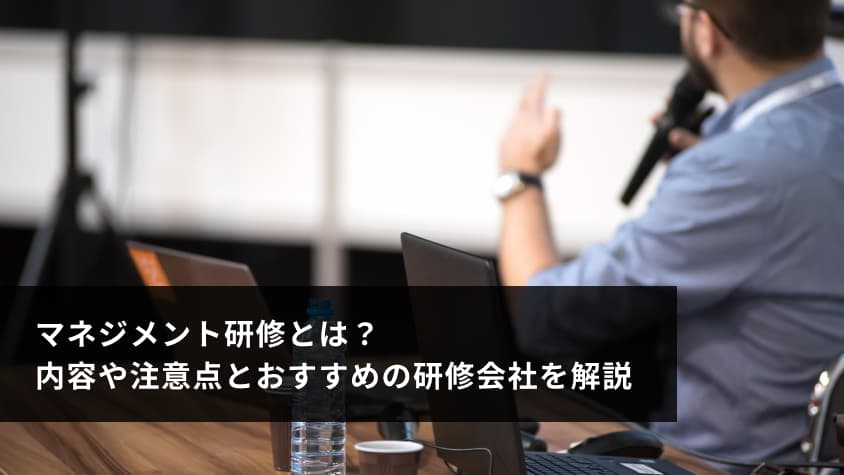
キャリアパスを考える場を設ける
人事評価後におこなうマンツーマンフィードバックや、同役職・同年代だけを集めておこなう研修の場で、キャリアパスを考えさせる方法です。
仕事や働き方に対する理想は人それぞれであり、目指すべき方向性も少しずつ異なるでしょう。
年収アップや役職アップを第一目標に据える人もいれば、マネジメントではなく現場で働くプロフェッショナルプレイヤーとしてスキルアップしていきたい人もいます。
自分の理想像を言語化し、人に伝える場を定期的に設けておけば、自分のやるべきことも見えやすくなります。
五里霧中状態で働く従業員を少なくできるため、離職防止施策として効果的です。



エンゲージメントを高める
従業員エンゲージメントや自社への帰属意識を高める方法です。
会社の先行きが不安と感じる従業員の多くは、自社のミッション・ビジョン・バリューを正確に理解できていないことが多いです。
成長戦略も見えておらず目先の業務だけに追われることが多いため、努力の目的や会社への貢献心を忘れてしまうケースもあるでしょう。
会社の考えや理念を全体に周知するうえで、有効なツールに社内報があります。
例えば、新たな商品サービスを展開するときは、社内報で「社運をかけている」という強いメッセージを配信したり、商品理解のための情報を発信したりできるため、有効活用していきましょう。
また、社内コミュニケーション活性化施策のひとつとして、社員インタビューや部署紹介をコンテンツとして盛り込んでいる企業も少なくありません。
自社についてより詳しく知ってもらい、仕事へのモチベーションにつなげるために、検討してみることをおすすめします。
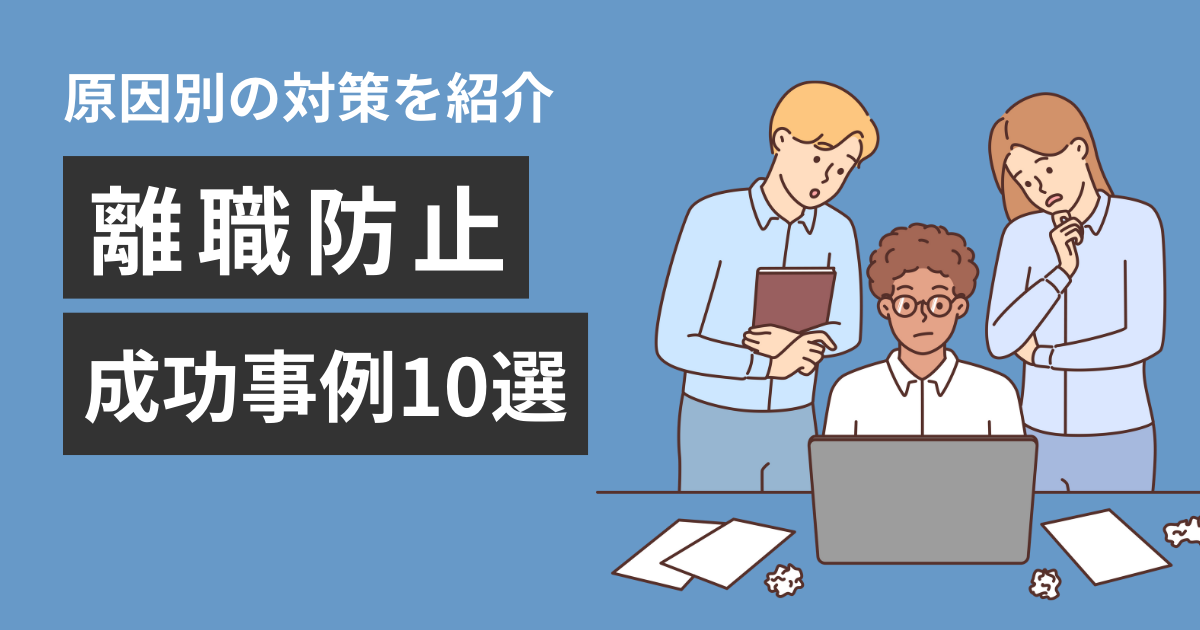
【資料】エンゲージメント向上に繋げる社内コミュニケーション施策の設計方法
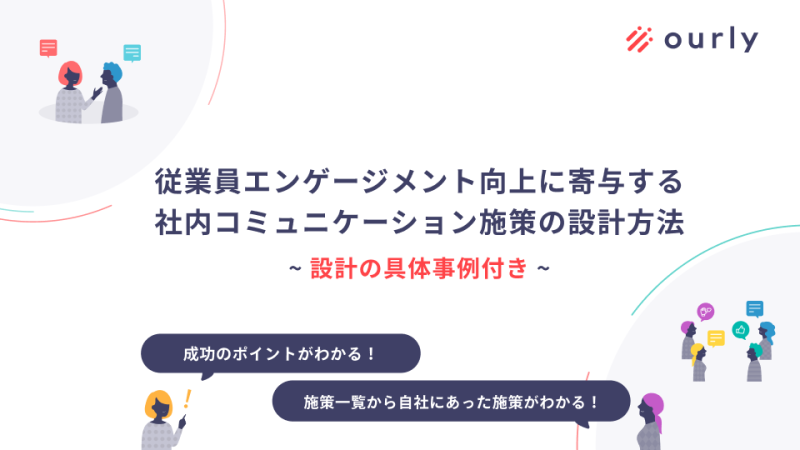
社内コミュニケーションの活性化は、組織にあった施策を適切に行い続けることで実現します。しかし、組織にあった施策を選ぶことは難しく、成果も見えづらいため、活性化に成功する企業は多くはありません。
そこで弊メディアでは、「自社にあった社内コミュニケーション施策の選び方」、「施策設計方法」「活用事例」をまとめた資料を作成しました。
組織の離職率やエンゲージメントスコア、理念・文化の浸透にお悩みの方は是非ご覧ください。
資料はこちら:https://ourly.jp/document/download_internalcommunication/
離職防止に適したweb社内報 ourly
ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
離職防止の一歩に社内報の導入を
離職防止施策は、業種・職種・地域・会社規模を問わずどんな会社でも急務の課題です。
従業員の離職によって生じる会社へのダメージを低減するためにも、従業員ひとりひとりにエンゲージメント高く働いてもらうためにも、離職防止施策を打ち出すことをおすすめします。
社内報は、社内コミュニケーションを活性化しながら会社の方向性を広く伝えられる手法として根強い人気があります。
特定の部署同士でしか会話が生まれないことに悩んでいる会社や、一方的なトップダウンでしか企業理念を示せない事に課題感を覚えている会社とも相性がよいでしょう。
まずは、施策の第一歩として社内報を導入してみてはいかがでしょうか。