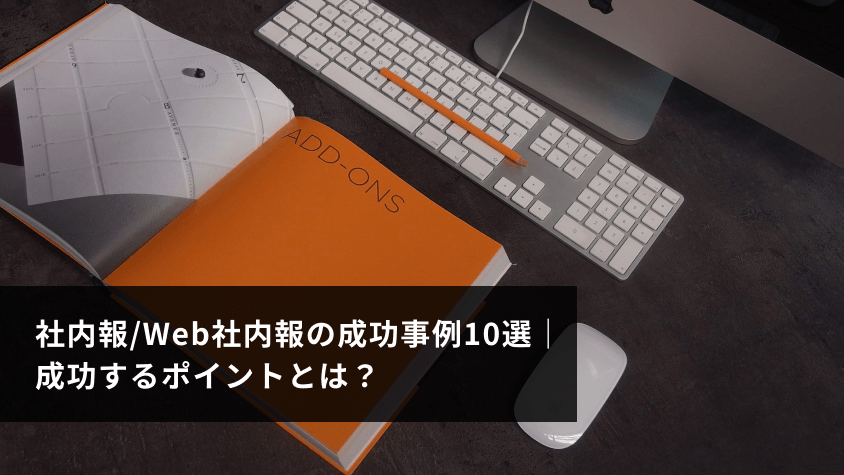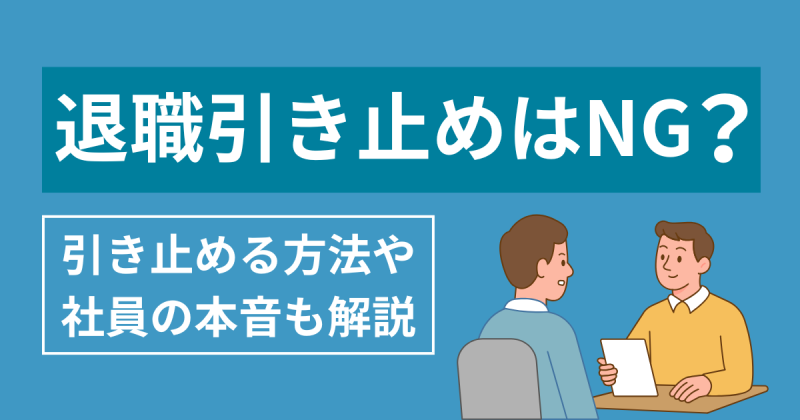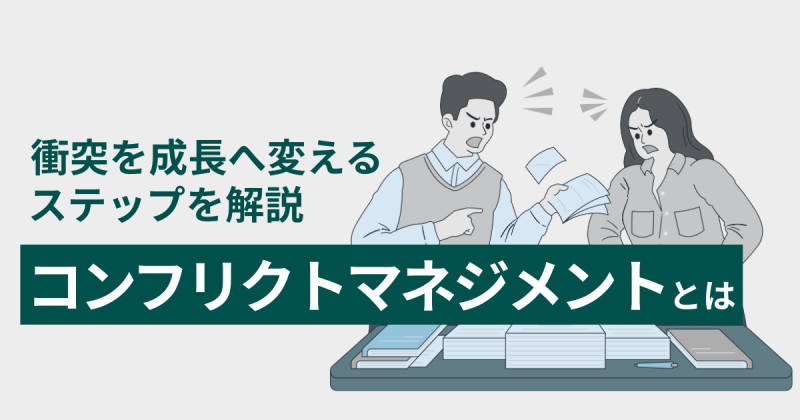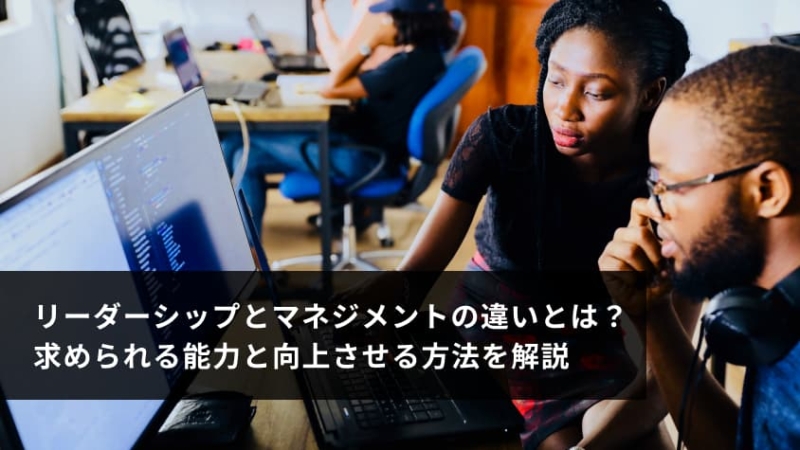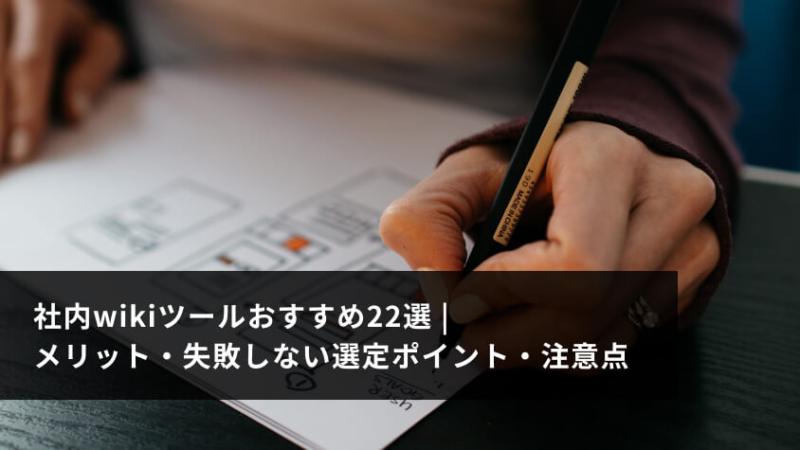どんなに離職防止の対策をしていても、想定外の退職を防ぎきることはできません。突然出される退職希望に直面し、対応を苦慮している方も多いのではないでしょうか。
本記事では、
- 退職しかねない社員の引き止め方を知りたい
- 退職の申し出があったときの注意点を確認したい
- 退職希望者への対応や接し方が分からず困っている
といった方々のために、不本意な退職を引き止める際に必要な対応や、避けるべきNG行動を解説します。退職の申し出をきっかけに社員の本音を把握し、企業における課題改善につなげていただけると幸いです。
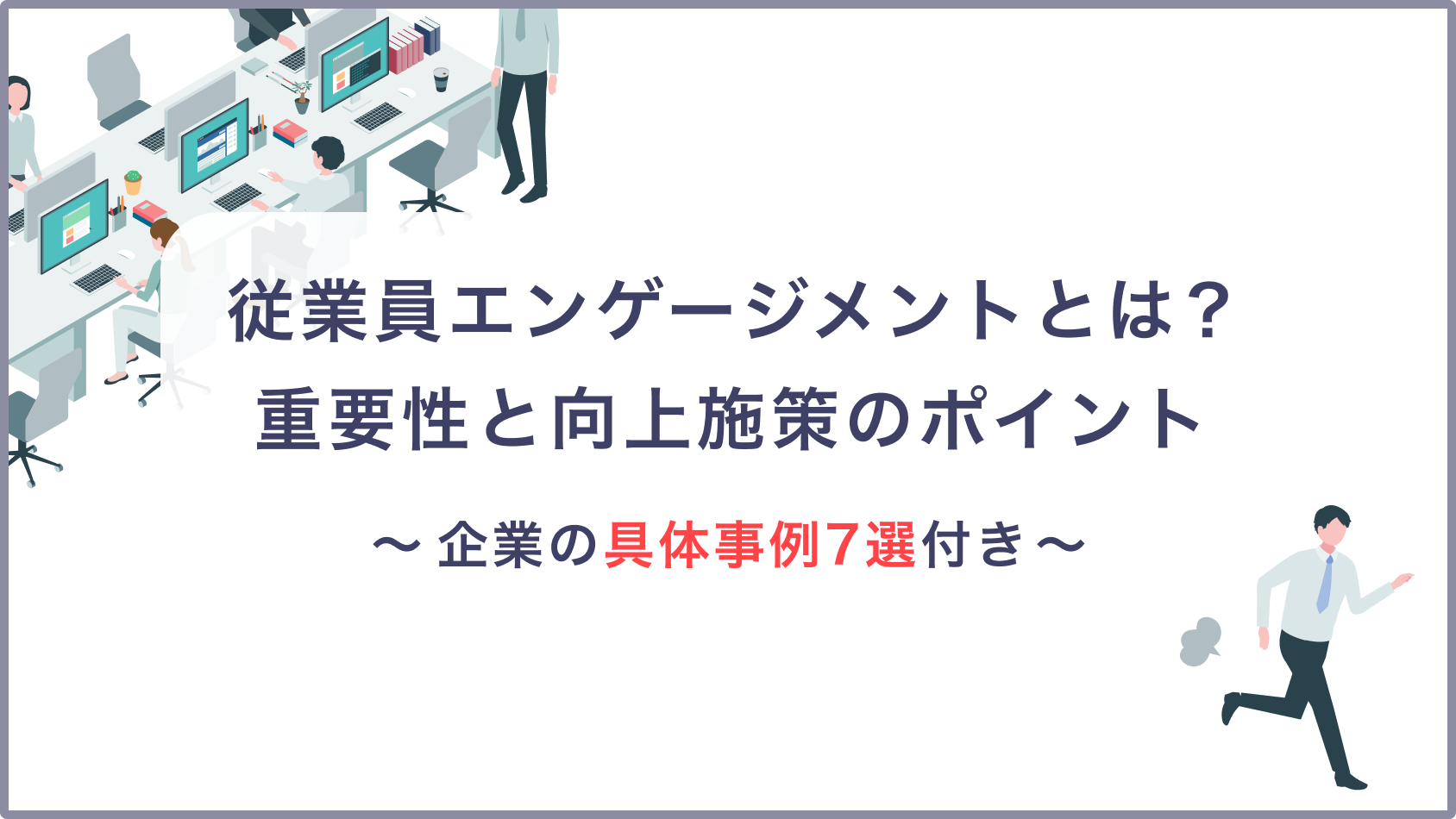
退職引き止めはNG?まず知っておきたい基本姿勢
部下から退職の相談を受けた際、まず考えるべきは「引き止めても良いのか」という点です。結論から言えば、引き止めること自体が問題になるわけではありません。しかし、その方法には細心の注意が必要です。
引き止めは違法ではないが、強要は禁物
労働者には「退職の自由」が法律で認められており、企業側が退職を無理に妨害することはできません。引き止めが度を越して、退職届の受理を拒否したり、脅迫的な言動で翻意を迫ったりすると「在職強要」とみなされ、違法行為となる可能性があります。あくまでも、部下の意思を尊重する姿勢が基本です。引き止めは、説得や交渉の範囲に留めるべきであり、決して強要になってはなりません。
退職理由の真意を理解することが第一歩
部下が口にする退職理由が、必ずしも本音であるとは限りません。円満な退職を望むあまり、当たり障りのない理由を建前として話しているケースは少なくないのです。例えば、「家庭の事情」や「一身上の都合」といった言葉の裏には、人間関係の悩みや待遇への不満、キャリアへの不安など、根深い問題が隠れている可能性があります。重要なのは、表面的な言葉を受け取るだけでなく、対話を通じて部下が本当に何に悩み、何を望んでいるのか、その真意を深く理解しようと努めることです。
退職を引き止める際に必要な4つの対応
退職を引き止める際、もっとも意識するべきことは、相手の気持ちや考えを理解しようとすることです。
退職を決断し意向を告げるまでに、本人のなかで相当な葛藤があったことが考えられます。熟慮の上の決断を頭ごなしに否定されると、それだけで「やはりこの会社にこれ以上いても無駄だ」という感情を呼びおこしてしまうでしょう。
どのような退職理由であれ、まず相手の話をすべて受け入れ、その上で引き止めの行動に出ることが原則です。
傾聴に徹し、本音を聞き出す
部下から退職の話を切り出されたら、まずは冷静に、そして真摯に相手の話を聞くことに徹してください。驚きや焦りから、すぐに反論したり、自分の意見を述べたりするのは禁物です。「そうか、話してくれてありがとう。まずは、どうしてそう考えるようになったのか、詳しく聞かせてもらえないかな?」と、相手が話しやすい雰囲気を作ることが重要です。遮ることなく、相づちを打ちながら、部下が自分の言葉で気持ちを整理し、話し尽くせるように促しましょう。この段階の目的は、説得ではなく、あくまでも理解です。
これまでの貢献への感謝を具体的に伝える
部下の話を一通り聞いた後は、これまでの会社やチームへの貢献に対して、具体的なエピソードを交えながら感謝の気持ちを伝えます。「〇〇のプロジェクトでは、君の粘り強い交渉のおかげで契約が取れた。本当に助かったよ」「いつもチームのムードメーカーとして、周りを明るくしてくれて感謝している」のように、具体的に伝えることで、会社があなたの働きをきちんと見て、評価していたというメッセージが伝わります。これは、部下の自尊心を満たし、冷静に今後のことを考えるきっかけを与える効果があります。
実現可能な改善策を具体的に提示する
部下の退職理由が、会社側の努力で改善できる問題である場合、具体的な解決策を提示します。例えば、業務負荷が原因であれば、人員の補充や業務分担の見直しを約束します。人間関係であれば、配置転換や他部署との連携強化を検討します。ここで重要なのは、その場で安易に実現不可能な約束をしないことです。「一旦持ち帰って、実現できるかどうかを真剣に検討させてほしい」と伝え、誠実に対応する姿勢を見せることが、信頼を得る上で不可欠です。
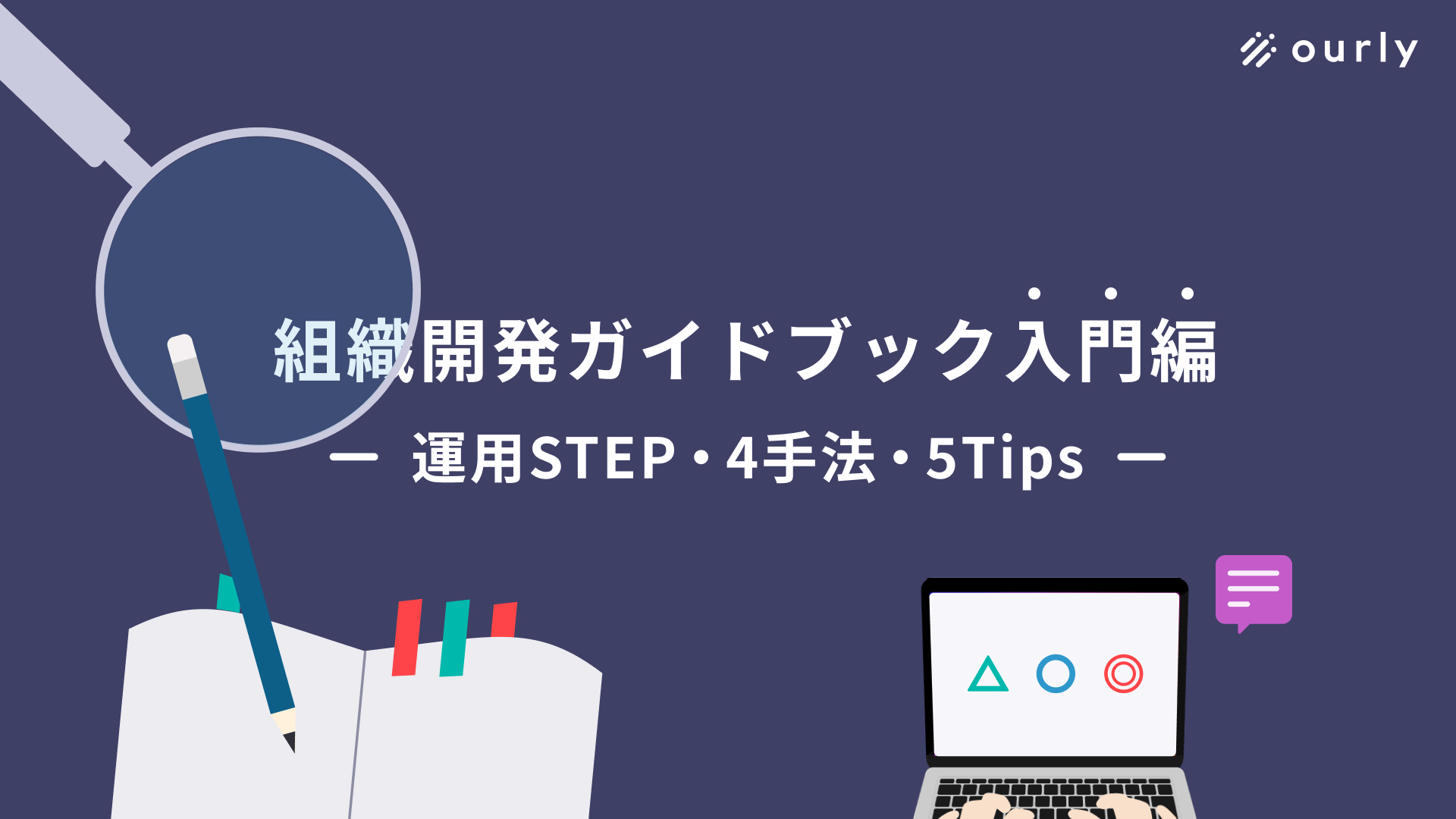
最終的な意思を尊重し、円満な着地点を探る
改善策を提示しても、部下の退職の意思が固い場合もあります。その際は、本人の決断を尊重する姿勢が大切です。「君の決意が固いことはよく分かった。会社としては非常に残念だけれど、君の新しい挑戦を応援したい」と伝え、円満な退職に向けた手続きに協力する意思を示しましょう。無理に引き止めて関係が悪化するよりも、快く送り出すことで、将来的に良好な関係を維持できる可能性があります。
退職を引き止める際に避けたい4つのNG行動
退職を申し出られた上司は、ショックから感情的になってしまうことも考えられます。しかし感情的になっても、引き止めに成功することは、まずないでしょう。引き止めの際に避けたいNG行動として、以下の4つを解説します。
- 感情をあおる言葉
- その場しのぎの約束
- 他の社員に不公平感を与える特別扱いをする
- 退職の意向を第三者に漏らす
いずれも、信頼関係を損ね、周囲へも悪影響を及ぼすため注意が必要です。
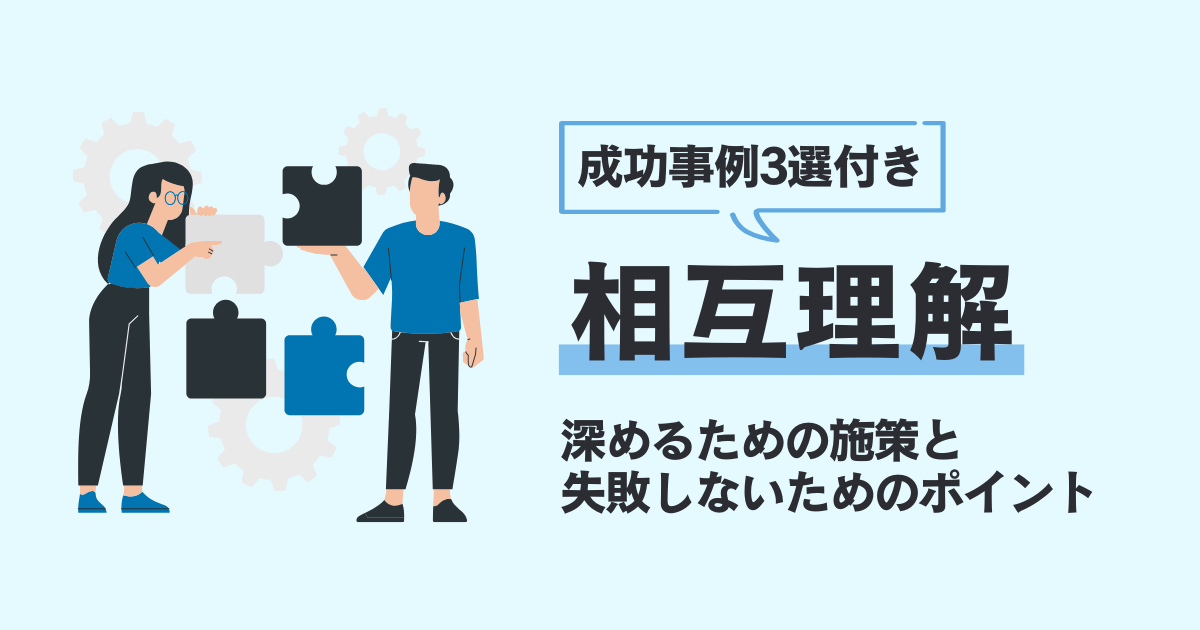
感情をあおる言動
退職の意向を告げられショックや怒りから、相手にネガティブな発言を投げかけることは避けるべきです。また心配するあまり、不安をあおるような発言もしてしまいがちですが、これも避けた方が良いでしょう。
「この先苦労するよ」とか「今の実力ではどこに行っても通用しない」など、ネガティブな発言は相手を傷つけるため、引き止めを成功させる可能性を限りなくゼロに近づけてしまいます。
その場しのぎの約束
退職理由となった不満が、給与面や人間関係であった場合、改善を申し出て引き止めることもあるかもしれません。しかし、人事異動や給与の改善がその場しのぎの口約束で終わった場合、たとえ退職を思いとどまったとしても、その後の信頼関係は望めません。
また、次の人員が決まるまで待つように頼むこともNGです。会社の都合を押し付けられているように感じ、不信感を抱いてしまいます。少なくとも、自分を必要としているのではないと感じ、気持ちが冷めてしまうでしょう。
退職を遺留する際は、「本当に相手のことを思って発言しているか」を常に顧みながら話しを進めなくてはいけません。
他の社員に不公平感を与える特別扱いをする
退職を申し出た部下だけを特別扱いすることも問題です。例えば、その部下だけに大幅な昇給を認めたり、特別な役職を与えたりすると、他の社員から「辞めると言った者勝ちか」という不満や不公平感が生じます。これは、チーム全体の士気を著しく低下させ、新たな退職者を生む火種になりかねません。待遇改善は、全社員に適用される公平な評価制度に基づいて行うべきです。
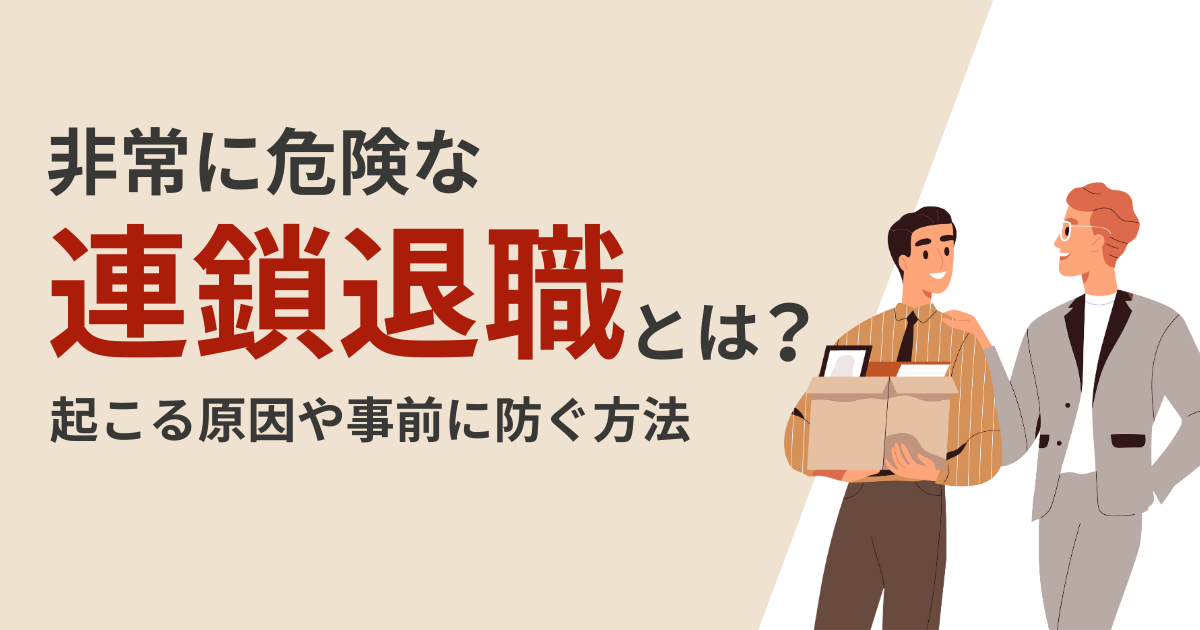
退職の意向を第三者に漏らす
部下から受けた退職の相談は、非常にデリケートな個人情報です。本人の許可なく、他の社員や関係のない部署の人に話してしまうことは、プライバシーの侵害にあたります。退職交渉中に噂が広まると、部下は会社に居づらくなり、退職の意思を撤回しにくくなってしまいます。相談は必ず当事者間、もしくは人事担当者など、必要最低限の範囲に留め、秘密を厳守してください。
退職を引き止められない場合の注意点
退職を申し出る社員は、相当の覚悟で意向を告げてきます。退職を思いとどまらせるのは、「まず難しい」という前提で話をすることが大切です。
そして、遺留できなかったとしても、「あなたの退職を今後の会社の改善に生かしたい」という姿勢を示すことも重要です。次の退職者が出ないよう、組織改善の糧にしなくてはなりません。
また、退職が決定しても、周囲が態度を変えないことも大切です。良いイメージのまま円満退職してもらうことで、退職後も自社にプラスの影響を与えてくれるかもしれません。

退職を希望する社員の本音
円満退社を希望する社員は、本音の退職理由を明かすことは少ないでしょう。しかし、本音の退職理由こそが、組織改善につながる大切なヒントであることは前述したとおりです。
退職を希望する社員の本音は、大きく次の3つに分類できます。
- 職場環境への不満
- 待遇への不満
- 将来への不安
社員が退職を考えるのは、これらの理由が単独、ないしは複合的に組み合わさっていると考えるべきでしょう。
社員が退職を希望する主な理由
職場環境の不満として挙げられるのが、「職場の人間関係」です。なかでも上司への不満が理由になっているケースは多いでしょう。
待遇への不満に挙げられるのが、給与や評価への不満です。仕事内容や労働時間が給与に見合っていなかったり、評価により将来の昇給に希望を見いだせなかったりする場合、生活面を考えて退職を決意することも考えられます。
また、会社の将来性や、自身のキャリアに展望がもてず、不安を感じての退職も増えているようです。転職市場が活況を呈するなか、自身のキャリアアップを目指しての転職は、若手人材にとって当たり前のことになりつつあります。
退職しかねない社員に見られる兆候
退職を考えている社員には、なんらかの兆候が見られるものです。まれに、なんの兆候もなく突然、退職の申し出に至る場合もありますが、多くは普段から注意して見ておくことで気がつけるものです。具体的な兆候を以下に挙げます。
- 勤務態度の変化(遅刻・早退が増える)
- 身だしなみの変化(急に整った身だしなみ)
- よそよそしい態度(挨拶をしない、付き合いが悪くなる)
- デスクの整理を始める(退職に向けての最終段階)
こうした兆候が感じられたら、できるだけ早い段階で話をしてみることです。
退職を引き止めるために日頃から意識すること
企業として社員の退職を防ぐためには、普段から社員に不満や不安を感じさせないことが大切です。そのためには、社員に魅力を感じてもらえるような組織風土の形成をしなくてはなりません。

社内コミュニケーションの活性化
社内コミュニケーションの活性化は、社員の退職を防ぐもっとも基本的な取り組みといえます。部署内のコミュニケーションだけにとどまらず、組織を横断したプロジェクトを立ち上げるなどして、積極的に組織内のコミュニケーションを推進している企業もあります。
また、人間関係の不満を解消するのもコミュニケーションの力です。上司と部下の良好な関係を構築するために、1on1ミーティングの実施も有効です。仕事上の悩みや、キャリア相談の窓口設置なども、良い取り組みといえるでしょう。
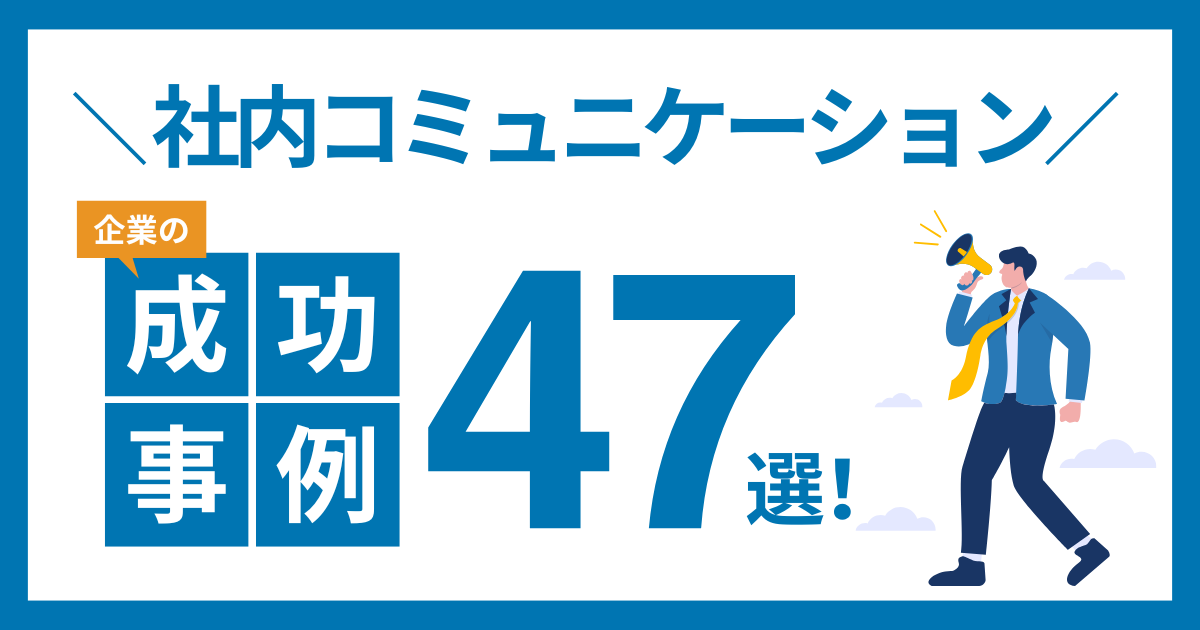
評価制度の定期的な見直し
自身の仕事が正しく評価されていないと感じることも、退職を考える大きな理由になります。評価制度に問題がある場合は、こうした社員が増えてしまいます。
評価制度は可能な限り、客観性と透明性が確保されていなければなりません。評価者である上司の好き嫌いといった主観が入りやすい制度は、社員の不満の種となります。
社員一人ひとりの、能力や貢献度が公平・公正に評価でき、適切に処遇に反映できる人事制度が理想です。定期的に見直しを図り、問題があれば改善し続けなくてはなりません。
離職対策に効果的|web社内報ourly
ourlyは、従業員のつながりを強化し、組織の離職リスクを低下できるweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとしても魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
退職を引き止められなくても企業改善に生かそう
退職の申し出を遺留することは、簡単ではありません。引き止められなかったとしても、本音の退職理由を正しく把握し、組織改善に生かしていくことで、次の退職者を出さないようにしていかなくてはなりません。
社員の退職を防ぐ根本的な取り組みは、社内コミュニケーションの活性化にあることに触れました。コミュニケーション活性化の施策として、Web社内報の導入という選択肢もあります。ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。