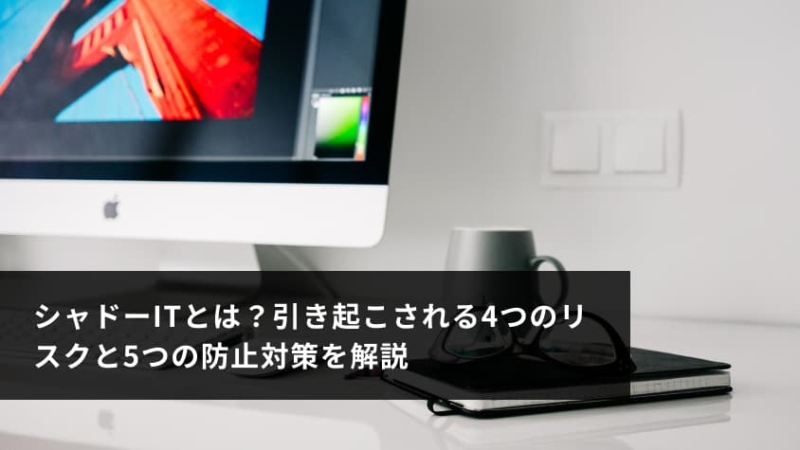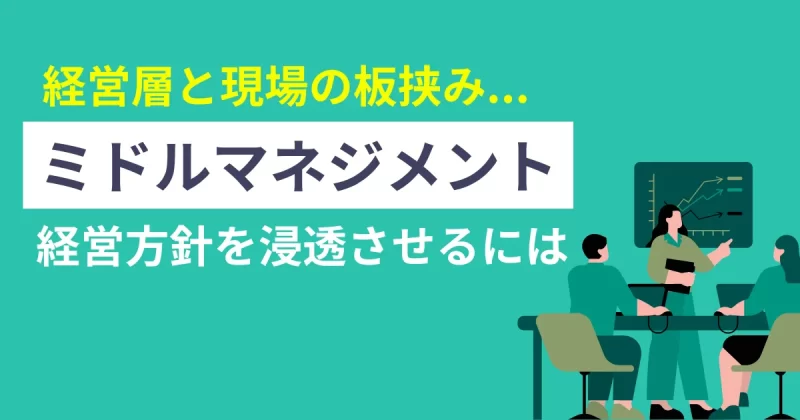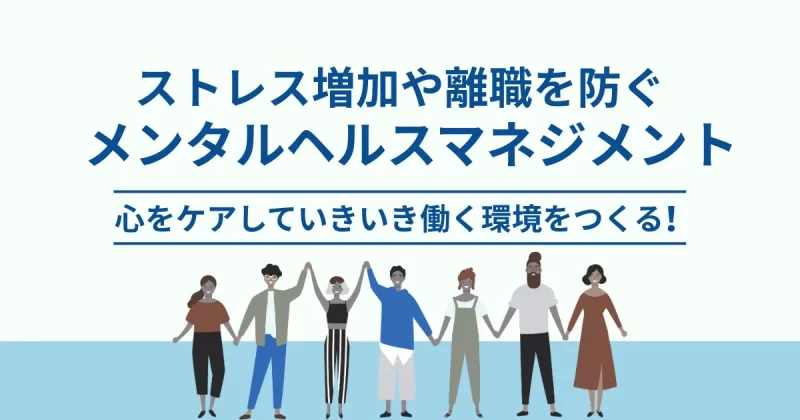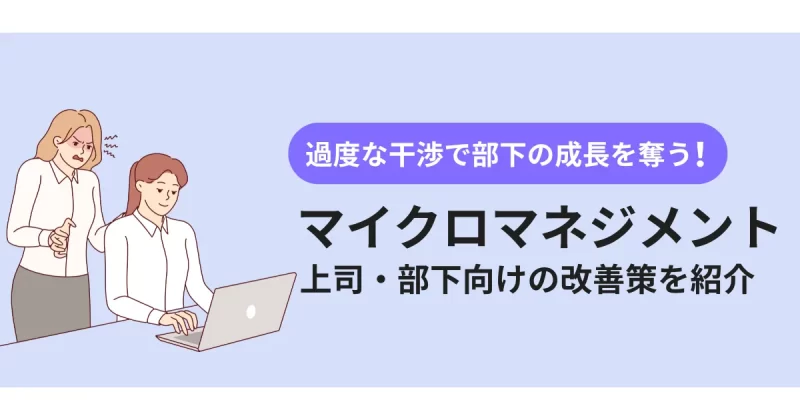シャドーITとは、企業の許可なしで従業員が使うデバイスやソフトウェア、クラウドサービスを指します。シャドーITが生まれる背景には、個人向けの便利なサービスが次々とリリースされるなかで、組織のIT環境整備が追い付いていない現状があります。
情報漏洩やデータの損失など、シャドーITがもたらすリスクは深刻です。また、コロナ禍を契機としたテレワークの普及により、これまで以上にシャドーITの危険性が高まっています。
本記事では、シャドーITを従業員が使う理由やシャドーITが引き起こす4つのリスク、そして5つの防止対策等について解説しています。これから社内のシャドーIT対策を進めたい企業や組織の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
シャドーITとは

シャドーITとは、企業の許可なしで従業員が使うデバイス・ソフトウェア・クラウドサービスを指します。会社の統制下にないままツールが使われてしまうので管理部門や上司が関与できず、知らぬうちにリスクが拡大してしまうことも少なくありません。
また、シャドーITはスマートフォンやクラウドの利用拡大に伴い、年々増加しています。シャドーIT対策することが自社のセキュリティ対策をするうえで重要視されているので、自社の危険性を正しく判定しておきましょう。
シャドーITが今注目される理由
シャドーITが注目されるようになった理由として、スマートフォンやタブレットなど手軽に使えるデバイスの普及が挙げられます。
これまで、仕事をする場合はオフィスにあるパソコンを操作するしかなく、上司・管理部門の監視下で働くのが一般的でした。しかしスマートフォンやタブレットなど移動型のデバイスが普及し、いつでもどこでも仕事ができるようになりました。そのため、プライベート用のスマートフォンを業務で使う、などの抜け道が発生しています。
同じく、クラウド上にデータを保存するようになったことで社外からのアクセスが容易になったり、テレワークの普及により管理の難易度が上がったりしたことも関係しています。
シャドーITとBYODとの違い
BYODとは、プライベート用のデバイスを業務に使うことを指します。
一見するとシャドーITと似ていますが、BYODはあくまでも「プライベート用のデバイスを使用することを管理部門が知っている」状態であることに注目しておきましょう。
一方でシャドーITは「プライベート用のデバイスが使用されていることを管理部門が知らない」状態であり、リスクを検知することすらできません。BYODが戦略的におこなわれるのに対し、シャドーITは想定外の出来事である、と言えます。
シャドーITを従業員が使う理由

シャドーITを禁止している企業であっても、なぜシャドーITが発生するのか理由を探っていきましょう。自社で下記に該当する要素があれば、知らず知らずのうちにリスクが生じている可能性も高いです。
1. 作業効率を高めるため
「プライベート用のスマートフォンを使った方が作業効率が高い」と感じられる場合、シャドーITが生じやすくなります。例えば、会社に指定されているツールが使いづらい・丁寧なオンボーディングがおこなわれておらず形骸化している、などが理由として挙げられます。
また、情報システム部門の監査が厳しく承認を受けられない場合や、意図の伝わらない社内ルールが蔓延していたりするときも、抜け穴を見つけるためシャドーITが蔓延する可能性が高いです。
2. セキュリティ意識が低いため
セキュリティ意識が低く、「この程度であれば大丈夫だろう」という安易な考えに基づいてシャドーITが起きているケースもあります。また、そもそも会社がシャドーITを明確に禁止していなかったり、「当然シャドーITはしないだろう」という思い込みで教育をしていなかったりする場合も当てはまります。
現場の末端に至るまでセキュリティ対策が講じられているか、シャドーITを禁止する意義・目的に至るまで広く共有できているか、今一度社内を見直してみましょう。
シャドーITが引き起こす4つのリスク

ここでは、シャドーITが引き起こす4つのリスクを解説します。そもそもなぜシャドーITを禁止する企業が多いのか、理由・背景を探っていきましょう。
マルウェアに感染する
コンピューターウイルスやスパイウェアなどのマルウェアに感染した場合、情報の漏洩・書き換え・ロックなど不利益が生じます。他にも、監視用マルウェアを入れられて知らないうちに動向を探られるケースもあるので注意しましょう。
特に、セキュリティレベルの低い公共Wi-Fiで業務用ツールにアクセスする場合、マルウェアに感染するリスクが上がります。最終的に大規模なサイバー攻撃を受けて営業できなくなるなど、思わぬトラブルに発展することもあるので注意しましょう。
情報が漏洩する
マルウェアに感染して情報を抜き取られたり、情報を書き換えられて意図せぬことが起きたりすることもあります。また、機密情報を別の担当者に送信してしまったり、パソコンを電車内に置き忘れたり、ヒューマンエラーによる漏洩が起こる可能性もあるので注意しましょう。
シャドーITの場合、情報漏洩が起きても本人が気付かない限り早期発見が難しいのも難点です。反対に、会社のデバイスやツールを使っていれば管理部門や上司が気づき、早いうちに手を打てる可能性もあります。
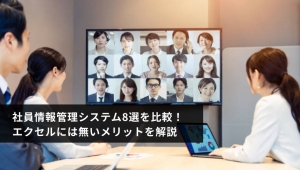
アカウントを乗っ取られる
アカウントの乗っ取り・なりすましが起き、正常に業務が遂行できなくなる可能性があります。
知らないうちにPWを書き換えられてしまった場合、本人ですらログインできないままアカウントだけが暴走する可能性もあるでしょう。取引先に迷惑メールやスパムを発信したり、情報を消失させたりすれば、多大な損失につながります。
場合によっては損害賠償が生じることもあるので、「アカウントを作り直せばいい」と安易に考えないことが重要です。
データを損失する
データを損失・紛失・消滅させることにより、営業に多大なダメージが加わる可能性があります。
例えば、顧客情報を勝手に書き換えられて社名・担当者名・連絡先などがごちゃごちゃになってしまった場合、正しい情報を把握しなおすまで相当な時間がかかります。過去のデータを消されれば自社のナレッジが奪われたにも等しく、今後の戦略づくりにも影響します。
また、完全にデータを紛失した場合、復旧は非常に困難です。いかにシャドーITが多大なリスクを持つか知り、対策していきましょう。
シャドーITの5つの防止対策

最後に、シャドーITを防止する対策法を解説します。自社で足りていない取組みがあれば強化しておきましょう。
1. 社内の現状を把握する
まずは、社内の現状を把握することが大切です。シャドーITを禁止するだけでは、問題の解決はできません。なぜシャドーITを使いたくなるのか、今あるツールやデバイスでは何が不便なのか、詳細に至るまでヒアリングしていきましょう。
また、現時点でシャドーITを使っている従業員を必要以上に叱責せず、むしろ改革に協力してもらうことが大切です。社内からの反発を招かないためにも、ルールづくりから始めましょう。
2. ガイドラインを策定する
デバイスやツール使用を適正化するため、ガイドラインを策定します。経営者や情報システム部門はもちろん、デバイスを管理する総務・庶務やコスト計算を担当する経理、現場でデバイスを使う人なども含めて検討するのが大切です。
特に現場の声は積極的に取り入れ、策定後のガイドラインが形骸化しないよう配慮しておきましょう。使いやすさやわかりやすさを重視したうえで、策定後は広く社内に共有することもポイントです。
3. 従業員を教育する
シャドーITの危険性を広く周知し、セキュリティリスクに関する社内教育をおこないます。新入社員など新たに加わった人はもちろん、既存社員にも定期的に教育するなど対策するのが理想です。
また、管理する側であるマネージャーや部署長についても、マネジメント研修のなかにシャドーIT対策を組み込むなどして教育していきましょう。万が一シャドーITが発覚した場合のフローも含めて検討し、現場で動きやすくすることが大切です。
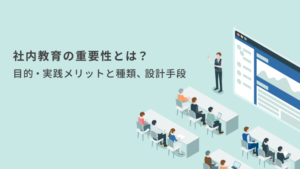
4. 代案となるIT環境を提供する
会社が提供するデバイスやツールが不便でシャドーITが発生しているのであれば、代案となるIT環境を提供します。
例えば、デバイスを入れ替える・DXに役立つ新たなツールを導入する・セキュリティレベルの高いソフトウェアを使う、などの方法が挙げられます。シャドーITを使わなくて良い環境が作れれば、そもそもシャドーITを使おうとする人を減らせるでしょう。
事前にヒアリングした内容に合わせて変革できれば、さらに効果が高まります。
5. 管理のためのツールを導入する
管理用のツールを導入し、利用状況を可視化する方法もあります。もしくは社員だけが使えるクラウドやワークスペースを導入し、誰がいつ何を目的にアクセスしたのか分析してもよいでしょう。
特に、クラウドサービスの利用適正化を図る「CASB(=Cloud Access Security Broker)」などのツールを導入する企業が多いです。機密情報を含んだファイルがアップロードされようとした場合に自動でブロックしたり、管理部門の招待を受けた人しかアクセスできないよう設定したりする機能が搭載されているので、セキュリティレベルを高められます。
シャドーIT対策の情報共有に ourly
ourlyは、組織の意識改善を支援するweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能があり、施策の効果測定が可能になります。
またourlyは、単なるツールにとどまらず、専門の組織コンサルタントが運用をサポートし、ゴール設定、現状把握、行動計画、改善提案など一気通貫で支援を行います。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「社内広報施策の効果測定ができない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
社内の実情を把握してシャドーITの防止対策を
シャドーITは「見えないリスク」になることが多く、通常時であれば一見何も問題ないように感じられますが、いざトラブルが発生したときのダメージが大きいことが特徴です。適切なシャドーIT対策をすることが会社を守る要因になるので、課題がある企業は早期に対処していきましょう。
また、シャドーITに関するリスクの周知やセキュリティ意識の向上を目的に、定期的に社内報にコンテンツを掲載するのもおすすめです。日々の忙しい業務に追われて忘れがちになってしまいそうなことこそ、繰り返し発信していくことが大切です。