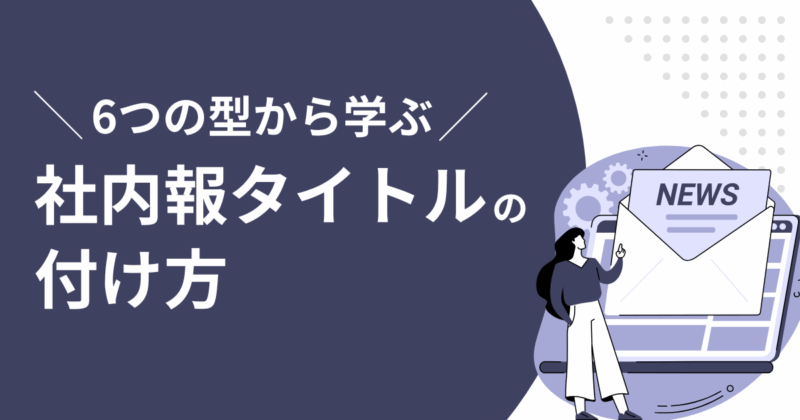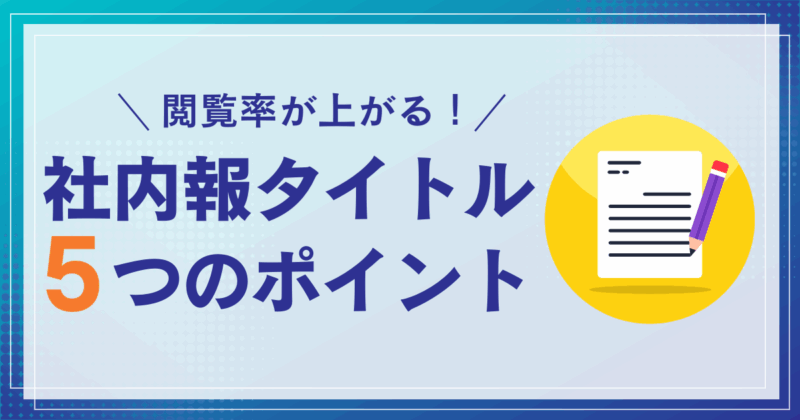社内報を発行する際、タイトルで企業の個性を表現したいと考える方もいるのではないでしょうか。
例えば、本を購入する際、最初に注意を引くのはそのタイトルです。同様に、社内報のタイトルも社員の興味を引く重要な要素です。
それでは、どのようなタイトルを付けると社員にとって認知されやすく、愛着が湧きやすくなるのでしょうか。本記事では、社内報タイトルの付け方に関する実践的なコツや、成功したパターン、他社の事例、さらに避けるべきタイトルについて解説していきます。
閲覧率が上がる記事ごとのタイトルの付け方について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
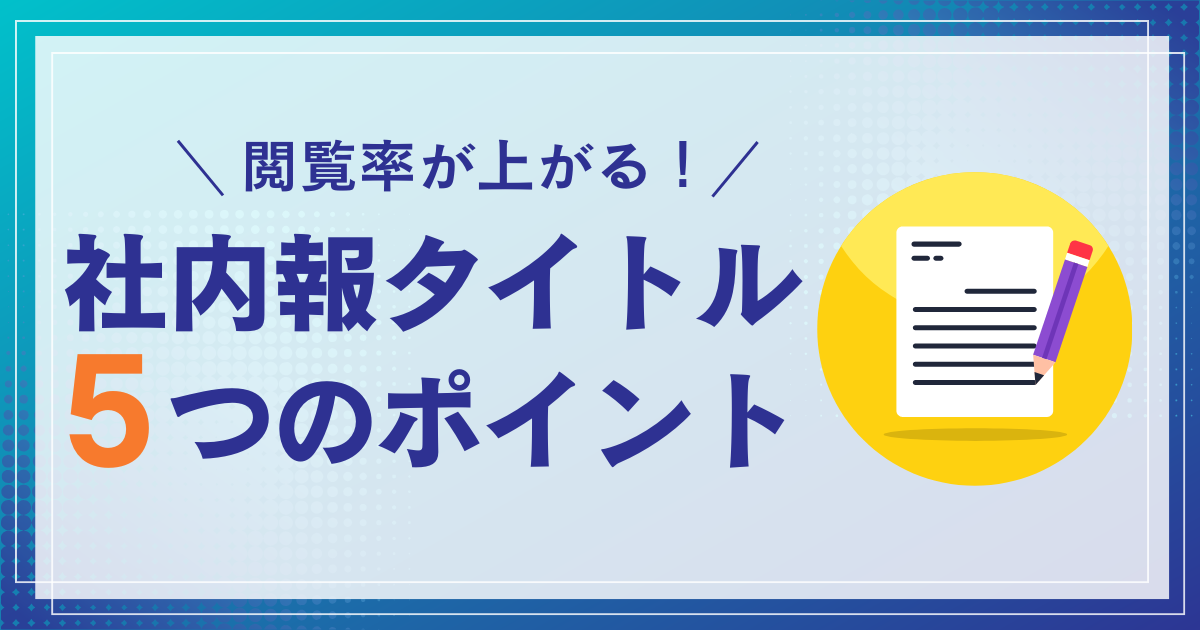
社内報タイトルの6つのパターン【事例付き】
まずは、社内報タイトルの典型例を紹介していきます。
代表例としては、「社名+マガジン」「社名+ペーパー」など、社名に社内報とわかるようなワードを加える社内報タイトルが挙げられます。例えば「トヨタイムズ」や「KAGOME通信」がこのパターンです。他にも「絆」などのコンセプトや企業理念を用いる事例もあります。
6つのパターンに分けて詳しく紹介していきます。
1.社名を用いる
1つ目のパターンとして、社名を用い、その後に社内報とわかるようなワードを加えるような場合があります。シンプルで最も典型的といえるでしょう。以下がその例です。
・◯◯マガジン(Magazine)
・◯◯ペーパー(Paper)
・◯◯ナンバー(Number)
・◯◯イシュー(Issue)
・◯◯タイムズ(Times)
・◯◯ニュース(News)
・◯◯レター(Letter)
・◯◯だより
・ウィークリー(Weekly)◯◯
・マンスリー(Monthly)◯◯
また、具体的にイメージしやすいように、有名企業のタイトル例をご紹介します。
トヨタ自動車株式会社:トヨタイムズ

トヨタ自動車株式会社は、「トヨタイムズ」というタイトルの社内報を発行しています。CMでも流れていることから、多くの人に馴染みがあるかもしれません。
トヨタの社内報タイトルは、社名である「トヨタ」と、社内報とわかるようなワードである「タイムズ」をつなげたものです。
社名の前後に、社内報と関連付いたワードを添えています。そのため、社員やその家族に対して、社内報を浸透させやすいタイトルといえます。
カゴメ株式会社:KAGOME通信
カゴメ株式会社は、「KAGOME通信」という社内報を発行しています。社名を利用しており、社内報とわかるようなワードと社名の組み合わせと言えます。
2.社内報の目的やコンセプト・想いを用いる
2つ目のパターンとして、社内報のコンセプト・想いを用いる場合があります。社名を用いるパターンよりも簡潔で、さらにインパクトがあります。社内報を運用する目的に沿って決めてもよいでしょう。
以下が、社内報のコンセプト・想いを用いた例です。
・絆
・愛
・心
・diverse
・One
・Many
また、具体的にイメージしやすいように、有名企業のタイトル例をご紹介します。
大阪ガス株式会社(Daigasグループ):Webがす燈
大阪ガス株式会社は、「Webがす燈」というタイトルのweb社内報を発信しています。大阪ガスの業種であり社名にも含まれる「ガス」と、灯の旧字体である「燈」をつなげたタイトルになっています。
社名と、社内報のコンセプト・想いを組み合わせたものと言えるでしょう。
サントリーホールディングス株式会社:まど
サントリーホールディングス株式会社は、「まど」というタイトルの社内報を発行しています。
この「まど」という社内報は1955年から受け継がれています。またそのタイトルは、社内報のコンセプト・想いを利用しているといえます。
タイトルに社名を使う場合などとは違い、タイトルを見ただけでは、それが社内報とはわかりません。そのため、誌名の浸透に力を入れることが不可欠です。
3.企業理念を用いる
3つ目のパターンとして、企業理念や企業のミッションなどを用いる場合があります。以下が企業理念を用いた場合の例です。
・diversity
・hospitality
企業理念などを利用することにより、社内報自体のみならず、それらの理念浸透にも役立ちます。
住商ビルマネージメント株式会社:ラブメ!
住商ビルマネージメント株式会社は、「ラブメ!」というタイトルのweb社内報を発信しています。
社長の座右の銘である「愛とお作法」を英訳した「Love & Method(ラブアンドメソッド)」からタイトルを作っています。またロゴを作成して、社員によって愛着が湧くような工夫もしています。
4.会社の業種に合う言葉を用いる
4つ目のパターンとして、各企業の業種に合う言葉を用いる場合があります。以下がその例です。
・セキュリティー会社:守る、SAFETY
・飲食業:飯、EAT
・IT企業:CLOUD、TECHNOLOGY
読者が、自身の企業に関係があるとすぐわかるようなワードが良いでしょう。
5.親しみやすい言葉を用いる
5つ目のパターンとして、親しみやすい言葉を利用する場合があります。以下がその例です。
・BEYOND
・UP
・THANKS
・BEST
・GOOD
・SMILE
・ENJOY
・HAPPY
・HAPPINESS
社内報は、その企業のイベントや成果、さらには砕けた話などを企業全体に共有できるツールです。そのため、多くの人々に読んでもらってこそ意味があります。
親しみやすく愛着がわくタイトルにすることにより、硬い内容ではなく、読みやすいイメージを持たせることができ、多くの人に気軽に読んでもらえるようになるでしょう。
6.ビジネス関連の言葉を用いる
6つ目のパターンとして、ビジネス関連の言葉を用いる場合があります。以下がビジネス関連の言葉を用いた例です。
・SUCCESS
・AGENDA
・ECONOMY
・GROWTH
・MANAGE
・STRATEGY
・COOPERATION
また、具体的にイメージしやすいように、有名企業のタイトル例をご紹介します。
双日株式会社:HORIZON
双日株式会社のグループシンボルである「グローバルアローズ」のモチーフから取られた名前です。
社員が業務でよく使うワードなど、各企業にとって馴染みのあるビジネス系ワードがあれば、それを使用することも効果的です。
読まれる!社内報タイトルの付け方のコツ
社内報を運用するにあたり、タイトルに悩む人は多いのではないでしょうか。社内報は、社員やその家族に読まれてこそ、発行する意味があるといえるでしょう。
そのため、読者が手に取って見たくなるようなタイトルにすることが重要です。では、どのようなタイトルをつけると効果的なのでしょうか。
社員の視点からネーミングする
タイトルをつける上で、読者の立場になって考えることが重要です。
その企業には、どのような人材が多いのか、また社員は企業に対してどのような感情を抱いているのかなど、社員の特徴をつかむことが大事です。
社員の気持ちや個性を理解し、興味を引くタイトルや、誇りに思われるタイトルが有効でしょう。
会社ならではのユニークさを
読者が、タイトルを一目見て自身の会社に関するものだとわかるようなタイトルが有効でしょう。
その会社の名を利用したものや、経営理念など、企業が大事にする言葉を使用すれば、読者は自社の社内報だと理解しやすいです。
さらには、馴染みの深い言葉は、読者にとって記憶しやすく、社内報の浸透に役立つでしょう。
長すぎず、キャッチーに
読者がタイトルを覚えやすくするためにも、長すぎずスマートなタイトルが好ましいです。
その会社ならではの個性を、タイトルによって表現することも重要です。しかし、長ければ長いほど読者はそのタイトルを覚えにくいので浸透しづらく、社内報の効果を最大限発揮できないでしょう。
長いタイトルになってしまっても、略して呼べるようなタイトルであれば問題ありません。キャッチーなタイトルをつけるようにしましょう。
避けるべき社内報のタイトル
社内報タイトルのつけ方のコツや、いくつかパターンを紹介しました。では、逆に避けるべき社内報のタイトルとは、どのようなものでしょうか。
長く、冗長であるもの
まず、長く、冗長であるものは避けるべきです。社内報タイトルのつけ方でも述べたように、タイトルはスマートなものが良いでしょう。
社内報作成の想いを、簡潔なワードで伝えることを目指しましょう。
会社のイメージや経営方針と異なるもの
会社のイメージや経営方針と異なるタイトルは避けるべきです。タイトルを見て、その会社の社内報だとすぐわかるようなものが良いでしょう。
おすすめは企業理念やMVVに用いられているワードを使うことです。会社のイメージや方針に確実に合うだけでなく、社内外への理念浸透・ブランディングに役立ちます。
タイトルを見ただけでは社内報と分からないもの
先ほど「社内報の目的やコンセプト・想い」の章でも解説した通り、社名や事業内容との関連性が低いネーミングは浸透に時間がかかるでしょう。
決定に際しては、果たして自社らしさが表現できているネーミングなのか、もう一度検討することをおすすめします。社内報の運用に不安がある場合は、できるだけ避けた方がよいでしょう。
十分に検討した上でこのパターンのタイトルに決めた場合は、社内報の浸透施策を多めに打つ、ロゴのデザインをこだわって制作する、web社内報ツールなどを利用して読まれやすい社内報を発行するなど工夫することがおすすめです。
社内報タイトルをロゴにする
社内報のタイトルをロゴにすることで、社員が親しみや愛着を感じやすくなり、社内報が浸透します。
今回はロゴを制作する流れを「自分で制作するパターン」で解説します。社内にデザイナーがいる場合は、社内報のコンセプトや伝えたいメッセージを言語化して、作成を依頼しましょう。
自分で施策する流れ
ステップ1:コンセプト設計と参考イメージ収集
まずはロゴのイメージを決めます。社内報の雰囲気やターゲットに合わせて、参考になるロゴデザインをインターネット上で収集しておくと作業が簡単です。
ステップ2:デザインツールの選定
初心者でも簡単にロゴが作れるデザインツールを利用しましょう。代表的なツールには以下のようなものがあります。
・Canva(キャンバ)
・Adobe Express(アドビ・エクスプレス)
・Logo Maker(ロゴメーカー)系サービス
ステップ3:ラフデザインの作成
選定したデザインツールで、まずはラフデザインを作ります。タイトル名を入力し、フォントの種類やサイズ、カラー、レイアウトなどを調整していきます。数パターン作って見比べると、よりよいロゴが作りやすくなります。
ステップ4:社内で確認をしてもらう
作成したロゴ案を同僚や関係者に見てもらい、フィードバックをもらいましょう。第三者視点で客観的な意見を聞くことで、ロゴの印象や視認性などを改善することができます。
ステップ5:修正とデータ保存
社員の意見を反映させて最終調整を行います。完成したロゴは、高解像度で書き出しておきます。PNGやJPEG形式のほか、可能ならPDFやSVG形式でも保存しておくと、さまざまな用途に応用しやすくなります。
社内報には読みたくなるタイトルを付けよう
社内報を発行しても、なかなか読まれないという課題がある企業も少なくはありません。発行するからには、社員やその家族などに毎回読まれるような社内報を作成したいものです。
その会社にしか付けられないようなタイトルを考え、後世に受け継がれていくような社内報を目指しましょう。