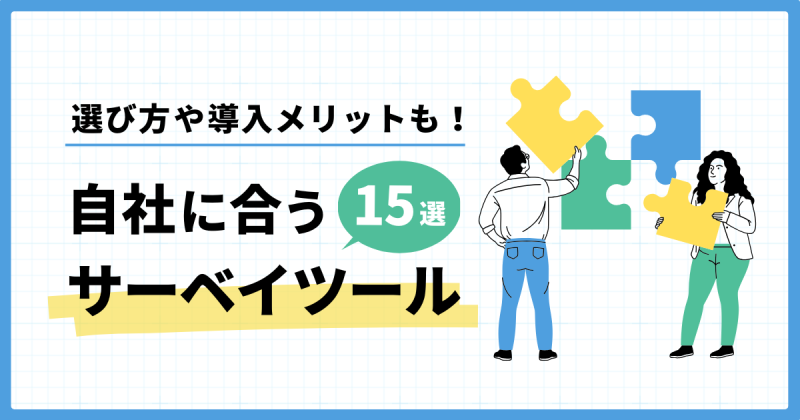近年、働き方の多様化や人材の流動化が進む中で、従業員のエンゲージメントを高め、組織の課題を可視化することの重要性が増しています。その解決策として注目されているのが「サーベイツール」です。しかし、多くのツールが存在するため、「自社にどれが合うのかわからない」「導入して本当に効果があるのか不安」と感じる人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、サーベイツールの基本的な役割から、導入のメリット、自社の目的や課題に合わせた選び方までを網羅的に解説します。さらに、最新のおすすめツール14選を目的別に比較紹介し、ツール導入を成功に導くためのポイントを明らかにします。この記事を読めば、自社の組織力を最大化するための最適な一手が見つかるはずです。
サーベイツールとは?
サーベイツールとは、従業員や組織の状態を定量的に測定し、見えにくい課題を可視化するためのシステムです。アンケート形式で従業員の意見やコンディションを収集し、その結果を自動で集計・分析することで、人事戦略や組織改善に役立つ客観的なデータを提供します。
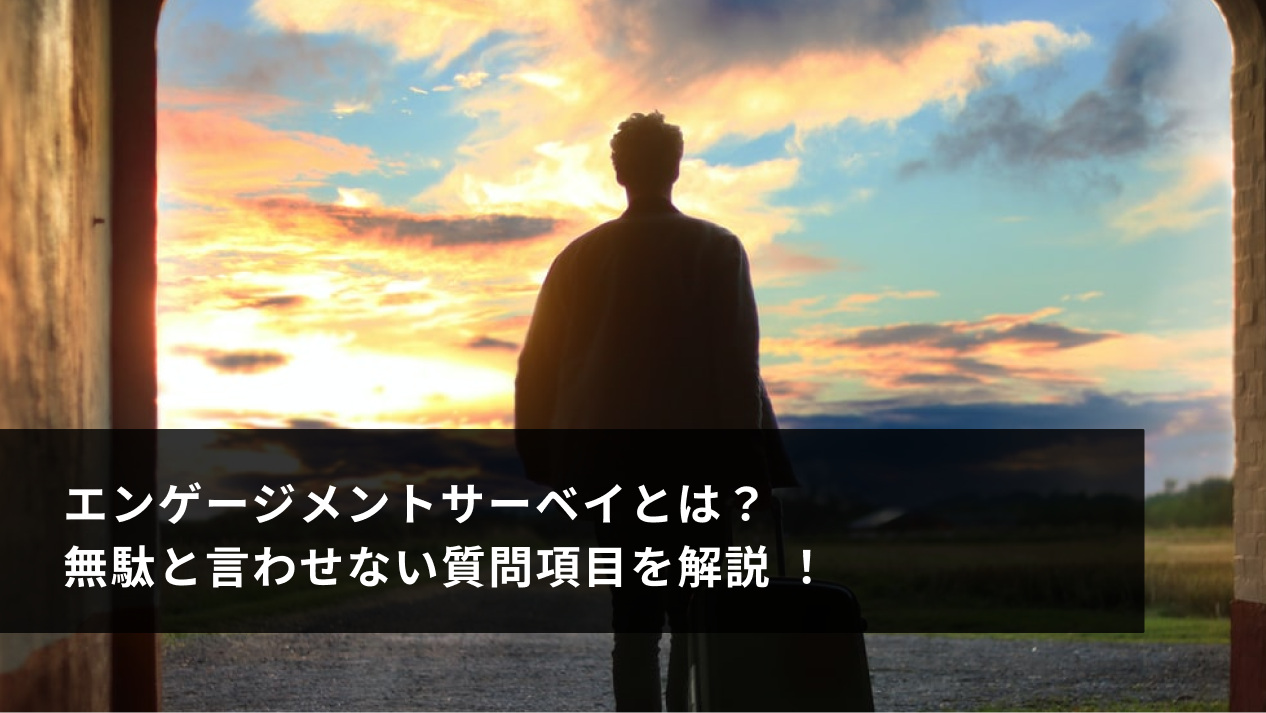
人事・組織の課題を発見・可視化するツール
多くの企業では「なんとなく社内の風通しが悪い」「若手社員の離職が続いている」といった漠然とした課題感を抱えています。
サーベイツールは、こうした感覚的な問題を具体的な数値やデータとして明らかにすることが可能です。 例えば、従業員エンゲージメント、仕事への満足度、人間関係、健康状態などをスコア化することで、どの部署で、どの階層の従業員が、何に問題を抱えているのかを正確に特定できます。これにより、これまで気づかなかった潜在的なリスクや課題を発見し、手遅れになる前に対策を講じることが可能になります。
課題解決に向けた具体的なアクションプランを明確にする
サーベイツールは、単に課題を発見するだけではありません。分析結果をもとに、課題解決のために何をすべきか、その方向性を示してくれます。
たとえば、「上司のサポート不足がエンゲージメント低下の要因」という分析結果が出た場合、「管理職向けの1on1研修を実施する」「フィードバックの機会を増やす」といった具体的なアクションプランの立案につながります。ツールによっては、他社の成功事例を提示したり、AIが改善策を提案したりする機能も備わっており、データに基づいた効果的な施策実行を強力にサポートしてくれるのです。
サーベイツール導入の主な目的
企業がサーベイツールを導入する背景には、多様な目的が存在します。組織の状態を正確に知ることから、優秀な人材の定着、さらには社会的な要請への対応まで、その活用範囲は多岐にわたります。
組織の状況や課題を正確に把握する
サーベイツール導入の最も基本的な目的は、組織や従業員のリアルな状況を客観的なデータで把握することです。 従業員のエンゲージメントや満足度を定期的に測定・分析することで、普段のコミュニケーションだけでは見えにくい業務負荷の状況や、人間関係のストレスといった心理状態を可視化できます。
これにより、経営層や管理職は、現場の実態に基づいた改善施策の立案や意思決定を行えるようになります。
| 調査領域 | 可視化できることの例 |
| エンゲージメント | 仕事への熱意、貢献意欲、会社への愛着 |
| 満足度 | 業務内容、労働環境、福利厚生への満足度 |
| 人間関係 | 上司や同僚との関係性、コミュニケーションの質 |
| 健康状態 | 心身のストレスレベル、ワークライフバランス |
従業員の休職や離職を未然に防ぐ
上昇傾向にある離職率は、従業員のコンディションが悪化しているサインかもしれません。 サーベイツール、特に「パルスサーベイ」と呼ばれる高頻度の調査を活用することで、個々の従業員のコンディション変化をタイムリーに察知できます。
スコアが急に低下した従業員を早期に発見し、上司による面談や人事部門によるサポートをおこなうことで、深刻なメンタルヘルスの不調や突然の離職といった事態を未然に防ぐことが期待できます。

データに基づいた効果的な人事施策を立案する
サーベイによって収集されたデータは、効果的な人事施策を立案するための貴重な資源となります。 例えば、「若手社員の成長実感の低さ」が課題として浮かび上がった場合、「メンター制度の導入」や「キャリア研修の充実」といった施策が考えられます。
サーベイ結果という客観的な根拠があるため、施策の必要性を経営層に説明しやすく、予算獲得にもつながりやすいことが利点です。
人的資本経営に関する情報開示に対応する
2023年3月期決算から、大手上場企業を対象に「人的資本の情報開示」が義務化されました。開示が求められる項目の中には「従業員エンゲージメント」も含まれており、サーベイツールはこれらの数値を客観的に測定し、外部へ報告するための重要なツールとなります。
今後、この動きは中堅・中小企業にも広がると予想されており、投資家や社会からの信頼を得るためにも、サーベイの活用は不可欠になっていくでしょう。
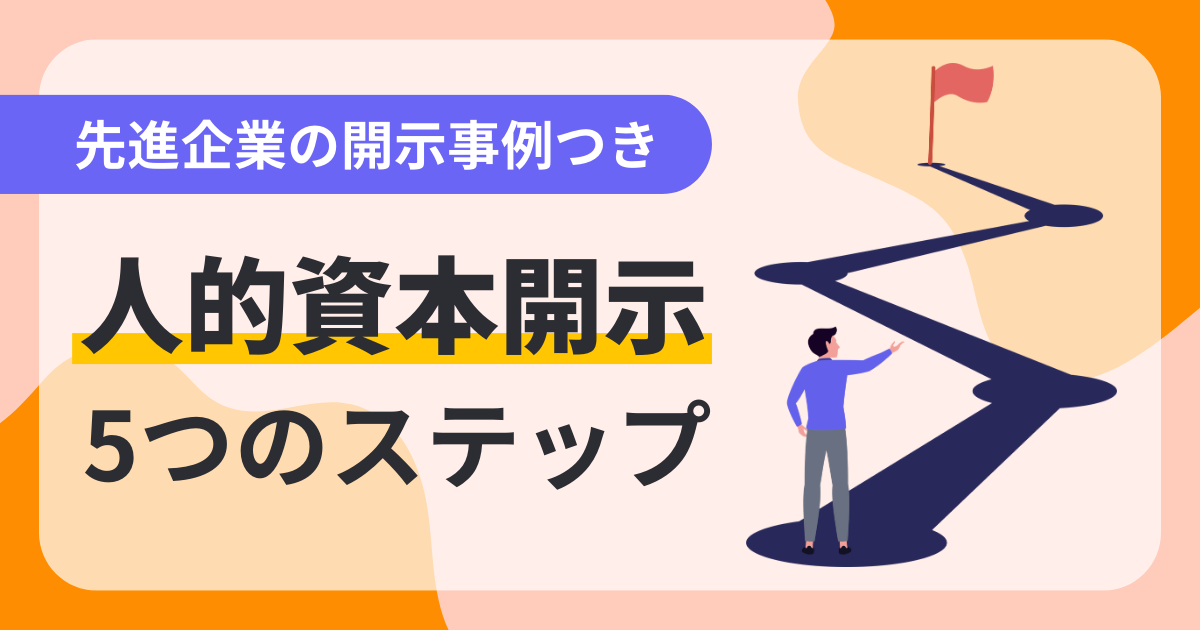
サーベイツール導入の3つのメリット
サーベイツールを戦略的に活用することで、企業は多くのメリットを享受できます。従業員の働く意欲を高め、人材が定着し、結果として組織全体のパフォーマンスが向上するという好循環を生み出すことが可能です。
従業員のモチベーションが向上する
サーベイを通じて、企業が従業員の声に耳を傾け、職場環境の改善や制度の見直しに取り組む姿勢を示すことは、従業員の会社に対する信頼感を高めます。自分の意見が組織運営に反映されるという実感は、「自分は大切にされている」という認識につながり、仕事へのモチベーションを大きく向上させるでしょう。
モチベーションの高い従業員は、自発的に業務改善に取り組んだり、新しいアイデアを提案したりと、組織に活気をもたらします。
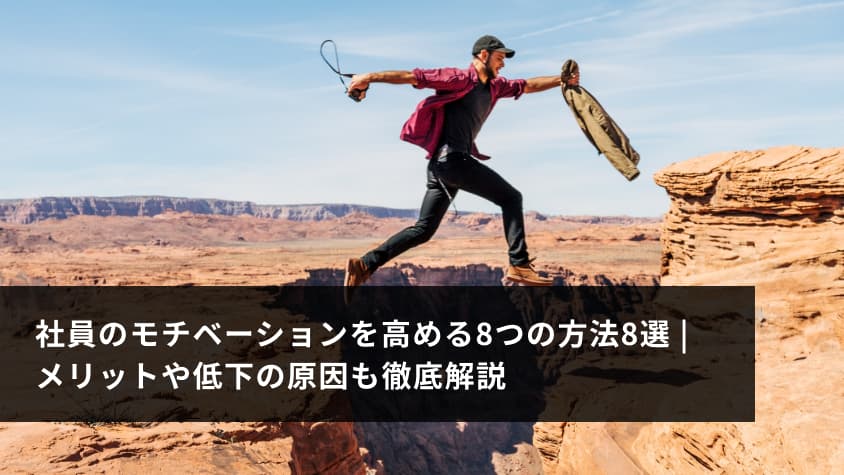
人材の定着率が高まる
従業員のコンディション変化を早期に察知し、離職の兆候が見られた際に迅速なフォローアップを行うことで、優秀な人材の流出を防ぎます。 また、サーベイ結果に基づき、働きがいのある職場環境を整備していくことは、従業員の「この会社で働き続けたい」という愛社精神(エンゲージメント)を育みます。
エンゲージメントスコアと離職率には相関関係があることが知られており、エンゲージメントの向上は、結果的に人材の定着率向上に直結するのです。
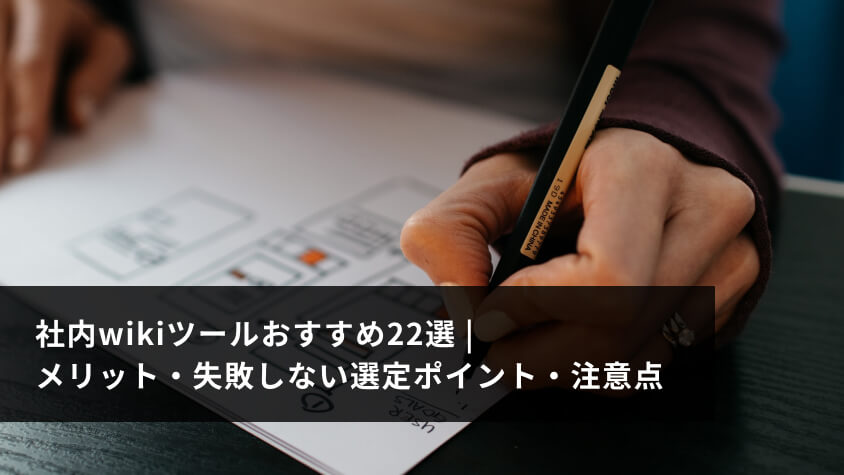
組織全体の生産性が向上する
従業員一人ひとりのモチベーションとエンゲージメントが高まることで、組織全体の生産性も向上します。 ニッセイ基礎研究所の調査によれば、ワークエンゲージメントのスコアが高い従業員ほど、生産性も高い傾向にあることが示されています。
サーベイを通じて業務プロセスの非効率な点や、コミュニケーションのボトルネックといった課題を特定し改善することで、よりスムーズで生産性の高い組織運営が実現できるのです。
| メリット | 期待される具体的な効果 |
| モチベーション向上 | 自発的な業務改善、イノベーションの促進 |
| 定着率向上 | 採用・育成コストの削減、ノウハウの蓄積 |
| 生産性向上 | 業績向上、企業の競争力強化 |
【参考】https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=73022?site=nli

サーベイツールの主な種類と特徴
サーベイツールは、その目的や機能によっていくつかのタイプに分類されます。自社の課題や目指すゴールに応じて、最適なタイプを選択することが重要です。ここでは、代表的な3つの種類とその特徴を解説します。
離職防止特化型:個人のコンディション変化をリアルタイムで把握
離職防止に特化したツールは、従業員一人ひとりの心理状態の変化やストレスレベルを測定し、離職リスクを早期に察知することを得意とします。 週に1回や月に1回といった短い間隔で簡単な質問に回答してもらう「パルスサーベイ」が主な手法です。
コンディションの低下が見られた従業員にはアラートが通知され、管理者が迅速に面談などのケアを行うことができます。人材の流出が経営課題となっている企業や、従業員のメンタルヘルスケアを重視する企業に適しています。
組織診断特化型:組織全体の課題や文化を多角的に分析
組織診断を主目的とするツールは、組織全体のエンゲージメントレベル、価値観、強み・弱みなどを多角的に分析し、課題を可視化します。
半年や1年に1回、数十問からなる詳細なアンケート(センサスサーベイ)を実施するのが一般的です。
部署間や役職間の比較分析、経年変化の追跡などが可能で、組織開発や風土改革の基盤となる詳細なデータを得たい企業に向いています。
人材データベース連携型:人事情報と掛け合わせ、包括的な分析を実現
タレントマネジメントシステムの一部としてサーベイ機能を提供するタイプです。従業員の基本情報、評価、スキル、経歴といった既存の人事データとサーベイ結果を掛け合わせて分析できるのが最大の特徴です。 例えば、「高評価者と低評価者のエンゲージメントスコアの違い」や「特定の研修を受けた後の従業員の意識変化」などを分析できます。人事データを一元管理し、より戦略的な人材活用を目指す企業におすすめです。
自社に合ったサーベイツールの選び方と比較ポイント
まず、自社の目的に合った調査方法に対応しているかを確認しましょう。
- パルスサーベイ:短い間隔(週次・月次)で少ない質問(5〜15問程度)を実施し、個人のコンディション変化をリアルタイムに把握するのに適しています。離職防止やタイムリーなケアを重視する場合におすすめです。
- 組織診断サーベイ(センサスサーベイ):長い間隔(半期・年次)で多い質問(50〜100問以上)を実施し、組織全体の課題を網羅的・構造的に把握するのに向いています。組織改革や人事制度の見直しなど、根本的な課題解決を目指す場合に有効です。
ツールによっては両方に対応しているものもあるため、どのようなサイクルでPDCAを回したいかを検討しましょう。
課題解決につながる分析・サポート機能があるか
データを収集するだけで終わらせないためには、分析機能や改善を支援する機能が重要です。
部署別、役職別、年齢別などの属性で結果を絞り込める「クロス分析機能」や、業界平均と比較できる「ベンチマーク機能」があると、自社の立ち位置を客観的に把握できます。
また、分析結果から課題を特定し、具体的な改善アクションを提案してくれる「アクションプラン提案機能」や、専門家によるコンサルティングサポートが受けられるかどうかも、比較の重要なポイントです。
従業員と管理者の両方が直感的に操作できるか
ツールの導入効果は、従業員の回答率の高さに大きく左右されます。そのため、PCはもちろんスマートフォンからも簡単に、直感的に回答できる操作感は必須条件です。
同様に、管理者側のダッシュボードも見やすく、分析レポートがひと目で理解できるデザインであるかを確認しましょう。
多くのツールでは無料トライアルが提供されているので、実際に操作感を試してみることをお勧めします。
【目的別】おすすめのサーベイツール15選を徹底比較
ここでは、数あるサーベイツールの中から、目的別におすすめの14製品を厳選して紹介します。「離職防止」「組織診断」「人材データベース連携」の3つのカテゴリに分けて比較することで、自社のニーズに合ったツールを見つけやすくなります。
【離職防止に特化】おすすめサーベイツール5選
個々の従業員のコンディションをきめ細かく把握し、離職や休職のサインを早期にキャッチすることに長けたツールです。
| ツール名 | 特徴 | 費用(税込) |
| ourly(ourly survey) | 社内コミュニケーション活性化やエンゲージメント向上を支援するweb社内報ourlyが提供するサービス。社内報の閲覧状況と掛け合わせることで、離職可能性の分析や、エンゲージメントをより精緻に把握できる。 | 要問い合わせ |
| ミキワメ ウェルビーイングサーベイ | 臨床心理士が開発。性格分析に基づき個々に合わせたケア方法を提案。アラート機能で休職・離職リスクを早期に特定。 | 要問い合わせ |
| Geppo | リクルートとサイバーエージェントのノウハウを結集。毎月3問の簡単な質問で負担なく個人の課題を可視化。 | 22,000円〜/月 (25名まで) |
| LLax forest | SOMPOグループ提供。メンタル、フィジカル、エンゲージメントの3要素を総合的に測定。健康経営を目指す企業に最適。 | 2,640円/人/年 |
| MotifyHR | 離職可能性の高い社員を早期に発見し、自動メッセージなどで再オンボーディングを促す機能が充実。社内SNS機能も搭載。 | 要問い合わせ |
【組織診断で課題を可視化】おすすめサーベイツール6選
組織全体の強みや弱み、カルチャーをデータに基づいて明らかにし、組織開発の土台を築くためのツールです。
| ツール名 | 特徴 | 費用(税込) |
| ourly(ourly survey) | 社内コミュニケーション活性化やエンゲージメント向上を支援するourlyが提供するサービス。理想の組織状態から逆算した設問や回答方法を自由に設定できる。専門コンサルタントによる伴走支援つき。 | 要問い合わせ |
| Wevox | 3分で回答できる手軽なサーベイ。豊富な蓄積データとの比較分析が可能。AIによるチーム改善サポートも提供。 | 330円〜/人/月 |
| モチベーションクラウド | リンクアンドモチベーションが提供。国内最大級のデータベースとの比較で、組織課題の優先順位を明確化。 | 要問い合わせ |
| ラフールサーベイ | メンタルヘルスやハラスメントリスクも測定。専任のカスタマーサクセスが組織改善を伴走支援。 | 17,600円〜/月 |
| ミイダス組織サーベイ | 約5分のアンケートで「やりがい」「人間関係」など6つのカテゴリを分析。パフォーマンス阻害要因を特定。 | 要問い合わせ |
| ハタラクカルテ | 日本大学との共同研究に基づく設問設計。スマホのみ、アドレス不要で回答でき、現場の負担が少ない。 | 2,200円/人/年 |
【人材データベースと連携可能】おすすめサーベイツール5選
タレントマネジメントシステムの一部として、人事情報と連携した高度な分析を実現するツールです。
| ツール名 | 特徴 | 費用(税込) |
| カオナビ | シェアNo.1タレントマネジメントシステム。評価や経歴とサーベイ結果を掛け合わせ、ハイパフォーマー分析などが可能。 | 要問い合わせ |
| SmartHR | 労務管理からタレントマネジメントまで一元化。労務手続きで蓄積されたデータを活用し、人事評価や従業員サーベイなどの施策をすぐに実施できる。 | 要問い合わせ |
| HRBrain | 人材データベースを駆使し、独自の設問設計と分析で組織課題の優先順位を明確化。ISO30414にも対応。 | 要問い合わせ |
| タレントパレット | テキストマイニング技術でフリーコメントを分析し、従業員の「本音」を可視化。離職予兆の検知も可能。 | 要問い合わせ |
| HRMOSタレントマネジメント | ビズリーチが提供。従業員と組織の状況をリアルタイムで可視化し、データを自動グラフ化することで課題を特定し、適切な人材配置を支援する。 | 要問い合わせ |
“測って終わりにさせない” サーベイツール、ourly survey

ourly surveyは、自由な設問設計と施策立案・実行までを支援する“測って終わり”にさせないサーベイです。
細かい分析機能で組織課題を可視化
「所属/部署」「役職」「職種」「拠点」などのユーザー属性で回答結果を分析することが可能です。理念の浸透度合いや、エンゲージメントが低い層を見える化できます。
組織課題に応じた自由な設問
従業員エンゲージメントの向上や人事施策の成果測定、ビジョンの浸透度合いの計測など、自社が手に入れたい組織状態から逆算して自由に質問の作成が可能です。
行動データを組み合わせた分析
弊社が提供するweb社内報「ourly」の閲覧行動とサーベイで集計した結果をクロス分析することで、組織改善のサイクルを加速させます。
web社内報の閲覧率とエンゲージメントの数値に相関関係が見られており、実際に、web社内報の閲覧が減っている従業員は、数ヶ月後に離職が発生しやすいというデータも出ています。離職や休職の予測としてもご活用いただいていたり、離職した方のサーベイ結果やweb社内報の閲覧状況などを分析して、施策改善の軸としてご活用いただくケースもあります。
一気通貫した改善支援
弊社の組織開発コンサルタントが、サーベイで集計した結果をもとに組織課題の特定や改善施策の提案、実行を支援します。
以下の資料では、ourly surveyの具体的な特徴や機能を紹介しています。
サービスの比較や導入のご検討などに、ご活用ください。

サーベイツールを導入する際の注意点
サーベイツールは導入するだけで成果が出る魔法の杖ではありません。その効果を最大化するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。これらを怠ると、かえって従業員の不信感を招きかねません。
目的を明確にし、従業員へ事前に周知する
なぜサーベイを実施するのか、その目的を明確にし、全従業員に丁寧に説明することが不可欠です。「離職率を下げ、より働きやすい職場を作るため」「皆さんの意見を人事制度に反映させるため」といった具体的な目的を共有することで、従業員は安心して正直な意見を回答しやすくなります。目的が不明確なままでは、「また面倒なアンケートか」「何のために答えるのだろう」と形骸化してしまいます。
理想状態から逆算した設問設計をおこなう
目的を達成するのに必要なデータを得るための設問項目を用いることも重要です。
テンプレートの設問を闇雲に使うだけでは、エンゲージメントサーベイを実施すること自体が目的になりかねません
大事なのは、得たデータをどのように使って組織課題を解決するかです。理想の組織状態を実現するための設問を用いることを意識しましょう。
調査の実施だけで満足せず、改善アクションにつなげる
サーベイで明らかになった課題に対しては、必ず具体的な改善アクションプランを策定し、実行に移します。
よくあるのが、“サーベイだけ取って数字が低いことがわかったので、エンゲージメントを上げるようにしろ”という漠然とした依頼が社内で投げられるケースです。
エンゲージメントという用語自体の抽象度が高いため、戦略的に施策を実行していかなければいつまで経っても状況は改善されません。
施策を考える際は、エンゲージメント向上を妨げている原因を特定し、その原因を解消できるような施策を打ちましょう。以下の記事では、従業員のエンゲージメントを向上させるための施策と事例について詳しく解説しておりますので、併せてご覧ください。

定期的に実施して継続的な改善サイクルを回す
組織の状態や従業員の意識は常に変化します。一度のサーベイで満足するのではなく、半年に1回、あるいは年に1回など、定期的に実施することが大切です。継続的にデータを測定することで、前回からの変化を把握し、実行した改善策の効果を検証することができます。
このように、サーベイ→改善→効果測定というPDCAサイクルを回し続けることで、組織は着実に良い方向へ変わっていきます。

まとめ
本記事では、サーベイツールとは何かという基本的な定義から、その導入メリット、目的別の選び方、そして具体的なおすすめツールまでを包括的に解説しました。
サーベイツールは、従業員と組織の「健康診断」のようなものです。定期的に実施し、結果に基づいて適切な対策を講じることで、離職防止、生産性向上、そして働きがいのある組織文化の醸成といった、企業の持続的成長に不可欠な土台を築くことができます。
重要なのは、自社の課題と目的を明確にし、それに合ったツールを選ぶこと、そして調査結果を必ず具体的な改善アクションにつなげ、その進捗を従業員と共有するサイクルを確立することです。この記事が、貴社に最適なサーベイツールを見つけ、組織をより良い方向へ導くための一助となれば幸いです。