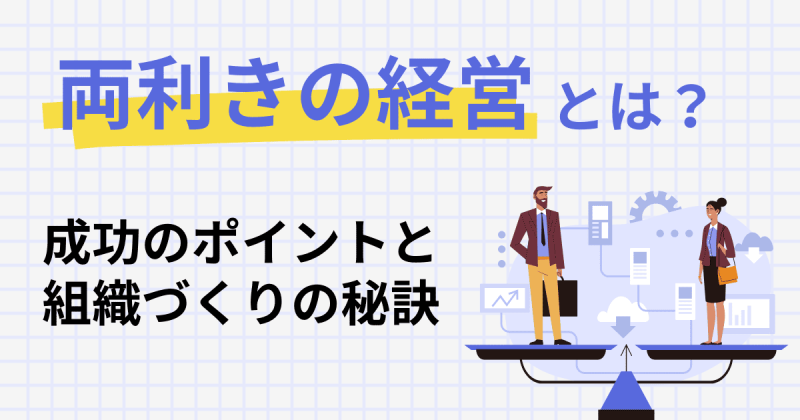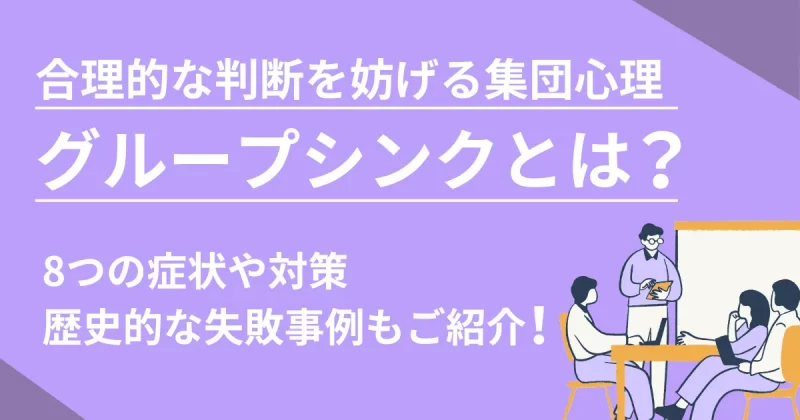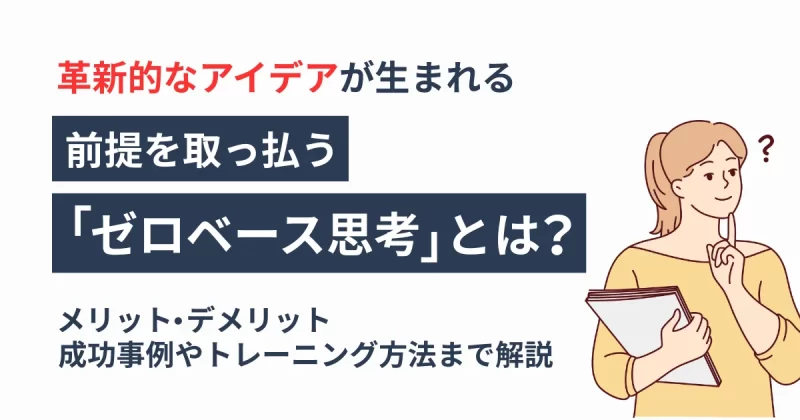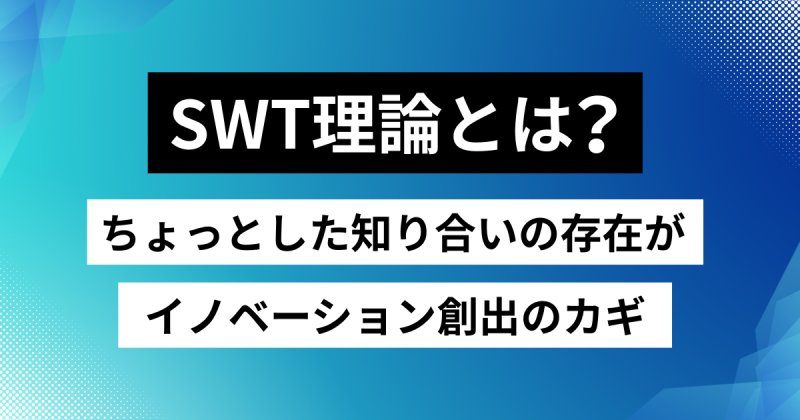企業の持続的な成長がこれまで以上に求められる現代において、「両利きの経営」という言葉が注目を集めています。これは、既存の事業を深掘りしつつ、全く新しい領域へも挑戦するという、二つの異なる活動を同時に進める経営スタイルを指します。
しかし、言葉は知っていても、なぜ重要なのか、そしてどうすれば自社で実践できるのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、両利きの経営の基本から、実践のポイント、成功企業の事例までを分かりやすく解説し、あなたの会社が未来を切り拓くためのヒントを提供します。
両利きの経営とは?基本を理解する
両利きの経営とは、企業の持続的成長のために「知の深化」と「知の探索」という、2つの異なる活動を高いレベルで両立させる経営手法です。
まるで利き手ではない方の手も器用に使える人のように、企業経営においても2つの活動を巧みに使い分けることから、この名が付きました。
この理論は、スタンフォード大学のチャールズ・A・オライリー教授らによって提唱され、変化の激しい現代市場を生き抜くための重要な経営モデルとされています。
既存事業を磨く「知の深化」
「知の深化(Exploitation)」とは、既存の事業領域において、継続的な改善や効率化を通じて収益性を高めていく活動を指します。
顧客のニーズを深く理解し、製品の品質向上や生産プロセスの改善、コスト削減などを地道に積み重ねていくことです。
これは、多くの日本企業が得意としてきた領域であり、短期的な収益確保と安定した経営基盤を築く上で不可欠な活動です。
| 活動の種類 | 具体例 | 目的 |
|---|---|---|
| 知の深化 | 製品のモデルチェンジ、生産性の向上、既存顧客へのアップセル | 収益性の最大化、競争力の維持 |
知の深化を支えるTMS理論
社会心理学者ダニエル・ウェグナーが提唱したTMS理論(Transactive Memory Systems theory)は、「誰が何を知っているか(know who)」を組織で共有することでパフォーマンスが高まるとする理論です。
これは、両利きの経営における「知の深化」を支える考え方として理解できます。
TMS理論についてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。
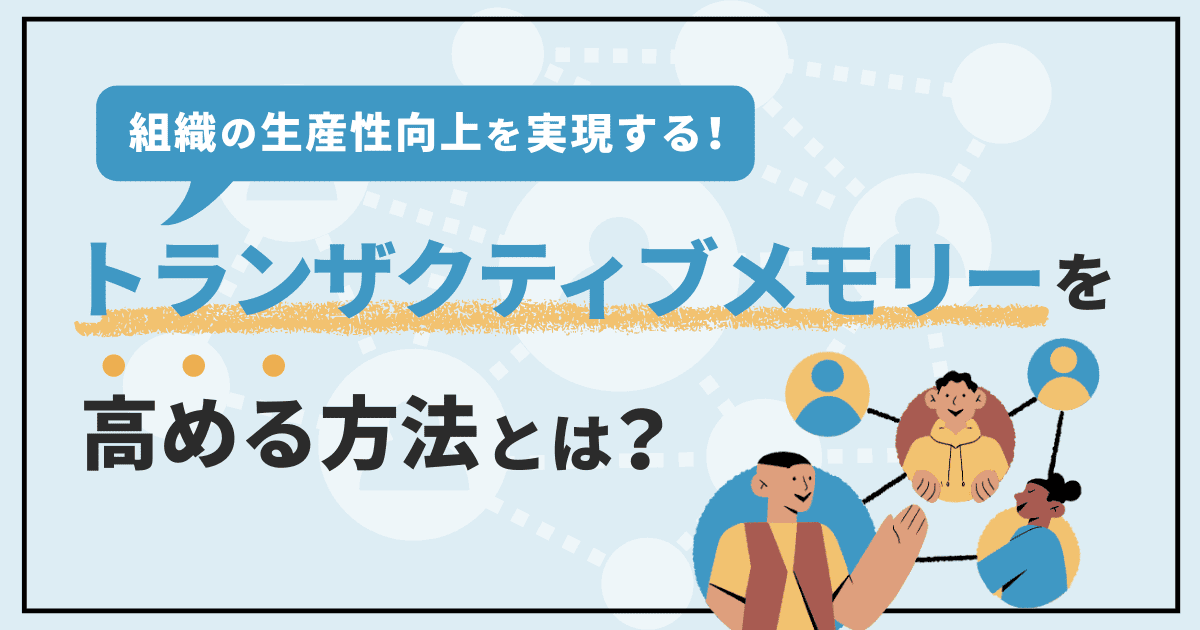
新しい価値を創る「知の探索」
一方、「知の探索(Exploration)」とは、現在の事業領域とは異なる分野に目を向け、新しい知識や技術、ビジネスモデルを探し求める活動です。
これまでの常識にとらわれず、失敗を恐れずに新しいチャレンジを繰り返し、未来の収益の柱となる可能性の種を見つけ出すことを目指します。
長期的な視点が必要であり、企業の将来を左右するイノベーションの源泉となります。
| 活動の種類 | 具体例 | 目的 |
|---|---|---|
| 知の探索 | 新規事業開発、異業種との連携、スタートアップへの投資 | 新たな市場の創出、持続的成長の実現 |
知の探索を支えるSWT理論
社会学者マーク・グラノヴェッターが提唱したSWT理論(Strength of Weak Ties theory)は、家族や親友のような「強いつながり」ではなく、知人や別コミュニティの人といった日常的にはあまり交流がない「弱いつながり」からこそ、新しい情報や多様な視点がもたらされると示した理論です。
これは、両利きの経営における「知の探索」を裏づける考え方として位置づけられます。SWT理論についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
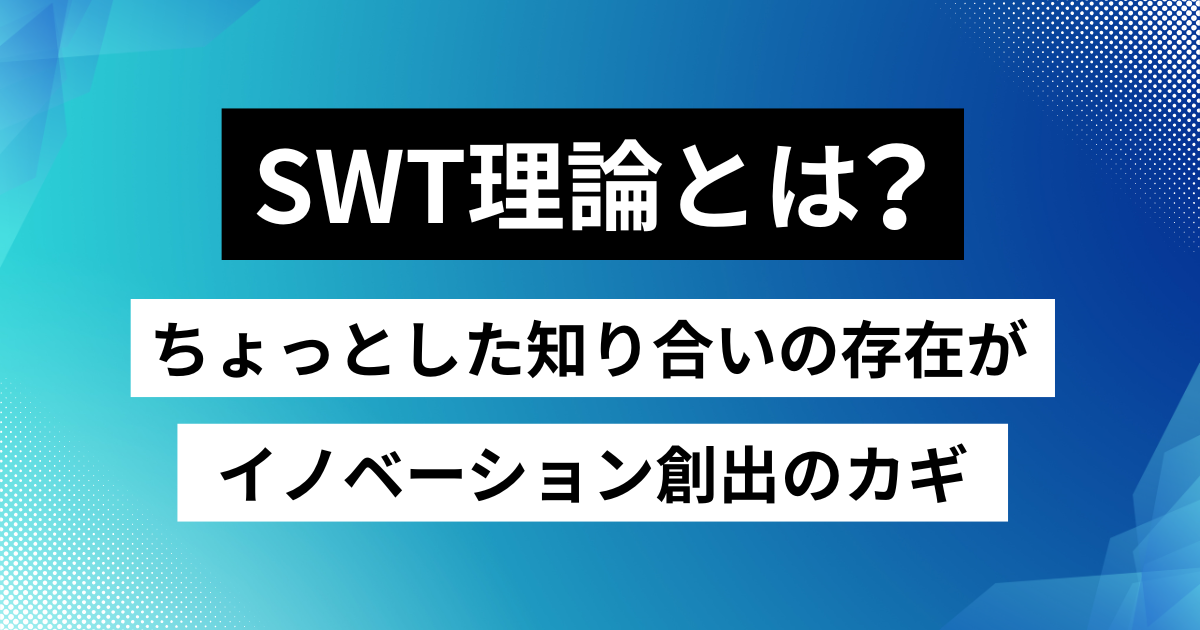

なぜ「両利き」である必要があるのか
企業が長期的に成長し続けるためには、「知の深化」と「知の探索」のどちらか一方だけでは不十分です。「深化」だけを追求すると、既存事業が市場の変化に対応できなくなった時に共倒れになるリスクがあります。
逆に「探索」ばかりに注力すると、短期的な収益が不安定になり、経営基盤そのものが揺らぎかねません。
「深化」で得た収益を「探索」に投資し、「探索」で得た新しい知見を既存事業に応用するというサイクルを生み出すことで、企業は持続的な成長を実現できるのです。
なぜ今、両利きの経営が注目されるのか
近年、両利きの経営という概念が、多くの経営者やビジネスリーダーから注目を集めています。その背景には、現代のビジネス環境が抱える大きな変化と、企業が乗り越えるべき課題があります。
市場の変化が激しいVUCA時代への対応
現代は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った「VUCA」の時代と呼ばれています。
デジタル技術の急速な進化やグローバル化、顧客ニーズの多様化などにより、市場環境は目まぐるしく変化し、将来の予測が非常に困難になっています。昨日までの成功法則が、今日には通用しなくなることも珍しくありません。
このような時代において、既存事業の「深化」だけに頼っていては、環境の変化に取り残されてしまいます。「探索」を通じて常に新しい可能性を模索し、変化に柔軟に対応できる体制を築くことが、企業の存続に不可欠なのです。
イノベーションのジレンマからの脱却
「イノベーションのジレンマ」とは、優良企業が既存顧客のニーズに応えるために製品の改良(知の深化)に集中するあまり、新しい技術やビジネスモデル(知の探索)への対応が遅れ、新興企業に市場を奪われてしまう現象です。
かつて写真フィルム市場で圧倒的なシェアを誇っていたコダックが、デジタル化の波に乗り遅れて経営破綻した事例はあまりにも有名です。両利きの経営は、このジレンマを克服するための具体的な処方箋として期待されています。
既存事業を守りながらも、意図的に「探索」のための組織や資源を確保することで、企業は非連続的な成長を実現し、破壊的なイノベーションの波を乗り越えることができるのです。
イノベーションのジレンマについてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
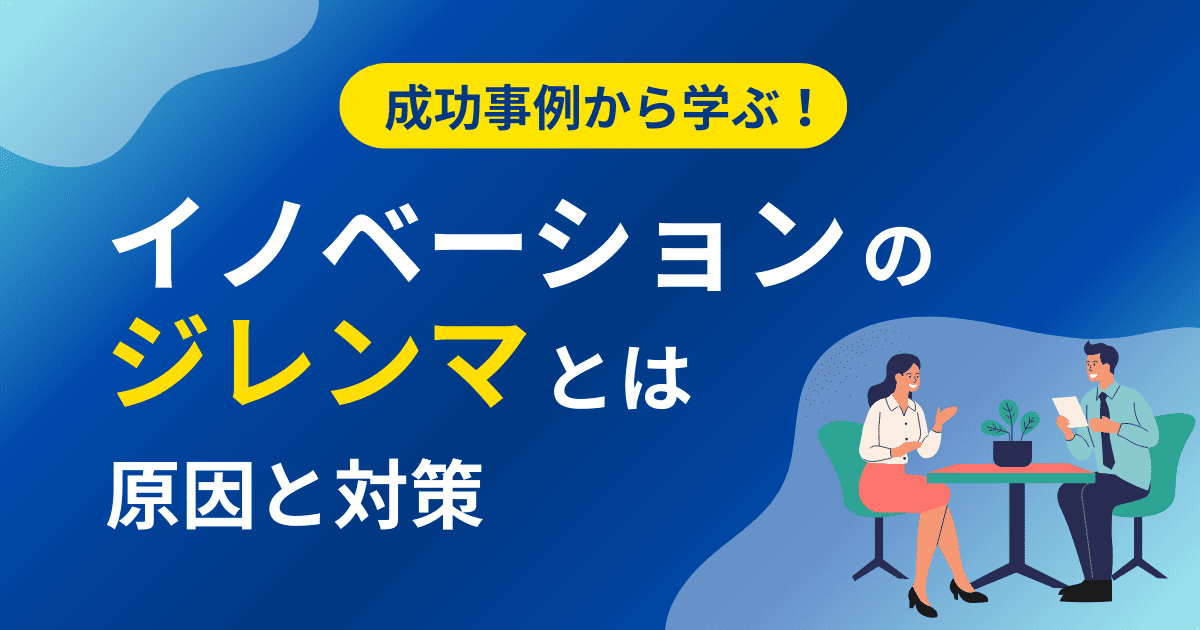

両利きの経営が失敗する2つの大きな壁
両利きの経営の重要性は理解できても、その実践は容易ではありません。
多くの企業が導入を試みながらも、成果を出せずに終わってしまうのには、いくつかの典型的な失敗要因があります。ここでは、特に陥りがちな2つの大きな壁について解説します。
「知の深化」に偏ってしまうコンピテンシー・トラップ
コンピテンシー・トラップとは、企業が過去の成功体験や得意なやり方(コンピテンシー)に固執するあまり、新しい挑戦を避け、結果的に環境変化に対応できなくなる状態を指します。
既存事業の「深化」は、短期的に成果が出やすく、評価もされやすいため、組織の資源や関心が自然とそちらに集中しがちです。
一方、「探索」活動は成果が出るまでに時間がかかり、失敗のリスクも高いため、社内での風当たりが強くなりがちです。「まだ利益の出ない事業に投資するより、儲かっている事業を強化すべきだ」という声が大きくなり、いつの間にか「探索」活動が縮小・停止してしまいます。
既存事業と新規事業の組織文化の対立
「深化」を担う組織と「探索」を担う組織では、求められるスキルセット、行動様式、価値観、そして組織文化が大きく異なります。
「深化」組織では効率性や正確性、計画性が重視されるのに対し、「探索」組織では自律性やスピード、試行錯誤が必要です。この違いを理解しないまま両利きの経営を進めようとすると、組織間で深刻な対立が生まれることがあります。
例えば、既存事業の基準で新規事業の進捗を評価したり、新規事業の自由な文化を既存事業の規律で縛ろうとしたりすると、探索チームのモチベーションは著しく低下し、イノベーションの芽は摘まれてしまいます。
両利きの経営を成功に導く4つのポイント
両利きの経営を阻む壁を乗り越え、成功に導くためには、戦略的に組織を設計し、運用していく必要があります。ここでは、そのために重要となる4つのポイントを紹介します。
経営トップによる強いコミットメント
両利きの経営は、経営トップがその重要性を深く理解し、「自らの代で必ず実現する」という強い意志と覚悟を持つことから始まります。
「深化」と「探索」の間に生まれる対立や矛盾を調整し、短期的な利益を求めるプレッシャーから「探索」活動を守ることは、経営トップにしかできない重要な役割です。
社長自らが両利きの経営の必要性を繰り返し語り、未来への投資を断行する姿勢を示すことが、全社的な取り組みの第一歩となります。

2つの組織をつなぐ共通のビジョン
「深化」と「探索」の組織は、評価基準や文化が異なる独立したユニットとして運営されるべきですが、完全に分離してしまうと協力関係が失われます。
そこで重要になるのが、両方の組織を統合する、より上位のビジョンやパーパス(企業の存在意義)です。
「我々の会社は、深化と探索を通じて、社会にどのような価値を提供するのか」という共通の目標を掲げることで、両組織の従業員は互いの活動の重要性を理解し、一体感を持ってそれぞれのミッションに取り組むことができます。
「探索」と「深化」で異なる評価制度の設計
両方の組織に同じ評価基準を適用することは、多くの場合、「探索」活動の失敗につながります。既存事業で使われる売上や利益といった短期的な財務指標を新規事業に適用すれば、ほとんどのプロジェクトは「失敗」と見なされてしまうでしょう。
「探索」組織には、学習の量や顧客との対話回数、仮説検証のスピードといった、活動量やプロセスを評価する指標を導入するなど、事業フェーズに合わせた独自の評価・報酬制度を設計することが不可欠です。
| 組織 | 評価指標の例 |
|---|---|
| 深化組織 | 売上高、利益率、マーケットシェア、生産性 |
| 探索組織 | 顧客インタビュー数、試作品の開発数、マイルストーンの達成度 |
両事業のリソース共有を促す仕組み
組織を分けつつも、両者の間でのリソースやノウハウの共有を意図的に促すことが、両利きの経営のメリットを最大化する上で重要です。
例えば、既存事業が持つ顧客基盤や販売チャネル、技術的な知見を新規事業チームが活用できるようにしたり、逆に新規事業で得られた市場の新しい兆候や顧客インサイトを既存事業にフィードバックしたりする仕組みを構築します。
これにより、企業全体として学習効果が高まり、イノベーションの成功確率が向上します。
【企業事例】両利きの経営の実践例
理論だけでなく、実際に両利きの経営を実践し、大きな変革を遂げた企業の事例から、成功のヒントを学びましょう。
富士フイルム:写真フィルムからヘルスケアへの転換
写真フィルム市場のデジタル化という存亡の危機に直面した富士フイルムは、両利きの経営の代表的な成功事例として知られています。
同社は、写真フィルムで培った化学合成や薄膜塗布といった高度な技術(知の深化)を応用し、液晶ディスプレイ用フィルムや化粧品、医薬品といった全く新しい事業領域(知の探索)へと進出しました。
既存技術というアセットを最大限に活用しながら、大胆な事業ポートフォリオの転換を成し遂げ、見事に危機を乗り越えたのです。
出典:【図解】富士フイルム事業転換の本質とは?~写真技術の新用途を開拓した技術マーケティング戦略の成功事例|Techno Producer
AGC:ガラス事業から多角的な素材メーカーへ
ガラスメーカーとして長い歴史を持つAGC(旧・旭硝子)も、両利きの経営によって変革を遂げた企業です。
同社は、従来のガラス事業を「コア事業」として深化させる一方で、「戦略事業」としてエレクトロニクスやライフサイエンスといった成長領域を探索しました。CEO自らが強いリーダーシップを発揮し、「素材の会社」としての新たなビジョンを提示。
2つの事業に異なるマネジメント手法を導入し、予算配分も戦略的に変更することで、高収益なグローバル素材メーカーへと進化を遂げました。
出典:戦略事業|AGC
Amazon:EC事業とクラウド事業のシナジー
巨大IT企業であるAmazonも、両利きの経営を巧みに実践しています。オンライン書店として始まったEC事業を徹底的に深化させ、世界的な物流網と顧客基盤を築き上げました。
その一方で、自社のECサイトを運営するために構築した巨大なITインフラを、外部の企業にも提供するというアイデアから「Amazon Web Services(AWS)」という新規事業を探索しました。
今やAWSは同社の営業利益の大部分を稼ぎ出す中核事業となっており、「深化」から生まれたアセットが「探索」を成功させ、企業全体の成長を牽引する好循環を生み出しています。
出典:創業30周年のAmazon、その利益の源泉とは ~急成長支えたB2Bサービス、たゆまぬ新事業の探求精神~北米トレンド|business leaders square wisdom
まとめ
本記事では、既存事業を磨く「知の深化」と、未来の価値を創る「知の探索」を両立させる「両利きの経営」について解説しました。
VUCA時代を生き抜き、持続的な成長を遂げるために、この経営手法はすべての企業にとって重要な意味を持ちます。
成功の鍵は、経営トップの強い意志のもと、2つの異なる活動を許容する組織を戦略的に設計し、粘り強く運営していくことにあります。