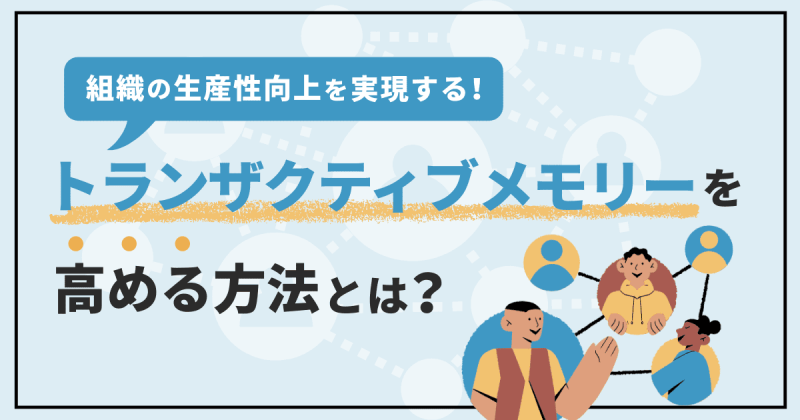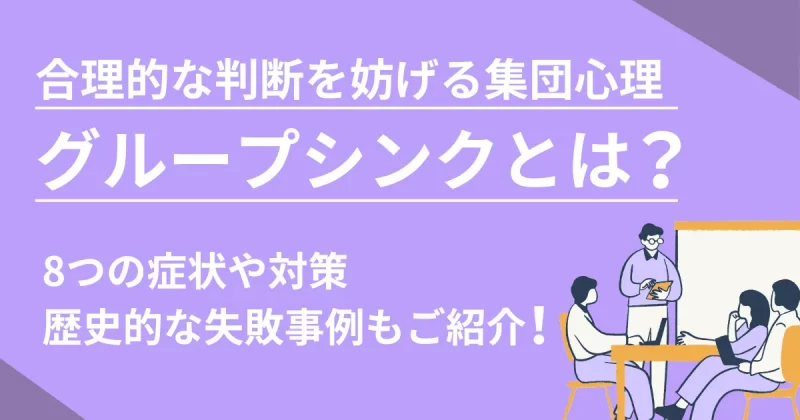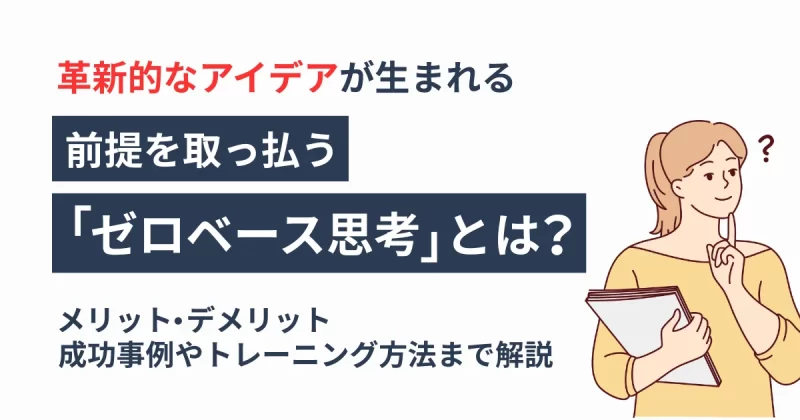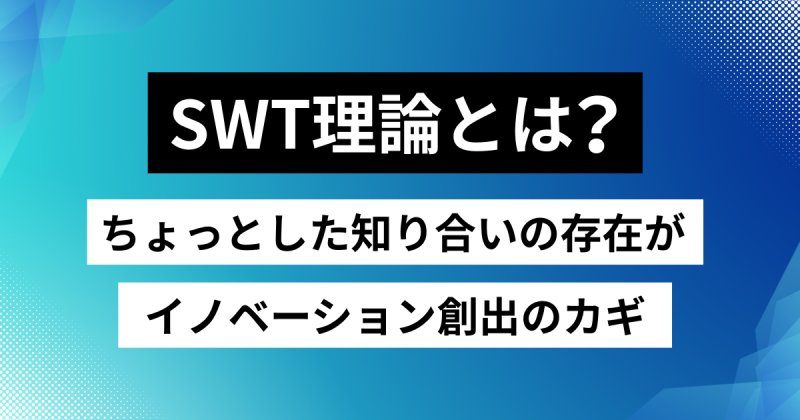近年、組織のパフォーマンスを最大化する手法として「トランザクティブメモリー」が注目されています。
これは、単に情報を共有するだけでなく、「誰が何を知っているか」を組織全体で把握し、活用する考え方です。
この記事では、トランザクティブメモリーの基本的な概念から、組織にもたらすメリット、具体的な高め方、そして企業の成功事例までをわかりやすく解説します。
チームの生産性向上や属人化の解消に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
トランザクティブメモリーとは?
トランザクティブメモリーは、組織の知識を管理し、活用するための重要な概念です。
日本語では「交換記憶」と訳されることもあります。
この考え方は、1980年代に社会心理学者のダニエル・ウェグナーによって提唱されました。
「誰が何を知っているか」を共有する考え方
トランザクティブメモリーの核心は、組織のメンバー全員が同じ知識を持つことを目指すのではなく、「組織の中で誰が、どのような知識やスキルを持っているのか」という情報を全員で共有し、必要な時にその知見を引き出せる状態を作ることです。
例えば、新しいプロジェクトで問題が発生した際に、「この技術的な課題についてはAさんが詳しい」「過去の類似案件のデータはBさんが持っている」ということがすぐに分かり、適切な人材にアクセスできる状態が、トランザクティブメモリーが機能している状態と言えます。
これにより、組織は個人の知識を集合的な知恵として活用できるようになります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 提唱者 | ダニエル・ウェグナー(Daniel M. Wegner) |
| 提唱時期 | 1980年代半ば |
| 日本語訳 | 交換記憶、対人交流的記憶 など |
| 中心的な考え方 | 「Who knows What(誰が何を知っているか)」の共有 |
組織学習や状況共有との違い
トランザクティブメモリーは、「組織学習」や「組織内状況共有」といった類似の概念としばしば比較されます。
「組織学習」は、組織が経験から学び、行動や仕組みを変化させていくプロセス全体を指す、より広範な概念です。
トランザクティブメモリーは、この組織学習を促進するための重要な要素の一つと位置づけられます。
一方、「組織内状況共有」は、プロジェクトの進捗状況や現在の課題など、全員が「同じ情報」をリアルタイムで把握している状態です。
これに対し、トランザクティブメモリーは、「情報のありか」や「専門知識の所有者」を共有する点で異なります。
組織の規模が大きくなるほど、全員がすべての情報を共有するのは非効率になるため、トランザクティブメモリーの重要性が増します。
トランザクティブメモリーがもたらす4つのメリット
トランザクティブメモリーを組織に導入することは、多くのメリットをもたらします。ここでは、代表的な4つのメリットについて解説します。
組織全体のパフォーマンスが向上する
トランザクティブメモリーが確立されると、必要な情報や知識を持つ専門家に迅速にアクセスできるため、問題解決のスピードと質が向上します。
各メンバーが自分の専門分野に集中し、他の領域は専門のメンバーに任せることで、組織全体の知識が効率的に活用され、パフォーマンスの最大化につながるのです。
多くの研究で、トランザクティブメモリーが高いチームほど、成果も高くなることが示されています。
業務の生産性が高まる
「この件は誰に聞けばいいのか」と探す時間が削減され、無駄なコミュニケーションコストが減少します。
また、同じ情報を複数の人が重複して調べる必要がなくなり、業務の効率が大幅に向上します。
必要な知識が円滑に流通することで、プロジェクトの進行がスムーズになり、生産性の向上に直結するのです。
従業員の負担が軽減される
すべての情報を一人で抱え込む必要がなくなり、個々の従業員の記憶に関する負担が軽減されます。
自分の専門外のことについては、他の専門家を頼ることができるという安心感が、精神的なストレスを和らげます。
これにより、従業員は自身の専門分野の業務に、より集中して取り組むことが可能です。
専門性の高い人材が育つ
各メンバーが特定の分野の知識を深めることが奨励されるため、自然と専門性の高い人材が育成されます。
自分の専門知識を他者に提供し、他者からも専門知識を得るという相互作用を通じて、組織全体の知識レベルが向上します。
このプロセスは、個人のキャリア形成にも良い影響を与え、学習意欲の高い組織風土を醸成します。
トランザクティブメモリーのデメリットと注意点
トランザクティブメモリーは多くのメリットがある一方で、導入や運用においては注意すべき点も存在します。
従業員の育成を阻害する可能性がある
トランザクティブメモリーは専門性を高める一方で、特定の分野に知識が偏り、ジェネラリストの育成を阻害する可能性があります。
従業員が自身の専門分野以外の知識を学ぶ機会が減ってしまうと、多角的な視点を持つ人材が育ちにくくなる恐れがあります。
そのため、計画的なジョブローテーションや研修制度を組み合わせるなど、バランスの取れた人材育成計画が必要です。
情報共有システムの構築が必要になる
トランザクティブメモリーを効果的に機能させるためには、「誰が何を知っているか」を可視化し、誰もがアクセスできる仕組みが不可欠です。
そのためには、社内SNSやプロフィールツール、データベースなどの情報共有システムを導入・構築する必要があります。
システムの導入や運用にはコストや手間がかかるため、自社の規模や目的に合ったツールを慎重に選定することが重要です。
トランザクティブメモリーを高める具体的な方法
トランザクティブメモリーは自然に形成される部分もありますが、意識的に高めることで、その効果を最大化できます。
ここでは、そのための具体的な方法を紹介します。

| 方法 | 具体的な施策例 |
|---|---|
| 心理的安全性の確保 | 1on1ミーティングの実施、失敗を許容する文化の醸成 |
| 直接的な交流の促進 | 社内イベント、ランチ会、フリーアドレス制の導入 |
| 対話重視の文化 | 挨拶の奨励、オープンなミーティングスペースの設置 |
| ツールの活用 | 社内報やプロフィールの活用 |
組織の心理的安全性を高める
従業員が「こんなことを聞いたら、能力が低いと思われるかもしれない」といった不安を感じずに、自由に質問や相談ができる環境が不可欠です。
心理的安全性が高い組織では、活発なコミュニケーションが生まれ、自然と「誰が何を知っているか」という情報が共有されやすくなります。

直接的なコミュニケーションの機会を設ける
研究によれば、メールなどのテキストコミュニケーションよりも、顔を合わせた直接的な対話の方がトランザクティブメモリーを高める上で効果的であると報告されています。
定期的なミーティングや社内イベント、ランチ会などを通じて、部署や役職を超えた従業員同士が直接交流する機会を積極的に設けることが重要です。
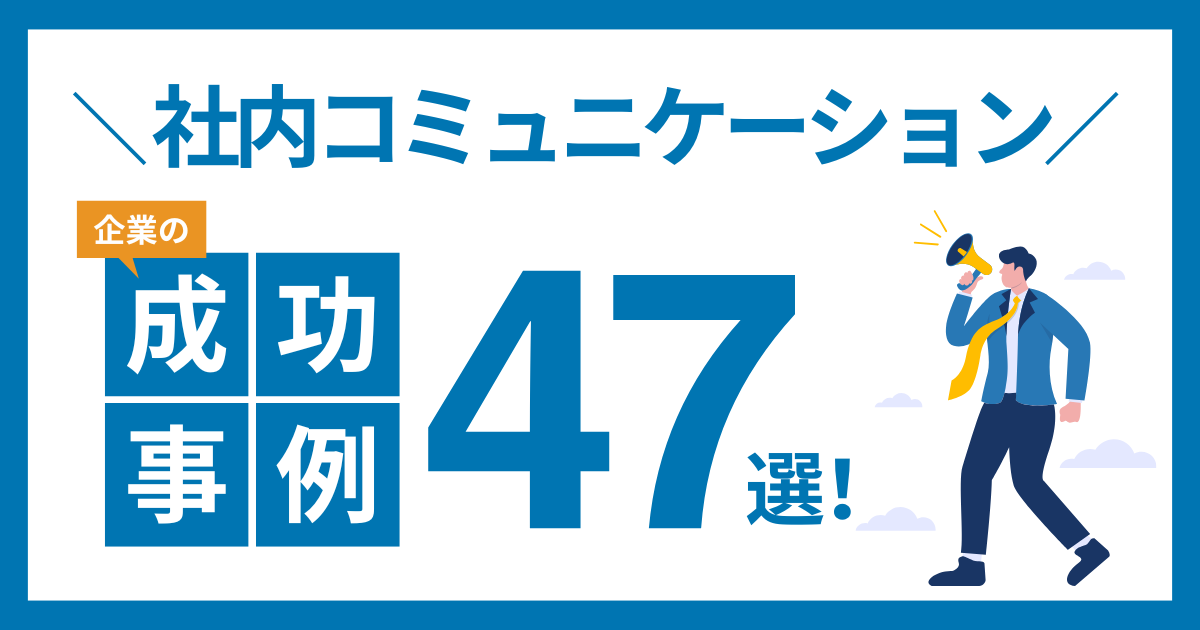
対話を重視した文化を醸成する
お互いの人となりや経験を知ることで、信頼関係が構築され、専門知識の交換がスムーズになります。
オープンな環境で雑談や意見交換がしやすい雰囲気を作ることも、トランザクティブメモリーの土台となります。
挨拶の奨励やフリーアドレスの導入なども、対話を促進する一つの方法です。
ビジネスツールを効果的に活用する
組織の規模が大きくなると、全員の顔と名前、専門性を把握するのは困難になります。
そこで有効なのが、社内報やプロフィールの活用を通じて、社員のスキルや経験、取り組みを可視化することです。
記事やプロフィールを通じて「誰が何を知っているか(know who)」が社内に浸透すれば、必要な知見に素早くアクセスできるようになり、トランザクティブメモリーの基盤が強化されます。
トランザクティブメモリーを高めるにはourlyプロフィール

ourly profile(アワリープロフィール)は、個人のプロフィールや組織図機能などにより、組織のサイロ化を解消する社内コラボレーション創出ツールです。
「誰が何を知っているか」を可視化し、組織内で知識や経験を引き出せるトランザクティブメモリーの実践を支援する仕組みとして活用いただけます。
3つの大きな特徴により、勤務形態・メンバー数にとらわれず、マネージャー(リーダー)とメンバーの相互理解を促します。
- 人となりが一目でわかる自己紹介画面
- タグ検索やプロフィールを通して、メンバーの意外なスキルや経験を知ることができる
- 組織図からメンバーの所属や役割が一目でわかる
こうした特徴から「この人がこんなスキルを持っていたんだ!」「Aさんにこの経験があったのか!」という新たな気づきを生み出し、トランザクティブメモリーを高めながら効率的なチームマネジメントやスムーズな情報共有を実現します。
チーム単位での導入も可能で、ユーザー規模に応じた料金をご用意しております。
トランザクティブメモリーの企業事例
実際にトランザクティブメモリーを導入し、成果を上げている企業の事例を3社紹介します。
株式会社リブ・コンサルティング
コンサルティング会社では、あるクライアントで得た知見やノウハウを案件に活かすことで、お客様への価値貢献が大きくなったり、スピードが早くなります。
株式会社リブ・コンサルティングでは、web社内報を通じてナレッジを蓄積し、さらにプロフィールを活用し、「誰が何の専門家なのか(know who)」を全社員に浸透させています。
これにより、課題解決に必要なベストプラクティスへ素早くアクセスできる環境を整えています。

株式会社NTTデータ
株式会社NTTデータでは、社員の自発的な活動を重視し、SNSツールを導入したコミュニケーションプラットフォーム「Nexti」を導入しました。
これにより、以前は「誰に聞けばいいか分からなかった」情報でも、プラットフォーム上で質問することで、適切な知識を持つ社員にスムーズにアクセスできるようになりました。
結果として、社内の知識が円滑に流通する基盤が構築されています。
出典:企業内SNSの利用状況と効果をめぐって~NTTデータのケースを中心に|株式会社NTTデータ経営研究所
株式会社パルコ
株式会社パルコは、グループ会社の社員同士が積極的にコミュニケーションを取れるように、プロジェクト機能やチーム機能を持つツールを導入しました。
このシステムにより、グループ間での情報交換が活性化し、部門や会社の垣根を越えた人間関係が構築され、トランザクティブメモリーの基盤が強化されています。
出典:株式会社パルコのグループ内イノベーション促進活動『I’PARCO(イノベーションダッシュパルコ)』に「チームランサーエンタープライズ」の導入が決定|PR TIMES
まとめ
本記事では、トランザクティブメモリーの基本的な概念からメリット、具体的な強化方法、そして企業の成功事例までを解説しました。
組織内の「誰が何を知っているか」を共有することは、業務効率化や組織力強化に直結します。
自社の組織風土やコミュニケーションのあり方を見直し、ツール活用なども視野に入れながら、トランザクティブメモリーの向上に取り組んでみてはいかがでしょうか。