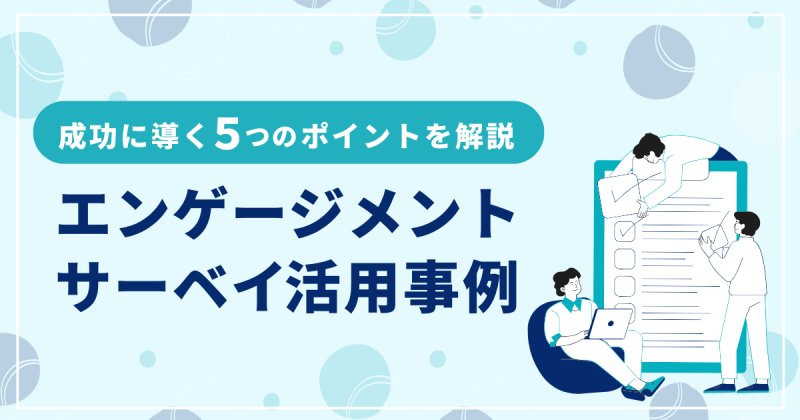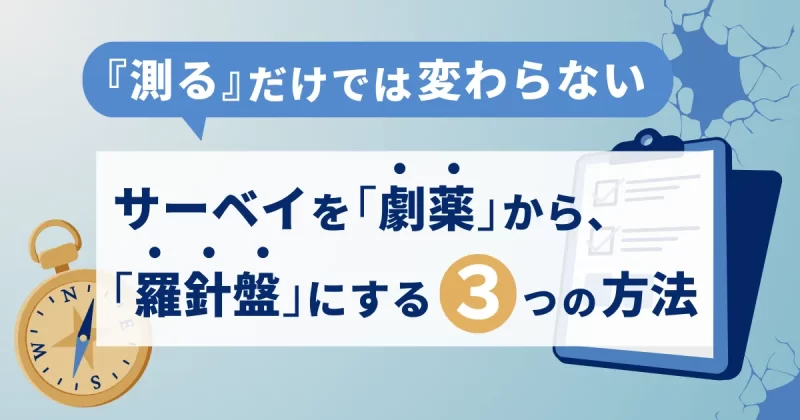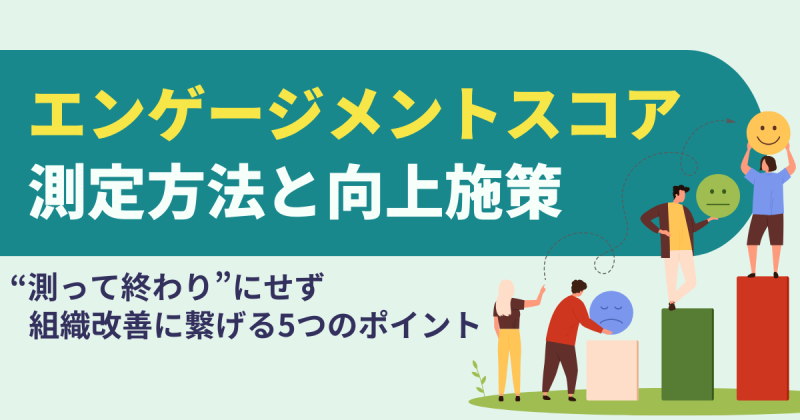近年、多くの企業が組織の成長と従業員の働きがい向上のために「エンゲージメントサーベイ」に注目しています。しかし、サーベイを実施したものの、「結果をどう活用すれば良いかわからない」「具体的な改善に繋がらない」といった悩みを抱える担当者の方も少なくありません。
この記事では、エンゲージメントサーベイの基本的な知識から、具体的な企業活用事例、そしてサーベイを成功に導くための実践的なポイントまでを網羅的に解説します。自社の組織課題を解決し、従業員一人ひとりが活躍できる環境づくりを進めるためのヒントとして、ぜひご活用ください。
エンゲージメントサーベイとは?
エンゲージメントサーベイとは、従業員が企業に対してどれくらいの愛着や貢献意欲を持っているか、いわゆる「従業員エンゲージメント」を測定・可視化するための調査です。単なる満足度調査とは異なり、従業員の自発的な貢献意欲に焦点を当てることで、組織の課題をより深く把握し、改善策に繋げることを目的としています。
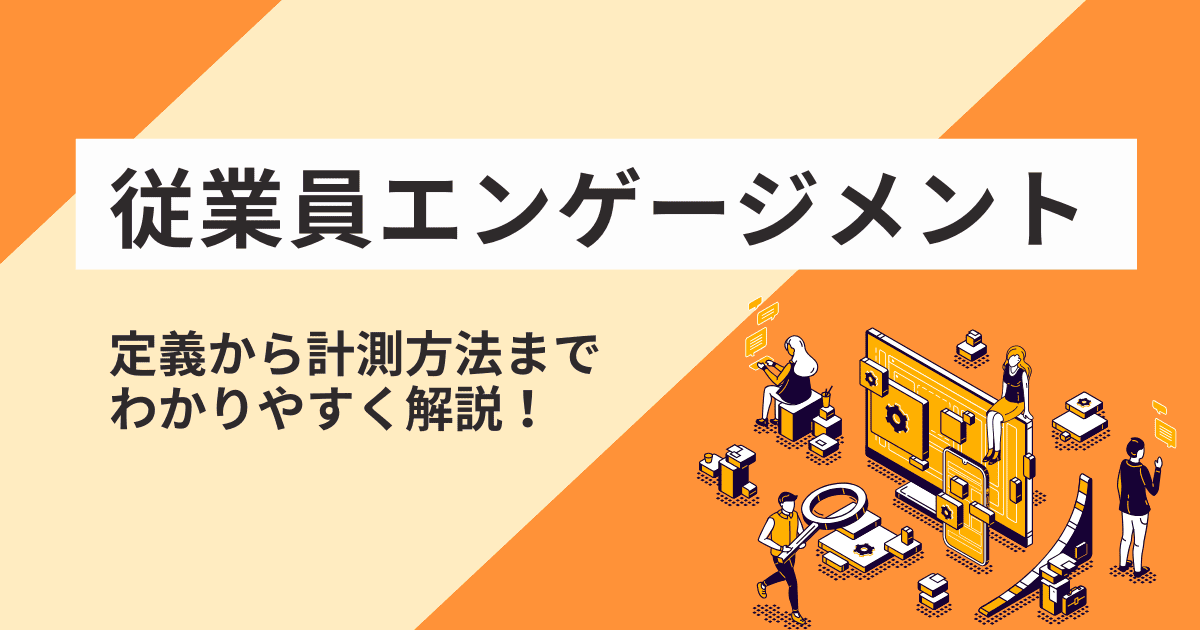
従業員満足度との違い
エンゲージメントサーベイと混同されやすいものに「従業員満足度調査」があります。この二つは似ているようで、測るものや目指すゴールが異なります。
| 項目 | エンゲージメント | 従業員満足度 |
| 定義 | 企業と従業員の相互の信頼関係・貢献意欲 | 従業員が待遇や環境に満足している度合い |
| 関係性 | 企業と従業員の対等なパートナー関係 | 企業から従業員への一方的な提供 |
| 指標 | 貢献意欲、成長実感、一体感など | 給与、福利厚生、職場環境など |
| 業績との関連 | 強い相関関係がある | 必ずしも相関しない |
従業員満足度は、給与や福利厚生といった待遇面に対する満足度を測るものであり、従業員の「居心地の良さ」を示す指標です。しかし、満足度が高くても、それが必ずしも業績向上に繋がるとは限りません。
一方、エンゲージメントは、従業員が企業のビジョンに共感し、自発的に仕事に取り組む意欲を測るものです。エンゲージメントの高い従業員は、企業の成長に貢献しようとするため、生産性の向上や離職率の低下といった形で、業績に直接的な好影響を与えることが期待されます。

なぜ今注目されているのか
エンゲージメントサーベイが注目される背景には、働き方の多様化と人材の流動化があります。終身雇用が当たり前ではなくなり、優秀な人材を確保し続けるためには、企業が従業員から「選ばれる」存在になる必要があります。
また、リモートワークの普及により、従業員の仕事ぶりやコンディションが見えにくくなりました。このような状況下で、従業員一人ひとりの状態を客観的なデータで把握し、組織としての一体感を醸成するツールとして、エンゲージメントサーベイの重要性が高まっています。
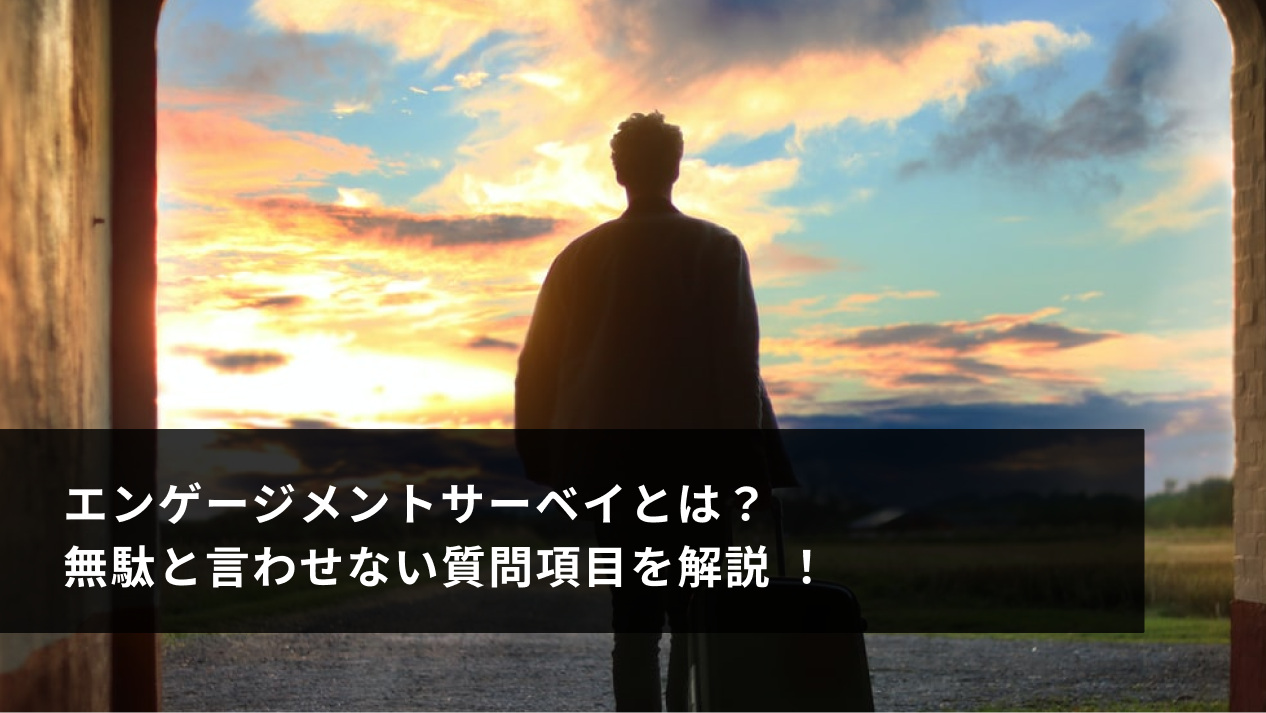
エンゲージメントサーベイの活用で得られる3つのメリット
エンゲージメントサーベイを効果的に活用することで、企業は様々なメリットを得られます。ここでは、代表的な3つのメリットについて解説します。
組織が抱える課題を可視化できる
エンゲージメントサーベイは、これまで感覚的にしか捉えられなかった組織の課題を、数値データとして客観的に可視化します。「コミュニケーションに問題がある」「成長機会が不足している」といった漠然とした課題感を、部署別、年代別、役職別などの具体的なデータで把握することが可能です。
これにより、問題の根本原因を特定しやすくなり、的確な対策を講じることが可能になります。
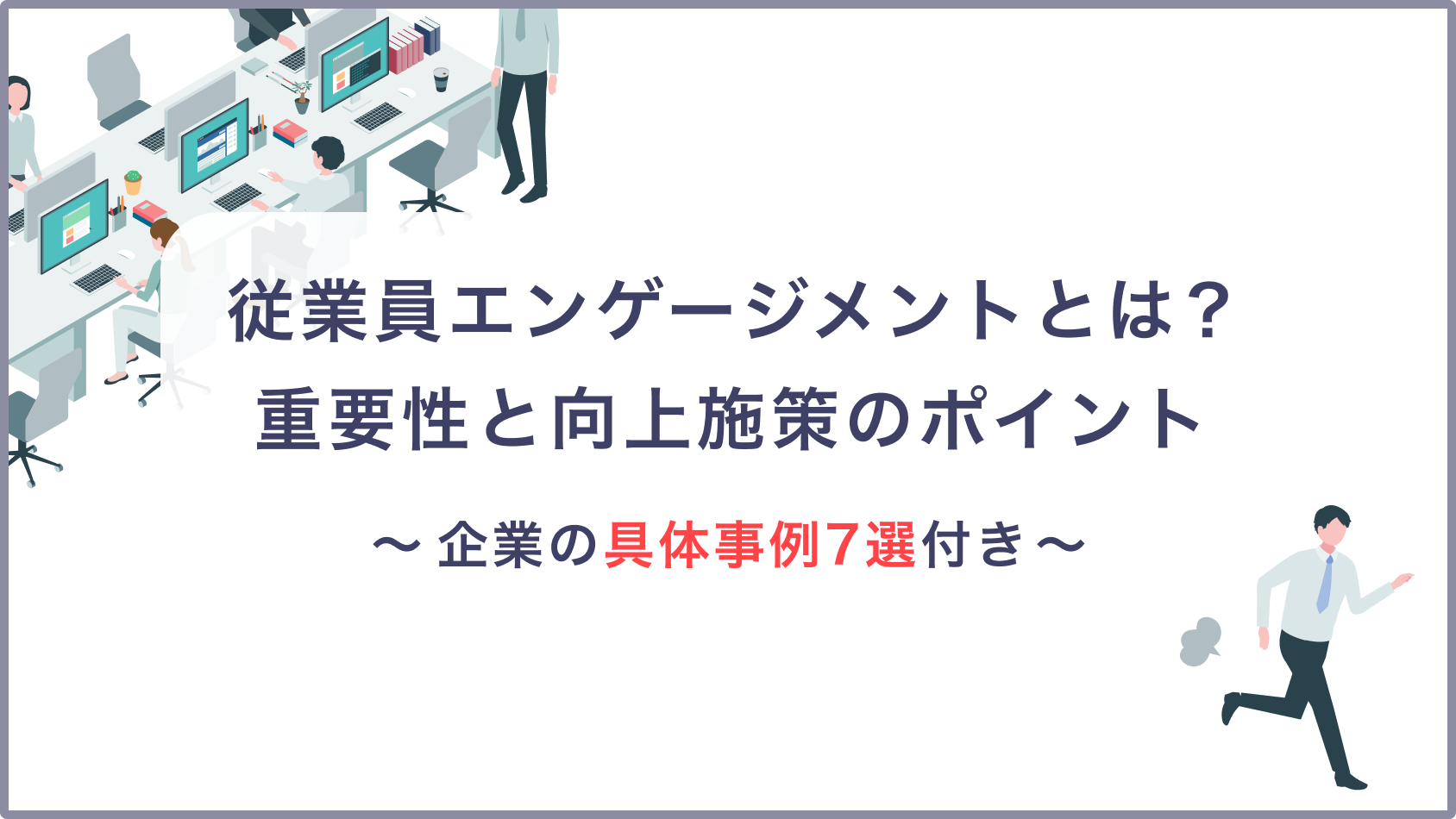
離職率の低下と人材定着に繋がる
エンゲージメントが高い従業員は、企業への帰属意識が高く、離職する可能性が低いことが分かっています。サーベイによってエンゲージメントが低下している部署や従業員の傾向を早期に察知し、1on1ミーティングなどの適切なフォローを行うことで、離職を未然に防ぐことが可能です。
また、サーベイ結果を基に職場環境の改善に取り組む姿勢を示すことは、従業員の企業に対する信頼感を高め、人材の定着に繋がります。
企業の生産性向上に貢献する
エンゲージメントの高い従業員は、自身の仕事に誇りとやりがいを感じ、自発的に業務の改善や新たな挑戦に取り組みます。このような主体的な働き方は、個人のパフォーマンスを高めるだけでなく、チーム全体の生産性向上にも大きく貢献します。
米ギャラップ社の調査では、エンゲージメントスコアが高い企業は、低い企業に比べて収益性や生産性が大幅に高いという結果も出ています。

エンゲージメントサーベイの活用事例3選
ここでは、実際にエンゲージメントサーベイを活用して組織改善に成功した企業の事例を3つ紹介します。自社で取り組む際の参考にしてください。
アイリスチトセ株式会社

アイリスチトセ株式会社では、エンゲージメントサーベイに「普段業務で関わる社員の顔と名前が一致しているか」という設問を設定していました。その結果、この項目のスコアが低く、実際に従業員間でも「顔と名前が一致しない」という課題がたびたび指摘されていました。
そこで同社は打ち手として、web社内報(ourly)を導入・運用。その後に再度エンゲージメントサーベイを実施したところ、該当項目のスコアが10ポイントも上昇したといいます。
エンゲージメントサーベイの結果を起点に組織課題を特定し、施策を実行することで解決につなげた、好例といえる事例です。
株式会社ペンシル

株式会社ペンシルでは、エンゲージメントサーベイの結果から「経営陣への信頼」に関するスコアが低いことが明らかになり、組織課題を特定しました。
当初は、福利厚生の充実や評価制度の整備など「働きやすさ」の改善に取り組みましたが、サーベイのスコアは思うように改善しませんでした。そこで次なる打ち手として、web社内報の刷新と運用を実施。その結果、サーベイの数値は徐々に上昇し、離職率も低下したといいます。
「サーベイの実施 → 施策の実行 → 効果検証 → 新たな施策の実行 → 効果検証」といったPDCAサイクルを回すことで、課題解決を実現した事例です。
株式会社LIXIL
株式会社LIXILは、従業員エンゲージメント向上のために調査システムを段階的に改善してきました。2015年から実施していた2年に1回の「LIXIL Heartbeat」調査を、2021年に四半期毎の「LIXIL VOICE」に変更し、現在は年1回の「LIXIL Voice従業員意見調査」として全従業員を対象に実施しています。
デジタル化により調査結果の分析を2週間で完了できるようになり、迅速な問題把握と解決策立案が可能となっています。このような体系的なアプローチにより、従業員エンゲージメントの向上とチーム結束力の強化を実現しています。
エンゲージメントサーベイの活用を成功させる6つのポイント
エンゲージメントサーベイを導入しても、やり方次第では効果が出ないこともあります。ここでは、サーベイを成功させるために押さえておきたい5つのポイントを解説します。
ポイント1:サーベイの実施目的を明確に伝える
サーベイを実施する前に、「なぜこの調査を行うのか」「結果を何に活用するのか」という目的を従業員に明確に伝えることが重要です。「離職率を改善し、働きやすい職場を作るため」といった具体的な目的を共有することで、従業員は調査の意義を理解し、真摯に回答してくれるようになります。
目的が曖昧なままでは、従業員から「また面倒な調査が始まった」と形骸化してしまい、正確なデータが得られません。
ポイント2:理想状態から逆算した設問設計をおこなう
目的を達成するのに必要なデータを得るための設問項目を用いることも重要です。
テンプレートの設問を闇雲に使うだけでは、エンゲージメントサーベイを実施すること自体が目的になりかねません
大事なのは、得たデータをどのように使って組織課題を解決するかです。理想の組織状態を実現するための設問を用いることを意識しましょう。
ポイント3:従業員に負担の少ない設問を設計する
サーベイの質問数が多すぎたり、回答に時間がかかりすぎたりすると、従業員の負担となり、回答率の低下や不正確な回答に繋がります。
目的を達成するために必要な質問は何かを吟味し、設問数を絞り込むことが大切です。最近では、週に1回、数問程度の簡単な質問でコンディションを測る「パルスサーベイ」も注目されています。自社の目的に合わせて、適切な頻度と設問数を選びましょう。

ポイント4:結果を速やかにフィードバックする
調査を実施したら、結果をできるだけ速やかに従業員にフィードバックすることが不可欠です。結果を共有せずにいると、従業員は「あの調査は何だったのか」と不信感を抱いてしまいます。
全体の結果はもちろん、部署ごとの結果も共有し、「私たちの部署にはこういう課題がある」と自分事として捉えてもらうことが、改善活動の第一歩となります。
ポイント5:分析結果から具体的な改善策を立てる
サーベイの結果を分析し、課題を特定したら、それを解決するための具体的なアクションプランを策定します。例えば、「上司とのコミュニケーション」のスコアが低い部署があれば、「1on1ミーティングを月1回実施する」「チームミーティングの冒頭で雑談の時間を設ける」といった具体的な施策を検討します。
課題を特定するだけで終わらせず、必ず次の行動に繋げることが重要です。
ポイント6:改善策を実行し効果を検証する
策定した改善策は、必ず実行に移し、その効果を検証します。施策を実行した後、次のサーベイで関連するスコアがどう変化したかを確認し、効果があったのか、なかったのかを評価します。
効果が不十分であれば、その原因を考え、新たな改善策を検討します。この「サーベイ→分析→施策立案→実行→効果検証」というPDCAサイクルを回し続けることが、組織を継続的に改善していく鍵となります。
エンゲージメントサーベイが無駄になると言われる理由と対策
多くの企業がエンゲージメントサーベイに取り組む一方で、「サーベイは無駄だ」「意味がない」という声が聞かれることもあります。なぜ、そのように言われてしまうのでしょうか。主な理由と対策を解説します。
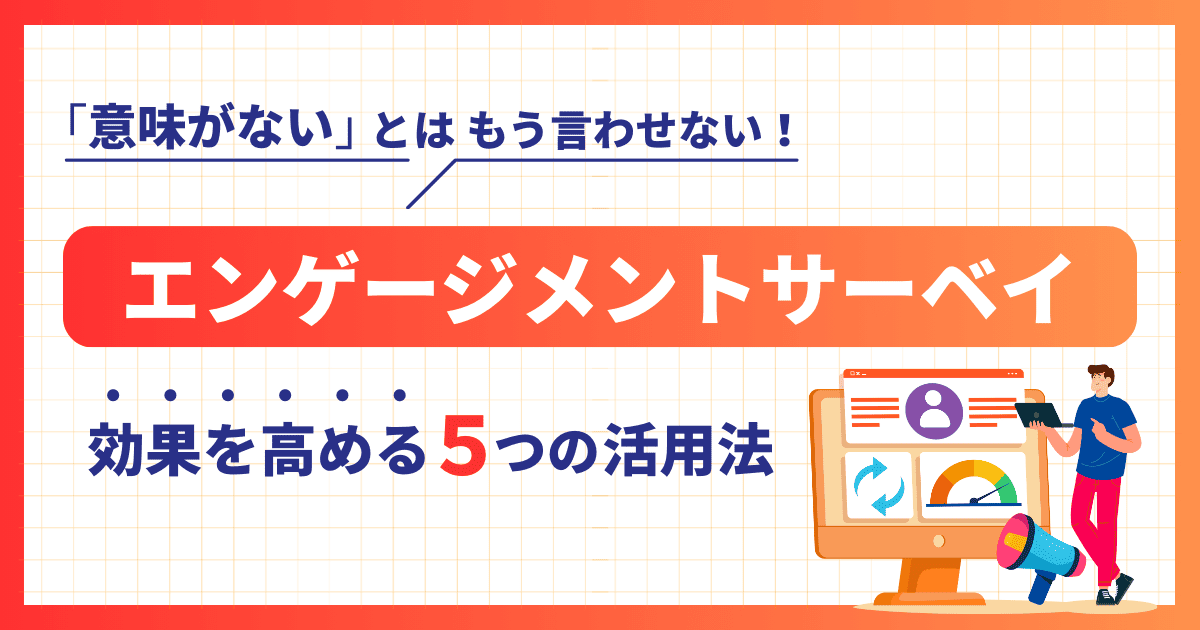
サーベイの実施が目的化している
最も多い失敗例が、サーベイを実施すること自体が目的になってしまうケースです。サーベイはあくまで組織の状態を把握するための「手段」であり、それ自体が組織を改善するわけではありません。
対策: 実施前から「サーベイ結果をもとに何をするか」というゴールを明確に設定し、経営層から現場まで共通認識を持つことが重要です。サーベイ後のアクションプランまで含めて計画を立てましょう。
結果の分析や改善策に繋がっていない
サーベイを実施し、結果が出たにもかかわらず、その後の分析や改善活動が行われず放置されてしまうケースも少なくありません。これでは、回答した従業員の期待を裏切ることになり、「どうせ回答しても何も変わらない」という無力感を組織に蔓延させてしまいます。
対策: サーベイの実施後、誰が、いつまでに結果を分析し、改善策を検討するのか、責任者とスケジュールを明確にしておきましょう。分析結果を基に、現場の従業員も巻き込んで改善策を考えるワークショップなどを開催するのも有効な手段です。

“測って終わりにさせない” サーベイツール、ourly survey
ourly surveyは、自由な設問設計と施策立案・実行までを支援する“測って終わり”にさせないサーベイです。
また、弊社が提供するweb社内報「ourly」との掛け合わせでより精緻な分析が可能になります。
細かい分析機能で組織課題を可視化
「所属/部署」「役職」「職種」「拠点」などのユーザー属性で回答結果を分析することが可能です。理念の浸透度合いや、エンゲージメントが低い層を見える化できます。
組織課題に応じた自由な設問
従業員エンゲージメントの向上や人事施策の成果測定、ビジョンの浸透度合いの計測など、自社が手に入れたい組織状態から逆算して自由に質問の作成が可能です。
行動データを組み合わせた分析
弊社が提供するweb社内報「ourly」の閲覧行動とサーベイで集計した結果をクロス分析することで、組織改善のサイクルを加速させます。
一気通貫した改善支援
弊社の組織開発コンサルタントが、サーベイで集計した結果をもとに組織課題の特定や改善施策の提案、実行を支援します。
以下の資料では、ourly surveyの具体的な特徴や機能を紹介しています。
サービスの比較や導入のご検討などに、ご活用ください。

まとめ
本記事では、エンゲージメントサーベイの活用事例から、そのメリット、成功させるためのポイントまでを解説しました。エンゲージメントサーベイは、正しく活用すれば、組織の課題を明らかにし、従業員の働きがいを高め、企業の持続的な成長を支える強力なツールとなります。
重要なのは、サーベイを実施して終わりにするのではなく、その結果と真摯に向き合い、具体的な改善アクションに繋げ、その効果を検証し続けることです。この記事が、貴社のエンゲージメント向上への取り組みの一助となれば幸いです。