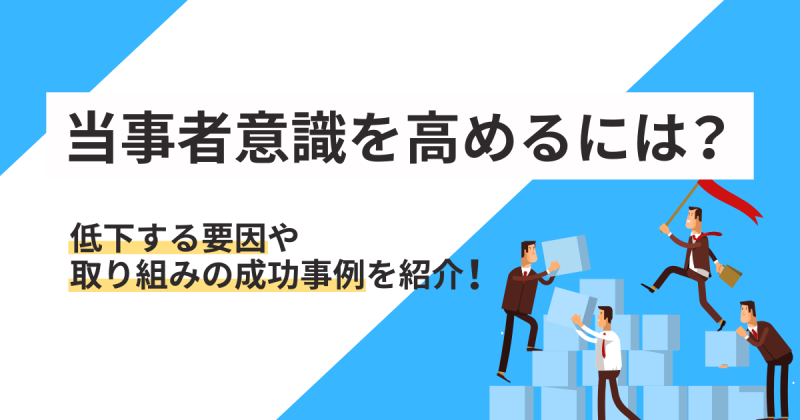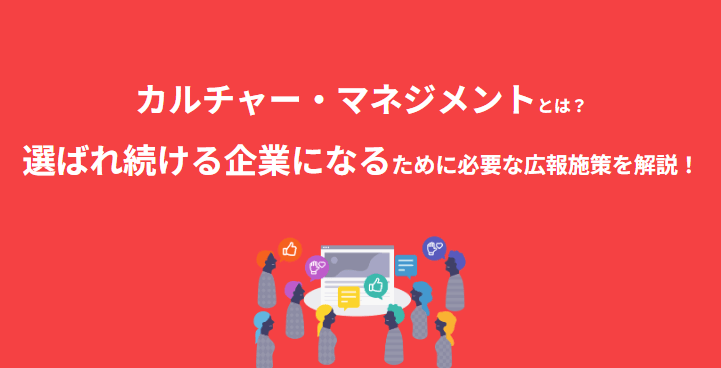当事者意識とは、物事に対して「自分が直接の関係者である」という意識のことです。
当事者意識をもち、仕事を自分ごと化して考えることができる人は、成果をあげるために主体的に行動を起こすことができます。
この記事では、当事者意識が低い人の特徴や高める方法を紹介していきます。
当事者意識とは?
当事者意識とは、物事に対して「自分が直接の関係者である」という意識のことです。この意識があることで、人はその物事に「主体性」をもって取り組めるようになります。
また「責任意識」「オーナーシップ」とも言い換えられます。中でも「オーナーシップ」とあるように、「当事者意識がある社員」は、会社のオーナーと同じ程度の意識で仕事に向き合う社員のことを指すといっても良いでしょう。
会社などの組織において、上位2割の人材が優れた働きをし、中位6割が人並み、下位の2割がローパフォーマーになるという262の法則ですが、当事者意識が高い人は必然的に上位2割に食い込む可能性が高まります。
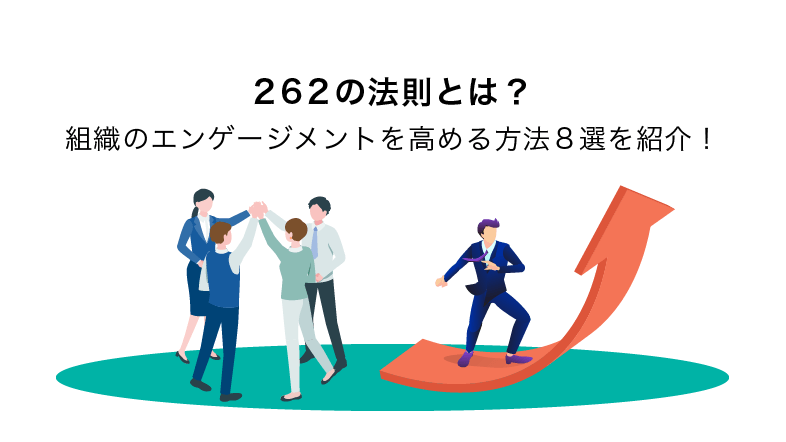
当事者意識が低い人の特徴
ここでは当事者意識が低い人の特徴を解説します。
当事者意識が低い場合、社員は仕事を「自分のこと」として捉えなくなるため、職場にさまざまな悪影響をもたらすようになります。
目的意識が低い
「何のために仕事をするのか」目的意識が低い場合、当事者意識も低くなります。自分に課せられた役割や責任が理解できていないからです。
このような状況では、周囲で起きたトラブルに対しても「自分は無関係」という態度をとるようになります。その結果、トラブルの火種が大きくなり、会社を揺るがす不祥事に発展する可能性もあります。
他人まかせである
当事者意識が低い人は、「他人まかせ」な態度をとることが多いです。
問題があっても自分の力で解決しようとせず、「これは自分の仕事ではない」「誰かがやるだろう」と考えます。こうした社員が増えれば、会社はスピード感をもった課題解決ができなくなり、組織の成長も鈍化するでしょう。
自分には無関係だと考える
当事者意識が低い人は、指示された仕事に対して「上司に言われたからやっているだけ」と考え、他人事として捉えます。
仕事を「指示通り」にこなすだけなので、状況変化への臨機応変な対応は望めません。こうした部下が多ければ、上司は常に進捗を確認し指示を修正しなくてはならず、業務が停滞することも考えられます。
責任逃れをする
当事者意識が低い人は、仕事でミスをしたときに言い訳や責任逃れをする傾向があります。
「面倒なことに巻き込まれたくない」という意識が強く、積極的にトラブルの解決に動くことをしません。自分のミスを素直に認めない人は、周囲から信頼を得ることはできないでしょう。
諦めが早い
当事者意識が低い人は、少しでもつまずくと簡単に諦めてしまいがちです。
そもそも、自分の仕事を「自分ごと」として捉えていないため、仕事をやり遂げる意識が薄く、少しでも上手くいかないと途中で投げ出してしまいます。周囲の人々はフォローに追われるため、こうした人は大事な仕事を任されなくなるでしょう。
自己評価が低い
当事者意識の低い人は、自己評価が低い場合も多いです。
自己評価が低く、周りからの評価を気にするあまり失敗を恐れ、チャレンジをしなくなります。その結果、成功体験を積めず、自信を得られないといった悪循環に陥ります。
こうしたことが、仕事に対する積極性を奪っているのかもしれません。
当事者意識が低い要因
当事者意識が低いのは、本人の性格や考え方だけでなく、組織状況が原因の可能性もあります。
以下で具体的に解説していきます。
評価基準が曖昧である
評価基準が曖昧だと、評価を上げるためにどのような行動をすれば良いか分からなくなります。
自分の行動が評価を上げるか分からず、積極的な行動を避けてしまい、当事者意識を持ちにくくなってしまいます。その結果、余計なことはしない、指示以上のことはしない意識づけがなされてしまう恐れがあります。
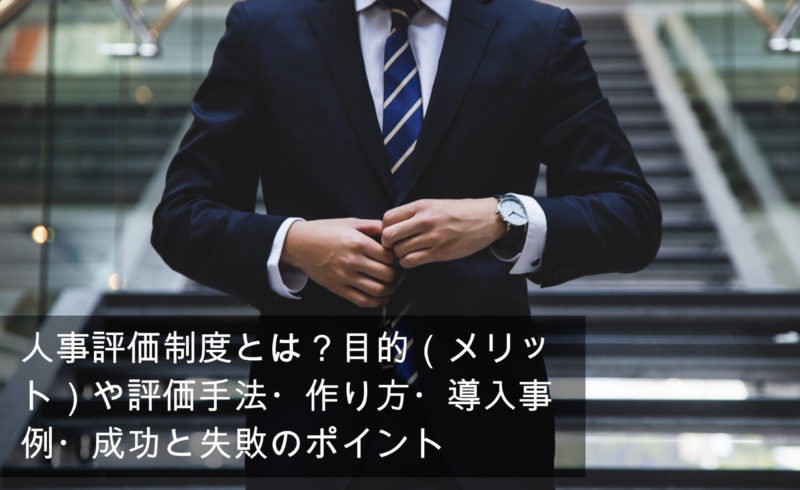
目的や目標が分かりにくい
目的や目標が理解できないと、主体的に行動する目的がなく、当事者意識を持ちにくい傾向にあります。
また目的や目標が与えられてばかりで、自分で設定できず自分ごとになっていない場合もあります。自ら目標設定することは、目標に向けて行動する主体性や責任感を持つために重要です。
業務量が多い
過大な業務量も当事者意識を低下させる要因になります。
膨大な業務量で余裕がなく、担当業務以外に関心を持てなくなります。その結果、主体的な行動を避けて担当業務のみこなす受け身の姿勢になりがちです。
心理的安全性が欠如している
職場で安心して自分を表現できる心理的安全性が低いと、当事者意識が低下していきます。
例えば、何か改善点を発見したとしても「意見を言っても聞き入れてもらえないだろう」「話しても取り合ってもらえないだろう」などと考え積極的な行動をとらなくなってしまいます。

従業員に意思決定の機会がない
トップダウン型の組織では、経営層や管理職がすべて意思決定し、従業員は指示を受けて行動するだけになり、当事者意識を持ちにくいです。
そのため、従業員は自ら考えたり意見を発信する機会が減り、組織の課題や目標を自分ごととして捉えにくくなります。
当事者意識を高める方法4選
続いて当事者意識を高める方法を4つ紹介します。
自社に合った方法を見つける参考にしてみてください。
コミュニケーションの機会を増やす
当事者意識を高めるためには、会社と社員、双方の良好な関係性が欠かせません。
そのために、会社がコミュニケーションの総量を増やすための施策を講じる必要があります。例えば、経営層が積極的に自社の理念や方針を発信すること、1on1を実施し上司と部下の対話の機会を確保するといった取り組みです。
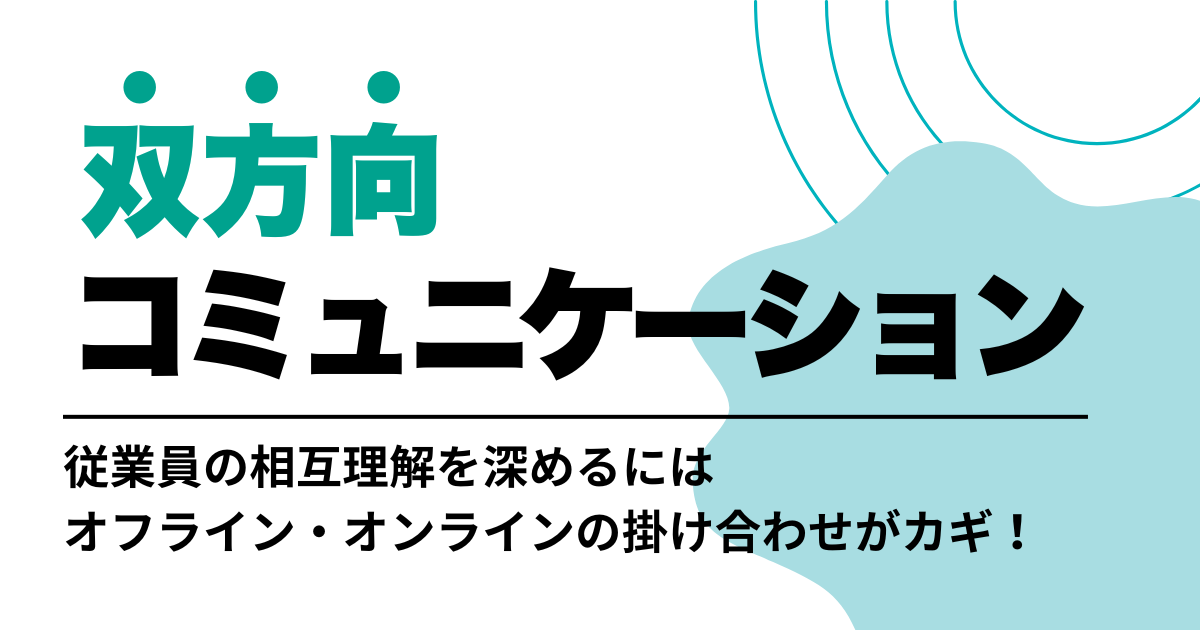
仕事の内容や役割、目標の把握
会社は社員の業務分担に際し、本人の得意・不得意を把握する必要があります。その上で「なぜ、あなたにこの業務をお願いするのか」理由を説明すると良いでしょう。
また、指示をするときは仕事内容だけでなく、求める役割と明確な目標・達成度を示します。こうすることで、「自分に期待されていること」を明確に把握できます。
フィードバックの機会を設ける
タイムリーなフィードバックの機会を設けることも、当事者意識の向上には欠かせません。
目標に対する進捗に上司がフィードバックをすることで、部下は上司が自分の仕事のどこを見ているかを把握できます。
部下である社員は、フィードバックから仕事のポイントを学び、アドバイスに素直に従うことで改善を重ね、自己成長につなげると良いでしょう。
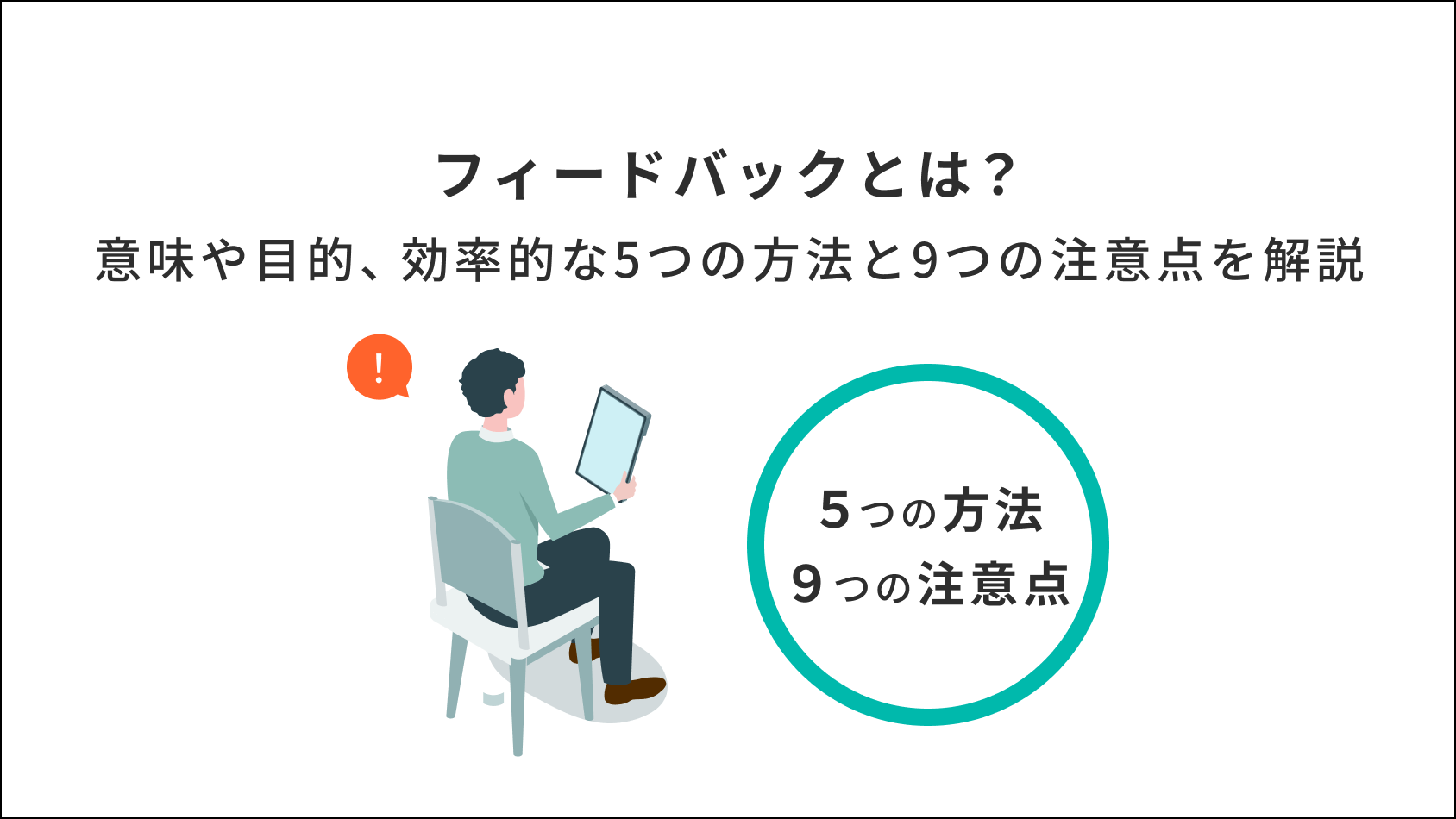
適切な評価をする・仕事を褒める
上司(会社)は、仕事の成果に対し、適切な評価をしなくてはなりません。
成果が出た場合は、社員の頑張りを認め、賞賛することが重要です。
成果が出なかった場合は、上手くいかなかった原因を一緒に考え、頑張りを認めた上で次につながるアドバイスが必要でしょう。
こうした上司からの温かい声かけは、部下のモチベーションを高めます。部下は、さらに難易度の高い仕事や目標の再チャレンジに励み、上司の期待に応えようとすることで当事者意識を高められるのではないでしょうか。
株式会社うるるさんではシナプス組織という組織形態をとることで、チームリーダー・メンバーともに当事者意識が求められる環境の形成に成功しています。実際のうるるさんの事例に関してはこちらの記事をご覧ください。
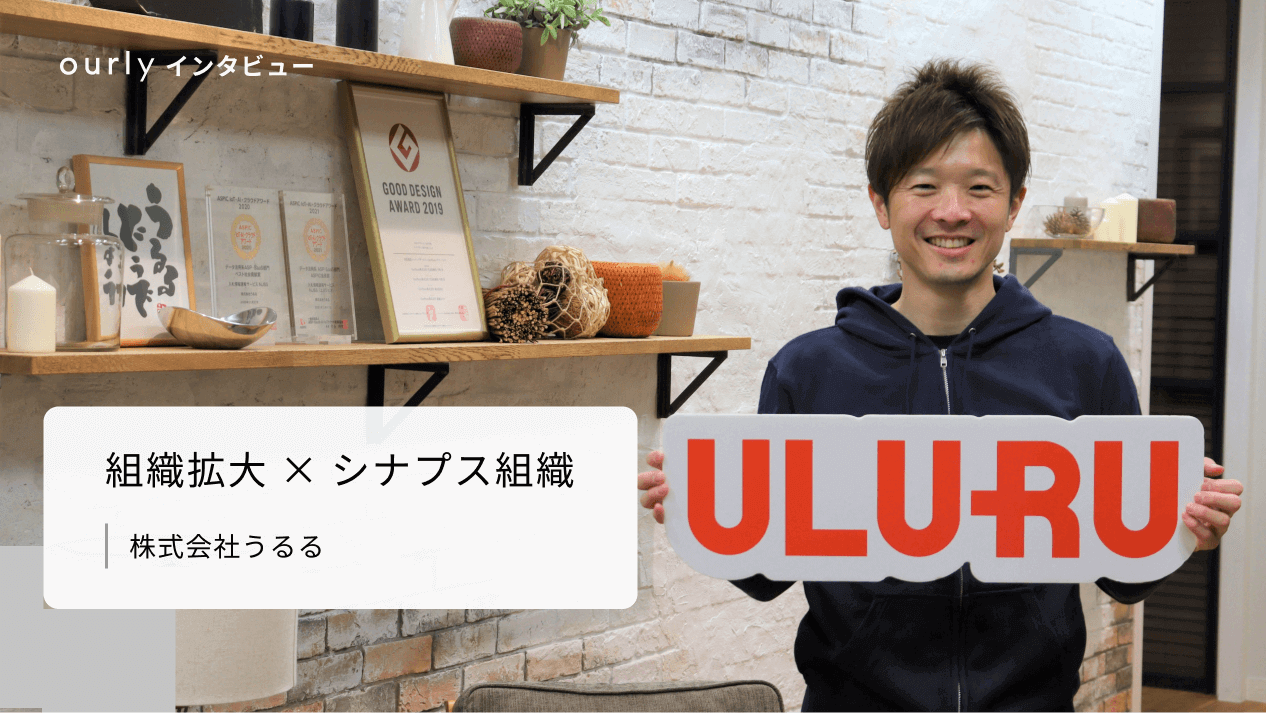
当事者意識を高めた企業の実例
当事者意識を高めた企業の実例を紹介します。
当事者意識を高めるためにどんな制度を導入したのかぜひ参考にしてみてください。
日本航空|破綻からの再生を支えた当事者意識
経営破綻前の日本航空では、「誰かが何とかしてくれる」という他人任せの空気が社内に広がっていました。
そこで稲盛和夫氏は、「JALフィロソフィ」の共有やアメーバ経営の導入を通じて、社員一人ひとりに経営視点と責任感を促しました。その結果、現場から幹部まで当事者意識が浸透し、自律的に行動する風土が醸成され、わずか2年8か月での再上場というV字回復を実現しました。
出典:日本航空の再生を支援(2010年)-日本航空を再生させた「フィロソフィ」と「アメーバ経営」-
メルカリ|感謝を送り合う制度
拠点や部署の拡大で一体感の薄れを課題としていたメルカリは、社内コミュニケーション活性化のためピアボーナス制度「メルチップ」を導入しました。
メルチップとは、毎週付与されるポイントで、社員同士がチャットツール上で「ありがとう」とともに1円相当のポイントを送り合う制度です。
この制度により、自分の行動が組織に役立っている実感が湧き、自発的な行動や連携が活発になりました。そして役職や部門を越えて協力する風土が生まれ、組織全体への当事者意識が高まりました。
出典:贈りあえるピアボーナス(成果給)制度『mertip(メルチップ)』を導入しました。
面白法人カヤック|全社員が人事に関わる制度
「自分が会社をつくっている」という実感を持たせるため、全社員が人事に関わる「ぜんいん人事部」制度、360度フィードバックや昇給の相互投票を導入しました。
こうした仕組みによって、社員一人ひとりが評価や採用に関わる当事者となり、会社を自分ごとと捉える文化が浸透しました。その結果、役職や年次に関係なく意見を言いやすい風土が生まれ、主体性と心理的安全性が高まりました。
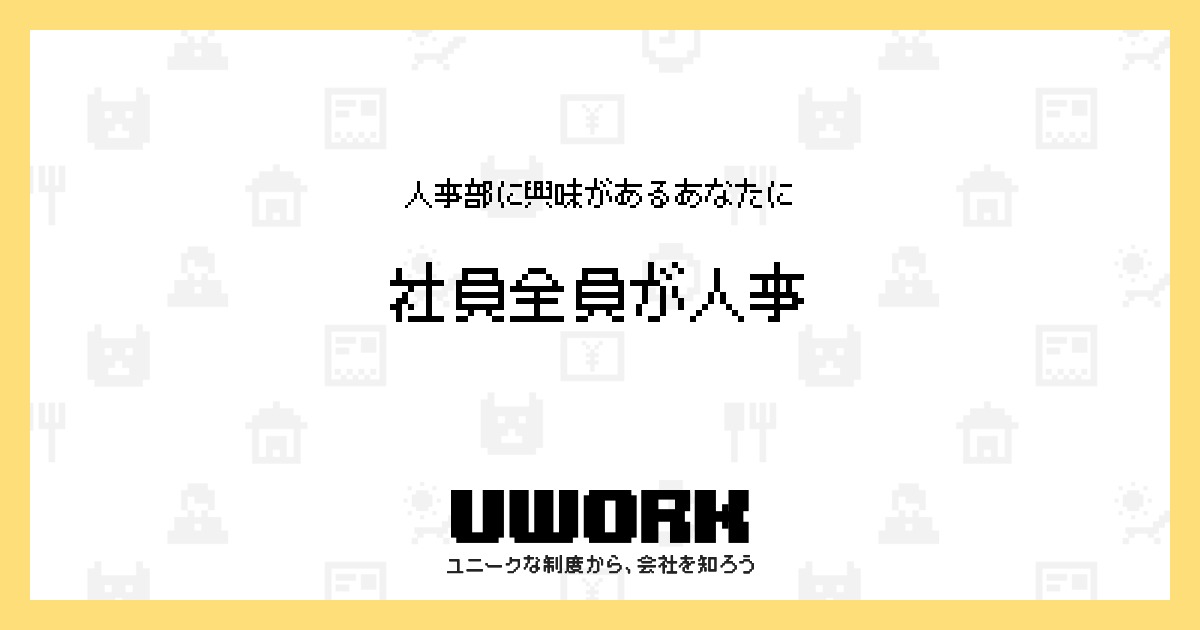
社員の当事者意識の向上ならourly

ourlyは一体感のある組織づくりを支援するweb社内報サービスです。
仕事への誇りややりがいの醸成、社内コミュニケーションの活性化により社員の当事者意識を自然に引き出すことができます。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる
- web知識不要で、誰でも発信できる
- 閲覧率・読了率の浸透度が可視化できる豊富な分析機能
- 支援体制が充実しており、運用負担が最小限にできる
「もっと社員の当事者意識を高めたい」そんなご担当者様におすすめの社内報ツールです。