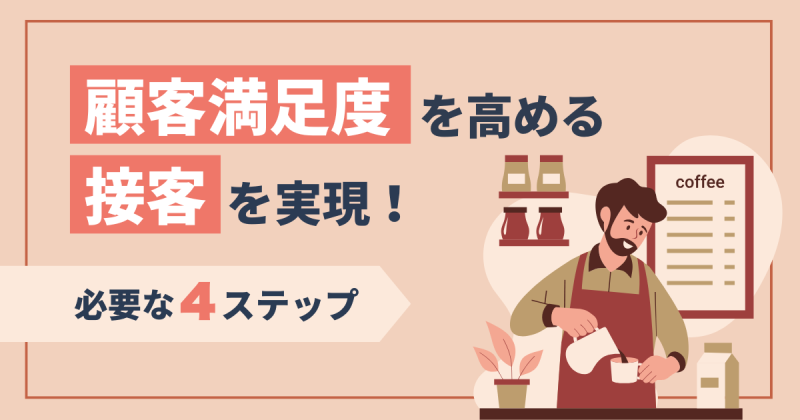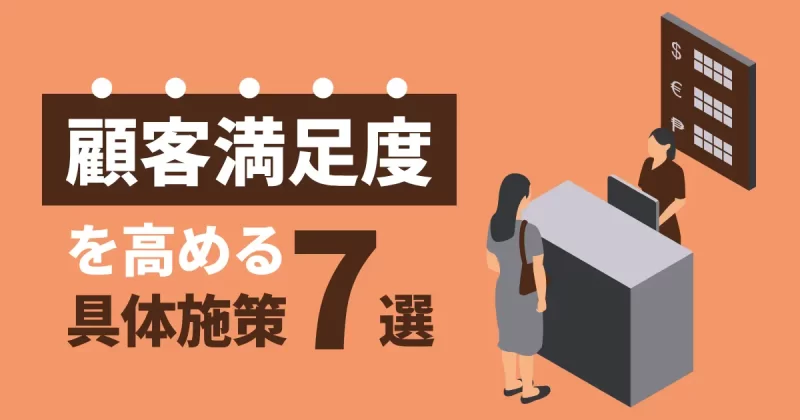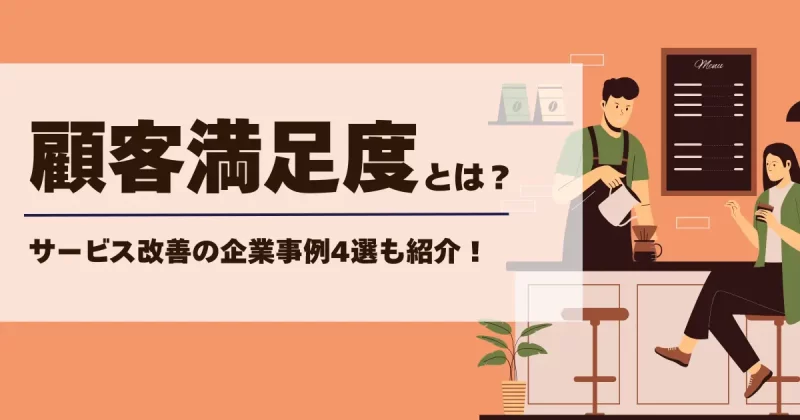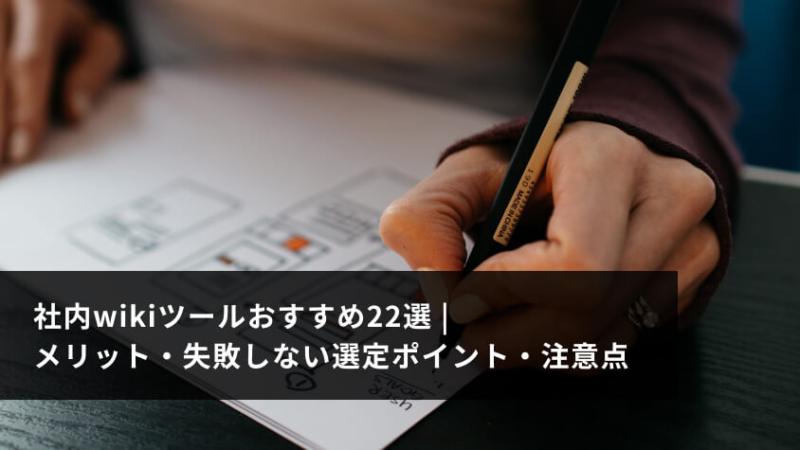「現場の接客レベルにばらつきが生じる」「研修の効果が一時的である」といった課題は、多くの企業に共通するものでしょう。その原因は、従業員個人のスキルのみならず、組織の「仕組み」にもあると考えられます。
本記事では、個別の接客テクニックに留まらず、企業の理念を浸透させ、従業員一人ひとりの主体的な行動を引き出すことで、組織全体で質の高い接客を実現するための本質的なアプローチについて解説します。
なぜ、「マニュアル通り」で止まるのか?
顧客満足度を向上させる接客には、いくつかの基本原則が存在します。これらは一般的に、企業の接客マニュアルにも反映されている内容です。
安心感・信頼感を与える接客:丁寧な言葉遣いや清潔感のある身だしなみ、豊富な商品知識など、顧客が安心してサービスを受けられる基盤となる要素です。
顧客の期待を超える特別感の提供:顧客一人ひとりの状況を察し、マニュアルにはないプラスアルファの提案や気遣いを行うことで、記憶に残る体験を創出します。
顧客に寄り添う共感の姿勢:顧客の言葉の背景にある感情やニーズを深く理解しようと努め、真摯に耳を傾けることで、信頼関係を築きます。
しかし、これらの原則を研修などで従業員に徹底しても、組織全体の顧客満足度が期待通りに向上しないケースは少なくありません。その背景には、個人のスキルだけでは解決が難しい、組織構造に起因する3つの課題、いわば「組織の壁」が存在します。
スキルの属人化の壁
特定の優秀な従業員の能力に依存することで、「あの人がいないと店舗が回らない」という状況が発生します。その従業員が異動や退職をした場合、店舗のサービスレベルが大きく低下するリスクを抱えます。
モチベーションのばらつきの壁
店舗やチーム、従業員個人によって、仕事への意欲や接客に対する考え方に差が生じます。この状態が「指示待ち」の従業員を増やし、改善活動が形骸化する一因となります。
理念と現場の乖離の壁
企業が掲げる「顧客第一主義」といった理念が、日々の現場業務にまで落とし込まれていない状態です。理念が形式的なものとなり、実際の接客行動とは結びついていません。

顧客満足度は、従業員エンゲージメントと理念浸透の「結果」
前述した「組織の壁」を乗り越えるためには、従来のアプローチを見直すことが有効です。具体的には、「スキル教育」を中心とした施策から、従業員の働きがいや貢献意欲、すなわち「従業員エンゲージメント」の向上を中心とした施策へのシフトです。
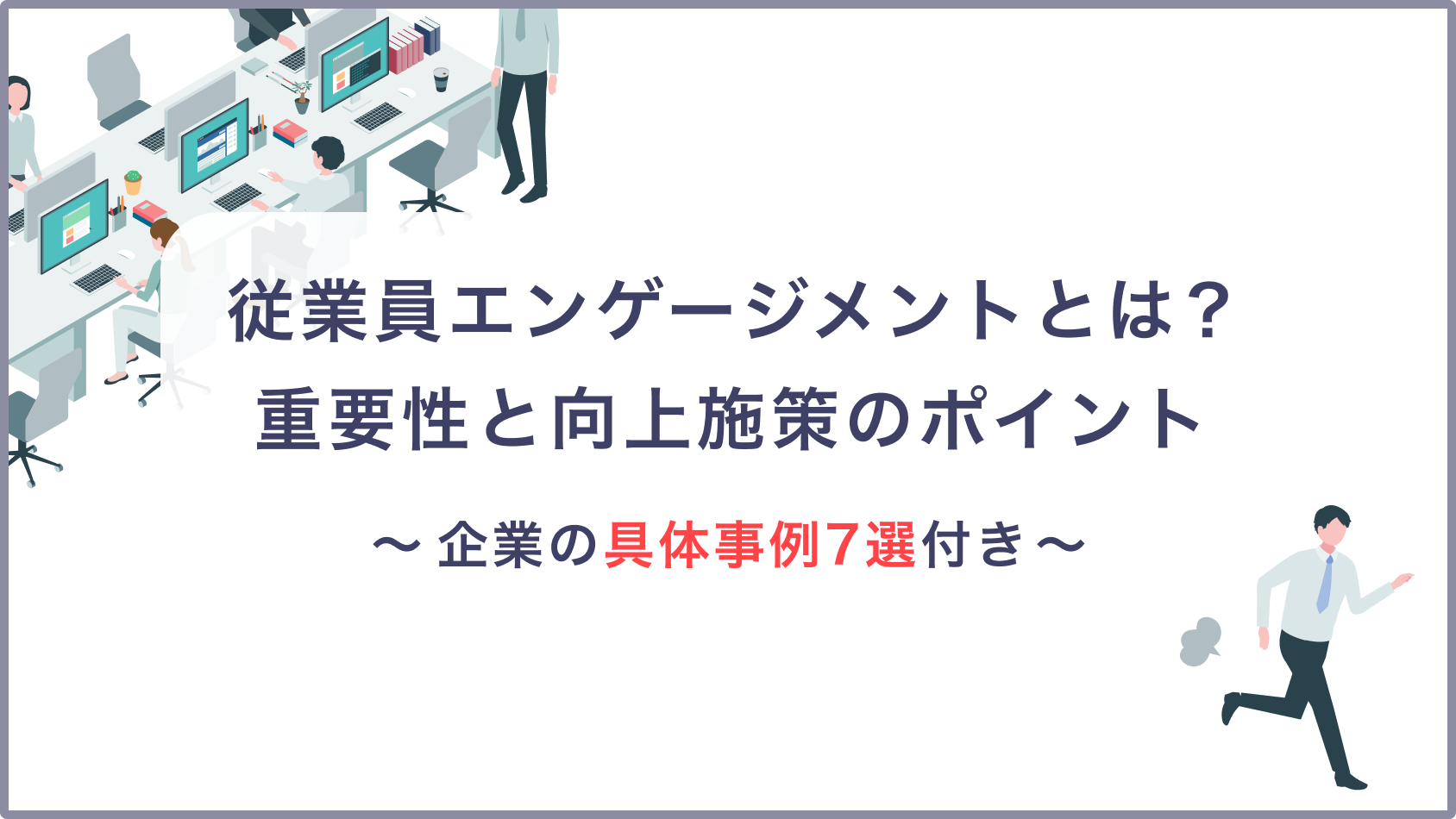
エンゲージメントが高い従業員は、自社の製品やサービス、そして企業理念に誇りを持ち、貢献意欲が高い状態にあるとされています。そのため、自身の仕事が顧客や会社にどう貢献するのかを理解し、「やらされ仕事」ではなく「自分ごと」として業務に取り組みます。この主体性と貢献意欲が、マニュアルを超えた付加価値の高い接客を生み出す源泉となります。
エンゲージメントの高い状態とは、従業員が企業のビジョンに共感し、自発的な貢献意欲を持つ状態を指します。この従業員エンゲージメントの基本を理解することが、第一歩となります。
また、企業理念への共感は、従業員の帰属意識を育み、自分の仕事への誇りの獲得に直結します。
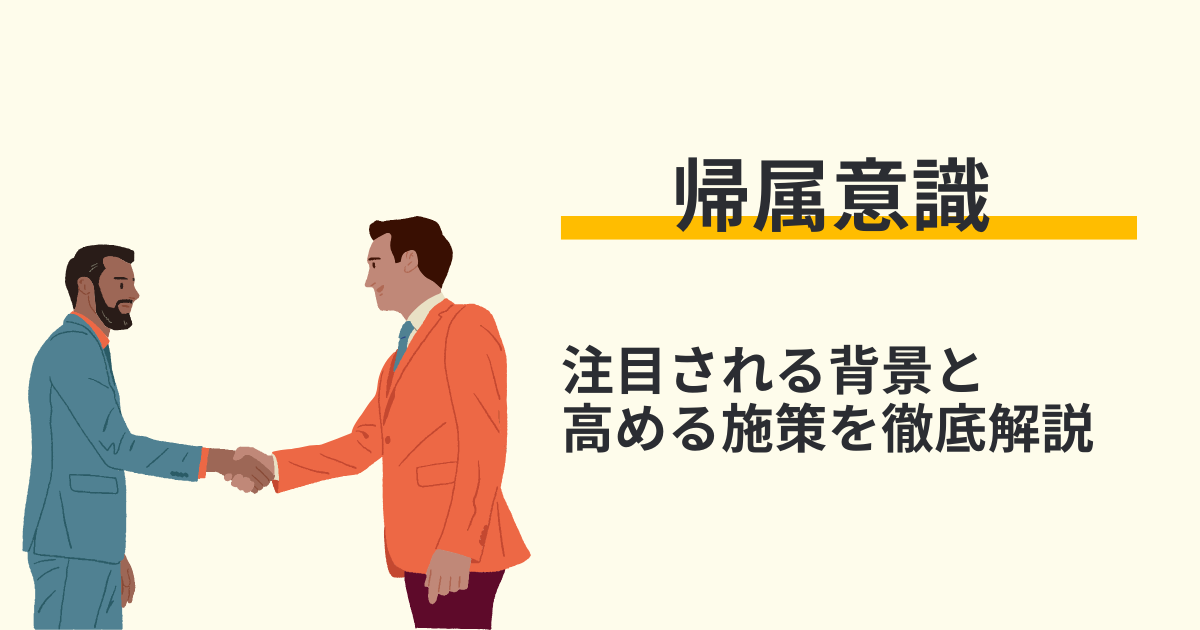
理念を「感動接客」に変えるための具体的な4ステップ
従業員エンゲージメントを高め、理念を現場の行動に反映させるためには、具体的な「仕組み」の構築が必要です。ここでは、そのための組織戦略を4つのステップで解説します。
ステップ1:理念を具体的な「行動指針(クレド)」に落とし込む

企業理念は、抽象的な表現のままでは、現場の具体的な行動に結びつきにくい傾向があります。理念を日々の業務における具体的な行動レベルまで翻訳することが重要です。
NG例:「お客様に寄り添う」
OK例:「私たちは、お客様が言葉にしない不安や期待を先読みし、3つの選択肢を提案します」
このように、誰もが同じ場面を想像でき、行動の判断基準となる言葉にまで落とし込むことが求められます。
ステップ2:行動指針を浸透させる「社内コミュニケーション」施策
言語化された行動指針は、組織内に浸透して初めて価値を持ちます。そのために、社内コミュニケーションを活性化させる施策が有効です。

成功事例の共有
行動指針を体現した優れた接客を実践した従業員を称賛し、そのストーリーを全社で共有する仕組みを構築します。web社内報や社内SNSなどを活用して成功の背景や工夫を共有することは、他の従業員の学びとなり、組織全体のサービスレベル向上に繋がります。
経営層からのメッセージ発信
企業のトップが、自らの言葉で理念と日々の業務の繋がりを繰り返し語ることも重要です。経営層のコミットメントが伝わることで、従業員は理念の重要性を再認識し、行動への動機付けが高まります。
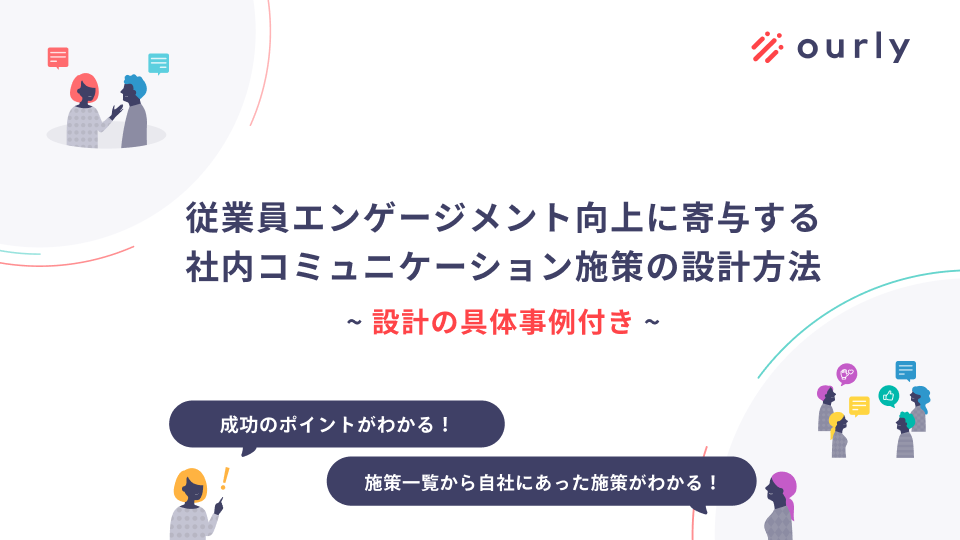
ステップ3:行動を評価し、称賛する「人事評価制度」の見直し
従業員の行動は、評価のあり方に大きく影響されます。売上目標のような定量的な指標だけでなく、理念に基づいた行動指針をどれだけ実践できたかを評価項目に加えることで、企業が本当に大切にしている価値観を従業員に示すことができます。
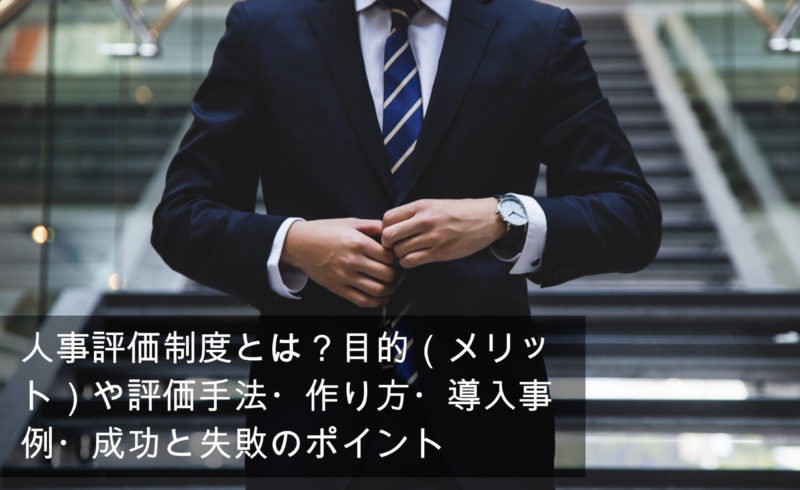
ステップ4:マニュアルを超えた行動を促す「現場への裁量権」
従業員を信頼し、一定の裁量権を与えることは、主体性の醸成に効果的です。例えば、ザ・リッツ・カールトンが従業員に決裁権を与えている事例は、「お客様のために最善だと判断したことは、会社のサポートのもとで実行して良い」という信頼のメッセージとして機能します。信頼された従業員は、責任感と誇りを持ち、マニュアルを超えた価値提供に挑戦しやすくなります。
『仕組み』で接客レベルを向上させた企業の取り組み
最後に、組織的な仕組みによって接客レベルを向上させている企業の事例を3つ紹介します。
GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainmentは、国内外で350店舗以上のアミューズメント施設「GiGO」を展開しています。同社は、店舗事業特有の課題として、ボトムアップ型の問題改善をいかに促進するかに悩んでいました。
そこで導入したのがweb社内報です。導入後、ある店舗の店長が改善アイデアを連載形式で共有するようになり、その成功事例が全社に広がることで、現場発信による問題改善の動きが加速しました。

星野リゾート
星野リゾートでは、「フラットな組織文化」が従業員の主体的なおもてなしを生み出す仕組みとして機能しています。役職や立場に関係なく、従業員全員が対等な立場で意見を交わし、顧客のために何が最善かを徹底的に議論します。この文化が、従業員一人ひとりに当事者意識を芽生えさせ、独創的で質の高いサービスへと繋がっています。
ロック・フィールド

株式会社ロック・フィールドは、全国に約300店舗の惣菜店を展開しています。製造拠点と販売店舗が全国各地に点在していることから、部門間の理解不足が課題となっていました。
この状況を解消するため、同社はweb社内報を活用。製造部門が持つ製品へのこだわりや、販売現場でのお客様の声を記事として発信することで、部門間の相互理解を促進しました。
顧客満足度向上のための従業員エンゲージメント施策にourly
小売業などのサービス業では、多店舗を抱える組織構造から、本部から店舗、店舗から店舗への情報共有が進まないケースがあります。それにより理念が浸透しづらかったり、ナレッジが共有されなかったりという問題が発生しやすくなっています。
web社内報ourlyは、拠点間のコミュニケーションの促進や企業理念の浸透などに効果的なツールです。
ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。
web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。
またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制に強みがあり、web社内報としてだけでなく組織課題を可視化するツールとして活用できることが魅力的なツールとなっています。
ourlyの特徴
- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現
- web知識が一切不要で簡単に投稿できる
- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる
- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる
- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる
「エンゲージメントスコアが低い」「離職率が高い」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。
まとめ:顧客満足度向上は、全社を巻き込むプロジェクトである
本記事では、顧客満足度を向上させる接客が、個人のスキルだけでなく、組織的な「仕組み」によって創出されるという視点を解説しました。
マニュアル通りの画一的な接客から脱却し、従業員が主体的に輝く組織を創るためには、理念の浸透、エンゲージメントの向上、そしてそれらを支える社内コミュニケーションや評価制度の設計が不可欠となります。
顧客満足度の向上は、もはや現場部門だけの課題ではありません。経営層や企画部門が主導する、全社を巻き込んだ組織開発プロジェクトとして捉えることが、その第一歩となるでしょう。