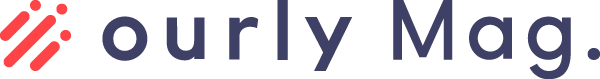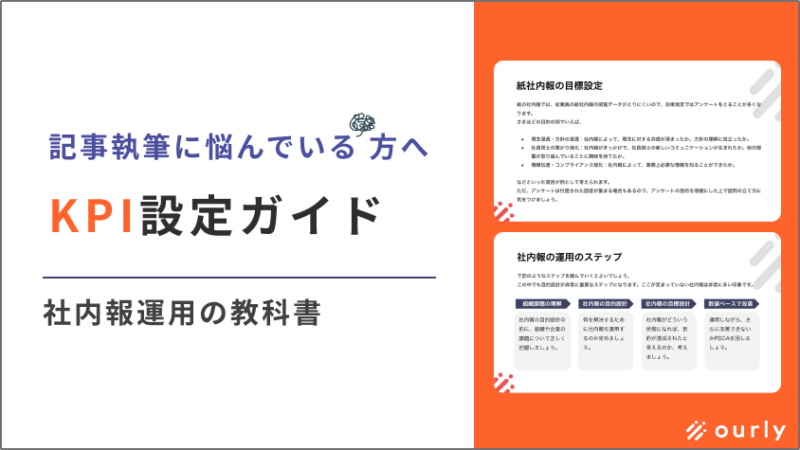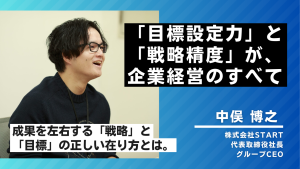「言わぬが花」ではいけない。コンカー代表が語るフィードバックの重要性と可能性

ハイコンテクストな文化(言葉にせずとも、共通の文脈を前提に察する文化)が根強い日本では、フィードバックをすること、されることに対して消極的な感情を抱くビジネスパーソンも少なくありません。しかしフィードバックを避けることで、知らず知らずのうちに、相手の成長機会を奪ってしまっているかもしれません。
今回は『みんなのフィードバック大全』(光文社)の著者であり、株式会社コンカー 代表取締役社長の三村 真宗(みむら まさむね)さんにインタビュー。フィードバックの重要性や、社内でフィードバック文化を醸成するための取り組みについてお話しを伺いました。
株式会社コンカーについて
世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense(経費精算・経費管理)』・『Concur Travel(出張管理)』・『Concur Invoice(請求書管理)』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。
コンカーの詳細については www.concur.co.jp をご覧ください。
同僚としての愛あるフィードバックに感銘を受けた

──著書『みんなのフィードバック大全』には、個人だけでなく会社や組織が成長するためのフィードバックの手法が記されています。そもそも三村さんがフィードバックが重要だと気づき、コンカーに広めていきたいと考えた原体験について教えてください。
私は新卒でSAPジャパンに入社し、13年間ITの領域でキャリアを積んできました。当時、その分野においてはトップランナーとして走っていたこともあり、周囲からフィードバックを受ける機会は少なかったんです。
その後自分のキャリアをイチから見つめ直すべく、コンサルティングファームの最高峰であるマッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン(以下、マッキンゼー)に転職しました。フィードバックの重要性に気づいたのは、それからです。
──マッキンゼーでフィードバックの重要性に気づいたんですね。
とくに印象に残っている体験は、入社2年目の若手コンサルタントからフィードバックを受けたことです。
ビジネス経験が長く、お客様の課題に対して経験則的に解決策を提案することが多かった私に、彼は「“ロジック”や“ファクト”で裏付けをしてアプローチすれば、三村さんはコンサルタントとしてもっと強くなれると思います」とフィードバックをしてくれました。
その言葉にすごく感銘を受けまして……。やはり、自分の至らない部分を見つめて、向き合って伝えてくれることは本当にありがたかったですし、同僚として「成長してほしい」と願う愛情を感じました。この経験が、フィードバックの重要性を感じた大きな原体験です。
フィードバック文化は不平不満や陰口の横行を防ぐ

──コンカーでフィードバック文化を浸透させようと思ったのは、組織規模としては何名くらいのタイミングだったのでしょうか。
ちょうど、40〜50名くらいの組織規模になったタイミングでした。1クラスくらいの規模になってくると、学校のグループと同じで、「あの部門は何をやっているのかわからない」「あの部門は全然動いてくれない」みたいな不平不満、陰口が出てきますよね。
非常に前向きな社員は、ほかの社員から不平不満や陰口を聞いても自分自身で遮断できます。しかし多くの社員は、飲み会に行って、会社や上司、社長の陰口を聞き続けていると、だんだんとその意見に染まってしまうんです。不平不満や陰の多い社員が組織に与えるダメージの大きさは、計り知れません。
当事者を呼び出して指導をするのも1つの方法ですが、当時は「この先、数百人の組織規模になるだろう」と目に見えていたので、文化として定着させなければいけないと感じたんです。
──つまり、フィードバック文化を定着させることで不平不満や陰口を防ぐことができる。
不平不満や陰口の源泉は、相手の課題に対するストレスです。相手に対する不平不満を溜め込んでいることで、陰口に発展する。しかしフィードバックをすれば、相手の課題に対して常にオープンでいられるため、不平不満やストレスを溜め込むことがありません。
フィードバック文化をしっかりと定着させれば、不平不満や陰口が横行することはなくなります。
経営者の決意と宣言がフィードバック文化醸成の一丁目一番地

──フィードバック文化を根付かせるために、意識すべきことはありますか?
「経営者の決意と宣言」が、フィードバック文化を根付かせる一丁目一番地です!
まずは経営者が、フィードバック文化を醸成していくんだと強く決意すること。経営者の決意なくして、社内の文化を醸成することは不可能です。次に、会社全体にフィードバック文化を醸成すると宣言すること。会社として宣言をすれば、フィードバックをすること、されることの抵抗感を下げることができます。
たとえば「フィードバックをしたら相手を不快な気持ちにしてしまうんじゃないか」と考えて、モヤモヤを溜め込んでしまい、結局陰口を言ってしまう人もいると思います。でも、会社としてフィードバックをしよう!と宣言してしまえば、伝えることが当たり前になり、伝えずに陰口を言うことに罪悪感を持つような文化を醸成できるんです。
──フィードバック文化を根付かせるためには、フィードバックを受け取る側の姿勢も重要だと考えます。なかには、フィードバックを快く受け取れない社員も存在すると思いますが、そういった社員へはどのような対応をされているのでしょうか。
コンカーでは、全社合宿の際にコーチャビリティの概念を社員に共有しました。コーチャビリティとは、「他者からの助言を聞き入れる能力」のこと。対して、他者からの助言を聞き入れられない状態をアンコーチャブルといいます。
合理的に考えるとコーチャブルであればそれだけで得をして、アンコーチャブルであればそれだけで損をしています。なぜならコーチャブルであれば、周囲からの助言に耳を傾けて、助言の内容を成長の糧にできる。より高いパフォーマンスを発揮できますし、成長や昇進や承継につながります。
アンコーチャブルはその逆です。他者からの助言を聞き入れられないので、成長は停滞し、パフォーマンスも発揮できなくなる。コーチャビリティを引き出すには「成長意欲」を刺激して、「忌避の気持ち」を減少させるのが効果的なので、それぞれがもたらす影響を社員全員にしっかりと伝えるようにしました。
──それでもアンコーチャブルな人には、どう対応していますか?
アンコーチャブル人は、「傲慢な人」と「恐怖を抱いている人」の2パターンがいると思います。傲慢な人に対しては、まずは謙虚になることの必要性を伝えます。自分は全知全能ではないこと。いわゆる「無知の知」を認識してもらうところから、はじめてもらいます。
恐怖を抱いている人には、相手や組織を信頼するよう伝えます。コンカーのフィードバック文化の中での大原則は「相手の成長を願ってフィードバックをすること」です。フィードバックをされることは、責められているわけでも、操作されているわけでもなく、相手からの成長を願う気持ちであることを認識してもらいます。
──なるほど。ただフィードバックをするだけではなく、その背景にしっかりと原則を定めているのですね。
ある種、大原則を全員が理解しているからこそ、耳が痛い話でも「これは相手が自分の成長を願って、言ってくれているんだ」と前向きに受け止められるんだと思います。このようなプロトコルがなければ、センシティブな人にとってはつらい環境になってしまう。組織全体で認識を揃えて取り組んでいくことが重要なんです。
先ほどお話しした「経営者の決意と宣言」と「プロトコル(共通認識)の制定」の2つを意識できていれば、ある程度フィードバック文化を醸成することは可能になると思います。
組織としてのコーチャビリティも忘れてはいけない

──先ほどの大原則のほかにも、組織全体で認識を揃えるために取り組んでいることはありますか。
組織がしっかりとフィードバックに対して誠実な姿勢を見せることですね。弊社では、年に1回「コンストラクティブフィードバック」という制度を回しています。これは、日々のコミュニケーションですくいきれない課題を洗い出すための制度です。
全社員必須回答で、会社・上司・他部門に対する強みと弱みを答えてもらっています。そのなかで短期的に解決できる課題があれば、すぐにアクションを起こして、発信する。組織として、代表としてのコーチャビリティをしっかりと持っていることを見せることで、コンカーへの信頼感を醸成しているんです。会社としての課題にしっかりと向き合うことで、社員1人ひとりがコーチャビリティへの意識を高めることにもつながります。
──会社への課題もしっかりと受け止めているんですね!
正直心が折れそうになることもありますが、会社の成長を願って回答してくれた社員の気持ちを受け止め、向き合い、会社の伸びしろとして真摯に受け止めています。
フィードバック文化が広まれば、成長機会が増加する

──兎にも角にも、組織として個人としてコーチャビリティを高めていくことがとても大切なのだと感じました。
日本はハイコンテクストの文化が根強いため、「言わぬが花」「あうんの呼吸」「空気を読む」などを重視してしまい、圧倒的にフィードバックのコミュニケーションが足りていないんですよ。
でもフィードバックを避けることは結果として、相手の課題を放置し、本来持っている強みや伸びしろを押さえ込んでいる。個人としても、組織としても成長の機会を損失してしまっているんです。私は日本社会全体にフィードバックというコミュニケーションのあり方が広まることで、組織や個人が、もっともっと成長してほしいと思っています。


Interview:Shimpei Takahashi
Write / Design:Sachi Kagayama
Edit:Nozomu Iino
Photo:Yuma Miyanaga